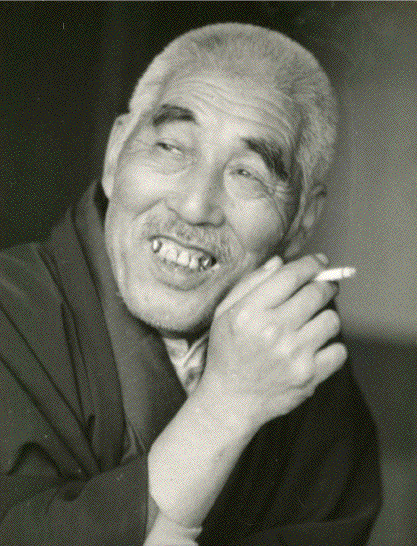 信時 潔(1887〜1965)
信時 潔(1887〜1965)
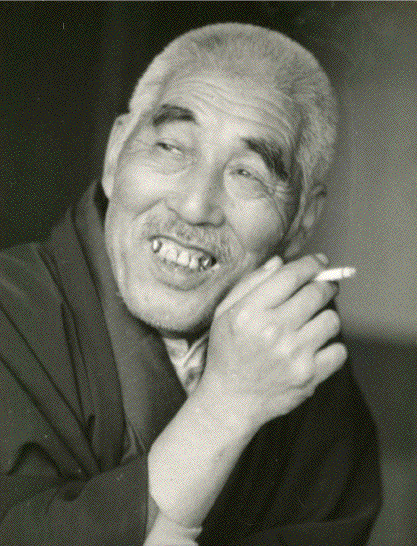 信時 潔(1887〜1965)
信時 潔(1887〜1965)
1887年12月29日:牧師・吉岡家の三男として大阪に生まれる。幼少期から賛美歌に親しむ。
1898年(10歳):大阪北教会の長老・信時家の養子となる。
1905年(17歳):東京音楽学校予科に入学。
1906年(18歳):東京音楽学校・本科の器楽科に入学、チェロを専攻。
1910年(22歳):本科を卒業し研究科器楽部に進む。アウグスト・ユンケル、ハインリヒ・ヴェルクマイスター、幸田延、安藤幸、神戸海らに学ぶ。
1912年(24歳):研究科作曲部に進む。
1915年(27歳):作曲部修了、東京音楽学校助教授に就任。
1920〜1922年(32〜34歳):文部省在外研究員として訪欧、作曲とチェロを研修(ドイツ、フランス、イギリス、スイス、イタリア)。ベルリンでゲオルク・シューマンに作曲を学ぶ。
1923年(35歳):東京音楽学校師範科卒業生の白坂ミイと結婚。東京音楽学校教授に就任。
1924年(36歳)〜:合唱曲、歌曲、ピアノ曲、ヴァイオリン曲を数多く発表。教科書の編纂にも多数携わる。
1926年(38歳):歌曲集『小曲五章』(詩:与謝野晶子)。
1930年(42歳):東京音楽学校の管弦楽部長。合唱曲『いろはうた』(「いろはにほへと…」に、雅楽の越天楽の旋律を用いて作曲した変奏曲)。
1931年(43歳):東京音楽学校本科作曲部の創設に尽力し、実現をみる(新入生の受け入れは1932年から)。初代教授は橋本國彦。
信時本人は教授を辞任し講師に。雑務から解放されて作曲に専念。
文部省「新訂尋常小学校唱歌」として「一番星見つけた」「電車ごっこ」などを作曲。
1934年(46歳):「『鶯の卵』より」。
1936年(48歳):歌曲集『沙羅』(詩:清水重道)、ピアノ組曲『木の葉集』。
1937年(49歳):合唱組曲『紀の国の歌』。NHKの依頼により『海ゆかば』作曲。以降国民歌謡多数発表。
1940年(52歳):皇紀二千六百年奉祝曲として交声曲『海道東征』(詩:北原白秋)を作曲。『慶應義塾塾歌』。
1942年(54歳):満州視察。日本芸術院会員となる。
1943年(55歳):朝日賞受賞、南京で開かれた中日文化協会全国文化代表大会に参加。
1947年(59歳):新憲法施行記念国民歌『われらの日本』(詩:土岐善麿)。
1948年(60歳):歌曲集『古歌二十五首』。
1951年(63歳):平和条約発効ならびに憲法施行5周年記念式式典歌『日本のあさあけ』(詩:斎藤茂吉)。
1954年(66歳):東京芸術大学音楽部講師退任。
1962年(74歳):『海道東征』戦後初の再演(当時朝日放送社員であった阪田寛夫の企画によるもの)。
1963年(75歳):文化功労者。
1964年(76歳):勲三等旭日中綬章受章。
1965年(77歳):歌曲/合唱曲集『女人和歌連曲』(遺作)、オペラ『古事記』(未完)。
1965年8月1日:心筋梗塞のため死去(満77歳)。墓所は雑司ヶ谷霊園。
2.主な作品
歌曲が中心で、管弦楽を含む作品はごく少数しかありません。
信時の作曲に対する考え方は、第一次大戦直後のヨーロッパへの留学中にリヒャルト・シュトラウスやシュレーカーなどの肥大化した管弦楽曲を聴いて限界を感じ、逆にストラヴィンスキーの「兵士の物語」などの新古典主義に転向した簡潔な響きに将来の可能性を見出したことから、下記のようなものだったといいます。(片山杜秀氏の著作からの受け売り)
(1)大編成の複雑な音楽はしだいに廃れる。
(2)今後の音楽は線的・対位法的な方向で簡潔になっていく。
(3)対位法の根幹は三声体であり、切りつめられた三声部の音楽に未来の一理想がある。
(4)モノクロームな音色でメゾ・フォルテでモデラートでやって聴くに耐えるものが本物の音楽である。
そんな信念から、信時が範例とみなしたのが、線的書法を特徴として「現代のバッハ」との呼び声も高かったヒンデミット(1895〜1963)だそうです。
そのため、信時は弟子の下総皖一(1898〜1962)をドイツ留学でヒンデミットに師事させました。
(下総の代表作は唱歌「たなばたさま」=「ささのはさらさら のきばにゆれる」)
その下総が、さらにその弟子の團伊玖磨(1924〜2001)に上記の「三声体」をしつこく教えたため、團は下総を忌避し、東京音楽学校在学中にもかかわらず学外の山田耕筰に師事することとなり、東京音楽科学校出身でありながら「山田耕筰の弟子」といわれるようになりました。
信時の直系の弟子はこの下総でしたが、1931年に東京音楽学校に発足した「作曲科」を盛り立てるため、作風が大きく異なるが実力と人気のあった橋本國彦(1904〜1949)を作曲家教授に任じたようです。一種の「客寄せパンダ」だったのでしょう。
そんな逸話があるほどに、信時の作風は古風かつ保守的だったようです。
2.1 歌曲
信時本人にとっては不本意でしょうが、信時の最大の代表作といわれるのは「海ゆかば」でしょう。
この曲は、日本放送協会の委嘱で大伴家持の万葉集の詩に曲をつけたもので、国民精神総動員強化週間の放送の主題曲として発表され、さらに国民歌謡としても放送されました。
その後、1942年3月に真珠湾特別攻撃隊の戦死者報道のバックにこの「海ゆかば」が流されて以来、玉砕報道のたびにこの曲が使われ、戦時中の鎮魂曲の意味合いを強めて行きました。
「海ゆかば」の楽譜(藝大・信時文庫)
海ゆかば 水漬(みづ)く屍(かばね)
山ゆかば 草生(くさむ)す屍(かばね)
大君(おほきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ
かへりみはせじ
第1曲「丹沢」
第2曲「あづまやの」
第3曲「北秋(きたあき)の」
第4曲「沙羅」
第5曲「鴉(からす)」
第6曲「行々子(よりきり)」
第7曲「占ふと」
第8曲「ゆめ」
2.2 声楽曲
(1)交声曲「海道東征」(1940年)
1940年に、工期2600年奉祝曲のひとつとして作曲された交声曲(カンタータ)であり、詞は晩年の北原白秋(1885〜1942年)によります。(白秋はその2年後に没)
1940年11月20日、東京音楽学校奏楽堂において抜粋5曲が木下保指揮・東京音楽学校管弦楽部らによって演奏され、全曲は11月26日に日比谷公会堂で初演されました。
初演以降、1943年にかけて日本全国、満州国・中国・朝鮮(1942年の建国十周年演奏旅行)、出陣学徒壮行演奏会などで計67回演奏されたそうです。なお、演奏記録によると1944年には朝比奈隆が大阪放送管弦楽団を指揮して演奏しているそうです。
内容は日本神話をもとにしたもので、九州の高千穂を出た神武天皇が瀬戸内海を東に進み、大和に上陸して大和の国を建国する物語が8つの楽章で歌われます。
曲は清楚で古典的なバランスをもったもので、随所に日本調の音楽が取り入れられています。
第1章「高千穂(たかちほ)」
冒頭には雅楽調が取り入れられている。「君が代」と同様の日本長音階により、堂々とした風格で歌われる。
第2章「大和思慕(やまとしぼ)」
ヤマトタケルの望郷の歌「思国歌(くにしのびの歌)」が引用される。
音調は西洋音階による。
第3章「御船出(みふなで)」
西洋音階による。前半のメンデルスゾーンを思わせる「荒海」から、後半の勇壮な船出の音楽では東征に至るまでの経緯も歌われる。額田王の和歌も引用されている。
第4章「御船謡(みふなうた)」
ピアノ(ハープ)のアルペッジョの上にバリトン独唱が船出の祝いを歌う(楽譜ではピアノとなっているが、本来はハープを使いたかったものとして藝大盤ではハープで演奏されている)。
後半ではテノール・合唱も加わり、日本の民謡調が取り入れられて航海の安全を歌う。(なんとなく「あわて床屋」(北原白秋作詞、山田耕筰作曲)を思い浮かべる曲調)
第5章「速吸と菟狭(はやすい と うさ)」
流れの速い予豊海峡を国津神が亀に乗って先導したという古事記を受けて、児童合唱がわらべうた風の歌を歌う。日本音階の「都節」(陰旋法)によっている。
第6章「海道回顧(かいどう かいこ)」
中国地方で戦いの準備をする中で、第1章「高千穂」が回顧されるとともに、これから向かう大和に思いをはせる。全体として西洋音階によっている。
第7章「白肩津上陸(しらかたのつ じょうりく)」
白肩津とは現在の東大阪市あるいは枚方(ひらかた)のあたりらしい(大阪は波(浪)が速い入江だった)。
トランペットのファンファーレとともに、大和を支配していた豪族・長髄彦(那賀須泥毘古)との戦いが始まる。東征軍は敗北をきたす。
第8章「天業恢弘(てんぎょう かいこう)」
敗北の場面から、一転して第1章「高千穂」の音楽に回帰する。東征軍は紀伊に回って熊野から大和・橿原に地に至り、そこで神武天皇として即位する。その偉業と日本の山河の美しさを讃えつつ力強く終止する。
内容が第7曲「白肩津上陸」での敗北から突然第8曲(神武天皇即位)に飛躍するのは、作詞した北原白秋が第7章までですでに既定の字数を大幅にオーバーしてしまったためのようです。
白秋自身は、これを「第一部」として、続けて「第二部」「第三部」を作って「三部作」にしたいという希望を述べていたようですが、この曲の作曲・初演から2年後の1942年に他界して果たすことはできませんでした。
戦意高揚、皇室礼賛の内容から、戦後はほとんど演奏されることはなくなりましたが、1962年に大阪朝日放送によって再演されたことがありました。このときに大阪朝日放送の社員で演奏を企画した阪田寛夫は、作家として独立後の1987年に小説「海道東征」を発表して川端康成文学賞を受賞しています。
しかし、その後もほとんど顧みられることはありませんでした。
21世紀になるとにわかに再評価の気運が高まって再演の機会が増え、2003年にオーケストラ・ニッポニカが演奏会で取り上げるとともに(指揮:本名徹次)、2014年に横浜シンフォニエッタ(指揮:山田和樹)が熊本で、2015年に大阪フィル(指揮:北原幸夫)が大阪で、東京藝大シンフォニー・オーケストラ(指揮:湯浅卓雄)が東京で演奏し、山田和樹、湯浅卓雄の演奏はCDとして発売されています。
2.3 管弦楽曲
残念ながら、信時にはこれといった管弦楽作品はないようです。
3.CD情報
上にも書いたように、交声曲「海道東征」については下記のCDがあります。
日本のクラシック音楽の1つの代表作として、広く聞かれればよいなと思います。
交聲曲『海道東征』、絃楽四部合奏、合唱曲集 山田和樹・指揮/横浜シンフォニエッタ、海道東征合同合唱団、熊本県庁合唱団、他(EXTON)
交聲曲『海道東征』、『我国と音楽との関係を思ひて』、絃楽四部合奏 湯浅卓雄&東京藝大シンフォニーオーケストラ、東京藝術大学音楽学部声楽科学生、他(Naxos)
交聲曲 海道東征: 北原幸男 / 東京so 東京混声合唱団 森谷真理 盛田麻央 小泉詠子 樋口達哉 原田圭
交聲曲『海道東征』、シューベルト:交響曲第8番『未完成』 阼島章恭&大阪フィル(EXTON)
また、信時 潔の作品の中心を占める歌曲に関しては、下記のCDがあります。
