測量から印刷まで。地図作りの行程
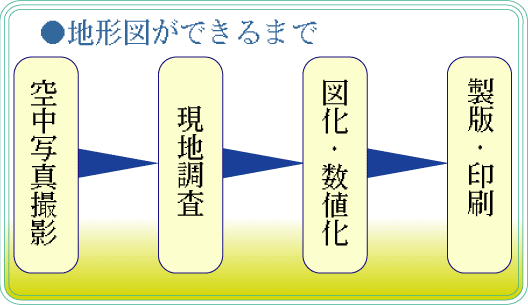
地形図の基本は空中写真です。高度6000m上空から正確に地表を撮影します。撮影は目標地域を複数撮影し、ステレオ写真の要領で立体画像にして、等高線などに記号化します。ただし、写真に写らない部分も数多くあります。これらは、実際に測量官が現地に調査にいきます。山間部では約15年に一度、開発が盛んな市街地では頻繁に測量しなおします。5万分の1地形図で約1300枚。日本国内毎日どこかで測量が行われているはずです。
こうした測量の結果を空中写真に図化機と呼ばれるもので描いて地図ができあがります。最近は、コンピュータ合成も盛んに行われていますが、図化の重要な部分は手作業で行われています。
測量の基準になるもの
土地の高さの基準になるのが、水準点。東京湾の平均海面を標高0mとしています。左上の写真は憲政記念館内にある日本水準原点です。建物の内部には原点標石があり、そこに埋め込んだ水晶板の0の目盛りが、標高24.4140mと決められています。
下の写真は、左が三角点。一等から四等まで約10万点設置されていて、緯度経度が正確に求められていて、地図作製、道路建設、都市開発の基準として使われます。通常、山頂などの見晴らしのいい場所に設置されます。
右は水準点です。水準原点で説明したように、標高を求める基準になります。主要道路沿いに約2kmごとに設置されています。地殻変動、地盤沈下対策など、土地の標高測定は地図作り以外にも重要な測量活動です。ただ、三角点ほど頑丈に作られていないため、道路工事などで破損や亡失も少なくありません。同じ省庁で一体何やってるのでしょう。

