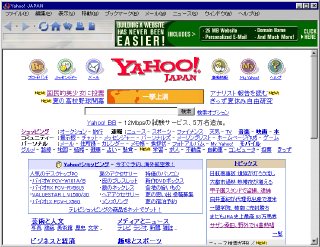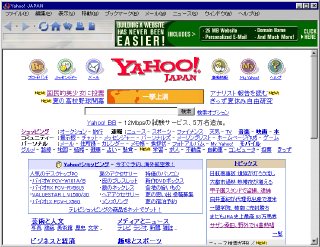Windows 2000 の導入
とうとう Windows 2000(以下 Win 2k と記す)を導入しました。近況の項にも書いたとおり職場に Win 2kマシンが入ったものの、
下手に設定をいじってパソコンがダウンしてしまうとまずいので、自宅のマシンで勉強しようというわけです。
新しいマシンを買ってもよかったのですが、例によって web を巡回していると 760EL が 10k円で売りに出ていました。このマシンの
詳細はいずれ別項目に記しますが、Pentium-133Mhz(2次キャッシュ 256KB), メモリー32MB, HDDの容量が 2GBで、Mwave を搭載しない
ことを除けば 760E とほぼ同等のスペックです。電源アダプタが付属しないため安かったのですが、このタイプのアダプタは幸いいくつも
持っています。この本体に メモリーをさらに 32MB追加して合計 64MBにすれば、Win 2k の動作環境をかろうじて満たします。OS(アカデミック版)
と合わせて計30k円ほどで Win 2kマシンが出来上がりました。
システムをインストールした段階でハードディスクは半分ほど埋まってしまいました。さすがに動作はやや重ですが、試験運用には
これで十分です。アプリケーションの中には Win 2k 非対応のものや、対応モジュールを追加しなければならないものもありますが、少しずつ
テストしていこうと思っています。
ついでに、760E のほうもハードディスクの区画を設定し直しました。従来は 2GBのハードディスクを3分割して Windowsシステム,
Linuxシステム, Linuxのマスターファイルを入れていたのですが、それぞれの区画にわずかな空きがあるといった状況で、特に Windows の
入っている Cドライブが危機的な状況になっていました。これまでの使用実績から Linuxの区画をやや縮小し、Linux のマスターファイルを
Windows の区画に置くことでこれまでより余裕のある運用ができるようになりました。Win 98の再インストールによって不要なファイルの残骸も
一掃されてすっきりしました。
システムの再インストールと設定のやり直しなどで1日つぶれました。パソコンが趣味とは言ってもあまりやりたくない作業ですね。
当分は今の体制でやっていこうと思います。
2002年3月
Windows 2000を導入してから1ヶ月以上が過ぎましたので、しばらく使ってみた感想を書きます。
ThinkPad 760EL の項にも書きましたが、PCカード関連の不具合に遭遇しています。有線の LANカード、モデムカード、
カードバス SCSIカードが使えない状態です。無線 LANカードと、外付け CD-ROMドライブの IDEカード、コンパクトフラッシュ(+アダプター)
は IRQを変更することで利用できるようになりましたが、他のカードはこの方法でも動きません。Win 95に付属していた Microsoft Fax は Win98 SE
ではなくなってしまいましたが、Win 2k には FAX機能が搭載されています。モデムカードを差してこの機能を利用しようと考えたのですが、
現状ではできません。モデム内蔵の 701Cs(Win 95) が隠居状態なので、一応 FAX機として使うことはできるのですが。
どうも不具合の多い、というか、私にはよくわからない Win 2k ですが、よい点としてはスタンバイからの復帰が早いということがあります。
760E(Win 98)では黒い画面にカーソルが点灯した状態で長く待たされますが、Win 2k では Win 95 の時と同様すぐに復帰します。それと
黒いマウスポインターが標準装備されていて、ポインターの動作も極めて速く動くように設定できるので、外付けマウスを使わない
私には好都合です。黒いポインターは、光線の関係で見づらくなる液晶ディスプレイ上でポインターの視認性を高めるのに役立ちます。古くは
ThinkPad 360Cs(Win 3.1)に IBM独自のユーティリティーとして付属していました。余談になりますが、私は Win 98上では Logitech の MouseWare と
いうソフトを利用しています。これには様々な大きさの黒いポインターが含まれています。前述のように外付けマウスをほとんど使わないにもかかわらず、
ユーティリティーだけ利用させてもらっています。
Linux と同様に Win 2k の起動時には様々なサービスが自動起動しているようです。そのことがまた OS の動作を余計に重くしてしまっている
のかもしれません。自宅で Win 2k を積極的に使う理由は今のところありません。まだまだ試験運用が
続きそうです。
2002年4月
学校はどこでも同じだと思いますが、4月〜5月は新しい学年のすべり出しの時期なので仕事でばたばたしています。6月に入っても
教育実習や遠足・林間学校(某高校では)などで相変わらずあわただしい日が続いています。今年度から土日が完全に休みとなった関係で、以前なら
土曜日の午後にやれた残務整理も不可能になり平日はかえって忙しくなっています。要するに私個人としては学校週5日制に疑問を抱いているのですが、
愚痴はこれくらいにしてパソコンの話に入りましょう。
私は幸いなことにコンピュータウイルスの被害を受けたことはありませんが、3ヶ月ほど前に初めてウイルス付のメールを受信しました。
"returned mail"を装っていましたが自分としては思い当たるものがなかったので、添付ファイルをチェックしてみると明らかにウイルスで、直ちに
削除しました。これは古典的なウイルスなので実行しなければ問題ありませんが、Outlook Express を標的にするウイルスの中にはメールを
プリビューすると自動実行されてしまうものもあると聞いています。
OE は無償なので多くの人が使っており、操作性も悪くはありませんが、他によいソフトがあれば乗り換えたいと思っていました。
乗り換えの条件としては、けちだと思われるかもしれませんが「お金がかからないこと」と、「OE に似たユーザーインターフェイスを持っていること」
を考慮しました。IE/OE と共通のコンポーネントを利用するメーラーは危険なのでもちろんだめです。最終的に Eudora (by Qualcomm) と Shuriken
(by Justsystem) にしぼってテストし、動作の軽さと操作のしやすさから Shuriken に決めました。
最近、ウイルス対策として Shuriken Pro 2(有償)を利用する人が多くなっているようです。私の場合はたまたま「一太郎Lite2」に Shuriken 2.0 が
付属していたのでそれを利用しました。テキストメール以外は表示しない設定も可能ですし、フォルダのアイコンも郵便自動車やポストの絵になって
いて楽しめます。ちょっと古いソフトですが、Win Me や Win 2k に対応するモジュールも提供されているので「一太郎」を持っている人は試しに
使ってみてもいいのではないでしょうか。
2002年6月
また夏が巡ってきました。
とりあえず学校が休みに入ったので、比較的時間に余裕が生まれました。最近は学校週5日制と関連して教員は休みばかり取っている
のではないか、という批判もありますが、私個人としては週5日制を望んだわけではないし、学校が夏休みであっても、職員が皆休暇を取って
いるわけではないのですから、一般の人にも教員の置かれている状況を多少は理解してほしいという気持ちがあります。
さて、パソコンの話ですが、学校現場でもコンピュータが多用されるようになって2年前からコンピュータのアドバイザー(インストラクター)
が年2回学校を訪れるようになりました。県が民間の会社に委託して行なっているものですが、職員の関心は今一つです。普段からパソコンを利用
している人はインストラクターの世話になる必要はあまりないでしょう。一方、パソコンに関心のない人にとってはこういった行事自体どうでもよいこと
なのです。それでも今年から時間的に余裕のある夏休み中に機会を設けることになったので、数名の利用者がありました。
M$社のワープロソフトや表計算ソフトの使い方が中心です。私自身は以前にも書いたように、非M$のアプリを使っていますが、
担当者として講習会に立ち会って勉強してきました。多くの人は特に疑問を感じていないようですが、私はなぜM$社のソフトでなければいけないのか、
という疑問を持っています。確かに教える側としては、特定のアプリケーションに限定したほうがいろいろな点で効率がいいということはわかります。
ただ、私は多くの官公庁や企業がM$社のアプリを標準としていることに疑問を感じます。海の向こうでは訴訟が起こされたように、こういった状況は
必ずしも支持されてはいないわけですが、日本ではなぜか誰も疑問を持たないまま選択の余地を認めない方向に向かっています。
OS に関しては共通の基盤として標準化の必要があるわけですが、アプリまで特定の1社が独占、というのはどんなものでしょうか。
そう言う私も web ブラウザだけは IE から脱出できていません。大部分の web ページが IEをターゲットにして書かれているために
Netscape 4.xではレイアウトが崩れたり、表示できないページがあるからです。先日 Netscape 6 を試してみましたが、やけに動作が遅いな、と思って
動作環境を確かめてみたら、私の所有するパソコンでは力不足であることがわかりました。web ページはできるだけ多くの人に見てもらえるように、少々
古いパソコンでも表示できるように書く必要があると考えています。このページはいまだに「メモ帳」で書いています。
話は変わりますが、久しぶりに Linux を起動してみました。Linux でインターネットを利用するにはこれまでカード型モデムを利用していました。
LANカードがうまく認識されないことと、それがうまくいったとしても、NEC のルーターが Windows版のユーティリティで制御するようになっているので
ダイヤルアップできないという理由からです。しかしシリアルポートに TA を直結するのは試していないことに気づきました。考えてみれば、無線ルーターを
導入する前はシリアルケーブルでつないでいたわけです。いったん Windows を起動して ThinkPad 機能設定プログラムでシリアルポートを有効にし、
再起動して Linux を立ち上げるとシリアルポートが認識されました。あとは KPPP(ダイヤルアップツール)で TAの初期化コマンドを設定してやると
無事にネットにつながりました。非Windows の世界もたまにはいいものです。
2002年7月
最近電気屋の広告を見ると当然のことながら、Windows XP 搭載のパソコンばかりが並んでいます。売る側としてはどんどん新しいものを
買ってもらわなければ困るのでしょうけど、私は当分の間は Win 9x と Win 2k でやっていくことになるでしょう。私のメインマシンは 760E ですが、
これはファンがついていないので夏場は相当熱くなります。Win 2k 搭載の 760EL もよく似たものです。それでここのところ発熱の少ない 560 を
使っているのですが、Win 98 でのレスポンスは今一つなのです。OS の重さに加えて2次キャッシュなし、HDD の DMA 不可、などが原因なのでしょうか。
動作の軽い Win 95 にもどしてしまいました。
OS を軽くしたついでに、「第3のブラウザ」とも言われている Opera をダウンロードして使ってみました。起動は IE よりも時間がかかりますが、
いったん起動してしまえばなかなか快適です。Netscape 用のプラグインを利用するようになっているので、MIDI 再生用に久しぶりに YAMAHA の MIDPLUG を
インストールしました。このブラウザはノルウェーの会社が開発したもので ver 5.5 から日本語版ができたようです。無料で利用する場合は広告が表示されます。
(2005年12月現在の最新版は、日本語版 ver 8.50 です。完全なフリーソフトになり広告も表示されなくなりました。)
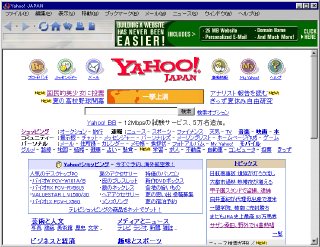
Opera ver 6.03
購入すれば広告はなくなるのですが、当面は試用ということで広告は消せません。そこで、560 の SVGA の画面を少しでも有効に使うために
カスタマイズした結果が上の図です。戻る進むといったボタン類の下にステータスバーを配置し、アドレスバーは非表示です。アドレスを入力する場合は
[F2]キーを押すか、メニューから選ぶことでダイアログボックスを呼び出せます。この配置ではステータスバーが短くてあまり役に立ちませんが、データ
の読み込み中は画面の下のほうに転送状況がポップアップで表示されるので特に不便はありません。
設定項目が多くてわかりにくい点は Netscape と似ているように思われます。「マウスジェスチャー」といってマウスを上下左右に動かすことで
いろいろな操作ができるようなのですが、私はマウス(トラックポイント)の使用は必要最小限にしてキーボードで操作することが多いので、この機能は
オフにしました。この辺は好みの分かれるところでしょう。
まだよくわからない部分もありますが、しばらくテストしてみようと思います。Opera は W3C(WWW コンソーシアム)が定めた HTMLタグの解釈に
忠実に設計されているとのことですが、M$ のサイトを表示するとレイアウトが崩れるのは M$の陰謀でしょうか。
2002年8月
その後 Opera を使ってみた感想です。履歴の表示は [Ctrl]+[Alt]+[H] を押すか、メニューから選択します。HTML形式の
ファイルにまとめられているようです。キーワードで検索することもできます。
最初のうちエラーが発生することがありました。設定項目の「ユーザー補助」で、「マウスジェスチャー」と「スクリーン
リーダーへの適合」はオフにしました。後者は[Alt]キーの使い方と関連があるようですが、
私の場合マウスやキーの操作がもとでエラーになっているように感じました。設定変更後はエラーはほとんど発生しなくなりました。
(私はキーボードでの操作が主体ですから普通の人にはあてはまらないかもしれません。)
760EL(Win 2k)にもインストールしてみました。560(Win 95)の場合より起動が速いです。ハードウエアの構成や OSが違うので単純に比べることは
できませんが、Opera は動作が軽いといってもメモリー搭載量はやはり多いほうがいいようです。Win 2kはメモリー 64MBではシステムの起動にかなり
時間がかかりますが、その割にアプリケーションの動作は重くないので不思議です。Win 9xでは動作条件ぎりぎりのメモリ搭載量ではアプリケーションの
動作も重くなります。要するに OSの構造が違うということでしょうか。
前述の MIDPLUG も問題なく動作します。MIDPLUGには IE用と Netscape用がありますが、もちろん Netscape用を使います。インストーラーは
Netscapeのフォルダにインストールすることを前提にしているので、Operaに用いる場合はインストール先フォルダを指定し直す必要があります。
パソコンに備わっている音源は貧弱なので、私は Win 9x では YAMAHA製 MIDI音源(ソフトウエア MIDI、Win 9x専用)を購入して使っています。これは
音がいいのですが、残念ながら Win 2kには対応していません。760EL本体の ESS音源にはあまり期待していなかったのですが、意外と音がいいので
コントロールパネルで確認してみると、なんとローランドの音源が使われていました。Win 2k は MIDI音源を標準で持っているのでした。
2002年8月
パソコンに異動がありました。i1200 の投入に伴い、win 2k の実験機 760EL は役目を終えて私の手もとを離れました。このマシンに搭載していた
32MBの EDO DIMM だけはもったいないので 760E のメモリ増設に流用しました。i1200 のほうも、たまたま 32MB のメモリが格安で手に入ったので増設し
96MBとなりました。
しかし、この程度のメモリ増設ではあまり違いは生じないようです。もともと私が使っているアプリケーションに古いものが多く、たくさんの
メモリを要求しないということもあるのでしょう。760E(Win 98)は 48MB ->64MB に増強しましたが、起動にかかる時間はほとんど変わりませんでした。
i1200(Win 2k)は64MB ->96MB への増強で、これは多少起動が速くなりました。複数のアプリケーションを同時に立ち上げた場合のパフォーマンスは
メモリが多いほどいいのでしょうが、私はパソコンを使い始めてから長らく貧弱な環境でやってきたのでそういう使い方はあまりしないのです。
話は変わりますが、東京で開かれた WPC EXPO 2002を見に行ってきました。たまたま学校の中間試験と時期が重なったので、1日休暇をとって
新幹線で往復しました。一つには ThinkPad 誕生10周年ということでその関連の展示が行なわれていたということがあります。それと、最寄駅である「国際展示場」
まで行く東京臨海高速鉄道の東京テレポート〜天王洲アイル間がいつのまにか延長開業していたのでこの区間をついでに乗ろうというわけです。鉄道ファンで
ありながら、最近はあまり旅行に出かけることもなく、したがって時刻表も買わないので、ささやかな延長開業に気づかないでいることも多くなりました。
行きは「ひかり」が満席とのことで「のぞみ」を利用、東京駅から浜松町に戻って東京モノレールで天王洲アイルまで行きました。しかし、
東京臨海高速の天王洲アイル駅はずいぶん離れていてすぐにわからず、時間をロスしました。あまり目立たない案内板を注意深くたどっていくとオフィスビルを
2,3通りぬけたところに、地下駅に向かうエレベータがありました。東京臨海高速はこの地点では東京湾の下を走っているので、トンネルはシールド工法で掘った
と思われる断面の丸いトンネルでした。
WPC での IBMのブースは ThinkPad 一色でした。R30系、X20系、T30などのデモ機の中になぜか1台だけ i1200 が置かれていました。歴代の主な ThinkPad
も展示されていました。一応他社のブースもひと通り回った後、新木場経由で東京駅まで出て「ひかり」で帰りました。「ひかり」は出張帰りのビジネスマンで
込んでいました。
2002年10月