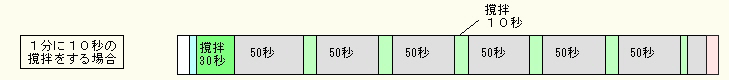
[現像のお話し Vol.08, 2002年05月17日UP]
このところ更新自体が久しぶりになってしまったんですが、ようやくモノクロ現像(フィルム)の完結編になります。 もちろんこれで最後にするわけじゃないし、もっと聞きたいことがあれば 「相談室」で答えますので、気軽に質問してください。 なお、いつものようにおやじ流で「上級編」としてますが、自分では割と基本的なことだと考えています。 でも皆さんそれぞれに要求や目的が違いますので、必要に応じて参考にしてみて下さいね。(^_^)
・現像編 … モノクロ現像で重要なのは、画像の「明暗」と「階調」をうまく出すことです
「明暗」
まず明暗ですが、これは全体の明るさのことで、これが足りないとネガは「薄く」なってしまい、
プリントすると暗い感じの写真(アンダー)が出来あがります。逆に多過ぎるとネガは「濃く」なってしまい、
普通に焼くと白っぽい写真(オーバー)になってしまいます。
明暗が変わってしまう原因には2つの要素があって、主に「露光」と「現像時間」です。
モノクロの場合この2つが明暗を決めるので、「現像の方法」で「露出」のかけ方自体が変わってきます。
もし、「標準的な現像」をするつもりなら、撮る時は「標準露光」をすることが基本になります。
「階調」
次は階調ですが、これは一般的に「トーン」とか「コントラスト」などと呼ばれ、具体的には白から黒までの変化のことです。
この変化があまり出ないと「軟調」となり、一般にはメリハリがないことで「眠い」と呼ばれます。
逆に白黒の変化が急過ぎると「硬調」になり、「硬い」と呼ばれるネガになります。
そして、軟調でも硬調でもないものは「中間調」と呼び、いわゆる普通の階調なんですが、ここで重要なのは中間調がベストではないことです。
つまり階調は写真の表現や意図によって変えるので、「合う・合わない」はあっても「良い・ダメ」はないんです。
|
・「アンダーネガ」と「オーバーネガ」 一般に薄めのネガを「アンダー」、濃いネガを「オーバー」と呼びますが、印画紙に焼きにくいのはアンダーの方になります。 そのせいかややオーバーめに仕上げる人も多いんですが、オーバーにも階調や粒状の問題が出てきます。 最初は安全にややオーバーにしてもいいですが、現像に慣れてきたら正確に現像するように心掛けましょう。 なお、お店に出すと「ややオーバー」が多いように思うのは、おやじの気のせいではないと思います。(^_^;) |
もし、続けて現像する時は、リールやタンク内の「水滴」を完全に拭き取って下さい。 現像前のフィルムに水が付着すると、そこだけ水滴状のムラができてしまいます。また、夏場にダークバッグでやるとけっこう暑いんですが、 手早くやるかタオルを入れるなどして「汗」がフィルムに付かないようにしましょう。
・薬品の準備
薬品は「薬品編」に書いてるように、出来れば前日までに用意しておきます。 ここでの「準備」は、使用できる状態に準備するという意味です。では、「使用できる状態」とは何でしょう?。 そうです、「液温」を合わせることです。現像は全て化学反応で進みます。ですから、適温の範囲が決まっていますので、 料理をするのと同じできちんと温度を守りましょう。
| −おいしい写真− おやじの偏見かもしれないですが、プロカメラマンには料理が得意な人も多いようです。 現像をやるとわかりますが、温度や時間の基本を守りつつ、経験と勘で条件を補正する作業は「料理」に似ている気がします。 おやじは「食う専門」ですが、いい結果が「時間と温度の加減」と「いい素材(撮影したフィルム)」によるのも写真と料理の共通点ですね。 皆さんもせっかく自分で現像するなら、出来るだけ手を抜かずに「おいしい写真」を作ってください。(^_^) |
詳しい温度調整の方法は「上級編」でやるつもりですが、ここでは以下の点に注意して薬品の温度を上げ下げしてください。 なお、最初は無理せず薬品の説明書やフィルムのデータシートに書いてある「推奨温度」と「推奨時間」でやった方がいいですよ。
1.現像液
現像液の温度管理は1番結果に影響しますので、正しく使うのが重要になります。通常は「20度」が目安になりますが、
結果を安定させるには「18度〜24度」の間におさまるようにしてください。なお、現像液の温度はそのまま「現像時間」にかかわります。
温度が範囲内に入っていても、時間が4分以下や15分以上になるような現像はしない方がいいと思います。
2.停止液
現像を止めるのが目的なので本来なら何度でも構わないのですが、出来れば「15度〜25度」の間で準備しましょう。
現像されただけのフィルムは表面がデリケートな状態になっていますので、10度以下の冷水や30度以上の温水にさらすのはちょっと危険です。
停止液は保存が出来ないため現像の直前に作るのですが、水温を20度前後に調整しておきましょう。
3.定着液
一般的な定着液は10度以下の低温では処理能力が極端に落ちてしまいます。しかも、30度以上の高温だと薬品がだめになってしまいます。
非常に面倒なんですが、事前に「18度〜25度」に調整しておきましょう。
そのために、冬場は30度以下のお湯でポリビンごと温めたり、夏は冷蔵庫でポリビンごと入れて下げたりします。
フィルム用の定着液は1リットルのポリビンで保管するのがいいと思います。
・道具の準備
現像は始まってしまうと「時間」との勝負になります。ですから、必要なものは前もって準備しておきますが、 作業中は混乱しやすいので余計なものを置かない方がいいでしょう。手の届く範囲は、必要なものだけ配置するのがベストです。 おやじの場合必要なものは、「フィルムの入ったタンク」「現像液の入ったメスカップ」「定着液のボトル」「水道の蛇口」「腕時計」「首にかけたタオル」です。 これを「流し」に用意して、これ以外は片付けてしまいます。(おやじは停止液を用意しませんが、使う人は用意しましょう)
|
−シミュレーション− ちゃんと用意しても、なれないうちは頭がパニックになることもあります。何十本もやってれば体が反応しますけど、 最初の頃はシミュレーションをしてみましょう。ばかばかしいかもしれませんが、口で確認しながら作業をすると一連の動きが身につくと思います。 特に、時間を計りながらタンクなどを振ると「いい練習」になりますよ。(^_^) |
まあ、ここまで問題なく準備出来たら、現像は80%成功したようなもんです。後は落ち着いて深呼吸でもしてください。(^_^)
・現像スタート!
さて、いよいよ現像をスタートするわけですが、いくつか作業をすることになります。流れに沿ってまとめて見ました。
| これは最初に入れる現像液をタンクに「注ぐ」ことです。「なんだ、ただ入れりゃいいじゃん」 と思うかもしれませんが、実は「手早く」「スムーズ」に入れる必要があります。というのも、この後の作業を1分以内にやらないと、 ムラが出やすくなるからです。細かい話しは次に書きますが、10秒以内をめどにしてください。 | ||
| 現像液が入ったばかりのタンクには「気泡」が入っています。多少は入ってても問題ないんですが、 フィルム面に「ついたまま」になるとそこだけ現像されないため、小さな穴が空いたようになります。 液を入れ終わったら、すばやく手でタンクの底を「トントン」と叩いてください。目安は5秒くらいです。 | ||
| 現像で1番難しく、1番重要な作業です。やり方や時間は人によって違いますが、今回はおやじの方法です。 詳しいやり方は後で説明しますが、簡単に言うとタンクを「振る」ことです。目的は液をタンク内で「循環」させるためで、 この作業で結果の安定性が変わり、やり方が悪いとムラを起こすこともあります。 | ||
| これは読んで字のごとく「待機」することで、「何もしないこと」です。 撹拌と撹拌の間はこの待機になりますが、タンクを動かすと液に余計な動きを与えてしまいます。手を触れずじっとしておきましょう。 それに手でタンクを握りっぱなしだと、体温で液温が変わってしまったりします。注意しましょう。 | ||
| さて、最後は「排出」つまり現像液を出すことですが、これは最初の注入と同じで手早く出すことが大事です。 注入と違うのは現像終了時間までに出し終わればいいということで、誰がやっても10秒以内に終わるでしょう。 時計とにらめっこしながら、終了する直前に液を戻してください。 |
現像で難しいのは「時間」と「作業」を正確に守ることです。その作業を時間のタイムテーブルで説明したいと思います。
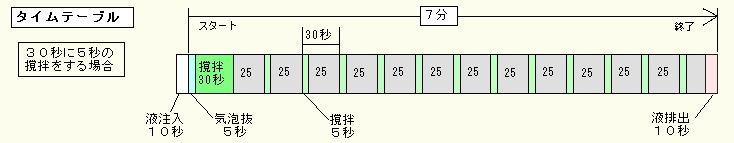
上の図は時間の内分けをグラフにしたもので、「7分」間の現像をする場合です。人によって違うんでしょうが、 おやじはこのようにします。まず手早く現像液を注ぎ、入れ終わった瞬間から時間を計り始めます。 そして、手早くトントンと底を叩いて気泡を抜き、最初の撹拌を連続で30秒やります。ここで一旦タンクを置いて、 時計が1分を指したら「5秒撹拌」してまたタンクを置きます。これを繰り返して「6分30秒」に最後の5秒撹拌をしたところで液の排出準備をします。 現像は液が出てもすぐには止まらないので、多少早めになっても大丈夫です。
30秒間隔があわただしくて難しい方は、下のように「1分間隔」にすることも出来ます。どちらがいいということはありませんので、
自分の好みで選んで見てください。なお、この場合は撹拌も倍の「10秒」になります。1つ重要なことは、自分で決めた方法は守るということです。
いつも違うやり方でやってると、撮影の露出も含めて結果が安定しなくなります。特に初心者はね..(^_^)。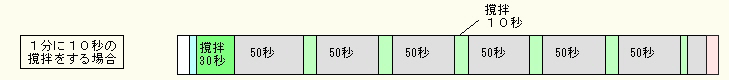
・スムーズな注入
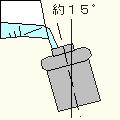 |
液をスムーズに入れるには、タンクによって違います。ベルトタイプや片溝式のようないわゆる「おわん型」は空気抜きが付いてますので、
よほど急いで入れない限りスムーズに入ると思います。しかし、金属タンクは口が狭く空気が抜けにくいので、左の図のように少し傾けて入れることになります。
この時、口全部をふさぐほど液を注ぎ込むと、空気の逃げ場が無くなってかえって入りづらくなります。上に少し空間を空けて注いでください。 もう1つコツとして、自分のタンクが「何ccで一杯になるか」を調べておきましょう。それを10秒間で注ぐわけですから、大体感覚がつかめますよね。 フィルムを入れないタンクに水を注いで、何回か練習してください。(^_^) |
・おやじの撹拌
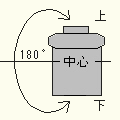 |
「撹拌」というのは「タンクを振ること」と書きました。では、どう振ればいいんでしょう?。実は個人でやり方が違いますし、
タンクの違いでも変わります。金属タンクで説明しますが、おやじの場合は左図のようにタンクの上下を入れ替えるだけです。
手首をひねるようにして回し、1回転を「1秒」でやります。(5秒撹拌なら5回ですね) これじゃ弱いと思う方もあるでしょうが、撹拌の目的は現像液を「対流」させることにあります。 沈殿した濃縮ジュースを振ればわかると思いますが、上下や左右に降るより、手早く回転させる方が液の移動が起こりますね。 「対流」に偏りや部分的な流れも起きにくく、今のところこれが1番安定しています。(^_^) |
・停止
ここまででずいぶん長くなったので、この先どうなるか心配でしょうが、実は「停止」まで行くとそれほどあせる必要はありません。 停止液を入れてしまうと現像が止まるので、後は定着液を入れるだけです。ここで注意することといえば、現像液を出したらすぐに入れることだけです。 「30秒」ほど連続で撹拌したら、停止液は捨ててしまいましょう。後は定着です。(^_^)
| −停止液の作り方− 停止液の作り方は「水1000cc」に「酢酸15cc」を入れるだけです。ただの「1.5%の酸性液」ですね。 保存も利かないし再利用も出来ないので、使ったら捨てましょう。なお、酢酸は写真用に70%の純度のものもありますから、 その場合は「21cc」になります。もっとも、おやじは面倒くさいのでただの水でやってますが..。(^_^;) |
・定着
定着もこれといって難しいことはありません。細かく話したいこともありますが、ここではやらずに「上級編」でやりたいと思います。 先に書いた「適温」と、「処理本数」さえ気をつけていればそれ程問題はないはずです。 時間は約10分(正確な時間はデータシートに書いてあります)程度で終わりますが、定着中は一応「撹拌」してください。 この時の撹拌は現像ほど「シビア」じゃなくてもいいですが、やらないとまずいので必ずしてください。 これさえ終わればフィルムは「ネガ」になってるはずです。後は水洗して乾燥させるだけです。(^_^)
| −定着終了− ここまで来ると光に当てても大丈夫なので、定着液をポリビンに戻してタンクを開けることになります。 ネガを見て異常がないか確認しましょう。稀に透明になってない場合がありますが、「定着不足」か「定着不良」です。 すぐに蓋を閉めて定着液を入れ、液に問題がないか調べましょう。定着不足なら時間をかければ透明になりますが、 定着不良(何らかの原因で定着が進まない)場合はあきらめることになります(T_T)。ま、そんなことがないように、 現像前にフィルムの「切れ端」を使って定着液の確認した方がいいでしょうね。(^_^) |
・フィルムの水洗
簡単に言えば「水で洗ってください」ということです。大体20度くらいの「水道水」をチョロチョロ流せば1時間くらいで終わるでしょう。 でも実は、ここにもいろいろ書きたい話があるんですが、これも次の「上級編」へ持ち込みます(^_^;)。長くなりすぎますからね..。 なお、この段階ではタンクの「上フタ」も開いてると思います。蛇口からタンクへ水を落とすことになるんですが、 強く出し過ぎると泡だらけになって薬品が落ちないこともあります。あくまでも「チョロチョロ」ですよ。(^_^;)
・フィルムの乾燥
 |
さて、水洗が終わるとフィルムを乾燥させるわけですが、ちゃんと乾かさないとムラが出来たりカールして後で困ったりします。
最後まで手を抜かず、きちんと仕上げましょう。 なお、この時使うのが左の「フィルムクリップ」です。他のもので代用できるかもしれませんが、高いものではないので揃えた方がいいですね。 2個で1セットになっており、濡れたフィルムの両端につけて吊るすことになります。このクリップは「おもり」になっているので、 フィルムがカールせず乾燥させることが出来ます。 ちなみに、36枚のフィルムはつるすと1.5mくらいになります。高い場所に吊るさないと乾燥できないので、場所も考えてくださいね。(^_^;) |
ところで、水滴がついたままフィルムを乾かすと「水滴ムラ」が起きてしまいます。これを防ぐには乾燥前に水滴を拭き取る必要があります。 いくつか方法や道具があるんですが、下の2つが代表的なものです。
1.スポンジを使う場合
スポンジは食器を洗うものではなく「写真用」を使ってください。黄色い海綿状のものや、白いハンペン状などが写真屋さんで売ってます。
なお、乾燥させると使えなくなるものもありますし、汚れてるとフィルムを傷つけることもあります。きちんと手入れをして使いましょう。
使い方はクリップで吊るした後、二つのスポンジを使ってフィルムの裏と表から挟みます。あまり力を入れないように、上から下へ動かします。
途中で止めたり途中からやったりせず、上から下へ一気に拭き取ってください。
2.ドライウエルを使う場合
「ドライウエル」は富士フイルムの商品名です。中味は「界面活性剤」というもので、薄い中性洗剤のようなものです。
これを水洗が終わったフィルムに付けると、表面に水滴が出来ずに水が下に落ちてくれます。
フィルムに直接触らないので傷をつける心配はないんですが、ホコリやゴミがついてしまうと乾いた後で手におえなくなってしまいます。
スポンジで処理したフィルムもそうですが、乾燥の時のゴミ、ホコリには十分注意してください。
| 乾燥中の乳剤面は柔らかくなってるんですが、これが乾く時にホコリがつくとフィルムに食い込んだようになってしまいます。 こうなると、ネガから取るのはまず無理です。乾燥中は極力注意しましょう。風呂場などを使うといいかもしれませんが、 窓を閉め切って風が入らないようにしないと、ホコリだらけになりますよ。まして、ドライヤーなどで乾かすのは良くないですね。 おやじは部屋を閉め切ってフィルムを吊るし、乾燥する1〜2時間は外出して部屋にいないようにしています。(^_^;) |
・フィルムを整理する
乾燥が終わったネガはハサミで「6コマ」ずつ切ってネガシートに整理します。36コマ以上写すとこの時困るので、 おやじは「36枚」で撮り終るようにしています。人それぞれなので「5コマ」カットで収納してる人もいます。 また、ネガシートもいろんなタイプがありますので、皆さんが気に入ったものを使ってください。 ここでの注意点はありませんが、コマ間は「2mm」くらいしかありません。誤って「コマ」を切ってしまわないように..。(^_^;)
|
こうやって書いて見ると、基本だけなのに「長編」になってしまいましたね(^_^;)。
おやじが最初に現像をしたのは13歳でしたが、濃度の薄い「現像不足」というネガになってしまいました。
多分、現像中に液温が下がったんだと思いますが、自分で写真を作ったような気になって嬉しかった憶えがあります。(^_^) 今回は何度も「失敗しないように」と書いていますが、恐らく失敗なしで「現像」を身につける方はいないと思います。 おやじは大学時代でも、現像液と定着液を逆にして「素抜け」のネガにしたことがあります。 でも実は液を間違えたのは先生だったんです。今は笑い話ですが、あの時は「愕然」としましたね。(^_^;) |