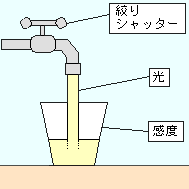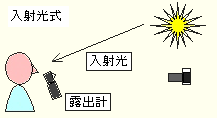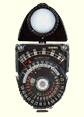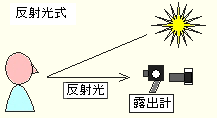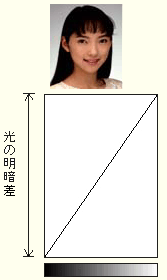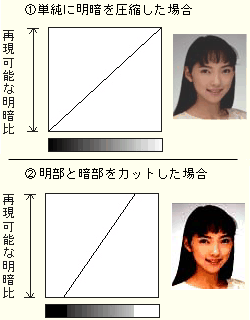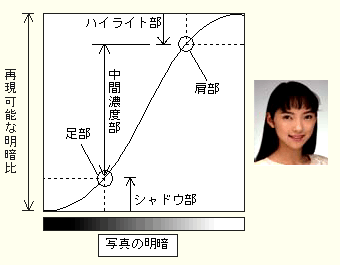「露出」って何?
[写真一般のお話し Vol.05, 2000年10月24日UP]
この話しをするならもっと早い時期にやるべきだったんですが、最近はAFに自動露出なので説明しなくていいと思い込んでました。
でも、皆さんの話しを聞いてると「やっぱり露出って難しいのかな?」と考えてやることにしました。
ただ、この話しも本格的にすれば相当ムズカシイです。(それこそモノクロの「ゾーンシステム」まで行っちゃいますし..。)
それに頭の中で理論がいくらわかっても、実際に撮ってみて「感覚」を身につけないと役に立たないのは事実です。
ま、何にせよ写真は「経験」ということで..(^_^;)。
・「露出」とは..
皆さんは「露出」というと何を思い浮かべますか?。あまり良くない例えですが「露出狂」などの言葉があるように「さらす」という意味があります。
フィルムに画像を取り込むには、「光にさらす」ことが必要で、英語では「Exposure」(露光)といいます。
そして、露光するのに最適な値を出すことを「露出」と呼んでます。(でも良く考えると「露光値」の方がいいような気もするなぁ。
だって「自動露出」って自動でシャッターが切れるみたいなイメージが..。)それでは、下の簡単な例で具体的に説明します。
露出の概念は右の図のようになります。まず、「光(この場合は水)」の量をコントロールする2つ要素「1.絞り」と「2.シャッター速度」
(この場合は蛇口の栓)があります。そして、受けるフィルムの「感度」(コップ)にマッチさせるのが「露出」です。
「ぴったりの量」にすることで最適の画像が得られますが、多すぎると水があふれ(露出オーバー)、足りなければコップが一杯にならない(露出アンダー)ので、
栓(絞りとシャッター)をひねって調節することになります。
「絞り」は開ける栓の「口径」で、開く程たくさんの水(光)が出ます。「シャッター」は開く「時間」で、
長くあければたくさんの水を出すことが出来ます。一方「感度」は、一杯になる「速さ(スピード)」で、高感度フィルムはコップが小さく、
低感度は大きいサイズと考えればわかりやすいです。
このことから、感度と被写体の明るさが同じなら、「一定量の光(水)」をカメラに取込めば露出は合うことになります。
つまり「少しずつ長い時間出す(長時間露光)」ことも、「たくさんの量を一気に出す(高速シャッター)」ことも出来るわけです。
具体的に感度100のフィルムで露出が「F11で1/125秒」だったとしたら、「F4で1/1000秒」や「F32で1/15秒」で写すことが出来ます。
|
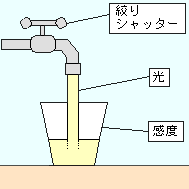 |
「絞り」の数字的な説明は、以前に書いた‘「レンズ」ついて’をご覧ください。
「シャッター速度」はそのままシャッターが開いてる「時間」ですので、1/125秒は、1/250秒の2倍の時間だけ開いていることになります。
また、シャッターと絞りの組合わせを変える時には「計算上」は大丈夫でも、実際には問題が出ることがあります。
これが「相反則不規」で、超スローシャッター(10秒以上とか)を使った時などに起きます。
リバーサル以外では気にする必要はないと思いますが、あまり極端な組合わせをしないようにするか、フィルムの箱に書いてある可能な速度範囲を確認しましょう。
|
・自動露出について
さて、じゃあ一般のカメラに採用されてる「自動露出」って何でしょう?。
そうです、コップが一杯になるところを自動で測ってくれる仕組みのことです。
風呂の「自動給湯システム」と似たようなもんで、ちゃんと適量を満たしてくれればこれほど便利なものはありません。
でも、的確に測らないと「全て」失敗してくれる危ないものでもあります。(^_^;)
ということで、次は自動露出の要「測光方式(光を測る方法)」を説明したいと思います。
1.測光方式
光の測り方はいろいろあるんですが、大きく分けると次の二つがあります。
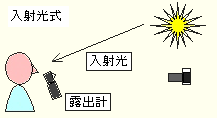 | 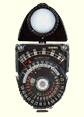 |
入射光式というのは、被写体にあたる光を測る方法です。光だけを測るので被写体の色に左右されず、正確な露出を得られるのが特徴です。
そのため、被写体の色が白なら白に、黒なら黒に写すことができます。
欠点としては、被写体のところまで行かないと測れないことで、カメラに組み込んだりすることは出来ません。
また、被写体に届く光の「角度」や、露出を決める光線を見極める目が必要になりますので、
慣れない初心者が使うにはやや難しいかもしれません。(ちなみに、ストロボを測るメーターはこのタイプが多いです。)
|
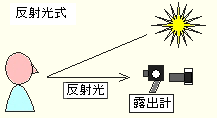 |  |
こちらは、被写体に反射した光を測る方式です。離れた場所から測れるので、カメラに内蔵させることも出来ます。
覗きながら測るので、露出に必要な部分を確認しやすいメリットもあります。欠点は反射した光の強弱をとるため、
被写体の明るさで露出が狂うことです。測定結果はすべて18%のグレイになるよう設定されてるため、
そのまま写せば被写体が白でも黒でも「グレイ」になります。
この18%というのは、世の中の被写体を平均化するとこの反射率になると言われ、全ての反射光式で基準になっています。
(この方式は単体の露出計型もありますが、カメラに組み込まれたタイプが多いですね。)
|
2.自動露出の種類
さて、上の説明でわかるように、カメラの自動露出に組み込むには「反射光式」じゃないと不可能です。
とすると、上で説明した「18%グレイ」で計算する欠点があるわけで、それを補うためにいろいろな工夫がなされてきました。
| 平均測光 |  |
これは、カメラに写る範囲を全て同じように測る方式です。大昔の一眼レフや、安いコンパクトカメラは今でもこの方式ですが、
どちらかといえばもう過去の測光方式です。どこも同じレベルで光を測るため、画面の片隅に太陽や空があったりすると、その分まで平均値に入れて計算します。
そのため、被写体が明るいと判断を誤り、結果的に露出不足になり、アンダーで黒っぽい写真が出来てしまいます。
よって、この方式のカメラは人間が手で補正する「露出補正」機能がついており、本当の意味で「自動露出」とは言いがたいです。
|
| 中央重点測光 |  |
平均測光の欠点を改良した方式で、正確には中央重点式平均測光といいます。最近の一眼レフでも使われていますが、少し前の主流でほとんどはこの方式でした。
図を見るとわかりますが、中央部分を重要視して周辺に行くほど計算に反映しないようになっています。
これは、「大事なものは写真の真中に入れる」という発想で、真中をメインに測るわけですが、空や太陽が入っても測定が狂いにくく、
単純な発想の割に意外と良い結果が出ます。
もちろん真中が被写体じゃないのに白いものがあったりすると露出が狂うわけですが、平均測光に比べると失敗しにくいようです。
|
| スポット測光 |  |
この測光はプロ用の一眼レフなどに採用されている方式です。ピンポイントの中央部分だけで光の強さを測ります。
露出になれている人は、被写体のどこの部分を測ればいいかわかるため、全体を平均的に測るよりもこちらを好むことが多いです。
一番の特徴としては、シャドウやハイライトの露出も「部分的」に測れるため、輝度比を調べたり、細かい露出設定をすることが出来ます。
欠点としては1点のみの測定になりますので、被写体の測る場所を自分で判断できないと結果が大幅に狂うことになります。
あまり初心者にはお勧めできない測光方式です。
|
| パターン測光 |  |
基本的には平均測光なんですが、エリアを何個かにわけて測る方式です。
AFが普及して被写体までの距離がわかるようになったため、「何」を写すのかカメラが判断し、パターンを変えて測光します。
具体的なパターンは、カメラやメーカーによって違いますが、だいたい20パターンくらいで被写体を予想しているようです。
現在、主流になりつつある方式ですが、初心者でもほとんどカメラ任せに出来るメリットがあげられます。
欠点としてはパターンが当たらなかったときは露出が大幅に狂ったり、思った写真とぜんぜん違う結果になったりすることがあります。
|
これらの測光方式にはそれぞれ一長一短ありますので、自分にあった方式のカメラを選びましょう。
すでに持ってる人でも、自分のカメラがどの方式(切り替えできるカメラもあります)なのかを知っておくと失敗が減らせると思います。
そして、ここで重要なことは被写体によって「カメラ任せに出来る」状況と、「出来ない状況」があり、
写すときに見極めが出来るように経験を積むことです。
自動露出が間違った結果を出すのが最初からわかってる場合、カメラで「露出補正」をします。
プラスやマイナスの数字(たいていは1か2)が書いてあるのがそうで、プラスに設定すると明るくなり、マイナスにすると暗く写るようになってます。
(「1」で1絞り、「2」で2絞り分変化します)
この方法以外にも、必要な部分で測った露出をホールド(固定)できる「AEロック」というのもありますが、
どちらを使うにしても「使うべき状況」がわからなければ意味がないです。
やはり場数を踏むとともに、自分のカメラの測光の「癖」はしっかりと身につけましょう。(^_^)
|
・適正露出について
さて、今度は「適正露出」の話しなんですが、ここから少し話しが難しくなってきます。
そもそも皆さんは、「適性露出」って何だと思います?。最初のコップと水の話しでは「ぴったり」になればいいように書いたんで、
なにかピンポイントで「解答」があるように感じたと思います。でも、実は「露出」って正解の「絞り値」と「シャッター速度」を見つけることではありません。
被写体の「明暗比」を感材や画像の「再現可能な範囲」に収めることなんです。
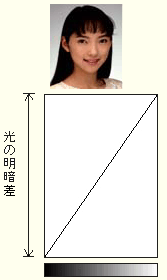 |
←まず左の画像とグラフを見てください。
一般的な撮影条件でも「光の当たった白」と「光の当たらない黒」の明暗差はかなりあるものです。
でも、それを再現する「写真」にはそんなに広い明暗を描画できる性能はありません。
つまり、どこかを「省略」しないと写真画像にするは「入りきれない」わけです。
そこでまず「省略」を単純にやると右上のグラフようになります。「単純に圧縮」は簡単な作業ですが、できあがる画像は写真でよく言う「眠い」状態になります。
これは画像に大事な「中間濃度」が圧縮されるので、全体としてメリハリのない写真になってしまいます。
別の方法として、右下のグラフのように大事な中間濃度はそのままにして、「明部(ハイライト)」と「暗部(シャドウ)」を切ってしまうことも考えられます。
しかし、実際には画像の「黒」がつぶれ、「白」の情報も飛んでしまうので、写真としては不自然なものになってしまいます。
ということで、フィルムや印画紙の銀塩感材では、次に説明するような「緩いSカーブ」を用いて明暗を圧縮し、画像を再現しています。
これを写真の世界では「特性曲線」と呼び、フィルムなどの性能を表す場合に使います。
| 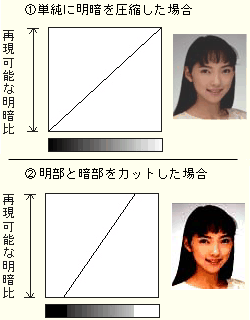 |
右のグラフが一般的なフィルムなどの特性曲線ですが、これは3つの部分に分かれます。ひとつは上の方を分けている「ハイライト」で、
レースのカーテンなどの「白い部分」表現する部分です。
ただ、ここにたくさん画像情報を与えてもあまり見た目が変わらないので、普通は緩やかに圧縮されています。
次は下の部分の「シャドウ」で、こちらは黒い髪の毛などの描写をする部分です。
ここもハイライトと同じであまり見え方は変化しないため、圧縮された状態になります。
ただし、圧縮されていてもハイライトとシャドウは写真に重要な部分です。
圧縮をかける濃度とカーブで写真の印象は大きく変わります。その重要な部分が「肩部」と「足部」で、グラフに書いてる丸の部分です。
これはカーブを人に見たてて、上を肩、下を足と呼んでるわけです。
つまり、「露出」とは画像の白を肩に、画像の黒を足に当てはめることが本当の目的で、
例えば「人間の顔」の明るさが、中間濃度の「真中あたりにくればいい」というものではありません。
そして、うまく明暗が画像の再現範囲と一致する露出を「適正露出」というわけです。
| 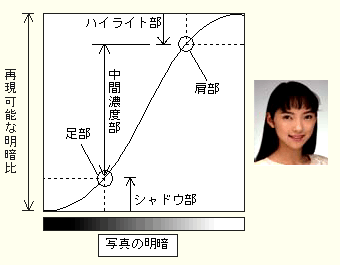
|
しかし、実際のフィルムはこんなにきれいな「S字カーブ」をしていません。フィルムの製造ロットによるバラツキや、
現像液の劣化ですぐに「歪んだS字」になってしまいます。また、仮に理想的な「特性曲線」だったとしても、
夏の炎天下で白い服なんて場合は明暗差を収めるなんて不可能です。(^_^;)
そこでカメラマンは「補助光」や「レフ板」を使ったり、日陰や逆光を利用してなんとか写真の再現範囲内に近づけるわけです。
ただ、どうしても入りきれない時は「ハイライト」か「シャドウ」のどちらかが犠牲になります..。(^_^;)
一口に「露出」と言っても、実に難しく奥深いものです。(-_-)しみじみ..
[おまけ]
最後にマニアックな「おまけ」を書きます。単体にしてもカメラ内蔵にしても、露出計には「受光素子」というものが使われます。
これは光を受けて信号を出したりするもので、いくつかの種類があります。雑学として表にまとめてみました。
| 受光素子 | 読み方 | 特徴 |
| Ce | セレン光電池 |
古くからある受光素子です。光電池というように、それ自身が光の量に応じた電流を流します。
したがって、動作に電池を必要としないメリットがあるんですが、素子が劣化しやすいとか、測れる光の範囲が狭いなどの欠点もあります。
どちらかというと安物のイメージがあるんですが、中にはおやじも使うプロ愛用の「スタデラL−398」や、「ゴッセン」などの高級機もあります。 |
| CdS | 硫化カドミウムセル |
これも昔からある受光素子で、よく一眼レフに組み込まれていました。CdSは光を受ける明るさによって抵抗値が変わる性質があるので、
電流を流すことで露出を測ることができます。電池が必要になるものの温度変化や劣化にも強く、安定した動作が特徴です。
唯一の欠点は低照度での感度が悪いため、暗いところの測光が苦手です。 |
| SPD | シリコン
フォトダイオード |
シリコンを使ったダイオード(整流器)で、やはり光の強さで流れる電流の強弱を変化させます。
アンプを組み合わせることで測光範囲を広くすることが出来るため、ある程度暗い場所でも測ることが出来ます。
CdSなどに比べるとやや電池を食う欠点はありますが、光の変化に対する反応も速いため現在では最も普及している受光素子です。 |
| GaAsP | ガリウム砒素リン
フォトダイオード |
原理や特徴はSPDとほぼ同じものです。シリコンをガリウムや砒素、リンの化合物に置きかえた受光素子です。
一部のメーカーが「SPDより反応が速い!」と自慢してカメラに採用してましたが、SPDほど普及しませんでした。
実際に使ったことありますが、確かに反応は「速い」です。しかし過敏に反応しすぎて、どこで露出を決めていいか判断しづらいものでした。
その後、改良されて動作を抑えたものになりましたが、「それじゃSPDと変わらないだろう!」と突っ込みたかったおやじです。(^_^;)
|
店内に戻る
TOPに戻る