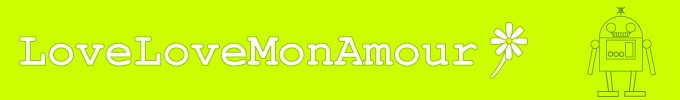
|
キミのフェロモン 前編
新二年生の約七割は、始業日の三日前には転校生が来ることを知っていた。 ”美少女である” その一言が噂の伝播に一役を担ったのは確かだろう。 しかし、ここまで早く、素晴らしい勢いで広がった一番の理由が、転校生が引っ越してきた家の隣に住んでいたのが澤井陽雪(つゆき)であったからなのは、誰の目にも明らかだった。 なにを好んでそんな所に引っ越したのか?そう思った者は少なくない。 澤井陽雪は”パパラッチ”の異名を持つ。 人の噂が三食の飯より好きな彼女の犠牲になった生徒は数知れない。 しかし、本物のパパラッチと違うのは、彼女がもたらす情報は信頼性が高いことを皆が知っていることだ。 標的にされた者には迷惑で恐ろしい話だが、一聴者の立場にとっては有能な話題提供者になる。 「女子の言による美少女」といった一見信憑性のない話も、澤井陽雪から伝わってきたとなれば、その言葉に何度も騙されてきた男子たちの間でも抜群の信頼性を持ち、あっという間に広がっていった。 始業日当時の朝までその情報を知らなかった二年生は、必殺技を編み出すべく山篭りをしていた将棋部 伊刈竜平だけだった。 もちろん、始業日の朝はその話題で持ちきりである。 噂を広めた澤井陽雪が春休みの間に彼氏と別れた話なんかは、皆の頭から完全に消え去ってしまっていた。 別れた彼氏、新井竹緒が転校生の話を知ったのは始業日の四日前の夕方だった。 携帯電話のディスプレイに映し出された発信者名に、わずかな期待と共に取られた受話器は、一分後には深いため息とともに下ろされた。 転校生の情報だけを一方的にしゃべって電話を切られれば、十日前に別れを告げてきたモトカノは自分に全く未練を持っていないことがにぶい竹緒にもやっと了解できた。 それが意図したものだったのかは不明だが、情報を広めつつも、竹緒にとどめをさしたのだ。 たいしたものだと、受話器と一緒にベッドに転がりながら思う。 でも、陽雪のそのさっぱりしたところも嫌いではなかった。 「私のことは忘れて転校生を狙え、ってことじゃないよな」 陽雪がそんな気を利かせる人間でないことは良く知っているし、竹緒がそんなに簡単に気持ちを入れ替えられる人間でないことを陽雪は知っているはずだ。 ただ、噂を広めるという欲求を満たす為に電話をしてきただけだ。 「美人の転校生か……」 自嘲にも似たその淡い期待は、四日後にあっさりと潰された。 「やぁ」 始業日の放課後、竹緒が校舎の屋上のフェンスに暗然とぶら下がっていると、明るい表情の澤井陽雪がやってきた。やけに嬉しそうに笑っている。 陽雪は美人ではないが、愛嬌のある笑顔を持っている。 ”パパラッチ”なんてあだ名を持っている噂好きは一歩間違えば嫌われ者になってしまいそうだが、陽雪はその笑顔のおかげで人気者だった。噂を流されても、陽雪なら仕方がないかと許させてしまうのだ。 竹緒がその笑顔を見たのは二週間ぶりだった。あの日、別れ話を切り出した時も、陽雪は今と同じように笑っていた。 竹緒は手に持っている紙パックの中に残っていたカフェオレを一気に吸い込んだ。 「なにやってんの?」 「会議があるから帰るなって部長に言われた」 「園芸部は一年生の部屋に集まってたぞ」 「帰るなって言われてから帰ってない」 「あいかわらず子供だな」 竹緒に並んで陽雪もフェンスにもたれかかる。校舎の屋上から四階分下では、体育会系の生徒が散らばって、グラウンド整備をしている。満開を少し過ぎた桜の花が、その隙間をぬうように舞っていく。 吸い過ぎた紙パックがべこべこと音を立てて潰れる。 「それで、五十鈴百音(いすずももね)となにがあったの?」 陽雪が満面の笑みを向けてくる。竹緒は春の空に向かって深い深いため息をついた。 「そんなの、オレが訊きたい」 特に意識はしていなかったが、登校して見れば噂の美少女転校生とクラスが一緒だった。しかも出席番号の巡り合わせで隣の席となれば、それなりに期待が沸き起こってくる。 男子生徒たちからは羨望と妬みが入り混じった視線を早くも向けられていた。 担任の紹介で現れた五十鈴百音は、皆の期待にそぐわぬ美少女だった。 澤井陽雪の信頼度が確実に十ポイントほど上がった。 黒板に白いチョークで書かれた、五十の鈴に百の音、なんて名付け親の感性を少々疑ってしまう名前も、彼女の美貌が全てを納得させた。 自分の魅力を知り尽くした笑顔と一緒に簡単な自己紹介が終わったときには、男子も女子も、クラス中が彼女のファンになっていた。 「五十鈴には窓際の一番前の特等席を用意しておいたぞ」 担任の岩坂先生も舞い上がって、そんなことを口走った。 「新井、ちゃんと面倒をみてやれよ」 せっかく振ってもらった千載一遇のチャンスだったが、それをうまく生かすことはできなかった。 それは担任に「あらい」と名を呼ばれたときだった。 その名を耳にした五十鈴百音は竹緒を見て大きく目を見開いた。 竹緒は自分がそんなに注目を集めるタイプでないことは知っている。背は男子の平均よりも低く痩せ型だ。顔はメガネをかけているのが唯一の特徴である平凡なものだ。背後の席でオーラを放っている将棋部の伊刈君とは違い、身体から発するものはなにもない。 そんな自分を見るのに、大きく目を見開く百音のしぐさは全くふさわしくなかった。 担任の前振りに合わせて愛想笑いを見せる、それがこの場にふさわしいしぐさのはずだ。 しかし百音は、一度大きく目を見開いて竹緒を凝視した。その時間はどれほどだったろうか?一度眉間に皺を寄せると今度はふいっと目を伏せて、自分の席に歩いていき、座った。 座る前に、後ろの席の伊東香莉奈が小さく振る手に応えて笑顔を見せた。その後はじっと黒板のほうを見て、竹緒には全く視線を向けない。 「新井、面倒を見ろとは言ったが、ずっと見張ってろなんて言ってないぞ。あ、見張ってるんじゃなくて見とれているのか」 目ざとい担任のつっこみに笑いが起こる。 「違います」と口の中で反論しながら目を逸らした。 竹緒の席は、自然に彼女を見るには一番不適切な席だ。だから、彼女がその時どんな顔をしているのかはちっとも分らなかった。 体育館で行われた始業式には、伊東香莉奈とその友人たちが転校生を連れて行ったから、竹緒の出番は全くなかった。もっとも、始業日前から二年生中の注目を集め、体育館に入れば校内中から注目を浴びることになった人物をエスコートするような度量はなかったから、助かったとさえ思った。 同じクラスになった友人たちに先ほどの失敗を冷やかされながら体育館に入れば、今度は並んでクラスの一番前に並ぶことになった。自分に向けられているわけではないと分っていたが、突き刺さってくる視線が痛かった。 三回ほど隣を盗み見た。髪がかかった横顔はとても端正で綺麗だった。 改めて思う。 あの見開いた目の意味はなんだったのだろうか? その疑問が解決する前に、竹緒はもう一度その目を見ることになった。 始業式が終わった後のホームルームで、新しいクラス恒例の自己紹介が行われた。 窓際の一番前の席である百音の自己紹介がすでに終わっていたので、廊下側の一番の後ろの席から始まったアピールの主な矛先は明らかに転校生に向けてだった。 様々な笑いを伴いながら、竹緒まで順番が回ってくる。 「新井竹緒です。一年B組でした。園芸部の幽霊部員です。よろしくお願いします」 今日は一度目立ってしまっているから、あまり派手なアピールはしなかった。 もっとも、パパラッチ澤井陽雪と付き合っていたので、すでにそれなりの有名人になってしまっている。 席に着く前に百音の反応をちらりとでも見たいと思い、座りつつ首を廻らせた。 そして再び、大きく見開かれた目を見た。 さっきよりも大きな目だった。 自己紹介が始まってから、竹緒は一度も百音の方を見ていなかった。だから彼女がクラスメートの自己紹介にどんな反応をしていたのかは知らない。 でも、他の人に対してはこんな表情を見せていなかったと断言できるほど、大きな目だった。 しかし、竹緒の視線に気づくと、すぐに悠然と立ち上がった伊刈君に向けられた。 竹緒も仕方がなく視線を切りながら、あの表情の意味はなんなのだろうと思う。伊刈君の皆を爆笑に誘う自己紹介に紛れて見た彼女の表情は、普通に笑っているだけだった。 ホームルームの後の大掃除中も、下校時間になっても、竹緒に百音と話す機会は与えられなかったから、あの目の意味を知ることはできなかった。 もっとも話せたとしても、どうして僕を見るときはびっくりしたかのように大きな目をするんだ、なんて訊けるはずもない。 更には、どうして僕を避けるんですか、なんてとても訊けない。 そう、自己紹介が終わった後の五十鈴百音の行動は、明らかに新井竹緒を避けていた。 「それで落ち込んでこんな所でたそがれてるんだ」 澤井陽雪の細い目が大きく見開かれる。興味深々になった証拠だ。 残念ながら陽雪がどんなに頑張っても、百音の目の大きさには全く適わない。 「別に落ち込んでない」 なんだか一人になりたくなっただけだ。 「ふぅん。タケにはなにか思い当たるところはないの?実は春休み中に会ってたとか」 「いや」 「ずっと子供のころに会ったことがあるとか」 「………ないと思う」 あれほどの美貌なら、子供のころから飛びぬけてかわいかったに違いないが、そんな美少女の記憶はなかった。 「そ」 短く言って陽雪はフェンスから離れた。竹緒から取れる情報は取りきったと判断したのだろう。彼女のさっぱりとした性格は身に染みている。 しかし、陽雪は予想に反して、思いがけない言葉をぶつけてきた。 「彼女、タケに興味があるみたい」 「なにが?」 思わず振り返ってしまうと、陽雪がいたずらっぽく笑っている。 「クララが言ってた。それとなくタケのことを訊いてたって」 クララこと茂木倉子は、陽雪とも仲の良い伊東香莉奈の友達の一人だ。陽雪は情報収集をした上で、竹緒のところにやってきたのだ。 「なんで?」 「さぁ、自分で訊いたら?明日は一緒に日直だろ」 陽雪はくるりと背を向け、「気が向いたら結果を教えて」と言いながら手を振った。 「澤井さん」 その背中を竹緒が呼んだ。 「なんでオレと付き合ったの?」 唐突だったのに、もう一度くるりと半回転した陽雪は笑顔だった。 「なんで別れたの?、じゃなくて付き合ったことなんだ」 告白してきたのは陽雪からだった。なんで自分なんかと付き合おうと思ったのかを聞きだす前に、別れ話を切り出された。 もちろん、別れの理由も聞き出せていない。 不意をつかれて戸惑っている竹緒に、陽雪はやさしく微笑む。 「強いて言えばそんなところかな。じゃ、グッドラック!」 ビっと親指を立てて今度こそ去っていった。昇降口に姿が消える。 「どっちがだよ」 似合わないことに悩むもんじゃないと頭を抱える。 息をぷーっと吹き込むと、紙パックはベコベコと膨らんだ。
|