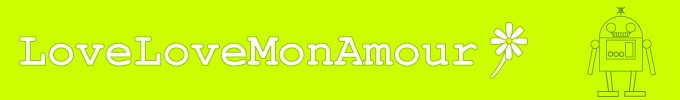
|
キミのフェロモン 前編
「おはよう」 「お、おはよぅ」 伊東香莉奈一派に囲まれている五十鈴百音に朝の挨拶をすると、びっくりしたかのように少し上ずった声で応えてくれたが、その後すぐに目を伏せられた。 心の中でちょっだけ落ち込みながら続ける。 「五十鈴さん、今日はオレと一緒に日直だから」 意識しすぎたって仕方がない。それが昨晩出した結論だった。 昨日は百音に避けられているように感じたが、ただの錯覚かもしれない。彼女は男子が苦手なだけなのかもしれない。自分も陽雪のせいで転校生に対して意識しすぎていたのだ。自意識過剰すぎたのだ。 陽雪が屋上まで来て言い残していった言葉、「それとなくタケのことを訊いてたって」ってのも気にはなる。 しかし三ヶ月の付き合いの中でも、結局表面上のことしか知ることができなかった。今更、陽雪の思惑を見通せるとは思えない。 だったらへたに考えてもしかたがない。五十鈴百音に対しても普通に付き合えば良い。 転校生を迎えた一男子生徒の役で良い。 嫌われているのならそれはそれでそれまでのことだ。 そもそも、自分は女子に人気のあるタイプじゃない。 だから日直を口実にしても否定の言葉が出てくることを覚悟していたが、百音は素直に席を立った。 「ちょっとごめんなさい」と伊東香莉奈一派の包囲網から出てきて言った。 「なにをするの?」 百音の背後から女子たちが思わせぶりに視線を向けてくる。陽雪と仲の良い茂木倉子もその中にいる。竹緒はそれらを気にしていないように振舞いながら、百音を黒板へ連れて行った。 「そんなに大した仕事はないんだけど。とりあえず朝は黒板が汚れていたら掃除しておく。休み時間は、次の授業が始まるまでに掃除をしておく。ああそうだ、本当ならここに前の日の日直が次の日の日直の名前を書くんだけど、昨日は日直がいなかったから」 そう説明しながら黒板の右端に「新井」と白チョークで書いてから告げた。 「オレは新井竹緒って言うんだ。よろしく」 「知ってる」 百音はちょっと笑いながら竹緒の手からチョークを取り上げて「五十鈴」と並べて書いた。 「私は五十鈴百音。よろしく」 「知ってる」 二人は黒板の前で一緒に少し笑った。 「なになになになに、なに二人でいい感じの空気を作ってんの」 竹緒の肩に手を回しながら二人の間に入ってきたのは、かるーい感じの優男である西條輝(てる)だ。竹緒は背の高い西條に押しつぶされた形になってしまう。特に面識もない相手にそんなことをされて腹が立ったが、抗議する前に新たな男子が加わった。 「さいじょー止めてやれよ。あ、ちなみにオレは南田。なんだなんだの南田。よろしくね」 その後はもう歯止めがなかった。 伊東香莉奈たちに接触が阻まれていた男子たちが一斉に群がってくる。背が小さければ押しも弱い竹緒はあっという間に輪の外に追い出されてしまった。 次から次へ繰り出される質問に百音が愛想良く応えているのが輪の中から聞こえてくる。 しかたがないか、と竹緒は自分の席に戻った。日直は今日一日続く。話をする機会はまたあるだろう。 男子の他にも、伊東グループ以外の女子を含めた「転校生を囲む会」は、担任が現れるまで続いた。 竹緒の予想に反して、百音と話す機会は放課後まで訪れなかった。自分で言っていたとおり、日直に大した仕事はないのだ。 授業前後の号令と、休み時間に黒板を掃除するぐらい。 その間にも男子たちの攻勢は続いていたし、昼休みは休み時間の分を取り返そうとしているかのように伊東香莉奈ががっちりとガードしながら学食へ連れて行ってしまった。 二人きりになれたのは放課後になってからだった。それだって、仕事があるからと百音が西條たちをやんわりと追い払ったからだった。 しかし、一度失ってしまったきっかけを取り戻すのは難しかった。特別な話をすることもなく日誌を書き終えると、職員室に届けるために二人で教室を出た。無言で廊下を歩いていると、倉田と話している陽雪がいた。 当然のことながら、パパラッチはこちらを目ざとく見つける。 「百音、もう帰るの?一緒に帰ろ?」 「ええ、職員室に日誌を届けてくるから待っててくれる?」 「分かった。校門で待ってる。タケもバイバイ」 陽雪はくったくなくひらひらと手を振る。 「澤井さんと仲が良いの」 竹緒は二人きりに戻ってから訊いてみた。 「ええ、家が隣だから色々と教えてもらっているの。良い人よね、彼女。親切だし、楽しいし」 「そうだね」 少し付け足したい感想を心の中に隠しながら答える。 そんな空気を察したのか、百音は一拍置いた後に訊ねてきた。 「陽雪と付き合っていたって本当なの?」 「春休み中に別れちゃったけどね」 「どうして?」 どうしてか…。それが知りたいのは竹緒の方だった。付き合ったのも別れたのも陽雪からの一方的な話だった。 「どうしてかな」 それが竹緒の正直な気持ちだったが、百音ははぐらかされたと感じたらしく、眉をひそめる。 「着いた」 百音はまだ訊きたいことがあるようだったが、それを遮った。竹緒的には愉快な話題ではない。 職員室に入り、担任に日誌を手渡す。 「なにか困ったことはないか」 岩坂先生は、日誌を確認しながら転校生に尋ねた。 「大丈夫です。みんな親切にしてくれていますし、今日は新井君に色々と教えてもらったし」 百音は笑顔と一緒にハキハキと答える。 「色々って新井、なにを教えたんだ」 「日直の仕事です」 憮然と答える。 学生時代はラグビーをやっていた岩坂先生は、背は高くないががっちりした体格をしている。無精ひげが良いアクセントになっている丸顔は愛嬌がある。 話も面白く、生徒の人気も高い。 しかし、生徒弄りを趣味としているところがあり、竹緒は見ているのはともかく、弄られる対象にされるのは苦手だった。 「なんだつまらん。そういえばお前、澤井と別れたらしいな」 「それはもう知られていました」 「ははは、そういえば五十鈴は澤井と家が隣らしいな。でも残念だな。オレはお前たちは面白い組み合わせだと思って注目していたのに」 「……面白いですか?」 「面白いだろう。自分ではそんな風に思わなかったか?」 「岩坂先生」 身を乗り出してきた岩坂先生をきつい声が咎めた。少し離れた席から、構(かまえ)先生がパソコンのキーボードを打つ手を止めて、メガネ越しにじっと見てきていた。 「おおっといけねー」 岩坂先生は大げさに慌ててみせる。岩坂先生は構先生に気があるとの噂がある。 「それじゃあこの話はまたの機会にじっくりと聞かせてくれ。今日はお疲れさん。気をつけて帰れ」 廊下に出ると、百音が口を開いた。 「陽雪に聞いたんじゃないわよ」 最初、その言葉の意味が分らなかった。しばらくして、別れ話のことだと気がついた。岩坂先生が、百音が別れ話を聞いたのは陽雪からだと誤解していたのを訂正したのだ。 「ん…、別に気にしてないから」 陽雪と付き合いがあるのならばいずれは知った話だろう。その出所がどこであっても竹緒にとっては変わらない。陽雪は必要があればためらいなくそれを明らかにするだろうし、それを咎める気はない。 並んで教室へと歩いていく。校内にはまだそれなりの数の生徒が残っていた。 「もうなんとも思ってないの?」 問いかけてくる百音を、不思議に思う。 クラスの中での彼女は主に質問を受ける方で、する方ではない。もっとも、する立場に回れないほどの質問攻めに合っているのも確かだが。 「別に…、今も普通に話しているし。別れたって言っても特に何も変わってないから」 「変わってないの?それじゃあ、今でも陽雪を好きなの?」 陽雪を好きなのか? それはどこか新鮮な問いかけだった。 陽雪のことを好きかどうか。そんなことを真剣に考えたことはなかった。 「さぁ、よく分らないな。それより五十鈴さんには好きな人はいないの?前の学校で付き合っている人がいたとか」 竹緒はよく分らないから百音に振り返した。 百音がその話題を嫌がるのは分っていた。昨日から何度もその質問を繰り返され、同じ答えを何度も繰り返すのを隣で聞いていた。 「いじわるね、知っているでしょ」 百音も分っているらしく、じとっとした目で睨んだ後、ほっと空中に息をついた。 ちょうどその時教室についた。 「新井くんももう帰るの?だったら校門まで一緒に行きましょう」 百音の誘いは結果として教室に残っていた男子たちを制することになった。怒り甚だしい男たちの後の報復を覚悟しながら、竹緒は了解する。 「前の学校で付き合っていた人はいないわ」 荷物を持って教室を出ると、百音は律儀にも先ほどの答えを返してきた。隣の席で何度も耳にした話だ。 「でもね、」 しかし、そこから先の話は初耳だった。 「好きな人はいるかもしれない」 「……へぇ」 いるかもしれない? 中途半端な答えに曖昧な返事を返した。 「子供の頃のこととか覚えてる?」 竹緒の思考を打ち切らせるように、百音は明るい声で話題を変える。 「うーん、あんまり」 「子供の頃って、ちょっと仲が良いだけでその子と将来結婚するんだとか思わなかった?約束しちゃったり」 「そうかな?」 「テレビなんかでも良くあるじゃない。子供の頃に結婚を約束して、その後離れ離れになって、大きくなってから再会するの」 「でもあれってテレビの中の話だろ」 「新井くんはしなかったの?」 「はっきりとは覚えていないけど、そんな約束はしていないと思うな」 女の子と付き合ったのは陽雪が初めてだった。それ以前にそれほど仲の良かった女の子の記憶はない。 「そう…」 その答えに百音は眉間にしわを寄せたが、それなりに一生懸命に子供の頃を思い出そうとしていた竹緒は気がつかなかった。 「でもね、そんな約束をした二人いて、長い別れの後にまた出会ったら素敵だと思わない?」 百音の口調が少々無理のある明るさに変わっていくが、竹緒は気がつかない。 「それはロマンチックかもしれないけど、それこそテレビの中だけの話だろ。子供の頃は大した考えもなしにそんな約束をしてしまうかもしれないけど、大きくなったら忘れてしまうだろうし、覚えていても恥ずかしい思い出になるだけじゃない」 「……恥ずかしいんだ」 「五十鈴さん?」 竹緒はそこでようやく百音の異変に気がついたが、百音はたたっと校門まで走っていってしまった。 「お待たせ」 「あ、うん」 校門で待っていた陽雪が、何かあったのかと視線で尋ねてくる。百音はそんな表情をしているのだろう。しかし、竹緒は訳が分らずに首を振るしかなかった。 百音はそのままさよならも言わずに陽雪と帰っていった。 暮れ始めの空の下、竹緒は力なく首を振る。 陽雪といい百音といい、女の子はさっぱり分からない。
|