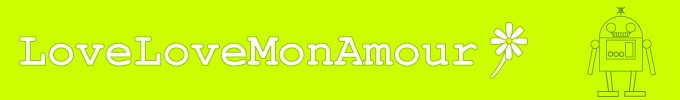
|
キミのフェロモン 前編
土曜日の昼過ぎ、竹緒は自転車に乗って家を出た。 穏やかに暖かさを振りまいてくれている日差しは、新学期が始まってから続いているもやもやを忘れさせてくれそうな心地よさだった。 しかし、気を抜くとすぐにもやもやの原因が頭をよぎってしまう。 昨日の五十鈴百音は、挨拶もせずに帰ってしまった前日の気分を引きずっているようであった。 他のクラスメートとは今までと同じように接していたが、隣の席に座る竹緒には全く話しかけてこなかった。 竹緒も百音の豹変の理由が分からないままでは話しかけづらく、なんの進展も解決もないままに放課後をむかえてしまった。友人とゲームセンターに遊びに行ったが、心はちっとも晴れなかった。 もやもやとした気分を引きずりながら小さな公園の中に自転車を乗り入れ、ベンチの横で止めた。 ぐるりと見回すと、コンビニ弁当を食っている暇そうな男がいるだけで人影はない。 この公園は小さいわりには樹木が多いのが特徴だ。自転車から降りると、ベンチ裏の木々の間に入ってき、中腰になって地面を観察する。一週間ほど雨が降っていないために地面は乾燥しており、落ち葉もあまりない。観察しやすい状態だったが、目的のものはなかなか見つからなかった。 「まだ早かったかな」 つぶやきながら移動すると……、いた。 地面の上を動く小さな点、アリだ。周囲に他のアリがいないか注意しながら近づいていく。こんな時、他の生き物なら警戒して逃げて行くかもしれないが、アリは人間などにはお構いなしだ。 特に珍しくもない典型的な黒アリだ。アリは基本的に単独行動をしない。すぐに他のアリも発見することができた。それらのアリの配置から見当をつけて木の根元にあった石をひっくり返すと、予想通りに石の下から小さな黒い軍団が湧き出てきた。しゃがみこんでアリたちが突然の天変地異に慌てふためいている様をじっと眺める。 アリの観察は竹緒の昔からの趣味だった。好きになった理由は特にない。子供の頃からアリを見ているのが好きで、今もその延長線上にいるだけだ。 アリ以外の昆虫にはあまり興味がなかった。小さな身体しか持っていないくせに、集団で大きなことを為すところが見ていて飽きない。 自分も身体が小さいから、そこに共感を持って好きになったのかと考えたこともあったが、その割には自分自身は集団行動が苦手で、それを直そうという努力もしない。不思議な話だ。 「新井くん!」 観察に熱中していたために、その声にはなかなか気がつかなかった。ようやく気がついて振り返ると、女生徒が険しい顔をして立っていた。 「あ、部長」 「あ、部長、じゃないわよ」 園芸部部長、大庭環の声はひどく刺々しかった。竹緒のすぐ後ろに立っていたということは、呼んでもなかなか気がつかなかったために、木々の間にまで入ってきたのだろう。 そして、環が怒っている理由はそれだけではない。 「アリもいいけど、たまにはクラブにも出てきてくれないかな。新年度で色々と忙しいの」 「今日も登校していたんですか?」 環は休みなのに制服を来ていた。黒縁メガネ、肩まである髪をきつく三つ網で縛り、大きなリュックサックを背負っている。いつもどおりの格好だ。 「誰かさんが来てくれなかったから一人でね」 環は言い捨てると早足で植え込みの中から出て行ってしまったから、竹緒は仕方なく後を追った。環はベンチの上でリュックサックを開くと、取り出した紙を突き出してきた。 「どうせ、まだ受け取ってないんでしょ。渡しておくから当番ぐらいは守ってよね」 園芸部員には花壇などの世話をする当番日が割り振られている。竹緒はしぶしぶ受け取り、当番表に目を落とした。 「あれ、今日はオレが当番だ」 「言ったでしょ、誰かさんが来てくれなかったから一人でやったって」 「すいません。……でもひどいな、いない間に勝手に当番を決めるなんて」 「始業式の日に残っててって言ったでしょう」 さすがにそこで、学校には残ってました、と屁理屈を言う度胸はない。 「すいません」 「もういいわ。当番表は渡したからね。次からはしっかりやってよね。都合の悪い日は他の人に頼んで変わってもらっていいから」 「はい」 環は信用していないのを表現するかのように息を一つつくと、それじゃあね、と背を向けた。 「部長」 竹緒は気になっていたことがあったので呼び止めた。 「なんでオレがここにいるって分ったんですか?」 「ここは私の通り道なの。その通り道に見たことのある自転車が止まっていたから、ちょっと覗いて見ただけ」 環は、お分かり?っといった感じでメガネの奥からじっと睨んだ後に去っていった。 「あーあ」 竹緒はベンチに腰掛け、当番表を持った手を頭上にやって仰ぎ見る。 四月の当番日は今日を合わせて四日、そのうち三日が環と一緒だった。 「信用されてないな」 当番表を下ろすと青い空が飛び込んできて、慌てて目を細めた。徐々に目を慣らしながら空を見上げる。 暖かな空には薄い雲が浮かんでいる。 そのままの姿勢でぼーっとしていると、わずらわしいなにもかもを忘れられそうだ。この平和な時間がずっと続けば良いと願う。 しかしその願いはあっさりと破られた。 そんな平穏を許さないとでも言うかのように、不意に影がさした。 「なにしてるの?」 影の犯人は意外な人物だった。 「ひなたっぼっこ」 「ふぅん」 五十鈴百音は昨日から引き続いて、難しい顔をしていた。そんな顔をしていても、私服姿は新鮮で素敵だ。 「隣に座ってもいい?」 「うん」 竹緒は内心ドキドキしながらも、平静を装って答える。理由は分らないが、百音が一昨日から自分に対して怒っていたのは確かだった。昨日はほとんど無視に近い状態だったし、今だって怒った顔をしている。 怒っている女の子の相手なんてどうすればいいのか分らない。 しかしその反面、美人の女の子と二人でベンチに座ることを喜んでいたのも確かだった。 そんな男子の心の葛藤など気にせずに、百音は不愉快な様子を隠しもせずに口を開いた。 「さっきの人は誰なの?」 「さっきの人?」 「うちの制服を来ていた人」 「ああ、部長のことか」 すぐに分らなかったのは、環が去ってからすでにそれなりの時間が経過していたからだった。 百音が今までなにをしていたのか少し気になるが、それを訊くのは墓穴を掘る行為と思えた。 「大庭先輩。園芸部の部長」 「そういえば新井くんて園芸部だったっけ」 「幽霊部員だけどな。今日も当番日なのにさぼったから、怒られてたんだ」 「なんで園芸部なの?」 「うーん、夏合宿が楽しそうだったからかな」 竹緒は最初ワンダーフォーゲル部に入った。山へ行ってアリの観察ができると思ったからだ。しかし、ワンダーフォーゲル部は過酷なクラブ活動である。テント用具などの入った重い荷物を背負わされ、山道を延々と歩かされる。しかも歩くことが主目的なので、アリの観察などといった悠長なことをやっている余裕はない。 しかも山男の掟なるものが存在し、上下関係も厳しかった。竹緒は体験キャンプから帰ってくるとすぐに退部した。 次に選んだのが園芸部だ。 「園芸部の夏合宿ってなにをするの?」 「田舎の農家に体験学習に行くんだ」 「体験学習って農作業をするの?あんまりイメージじゃないわね」 「そうかな。農作業はしんどいけど、自分の手で収穫したものを食べたときはけっこう嬉しかったりする」 「ふぅん、そうなんだ」 これはウソだ。 竹緒は体験学習はさっさと抜け出して、アリの観察に没頭していた。部内では顰蹙を買ったが個人的には実に有意義な一週間だった。 夏合宿以外にも、学内でどうどうと土いじりをしてアリを観察できるのも園芸部の利点の一つだ。 しかしそんなことまでは話さない。 これまでの経験上、アリの観察なんかに興味を抱く女の子は皆無だったからだ。 「学校ではなにを作ってるの?」 どうやら園芸部の話題は百音の興味をひいたようだった。 「残念ながら今は食べられるようなものは作ってないな。その年に育てるものの決定権は部長が握っているから、部長の趣味に大きく左右されるんだ。昔は食べ物ばかり作りたがる部長がいたらしいけど、大庭先輩はそういうのには興味ないみたいだしな」 「部長さん、堅物っぽいもんね。じゃあ、お花を作ってるんだ」 「オレは食い物の方が良いけどね」 「じゃあ来年は食べ物三昧ね」 「幽霊部員が部長になれるわけないだろ」 「それはそうね」 百音は笑いながら跳ねるように立つと、そのまま走っていった。良く分らないが機嫌は直ったらしい。 「新井くん」 シーソーの横で大きく手を振っているので、こちらも小走りで近寄って行った。 機嫌がなおったのは良いが、相変わらず行動が唐突で付いていくのが大変だ。 百音がさっさとシーソーに座ってしまったので、仕方なく反対側に腰を下ろす。 シーソーに乗るのなんて小学校以来だ。 百音が楽しそうにこぎ始めたので、竹緒は周囲に人がいないことを感謝しながら付き合った。 勘を取り戻すのには少し時間がかかったが、一度取り戻してしまえば、それなりに楽しかった。 なによりも、百音が本当に楽しそうに笑っているのが良かった。 少し大げさに、夢のようだとさえ思った。 シーソーから降りた百音は、今度は滑り台へ走る。 美人ゆえに普段は落ち着いた印象があるが、ステップを一気に駆け上がる姿は、子供のそれと大差がない。 しかしそんなギャップもかわいいと思ってしまう。 「新井くん、はやく」 声をかけられれば逆らうことなどできるはずもなく、ふらふらと吸い寄せられて行ってしまう。 「ダメよ、そっちから上がってきて」 ステップを上がろうとすると、百音はそれを制し、降り口の方から上がってくるように命令した。 竹緒はどんどん嬉しくなっていく気持ちを隠しきれなくなりながら滑り台を回り込む。大人の背丈ぐらいしかない滑り台だ。子供の頃ならともかく、今なら斜面を上がっていくのは難しいことではない。 見上げると、頂上では百音が待ってくれている。 斜面を一気に駆け上がった。 滑り台の狭い頂上はたちまちいっぱいになる。 百音の顔が目の前にあった。 なにも考えずに駆け上がってきてしまった竹緒は、それだけでもうどうしたらいいのか分らなくなってしまった。 ギャグでも言わなければならない。突然そんな強迫観念がこみ上げてくるが、確実に滑りそうな極寒のギャグですら思い浮かばなかった。 竹緒はそんな状態だったから、百音が満面の笑みで迎えてくれたのではないことに気がついてはいなかった。 目の前の顔は、不安な表情を見せているんだってことに気づかなかった。 「思い出した?」 その問いにわずかに正気を取り戻すと、驚くほど近くに少女の長い睫毛があった。その先が小刻みに揺れているのがはっきりと分る。しかしそれらは決して閉ざされることはなく、一度の瞬きも許さずに、その奥から放たれる強い眼差しを遮らない。 潤んだ瞳はなにかを必死に訴えていた。 しかし、竹緒は始めて感じる息の詰まる距離感になにもできなかった。呼吸することすら忘れ、その瞳から逃げることもできず、ただ向き合っているしかなかった。 なにを思い出したのか? なにを思い出せばよいのか? そんなことを訊ねる余裕はなかった。 どれだけの時間をそうやって過ごしたのか。 百音の顔が当然歪んだかと思うと、次の瞬間には竹緒の身体は宙にいた。視界が回る。 悲鳴を上げる間もなく、背中に強い衝撃を感じる。一瞬息が詰まる。そのまま仰向けに滑り落ちていった。一番下まで落ちて、最後に地面で頭をごつんと打った。 「痛ってぇ」 今まで溜めに溜め込んだ言葉を、思いを吐き出すかのように声を絞り出す。ガラガラとした乾いた声だった。 視界はチカチカと瞬いている。 ガンガンガンと音が響くと、チカチカした視界の上を何かが横切っていった。 パタパタと遠ざかっていく足音が聞こえる。 百音のものであろうその足音は、しばらく待っても戻ってこなかった。 背中と頭にじんじんと響く痛みを抱えながらそのまま仰向けで倒れたままでいる。ようやく回復してきた目に、先ほどまでと変わらない青い空が見える。それはひどくのんきな光景に映った。 百音に突き落とされたのだろうということはなんとか想像できた。しかし、その理由はさっぱり分らない。 「なんなんだよ」 つぶやいてみても、やっぱり分らない。 のんきな空が恨めしかった。
|