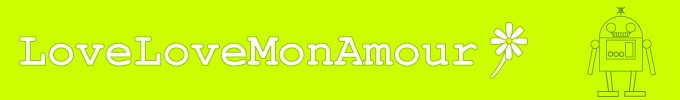
|
キミのフェロモン 中編
「アントクアリウム」というアリの飼育用具が話題になったことがある。 透明のアクリル板で作った薄い長方形の箱の中に水色のジェルが流し込まれている。その中にアリを入れると、ジェルを地面の代わりにして巣を作るというものだった。 土を使うよりは巣を作っていく過程が観察しやすく、また、ジェルはアリの食物になる物質なので餌もいらない。「お気軽飼育」が宣伝文句だった。 宣伝に使われていた写真では、アントクアリウムの中に見事なアリの巣ができており、それが窓際に置かれているのを見れば、ちょっぴりオシャレなアイテムに勘違いする者もいた。一時的なブームになったが、すぐに廃れてしまった。 理由は簡単だ。 宣伝写真に使われているような巣ができたケースがほとんどなかったからだ。それどころか、たいていのアリは巣を作る前にすぐに死んでしまった。アリは、手間を惜しんで飼えるほど簡単な生き物ではない。 アリの観察を趣味とする新井竹緒(あらいたけお)は、新しいアリ観察アイテムにもちろん興味を持ったが、購入はしなかった。 まず、窓際にアントクアリウムを置いている写真に顔をしかめた。アリに限った話ではないが、生き物は基本的に日光に弱い。飼育箱を日陰に置くのは初歩中の初歩だ。 日光が燦々と当たる場所に置くなんて言語道断である。 それに、五、六匹しか入れないコロニーはあまりにも寂しく見えた。加えて、女王アリがいないコロニーになんの意味があるのかとも思った。 アリは一匹の女王アリを中心とした集団、コロニーを形成する。女王アリの仕事はただ一つ、子供を生むことだけであり、その他のアリの仕事は二つだけ、子供の世話と、女王アリの世話である。アリはその為だけに、時には数万匹でコロニーを形成し、地下六メートルにも達する巨大な巣を作る。 なのにアントクアリウムの世界には女王アリがいない。当然子供がいないから、巣を作る意味がないのだ。 意味がないことをやりたくないのは、人間だってアリだって同じだ。 あんな勘違いアイテムが売れなくなるのは当たり前だと、竹緒は思った。 しかし、アリの仕事の意味を問うのは容易いが、人間の日々の生活の中で、それらの意味を見出すのは簡単ではない。たった二つしかない世界ならともかく、細分化され過ぎた仕事は、それら個々の意味を見えにくくしてしまう。 それが仕事でなければなおさらだ。 新学年の始まりと共にやってきた転校生、五十鈴百音(いすずももね)に振り回されっぱなしのここ数日間は、自分の人生においてどのような意味があるのかと、竹緒は真剣に考えていた。 転校してきてまだ一週間も経っていないのに、百音はすでに人気者になっている。それは彼女の桁外れの美貌だけによるものではなく、人当たりの良い性格からくるものだった。集まってくる皆に均等に極上の笑顔を振りまいている。 しかし、竹緒に対してだけは態度が違っていた。笑顔を見せていたかと思えば、急に不機嫌になったり、無視したり、突っかかってきたりする。そして思わせぶりなことを言い始めたかと思うと、最後まで言わずに去っていってしまう。 「思い出した?」 土曜日に近所の公園で偶然出会った百音は、滑り台の上で唐突にそんなことを訊いてきた。 間近にある百音の美しい顔に胸を打ち鳴らしてしまい、思い出すどころか何も考えられなかった竹緒は、滑り台から突き落とされた。 さすがに腹が立った。 意味不明な問いに答えられなかっただけで、なんで突き落とされなければならないのか。 あんな、顔と外面が良いだけの女とは二度と関わるまい。 そんな決心もむなしく、土曜日の残りと日曜日丸々を、何を思い出さなければならなかったのかを考えることだけで過ごしてしまった。 日曜日の夕方、部屋の窓の外にある街灯が瞬くのを見て、そろそろ宿題をやらなきゃいけないなと思った竹緒は、前述の事実に気がついて愕然とした。 もう関わらないと決めたクラスメイトの意味不明な問いにつきあうことに何の意味があるのか! 意味のないことで貴重な休日を潰してしまった。 そのまま暗澹とした気分で翌日の朝を迎えた。思い出さなきゃいけないことは、やっぱり思い出せないままだった。 週が変わっても、五十鈴百音は美人だった。そんなところがとても卑怯だと思う。 教室のドアを開けると、窓際の一番前の席に百音は座っていた。後ろの席の伊東香莉奈、そして本来は竹緒の席である隣の席に座っている女子と楽しそうに話している。 「おはよう」 わだかまりは解けていないし、積極的に関わらないと決めたが、クラスメイトとして一応朝の挨拶だけはしておく。 「お、おはよう」 百音は会話を切ると、目を泳がせながら答えた。 「あ、ごめんごめん。この席の人?」 竹緒の席に座っていた女子は、大きな声で訊きながら立ち上がった。メガネにボブカットの顔を見たことはあったが、このクラスではないはずだ。 「じゃあももちゃん、続きはまた今度ね」 名を知らぬ少女は百音に手を振ると、ドスドスと足音を響かせながら教室から出て行った。 百音にはもう関わらないと決めた。さっき教室のドアを開ける前にもそれを再確認した。 訊きたいことがたくさんある。でも、関わらないと決めたのでそれらを問うのは我慢している。だけど、これだけは、先ほどのその言葉についてだけは、問わずにいられなかった。 「ももちゃんって呼ばれてるの?」 問うと、百音の顔が一気に赤くなる。 「う、うるさいわね。なに盗み聞きしてるのよ!」 「盗み聞きって、人聞きの悪いことを言うなよ。あんなの、誰だって聞こえるだろ」 「うるさい、うるさい、うるさい」 「なんで急に照れるのよ、かっわいいなーももちゃん。ね、新井くんも、ももちゃんってかわいいと思わない?」 意外にも香莉奈が参加してきたが、事情を説明する気は全くなく、逆に火に油を注ぐのが目的のようだ。ここでうまくフォローできれば良いのだろうが、残念ながら竹緒はそんなテクニックを持っていない。 「そうかな?あんまり似合ってないと思うけど」 と、正直に答えてしまう。 美人の百音には「ももちゃん」なんてかわいい響きのする呼び方は似合わないと思った。しかし、ここは正直な感想を口にする場面ではない。 「なんですって!」 百音ががたんと椅子を鳴らして立ち上がると、教室の空気がざわっと変わった。三人の会話はしっかり聞き耳を立てられていたのだ。 「こ、金輪際そんな呼び方はしないで!香莉奈もよ!」 注目の的になっていることに気がついた百音は、そう言い捨てると髪をひるがえし、足早に教室から出て行った。学内一の称号を一週間で手にした美少女は、こんな時にでもどたどたと足音を立てたりしない。 「おやおや新井くん、今度はなにをやったのかな。ここはびしっとばしっと、詳しく詳細に事細かく報告したまえ」 するするっと近寄ってきた南田(なんだ)が肩を叩きながら言う。 「なんでお前に報告しなきゃいけないんだよ」 「それは、オレが学級委員様だからだ。慣れない学校に戸惑っている転校生がいれば、彼女に助けの手を差し伸べるのは学級委員様の仕事だろう」 「戸惑ってなんかないだろ。すっかり馴染んでるじゃないか」 「それは学級委員様としてのオレの努力の結果だな」 「……そうだね。そう思うよ」 「オレの偉大さを認めたところで教えろよ」 「勘弁してください」 興味津々に見守っていた他の男子たちも加わった追求に、竹緒は最後まで口を割らなかった。その様子をちょっといじわるな表情で楽しそうに見ている香莉奈が恨めしい。 予鈴と共に担任と談笑しながら教室に戻ってきた百音には、先ほどまでの取り乱した様子は全くなかった。ちょっぴり心配した涙の跡なんて全くついていない。皆の注目を集めながらも、何事もなかったかのように優雅に席につく。 そうなれば、休み時間に朝の騒動について探りを入れる者がいても、正面から真相を解明しようとするつわ者はいなかった。中途半端な探りは、慣れた感じではぐらかされた。 「ももちゃん疑惑」はこうして闇に葬り去られ、教室内には平和が戻った。 ただ竹緒だけは、隣の席からの突き刺すような視線を側頭部に感じながら、落ちつかない一日を過ごした。 真相究明の鍵を握っているのは今朝この席に座っていた女子だと竹緒が気がついたのは、一日の授業が終わった後のホームルームの最中だった。 その単純な答えに辿りつくのに一日かかった頭の回転の悪さに落胆すると同時に、結局今日も一日中、隣に座る少女に関することを考えていた事実に愕然とする。 いつまでこんな意味のないことを続ければよいのか! 竹緒はホームルームが終わると同時に、もう絶対に百音とは関わらないという確固たる意思を持って教室を足早に出た。 百音は香莉奈と話をしていたが知ったことではない。 朝の少女は何組だろうかと、他のクラスを覗きながら廊下を歩いたが、ホームルームが長引いたこともあって、教室に残っている生徒はすでにまばらになっており、その中に目指す顔は見つけられなかった。 今日中に見つけ出すのを諦めて昇降口から外に出たところで、行く手に園芸部部長、大庭環(おおばたまき)を見つけた。友人と話している環はしばらくそこから動かない様子だったので、正門へ向かうのを諦めて校舎沿いに回りこんで裏門へ向かった。土曜日に渡された当番表によれば今日は当番ではなかったが、見つかればたまにはクラブに参加しろとぐらいは言われるだろう。 今は環と問答をする気分ではなかった。 校舎を回りこむと別棟になってる図書館の裏へ向かう。図書館裏と塀の間には人一人分の隙間があり、こっそりと帰るのに役立つ秘密の通路となっている。秘密とは言っても図書館の窓からは丸見えであり、利用者は少ない。 竹緒はこの通路を教えてもらった時以外に、この通路を使っている生徒を見たことはなかった。 だから後ろから足音が聞こえてきた時、竹緒は少し驚いた。後ろの変わり者は小走りだったので、道を空けてやろうと半身になりながら振り返って、また驚いた。 そこにいたのは百音だった。 彼女は追い越していかずに竹緒の前で立ち止まると、何かを言いかけて、飲み込んだ。細かく手を振り、目を泳がせながら一生懸命に考えをまとめようとしている。竹緒が無言でそれを見ていると、何かを決したかのように腰の横で手をぎゅっと握り、そのまますたすたと通り過ぎていった。 「なんなんだよ」心の中の呟きが聞こえたのか、百音は三歩ほど通り越してから振り返った。 「ごめんなさい」 振り返りざまに深々と頭を下げられてもなんのことだかさっぱり分からない。 「えっと、突き落としたのはさすがにやりすぎたかなって思って。ぶ、無事みたいで良かった」 土曜日に滑り台から突き落とされた件のようだった。 「無事じゃない。すっごいでかいたんこぶができたし」 「本当に?」 百音はすいっと近寄ってきて竹緒の頭を見ようとする。背は竹緒の方が若干高いがほとんど変わらない。軽くウェーブのかかった髪が顔の横にくる。シャンプーの匂いだろうか、とてもいい匂いがして頭がくらくらした。 「もう治ったから」 顔が紅潮しているのが頭にまで出てしまっている気がして、邪険に手を払いながら離れた。むっとしている百音の顔を見て、離れたら赤くなった顔を見られてしまうことに気がついて、今度は慌てて顔を伏せる。 「なによ、心配してあげてるのに」 「心配するぐらいなら、あんなことしなきゃいいだろ」 「しかたないでしょ、はずみだったんだから。私だって突き落としたくてやったんじゃないわよ」 「はずみだからなんて理由にならないだろ。これ以上バカになったらどうしてくれるんだ」 「そ、そもそも思い出さない程度の頭だから悪いんじゃない。逆に頭を打って少しは良くなったんじゃない。あれがきっかけで思い出したとか」 「そもそも思い出すとか思い出さないとか、意味が分からないよ」 「シーソーに乗って、滑り台に乗って、今朝は昔のあだ名まで聞いたのに、なんで思い出さないのよ。頭がおかしいんじゃない」 「頭がおかしいのはそっちだろ。何が言いたいのかさっぱり分からない。皆がちやほやしてくれるからって、誰もが良くしてくれるって思ってるんじゃないの」 「そんなんじゃないわよ」 「じゃあなんなんだよ。オレには妄想癖が激しいようにしか見えないよ」 「私の思い出を妄想なんかにしないでよ!」 百音は叫ぶと、背を向けて走り去り、そのまま裏門から出て行った。 カバンを持っていなかったが帰ってしまって良いのだろうか? まだ怒りは収まっていないのに、またそんな反立することを思ってしまう自分にも少し腹が立つ。 「知るかよ、あんな奴」 自分の立場を確認する言葉を呟きながら歩き始めた竹緒の前に、図書館の角からふらりと陽雪(つゆき)が姿を現した。 「あーあ、泣かしちゃった」 なんでこのタイミングでこいつが現れるんだと呆れる。 「……尾けてたの?」 「図書館にいたらタケが歩いていって、その後を百音が追いかけていったの。誰だって気になるだろ」 「一緒にするな」 言いながら振り返る。この場所はちょうど窓がなかったので言い争っていた現場を見られた心配はないが、開いていた窓から声が中に届いていたかもしれない。 「あんまり人はいなかったから、聞かれていないと思うな」 「……一番聞かれちゃいけない人に聞かれた気がするんだけど」 「酷いな。これでも口は堅いつもりなんだけど。未だに分かってくれていないなんて、それが別れた原因かな?」 答え辛い問いだったから、無言で答えた。そんなモトカレに陽雪は笑顔を見せる。 竹緒の元彼女、澤井陽雪はパパラッチの異名を持っており、学内の全ての噂は彼女の元に集まり、様々な噂が彼女から発せられる。 そんな陽雪に不快感を持つものは少なくないが、彼女の柔らかな笑顔はそれらを打ち消してしまう力を持つ。パパラッチなどと呼ばれながらも、嫌われていない理由だ 短期間とはいえ付き合っていた竹緒にはその笑顔は効かなかったが、陽雪がそんな人間だと理解していたから、特に腹も立たなかった。 「ま、私のことはどうだって良いんだ。問題は百音だ。放っておいていいの」 「……泣いてたの?」 「あれはウソ。一瞬だったから良く見えなかった。でも、泣いていた方が話としては面白いだろ」 「オレは面白くない」 「だったら面白くなるようにしたら良い。それが当事者の特権だろ」 「……オレは当事者なのか」 そんな自覚は全くない。 「噂の中心人物って表現でも良いよ。今朝のももちゃん発言の噂でも重要参考人として当局に指名手配されてるし」 「なんだ、ばっちり広まってるんだ」 クラス内では耳にしなかったから知られていないと思っていた。確かに、陽雪の情報収集能力をまだちゃんと分かっていないようだ 「さっきのことも噂として広まるの?」 「それはタケの心構え一つかな。質問。ももちゃんってあだ名に覚えはないの?」 「聞き覚えはあるんだ」 面倒くさいので正直に答えた。どうせ陽雪との駆け引きに勝算はない。 「子供の頃、聞いた気がする。でも、それが五十鈴さんとは結びつかないんだ。ももちゃんなんてそんなに珍しい呼び方じゃないだろ。全然別の人の呼び方だった気がする」 「確かに、ありそうな呼び方だね」 陽雪は満足気に頷いた。 「お礼に教えてあげる。今朝の女子はD組の草津澪(くさつれい)さん。百音は昔この辺りに住んでいて、保育園で一緒だったんだって」 「この辺りに住んでいたの?」 「噂だけどね。さて質問、子供の頃の記憶の中に百音は出てきた?」 「……考えておく」 「健闘を祈る。それじゃ」 陽雪は笑顔を一つ見せた後、去っていった。 「澤井さん」 竹緒はその後を追いかけた。 「五十鈴さんはカバンを持たずに帰っちゃったんだ。多分まだ教室にあると思う。だから、もし良かったら持っていってあげて欲しいんだけど……」 「ああ、いいよ。百音とは友達だからね。気がついてくれてありがとう」 陽雪は笑って了承すると、校舎へ歩いていった。 百音はカバンも持たずに追いかけてきた。多分、土曜日のことを謝ろうと一日中タイミングを待っていたのだろう。 先ほどまでの百音に対する怒りの気持ちはいつの間にか消えていて、今はそんな風に思えた。こんな風に切り替えることができたのは陽雪のおかげだった。 敵わないな、と思う。別れた今でも、いや、自分だけでなくこの学校で起こっていることの全ては彼女の手の内なのではないのかとまでも思う。 当事者だなんてとんでもない。今でも自分は彼女のコマの一つでしかないのだ。自虐的になりながら裏門をくぐる。 そういえば、なんで裏門なんて使っているのだろうか? 環の件を思い出したのは、三分後のことだった。
|