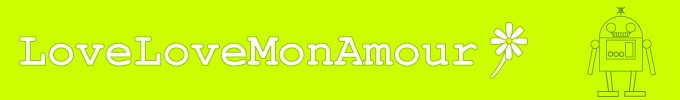
|
キミのフェロモン 中編
火曜日からの百音は、挨拶はするけどそれ以上の会話はしない無視モードに再び突入していた。カバンに関する礼はなかった。陽雪は何も言わなかったのかもしれない。その陽雪とも、廊下であったら挨拶をするぐらいだった。 子供の頃の記憶に、百音はまだ登場してこない。 草津澪が再び来ることを期待したが、廊下で見かけることはあっても百音と話していることはなかった。 新たな進展は嫌な噂を耳にしたぐらいだ。 百音が昔この付近に住んでいたが、父親が事業に失敗して夜逃げ同然にこの町から出て行ったらしい。 そして、十年の時を経て、大金を手にして出戻ってきた。 陽雪と付き合っていた頃に、彼女の家の隣に建設中だった家を見たことがあるが、それは豪邸と呼ぶにふさわしいものだった。 成り上がって帰ってきたものの、父親はこの町を出るときに色々とトラブルを残していたらしく、昔付き合いがあった人たちと揉めているらしい。 この噂が広っても、百音の人気に陰りは見られなかった。周囲に群がる生徒の数は減っていったが、それは噂の影響ではなく、美人の転校生が来たという流行病が治まっただけに思えた。 その証拠に、金曜日には百音の歓迎会の名を借りたクラスの親睦会も企画されている。 火曜日以降はそれ以上の特記事項はない。 このところトラブル続きだった竹緒にとっては、帰ってきた平和な一時であった。学校に来て眠たい授業を受け、友達とバカ話をし、環の監視を逃れて放課後はとっとと逃げ出し、暇を見つけてはアリを観察する。ずっと続けてきた日常だ。 しかし、トラブル慣れした身にとっては、その当たり前の日常が宙ぶらりんな状態に思えて、ひどく落ちつかなかった。 決めなければならない。 平和な日常を守るのか、トラブルの渦中に身を委ねるのか。 決めかねている間に、いや、自分がそんな分岐路に立っていることを否定している間に、時間はどんどんと過ぎ去っていき、竹緒の中ではイライラがつのっていた。 木曜日の放課後に庭園へ足を踏み入れたのは、イライラの持って行き場所が分からなくて迷った末に辿り着いただけだった。 「あら珍しい。当番日を覚えていたの?」 竹緒を見つけた環は、黒縁メガネの奥の目を丸くさせた。 「当番日でしたっけ?」 「偶然来ただけなの?感動した私がバカみたいじゃない。まぁいいわ。せっかく来たんだから、帰るなんて言わないでよね」 竹緒は仕方なく頷き、環の指示に従って準備を始める。少しは気晴らしになるだろう。 「でも、部長って今日は当番でしたっけ?」 「私はできる限り毎日出ているわよ。当番の人が急に出れなくなったり、さぼったりすることがあるからね。植物は毎日ちゃんと世話をしてあげないといけないんだから、誰かいないと困るでしょ、分かる?」 「はい、申し訳ないです」 環は謝る竹緒に笑顔を見せてから、他の部員の様子を見に行った。こんなに上機嫌な環を見るのは初めてだったが、いつも怒らせているのは自分だと気がつき、反省しながら作業を始めた。 園芸部は毎週火曜日を活動日にしており、その日は全部員が集まって会議をしたり、人数が必要な作業を行ったりする。ちなみに竹緒は今週の活動日もさぼった。 その他に、その年の部員数にもよるが、週一、二回の当番日が各部員に割り振られており、水遣りや雑草抜きなどの簡単な日常作業を行うことになっている。 この学校では園芸部所有の庭園以外に、学校のあちこちに置かれたプランターの世話も園芸部が担当することになっているので、簡単な作業とはいえその作業量は結構多い。 今は春なのでまだましだが、夏になれば雑草抜きだけでも重労働である。 竹緒が任されたのは庭園の水遣りだった。 今週の活動日に種が蒔かれたばかりらしく、目の前の庭園に見えているのは土ばかりで緑はない。畝の前に花の名が書かれた小さな札が立てられているだけの殺風景な様子だった。 竹緒はじょうろに水を汲み、水を撒く。芽でも出ていれば、早く大きくなれよ、的な感情も生まれるのだろうが、自分が種を植えたわけでもない地面に水を撒いていると少しむなしい気分になってくる。 実は環に騙されていて、まだ地面を作っただけで、何も植えられていなかったらバカみたいだ。隠れて笑っている者はいないかと周囲を見回したが、そんな人影は見られなかった。 もっとも、堅物の環がそんなことをするはずがない。これはそんな想像でも働かせなければ水遣りなどやっていられない竹緒の、精一杯の工夫である。 水遣りが終わっても環は戻ってこなかった。このまま帰ろうかと思いながら、じょうろに残った水を近くの植木に適当に撒く。 無味な庭園を見ながら今年は何を撒いたのだろうと思う。環のことだから花だろう。札を見れば名前は分かるだろうが、花の名前など知らないし、興味もない。 「食べ物三昧だと良いね」そう言って笑った百音を思い出した。 来年竹緒が三年生になれば、植えるものの提案ぐらいはできるだろう。その時の為に今から簡単に育てられる果物や野菜を調べようかと思う。収穫の時に百音を呼べば、きっと喜んでくれるだろう。 「だから!なんでまたあいつのことを考えてるんだよ!」 頭の中で自分自身に怒鳴った。 イライラから逃れるためにここまで来たのに、また、イライラの原因のことを考えてしまっている。どうしてそこまで百音が気になるのか、さっぱり分からない。 五十鈴百音は確かに美形だとは思う。スタイルも良い。人付き合いだって良い。 でも、それは表側だけ。表とは違う裏側をちゃんと持っている。性格が悪いとまでは思わないが、自分勝手で、自分本位で、自己中心的だ。態度がコロコロ変わるし、言っていることだってめちゃくちゃだ。 あれなら陽雪の方が全然良かった。噂好きなところは趣味が悪いと思っていたし、思わせぶりなところもたまに腹が立ったが、ちゃんと答えは明かしてくれたし、こちらの話も聞いてくれた。 別れてしまったが、竹緒は陽雪と付き合っている時間を、それなりに満足して過ごしていた。 でも……、陽雪のことがここまで気になったことはなかった。 「付き合って」と言われた時、「別れて」と言われた時はその理由をずっと考えていた。でも、それ以外の時間に陽雪のことで頭の中がいっぱいになったりはしなかった。 なんで百音のことはこんなに気になって気になって仕方がないのだろうか。 「ちっ」 苛立ちのままにじょうろで植木を殴った。数枚の若葉が散る。地面に落ちた葉を踏みつけた。青い汁が地面にこびりつく。そんなものを見ても、気分はちっともすっとしない。それでも竹緒は、数回その行為を繰り返した。 理由なんかない。しかし、そんなことでもしていなければやってられなかった。 破壊すればするほどわき上がってくる衝動は大きくなり自分でも止められなくなる。 この植木の葉を全て散らせてやる! 不意に頭に冷たいものを感じた。 小さく悲鳴を上げながら飛びのく。すぐに頭に水をかけられたのだと分かった。振り返ると、冷たい眼差しをした環が立っていた。 「止めてちょうだい」 環はよく怒る。 幽霊部員の竹緒は部内で怒られることが多かった。先輩は勿論、同級生にも怒られた。でも、彼等はしだいに怒らなくなった。園芸に興味のない部員を許容したのではなく、諦めたのだ。その中で環だけは怒り続けた。部長になる前から、なってからはますます怒り続けた。 だから竹緒の中での環の印象は、怒っている顔しかない。 でも、こんなに冷たい表情は見たことがなかった。 低く抑えられた声は聞いたことがなかった。 今までとは違う。環は本気で怒っているのだ。 「もっと頭を冷やしたい?」 環は抑えた声のまま、手にしたじょうろを振った。 「十分冷えました」 「そう、良かった」 環はじょうろを持った手を下げると、傷つけられた植木に近寄って葉を優しくさすった。無言で、葉を一枚一枚さすっていく。冷たい表情は消えていたが、それは怒りが冷めたからではなくて、植木を慈しむためなのは竹緒にも分かった。環は無言で葉を撫で続ける。 耐え難い沈黙の時間が続いた。このまま逃げてしまおうかとも思った。園芸部にいられなくなっても、夏合宿に行けないのが残念なぐらいで他に不都合なことはない。 でも、このまま立ち去って環に嫌われたくなかった。環にまで諦められたくなかった。 「すいませんでした」 どうすれば良いのか分からなかったから、とりあえず頭を下げた。 「私に謝ったって仕方がないわ」 環は冷たく返す。 ほんの少しだけ迷った後、もう一度、今度は植木に向かって頭を下げた。 「すいませんでした。もうしないんで許してください」 頭の上でクスリと笑った声が聞こえた気がしたが、顔を上げても環は笑っていなかった。 「何をイライラしていたのかは知らないけど、植物にあたるのは止めて。この子達は弱いんだから。新井君だって、アリを踏み潰して遊んでいる人がいたら腹が立つでしょう。同じことよ」 「はい」怒られながらも、アリを例に出してくれたのが嬉しかった。 「木を殴っても気分は晴れなかったでしょう。でも、植物は優しく接すればちゃんとその気持ちに答えてくれる、優しく接すれば、ちゃんと癒してくれるの。だからイライラした時は、植物にあたるんじゃなくて、そんな時こそ優しく接するの。そうすれば、植物は自分が一番良い気持ちにさせてくれるから」 「なんか、実感がこもってますね」 「そうよ。サボリ魔の後輩に腹が立ってばかりだから、植物に癒してもらってるの。どうしたらクラブに出てきてくれるんだろうって、相談しながらね」 「どんな答えが返ってくるんですか」 「残念ながらすごい難問みたい」 環はやさしい顔で微笑んだ。さっきの無表情な顔を思い出せば、これが植物の癒しのパワーかと、信じる気持ちになれた。 「そうだ!」 環は突然顔を輝かせた。 「アリは植物を食べるでしょう。だったら植物の好き嫌いがあるんじゃないかしら。花の蜜が好きなアリとかもいるかもしれない。逆にアリを利用している植物もいるんじゃない。他にも……アリを食べる植物とか。そんな風に考えたら園芸部の活動も少しは楽しくない?」 「……その木が教えてくれたんですか?」 「自分で考えたのよ」 環が嬉々として提案してくれたことは、知識としてすでに知っていることだった。日本ではアリは地面の中に巣を作るという考え方が一般的だが、木に巣を作る種類もたくさんいる。植物とアリの関係はとても密接だ。でも、そんなことは環に言わない。 「今度調べておきます」 「面白いことが分かったら教えてね。そうね、文化祭で発表するのも良いかもしれない」 「勘弁してください」 「せっかくの人材なんだから有効に使わないとね。それじゃあ、そろそろ帰りましょうか」 空はすでに薄暗くなっていた。月はどこだろうと探してみた時、校舎の窓からこちらを見下ろしている人影に気がついた。偶然なのか、竹緒の視線に合わせて人影はすぐに消えた。 長い髪を持った人影は百音のような気がした。でも、環と普通に話せて浮かれている今の竹緒は、「まだあの女のことを考えてるよ、こいつは」と笑い飛ばせるぐらい余裕だったので、それが誰なのかを真剣に考えたりはしなかった。 翌日、金曜日の五十鈴百音は明らかに不機嫌だった。 竹緒は朝の挨拶すら気づかないふりをされてしまった。 でも、昨日の環との会話を考えれば気にはならなかった。いつも怒られてばかりだった環とも普通に話せたのだ、百音の気分屋なところにもそのうち慣れるだろう。 放課後にカラオケボックスで行われたクラスの親睦会では、百音から遥か離れた席になってしまったが、仕方がないと思えた。例の噂はまだ収まっていなかったが、百音が人気者であることに変わりはない。男子女子入り乱れての熾烈な席取り合戦はなかなかに見物だった。 親睦会は盛況だった。クラブに入っていたり、塾に行っている者が多いはずなのだが、ほとんどがさぼって参加していた。百音人気もあるが、クラス委員長になった南田の求心力が強いのだろう。まだ始まったばかりだというのに南田の周囲では大騒ぎになっている。竹緒はあののりには入っていけない自分を実感しながら、隣に座る加賀見沙夏(かがみしゃな)に話しかけた。 「でも、加賀見さんが来るって意外だな。今日も塾だったんじゃないの?」 南田が人気で委員長に選ばれたのだとしたら、副委員長の加賀見は成績で選ばれたと言える。成績は学年では常にトップスリーに入っているし、塾で行われている全国模試でも百位以内の常連らしい。竹緒は昨年もクラスが一緒だったが、常に勉強をしているイメージしかなかった。 「幸運なことにね、塾はお休みだったの」 薄く笑う加賀見の顔は、陽雪のものとも、百音のものとも、昨日見たばかりの環の笑顔とも違った。 みんな、それぞれの笑顔を持っているのだ。 不意にそんなことに気がついてしまう。 「どうしたの?」 「なんでもない」 加賀見ならそんな話も落ちついて聞いてくれそうだったが、恥ずかしくて言えるわけがない。 「でも、こういう賑やかな場って苦手なイメージがあるんだけど」 「よく言われる。確かに得意ではないけれど、嫌いではないわ。あんな風に騒いだりはできないけど」 南田たちは肩を組んで流行歌を合唱している。ラップのパートなんてめちゃくちゃで何を歌っているのかさっぱり分からない。加賀見はその様子を楽しそうに見ながら言った。 「でも、最近の新井君も結構意外よ」 「オレが?」 「ええ、澤井さんと付き合った時もびっくりしたけど、別れたと思ったら今度は五十鈴さんでしょ。意外と恋多きタイプなのね」 「なんだよそれ。五十鈴さんとはなんでもないよ。澤井さんの時は、告られたのはこっちだし」 「否定しなくてもいいじゃない。恋多き青春って素敵だと思うわよ」 「そこまで言うなら、加賀見さんは恋してるの?」 「私は恋とか良く分からないから……」 「ずるいなぁ」 「そう、意外とずるい女なの」 「意外だなんて言ってない」 加賀見はくすくすと笑う。 その後は他愛のない世間話をした。トイレで席を外して戻ってきた時に他の女子に加賀見の隣が奪われていたのは少し残念だった。その後、伊刈君が山篭りで編み出した必殺技に大喜びで拍手したいるのをは見ていて面白かった。 クラス会は南田と西條の半裸でのデュエットで、大盛況のうちに幕を閉じた。 解散後、加賀見に声をかけられた。 「来週の土曜日からアントって映画が公開されるのは知ってるでしょう。南田君や倉田さんたちと見に行く約束をしているんだけど、新井君も来ない?」 渡り鳥から始まり、海洋物、ペンギンと続いている最近の大自然ドキュメンタリー映画のヒットにあやかって制作された映画「アント」は、アリをメインにおいたドキュメンタリー映画であり、竹緒はもちろん知っていた。ゴールデンウィーク中に何回観に行くのかを綿密に計画している。 来週の土曜日は始発で出発して並ぶ予定だった。頭の中で素早くスケジュールを組みなおす。すぐに、一日二回観ても何の問題もないと結論が出た。 「それじゃあ、詳しくは来週ね」 加賀見はそう言って帰って行った。去年はまともに話したことがなかったのに、今日一日で映画に誘われるぐらいの仲になったのはとても不思議な気分だった。話した分だけ意外な一面を知ることができた。それに、加賀見と南田が同じグループで映画を観に行くなんてのも面白い発見だ。 人は見かけでは判断できないのだと改めて思う。ちゃんと話してみなければ、お互いのことは分からない。 「オレが恋多き男だなんて誤解は解けたのだろうか?」それが少し気になった。 今日だって一度も百音の近くには座らなかったし、話もしていない。それでも十分に楽しく過ごせた。 五十鈴百音は歌が得意ではないって情報は頭にしっかりとインプットされたけれども、それはクラス全員の共通認識のはずだ。
|