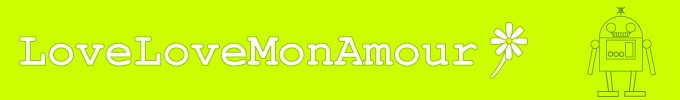
|
キミのフェロモン 中編
「なにを企んでいるの?」 土曜日の朝に竹緒が学校に姿を見せると、環はあからさまに怪訝な表情を見せた。 「先週さぼったから、その代わりに来たんです」 「本当にそれだけ?」 残念だが、木曜日の一件ぐらいでは信用を得られなかったらしい。 「それだけです。そんなことより部長一人なんですか?オレ以外にもさぼってる奴がいるじゃないですか」 「用事ができたってちゃんと連絡がありました。君と違ってね」 指摘する環の口調は怒ったときのものだったが、いつもとは様子が違った。ひどく慌てていて、それをごまかすために怒っているように見える。それに、おかしな点がもう一つある。 「すいません。でもそれは反省したから、今日はこうやって来てるんじゃないですか。それより、一つ訊いてもいいですか」 「なによ」 「さっきから後ろになにを隠してるんですか」 環と会ったのは庭園へ向かう通路だった。きつく縛られた三つ網は、後ろからでもその持ち主が誰なのかすぐに分かった。竹緒が声をかけると、振り返った環は慌てて手に持っていたものを背後に隠した。さっきからの会話の間にも、隠したものが見えないように体で必死にブロックしている。 「な、なんでもないわよ。肥料、そう肥料を撒こうと思って」 「活動日でもないのにですか?」 「いいでしょう。私は部長なんだから、肥料を撒く日を決める決定権を持ってるわ。今日はとても良い肥料日和なの。新井君も手伝ってくれるなら、倉庫からスコップを取ってきてくれる」 「はい」 答えたが、竹緒は動かない。 「は、早く行ってきてよ」 「だって倉庫はそっちじゃないですか」 倉庫があるのは環が向かっていた方向にあった。つまり、竹緒が倉庫に行くためには環の横を通っていかなければならない。 「た、体育用具倉庫に行けばいいでしょう」 「なんでわざわざグランドの端にまで行かなきゃいけないんですか。そもそもあっちにスコップなんかありましたっけ?」 「いいから行きなさいよ」 「……やっぱり嫌です」 環がそこまで隠したいのなら無理に見る気はないが、遠い体育倉庫にまで行くのも嫌だった。大人しく横を通って倉庫へ行こうとしたが、環は実力行使に出られると勘違いして、過剰に反応した。結果、環はバランスを崩してしまい、背中に隠していたものを落としてしまった。 小さな悲鳴と一緒に、軽い音を立てて薄緑色のプラスチック製のボウルが床に転がり、その中から更に赤いものが転がり出た。 「……イチゴ?」 ボウルからこぼれたのはイチゴだった。 環は慌てて落ちたイチゴを拾い集め始める。竹緒が手伝おうとすると、手を払われてしまった。 「もう隠す必要はないんじゃないですか?」 環は答えずに黙々とイチゴを拾っていたが、全て拾い終わると立ち上がり、深い息をついた。 「ついてきて」 そう言ってさっさと歩き始める。 「倉庫ですか?」 「うるさい」 連れて行かれたのは校舎の屋上だった。園芸部がこの一角にプランターを並べているのは、竹緒も土や肥料を運んだから知っている。環はプランターの間を縫って水道の蛇口まで行くと、落ちたイチゴを洗い始めた。 「あーあ、潰れちゃってるじゃない」 ぶつぶつと文句を言っている。 洗い終わると奥に立つ給水塔まで行き、イチゴの入ったボウルを竹緒に渡して梯子に手を伸ばした。二段だけ上るとすぐに降りてきて、ボウルを奪い返すと、先に上るように言った。 環の赤くなっている顔を見て、竹緒はスカートのことに気がついた。辺りを見回してから梯子を上る。後から上ってきた環に従って給水タンクの裏に行くと、狭いスペースにプランターが二つ置かれており、まだ熟しきっていないイチゴが実をつけていた。 「分かった?」 環はメガネの奥からじろりと睨むと、返事をまたずにさっさと戻っていった。梯子を降りると給水塔の壁に背を預けて床に座り、イチゴを食べ始めた。竹緒もボウルを挟んで腰を下ろした。 イチゴはどんどん減っていくけれども、環はなにも言ってくれない。竹緒が我慢できずに手を伸ばすと、「駄目よ」と止められてしまった。 「責任を持って、潰れた奴を食べなさい」 そう言って潰れたイチゴをつまみ上げると、ヘタを持って突きつけてくる。 つかの間、躊躇した。 しかし、環の鬼気迫る顔を見れば断ることはできなかった。 「すっぱー」 意を決して食いついたイチゴは予想に反して非常に酸っぱかった。 「そうね、ちょっと失敗しちゃった。もういらない?」 「頂きます」 残念ながら、環はもう手ずからは食べさせてはくれなかった。 潰れたイチゴを選んで食べたが、どれも酸っぱかった。これが品種改良されていないイチゴ本来の味なのかと勝手に解釈しながらどんどん食べる。 環には訊きたいことがいっぱいあったが、今はイチゴを食べることに集中していたくなった。環も無言でイチゴを口に運ぶ。酸っぱいイチゴはすぐになくなった。 環はプランターの土の中にヘタを捨て、ボウルを洗うとさっさと階段を降りていった。一階につくと、くるりと振り返る。 「当番の仕事は終わっているから、今日はもう帰っていいわよ」 「それじゃ、オレはイチゴを食べに学校に来ただけじゃないですか」 せっかくやる気になった気持ちを削がれた気分になって非難の声を上げたが、逆にぐいっとボウルを突きつけられた。 「分かっていると思うけど、今日のことは秘密だからね」 環の声は本気モードだった。 「えぇっと、秘密って言うのはどの辺りにですか?」 「全員よ」 「津田さんにも言ってないんですか」 「そうよ、私とキミだけの秘密」 その答えに竹緒は驚く。親しい園芸部員にも打ち上げずに一人で栽培していたとは思っていなかった。 「なにが秘密なの?」 静かな通路内に響いた声の持ち主は幸運にも園芸部員ではなかったが、不幸なことにもっと面倒な相手だった。 私服の五十鈴百音が腕を組み、不機嫌な顔で立っていた。 竹緒が答えあぐねていると、環がずいっと前に立って丁寧に答えた。 「ごめんなさい。部内の話なの」 「あなたに訊いてるんじゃないわ」 「どうして?部内の情報を外に出すかどうかは部長である私が決めるの」 「横暴なのね」 「それは部員が決めることよ。部外者のあなたが決めることではないわ」 先週の土曜日、百音は環を知らなかった。新学期早々有名になってしまった百音を環が知っていても不思議ではない。しかし、二人が初対面なのは確かだろう。その初対面であろう二人がいきなり言い争い始めた理由が、竹緒にはさっぱり分からない。 「それじゃ、私も入ればいいのね」 「あら、入部希望なの。歓迎するわ。但し、横暴な部長がいるらしいけど大丈夫?」 明らかに環の方が上手だった。年の功などと言うと環が怒るだろうが、、むしろ、百音はこの手の駆け引きが苦手なように思える。今も必死で反撃の一手を考えているのだろうが、出てくるのはきれいな顔を流れ落ちる脂汗ばかりで、気の利いた一言はいつまで経っても出てこない。 挙句の果てに、 「新井君、帰るわよ」 との捨て台詞を残して歩き始めた。 「え、帰る?」 百音は通路の端で立ち止まって首だけ振り返り、こちらを睨みつけてくる。そこでやっと、竹緒は先ほどの百音の言葉の意味に気がついた。 「早く!」 百音に急かされたので、考えるよりも先に身体が動いた。 「それじゃあ、失礼します」 あたふたと駆け寄るが、百音は待ってくれずにさっさと歩いていってしまう。ようやく追いついたのは校外へ出てからだった。 「待ってよ五十鈴さん。いったいどこへ行くの」 「どこ?」 百音はピタリと立ち止まって、竹緒の顔を見る。すぐに目を逸らすと、あわあわと話し始め、 「ど、どこに行こうかな。どこが良い?私はその、そういえば陽雪と約束があってって言うか、陽雪と遊んでて、それで、えーと用事があるからもう行くね。また来週」 と、手を振って去って行った。 さっぱり意味が分からない。 陽雪の名前が出ていたが、また彼女の差し金なのだろうか? 「あーあ」 竹緒は最近多くなったため息をつきながら歩き始めた。もう学校には帰れない。大人しく家に帰る気分にもなれない。 ただ、だらだらと歩き続ける。 「なんかまた、意味のない一日を過ごしているな」 百音と分りあえる日は一生来ないのではないだろうか。 顔を上げれば、憎らしいほどに青い空が広がっている。 気分は、水色のジェルの中にずぶずぶと沈んでいくアリのようだった。
|