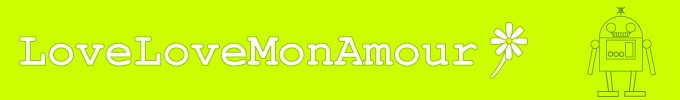
|
キミのフェロモン 後編
新学期が始まってから続いていた晴天は日曜日の午後から崩れ、夜には雨が降り始めた。 月曜日の朝も雨は降り続いていた。 新井竹緒(あらいたけお)はいつもより早めに登校し、色とりどりの傘をさして登校する生徒の中から澤井陽雪(さわいつゆき)を見つけ出した。噂好きの元彼女が、毎日早朝に登校して情報収集にいそんしんでいるのを知っているのは、付き合っていた頃に何度か付き合わされたからだ。 「タケから誘ってくるなんて珍しいな」 陽雪は屈託なく笑顔を作る。 パパラッチなんて好ましくはないあだ名をつけられながらも、本人は決して嫌われない魔法の笑顔だ。陽雪の標的にされた者は、例えその場では怒ったとしても、その笑顔を見るとなんとなく許してしまうのだ。 竹緒は見慣れたその笑顔に愛想笑いも返さずに先に立って歩き始めた。授業が始まるまでに訊いておきたいことがあった。いつものように煙にまかれて時間切れになるつもりはなかった。 理科室の扉を開く。 月曜日の一限目にこの教室を使うクラスはない。さらに月曜の朝は職員会議が行われているので隣の理科準備室に担当教師はいない。一般教室からは離れた場所にあるので、他人に聞かれたくない話をするには最適だ。と、陽雪に教えてもらった場所だ。 室内の空気がこもっている気がしたので窓を一つだけ開けたが、風は入ってこなかったため、じめじめした気分はあまり変わらなかった。 陽雪は教室の真ん中から竹緒を面白そうに観察している。 「土曜日のことだ」 竹緒は問う。 土曜日、園芸部の活動に参加する為に登校した竹緒は、園芸部部長である大場環(おおばたまき)の秘密を偶然知ってしまった。これまで、口やかましく怒ってくる先輩というイメージしかなかった環のかわいい秘密を知ることができたのは少し嬉しくて、おかげで少し親しくなれたのは嬉しかった。 そこに五十鈴百音(いすずももね)が突然現れた。 百音は一瞬でその場の平和な空気を力技でぶち壊し、竹緒を強引に連れ出した。 そのままデートにでも連れて行ってくれればよかったのだが、百音は意味不明なことを叫ぶと竹緒を置き去りにしてどこかへ行ってしまった。 二週間前の始業式に転校してきた百音は、一週間で校内一の称号を手に入れたほどの美少女である。その美貌をしっかりと自覚しつつも、鼻にかけずに、誰とでも気さくに付き合う、そんな高スキルを取得している少女だ。 しかし、なぜか竹緒に対する態度だけは違った。 それは自己紹介のとき、名前を名乗っただけで睨まれることから始まった。 それからは意味不明のちょっかいを受け続けている。 百音によれば竹緒は何かを忘れているらしい。それを思い出せと強要されているのだが、なんのことだかさっぱり分からなかった。思い出を共有しているのであれば、百音に会ったこともあるのだろうが、竹緒の人生においてこんな美少女と出会った記憶はなかった。 竹緒がいつまでも思い出さないことに、百音は怒り、無視し、暴力を振るう。 他のクラスメイトと接している時からは、全く想像できない姿だった。 そして土曜日、百音はようやく和解できた環との仲を再びぶち壊してくれた。本来であれば百音に抗議し、説明を求めれば良いのだろうが、これまでの経験からまともな話し合いにならないことは分かっていた。 ならば陽雪に訊くのが最適だと考えた。 陽雪の元には学内の様々な情報が集まっている。しかも、百音は去り際に先ほどまで陽雪と一緒にいたと言っていた。ならば、百音は陽雪になにかを吹き込まれたのだと考えるのが自然だ。 陽雪が好きなのは噂だけではない。 噂となりえるような状況を自ら作り出すことも好きなのだ。 それも付き合っていた頃に散々思い知らされた。 「五十鈴さんになにを言ったんだ」 「なにも」 陽雪はいつもと同じようにしれっと答える。 「土曜日は百音と一緒に出かける予定だったんだ。二人で歩いていたらタケが通りかかった。制服を着ていただろう。百音がなんで制服を着ているんだろうって訊ねてきたから、多分園芸部の仕事があるんだろって答えた。そうしたら、百音の表情が硬くなった」 陽雪は嬉しそうに笑う。 「だから言ってみたんだ。多分、あの女部長と二人っきりになるんだろうなって」 「なんだそりゃ」 確かに環と二人きりだったが、それは当番の生徒が休んだ為だ。竹緒は環が一人で作業をしていることは知らなかったし、環も竹緒が来るなどと思ってもいなかった。 二人きりになったのは事実だが、それは偶然だ。 いかに陽雪が情報通といえども、知っていたはずがない。 でたらめだ。 ではなぜ、陽雪はそんなでたらめを言ったのか? 「面白そうだから、もしくは興味深いからだな」 陽雪は質問にそう答える。 「面白い?」 いつだって彼女は楽しそうに噂をばらまいている。付き合い始める前から陽雪の数々の所業を見ていたから、竹緒はそれに関して疑問を持ったことはなかった。 女子が噂好きなのは珍しいことではない。陽雪はそれが際立っているだけだ。好きで好きで仕方がないから、あちらこちらで噂を収集し、あちらこちらでそれを広める。 それが全てだと思っていた。 でも、なにかがひっかかった。 今日に限っては、いつもの笑顔の後ろになにかがあるように感じた。 「澤井さんは……」 その疑問は竹緒の頭の中で生まれたばかりで、まだはっきりとした形になっていない。しかし、それが具体的な形を取るのを待ってはいられなかった。 竹緒にそんな疑問を抱かせた今の陽雪。いつもとは違う今の彼女に問いかけなければ、それに対する答えは絶対に返ってこないと直感が告げていた。 しかし、考えれば考えるほど頭の中が混乱して考えがまとまらない。 オレはなにを言おうとしているのか? オレはなにが聞きたいのか? 聞きたいこと……、興味があること……。 「澤井さんは、なにに興味があるんだ?」 竹緒の精一杯の問いかけに、陽雪の細い目がいよいよ細くなる。本当になくなってしまうのではないかと思わせるほどに細くなる。 極細の糸のような目で上弦の弧を作り、口元も大きな笑みを作る。 ニコニコマークそっくりだった。 陽雪はいつも笑っている。でも、こんな笑顔は始めて見た。 でも、ニコニコマークはすぐにいつもの笑みに戻ってしまった。 見慣れた笑顔、そしてとぼけた口調がそこにある。 「いつの時代だって、乙女の興味の対象は恋愛に決まっているだろ」 その答えは真実なのかもしれないが、竹緒は茶化された気がした。 「そんな話をしているんじゃない」 「そんな話だよ」 陽雪の言葉に合わせるように鐘が鳴った。 「時間切れだ」 陽雪はそう言うと机の上においていたカバンを手にとって、さっさと教室から出て行った。 竹緒が窓を閉めてから廊下に出ると、陽雪は待ってくれていた。二人は黙って歩き始める。 廊下は遅刻スレスレで飛び込んできた生徒たちが駆け回るトラックと化していたが、本鈴がなるまでにはまだ少し時間があったので二人はゆっくりと歩いた。 先に竹緒の教室の前に着いた。 「私からも質問していいかな」 陽雪の目は少しマジだった。 「百音と大庭先輩、本命はどっちなんだ?」 「は?」 全く予想外の質問だった。 百音と大庭先輩を比較する対象して考えたことなんてなかった。 本命も何も、大庭先輩は先輩だし、百音は…… 「おっと時間切れだ」 いつの間にか本鈴が鳴っていた。 我に返れば、目の前にあるのは百音でも大庭先輩でもなく、別れた彼女である陽雪の笑顔だった。 「それじゃ」 陽雪はすちゃっと手を上げると、質問の答えには興味がないかのように自分の教室へと走っていく。ぼんやりとそれを見送っていると、後ろから小突かれた。 「なにしてんだ、新井」 出席簿を持った岩坂先生は言いながらも、竹緒の視線の先に気づく。 「なんだ、お前らやっぱりまだ付き合っているのか?」 「そんなんじゃありません」 反論しながら教室に入る。その後に続いて岩坂先生が入ってきたので、生徒たちはバラバラと立ち上がった。竹緒は慌てて一番前の列の窓際から二列目の自分の席に急ぐ。一番窓際の席にちらりと目を向けると、百音は眉間にしわを寄せていた。 姫は今日も不機嫌なようだ。 やれやれと思いながら席につく。 雨はしばらく降り続きそうだった。
|