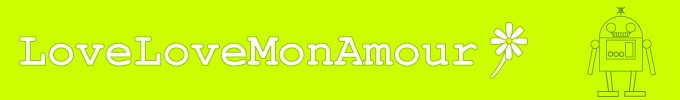
|
キミのフェロモン 後編
『最後の一枚は、絶対に死守するんだからね!』 子供っぽい声と共に、アニメキャラクターがポーズをつけている。 放課後、竹緒は南田慶二(なんだけいじ)に誘われて駅前のゲームセンターに来ていた。 竹緒は一人でゲームセンターに行くタイプではなかったが、誘われれば断ったりもしない。 クラス委員長である南田はあるゲームにはまっており、クラスメイトを誘ってはチャレンジを繰り返していた。 それが今プレイしている通信対戦型脱衣クイズゲーム「マジカル大作戦Qチーム」である。基本的にはクイズゲームであり、出題された問題に答えていく方式なのだが、このゲームの特徴として、正答すると出題者であるキャラクターの服を脱がせることができる。 序盤に登場してくる出題キャラクターは文房具や動物、老人やむさいおっさんという脱がせがいのないものだが、ゲームが進むにつれてそれらが美男美女へと代わっていく。 それに合わせてクイズの難度も上がっていく。 「我等がクラスの知力と友情を見せ付ける良いチャンスだ!」 南田はそんな言葉でクラスメイトを誘っては挑戦を繰り返しているが、どちらかが足らないのか、それともどちらも足りないのか、いまだにクリアしたことはないらしい。 しかし今日は快調だった。 すでにかなりの問題を覚えてしまっている南田。 必殺技が使える将棋部 伊刈竜平(いかりりゅうへい)。 アリの知識は豊富な竹緒。 この様に書くと竹緒一人が役立たずのようだが、二人が分からない問題が妙な具合に竹緒の知識や記憶に引っかかり、正答を重ねることに、服を脱がせることに役立っていた。 南田のこれまで犠牲になった百円玉の成果、伊刈の鋭い直観力、二人の穴を埋める竹緒、三人の力がうまく重なり、三人は脱がして脱がして脱がしまくった。 そして先ほど、最後の敵であるサッキュバスのグラマラスな肢体を拝むことができた。 しかしこのゲームはそこで終わりではない。 ラスボスを倒した時点での回答率が高かった場合にのみ進めるエクストラステージが存在し、そのステージではゲーム開始時に選択するアシスタントキャラクターと対戦する、つまり脱がすことができる。 南田が選んだのアシスタントキャラクター(標的)は「魔法少女パン・プリン」だった。 黄色のひらひらした服を着た少女は薄着に見えて攻略は簡単に思えるのだが、信じられない重ね着のために脱がしても脱がしてもなかなか終わりが見えなかった。 エクストラステージにはコンティニューなどといった軟弱な救済措置は存在しない。南田はこれまでに二度、エクストラステージまで辿りついたが、どちらも夢半ばで散って行ったらしい。 そして今、三人は最後の一枚に挑もうとしていた。 『最後の一枚は、絶対に死守するんだからね!』 子供っぽい声と共に、魔法少女パン・プリンが右手の人差し指を突きつけてくる。 しかし、左手はあらわになったわずかな胸のふくらみを隠し、下半身は白のパンツのみという格好では、いささか迫力に欠ける。マヌケな格好とも言える。 しかし、偉業達成を目前とする男たちには関係なかった。 「脱がす、絶対脱がす。今日こそ脱がす」 「花はいつか散るものと、身をもって知るがいい」 「オレたちは絶対に負けない」 裸のグラフィックが見たいのではない。 オレたちは脱がしきったのだ!その瞬間の感動を、一体感を求めて、テンションを最高潮にまで上げながら筐体に向かう。 『第一問!』 画面が切り替わると、三人は真剣な顔で画面を凝視する。 最終ステージのクリア条件は五問正答。ライフは使い切ってしまっているため、もう間違いは許されない。五問連続で正解しなければならない。 一問目は南田がクリア。 二問目は伊刈の直感がきらめく。 三問目も南田がクリアする。 一問ごとに三人のテンションはますます上がり、店の迷惑も考えずに奇声を上げて騒ぎまくる。 もっとも店内は多種多様なゲーム機の音で充満されているし、客のほとんどは同年代の学生ばかりだから、迷惑に感じているものなどいない。 『第四問!テレビ番組「昔・しんかんせん物語」で金太郎がモチーフとなっているキャラクターのニックネームは? 1.きんちゃん 2.ももちゃん 3.くまちゃん 4.まさちゃん』 「あぁ!昔見てたけど、……なんだっけ?」 まず南田が頭を抱える。 「見えんな」 額に指を当て、目を閉じていた伊刈が告げる。 「2番、ももちゃんだ」 竹緒は断言する。 「金太郎だぞ。金太郎なのにももちゃん?」 「間違いない。キビ団子を持ってたから勘違いされたんだ」 「そうだ!」 南田が叫んでボタンを押す。時間切れぎりぎりで正解の音楽が流れた。 「思い出した思い出した。尻を出して、ピーチサイン、ってやる奴だ」 昔・しんかんせん物語は「しんかんせん」と名がつくわりには新幹線は全く出てこない不思議な子供向け番組だった。昔話のキャラクターたちが騒動を起こしながら東海道を旅していくストーリーだった。 それほど人気はなかったが竹緒は好きだった。特に、本当は金太郎なのにキビ団子を持っていただけで桃太郎扱いされていた「ももちゃん」が好きだった。 ああ、これか、と思い出した。 先日、百音が子供の頃の友人に「ももちゃん」と呼ばれているのを聞いた時、その呼び名に聞き覚えがある気がした。しかし、それは百音とはどうしても結びつかなかったのだ。 百音はそれにも不満を持っていたようだったが、そもそも竹緒の中での「ももちゃん」は百音ではなく、テレビアニメのキャラクターだったのだ。 謎が一つ解けて少しほっとした。 しかし安心はできない。百音絡みの謎はまだいくつも残されているのだ。 「よっしゃーぁぁぁぁあああ」 竹緒の気がゲームから離れている間に、南田たちは最終問題をクリアしていた。ついに完全制覇である。南田は大声で咆哮し、両手をあげて喜ぶ。その手が勢いよく竹緒に当たった。 二人用のシートに三人で腰掛けてただでさえバランスが悪い。加えて、意識が他に向いていた竹緒の小さな身体は、そのまま後ろにひっくり返った。 慌てて南田の肩を掴もうとしたが、手はむなしく空を掴んだ。 このまま後頭部から床に突っ込むのだと頭の隅で覚悟した竹緒だったが、後頭部は床に達するよりもかなり手前でなにかにぶつかった。 小さな叫び声と感触から、後ろにいた人にぶつかったのだと分かった。 「すみません」 南田に助けてもらいながら身体を一度起こしてから、振り返って謝った。 そこにいたのは竹緒にとってあまり会いたくない人物だった。 それは相手にとっても同じだったらしい。 「お前……」 男はそう呟いて目じりをぴくりと上げて何かを言いかけたが、その言葉を飲み込んで連れと一緒にその場を去ろうとした。しかし、竹緒が胸をなでおろす前に歩みを止め、振り返った。ずいっと竹緒の前に立つ。竹緒たちと同じ制服を着た男子生徒の身長は高く、体格はがっちりとしており、目の前に立っているだけで迫力がある。 更に鋭い眼光で見下ろされると恐怖すら感じる。 「お前、ちょっと付き合え」 男は低い声でそう告げた。その声に竹緒よりも南田が先に反応する。 「おいおい、ちょっとぶつかっただけだろ」 南田と一緒に伊刈も立ち上がる。三人の背後のモニターでは魔法少女があられもない姿をさらしていたが、男たちはそんなものには目もくれずに新たに現れた敵に対峙する。 「そんなんじゃねー。こいつとちょっと話があるだけだ」 男は難儀そうに手を振って竹緒に目を向ける。 「いいだろ」 竹緒は頷いてから立ち上がり、南田たちに告げた。 「ありがとう。でも多分大丈夫だから」 「やばくなったらすぐ呼べよ」 「大丈夫だろ。体育会系がこの時期に不祥事を起こしたりしない。ですよね、先輩」 「さっさと来い」 バレー部の主将は質問には答えずに背中を見せた。 西浩二郎。竹緒の前に、陽雪と付き合っていた男である。 澤井陽雪は噂の発信源として有名である一方、噂のネタとしても有名だった。 彼女は去年一年間だけで五人の男と付き合い、そのたびに噂が広まった。噂の発信元は今でも不明だが、陽雪が自分で流したとする説が有力である。 陽雪は入学式の次の日には、答辞を読んだ主席と付き合っていた。最初の中間試験が終わる頃には地元のライブ会場を沸かせている軽音楽部の三年生と付き合い始めていたが、夏休みを一緒に過ごしていたのは一年生のオタク男子だった。 そして、二学期の途中から付き合っていたのがバレー部エースの西である。 バレーの腕は確かだが、長身で強面、ぶっきらぼうな物言いで後輩はもちろん先輩どころか教師からも恐れられている男が女子と付き合うというだけでも意外だったが、その相手が陽雪ということで、学校中の注目の的となった。 しかしその関係も冬休み前、クリスマス直前に破局となったが、それ自体は大きな話題にならなかった。。 その頃には、何ヶ月で別れるのかが賭けの対象になっていたし、次の相手が誰になるのかが話題の中心だったからだ。 そして次の相手としては誰も予想していなかった竹緒が選ばれた。オッズ二百六十一倍で親の総取りの関係は、二ヵ月半という最長記録で終わった。 竹緒自身も、クラスメイト以上の付き合いをしたことがなかった陽雪の彼氏になることを予想も期待もしていなかった。付き合っていた頃も、何がなんだか分からないままに付き合い、分からないままに別れた。そんな印象しかなかった。 不思議な関係だった。 今になっても、陽雪の気持ちも考えも分からない。 では、他の彼氏たちはどうだったのだろうか? それは少なからず興味のあることだった。 西はゲームセンターから出ると、傘をささずに少し離れた店へ走っていった。潰れたタバコ屋の中は壁一面に自動販売機が並び、その真ん中にボロボロのベンチが置かれている。 店内に照明はなく、自動販売機からの光だけが薄暗いタバコ屋の中を照らしている。 西は自動販売機でコーラを二つ買うと、一方を思い切りよく何度も振ってから、遅れて入ってきた竹緒へポンと投げた。竹緒は受け取ったものの、困ってしまう。嫌がらせとしか思えないが、どのように反応すべきだろうか。 「冗談だ」 西は竹緒の手からコーラの缶を奪うともう一方を押し付けてきた。そして缶の縁を口元まで持って行き、がりっと噛み付いた。勢いよくコーラが噴き出したが、西は一滴もこぼすことなくそれを口で受け止めた。噴出が止まると、満足気にベンチに腰を下ろす。 これが彼の得意技なのだろうか。ここは褒めるべきなのだろうか。 迷った竹緒はとりあえず感心して見せた。 「陽雪は大喜びしてくれたんだけどな」 西のぼやきに、竹緒はあいまいにうなずく。 だからどうしたと言うのだ。竹緒はモトカノの前の彼氏なんて、微妙な立場の人間の感傷に付き合う趣味はない。当初の興味は薄まり、さっさと終わらせたくなったから、自分から話を切り出した。 「なんの用ですか?」 「用……、別に用ってわけじゃないんだが……」 まだ言葉をにごす先輩にいらいらしながら、結論を急がせる。 「澤井さんのことですよね」 想像していたよりも押しの強い後輩にうながされて、西はようやく本題に入った。 「お前は陽雪と別れたのか?」 「別れましたよ、なんでですか」 竹緒が陽雪と別れたのは春休みの直前で、しかも新学期は百音という新たな話題の中心が現れたために、別れ話の噂はそれほど大きくはならなかった。しかし、陽雪に興味を持っている者が聞き逃すほどではなかったはずだ。 「そのわりにはまだ仲良くしているみたいじゃないか」 「それは……、同じ学年ですから」 「八角もデブ小田も、お前のように親しくしていない」 西は同学年の主席とオタクの名を上げる。確かにそうかもしれない。だとすれば考えられる可能性は一つで、竹緒はそのことにずっと前から気がついていた。 「今、一番噂になっている人物、その近くにオレがいるからだと思います」 「……五十鈴百音か」 陽雪が興味を持つのは噂の対象となる者だ。現在、学内で一番の噂のネタが百音であるのは間違いなく、竹緒は少なからず彼女に関わっている。だから陽雪は竹緒にも興味を持ち、近づいてくる。 そこには元彼氏に対する感情なんて一欠けらもない。 他の噂のネタと同列の対象だ。 そうでなければ、春休みの間に電話ぐらいかかってきたはずだ。 一度だけかかってきた電話は、転校生に関する噂を広げるためだけのものだった。 陽雪は噂のネタにひかれる。それは同じモトカレである西を納得させるには十分な理由だった。 「なんで別れたんだ?」 質問の内容が変わった。 「知りません。一方的に別れを告げられたんです。ちなみに、付き合ったときも一方的に告白されたんです」 「そうか、みんな一緒か」 「先輩もですか」 「五人全員だ」 西の手の中で空き缶がベコベコと音を立てて潰れた。 しばらく無言になった二人の後ろで雨が降り続く。やがて西が立ち上がり、ぺしゃんこに潰れた空き缶をゴミ箱に投げ込んだ。空き缶を握り潰すことにも陽雪は喜んで見せたのかもしれないと、竹緒はぼんやりと思った。 そして、目の前のぶっきらぼうな大男は、本気で陽雪を好きだったんだろうな、と思った。 「じゃあな」 傘をささずに出て行く先輩に声をかける。 「試合、頑張ってください」 竹緒は自分自身なんでそんなことを言ったのか分からなかった。バレー部がそれなりに強いことは知っているが、現在の戦績がどうなっているのかは全く知らなかった。でも、なんだかそう言いたくなった。 西は右手を軽く上げるとそのまま去って行った。 その背中をぼんやりと見送っていると、南田と伊刈が駆けつけてきてくれた。
|