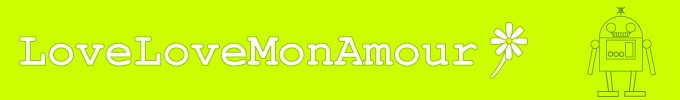
|
キミのフェロモン 後編
土曜日の朝、竹緒は駅前の駐輪場に自転車を止めた。クラスメイトたちと映画を観に行く約束をしていた。アリマニアである竹緒がずっと楽しみにしていたアリを題材にしたドキュメンタリー映画「アント」の公開初日だった。 駅へ歩く途中で、タバコ屋が目に入った。 自然に西とのやり取りが思い出される。 あの後、身長の高い西の姿はたまに見かけたが、わざわざ挨拶を交わしにいったりはしなかった。 陽雪とは挨拶はしても話すことはなかった。 園芸部の定例会議で居眠りをしていたら環に怒られた。 百音は火曜日からずっと学校を休んでいる。 教師がその理由を家庭の事情だとしか説明しなかったため、またしても新たな噂が駆け巡っている。 竹緒に尋ねてくる者もいたが、もちろんなにも知らなかった。 そして不気味なことに、学内一の情報通であり、しかも百音の家の隣に住んでいる陽雪からは一切の情報も噂も出てきておらず、それが更なる噂を呼んでいた。 信憑性のない噂が駆け巡る昨日の午後、雨が止むのを待っていたかのように百音が唐突に姿を現した。 颯爽と長い黒髪をひるがえし、切れ長の瞳と血色のいい唇で笑顔をばらまく。ただそれだけで、質問を浴びせようとしていたクラスメイトたちを黙らせた。やはり持っているものが違うな、と竹緒は彼女が隣の席につくのを感心しながら見ていた。 休み時間に果敢に情報を得ようとする者もいたが、いつもと同じように百音はそれを器用にそれをかわし、クラスでは一番仲が良いように見える伊藤香莉奈でさえも、わずかな情報も引き出せなかった。 竹緒にだけ、秘密の話を教えてくれた。残念ながらそんなシチュエーションも全くなかった。 つかの間の登校は、新たな噂を呼んだだけ。 今日はどんな噂を聞かされるのか? 休日で浮かれる人でいっぱいの電車に揺られながら、竹緒はそんなことを思った。 まさかメンバーの中に、百音当人がいるだなんて思ってもいなかった。 黄色のワンピースに紺色のボレロ、左胸を白のコサージュが飾っている。大きく開いた胸元を緑色のネックレスが彩り、足元には同色のサンダルを履いている。長い黒髪はアップにされ、二つのお団子の中に納まっている。 いつもは美人のイメージが強い百音だが、今日の装いはかわいらしさをアップさせつつ、少し大人のイメージを付け加えている。 駅前広場に立つその姿は周りと比較しても明らかに際立っており、目を引いていた。男性はもちろん、女性でさえも振り返りながらその場を通り過ぎていく。そんな視線に慣れているのであろう百音は普段と変わらない様子だったが、その周囲にいるクラスメイトたちが変になにかを意識して緊張しまくっていた。 おかげで竹緒も、クラスメイトに声をかけるだけだというのに少し緊張してしまった。 百音はちらりと視線を向けてきたが、すぐに会話に戻ってしまった。相手はなぜかクラスの違う草津澪(くさつれい)だった。今回どのようなメンバーに声がかけられたのか竹緒は知らなかったが、少なくとも現在集まっているのは同じクラスの者だけだ。 なぜ草津がここにいるのか? そして、なぜ百音がここにいるのか? 昨日、スケジュールを竹緒に伝えに来た南田は、先に隣の席に座る百音に声をかけた。 「ごめんなさい。やっぱり都合が合わないの」 百音は確かにそう答えていた。 竹緒は南田の説明を聞きながら、百音は来ないのかと少し残念に思った。 なのに、百音はここにいる。 みんなから少し離れた場所で立っていた竹緒の肩が軽く叩かれた。 「なにをぼんやりしているの?」 振り返った竹緒は、副委員長にして学年一の才女である加賀見沙夏(かがみしゃな)の格好に驚いた。 「どうしたの?」 「いや、私服を見たの初めてだったから」 「まさか制服で来ると思っていた?そこまで堅物じゃないわ。もっとも、五十鈴さんが来るんだったら、制服を着てきたほうがインパクトがあったかもしれないけどね」 冗談めかして言う加賀見は、白のシャツにデニムパンツといったシンプルな格好だった。それでもシャツにはポイント的にフリルが入っていたり、唇には少し紅がのっていたりして、学校で見る姿とは明らかに違っていて、新鮮だった。 「加賀見さんも、よく似合ってる」 「ありがとう。それ、五十鈴さんにもちゃんと言ってあげた?」 「別にオレなんかが言う必要はないだろう」 「駄目よ、ちゃんと言ってあげなくっちゃ。彼女は来ない予定だったのに、昨日の晩に南田くんのところに連絡があって、急に参加が決まったのよ。なんでだと思う?」 「……加賀見さんの中では、オレはまだ恋多き男なのかな?」 「そんなことないわ。気にしていたのなら謝る。でも、今も五十鈴さんがこちらを睨んできているって事実はちゃんと気づいてあげて欲しいな」 加賀見にそそのかされて竹緒が視線を動かすと、百音はすぐに視線を動かした。こちらを見ていた気もするが、確証は持てない。 「そんなに自意識過剰にはなれないな」 「でも、新井くんは好きなんでしょ」 「な、なにが」 いきなりの加賀見の言葉に、胸がどきりとした。 「自分の胸に聞いてみて」 そう言われて、竹緒の胸の高まりはさらに速く強くなる。 「ごめんなさい、言い過ぎたわね」 胸の内を見透かされているかのような追及は、その本人によって唐突に幕が下ろされた。加賀見は困った顔を見せる。 「これも意外だって言われるんだけど、私は策を練ったりだとか、様子を見たりだとか、そういうまだるっこしいことが嫌いなの。物事はスムーズにストレートに進めたいの。でも、それは私の勝手。あなたたちにはあなたたちのペースがあるものね。それを守るほうが大事だわ」 さばさばと手をひいてくれるのは助かったが、その物言いはなんだか下に見られているようで、竹緒は少し不満だった。 しかしそれ以外にも引っかかる点があった。節目節目には必ず現れるあれ、あれの感触が微かにする。 「それだけ?」 才女は竹緒の短い質問だけで、その奥の真意を読み取ってみせた。 「澤井さんにもよろしくねって頼まれてるけど、でも、私も興味を持っているのは本当よ」 「……澤井さんの友達だったんだ」 やはりこういう場には陽雪が姿を現す。陽雪の交友関係の広さは知っていたが、加賀見がその中に入っているとは知らなかった。もっとも昨年は同じクラスだったのだから、不思議ではない。 「最近色々とお世話になっているの」 「加賀見さんも噂に興味があったりするんだ」 「それも意外?興味がある事に関する噂は知りたいわ。あら、みんな集まったみたい。行きましょう」 加賀見はぱっと話を打ち切ると南田の元に駆け寄り、一緒に皆の誘導を始めた。二人はプライベートでも、委員長と副委員長の仕事をまっとうする気らしい。 竹緒はぼりぼりと頭をかきながら最後尾についた。 「じゃあ、席はくじ引きで決めるぜ。さくさくさくっと望みの席をひいてくれ」 陽雪が絡んでいると知ると、南田の提案も怪しく聞こえてしまう。しかもくじを回しているのが加賀見となると、疑いの目で見ざるをえない。 先ほどは策を練ったりするのは嫌いだと言っていたが、学内一の才女は嫌いなことにおいても能力を発揮するだろう。竹緒はどのような策が張り巡らされているのかと思いながら、差し出されたくじを引いた。その結果を見て、加賀見はにっこりと笑った。 アリの生態を撮影したドキュメンタリー映画「アント」は地味な映画であり、普通なら変わり者のアリマニアしか観なかっただろうが、最近の大自然ドキュメンタリー映画ブームの影響で、かなりの賑わいを見せていた。 そうなると十人全員がまとまって座れるような席を取ることはできず、いくつかのグループに分かれることになった。 加賀見が細工をしたのかどうか、竹緒はみんなから少し離れた席に決まった。 百音と二人きりでである。 おおっと百音を除く女子陣が一様に手を叩く。全員がグルなのだろうか? 男子陣からは「またお前かよ!」的な視線が遠慮なく竹緒にぶつけられてくる。それを南田がなだめて回っているというのは、奴も加賀見とグルだからなのだろうか? 百音は手に持ったままのくじをじっと見つめている。 彼女は加賀見が不正をしている可能性があることを知らないはずだ。 だとすればなにを考えているのだろうか。 喜んでいるのか? 困っているのか? 百音はくじから目を離して顔を上げると、草津に二言三言声をかけた。いつもはクラスメイトみんなと均等な距離を保とうとしているように見える百音だが、今日は草津とばかり話をしている。誰とでもうまく付き合っているように見える百音だが、出会ってから三週間足らずのクラスメイトよりは、やはり幼馴染の方が気が楽なのだろうか。 見ていると、百音は草津と別れて近づいてきた。 高くきれいに通った鼻をつんと上げ、口元には形の良い笑みを浮かべ、大きな瞳でこちらを見つめてくる。竹緒は久しぶりにそんなものを真正面から見てしまい、頭がくらくらした。 「でも、新井くんは好きなんでしょ」 加賀見の言葉が頭をよぎる。 そうなのか? これが好きってことなのか? 「行きましょうか」 百音が笑う。 今から大好きなアリの映画を観るんだってことを一発で頭の中から吹き飛ばしてしまう笑顔だった。 ぎこちなく歩き始めてから、クラスメイト達が売店に並んでいるのに気がついた。 「五十鈴さんは何か飲む?」 「そうね。アイスティーにしようかな」 「分かった。持って行くから、先に席に行ってて」 「でも……」 「いいから」 竹緒が強く言うと、百音はしぶしぶといった表情で背中を見せた。 百音は明らかに不機嫌だったが、動転している竹緒には、それに気づくほどの余裕はなかった。 ポップコーンとアイスティーを持って席についてようやく、失敗に気がついた。百音の笑顔はすっかり消えてしまっていた。 アイスティーを手渡しても、短く礼を返されただけで、気まずい空気が漂う。 開演までにはまだ少し時間がある。それをこのまま無言で待ってはいけないことぐらい、竹緒にも分かっていた。 「久しぶりだな」 「昨日会ったじゃない」 予想通り、百音のご機嫌は斜めに傾いていた。 「でも、昨日は話す時間がなかったから」 「そう?隣の席なんだから、その気があるなら話ぐらいできるでしょ。南田くんと話をしている時間があるなら、私に話しかければいいでしょ」 「あれは今日のスケジュールを伝えに来てくれただけだ。でもあの時、五十鈴さんは用事があるから来れないって言ってなかったっけ」 「あったけど、都合をつけたの。私が来たらいけないことでもあった?」 「そんなことない。嬉しい」 竹緒自身がびっくりするぐらい、本音がぽろりとこぼれ出た。 今日はずっと前から楽しみにしていた映画の公開日だ。でもその映画を観られる嬉しさよりも、百音が待ち合わせ場所にいるのを見つけたときのほうが、百音と隣の席になれたことのほうが、よっぽど嬉しかった。 その本音がぽろりとこぼれ出た。百音の顔がさっと赤くなる。加賀見の言葉がしつこくリフレインしてくる。 「でも、新井くんは好きなんでしょ」 タイミングよく開演のブザーが鳴った。 百音は気まずそうに口をつぐみ、スクリーンへ視線を向ける。 照明が徐々に落とされ、場内のざわめきが小さくなっていく。スクリーンでは予告が上映され始めた。 「……」 百音がなにかをつぶやいたが、予告映画の爆発音と重なってしまって内容が聞こえなかった。 「なに?」 「なんでもない」 問いかけたが答えを教えてはくれなかった。 でもその声に先ほどまでの硬さは見られなかった。とても優しくて、気持ちのいい声だった。 横顔を見つめる。 「なによ」 百音は顔をスクリーンに向けたまま、目だけをこちらに向ける。 「なんでもない」 竹緒は答えて前を向く。予告が終わり、いよいよ待ちに待った映画が始まったのに、隣がやけに気になった。
|