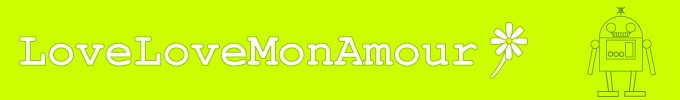
|
パワーポイント
まずは目を疑った。 「見間違いに決まっている」そう思った。 目を閉じ、その上を手でごしごしとこすってから、開く。変わっていない。 バシバシと瞬きをしても同じだった。 見間違いじゃない。 耳があった。 オレ、里崎祥平は中規模商社の新入社員。三ヶ月の研修を終え、先輩にくっついて回るだけの日々が四ヶ月。雑用ばかりで大した仕事をしてこなかった七ヶ月間だった。 しかし、大したことのない日々は昨日終わった。今日は部長と羽生先輩の三人で、主要客先の一つである輝星コーポレーションを訪問していた。これまでにも何度か訪問していたが、今日は契約書を交わす場に始めて同席させてもらうのだ。記念すべき日だ。 しかも課長ではなく、部長がわざわざ出席するほどの、それなりに大きな案件だ。 同席するだけでも緊張ものだが、更にプレゼンに使う資料の作成を始めて任された。不安もあったが、おおいに奮起し、連日残業をして作り上げた。 その成果がこれから披露される……はずだった。 「プレゼン資料良かったぞ」帰りの居酒屋で祝杯をあげながら、部長に褒められる、先走ってそんなシーンを想像していた。 しかしそれらの思いは全部吹っ飛んでしまった。 プレゼンの成否なんかどうでもよくなってしまった。 あの耳のせいだ。 アポイントの時間の五分前に到着したオレ達が応接室に通されるとすぐに、相手先の人間が姿を見せた。先頭の男女二人はいつも会っている担当者だ。続く中年の男が二人の上司であろうことは容易に予測できた。 しかし、続いて入ってきた見覚えのない若い女の正体は分からなかった。 まだ少女とも呼べるような幼い顔立ちをしていてかなりかわいい。最近では珍しい黒のストレートヘアが良く似合っている。 しかし耳がある。 耳と言っても、黒髪の間からチラチラと姿を見せる耳、もちろんそんなものは問題じゃない。 問題になるのは頭の上についている耳だ。 頭の上に人間の耳が乗っかっていたらちょとしたホラーだが、猫の耳がついていたらなんだ?ファンタジーか?萌えか? 触ってみないことには分からないが本物の猫の耳に見える。 猫の耳が頭の上にくっついている。 ネコミミだ。 目を疑い、口をポカンと開けるぐらい許されてしかるべきだ。むしろ、「なんじゃそりゃ」と叫ばなかったことを褒められるべきだ。 オタクの世界では、猫の耳をつけた少女を示す「ネコミミ」というジャンルがあり、それらに扮する為のグッズが発売されていることはテレビなどからの情報で知っている。オタクだけではなく、一般人の間でもそれなりにはやっているらしい。 昼休みにその手のグッズで遊んでいて外すのを忘れたのかとも思おうとした。しかし、相手先の他の三人も気づいていないはずはないと思うが、注意をする素振りを見せない。この会社では当たり前のことなのだろうか? 目の錯覚かとも思ったが、横を見れば部長と羽生先輩もこそこそと話をしている。 パニックは収まらぬままに、担当者に紹介されて中年の男と名刺を交換した。部長クラスだと思っていたが、関課長と記されていた。 部長と羽生先輩は会ったことがあるらしく、談笑を交わしている。 続いて問題のネコミミ女。 「営業三課の若村みそのです。よろしくお願いいたします」 ぺこりと頭を下げられると、頭上のネコミミが目の前に迫る。 いけないと分かりつつも凝視してしまい、頭を下げるのを忘れてしまった。 そんな動揺を見通しているかのようにネコミミがひょこっと動iいた。その動きに促されたかのように慌てて頭を下げた。 その後のことはよく覚えていない。 力作の資料を使って羽生先輩が説明をしたはずだが、全く記憶に残っていない。 ぼーっとネコミミを見ている間に、契約がまとまるはずだった席の雲行きはどんどんと怪しくなっていき、いつもなら普段のひょうひょうとした姿からは信じられないような粘りを見せるはずの羽生先輩もその流れにあっさりと巻き込まれてしまい、だからといって部長が踏ん張りを見せることもなく、宿題をもらってその場を退散することとなった。 惨敗だ。 もっとも、一言もしゃべらなかったオレに、偉そうなことを言う資格はない。 そしてオレと同じく、ネコミミ女も一度も口を開かなかった。 話が分かっているのかいないのか、たまに資料に目を通し、後はじっとこちら側三人の顔を見ていただけだった。 最後の最後まで、誰も彼女がネコミミをつけていることについて触れなかった。 「いやいや参った」 輝星コーポレーションを出てタクシーに乗り込むと、部長は珍しく大きな声を上げて頭を抱えた。 「全くですよぉ。……条件の見直しですかねぇ」 「見直さざるをえんだろう。それとも君にはなにか秘策があるのか?」 「ドレインモーターの件ではお世話になりましたし、今回はこちらが折れないと仕方がないでしょうねぇ」 「それがあったか。相変わらず食えない奴だ。仕方がない、社内の調整は任せる」 「大滝部長には?」 「それは私のほうから話をしておく」 「あの…」 助手席に座っていたオレは、我慢できずに振り返って二人の会話に割り込んだ。 「なんだね?」 後部座席の二人は、新人は黙っていろという顔をしていたが構わずに訊いた。 「あの人はなんなんですか?」 「あの人?関課長か?」 「違います!若村みそのです!あのネコミミの!」 「彼女がどうかしたのかね?」 「なんだ、好みだったのかぁ」 「違います。ネコミミですよ、ネコミミ。なんで誰も何も言わないんですか?」 「なにを言う必要があるんだぁ?」 ネコミミはオレの目の錯覚ではなかったようだが、羽生先輩は本当に理由が分かりかねるという表情を見せている。 部長と先輩は彼女と名刺交換をしていなかった。ということは以前にも会ったことがあるのだ。ネコミミの秘密も知っているのだ! 「なんでって、ネコミミですよ。おかしいと思わないんですか」 「取引の間中ぼーっとしていると思ったらそんなことを考えていたのかぁ。ちゃんと仕事に集中しろよ」 「すいません、でもっ」 「ネコミミがついていたから何だって言うんだぁ?そんなのはただの身体的な特徴であって大したことじゃないだろ。世の中には色んな人がいるんだ、ネコミミがついている人がいたっておかしくないだろぉ。それが今日のビジネスとなんの関係がある。今問題になっているのは若村さんの頭にネコミミがついていることではなくて、相手さんが急に契約の内容を変更してきて、当初より三割も予算をカットしてきたってことだ。違うかぁ?」 「そうですけど……」 事実を積み重ねられても、納得できないものは納得できない。 「まぁだ不満があるのか?」 そんな気分を見抜かれたから、逆に開き直った。 「彼女はなんなんですか?」 「人間だろぉ」 「人間なんですか?」 「人間だろ。ネコミミのついた人間。じゃなかったらなんなんだよ」 「それは……分かりませんけど……」 気の利いた答えを思いつけずに口ごもり、前を向き直った。 これはオレの社会人としての経験が浅いゆえの疑問なのだろうか?これから経験を積み重ねていけば、ネコミミぐらい当たり前のものとしてあしらえるようになるのだろうか? ダッシュボードの上の運転手の写真が仏像面でオレを見ている。横を見ると同じような仏像面が運転していた。 「そぉだ部長。今回の件を里崎に任せませんかぁ?」 羽生先輩が急にとんでもない提案を始め、そのまま部長の許可を待たずに勝手に話を進めていく。 「里崎、今回の件はお前に任せるからぁ価格交渉して来い。元の値段に戻せとは言わないけどぉ、コストカットをできる限り押さえてこい。向こうは若村さんが担当になったから、いくらでも会えるぞぉ」 「お、オレが担当になるんですか?」 突然の展開に声が上擦る。うちの会社では、新入社員が担当を持たせてもらった話を聞いたことがない。 「二割減に抑えて来い」 明確な目標付きで部長からの許可もあっさりと出た。 慌てて振り返ると、部長は大きく頷き、羽生先輩は目を細めた。 「良かったねぇ、兄ちゃん」 仏像が隣の席でがははははと笑った。 「なにこれ?」 先ほどまで明るかった千晶の表情は包みを解くと一変した。 一度オレの顔を見てからもう一度包みの中を確認するが、そんなことをしても中身が変わるわけがない。千晶はもう一度不機嫌な表情でオレの顔を見た。 「え~と、ネコミミ?」 半笑いで答える 「疑問形?」 「ネコミミです」 「なんで私はネコミミを渡されているの?」 「え~と、それには長い理由がありまして……」 「コスプレしたいなら早く言ってよ。受付で服を借りてきたんだから。今からわざわざ借りに行くのって恥ずかしいなぁ」 千晶は急にウキウキとホテルの案内書をめくり始めた。 長い理由は聞く気ないのかよ! ほっとしながらも聞いてもらえなくて少し悔しいので、代わりに皆さんに聞いていただこう。 輝星コーポレーションでの商談が終わった後、羽生先輩はタクシーを途中で降りてどこかに出かけてしまい、部長と二人で会社に戻った。 部長の表情から商談がうまくいかなかったのが分かったのだろう、部内の人間は誰も結果を訊いてこなかった。 タクシーの中では始めて担当を任された喜びを誰かに伝えたい気持ちでいっぱいだったオレも、浮わついた状態から冷めつつあった。それよりもプレッシャーがむくむくと大きくなって、のしかかり始めていた。 冷静に考えてみれば、羽生先輩も部長も大した抵抗もできずにすごすごと帰ってきてしまったほどの案件なのだ。簡単であるはずがない。 そんな困難な案件を解決すれば評価も急上昇するだろうが、そこまでポジティブシンキングはできない。 すぐには手をつけることができず、留守中にたまっていた客先からの電話やメール、雑用に対応している間に定時をいつの間にか回っていた。 他にやる仕事もなくなり、覚悟を決めて今日使われたプレゼン資料ファイルの上にカーソルを持っていく。しかし、なかなか開くことができなかった。マウスをクリックしない程度に軽く、何度も叩く。 「里崎」 突然背後から部長の声がして、肩をもまれた。 「今日はもう帰っていいぞ」 「……ありがとうございます」 部長の言葉に甘えてすぐに会社を出て、電話をかけた。その先は大学時代の知り合いだが、あまり親しくはなかったので、携帯に番号を登録してはあるもののかけるのは初めてだった。 案の定、相手も突然の電話に怪訝な声で応対してきた。 しかしオレの用件を聞くとすぐに態度が豹変し、ていねいに質問に答えてくれた。聞いていないことまで事細かに説明してくれた後、とっておきの情報とやらまで教えてくれた。 とっておきの店はオレの予想していたのとは全く違う駅の近くにあったが、好都合なことに彼女である千晶の勤め先の近くだった。 馴染みがない関連の店が雑多に詰め込まれたビルの一角にその店はあった。そんなものが一般に販売されていると考えたこともないような品がところ狭しと置かれている。 とっておきの物は、ショーケースに入れられて鎮座していたのですぐに分かった。素人目にもとっておきであることが一目で分かる。 値段も想像以上であったが、思い切って購入した。 合流した千晶と軽く食事を済ませると、明日も仕事があるからと軽く抵抗するのを説き伏せてホテルへ連れて行った。 シャワーから出てきた千晶に包みを差し出すと、最初は「なになに?」と嬉しげな表情を見せていたが、その中身を見ると表情が一変した。 「なにこれ?」 「え~と、ネコミミ?」 千晶がコスプレプレイも満更ではないと分かったのは大きな収穫であるが、今日の目的はそこではない。時間もあまりないことだし、さっさと目的を済ませなければならない。 「コスプレは今度借りるから、とりあえずこれを付けて」 「ネコミミ?」 「ネコミミ」 「いいけど……。でも、湯上りバスタオルにネコミミって変じゃない?」 千晶は包みからネコミミを取り出す。ぶつぶつ言いながらも、表情はほころんでいる。 ネコミミには大きく分けて二種類あるらしい。 カチューシャに耳がついているものと、髪留めに耳がついているものだ。 オレが買ってきたのは髪留めタイプのものだ。ディズニーランドで同じようなタイプを見たことがあるが、あんなちゃちいものではない。遠目には、猫の耳を切り取ってきたのではないかと思えるほどリアルだ。 店員の話では、この手のものはリアルさを追求すると重くなる傾向にあるらしい。特に髪留めタイプは重くなると非常に不安定になり、頭の上できちんと固定されずにぐらぐらしてしまう。 この店の製品はそこに工夫を凝らし、リアルでありながら軽量、快適な着脱制を達成したとっておきの一品らしい。 よく分からないが。 「どう、似合う?」 ネコミミが似合うというのもどうなのかと思う。 もっとも似合う似合わない以前に、目の前で装着している風景はひどく興冷めだったし、千晶の髪の色に合わせて茶系のネコミミを買ってきたのだが、微妙に色が合っていないのが物悲しかった。 なにより、若村みそのの方が圧倒的に似合っていた。本物っぽいとかそんな次元ではなく、圧倒的にネコミミが似合っていた。 ネコミミとしての格は違う。 しかし、そんな本当のことを言えるわけがない。 「お、可愛い可愛い」 「本当かにゃーん」 突風が吹きぬけた。 ひたすら寒かった。 付けさせておいてなんだが、自分にはそちら方面の趣味がないことがはっきり分かった。 「にゃーん、にゃーん、にゃーん」 しかしオレのひきつった顔に気がつかない千晶は、楽しそうに部屋の中を徘徊し始めた。 「にゃーん、にゃーん、にゃーん」 裸にバスタオルを巻きつけ、ネコミミをつけた女が甘えた声を出しながら部屋を歩き回っている。 オレにはその趣味はないけれどもなんだかむらむらしてきた。 「にゃーん、にゃーん」 襲いかかった。 「がおー」 「にゃぁん」
|