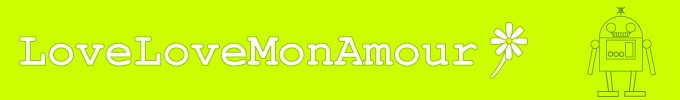
|
パステルなライオン
「ごめんねぇ」 聞き慣れたフレーズをいつものかわいらしい旋律にのせて、彼女はゆっくりと僕の顔を覗き込んだ。 僕の視界の中で大きな瞳が輝き、黒い髪がさらさらと流れる。そのさまは何度見ても美しいと思い、あまつさえ感動までしてしまうものだから、僕は彼女を怒れなくなってしまい、怒られない彼女は待ち合わせのたびに同じフレーズを繰り返す。 「雨、まだ止んでないの?」 彼女が手にする傘の先に小さな水溜まりができ始めている。 天気予報では昼過ぎには回復すると言っていたが、僕が仕事を終えて会社を出た時にもまだ降り止む気配は見せていなかったし、この派手なショッピングモールは色彩り彩りの傘に囲まれていた。 待ち合わせにしていた広間からは外の様子は見えない。 「うん…」 文庫本を閉じる僕の前で、彼女は肩の水滴を払っている。もう一度傘に目を移してから口を開いた。 「傘、買ったんだ。かわいいね」 「そうでしょう」 とてもさりげない振りをしながら、でもとても嬉しそうに彼女は答える。喜びはとても隠し通すことができずに、はにかんだ笑みとなって零れ落ちる。 彼女の趣味に合わせたパステルカラーのブルーの傘。顔のパーツの一つ一つが大作りな彼女には原色系の服の方が似合うと僕は思っているのだが、本人はパステルカラーが好きだった。派手目な顔を少しでも和らげようとしているかのように淡い色彩を好んだ。一緒に買い物に行った時などに原色系のものをそれとなく勧めてみたりはしているが、きちんと試着した後に数多の候補から真っ先に落とされるのが常だった。 プレゼントした服が着てもらえないなんて悲しすぎるのでそんなことはしない。それに僕の趣味に合わない服を着ているからといって彼女の魅力が損なわれるわけではない。 「どこに行こうか?」 「おまかせ」と答えが返ってくるのが分かっていても一応尋ねる。もしかしたら雑誌の1ページに花丸を付けて来たかもしれない。今までそんなことは一度もなかったけれど。もしかしたら雑誌は花丸だらけで、でもどれか一つに絞り込むのにはいつも失敗していて、「おまかせ」と言っているだけかもしれないけれど、とりあえず今まで彼女は自分の積極的な希望を述べたことはなかったし、僕の提案に意を唱えたこともなかった。 だから今日もきっとそうだと思っていた。 部屋で一生懸命に雑誌を花丸で埋め尽くしている彼女を想像して少し嬉しくなったりしていたのだ。 「ごめんねぇ。今日はサークルの人と食べてきてしまったの」 「はぇえ?」 思わず間抜けな声を出してしまった。 彼女の前ではそんな声を出さないように必死に努力してきたのに、全く予想していなかった一言にその努力はあっさりと無に帰された。 しまった!なんて僕の内なる叫びに全く気づかず、もっとも気づかれてはダメなのだけど、彼女は続ける。 「今日は空き教室がなくって、ファミレスで会議をすることになったの。それで、会議が終わった後にそのまま食事をしていこうってことになっちゃって。わたしは帰ろうとしたんだよ。久し振りに待ち合わせに遅れないですむって心の中でガッツポーズしてたんだから。なのにアケミンとさーこちゃんが両脇からこうがっちとしてぎゅーっと私を挟み込んじゃって、出られなくなったの。出して出してーって言っているのに全然出してくれなくて、それで…そのままご飯を食べてきてしまいました」 最初は一生懸命言い訳をしようとしていたみたいなのに、最後は「おわり、まる」みたいな、昔話があるべく終着点に辿り着いたかのような感じで終わってしまった。 彼女は「ちゃんちゃん」と音が聞こえてきそうなごまかし笑いを浮かべている。いや、ごまかし笑いなんかではない。彼女の中ではもう謝罪の気持ちは終わっていて、僕の許しの言葉を待っているのだ。 しかしそんな笑顔であっさりと許せるわけがない。これで許してしまってはポストイットを貼り付けられまくり、極太のマジックで丸を書かれた僕の部屋に転がっている雑誌に申し訳が立たない。この際、下見までした僕の努力は置いておいても良い。 それに久し振りに遅刻しないだなんて。 今まで自分が時間通りに来たことがあったと本気で思っているのだろうか? 今日で七回目のデートだけれど、彼女が時間通りに来たことは一度もない。一番酷かったのはなんとかいう外国のバンドの日本公演のときだった。彼女はそのバンドの熱狂的なファンであることを何度も熱く熱く語ってくれ、日本公演に対する意気込み、そしてそのチケットを入手することがいかに困難なのかを教えてくれた。説明している最中に泣き出してしまうぐらいに熱心にだ。 そのチケットを入手させられるのではないかとヒヤヒヤしたが、彼女は自慢気に2枚のチケットを僕の顔の前でひらひらとさせ、当日は念を持って開演2時間前に集合、その集合時間にも絶対に遅れないようにと申し付けた。 僕はなんの興味もないバンドのためにその日は午後から半休を取った。 結論から言えば、彼女が来たのはアンコールが始まろうとしていたときだった。場内に辿りついたのはちょうどアンコールが終わったところだった。 彼女のあまりの落ち込みように僕の不満を飲み込まざるを得なかったことを不意に思い出す。 「でも、ヒロ君はご飯を食べずに待っていてくれたんでしょ。だから、私は食べないけど、ご飯を食べに行こうよ。今日はお詫びに私が奢ります。ヒロ君の好きなところで良いから。ね。お腹空いているんでしょ。」 その時の僕はちょっとぷっつんといってしまっていた。 色々と積み重なってきたことが、一気に崩れ落ちてきて、どうしようだとか、どうしてくれようだとかそんなことが綯い交ぜになって、ぷっつんと切れてしまった。 ポストイットだらけで極太マジックで書き込みがなされた雑誌の姿がフラッシュバックされる。 「どこでもいいの?」 それでも、怒った声は出さなかったと思う。 「いいよ」 きちんといつもどおりに彼女をエスコートしていたとは思う。でも、いつもなら細心の注意を払って、後で一人反省会ができるぐらいに詳細に覚えているのだが、このときに限ってはどうやってそこに辿りついたのかよく分からなかった。 ぷっつんしていたとはいえ、よりにもよってこの店を選んだ自分をどうかとも思う。 「どうしたの?」 店の前でぼんやりと看板を見上げている僕を彼女が気遣う。 「なんでもない」答えながら、ショッピングモールを出て、雨の降る道を駅の方向に3分ほど戻ったところにあるオレンジ色の看板の店に僕たちは入った。独特の匂いが鼻をつく。狭い店内の客の姿はまばらだった。 「いらっしゃいませ」若い男の店員が大きな声を張り上げ、カウンターに座った僕と彼女の前に湯飲みをどんと置いた。 「特盛つゆダク卵と味噌汁」 一気にメニューを告げる。店員は店の奥に向かってメニューを繰り返し、彼女の方を向く。 「ごめんなさい、私は良いです」 会話をする間もなく、注文した品が次々と運ばれてくる。 牛丼のてっぺんに小さな穴を開け、適当にかき混ぜた卵を流し込む。おしんこを取り出し、その上にかける。紅生姜もたっぷり取ってその上に乗せ、最後に七味唐辛子を思い切り振りかける。それらをぐちゃぐちゃにかき混ぜ、ようやく儀式は完了した。 迷いのない僕の流れるような動きをじっと見ている彼女を気にせず、いや本当は気になるけどやけくそ気味に目の前のものをかき込んだ。迷いがないのは当たり前だ。特盛を並に変えれば、それは僕の昼食の定番メニューなのだから。 黙々とかき込む僕の姿を彼女はじっと見つめている。 もしかしたら呆れられたかもしれない。 今頃になってそんな不安が浮かび上がる。 いきなりこんな店につれてくるのはあまりにもショックが大きすぎたかもしれない。 まさか今どき牛丼を食べたことがないなんてことはないだろうと考えていたが、彼女ならありえるかもしれない。 焼肉やしゃぶしゃぶもあまり好きではないし、いつも魚や鳥系のメニューを頼んでいる。 パステルカラーで自分を染め上げる彼女に肉食のイメージはないし、牛丼なんて全く似合わない。 やりすぎたかもしれない。その言葉が頭をよぎったのに合わせるかのように彼女がため息をつき、僕をドキッとさせる。 「ヒロ君が食べているのを見てたらわたしも食べたくなっちゃった。すいませーん」 彼女は店員を呼ぶと、 「並ねぎダクギョク」 と淀みなく注文した。 そして顔の前で指を組み、今までどんな店に連れて行っても見ることのできなかった、待ち焦がれているような表情を見せる。 僕はそんな彼女をぽかーんと眺める。 箸は止まってしまっていた。 そんな顔を見せてはダメだと心の奥底で警鐘が鳴っていたけれども、僕はぽかーんと眺め続けた。 「どうした、の?」 彼女が笑う。 その大きな口は、牛丼を食べるのにとても似合うだろう、と思った。
|