中教審・教育課程部会傍聴記
知里 保 (ジャーナリスト)
400時間を越える改訂審議だったと銭谷眞美文部科学事務次官はいいました。2007年11月7日の中教審・教育課程部会で、「審議のまとめ」を決定した直後のあいさつのなかです。教育課程部会とそのもとに置く小中高3つの校種別部会、教科・領域別の16の専門部会に所属する計400人以上の委員たち。その意見は受けとめられたのでしょうか。
委員は文科省が任命します。その発言は当然、進行する教育施策を是とする立場が基調です。しかし政府・文科省への正当な批判もかいま見ることができます。
教育3法成立直後、その内容の説明をうけた討論での発言は1人で終わりました。作家の委員が学校図書館の充実を求めただけでした。しかし、別な日の会議で、副校長、主幹を新たに置いたがために、校内の情報交換がかえって必要になるという発言がありました。「学校の教育力は教員の連合体にある。全体でどうすすめるかを考えあう時間が必要だ」という発言もありました。それでも、学校の教育力向上には教師の同僚性の発揮が大切だという観点は、改訂方針案には盛り込まれずにいます。
全国いっせい学力テストについても、結果報告を受けた審議のさいではなく、後日の審議で、今後「悉皆(全員)調査は数年おきで、その間は抽出調査でいいのではないか。学校現場は、都道府県や市町村独自の学力調査であけくれ、その分析まで手がまわらない」と、既定方針の再考を求める発言がありました。
「抵抗」発言が改訂方針に反映されたものもあります。たとえば授業時数増です。「時間数を増やせば、子どもに学力がほんとうにつくのか。フィンランドはちがうではないか」「中学校の授業時数は現行どおりやってほしい。部活動の時間がなくなるのは中学校教育としてはよくない」などの発言が繰り返しありました。
このため、「年間の総授業時数」の項なのに、定数改善要求の叙述が唐突に出てくるという改訂方針案になりました。中学の項で「授業時数を増加するに当たっては、小学校と同様、教職員定数の改善をはじめ指導体制の整備を進める必要がある」とあります。
内容のうえで改訂の柱のひとつである道徳教育の充実について、方針案は、教育再生会議方針である、道徳の時間の教科「徳育」化を、その賛否両論を併記し、引き続きの課題にして、事実上の見送りにしました。
その一方で、法の遵守、規範意識の重視などを新たに強調しています。その危険性を数人の委員が指摘しました。
「規範意識をある方向で強調しすぎると、いかに守らせるかになり、よくない。(法や決まりは)自分が生かされることになることを理解させる。ルールの形成に参画し、責任をもつことが重要だ」「法や決まりは権利を守るために定められなければならないことを教えなければならない」「規範意識は政治用語になりつつある。共生社会へ市民として参加しうる、態度、生き様こそ求められる。徳目主義ではだめだ」。これらの意見に逆らい、主権者養成の観点を周到に排除しているのが改訂案です。
評価をめぐっては疑問が噴出しました。
文科省は前回の学習指導要領の改訂のさい、それとあわせて、指導要録の様式を改め評価規準の資料をつくりました。国立教育政策研究所(国研)がきわめて細かな評価基準を示しました。その結果なにがおきたか。「1単位時間の授業において評価の4観点(関心・意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識・理解)のすべてを評価しようとしたり、授業冒頭に『進んで取り組んでいるかどうか』をチェックし、チェック終了後授業に入ったりするなど評価のための評価になっている」、「評価活動が複雑になり余裕がなくなった」と小学校66%、中学校78%の教師が捉えている―。そのように改訂方針案はいいます。
審議での発言は―。「国研の評価規準は膨大だ。ある程度1時間ごとの基準をつくらざるをえない。時間がかかる。責められる」「国研の規準に関係する現場の事務量、負担は現実には相当なものだ」。文科省がそういう状況をつくりだしておきながら、人ごとのように現場のせいにするのはおかしいというわけです。
ではどうするか。関係専門部会の委員から示された提案は、思考力、判断力、表現力などを「活用力」としてひとくくりにして、それを、知識・技能の習得、意欲・態度、とともに、指導要録の評価の3観点の1つにして、さらにそれを到達目標化することです。また、単元末直前に、単元で学んだことの理解、定着を確かめるテスト(形成的テスト)をして、その結果から、補充指導、発展学習をすることです。「指導と評価の一体化」をして、学力を保障する「指導の結果責任」を徹底すると強調しました。
これを疑問視する発言が続きました。
「到達目標を、思考力、判断力、表現力で示すことができるか」「保障をどう具体化するか。それを示さないと、到達目標を明確化すると現場は困る。対応策をきちんと示さないといけない」「評価がシンプルなものになるのか。授業者にやりやすいものになるか。現場の大変さは伝わってきている」「単元が終わる前にテストをするのでは、単元そのものの学習時間が圧迫される」「指導と評価の一体化は、時間の確保ができない。補充、発展をいつ、だれがやるのか。実際、教えようがない。条件整備はぜひやらないといけない」
この結果、改訂方針案は「簡素で効率的な学習評価」を検討していくと書かざるをえませんでした。しかし「指導と評価の一体化により」「指導の結果責任も問われていることを前提に」すると明示しています。審議が今後どう展開していくか注目しなければならいでしょう。
委員たちがどのテーマの審議のなかでも必ず言及したことがあります。条件整備の必要です。そのため「教師が子どもたちと向き合う時間の確保などの教育条件の整備等」がひとつの章になるという、異例の構成になりました。その章の筆頭項目は、政府の教職員削減方針に反する、教職員定数の改善です。
しかし、少人数学級の実現だけは、繰り返しの発言にもかかわらず、何度会議を開いても案に出てきません。事務局(文科省)が書かないのです。でもあきらめず発言は続きます。「審議のまとめ」が決定されたあとも続きました。
「1学級当たりの児童生徒数の改善をしないと問題の解決にならない。教員の量を増やし余裕を。そうすれば質も上がる」(スポーツジャーナリストの増田明美氏)
11月27、29の両日、教育課程部会が開いた、「審議のまとめ」についての42団体からのヒアリング(意見聴取)の場でも、教育関係団体はすべて、教職員定数の改善を求めました。
「加配措置でなく定数法改正を」(全国都道府県教育長協議会)、「授業時数増で教員はいっそう多忙化する。定数増のための予算増が最低限必要だ」(日本PTA全国協議会)などです。
ヒアリングでは、全国学力テスト、授業時数増、「徳育」化などに疑問が出ました。
「(全国学力テストは)ほんとうに悉皆でいいのか。内容の検討も今後必要だ」「(結果を)情報公開で示さざるをえないことから、格差が見えてしまい、安易な学力向上策がとられてしまう」(全国連合小学校長会)、「たんに授業時数を増やしても、子どもに新たな負担を強いることになる」(日本教育大学協会)、「道徳の教科化は反対。心の教育は教師が一方的に教え込むことではない」(日本PTA全国協議会)。
改訂方針案は、現場の実態や教育の論理を反映する意見の多くを排して成立しました。
その結果は学習指導要領の性格を大きく変化させます。教育内容の基準を示すにとどまらず、授業のあり方や学び方をこまかく指示し、態度や思考力をもふくむ目標の達成を子どもと教師に自己責任で強いるシステムをつくり、格差を拡大するしくみを内包する、という構造の変化です。これらの問題の検討を急ぎたいものです。
(ちり たもつ)
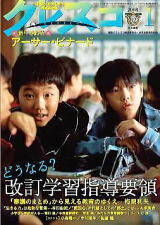
ページの先頭へ
トップページへ
|
|