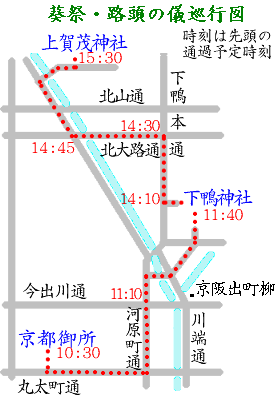|
祇園祭、時代祭は町衆参加の、町の
人が主体の祭りと云えますが、葵祭は
官の祭であったことが色濃く残る祭です。
今では路頭の儀、社頭の儀が一般に
知られており、路頭の儀は奉幣使参内の
行列のことで、勅使、検非違使、内蔵使、
山城使、牛車、風流傘、斎王代など、
平安朝貴族の装束を身にまとい、京都御所
から下鴨神社を経て、上賀茂神社へと延々
8Kmを行列します。一般にはこの行列の
ことを葵祭と呼ぶことが多いです。
|
 |
社頭の儀は、両社社頭において行わ
れるもので、神職による神前の儀を
はじめ、御幣物の奉奠(ほうてん)、
御祭(ごさい)文の奉上や、二頭の馬が
舞殿を三度回る牽馬(ひきうま)や古代の
歌舞の舞人東遊(まいびとあずまあそび)
などが厳かに行われます。
この社頭の儀は、一般には見学できま
せんが、事前に申し込み許可を得れば、
限られた人数ですが、見ることが出来ます。
余裕があれば当日も受付があるようです。
|
 |
・5月3日、流鏑馬神事、下鴨神社
・5月4日、斎王代・女人列御禊神事
・5月5日、歩射神事、下鴨神社
・5月5日、賀茂競馬、上賀茂神社
・5月12日、御蔭祭、御蔭神社、下鴨神社
御阿礼神事、上賀茂神社
これらの祭事、行事も葵祭の前儀式として
執り行われるもので、葵祭の清めの意味が
あります。
新緑も綺麗な五月の一日、葵祭見物は
いかが〜。牛車のギッシ、ギッシと云う
独特の音と供に繰り広げられる王朝絵巻が
葵祭です。
順路は長いです、加茂川堤が絵になるの
だけれど、人出も多くなります。
|