/// 鳥羽伏見の戦い /// (03/09/13)
慶応四年(1868)、正月もまだ3日のこと。 時刻は午後4時過ぎ頃のこと、小枝橋付近での出来事。 幕府最後の15代将軍、徳川慶喜(よしのぶ)上洛の先発隊を 率いる大目付滝川具拳(ともあき)と、薩摩藩指揮官、 椎原小弥太の押し問答から事は始まります。 「勅命で通る」と言い放つ滝川、「そんなことは聞いていない、 通すわけにはいかぬ」と制する椎原。季節は正月のこと、 そうこうする内に日は暮れかかります。 ついに滝川は「もはやこれまで、押して罷り通る」と言い 放って前進を始めます。 その時、対する薩摩軍の大砲が火を放ちます。これを聞いた 御香宮に屯所を構えていた薩長軍も、わずかの距離の伏見 奉行所に陣を置いていた土方歳三らの新撰組、林権助らの 会津藩士、そして久保田備中守らの伝習隊などに対して砲撃を 開始します。 ここにいわゆる鳥羽伏見の戦いが切って落とされます。 翌年の函館五稜郭の戦いに至るまで一年半にわたる内戦、 戊辰戦争へと歴史はつながります。 その背景を知らないと、鳥羽伏見の戦いの意味合いも判らなく なるので、ちょっと簡単に歴史のおさらいです。その背景には 三百年を誇った徳川幕府と新政府を目指す薩長軍を主とする勢力、 そして朝廷との微妙な三角関係があります。 慶応四年と書きましたが、明治改元の布告が九月八日に出され、 この年は明治元年であったりもします。時に明治元年を10月23日 と記した資料なんかもありますが、これは新暦で表した日付です。 新暦が正式に使われるのは明治6年1月1日からなので、 この当たりは注意が必要です。 |

|
話は逸れましたが、慶応三年には慶喜が 「王政復古の大号令」を発し大政奉還を 成します。これは飢饉などにより幕藩体制 が行き詰まりを見せる中で、幕府の武力 討伐に傾きつつあった朝廷との融和を図り、 朝廷との連合政権、公武合体を目指した 苦肉の策だったようです。 しかし、西郷隆盛らが訴えたように「二百 年余にわたって、太平の旧習に慣れた 人心の一新をはかるには、死中に活をもと めることこそ大事である。」 この言葉が象徴するように薩摩藩、長州藩 が目指す倒幕の歴史の大きな流れは、 もはや誰にも止めることは出来なかったの でしょう。 朝廷の権力はあくまで形式的で統治力、 政治力があった訳でもなく、単に祭り上げ られてきただけの朝廷なので、突然に政権 を返上されたからと云って、迫りくる混乱、 窮状を打開できる筈もなく、単なる日和見 の体質でしかなかった。 |

|
さらりと書いていますが、この頃の歴史は 複雑怪奇、権謀術数が渦巻く、一見、一読 しただけでは表も裏も判らぬ出来事が頻発、 京都においても日々に怪事件、暗殺、決闘 が繰り返されていたのでした。そこには 新撰組、坂本龍馬、中岡慎太郎、桂小五郎、 佐久間象山、高杉晋作、大久保利通など、 あげればきりがないほどの、知られる 人物が登場します。 江戸では倒幕の口実作りのために幕府側 への挑発行為が頻発し、巷では「ええじゃ ないか」の乱舞騒動も起こり、世の中は 混乱の極みに達します。そんな混沌とした 世情の中で、慶喜はついに慶応四年1月 1日、開戦を決意し幕府軍は大阪城から 京都を目指したのでした。 |

|
小枝橋、御香宮で衝突した両軍、幕府軍 総勢1万5千名、薩長を主とする新政府軍 は5千名。数の上では勝る幕府軍だった けれど、旧態依然の装備で戦う幕府軍に 対し、新式の装備で戦う新政府軍、そして 何よりも朝廷との密約が成されており、 錦の御旗を掲げ戦う新政府軍に対して、 もはや幕府軍には大義名分が成り立たなく なって戦意は喪失、譜代の大名であった 淀藩、その淀城の入城も拒否され、周辺 諸藩の寝返りなどもあり総崩れとなって、 大阪へ退いたのでした。 大阪から逃げ延びた慶喜は、恭順の意を 示し4月には江戸城は無血開城され、5月、 上野における彰義隊の戦い、7月の越後 長岡城の戦い、9月、白虎隊の会津若松の 戦い、翌年5月の函館五稜郭の戦いで、 旧幕臣の榎本武揚(えのもとたけあき)が 降伏するまで戦乱は続きます。 |
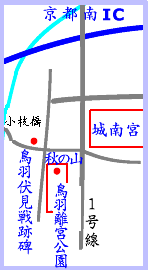
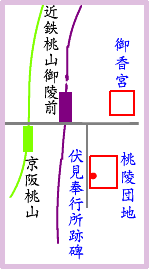
|
京都から外れる話題なので省略しますが、 今に残る戦死者名簿には二十代の若者が 多く名を連ねます。白虎隊などは十六、 十七才の若者です。多くの若者が国の行く 末を思い、真剣に生きて、戦って果てたと 云う史実が残ります。 どちらが悪、どちらが正義とも言い難い 鳥羽伏見の戦いです。国のあり方の主義、 主張が少し異なっただけの事。「勝てば 官軍、負ければ賊軍」と云う言葉が残り ますが、言葉を代えれば、「たまたま 勝った方が正義、負けた方が悪者」、 どちらが勝つにせよ、勝った方に歴史が 動いたと云えます。 ただ、この戊辰戦争がなかったならば 日本の近代化は百年は遅れただろうとも 云われます。 |

|
今に目に見える形で残る鳥羽伏見の戦い の史跡は、城南宮の少し西側、戦いの 発端の地である小枝橋近くには”鳥羽 伏見戦跡”の碑、今は鳥羽離宮公園と なっていますが、かつては鳥羽離宮庭園 の築山と云われる小高い、秋の山には、 ”鳥羽伏見戦跡碑”があり、この小山は 薩摩藩の大砲があった地点、この大砲の 一発が歴史を変えることとなったの でした。 また、下鳥羽小学校の南側にある悲願寺 墓地には”戊辰戦争東軍戦死者埋骨地” の石碑が残ります。 そして、前回紹介した御香宮の”伏見の 戦碑”、”伏見奉行所跡”なども関連 史跡ですね。 あと、料理屋の格子や民家にも弾痕が 残る建物などもあるようです。 |