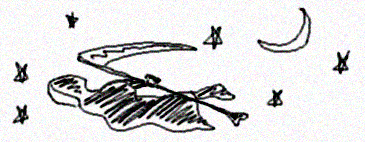
「序」 プロ野球のイチロー選手が世を席巻するまで、この物語の主人公「鈴木一郎(24)」は自分の名前が好きではなかった。 どこにでもある「鈴木」という姓と、どこにでもある「一郎」という名の組合わせがその理由だった。 彼の会社の同じフロアーには他の「鈴木」さんが5人いる。誰かが「鈴木さん」と呼べば、一斉に6人が振り返った。 そして他の「一郎」さんが3人いる。誰かが「一郎さんいらっしゃいますか」と聞けば4人が手を挙げるといった具合だった。 それを面白がる者もいるが、彼にとっては迷惑なだけで、いいことなど一つもない。 今までの彼の人生は、この名前のように平凡そのものであった。 平凡な家庭に生まれ、平凡な学校を平凡な成績で卒業し、平凡な会社に入社し、平凡な将来を考えている。彼はそういういたって平凡な人物なのだ。 「こんな平凡な人生から抜け出してみたい。波乱とスリリングに富んだ人生も送ってみたい」 そう思うことがよくあった。でも平凡がすっかり染みついた彼はどうしても安全で無難な道を選んでしまう、そんな自分の性格を自分の名前の平凡さがより際だたせていると感じていたのだ。 しかしあのスーパースター「イチロー」の登場によって状況は一変した。彼は「鈴木さん」と呼ばれても振り返らなくて済むようになった。 あのスーパースター「イチロー」と同姓同名であることから「イチロー」のニックネームで呼ばれるようになっていたのだ。「鈴木」と「一郎」の組合わせを持つのは彼一人だけだったのだ。 「イチロー」 以前なら無礼に感じた呼び捨ても今では彼の愛称である。 「イチロー、書類出来たかね」 「おいイチロー、これから一杯どうだ」 「今日の調子はどうだいイチロー」 「おおっ。さすがイチロー、また打率を上げたな」 今では誰もが親近感をもって彼の「名前」を呼び捨てている。そして誰もが彼をすぐ覚えてくれた。 イチローには「所沢範子」という恋人がいる。範子は今時珍しい大和撫子で、古風で一途な面を持っていた。その範子との馴れ初めも実は「イチロー」効果のおかげであった。 会社の福利厚生で催されたプロ野球観戦ツアーで、同僚が「こいつもイチローって言うんだゼ」と「イチロー」ファンの範子に紹介したのがきっかけである。 実は、イチローは会社で毎朝顔を合わせる範子のことを気にかけていたので、これを機会に急接近した。 まだ一緒に食事をしたりカラオケへ行ったりするだけの仲ではあったが、二人とも将来の結婚を意識して付き合っている。 そんな「イチロー」は公私ともに充実していた。今正に人生の絶好調期であることを実感していた。 「イチロー」 それは、幸運だけがやってくるラッキーネームだと思っていた。 「接触編」 今は春がもうすぐの3月、日曜の朝。 年度末で仕事が忙しい中、イチローは昨日引越してきたばかりであった。その散らかったアパートでイチローは「さあ今日でみんな片づけるぞ」と気合を入れて早起きしていた。 「埼玉ニュータウン」は東京近郊のサラリーマン用に農地を開拓した新興住宅地だ。 その「埼玉ニュータウン」にある新居「川瀬アパート」からイチローの勤める神田の会社までは、バスと電車を乗継いで1時間30分かかる。 この町には近々、東京へ直通で行ける地下鉄の駅が出来る予定があり、そうなれば通勤時間が1時間に短縮される。イチローはそれを見込んで千葉から越してきたばかりなのだ。 彼の部屋は2階の角部屋で、階段を上がってすぐの部屋だ。その1DKの家賃が月6万円である。 この町は学生の町といわれ、いくつもの大学や研究所が散在している。環境も静かで、住むにはもってこいといえる。 1DKではちょっと狭い気もするが独身で、きつい仕事に追われて寝るだけに帰ってくるような彼には十分な広さであった。逆に家財道具をほとんど持たない彼にとっては、どこに何を置こうか迷うくらいであった。 そして、引越しの理由はまだ他にもあった、範子の家がずっと近くなるのだ。 「さて、どれから片づけようか」 イチローが腰を上げた時「コンコン」と誰かがドアを叩く音がした。 「こんにちは鈴木さん、いらっしゃいますかァ」 ドアの向うは若い女性のようだ。しかしイチローはその甘い声に聞き覚えはなかった。少なくとも所沢範子ではない事は確かであった。 「はい、ちょっと待って!」 <ガス屋かな? 新聞屋かな?> 相手を推理しながら、まだ片づけられていない荷物の隙間を縫って玄関へ向かった。施錠はしていなかったが相手は扉を開けてもらうのを待っているようだった。 「こんにちは、お休みの所すいません。鈴木一郎さんですね?」 そこには薄化粧なのに飛抜けて美人で、それでいて愛らしい女性が立っていた。銀行員のようなグレーの上下で年の頃は二十歳前後といったところだ。 イチローはその美貌に一瞬見とれてしまい、ややしばらく返事が出来なかった。 「野球のイチロー選手と同じ名前なんですね」微笑みながら言った彼女の言葉に「お決まりの台詞だな」とイチローは思った。 「ええ、まあよく言われるけど...ところでどちら様?」 「あっ、はじめまして、申し遅れましたが私...シニガミですぅ」 「えっ?」 イチローは空耳を聞いたと思った。そして妙におかしくなり、ちょっと吹き出しそうになってしまった。 <死神だって? ははは、石上とか西神とかと聞き違えたかな、まさかそんな縁起の悪い名前が日本にある訳はないものな> 「西神さん?」 「いいえ、死神です。あなたは残念ながら一週間後に死ぬことなりました。そのため私がやってまいりましたぁ」 そうはっきり言って彼女は「にこっ」と美しい笑顔を見せた。 その笑顔とは対照的にイチローの顔には笑みが消えていた。 <言うに事欠いて死神とは何だ、しかも俺が死ぬだなんて...> 「間に合ってます」 イチローはそう吐き捨ててドアを閉めようとした。 「ちょっ、ちょっと待ってくださぁいっ!」 イチローがかまわずドアを閉めると下の方で「ドスッ」と鈍い音がした。音の方を見ると彼女の左足がドアに挟まっている。閉められまいとしてとっさに足を出したようだ。 悪徳な押売りみたいな手口だったが結構強く引いたからかなり痛かったはずである。それでもかまわずドアをぐいぐい引いてやると、やっぱり痛かったらしい。 「あっ、ごめんなさい、言い方が悪かったですね。痛いいっ、お願いですから、いたっ、話だけ、いたたっ、聞いてくださぁい!」 彼女は痛さをこらえながらあくまで引き下がらないつもりのようだ。 「死ぬ人間に保険のセールスでもしようというのかい?」 「ちがいますぅ、私はセールスでも勧誘でももありませんっ。あっ、そうそう、この名刺を見ていたたっ...見ていただければ判りますぅ」 そう言って彼女が、ドアの隙間から名刺を差し出してきた。 「名刺...?」 おもわずその名刺を受取ろうとしたイチローの手がドアのノブから離れた。そしてその次の瞬間「おじゃましまぁす」と彼女は中へ飛び込んで来た。 その早業にイチローは、あっけにとられて呆然とした。 「うふふ...ごめんなさぁい、でもこの名刺見てください。私こういうものです」 「こういう者?」 ドングリになったイチローの目は、その視線を、侵入に成功して喜々とする彼女から手渡された名刺へと移した。その名刺には女の子らしくピンクの模様が縁取られていた。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 死神 『マーヤ』こと摩耶 京子 −−−−−−−−−−−−−−−−−− イチローは思わず彼女を見返した。 「ねっ、ウソじゃないでしょっ」 口にはしなかったが彼女の目がそう言っていた。 生れつき人がよいイチローは、引越したばかりの荷物の中からコタツを用意し、キャンプ用のコンロで(まだ都市ガスの元栓が開かれていないので)お湯を沸かし、お茶を振る舞おうとしていた。やっかいな客ではあるが、彼女の美貌にはそれを許すだけの説得力を持っていた。 彼女は散らかった部屋の空いているスペースへ「ペタン」と座り込んでいた。 <まあ、適当に世間話でもして追い返そう> そんなつもりで中へ招き入れたのだが男たるもの美人には弱い。 <これを機会に...> ちょっと下心が湧いてきた途端に範子の顔が浮かび、それ以降を考えるのをやめた。 その間この「死神」と名乗る女性は「どうぞ、お構いなく」と言ったきり、ただニコニコして待っていた。そして時々落着き無くキョロキョロと周りを見回していた。どうやら散らかった部屋の中が気になるようだ。 「どうぞ」と言って、お茶を差し出すと彼女はペコリと頭を下げ、イチローの出した湯飲みへ手を出した。二人は今、コタツに向い合って座っている。 「ご用件は?『マーヤ』さん....」 「....ズズズ」彼女はおいしそうにお茶を飲んでいる。 「セールスでも勧誘でもないんだよね?」イチローはコタツに肘をついて「おしゃれ」な名刺を眺めながら言った。 「ああ、そうか、解ったぞ...新装開店のスナック『死神』か、それじゃなきゃパブか何かだな。君はそこの店員だろ、ほう..源氏名が『マーヤ』か、それで本名が...マア? キョウコだ、そうだろう?」 イチローは彼女の表情が少し曇ったように感じた。 「それ、マヤキョウコと読みます。私、死神です...本物ですよ」 <またそれか>とイチローは思った。 「びっくりしたでしょ? でも本当に私死神なんですよ、まだ新入りですけどネ。本当の本当に死神なんです、信じてください」 「信じろって言われてもねえ...」 信じてくれと言われるとかえって疑うのが人情である。しかし彼女が「死神」だなんていう話は疑う以前の問題だ。一体彼女は死神だと言い張ってこれから何をしようというのだろうか。 イチローは追い返す前にそれだけは聞き出しておこうと考えた。 「お茶までごちそうしてくれてありがとうございます。こんなにうまくいくとは...いえ、こんなにいい方だとは思っていませんでした。あなたは私の初めての人なんですからぁ...あっ、ごめんなさい、言い方が変だったかしら? ちょっと感激しちゃったものですから」 確かに彼女の目が少し潤んでいた。それを彼女はハンカチで拭おうとしている。 そのわざとらしい演出に、ただただあきれるイチローであったが、まだ彼女の訪問の本当の理由は聞き出せていない。 「感激してもらってどうもありがとう。それで、もう一回聞くけれど今日『マーヤ』はどうして僕の所へ来たのぉ?」 イライラが募って思わず口調を真似るイチローだった。 「はい、残念なことですがぁ、あなたは一週間後にぃ...」と言いかけて彼女は思いとどまった。 「...そういえば先ほどは失礼を申し上げました。言い直させていただきます」彼女は少々かしこまって、その言い直しを始めた。 「まことに、悲しむべき事ですが、あなたの寿命は、あと一週間なんですぅ」 <全然同じじゃねぇかっ!> そう叫んで、コタツを力一杯ひっくり返したかったイチローだが、そうはしなかった。 「へえーっ、でも、そもそも君は人間そのものじゃないか。だいたい『死神』っていうのは、こう、真っ黒なマントに大きなカマを持って...」と、イチローは最近見た映画の死神をイメージしていた。 「...こんな美人の死神なんて納得できないなあ」 「ありがとうございますぅ」 「それに、僕の寿命があと一週間だなんて、ホントだったらそんなこと言わずにさっさと魂を奪ってしまえばいいじゃない。それがなんで人のうちに上がり込んで呑気にお茶飲んでるの?」 イチローはちょっと意地悪に聞いてみた。 「このお茶おいしいですねぇ。私、お茶を飲むのが久しぶりなんです」 <誤魔化したな>そう思いながらイチローは彼女がさっき挟まれた左足をさすり始めた事を見逃さなかった。 「あっ、足痛いんだ。やっぱり人間だ」 「いいえっ、死神ですぅ!」 その真剣な表情にイチローが引いてしまったので少しの間沈黙があった。彼女の真剣な表情は演技であるならここまで出来るものかと感心できるほどであった。 「それでは鈴木様のご質問に対して一通りご説明させていただきますので最後までよく聞いて下さい」 そう言う彼女は事務的な表情へ変わり、「ふっ」と小さく深呼吸した。 イチローは沈黙を続けていたので彼女は「いいですか?」と目で聞いてきた。 「ああどうぞ」とイチローも目で答えた。 「改めて、わたくし『摩耶京子』と申します。 先ほども申上げたとおり、わたくしが担当とさせていただきます鈴木一郎様は、あと一週間の期間をもちましてご寿命が満期となり、その生命を全うされることとなりました。まだ若くしていらっしゃるのに誠に残念なことと痛感の念を隠し得ません。 鈴木様にはご不満も多々ございましょうが、致し方ないこととご了承いただきたく存じます。 わたくしどもも鈴木様の無念であろうことを重々考慮し、最善を尽すショゾンです。」 「ふあああ...」 イチローはわざと退屈そうに大あくびをして見せた。冗談でも自分が死ぬなんて話は聞いていておもしろくない。しかしそのイチローの態度に全く気がつかないのか、彼女はうつむき加減で話を進めた。 「本日お伺いさせていただいたのは、この避けられぬ運命を鈴木様にご納得いただき、残された一週間を悔いなく生き抜いて頂こうと考えるからに他なりません。 そのお手伝い役として、また一週間の後には進むべき道への案内役としてやってまいりました。 つきましては、本日より一週間、わたくし『摩耶京子』こと、死神名『マーヤ』が鈴木様のお側にお付添いさせていただきます。 なお、人間界での鈴木様のご生活に不都合が発生しないよう、そして人間界にいらぬ騒動を引き起こさないよう、わたくし『マーヤ』は人間の姿を借りて違和の無いように行動させていただきます」 <うまいこと考えたな>イチローは思った。 「死神といっても決して世間で言われるように恐ろしい存在ではございません。人間界のメディアでは死神のことが地獄の使者であるかのように扱われていますが、死神界の者としては非常に残念でなりません。どうぞ、なんでも気楽に話しかけて下さい。なるべく鈴木様のご意向に沿うように勤めてまいります。 また、私事でキョウシュクですが、なにぶん経験も浅く、いろいろとご迷惑をおかけしてしまうこともあるでしょうが、わたくし、一生懸命がんばるショゾンでございますので、ご協力、ご指導のほど宜しくお願いいたします」 彼女は語り終って「ふぅ」と小さなため息をはいたあと「うまくできたかな」という目でイチローの方を見上げた。 イチローは皮肉を込めて「パチパチ」と拍手を送った。彼女は、それを真に受けたのか、はにかみながら満面の笑みを浮べた。 <こいつは手強いぞ>イチローはしかめっ面になっていた。 そのとき、彼女の左手で「がさっ」と音がしたのをイチローは見逃さなかった。 「あれっ、今、何か隠した?」 「わっ!」 「それカンペだなっ」 見破られた彼女はあわてて口上を書いたメモをハンドバックの中に隠そうとした。 「ちょっと見せてみなよ...どれっ...いいじゃん」 「あれーっ、やめて下さい、はずかしいっ」 コタツを挟んでイチローとマーヤはカンニングペーパーの奪い合いとなった。 そのもみ合いの時、勢い余ったイチローの手が彼女のハンドバックに当り、口の開いたバックの中から彼女の持ち物が「ばさばさ」と床へ放り出されてしまった。 「きゃっ」 「おっと、ごめんよ...なんだこりゃあ?」 イチローは散らばった彼女の持ち物を拾ってあげようとしたのだが、その中に妙な本が2冊あった。 死神くん 第7巻(えんど・コイチ) 人前でアガらない方法−人をカボチャと思え! 「おまえ、こんなの参考にして来たのか? この唐変木! 俺はカボチャか!」 「ひどーい、おまえだなんてぇ。マーヤと呼んでください...かえしてっ」 彼女はイチローから本を奪い返し、ハンドバックへ慌ててしまい込んだ。 イチローはしばらく腕組みをして、考え込んでいた。もういい加減に彼女を追い返さなければならない。 「俺は全然信じられないぞ、死神だなんて話...ちょっとおかしいんじゃないか? 人を騙すんだったらもっとありそうな話を用意しろよ。さあ、充分おもしろかったからどうぞ帰ってちょーだい」 がさごそとハンドバックをしまい直している彼女の肩をつかんで、イチローはぐいっと玄関の方へ押しやった。ついにイチローの実力行使が始まった。 「いやっ」 彼女は両足を開いてその重心を落とし「動くもんか」と必死に抵抗しようとしている。 「もう出てってくれよ、この疫病神!」 「いいえっ、死神ですってばぁ、どうすれば信じてもらえるの」 「まだ言うかっ、信じるもなにも...じゃあウルトラマンに変身できるか? そりゃあ死神でも無理だな...じゃあ空でも飛んでもらおうか!」 「空を飛べですってぇ?!」 そのイチローの無理な注文にマーヤの目が輝いた。 |