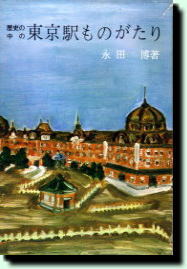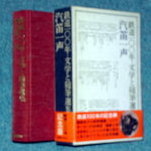(9)初代の東京駅長・・・書籍から抜粋
◆高橋駅長についての記述で一番詳しいのは、本書と思われる。
「鉄道開業50年と東京駅」の部で 10ページにわたって、駅長の名物ぶりが紹介されている。
鉄道100年*文学と随筆選集」「汽笛一声」にも、同文が掲載されている。
初代の東京駅長
鉄道の高橋か、高橋の鉄道かといわれて外国までその名がしられていた初代東京駅長高橋善一氏は、安政4年8月、河合善七の二男として福井県に生まれた。(編注:愛知県豊橋が正しい) のち高橋家の養子となったが、明治6年に鉄道に入り、新橋の機関車の油さしになった。 本当は海軍の軍人になりたかったといわれているが、どういうわけか鉄道に入った。
その後、目をかけてくれる人があって、関西に行き、車掌なんかもしていたが 、その人柄や仕事ぶりを見た井上勝(明治の鉄道建設に当たって、政治的にもっとも力があったのは大隈重信と伊藤博文の二人であるが、この二人がまいた種を丹精して立派な作物をつくりあげたのは井上勝である。鉄道の父といわれている。)に見出され、抜擢されて馬場、現在の膳所駅長になった。
そしてこの後、初代の長浜駅長をやり、明治19年3月、武豊線が開通すると武豊から熱田までの統括駅長、5月に名古屋駅が出来ると、名古屋駅長を兼任した。
その後大垣駅長、そして大阪駅長を経て、明治28年11月5日、第3代目新橋駅長(いまの汐留駅)を命ぜられ、そして大正3年に東京駅が出来ると、今度はその駅長を命ぜられた。
約9年後の大正12年に退職したが、その年の5月20日、自動車事故で死んだ。 72歳であった。(編注:享年 67歳が正しい)
この人は人生の大半を駅長で過ごした人である。
戦前の東京、大阪、名古屋は特別一等駅であったが、高橋善一氏は、この三つの駅長を一つ残らずやったわけだ。 (中略)
鉄道の歴史をよく知っていることにかけては第一人者といわれる青木槐三氏は「鉄道黎明期の人々」の中で、高橋東京駅長について、つぎのように書いている。
「高橋駅長は一代の名物男で、もう伝説裡の人となっているが、鉄道の現場に最も精通し、彼の鉄道生活の一生に、一つのあやまちもなかったのは特記大書すべきである。」
青木槐三氏は高橋駅長から「おい新聞屋」といわれたことがあると書いているが、その書いたものによると、明治天皇は高橋駅長を呼ぶのに 「善一、 善一」といっていたそうである。
また首相をやったこともある桂太郎公爵は、高橋駅長の肩を抱いて、「君さえおれば鉄道は心配ない」といったそうである。 (後略)
歴史の中の
東京駅ものがたり
永田 博著
(株)雪華社
昭和44年6月発行
「汽笛一声」
鉄道100年*文学と随筆選集
実業之日本社
昭和47年10月発行
目次に戻る
次ページ