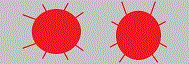
タカラダニ・駆除・実戦記
タカラダニを駆除した実際の記録です。

新築にもかかわらずタカラダニが発生してビックリ、その対策をまとめました。
(全てをまとめた総合ページはこちらです。)
通常、コンクリートが古くなって、ヒビとか穴が増えてくると発生すると言われています。
そこが最適な住み家になるからです。
タカラダニについての一般的な解説は、Wikipediaでご覧ください。
東京都健康安全研究センター研究年報のタカラダニ調査とその関連のみリンクします。
その1、
その2、
その3、
その4
何で赤いのかは、こちら
春先の紫外線から体を守る抗酸化物質を大量に蓄積しているため、だそうです。
今回は、外構工事が10月から11月、タカラダニ発生が翌年5月、ありえません。
1年目はともかく発生したタカラダニを朝、昼、夕とその都度駆除していました。
2年目も同じように1日に最低3回は行っていましたが、途中から元を断つように考えて駆除しました。
何とか大発生は防ぎつつあるようです。
当初、タカラダニは足が速く、どこで発生しているかが良くわかりませんでした。
1匹を駆除するために他の場所から目を離し、駆除後に目を戻すともうそこにタカラダニがいました。
どこから出てきたかはわからないままスプレーの殺虫剤を噴霧していました。
2年目は、よく観察してみましたら、すぐそばの穴からタカラダニが這い出して来るのが見えました。
目ではコンクリートの穴は見えないのですが、小さな穴から体を小さくして這い出して来るようです。
更に慣れてきますと、這い出す寸前立ち止まっているのもわかるようになりました。
コンクリート壁やコンクリート床にタカラダニがいて、殺虫剤を噴霧すると周辺にタカラダニが出現します。
その場合は、その場所(穴の中)に多くのタカラダニが生息しているようです。
止まっている(食事中?)タカラダニは気が付きにくいです。
何かのショックで動き出すと認識できるようになり急に出てきたと見える場合もあります。
一匹に殺虫剤を噴霧して急に周りにタカラダニが出現する場合はその可能性もあります。
 タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。
タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。
写真は、フェンスの上部です。
コンクリートブロックの基部を登り、フェンスの縦棒を登り上部に到達します。
この場合には、この周囲に生息地は無く、コンクリートブロックの基部下の砂利部分に生息しているような感じです。
はっきりとはわかりません。
又、ドアノブの上部、自転車カバーの上にもいますし、もちろんフェンスの網にもいますし、基礎の上の水切りを歩いています。
エアコン室外機の上部もお好みのようです。
玄関アプローチでは、隣の月極駐車場から境界部分20cm幅くらいの砂利を経由してこちらにやってくるようです。
少なくとも、隣の駐車場のアスファルトの石と石とのすき間や穴には大量のタカラダニが見られ、駆除しても駆除しても発生しています。
白に赤は目立ちますが、黒に赤も目立ちます。茶色(土色)では見えません。
次のページは、その対策です、下の右矢印をクリックして下さい。
 ホームへ
ホームへ 
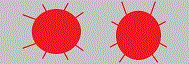

 タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。
タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。
 ホームへ
ホームへ 