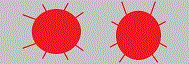
タカラダニ駆除実戦記
タカラダニを駆除した実際の記録3です。

殺虫剤を噴霧して一安心、まとめです。
一匹ずつの殺虫は、水性のゴキブリ用殺虫剤を水に溶かして使用するのに限ります。
何より安い、安全性は市販品なのでそれなりに確保されている、というのが理由です。
スプレーする際は、なるべくゴム手をするほうが良いかと思います。
しばらく手袋無しで行っていましたが、指紋が薄くなって指がすべすべする感じがあります。
因果関係ははっきりしませんが、転ばぬ先の杖です。
油性の強力殺虫剤は、本当に効果あります。
油性なので持続性があります、しかも強力なので、タカラダニ程度では数日間効果が持続しているようです。
但し、噴霧された場所に関しては効果があるもののそこが生息地でなければ効果は弱くなります。
噴霧場所には嫌がって来なくなる効果はあるものの、殺虫されるのは間違ってきてしまった奴だけになります。
粉剤も同じです、嫌がってその場所に来なくなるだけで、元々の生息場所にはそのままいるはずです。
防水塗料をコンクリートに塗ると発生が抑えられるという記事を見たことがあります。
おそらく、その場所で発生していた連中の住み家が防水塗料の厚い塗膜で覆われて無くなったからと思われます。
通常の床塗料ではほとんど効果がありませんでした。
我が家の壁を登るタカラダニはほとんど見かけませんでした。
モルタルに掻き落し仕上げをしているもので、表面がざらざらです。
なので、嫌がって登らなかったと思われます。
骨材に樹脂が混入されているので、ざらつきはあるものの生息出来る穴が少ないのではないか、だから避けていた、と思われます。
壁の下部は金属の水切りですが、そこはそれなりに見かけました。
もちろん壁に設置したキーケース、郵便受けにいましたので、そこは壁を登らないと到達しませんので、全く上らなかったというわけではありません。
但し、外壁がタイルのマンションの6Fにも出現していましたので、外壁がざらざらだとかなり抑えられるようです。
アリやクモが天敵という記述も見たことがありますが、実際にアリが捕食しているのを見たことがありません。
タカラダニのそばにアリがいても全く無視しています。クモも同様に見かけませんでした。
タカラダニは昼間に活発に活動し、アリやクモは朝か夕方に活動し、活動時間が異なりますし期待しないほうが良いと思います。
さて、5月の連休明け位から梅雨入り前まで良く活動しているタカラダニですが、本当はいつまで生きているのでしょうか?
春はいつから孵化して発生するかは当初わかりませんでしたが、3年目の春、4月21日に植木鉢の縁に3匹発見しました。
そして、その日以降、見に行く度に10匹以上発見することになりました。
サイズはやっと見える程度、生まれて間もないようですが、色は赤いので判別できます。(下の写真右側、ピンボケ)
翌月8日、玄関ドアにかなり大きくなったのを発見しました。
まだ濃い赤とはなっておらず、透明感のある赤でした。隣地駐車場にも発生が始まっています。
2年目は、梅雨の合間の晴れた時に成虫を3回(匹)見かけました。
いずれも直接雨の当たらないところで生き延びていたようです。

 これは同じく2年目の梅雨末期、幼虫もいました。
これは同じく2年目の梅雨末期、幼虫もいました。
こんな時期でも卵から孵っているようです。
曇天でしたが、雨が上がって喜んで出てきたのかもしれません。
植木鉢の縁にいましたから、おそらく土の中の卵から孵ったのだと思います。
もしくは、縁の内側、折り返し部分かもしれません。
緑の葉っぱは、ニチニチソウの葉で、濡れているのは水性殺虫剤です。
サイズは、0.5mmくらいです。
真夏はほとんど見かけませんでしたが、ピンク色の個体を見かけた記憶がありますし、今年は雨上がりに植木鉢で見かけました。
どこに隠れていたのかはわかりませんが、成虫になりかけのものでした。
昨年は11月までその姿がありました。
但しかなり弱っているのでしょう、赤い色が薄れて薄いピンク色になって目立たなくなっていました。

 左は、今年(2019年)の11月3日です。
左は、今年(2019年)の11月3日です。
既に水性殺虫剤噴霧済で、胴体が液と共に落ち気味)になっています。
気温は17℃、曇り、午後2時過ぎ、平年に比べると暖かいようです。
この葉は西洋アサガオですが、まだ花が咲いています。
植木鉢からは1mくらい上です。
サイズは、1mmくらい、元気に動き回っていました。
他にいないか探しましたが、見つかりませんでした。
右は、同年の11月21日、風は冷たいですが、小春日和でした。
玄関アプローチのタイル端、ワイヤープランツの葉の下にいました。
既に水性殺虫剤噴霧済、液を吸って丸くなってしまっています。
1ページ目のリンクその4を見ますと、タカラダニの最適活動表面温度は、20℃から30℃のようです。
4月、5月の朝、気温15℃として太陽が照りだすと、コンクリート表面は10度は温度が上昇するはずです。
そうすると、最適温度になります。6月、気温20℃で、コンクリート表面30℃、確かによく動き回っています。
6月の昼間、太陽照射面は暑すぎて活動できないようです、夕方になると見かけるようになりますが、温度的には符合します。
45度の金属表面でも観測される事があるそうで、梅雨時の雨を避けられれば夏でも生きている事がわかります。
次のページ、最後は覚書です。
 ホームへ
ホームへ  前のページへ
前のページへ
 ホームへ
ホームへ  前のページへ
前のページへ
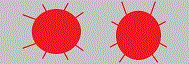


 これは同じく2年目の梅雨末期、幼虫もいました。
これは同じく2年目の梅雨末期、幼虫もいました。

 左は、今年(2019年)の11月3日です。
左は、今年(2019年)の11月3日です。