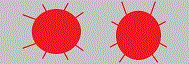
タカラダニ駆除実戦記
タカラダニを駆除した実際の記録4です。

2年間観察してわかったこと覚書です。
足が速いとはネット上で見かけますが、一体どの位の速さか具体的に書かれたのを見たことがありません。
実際には測ったことは無いのですが、見た目で分速3m、秒速5cmくらいのような感じです。
なぜそのように早く移動するのかはわかりません。
ひょっとしたら地面が熱くて仕方ないのでそうでない場所を求めて早く歩いているのかもしれません。
直線的に進まず、ダンスをしているように一定の広さを速いスピードで歩き回っているのもいます。
熱い、熱いと跳ね回っているのでしょうか?
生息場所は、壁面とよく書かれていますが、アスファルト舗装面(月極駐車場の端部)の凸凹の穴に大量にいました。
4月から6月にかけては雨が少ないので、雨が直接当たる場所でもなんとか生き延びられるようです。
よく、成虫になる前は昆虫に寄生して、大きくなって分離する、と書かれているものがあります。
タカラダニの名前の由来の1つはその生態からだそうですが、都会ではそんな昆虫はいません。
卵の大きさは、0.2mmx0.15mmの楕円形だそうですが、そこから生まれるならば、大きさは0.2mm程度あると思われます。
0.2mmはギリギリ見る事が出来ます。
成虫に交じってそのくらいのサイズのものは、何度も見かけましたし、駆除していました。
但し、広い面には少なかったような記憶です。
土の中やらこけの中で孵化してコンクリート面に這いあがってくるように感じました。
きちんと検証しているわけではありません、あくまで印象です。
タカラダニはどこを目指して、何を目指して移動するのでしょうか?。
タカラダニの目は赤外線センサーも兼ねているのではないかと思います。
25℃から35℃に反応するセンサーです。
広い面でそういう温度域があると、そこを目指して進むのではないかと思われます。
そうでないと、到達するのに大変な 手すり(金属)、郵便受け(ステンレス製)、自転車カバー(アルミコーティング)、配管パイプ(金属)、エアコン室外機(樹脂)に上ってくる理由が考えられません。
焦点は近くに固定、エサは良く見え、遠くの物はボケておおざっぱ見えている(温度の高低のみ判断できる)のではないかと思います。
モルタル掻き落としの壁にあまり上らないのは、表面がざらざらの為ではなく、温度が低いのかもしれません。
登り始めたらそのまま直線的に上に登ればよいと思うのですが、そうでなく、郵便受けやキーケースにとどまる理由がわかりません。
サーモビュワーがあれば確認できるのですが。
暖かいところを目指して登ってくる性質を利用してタカラダニホイホイが作れないかどうか試してみましたが、失敗でした。
お豆腐の入れ物にアルミ箔を貼って、ひっくり返し、コンクリートの床に貼ってみました。
豆腐の入れ物程度では小さすぎるのか、貼るときに使った養生テープが悪いのか原因ははっきりしません。
次回機会があればいろいろ条件を変えて試してみたいと思います。
ネット上の情報は出本が1つではないかと思われるものが多く、あまり参考にはなりませんでした。
特に名前の由来、食べ物、住み家、等はあるところの情報のコピペばかりだと思いました。
中性洗剤を水で薄めて殺虫するというのもありましたが、乾いた後大丈夫なのか、雨が降ったら泡だらけにならないだろうかと心配になりました。
そこまで書いてあるものは皆無でした。
そういう事、1つずつ自分で体験して自分で考えるほうが良いようです。
以上、タカラダニにお困りの方の参考になれば幸いです。
なお、状況をよく観察して対処されることをお勧めします。
次のページは3年目の状況です。
 ホームへ
ホームへ  前のページへ
前のページへ
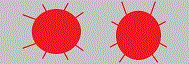

 ホームへ
ホームへ  前のページへ
前のページへ