昨年は、石澤酒店をご愛顧いただき本当にありがとうございます。
年末には、毎日たくさんのお客様にいらしていただいて、「日本酒を好きな人はこんなにいるんだなぁ」と、うれしくてルンルンと元気に毎日を過ごしました。
朝から夜までクタクタでも商いをやっていて忙しいのは、なんとなく気持ちも晴れて明日もガンバロウという気になります。皆様のおかげですね。本当にありがとうございました。
本年も少しづつですが前に向かって進んでゆきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
さてここのところのお客様とのやりとりで強く感じるのですが、「日本酒を知りたい」という方が多いという事です。
味や種類の質問の他に酒造りに関しての質問が思いの他に多いのです。
そんな訳で、今年は酒造りの事などを、なるべく多くご紹介したいと思っています。
自分たちも酒造りのプロではないので間違えることもあると思いますが、初心にかえって勉強しながら、なるべくわかりやすく紹介できればと思います。
昨年の「日本酒のこと知ってる?(1)」の続きとして今回は、日本酒はどの様な工程で造られるのかをご紹介したいと思います。
年末に多かった質問から順番にご紹介できればいいなぁと考えています。
11月13日で湯島酒堂も3回目を数え、話もだんだん難しくなってきました。
今回1部の篠田先生の話は「酒の風俗」「何故酒を飲むのか?」というもので飲酒の要求を「個人的要因」と「社会的要因」にわけ、社会的要因を以下の4つに分類。
人は、
に酒を飲んでいた。
1は文化人類学者はいう説で人類は酒の酩酊によって神に近づくというもの。2は地鎮祭や棟上げ。3は殿様と家来(民衆)、組関係の盃、官官接待、官民接待。4はそのまま冠婚葬祭で。
ここで、日本酒の消費要因の中に社会的要因があり、それがどう変貌しているかで日本酒の数量的消費が変化します。
先に挙げた4つの社会的要因のうち、3番以外では数量的消費が望めない事がわかりました。
2または4番で量的消費があったとしても、大勢に影響を及ぼすものでなかったと理解できると思います。とすると、「酒を飲む要望」の社会的要因というものがあるとすれば、3番をおいて他にないということがわかります。
ここで挙げた「権威と従属」を証明し、共用する場には、儀式用とさえいえるように日本酒がありました。儀式がすむと後は「無礼講」と称して、おおいに飲むのであります。この儀式は、江戸時代に来日したペリーの従者が当時のことをこう記しています。
「上座にホストが座ると居並ぶ一同は、下座から膝行してホストの前に進み、畳に頭をすりつけるほど平伏し盃を賜る。やがてホストが座を外すと、あとは一変して飲めや歌えやの酒盛りになる」と。
この状況は決して150年前のものとは言い切れません。10数年前まで大いに、いや、ごく数年前まで一部では行われていたといえます(接待という形で)。
この場は日本酒が主流で他の酒類から難攻不落と思われていましたが、時流は「二本箸作戦」でウイスキーに侵食され、「とりあえず」によってビールに攻め込まれました。しかし、日本酒はこの砦にしぶとく残っていました。ただ、いうなれば儀式の演出材料のようなものでありましたから「有名銘柄」でありさえすればよく、品質を問われるようなことはなかったのです。
次に個人的要因はウイスキーやビールの需要開発によって広がってきました。ウイスキーがトリスバーを拠点に、ビールが家庭用冷蔵庫の普及に乗って消費を拡大させていったのに対して、日本酒は昭和50年に始まる民間活力の地酒発見までなにもされなかったといってもいいと思います。
この数年、日本酒消費が激減しています。
年によっては2桁に近い減少。間もなく戦前の最高数値まで落ちるだろうとも言われています。
それは、清酒業界が個人的要求分野の需要開拓を怠り、社会的要因市場(大量消費の場である飲食店)の奪い合いに終始し、テレビCMも個人的需要が目的でなく、ひたすら「有名ブランド」であるために流していたからです。
現在、清酒業界は、個人的要求の市場向けメーカーと社会的要因市場向けメーカーとでは、天と地ほどの内容差が出ています。
つまり、個人比率の高いところは小規模であっても高収益にあり、社会的要因市場比率の高いところは酒の出口を廉価戦略に頼らざるを得ず、内容を言うのも、はばかれるようなありさまです。
いま、清酒業界にいうことは、市場は耕さなければならない。種を蒔かねば収穫は得られない。栄養を失った大地に種を蒔いても芽はでないということです。
個人的要求の市場はこれからも伸びます。そのためには「日本酒といえば、権威に従属されるようなイメージ」を払拭しなくてはいけないでしょう。
・「新しい日本酒は新しい酒袋に」
以上のような内容で最初は「何故日本酒を飲むのか」という題目だったんですが、最後には何故、日本酒が廃れてしまったのかになってしまいました。
しかし、今こうして日本酒を飲もうとしていることが、とても意義のあることのように感じる講義でした。(もう少し、考えながらお酒を飲まないといけないのかなぁ?)
1部が長くなってしまいましたが、2部は皆川美恵子先生で児童文学と酒というタイトルで安房直子(著)「ハンカチの上の花畑」を使っての講義で、これは、おばあさんが、不思議な壷を持っていて、それをあずかった郵便配達員の話で、この壷には、ハンカチの上に菊の花畑を作って、その菊の花からお酒を造る5人の小人が入っているんですが、先生の解釈では...。
というもので「児童文学と酒」というのは全然つながりがないようにみえていたんですが、講義が進むにつれてなるほどと思うようになりました。
3部はきき酒ですが、今回は「蔵が違うと酒が違う」で1本は刈穂「大吟醸」、もう1本は出羽鶴大吟醸「飛翔の舞」で、この2つは蔵の違いもそうですが水が硬水と軟水で性質の異なるもので味もまるで違うのには驚かされました。
(僕はどうも貧乏舌みたいで、硬水の方が甘く感じ、軟水の方が辛く感じて他の人とは違った意見になってしまいました)
戸隠貞男
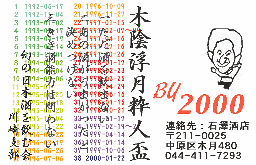 毎年、粋人盃の会員カードを作って下さる鈴木さん、いつもありがとうございます。今年は今までの会の日時が書き込まれています。来月よりお渡しできると思います。
毎年、粋人盃の会員カードを作って下さる鈴木さん、いつもありがとうございます。今年は今までの会の日時が書き込まれています。来月よりお渡しできると思います。
年会費の振り込みなど来月号にて詳しくお知らせします。
日本酒はお米を醗酵させて造られる醸造酒です。醗酵は酵母が糖分を食べてアルコールになること。お米を醗酵させるにはまず、お米のでんぷんを糖分にかえ、酵母の力でアルコールに醗酵させます(リンク先を見て下さい)。
醗酵したモロミをあらく漉したお酒です、火入れをしていない生酒なので酵母が生きていてビンの中でも醗酵し、炭酸ガスを含んでいるので口の中でピチピチとさわやかにはじけます。
吟醸純米活性にごり酒。パート1は「喜三郎の酒」のタンクから取りました。酒蔵を訪ねて、モロミタンクより汲んで飲ませていただくお酒。醗酵の炭酸ガスがピリッとしていて旨い。酒蔵でしか口に出来なかったそんなお酒です。今年はパート4までです。体験した事のない方は、ぜひチャレンジしてみてね。
1800ml・・・4000円
今年はメチャメチャ元気が良いです。開栓には時間がかかりちょっと大変。でも、この開ける時が楽しいんだよね。ワクワクしながら開けてください。ピチピチ感のあるキリッと辛口。
720ml・・・1600円、1800ml・・・3200円
ガッチリ骨太の辛口タイプ。1800ml・・・4300円
最終便が入荷してまいりました。この酒も不思議な反応のある酒です。なぜって?新酒のピリッとした若さ、山廃仕込みのオシ、そして原酒のもつアルコールの強さ、等々が一つのかたまりの様に口中を駆けまわります。これでもかと言う感じで主張してきます。これが意外と若い女性が旨いというのです。本当ですヨ。(←年末の試飲の結果)
こっちがビックリします。男性の皆様、女性は軽くてフルーティで低アルコールの方が・・・なんて決めつけないで下さい。
無炉過生原酒 1800ml・・・3434円
当店では「渡舟」でおなじみの府中酒蔵さんのお酒です。太平海とは昔使っていた名前なのだそうです。若々しくフルーティな香り、口中でフワッと広がってスッキリとキレてゆく辛口タイプ。
1800ml・・・2350円
限定無炉過本生1800ml・・・3050円
新酒のはじける様な若々しい香りとギュッと引きしまった辛口のお酒。昨年よりも、ぐっと味わいの方向へ重点が置かれた感じです。
むく限定おりがらみ本生1800ml・・・3050円
上のお酒にほんの少しだけオリが含まれたお酒です。オリが含まれるので少しソフトな口当たりでフッとモロミの香りが上がって来ます。ほんとに淡いにごり酒の様な色なので透明のグラスなどで楽しむとキレイ。