

学生の身分でありながら机を2つ占領していたことになる。申し訳ない。
宇宙研の衛星・探査機のペーパークラフトを宇宙研で作るという活動を続けてきた宇宙工房ですが、連載10回目の今回で最終回とし、これで宇宙工房の活動はひとまず終了します。
私が宇宙研に来て間もない頃、私の机の後ろの誰も使っていないPCラックを「宇宙工房」と名づけてペーパークラフトの組み立て作業に使ったのが、この企画の始まりでした。
私は実はそれまでペーパークラフトを作る趣味など無かったのですが、もともと図画工作が好きだったところに、衛星のシステムが実感しやすいこと、宇宙科学の普及活動に役立つことを見出して、ペーパークラフト作りに目覚めました。ペーパークラフトを一般公開などのイベントに使ったり、マイナー局ながらも、テレビに出たりもしました(私じゃなくて、私のペーパークラフトが)。机を勝手に使っていても、研究や雑用をサボって作業をしていても、苦情や不満を言わずに応援してくださった宇宙研の皆様には本当に感謝しています。
 | 2006年一般公開の準備の頃。2週間ほど研究をお休みし、おもちゃ作りと、「あけぼの」ペーパークラフトの設計、太陽系クイズの作成などの作業を行っていた。 |
 | 右が大木社長の机、左が「宇宙工房」。 学生の身分でありながら机を2つ占領していたことになる。申し訳ない。 |
私はこの宇宙工房を始めるにあたって、シリーズ初回の宇宙工房 concepts(2005年11月)で、(半分冗談で)このようなコンセプトを掲げてみました。
私は、この研究所という地味な世界に、少しだけアートの発想を取り入れ、アートと宇宙科学の橋渡しができないか、両者の面白味を引き出すことができないか、と偉そうなことを考えていました。そこで衛星のペーパークラフト作りをする場所を宇宙工房の机か、できればその衛星の運用室、使う道具は全て部屋の文房具や不要品とし、全てを宇宙研にあるものでまかないました。これには、お金を掛けたくなかったからというよりも、宇宙研というこの《環境》の中で生まれる活動をしたかったという理由からです。
宇宙工房で作ったものは実際は単なるペーパークラフトで、誰でも作れるものです。高度な芸術的技法を用いているわけではありません。しかし、宇宙研の部屋の中に、工房という名の付いた異質なものを置くことで、関係者からも、またWebを通じて外の人からも面白い反応が返ってきて、少しは宇宙と文化・社会を繋ぐことができたように感じられました。
宇宙開発は、科学や技術だけの問題ではなく、広報、教育、そして芸術活動を通じて文化・社会を豊かにする力があると思います。また、それをしなければ宇宙開発の将来も危ういものになるでしょう。例えば、技術を悪用して、人の感性が欠如したとんでもない活動をするようになるかもしれません。
これが、コンセプトに掲げた「宇宙はアートであり、アートは宇宙であるという崇高な思想」ということの意味です。
 | コンセプトの3.に従って、宇宙研にある道具だけを使った。初めはプリントを何枚も重ねてカッター台にしていたが、その後、書類郵送用の厚紙を提供されて使い始めたらだいぶ使い心地が良くなった。 |
 | 「のぞみ」のペーパークラフトを作る作業は「のぞみ」の運用室で。ペーパークラフトそのものだけではなく、こういう体当たりの活動こそが自分のアートだったのかもしれない。ともかく、この「のぞみ」のネタがきっかけで「衛星のペーパークラフトをその衛星の運用室で作る」というスタイルが確立された。 |
 | 一般公開で、ペーパークラフトを透明の球体に閉じ込めたおもちゃを作り、ミニアトラクションで子供達に遊んでもらった。 |
宇宙工房の1年半の活動で作ったペーパークラフトを改めてリストにしてみました。いずれも宇宙研の人工衛星・探査機で、
このうち「あけぼの」「あかり」「Cross-Scale」については、ゼロから作った、つまり図案から自分で書き上げて作りました。このうち「あけぼの」については2006年宇宙研一般公開で配布を開始し、「あかり」は「あかり」チームのメンバーの手によって仕上げていただき、2007年宇宙研一般公開で配布を開始しました。
また、上記リストの月・惑星のペーパークラフトや、あまり関係ないエレメンタッチなども製作しました。
 | これまで作ったペーパークラフト(の一部) |
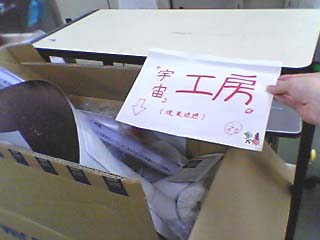 | 宇宙工房撤収作業。荷物をまとめて、宇宙工房の目印を取り外した。 |
さて、これで、宇宙研でのペーパークラフト作りの活動をしてきたこの宇宙工房シリーズを完結します。
今後も引き続き、宇宙開発に関する広報・普及活動と、宇宙とアートの可能性を探る試みはできる限りやっていきたいと思っています。いま私がそんな目標を持つことができるのも、宇宙工房でやってきた活動のお陰かもしれません。
これまで宇宙工房を応援してくださった方、仕事を依頼してくださった方、ペーパークラフトで楽しんでくれた方、ありがとうございました。また何かの機会にご一緒しましょう。
Copyright(C) 2007 大木社長