![]()
���w���̃L�b�J�P
| �@���ڂ��n�߂��̂̓A���~�t���[���̂e�S�^�ɂȂ������B�R�^�͓S�t���[���̏d�����l�b�N��������ł����A�P�Vkg���y�ʉ�����܂����B���炭�a�����������ōs���C�ł������߁A�l�q�������ߍ���ł���ƁA�X�Ƀ��[�X�����Ƀ��f���`�F���W����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�l�I�Ƀc�[�����O�����̐��i���D�܂����������߁A������V�ԂŔ������Ǝv���Ă����v���O�|�����܂����B �@�E�z���_�̎l���ł���i��x�͏�肽�������j �@�E�t���J�E���ō������y���� �@�E�����d�l������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����̂��A���R�Ƃ����Η��R�ł��傤���B �@���C���X�^���h�����邱�Ƃ��|�C���g�������ł��B�`�F�[�������e���ɉ_�D�̍��ł��B��̌^�_�u���V�[�g���^���f�������^�����̂��߁A�ו����ς݂₷���ł��B�V�[�g���̐ύڔ\�͂͂قڃ[���Ȃ̂ŁA�V�[�g�o�b�N���g��Ȃ��Ȃ�A�V���O���V�[�g���ɂȂ����V�^(���s�^)�̕�����������ς߂�͂��ł���.......�B |
 |
| �@���� | �@�G���W���͐����@�B�ł��B�܂��A���~�����`���[�N��������������n���i���̂܂ܒg�C��������ƁA���R�J�u���܂��j�B�o���I�X�Ō��\��J�����̂Ŋ������܂����B��^�Ȃ瓖����O�ł����ˁB �@�����̘r�O�ł́A��������ȏ�͗v��Ȃ���˂Ǝv�킹��ԑ̂ƃG���W���̊����x�B���Ƀ^���N�̃j�[�O���b�v�����̌`��Ɋ����B�o���I�X���݂邵�̕��Ȃ�A������͂������߃I�[�_�[���C�h�i�Ƃ�����o���f���ł��B���ڑS�̂ŃO���b�v���₷���ł��B �@�t���J�E���䂦�������s���y�B�X�s�[�h�����R�����̂ŁA���x���߂ɗv���Ӂi�Z���H�j�B |
| �@ | �@ |
| �@�Z�� | �@�G���W�������܂�O�H�_���_���������Ē�܂�ƁA�G���W�����~�܂肻���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�A�N�Z����������Α��v�ł����B �@���[�X�y�[�X�̂Ȃ��B�V�[�g���́A�ԍڍH��Ƃt�����b�N�̂ݎ��[�B���ƃc�[�����O�l�b�g�����肬����߂��܂��B �@�ᑬ�g���N���v���������Ȃ��B���Ƃ��ƍ���]�^�G���W��������S�O�O�����Ȃ��̂ł́A�Ǝv������Ȃ��B �@�N���b�`�̂Ȃ��肪�킩��ɂ����B��L�ᑬ�g���N�Ƒ��܂��āA���t�^�[���̂Ƃ��A�G���X�g�E�����S�P���Ă��܂��܂����B ��̓I�Ɍ����ƁA�o���I�X�ł́A�G���W�������A�q���[���A�O���b�O���b(�G���X�g���O)�J�^�b�i��~�I�j�ƁA���m�������̂ł����A�b�a�q�́A�q���[���A(�`�N���b�`�Ȃ�)�J�^�b�i��~�I�j�ƁA�G���X�g���O�܂Ŋ��炩�ɉ���Ă��邽�߁A�ˑR�~�܂��ۂł��B���܂肤�܂��\���ł��܂��B |
�@
| �����_ | |
| �t���[���X���C�_�[ | �������L�̃t���[���X���C�_�[�����܂����B |
| �^���N��p�b�h | ���̃^���N�p�b�h�B��p�i�ł��B |
| �^���N��p�b�h2 | �z�[���h���₷���悤�A�^���N�p�b�h�lj����܂����B |
| ���g��C�[�W�[ | �m��l���m��A�n�����p�w�b�h���C�g�����p�[�c�B |
| �w�b�h���C�g�����[���A�[�V���O | ���C�g�𖾂邭���邽�߂̃����[�ƁA�A�[�V���O���s���܂����B |
| �o�b�N�X�e�b�v | ���A���o�����X���X�e�b�v�Ɍ������܂����B |
| �G�A�N���[�i�[ | �j���m�̏������v���C�X�^�t�B���^�[�B����čĎg�p�ł��A�p���[���A�b�v����I |
| �I�C���t�B���^�@ | Vesrah�i�^�J���j�̃I�C���t�B���^�[�B�Ή��N���ɂ������ȈႢ����B |
| �o�b�e���[ | ����������łȂ����i�i���R�A�����j���g���Ă���Ƃ����Ӗ��ŁB |
| �`�^���R�[�e�B���O���H | �t�����g�t�H�[�N�̃C���i�[�`���[�u�ɁA�R�[�e�B���O���s���܂����B |
| �C���V�����[�^�[���H | �����d�l�ł͔����ǂ���Ă���z�C�����A�t���p���[�d�l�Ɠ����ɉ��H���܂����B |
| �X���b�v�I���}�t���[ | LeoVince(���I�r���`)�̃X���b�v�I���}�t���[�����܂����B |
| �����t�F���_�[ | �}�W�J�����[�V���O�������t�F���_�[�����܂����B |
�@
| �����e�i���X | |
| �u���[�L���| | �Ǘ��l�͔��N�ɂ����炢��������ĂȂ��ł��B |
| �u���[�L�p�b�h���� | �x�X���̃p�b�h���g���Ă݂܂����B |
| �t�H�[�N�I�C������ | �t�����g�t�H�[�N�I�C�����������܂����B�W���b�L��������A���Ɗy�ł��B |
| �G���W���I�C������ | �I�C�������ύX�̂��߁A�t���b�V���O���܂����i�I�C���̓��g���b�N�X���g�p�j�B |
| �y�_���ސ��| | ���\�t�B�[�����O���ς��g�R���ł��B�܂߂ɂ�����������������B |
| �N���b�`���C���[���� | ��{���̊�{�B�F����A����Ă܂����`�H(�Ǘ��l�͑O�����Y�ꂽ���ɂ���Ă���.....) |
| �X�p�[�N�v���O���� | �J�E���t�ԗ��ł͂�肽���Ȃ���Ƃ̂ЂƂB�T�[�r�X�}�j���A���Ƃ͈Ⴄ�菇�ŁB |
�@
�@
�������_�@�@
| �@�t���[���X���C�_�[ | �@  �@ �@ �@�@�@���Â炢���Ǒ�������ƁA����Ȋ����ł��B �@�@�@�@�@�@�E���͋C�x�߂ɂ��Ȃ�Ȃ��ł��� |
| �@�ǂ̃��[�J�[�̂ł��ǂ������̂ł�����X���ɂ������������L���Ɍ���BNAPS���c�J�X�ɂ�\5,840�i���B�b�a�q�U�O�O�e�p�̂��͎̂�t�{���g�̊W����A�ǂ���J�E���Ɍ����J����K�v������܂��B�����̂Ƃ���A�X���C�_�[�{�͍̂��E��Ώ́B�����ۂ��S�{���g���t�����Ă��܂��B�����͓������������Ă���̂�.....�B �ԑ̂ւ̎�t �@�܂��g���N�����`�A12mm�\�P�b�g��p�ӂ��܂��B�K��g���N��4.0Kg/m�B���ߕt���邾���A���r�߂Ă������Ă��܂������A�E�����t���I����A������t���悤�Ƃ��āA�t���̃{���g����߂���ł����ƁA�K��g���N�ɒB����O�ɁA�u�o�V���b�I�v�Ɛ���ȉ������āA�G���W�����̎��˂����ꕔ�ӂ��U��܂����B�i���j �@�t���̃{���g�ł͔������炢�������l�W�ɂ������Ă��Ȃ��悤�ŁA����ɃX���C�_�[�{�́i��������)���ԑ̂ɐڂ��Ă��邽�߁A�g���N�����`������ɍ쓮���Ȃ������̂��H �{���g�i�S)VS�G���W���i�A���~)�ŁA���R�G���W���������������......�B��]�p�Ńg���N�Ǘ����������ǂ������ł��B �@�d�����Ȃ��̂ŁA�ʓr�����X�e�����X�{���g�B���āA�ꉞ���t���I���B �J�E�����H �@�T�[�N���J�b�^�[�ȂǂȂ��̂ŁA�n���Ɍ����J���܂��B�v���X�`�b�N�p�J�b�^�[(�o�J�b�^�[�j�A�f�U�C���i�C�t�A�ϐ��y�[�p�[(���₷��)�A�y���`��p�ӂ��܂����B �@�܂��J�E���ɏ����߂Ɍ��̖ڈ��t���A�o�J�b�^�[�ʼn~�`�̍a��܂��B�a����y���`�Ő܂���Ɗy�ł��B��܂��Ɍ����������礂��Ƃ͎ԑ̂Ɏ��t�����X���C�_�[�ƌ������킹�ō��܂��B�ׂ�����荞�݂̓f�U�C���i�C�t�ōs���A�ŏI�I�Ȍ`�Ɏd�オ������ϐ��y�[�p�[�Ŗ����ƁA�ʐ^�̂悤�Ȏd�オ��ɂȂ�܂��B �@�Ȃ��A�J�E�����O���Ă݂�ƁA����Ȋ����ł��B |
�@
�@
�@�^���N�p�b�h |
 |
| �@N-PROJECT���J�[�{���^���N�V�[���h�i���iNo.00613/�^���N�p�b�h�j�ł��B�����͕t���̗��ʃX�|���W�e�[�v�œ\��t���邾���ł��B���ʃe�[�v�̌��ݕ������������Ԃ��J���܂��B��p�i�Ȃ̂ł������ɂ҂�����ł��B�����ɂ����ł����A�^���Ƀ��f�����̂́u�b�a�q�v�̕������A���[���h����Ă��܂��B �@���������O�ɁAJTC���P�s�[�X�v���e�N�V�����p�b�h(���iNo.7722 �A���}�C�g�J���[/��)���g�����Ƃ����̂ł����A�g�߂ď_��ɂ��ē\��t���Ă��A���炭����ƕ����オ���Ă��܂��A���ǎg�p�o���܂���ł����B���S�ɓ\��t����^�C�v�͕������łȂ��ƁA�^���N�̊ۂ݂ɍ���Ȃ��悤�ł��B |
|
�@
�@
| ����X�|���W�^���N�p�b�h �@�d���X�|���W�̃^���N�p�b�h�����܂����B���ʂ̃j�[�O���b�v�����ł��B���x���̍������쐫��Nj�����ƁA���Ȃ�傫�Ȃ��̂����Ȃ��Ƒʖڂł��傤���A���C�y�����e�炵�����h���Ȃ�Ȃ����x�ɁA�E�B���O�}�[�N�ɍ��킹�Ă��Ă݂܂����B����Ȃ�m�[�}�����ۂ��Ėڗ����Ȃ��ł��傤(�ʐ^)�B �@�܂��K���Ȏ��Ō^�������A����ɍ��킹�čd���X�|���W�i�d���Ƃ����Ă����Ȃ�_�炩���j���o���܂����B���ɔS���܂����Ă���^�C�v���Ƃ��̂܂ܓ\��Ċy�ł����A���̑傫���ł͋ߏ��̃z�[���Z���^�[�̍ɂɂ͂���܂���ł����B�g�p�����̂͌����Tmm�A�S���ނȂ��̃^�C�v�Ȃ̂ŁA300�~300mm�Ł��Q�V�O�ƁA���Ȃ�����ł��B���ʃe�[�v��S�ʂɒ���i����Ȋ����j�A�^���N�ɓ\��܂��B�_�炩�߂Ȃ̂őϋv���͂ǂ����H �@������ �@����̂悤�ɏ������ʐςł�邾���ł����Ȃ���ʂ���B�X���ł��������ق�����Ɋy�`���ł��B���Ƃ��キ�Ă��j�[�O���b�v�������Ă���A�^���N�����ւ̂��艺���肪�����Ȃ�A�����g�����肷��̂Ŏ��삪�Ԃ�Ȃ��ł��B�����A�^���N���ʁi�������j���ׂĂ��Ă��܂����������Ă��܂������A�Ǘ��l�͂Ƃ肠�������ꂾ���ő��v�����ł��B �@���Ȃ݂ɂ��̓V�R�S���͑ό͂��܂�Ȃ������ł��B���݁A�����P�N�ŁA�\�ʂ�������ƁA�ۂ�ۂ덕�����ɂȂ��Ă��銴���ł��B���S�ɕ����킯�ł͂Ȃ��ł����A�F�̔����Y�{���ł́A�j�[�O���b�v�̐Ղ��c���Ă��܂��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2009. 2 �NjL�j |
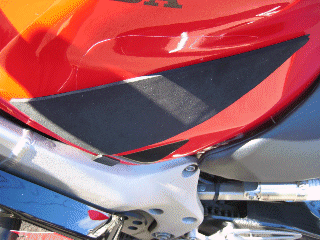 �X�|���W�S����\�����Ƃ���B���Ƃ��Ƃ̃E�B���O�}�[�N�̌` �����F�Ȃ̂ŁA��a���[���B�ł����ʂ͂��Ȃ�̂��̂ł��B |
�@
�@
| �@���g��C�[�W�[ | 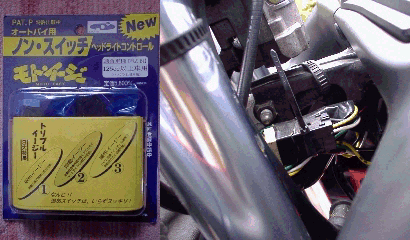 �@�@ �@�@ |
| �@�l���g�E�j���[�������g��C�[�W�[�ł��B�G���W���n�����̃o�b�e���[�̕��S���y�����邽�߂̑����ł��B �@�펞�_�����̎Ԏ�Ɏ��t���āA�G���W���n�����ɂ̓w�b�h���C�g�����������܂܂ŁA��������n�C�r�[���Ɂior�p�b�V���O�j����Ɠ_������Ƃ������̂ł��B�ď����������Ƃ��́A�Z���X�C�b�`���Z�������Ȃ����x�ɉ��������i�Ԏ�ɂ��Ⴂ�܂��B���}�n�A�z���_�̈ꕔ�͕ʓr���i���w������K�v����B�v���X�����Ƃ������́j�B �@���t���͊ȒP�Ť�w�b�h���C�g�o���u�̂Ƃ���̃\�P�b�g�ɁA���g��C�[�W�[�̃\�P�b�g�����܂��邾���ł��B�J�E�����O���K�v������܂���B�{�̂͌��\�傫���̂Ť�J�E���X�e�[�Ȃǂɂ�������Œ肵�܂��傤�B���͎ʐ^�E�̂悤�Ɂu�́v�̎��^�ɔz�����܂Ƃ߂āA�^�C���b�v�ŃJ�E���X�e�C�ɌŒ肵�Ă��܂��B ���݁A�����[���̏Ⴕ�����ߓ��삵�Ȃ��Ȃ����̂ŁA�O���܂����B�g�p�p�x�͂���قǂł��Ȃ������̂ł����A�c�O�B |
|
�@
�@
�@�w�b�h���C�g�����[���A�[�V���O |
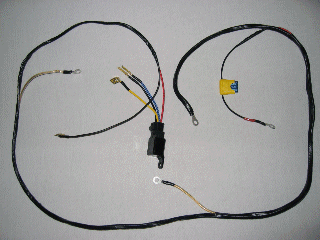 �@�����[�z���̓X�p�[�_�Ɠ����\���B �@�����ƍ�������o�Ă���ے[�q�� �@�A�[�X���B 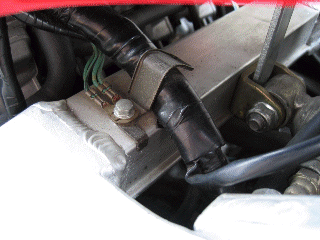 �@�^���N���̏����A�[�X�|�C���g |
�w�b�h���C�g�����[ �@CBR�̓m�[�}���ł̓}���`���t���N�^�[�Ȃ̂ɈӊO�ɈÂ��̂ł��B���R�Ƃ��Ă͌����g�U���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�����𖾂邭���Ă��̂��ł������葁���ł��ˁB�g�h�c�������ł����ʓI�ł����A�����̖�Ԃ𑖂�p�x�ƃR�X�g�Ƃ��l���A�����[�����ɂ��܂��B��p���郍�[�������A�o�b�e���[���璼�ɔz�������A�w�b�h���C�g�𖾂邭����̂ł��B �@�z���̂Ƃ�܂Ƃ߂Ȃǂ͊��Ɏ{�H�������̂Ɠ����Ȃ̂ŁA�p�ӂ��镔�i�̓X�p�[�_�̃y�[�W�i�������j���Q�Ƃ��������B �A�[�V���O �@CBR600F�̃T�[�r�X�}�j���A���z���}������ƁA�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�ɒ��ڌq����z���͂���܂���B�Ȃ̂ŁA�A�[�V���O�̌��ʂ͊��҂ł������ł��B�G���W�����M�ʂ������̂ŁA�t���[�����̂��G���Ă����Ȃ��قǔM���Ȃ�܂��B���x���オ��Ƌ����̓d�C��R�͑�����͂��Ȃ̂ŁA���̓_������A�����ʂ�����̂ł͂Ȃ����Ɓi���`�x�[�V�����ێ��̂��߂̊�]�I�ϑ��Ƃ�����ł��j�B �@�����̃A�[�X�|�C���g�́A���W�G�[�^�[�e�ƁA�㑤�̃����T�X�y���V�����x�����t��(�^���N��)�̂Q�ӏ��B�܂��A��������o�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�ւ����ɔz�����s���܂��B�����n�[�l�X�̗ΐF�̔z�����Ȃ����Ă���̂ŁA�����킩��܂��B �@��q�̒ʂ肩�Ȃ�̔��M�ʂȂ̂ŁA�z���̎��ɂ͋C�������܂��B��{�I�ɏ����n�[�l�X�ɉ��킹�Ă��n�j�ł����A�G���W���͂������A�����M���Ȃ�t���[���ɂ��ڐG������̂́A�D�܂����Ȃ��ł��傤�B�^�C���b�v���g�p���ď����z���ƕ��ׂĎ��܂��B���ɁA�G�A�N���[�i�[�ƃt���[���̊Ԃɒʂ������̓��C���n�[�l�X���������Ȃ��Ă���A���炭���ނ��f�M�ނɕ�܂�Ă���Ǝv���܂��B�����̔z���́A���ɒ��ӂ��ď����z���ƈ�̉������i�҂����艈�킹�j�܂����B �@�z�����̂́A�X�p�[�_�p�ɍ�������̂Ɠ��l�A�w�b�h���C�g(���[��)�����z�������[�ƁA�A�[�V���O�z�����T�u�n�[�l�X�Ƃ��Ĉ�̉����܂����i�ʐ^�j�B�E���̉��F�����m���q���[�Y�ŁA�o�b�e���[�̃v���X�ւȂ��A�����Ȃ��ے[�q�����}�C�i�X�ւȂ���܂��B �A�[�V���O �@���ʂ́A���^CBR(�L���u�ԂƂ�������)�ɃA�[�V���O���āu���]���͋����Ȃ����v�Ə�����Ă���g�o���������̂ŁA���ȁ`����҂����̂ł����A�݂��Ǘ��l�ɂ͕ω��͊������܂���ł����B�܂���������Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�킩��Â炢���낤�Ǝv���Ă����̂ł����B�w�b�h���C�g�ɂ��ẮA���喳�����邭�Ȃ����̂ŁA�ꉞ�ǂ��Ƃ��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2007. 9�j |
|
�@
�@
| �@�o�b�N�X�e�b�v | |||
�@���A���o�����X���o�b�N�X�e�b�v�ł��B�艿\19,950�ł������Õi���i���œ���B�����������������̂ŁA���[�J�[�ɖ₢���킹��ƃp�[�c���i�Ǝ��t�����@���L�ڂ����o�c�e�t�@�C���𑗂��Ă���܂����B�e�ł��B �@���̃��[�J�[���i�̓����́A�����V�t�g�E�u���[�L�y�_�����g�p����`�ԂŁA�R�X�g�������Ă���_�ł��B �d�グ�ɍ������͂���܂��A���Ђ��f�R���[�R�X�g�A�|�W�V�����͌Œ�ł��B |
�@ 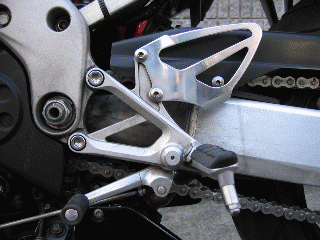 �@�m�[�}���X�e�b�v�̃|�W�V�����B����͂���ŗǂ��̂ł���.....�B |
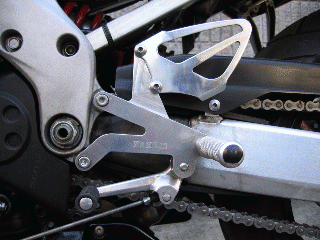 �@�o�b�N�X�e�b�v�̃|�W�V�����B�X�C���O�A�[���Ƃ̈ʒu�W �@�ŁA��オ���Ă���|�W�V�����ł��邱�Ƃ��킩��܂��B |
|
| �@CBR600F(99�`)�p�̃X�e�b�v�́A3cm�A�b�v�̌Œ�|�W�V�����Ȃ̂ŁA���m�ɂ̓A�b�v�X�e�b�v���Ă��Ƃł��傤���B����͎ʐ^�̂悤�Ƀ��[���b�g���H���ꂽ�Œ莮�X�e�b�v�Ȃ̂ŁA�����̉|���X�e�b�v�̂悤�ɁA�J�^�J�^���Ȃ��̂��ǂ��ł��B���ݕς��̂Ƃ����S�O��������܂��B �@���ۂɑ����������́A�܂��O�X��������������悤�ɂȂ�܂��B���̋C�ɂȂ��đ���Ƃ��ȊO�́A������Ƃ����Ȃ�܂���(�� ����܂���)�B���ł�������z�[���h����Ƃ��ɂ́A�Œ莮�̂��߈��S��������A�Ǘ��l�̐g��(170cm)�ł̓X�e�b�v�ʒu���▭�ɗǂ������ł��B �@�l�K�e�B�u�ʂ́A�V�t�g���o�[���ɃJ���[����܂��Ă���W���炩�A�V�t�g�t�B�[�����킩��Â炭�Ȃ������ƁB�Ǘ��l�̏����ł͗\�����Ȃ��Ƃ��Ƀj���[�g�����ɓ����Ă��܂����Ƃ�����܂����B�B�B�ƁA�����Ă����̂��S���������̂ł����A������A���̂܂�葱���Ă�����A��L�Ǐ�͖����Ȃ�܂����B�������肵�܂��A�P�Ɋ���̖�肾�����悤�ł�......�B�i2005. 9�j |
|||
�@
�@
| �@�G�A�N���[�i�[ | ||
| �@��Ԃ̂j���m�t�B���^�[�i�����`��j�ł��B�����i�ƈႢ�A����čĎg�p�ł��܂��B �@�v���g�̃J�^���O�ɂ��ƁA�艿�x�[�X��99-00�N��(�L���u���^�[��)����\12,000�A���̔N����\8,500�ʁB���̂��߁A�������������Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�I�I�������ʂ̓v���g�ƃA�N�e�B�u�ň���������(���ɂ����邩��)�悤�ŁA�S�������i���A�N�e�B�u��\8,500�ʂ������̂ŁA�A�N�e�B�u�ɒ����B�X������ɂ��ƁA���i���肪�������̂ɁA�v���g�̃J�^���O���X�V����Ă��Ȃ��̂ł́H�Ƃ������Ƃł����B���ۂɂ̓Z�[�����i�̖�\6,300�ōw���B �@�ׂ��������ƃL���v�Z�b�e�B���O���K�v�����m��܂��A�Ƃ肠�����|���t���Łi���͍����m�[�}���d�l�̂܂܁j�g���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B ���t�� �@�܂�5mm�w�b�N�X�����`�A8mm�\�P�b�g�A�{�Q�h���C�o�[��p�ӂ��܂��B�_�N�g�J�o�[�̃w�b�N�X�{���g���O���A�J�o�[������ă^���N�O����8mm�{���g���O���܂��B�S���u�b�V����̊ۍ����A�����̋����u�b�V���̒E���ɒ��ӂ��܂��B��͎Ԃ̎戵�������ɂ���悤�ɁA�ԍڍH���27mm���K�l���x���Ƃ��ă^���N�������グ��A�G�A�N���[�i�[�{�b�N�X�ɓ��B�ł��܂��B �@�G�A�N���[�i�[�����ƁA�T�u�G�������g�̋�C��������������܂��B�v���X�l�W�Q�{���O���A�T�u�G�������g�̌������o���܂��B�G�A�_�N�g���͂��Ȃ艘��Ă��锤�Ȃ̂ŁA��C�ł��݂����Ă���̕��������Ǝv���܂��B�Ǘ��l�͏��^�|���@�����Ă��ꂢ�ɂ��܂���.....�B �@�|�����ς���t���ł��B�Б��������̖Ԃŕ����Ă��鍑�������i�ƈ���āAK&N�͗��ʂ��J���Ă��āA�悭��C���ʂ肻���ł��BCBR600F�p�̂́A�H��o���ɃI�C�����h�z���Ă���A�\���͂킩��Â炢�ł����A�ӂ��� THIS SIDE UP �Ƃ������Ă���܂����BK&N�V�i�́A���������r�~���[�Ɍ��݂�����悤�ŁA���̂܂܂ł̓G�A�N���[�i�[�{�b�N�X�̂ӂ����A��������܂�܂���ł����B�ӂ����ϓ��ɉ��������Ȃ���A�Ίp����̃r�X�����X�ɒ��ߕt���Ă������t���I���B ���� �@�܂��ߏ���������Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ŁA���܂�Ⴂ�͂킩��Ȃ��ł��B�킴�ƒᑬ�ŃV�t�g�A�b�v���Ă݂�ƁA�ȑO���A�N�Z���ɂ��Ă��銴���͂��܂��B�����ƍ���]�ō����o�Ă���̂ł��傤�B������������......�B(2005. 9) |
 �@�@CBR600F(99-00)�p�́A�i��HA-6099 �ł��B �@�@�@�ʐ^�̂悤�Ƀt�B���^�{�́A���[�U�[�o�^�A �@�@�@���̃t�B���^�[�͎̂Ă�ȁI�̃X�e�b�J�[�AK&N�}�[�N �@�@�@�̃X�e�b�J�[�B �@�@�@�@�g�p���@�̐����͂������肵�Ă��Ė��h�����ʂ��� �@�@�@�Ȃ������i���܂��ɓ��{��\�L�͂�����Ă�j�����ɁA �@�@�@���[�U�[�o�^�̎���ׂ̍������ƁI�E�ƂŁu�R���v �@�@�@�̑I����������Ƃ��낪�A�A�����J�����������܂��B |
|
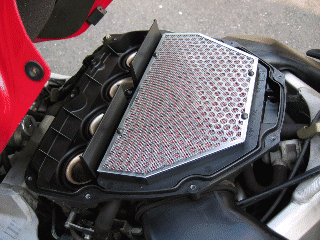 �@�@�@�����t�B���^�B���邩��ɋz�C��R�ɂȂ肻���� �@�@�@�@ �������t���Ă܂��B���ꂪ�g���̂ĂȂ�ł� �@�@�@�@ ����A�ܑ̖����B |
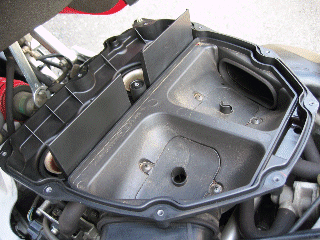 �@�@�@�@�|���O�B�ꌩ���ꂢ�ł����A�ׂ��������̂悤�� �@�@�@�@�@���݂��C�b�p�C�ł��B��̏�ԂŃT�u�G�������g�� �@�@�@�@�@�W���J������A���ɂ��݂������ďł���.......�B |
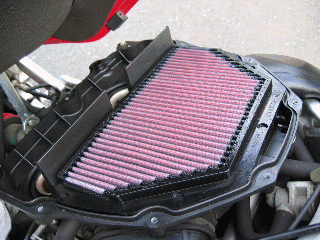 �@�@�@K&N������B���\�A�I�C���ׂ�����ł��B�����ς� �@�@�@ ��C���z���Ă��ꂻ���ł��B���ƁA�����́u�̂Ă�ȁI�v �@�@�@ �X�e�b�J�[���G�A�N���{�b�N�X�ɓ\��܂����B |
�@
�@
�@�I�C���t�B���^ |
 |
| �@Vesrah���I�C���t�B���^�ł��B�K���͂Ƃ����ƁA �@�x�X���i��SF-4005 �� CBR600F�i97�`00�j�����d�l�ASF-4007 �� CBR600F4i(01�`)�ƂȂ��Ă��܂��B �@SF-4005�̕��������A�d�ʂ�230g���ASF-4007��180g���ł����B�܂�F4i�p���g�p����Όy�ʉ��ł��܂��B�B�Ƃ����Ă����[�^�[�T�C�N���ł͂��܂�Ӗ����Ȃ��ł����A�y�ʉ��t�F�`�̕��͂���Ă݂Ă����������B�Ǘ��l��SF-4007���Ԉ���čw���������ߓ��g�p���Ă��܂����A�����œ��i�g���u���͔������Ă���܂���B�T�[�L�b�g�Ƃ��ŋ���Ȏg�����������肷��킩��܂���ǁB �@�Ȃ��ACBR�p�ł͂Ȃ��ł����A�X�p�[�_�ȂǃS���p�b�L�����K�v�Ȃ��̂́AVesrah�Ȃǒʏ�̃t�B���^�ł͕ʔ���ł����A���j�I���Y�Ƃ̃t�B���^�͒l�i�������A�p�b�L���t���Ȃ̂ł��C�ɓ���ł��B���j�I���Y�Ƃ̌^�Ԃ́ACBR600F(99�`00)�p��MC-560�AVT250SPADA�p��MO-512�ł����B |
|
�@
�@
�@�o�b�e���[ |
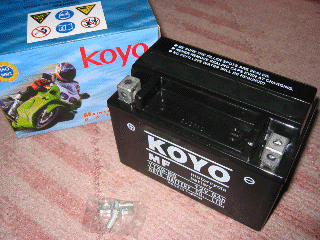 |
| �@KOYO���o�b�e���[(YTX-9BS)�ł��B�ʔ̂ōw���B �@���܂����܂��g���Ă����o�b�e���[���A���ɂ��S���Ȃ�Ȃ�܂����B��[�d���Ă��A�a�ؘH���������邾���ōĎn���s�\�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����Ńo�b�e���[���������邱�Ƃɂ����̂ł����A���K�i�͂ƂĂ��Ȃ��l�オ�肵�Ă���̂ŁA�����Ȑ��i��T���Ă݂܂����B �@������(Made in China)�͑ʖځA��p���͐M���ł������Ȃ̂ŁAKOYO�o�b�e���[�̂��̂�I�т܂����B���̃��[�J�[�́A���{�̃o�b�e���[���[�J�[���Z�p�w�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�s�Ǖi�������{���Ɠ����x�̂悤�ł��B�p�b�P�[�W���Ȃ��Ȃ��C�������Ă܂��B �@�������A���̎ʐ^�̂悤�Ƀo�b�e���[�^�[�~�i���̌`���A�Œ�i�b�g�������甲����悤�ɂȂ��Ă���A���{���̂悤�Ƀi�b�g�̗����h�~��(�Ƃ������ˋN)������܂���B���̂�����͊����x���Ⴂ�Ƃ������A���߂ȂƂ���ł����A�����Ђ�܂�Ȃ��������̂悤�Ȓ������ƈ���Ă������肵�Ă��邵�A�p�ɂɎ��O�������Ȃ��̂Œ��߂悤�Ǝv���܂��B �@�͂͂�����Ȃ��̂ŁA�����̓n�[�l�X�e�[�v��������̂�A�����h�~�Ƃ��܂����B �@�V�i���i�ł��̂ŁA���R�̂��Ƃ��A�����ł��B��]�����C�ɂȂ����C�����܂��B���Ƃ͂ǂꂾ�������Ă���邩�H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2008. 5) |
|
�@
�@
�@�`�^���R�[�e�B���O���H |
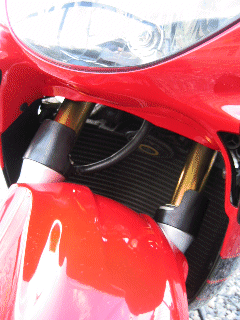 |
�@�����m�d���Ɉ˗����āA�C���i�[�`���[�u�̃C�I���v���[�e�B���O���H�����Ă݂܂����B������`�^���R�[�e�B���O�Ƃ�����ł��B�t�H�[�N�����C���i�[�P�̂ɂ��đ���A�l������t���Ă���܂��B ����Ń��[�N�X�`�[�����݂̓����̃t�H�[�N.....�͖����ɂ��Ă��A�ŐV�^�ɂ́i�C���I�Ɂj�����Ȃ��t�H�[�N�ɂȂ�܂����B �@�ŁA����Ԃ���Ă����C���i�[������Ȋ����B�V�[���ނƎC��Ȃ����́A�R�[�e�B���O���Ă���܂���B�����A�S�̂��グ�Ă���炵���A�ʐ^�Ō�����f�荞�݂����炵���ǂ��Ȃ��Ă��܂����B�܂��A���������t�H�[�N��g��ł���Ƃ���܂ł́A�����A���ׂ肪�������ȁH�ʂł������A���ۂɑ��点�Ă݂�ƁA�������������ǂ��Ȃ��Ă��銴���ł��B �@���i�ʂ铹�ŁA�W�O�������炢�Łu�S���v�Ƃ����Ռ��̗���r�ꂽ�H�ʂ�����̂ł����A�R�[�e�B���O��͂��܂艚�ʂ��ӎ����Ȃ��ł�����l�ɂȂ�܂����B���ʂ�����̂͂킩��̂ł����A�s���ȗ���A�Ռ������قƂ�ǂ���܂���B����ȂɎ����ł��������邭�炢�ɕς��Ƃ͑S���v���Ă��Ȃ������̂ŁA�z���ȏ�̕ω��ł��B �@�I�[�o�[�z�[���ɔ����I�C������ւ��ƁA�v���V�[�{�����������Ă��A���Ȃ�̍�������܂��B�Ǘ��l�ɂ͂������������r�͂Ȃ��ɂ��Ă��A���Ȃ��Ƃ����S�n�͒f�R�A�b�v���Ă���̂ŁA���i�g���̂u�s�ɂ��A���H�������Ȃ��Ă��܂��܂����B�o����Α�����肽���B�B�B���̓R�X�g�ł��B��{�����聏�Q�Q,�O�O�O�i2008.9���݁j�B�������Ǘ��l�ɂƂ��ẮA�l�i�������̉��l�͂���܂����B �@�G���W���̓p���[�A�b�v���Ă��g���ꏊ�����Ȃ�����܂��B�ł��T�X�y���V�����̃O���[�h�A�b�v�͑����Ă���Ԓ��A�����Ƃ��̉��b�ɗ^��܂��B�V���b�v��ʂ��ƌ��\�ȋ��z�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�t�H�[�N���ł�����ɂ���l�́A������ׂ��ƒf�����܂��B���̂��炢�X�S�C�ω��ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2009. 2�j |
|
�@
�@
| �C���V�����[�^���H�@ | ||
| �@CBR600F�͍��������ł́A�L���u�E�G���W���Ԃ̃C���V�����[�^���������炢�ǂ��ł���A�p���[�𗎂Ƃ���Ă��܂��B�L���u���O���@����������łɁA���H���Ă݂܂����B �@�t���p���[���ɂ��ẮA���ɑ����̔}�̂ł��Љ��Ă��܂����A�ύX����_�� �@�@�@�C���V�����[�^�̃A���~�P�� �@�@�A��ԁE�O�Ԃ̃��C���W�F�b�g�Ԏ��ύX�i132��135�ցj �@�@�B�}�t���[��A�o�d�l�֕ύX �@�@�C�C�O�i�C�^�[��A�o�d�l�֕ύX�i���邢�̓m�[�}���̂܂܁A�z�������H�j �@�@�D���[�^�[���C�O�d�l�ɕύX �@�@�E�h���u���X�v���P�b�g�y�у`�F�[����ύX �@�ȏ���s���ƁA���S�ȃt���p���[�ɂȂ�悤�ł��B�����Ɍ����ƊC�O�d�l�̓J���V���t�g������čX�Ƀp���t���炵���ł����A�Ǘ��l�͂����܂ŗv��Ȃ��B �@���ۂɃp���[���o���͇̂@�`�B�ŁA�C�͑��x���~�b�^�[�����A�D�E�̓��[�^�[�덷�ɊW���Ă���悤�ł��B�Ƃ肠��������s�����͇̂@�A�ł��B �@�L���u���^�[���O���菇�́A��p�������^���N��G�A�N���{�b�N�X���O�����C���V�����[�^�[���ɂ߁A�L���u�����遨���C���[��n�[�l�X�ނ��O���A�̏��Ŏ��O���܂��B ���������� �@�܂����E�̃A���_�[�J�E�����O���Ă����܂��B��p���́A�ԑ̍����A�|���v�̏��̃{���g���ɂ߂�Ɣr�o�ł��܂��B���W�G�[�^�[�L���b�v���ɂ߂�ƁA�����悭�r�o����܂��B �@�^���N��G�A�N���{�b�N�X�ɂ��ẮA�X�p�[�N�v���O�����̍����Q�Ƃ��������B �@�C���V�����[�^�[�o���h���ɂ߂�̂ł����A���`���v���X�h���C�o���K�v�ł��B�莝���̃V�����N��200mm�̂��̂ł͒��������肸�A�V����450mm���w�����܂����B���������Z���̂��W���X�g�t�B�b�g���Ǝv���܂����A�X���ɂ��ꂵ���ɂ����������̂ŁB�J�E���X�e�[�t�߂̃t���[���ɑȉ~�̌����J���Ă��܂����A��������h���C�o�[���������݁A�o���h�X�N�����[���ɂ߂܂��B�����Q�C���̂��A�p�x�������Ă��Ȃ������ŁA�Ȃ߂₷���̂Œ��ӂ��K�v�B �@�L���u���O���ۂɂ́A�G���W�����C���V�����[�^�[�o���h���ɂ߂Ă���̂��m�F���Ă���A�L���u�S�̂����E�ɗh����悤�Ȋ����Ŏ����グ��ƊO��܂��B�Ǘ��l�͎ԑ̂Ɍׂ���܂����B�C���V�����[�^�[���L���u����O���ۂ́A�C���V�����[�^�[�o���h�i�L���u���j�̃l�W�����O���A�o���h���C���V�����[�^�[�̍a����O������ŁA�Ƃߍ��킹�̏���ό`������ƊO���܂��B�o���h���Œ�ʒu�̂܂܂��Əo���Ȃ��Ǝv���܂��B �@���Ƃ̓X���b�g���Z���T�[�̃J�v���[��A�`���[�N�E�X���b�g���P�[�u���A�Y�ꂪ���ȃX���b�g���X�g�b�v�X�N�����̌Œ�����O���܂��B�L���u��둤�̃`���[�u�́A�����s���^�łQ�ӏ��Őڑ�����Ă���̂��K�\�����`���[�u�A���̉��ɂ��鏭���ׂ߂̃`���[�u�ŁA�O����{���L���u�̊O�ցA������{���L���u�ɘA������Ă�����̂���p���z�[�X�ł��B���ꂼ��O���܂��B�K�\�����`���[�u�́A�����ӂ������̂�p�ӂ��Ă������ق����ǂ��ł��B�҂�����̃i�b�g���������̂ŁA���b�V���A�{���g�𝀂�����œ˂����݂܂����B �@�P�̂ɂȂ�Ίe�t���[�g���̃K�\�������̂��y�ł��B���Ȃ�ł����܂��Ă���̂ŁA�v���X�l�W���Ȃ߂Ȃ��悤���ӂ��A�^�Q�C�����̃t���[�g�`�����o���J���A�}�C�i�X�h���C�o�Ń��C���W�F�b�g���O������ւ��܂��B �@���C���W�F�b�g��NAPS�ɂ�\210�^�ōw���B�l�W�̓��ɓ��镔���̊O�����A�V�ӂɔԎ肪����Ă��܂��B��������͂��ꂼ�ꍏ��ʒu���Ⴂ�A���\�ɂ͉e���Ȃ��Ă��s�����łȂ����Ȋ����B ���H�� �@�ő�̎R��E�C���V�����[�^�[���H�̂��߂ɁA�h�������̃����[�^�[�i�}���`�v���j�����܂����B���H���Ȃ��ꍇ�A�A�o�d�l�C���V�����[�^�[���w�����邱�Ƃ�A�����[�^�[�ɑ��ɂ��g���ł����邱�Ƃ��l����A����قǒɂ��o��ł͂���܂���B29�_�̐�[�r�b�g�ނ��t�����āA�艿\18,000�ʂł��B�C���V�����[�^�[�̎Օ��ł͏������܂��Ă���̂ō��ɂ����ł����A�������Ɖ��H���ς܂��Ė߂��܂��B �@�t���p���[�����s���ƁA��͂�Z�b�e�B���O��ύX���Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ł��B�C���V�����[�^�[���H�E�j���m�t�B���^�������}�t���[���Ƃ�����A���܂��Ă���ƁA�G���W�������܋ꂵ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ǂ��������i�Ă����H�j����̂悤�Ȃ̂ŁA�X���[�n��Z�����Ă݂܂����B �@��̓I�ɂ͍����m�[�}���́A�p�C���b�g�X�N�����[���A�P�E7/8��]�߂����W���ł����A�A�o�d�l�͂R��]�߂��ł��B�A�o�d�l���Q�l�ɁA�߂���]�������킹�Ă݂�ƁA��L�̏Ǐ�͏����܂����B�����ɂ̓W�F�b�g���ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ���������Ȃ��̂ł����A�ꉞ�A���ʂɑ����̂ł���łn�j�Ƃ��܂����B ��ƌ��� �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2005.11) |
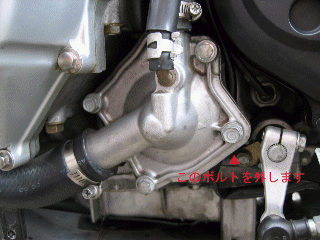 �@��p���̓|���v�̌�둤�Ɉʒu����{���g ���Ɣr�o�ł��܂��B���W�G�[�^�[�L���b�v ���O���Ă����܂��B 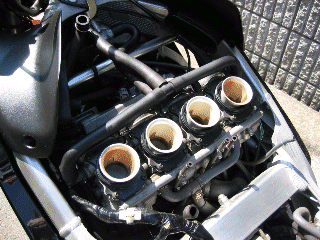 �@���̐����Ŕ���Â炢�z�[�X�ނ̐������� �����݂܂����B�N���b�N����ƊJ���܂��B 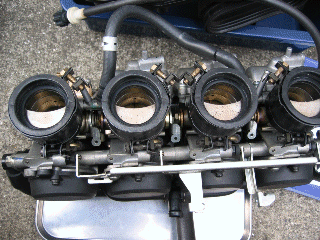 �@�L���u����O�����K�\�����`���[�u�͂��̂� �܂��Ɛ����̂ŁA�i�b�g�𝀂����{���g �ŊW�����Ă����܂����B  �@���������m�[�}����ԁA�E�����H��B���� �[�^�[�ō��܂����B�����d�l�͔������炢 �i���Ă���̂��킩��܂��B |
|
�@
�@
�@�X���b�v�I���}�t���[ |
 �@�p�b�P�[�W�ƃT�C�����T�[�ꎮ�B�X �v�����O�p�t�b�N(�H��)�����Ă܂��B ���B���S�̓V�[���ŁA�ʓr���x�b�g�� �߂̃v���[�g�ƁA�p�C�v���O�����p �̃{���g���t�����܂��B  �@���������אg�Ȃ��߁A��������� �y���Ɍ����܂��i���یy���j�B���́A �A�A�����ł��B |
| �@LeoVince(���I�r���`)��Evolution�U�X���b�v�I��(�A���~�E�I�[�o���^�C�v)�ł��BNaps�̃Z�[���ɂ�\39,690�ł����B �@�͂��ߏ����}�t���[�ɂ��悤�Ǝv���Ă��܂������A�I�[�N�V�����ł�F4i�p(�G�L�p�C�A�����܂ł̒������Ⴂ�܂�)�����ŃL���u�ԗp(99-00F4)�͌�������Ȃ��̂ŁA���Lj����X���b�v�I���ɗ��������܂����B�ЊO�i�ɂ���̂��S�O���Ă����̂́A���邳���}�t���[�������������߂ŁA���ƐÂ����Ƃ������I�r���`�Ɍ���B�ꉞ�A���B�ł͌����g�p�\�Ƃ������ƂŁA���҂��Ĕ����Ă݂��̂ł���....�B �@���̃^�C�v�́A��̕����p�C�v��˂�����ʼn��𗎂Ƃ��Ă���A�e�[���G���h�̃{���g���p�C�v���O���Ɗ��S�ȃX�g���[�g�r�C(���[�X�d�l)�ƂȂ�܂��B ������ �@�C�^���A���Ȃ̂Ő��x�̓A�o�E�g���Ǝv������A�������肵�����i�ł����B�����}�t���[�Ŏg�p����悤�ȃK�X�P�b�g�͕s�v�ł��B�O�̂��߁A�G�L�p�C�W�����ƃ}�t���[���̃p�C�v�̐ڍ����ɁA�t�̃K�X�P�b�g��h��܂������A�N���A�����X�������̂ŁA�w�ǂ��������鑤�̃p�C�v�ɂ���č킬���Ƃ���銴���ł��B�����A�����h��Ȃ��Ă����Ǝv���܂��B�n�ڂ��Y��ł��B�������̂́A���C���X�^���h�X�g�b�p�[���������ƁB�摖���ĊO���Ă������X�^���h�����Ȃ��Ă�.....�B �@�d�ʂ͏�����Tkg�ɑ��A��R.�Skg(����)�ł����B�G���������ł͌��\��v�����ł��B�A���~�͂����ƈ����ۂ��������Ǝv���Ă�����A�������������͋C�ŗǂ��ł��B�o�N�ω��̔��K���S�z�ł����A����͗l�q������ق��Ȃ������B ���� �@�C�ɂȂ鉹�̕��́A�A�C�h�����O�ߕӂł͂��قǁA���邳������܂���B�ł������C�ɂ���l���ߏ��ɏZ��ŋ���悤�ȂƂ���ł́A���߂ɃG���W����肽�������ł��B3,000��]�ӂ肩��A�m�[�}���ɖ����h�X�̗������ቹ�������܂��B�A���A�r�C���Ƀp�C�v���˂�����ł���\���̂������A���������ǂ��ꂽ�悤�Ȃ������������ɕ������܂��B�ᑬ�g���N���v�����قǗ����Ȃ������̂ő����I�ɍ��i�ł��B �@�����}�t���[�ɖ߂��đ���@��������̂ŁA���m�ɈႢ�������܂����B��͂蔲�����ǂ��̂ŁA��]���̏㏸�E���~�Ƃ��ɐ������ǂ��悤�ł��B�m�[�}�����ƁA�X���b�g���I�t�ʼn�]�������Ă��Ȃ����o�ɏP���܂��B�ᑬ�g���N�͂���قLjႢ�������Ȃ��̂ŁA�y�����܂߁A�X���b�v�I���̕����ǂ��ł��ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2006.2) |
|
�@
�@
�@�J�[�{�������t�F���_�[�i�}�W�J�����[�V���O �艿\24,000�j�����܂����B�I�[�N�V�����ɂĒ��Â��w���B���Õi�Ƃ������ƂŁA�S�̓I�ɍׂ����C�菝�Ȃǂ��������̂ł����A�s�J�[���Ŗ����Ă��Ƃ����Ԃ��ꂢ�ɂȂ�܂����B �@���ۂ̑����ɂ́A�����J�E���A�����̃^���f���X�e�b�v���O���܂��B�t�F���_�[�����Ă����O�ɁA�`�F�[���J�o�[�ƃ����u���[�L�z�[�X�̌Œ����O���̂����Y��Ȃ��B�`�F�[���J�o�[���O���Ă��܂��̂ŁA���炩���߃^�C�����X�e�b�J�[��������Ă����A�\��t���Ă݂܂����B �@�����X�e�b�J�[�ɏ����đO��^�C����C����^�C���T�C�Y�A�`�F�[���U�ꕝ�̐ݒ�l�̕\���X�e�b�J�[���o�b�ɂĂ��傱���傱�ƍ쐬���A�v�����^�[�o�́B�J�E���ی�p�̃E���^���V�[�g�X�e�b�J�[�̐�[���������̂ŁA�����������傫�߂ɐ���A��o�����X�e�b�J�[����\��t���܂��B�X�e�b�J�[���̗��ɂ͔���̗��ʃe�[�v��A�����Ă��Ȃ��悤�ɂ��܂����i����Ȋ����j�B�\���Ă���C�Â����̂ł����A�^�C�g���́uCAUTION�v�ł͂Ȃ��uTIRE INFORMATION�v�������ł��ˁB����i�����낤�H�j�́A������Ƒł������܂��B�����������V�[�������������肵��....���܂����I�I �@�t�F���_�[���̂ł����A�l�b�g�ł̓`�F�[�����u�̔�юU����w�E���郆�[�U�[�����܂������A�Ǘ��l�͋C�ɂȂ�قǂł͂���܂���ł����B��юU��ɂ������u���g�p���Ă��邹�������m��܂���B�^�C��(�p�C���b�g�X�|�[�c)�Ƃ̃N���A�����X���[���ŁA�W���w��̃^�C���Ȃ�����ɂ�炸���͂Ȃ������ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2007. 10�j |
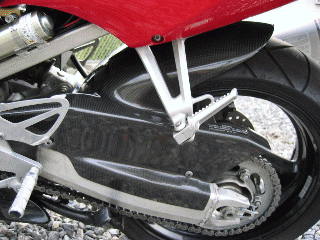 |
�@
�@
�@
�����탁���e�i���X
| �@�L�����p�[���ې��܂��B �@�p�ӂ�����̂́A��܁i������܂ŏ\���j�A�Ή�����傫���̃w�b�N�X�����`�A�\�P�b�g�����`�A�g���N�����`�A�u���V�召(���͎��u���V�ł����ł�)�A�R�A�u���[�L�O���X���ł��B���i�����Ղ��Ă������Ȃ�A�V�i��p�ӂ��Ă����Ƃ����ł��傤�B�p�b�h�s���͌��\�{���{���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������ł��B �@��܂͎��̓X�v���[���̃{�g���ɁA���ł������n�������̂����Ďg���Ă��܂��B�����Ƃ��낾���ɐ����t���āA���ł����Ɨ�����̂Ŋy�ł��B �@�܂��A�p�b�h�s��(�@�A)���ɂ߂܂��B���ŃL�����p�[�}�E���g�{���g�i�B�C�j���O���A�L�����p�[�̃{���g�̌��ȂǂɁA�R��ʂ��ēK���ȂƂ���ɂԂ牺���܂��i�ʐ^�E��j�B����̓u���[�L�z�[�X�ɏd�݂Ń_���[�W��^���Ȃ����߂ł��B�L�����p�[���Č��\�d���̂ŁB�t�����g���_�u���f�B�X�N�̂��̂́A���E��A������z�[�X�̃N�����v�{���g���O���܂��i�ʐ^�E���j�B�Ȃ�����̍�Ƃ̂��߂ɁA�A���_�[�J�E�����O���K�v�͂���܂���B |
�@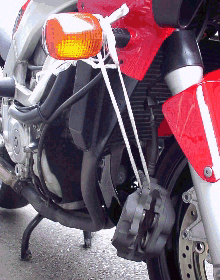 �@�@�@���̂悤�ɕR�ł邵�Ă����܂��B �@ 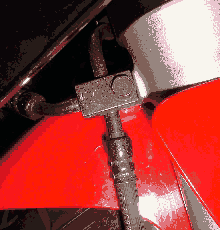 �@�@�@������A�\�ߊO���܂��傤�B |
||
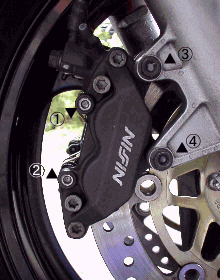 �u���[�L�L�����p�[��܂��B��Ƃ� ���ẮA�ʐ^�̂S�{�̃{���g���O�������B ����͐��|��Ȃ̂��Y��ȏ�Ԃł��B |
�@�L�����p�[���ԑ̂���O������A�ɂ߂Ă������p�b�h�s�������S�ɔ����܂��B�u���[�L�p�b�h���E������̂Œ��ӂ��܂��傤�B�o�b�N�v���[�g���O��܂��B�p�b�h�����݂̂̂Ƃ��́A�ԑ̂ɕt�����܂ܤ���̃v���[�g���O���ē���ւ��邱�Ƃ��o���܂��B�p�b�h���O������A���o�[����͌��ւł��B �@�ł����A�����߂̓p�b�h�������ɃL�����p�[���ې��邱�Ƃł��B�u���[�L�̌������S���Ƃ����Ă����قLjႢ�܂��B���ƁA�T�[�r�X�}�j���A�����ƌ��݂̂���V�i�p�b�h�����邽�߁A�s�X�g���������߂��悤�w�����Ă���܂����A���|�����ɉ����ƃs�X�g���O���̉���i�Œ����Ă��邱�Ƃ������B�ʐ^�����Q�Ɓj���V�[����ɂ߂Ă��܂��܂��B �@�����Ńp�b�h���O�����㤃L�����p�[�ɐ�܂����A�傫�ȃu���V�őS�̂�܂��B�s�X�g���O���͎��u���V�ł����������܂��B�ǂ����Ă������Ȃ���łȉ���́A�s�J�[�����ג����z�ɂ��āA�����|���Ė����Ǝ��܂��B�s�X�g������H�����g���ƕ֗��B �@�������ăL�����p�[��ƁA�ƂĂ��悭�����悤�ɂȂ�܂��B�s�X�g���O���ɃV���R���O���X�Ȃǂ𔖂��h�z���ē���܂��܂��傤�B�������^�����o�[�𐁂��āA�s�X�g���������܂��B |
||
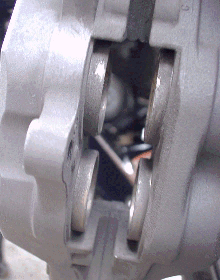 �@ �@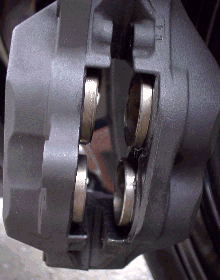 �@�@�@���ꂪ�͐ς����L�����p�[�B�@�@�@�@�@�@�@�@���|��̃L�����p�[�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���͂���ȐF�ł��B |
�@�p�b�h�s���Ȃǂ��Y�ꂸ�ɖ����܂��傤�B�E�̎ʐ^�̂悤�ȎS��ł������A���i�̎�z�����Ă��Ȃ��������߁A����͂��̂܂ܑg��ł��܂��܂��B�p�b�h�s���ɂ̓V���R���O���X�𔖂��h�z���Ă����܂��B���ƁA�p�b�h���ʂ̃s�X�g���������镔���ɂ��A���~�߃O���X�𔖂��h��܂��B �@���ꂢ�ɂȂ�����g�ݕt���ł��B�p�b�h�����t���A�o�b�N�v���[�g�i������ɂ��đg�݂܂��j�������Ȃ���p�b�h�s�����������݂܂��B�T�[�r�X�}�j���A���ɂ͓��Ɏw���͂���܂��A�E���̎ʐ^�̂悤�ɁA����(�A)�������Ȃ��ƁA���͑g�ݗ��Ă��Ȃ��̂ł���.......�B |
�@ 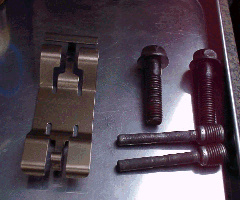 �@�p�b�h�s��������ł��܂��B���N�m�[�����e�� �@���߁A���̗L�l�B�o�b�N�v���[�g�̖���� �@��ł��傤���H�i�������j �@  |
| �@�g���N�����`���g�p���Ďԑ̂��L�����p�[�}�E���g�{���g(�B�C)�Ŏ��t���܂��B�ɂݖh�~�̂��߁A�������Ɏ�͂̕����ɉ����Ȃ���i��L�ԑ̑����̎ʐ^�ʼn������ɉ�����j�A�K��g���N(3.1kgfm)�Œ��ߕt���܂��B�p�b�h�s�����Y�ꂸ�ɖ{���߂��Ă����܂��傤�i1.8kgfm�j�B �@���t�����I��������A�u���[�L���o�[�����x�����삵�āA��������o���Ă����܂��傤�B�ŏ��͑S�������Ȃ��̂ŁA���̂܂ܑ���o���Ɗ댯�ł��B �@����͎ʐ^�B�e�Ȃǂ��Ȃ����Ƃ������߂Q���ԋ߂����������Ă��܂��܂������A��ƓI�ɂ͂���ȂɎ��Ԃ������炸�A�ȒP�ɏo���Č��ʂ͐��ł��B |
||
�@
�@����̓����p�b�h���������܂��B�菇�̓t�����g�L�����p�[�̊ېɏ����܂��B �@�p�ӂ������ �@���R�A�u���[�L�p�b�h�B����̓x�X�� �V���^�[�h���^���p�b�h���`���C�X�B �@�@���Ђg�o�ł́A�a�����̌��̍w���ɂ��Ă͕W�����i�̂Q�����ɂȂ鐧�x������܂��B �@�@����萔���͂�����܂����A�܂Ƃߔ�������Ό��\���������m��܂���B �@�H��́A���K�l(12mm)�A�w�b�N�X(5mm)�A�o�C�X�v���C���[�ƃ}�C�i�X�r�b�g�A���炢�ł��B �@��Ǝ菇 �@�܂��A�p�b�h�s���v���O���ɂ߂܂��B�}�C�i�X�h���C�o�Ȃ̂ł����A�}�t���[���������ē���܂���B�d���Ȃ��̂ŁA�Ǘ��l�̓o�C�X�v���C���Ń}�C�i�X�r�b�g��͂�ŁA����Ŋɂ߂Ă��܂��B���̌�A�w�b�N�X�����`�Ńp�b�h�s�����ɂ߂܂��傤�B �@���ŁA��둤�̃L�����p�[�{���g���ɂ߂܂��B���\�ł��̂Ŏ���Ԃ��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���ꂪ�O���ƁA�L�����p�[��둤�������グ���܂��B�p�b�h�s�����āA�p�b�h�����܂��B �@�L�����p�[�̐��|�̓t�����g�̂Ƃ��Ɠ����ł��B������Ɩ����ɂ����ł����A�Y��ɂ��܂��傤�B�L�����p�[�O���̃{���g������āA���S�Ƀt���[�ɂ��Ă����̂��ǂ���������܂���B�������S�ɊO���Ȃ�A�z�[�X�o���h���O���A�u���[�L�z�[�X�Ƀ_���[�W��^���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��B �@���i�𐴑|������A�Â��p�b�h����������̃��e�[�i�ƁA�������~�߁i�Ђ���Ƃ���ƒf�M�j�v���[�g���O���A�V�i�p�b�h�ɑg�ݕt���܂��B�V�i�p�b�h�̖ʎ��́A�f�B�X�N�̉�]�������l�����A�p�b�h�s������O����ɍ��܂��傤�B�Ǘ��l�͕n�R���Ȃ̂ŁA���܂��_�ɂ͍��܂���.....�B�ʎ��Ȃ̂�����A�傫�����K�v�͖����̂ł́H�Ƃ��v���܂��B �@�u���P�b�g�Ƀp�b�h�O�����Z�b�g���郊�e�[�i������̂ŁA������Ƃ͂߂Ă����܂��B�L�����p�[�㕔�������グ�A�p�b�h���Z�b�g���A�p�b�h�X�v�����O���O��Ȃ��悤���ӂ��Ȃ���L�����p�[�������܂��B���Ƃ̓L�����p�[�{���g�A�p�b�h�s�������ďI���ł��B �@�p�b�h�s���ɂ̓V���R���O���X�𔖂�(�\�ʂɖ������C���[�W��)�h�z���܂����B�܂��A����p�b�h�s���̂˂����Ƀ����u�f���O���X��h�z���Ă݂܂����B�O���Ƃ��قڌŒ����Ă����̂ŁA �@���t���I����A�u���[�L���o�[�𑀍삵�ē�������o���̂̓t�����g�Ɠ����ł��B �@�Ȃ��A�V���^�[�h(���^��)�p�b�h�̏ꍇ�A�V�i�͖ʏo�����I������܂ŁA�����͑啝�ɗ�����悤�ł��B�~�܂邱�Ƃ͎~�܂�̂ł����A�k���`���Ƃ��Ă��āA�M���b���ƐH���t������������܂���B���炭�́A���Ȃ�]�T�������ĉ^�]�����ق����ǂ������B �@�u���[�L�͏d�v�ۈ����i�ł��B�p�b�h��f�B�X�N�ɖ������Ȃ��悤�ɁA��������Ǘ����āA�����̑O�ɂ͂�����Ƒg�݂����������A�K���Ċm�F���܂��傤�B���Օ��i�Ƃ͂����A�����Ō�������Ƃ�舤�����N���܂��ˁB �@�K��g���N �@�@�L�����p�s���{���g(�O)�@�@�@2.8kgf-m �@�@�L�����p�{���g(��)�@�@�@�@�@ 2.3kgf-m �@�@�p�b�h�s���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@1.8kgf-m �@�@�p�b�h�s���v���O�@�@�@�@�@ �@�@0.3kgf-m |
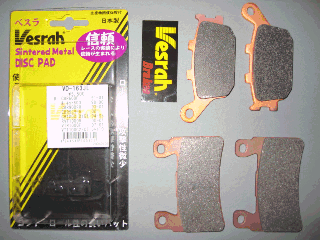 �@�����t�����g�p(VD-166JL)�A�オ�����p �@�@(VD-163JL)�B�����̂݃X�e�b�J�[�t���B 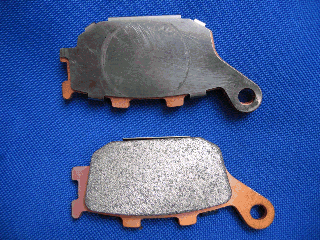 �@�y�`���ʎ�肵�Ă���̂������܂����H 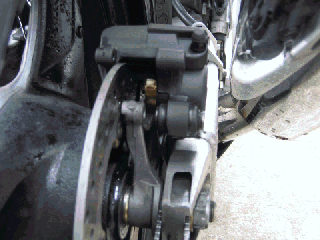 �@��Ƀg���N�����`�͓����.....�}�t���[�� �@�@���������A�b�v�^�C�v�Ȃ炢���̂ɁB |
|
�@
�@
 �@MOTOREX�̃p�b�P�[�W�B���������� �@�ɂȂ��Ă��āA500cc���ɖڐ�������A �@�c�ʂ��킩��܂��B�e�ł��B |
�@�I�C�������ł��B ����g�p����̂́A���������ŗǂ��]�����X�C�X�������g���b�N�X�ɂ��܂����B�ŏ㋉�O���[�h��PowerSYNT 4T(10W/60)�ł��i�ʐ^���j�B�~��ɂ͂�����ƍd���Ǝv���܂����A���傤�Lj����肵�Ă����̂ŁB�S�k����艿\6,000���p�b�P�[�W�����̂��߁A�Ȃ��\2,500�I�B���͕W����HONDA ULTRA GP(10W-40)�ł��B�����ėǂ����ǁA�����ɃV�t�g�t�B�[���������Ȃ��ł����.....�B |
|
�@�ŁA�H��̂ق��ɏ���������̂́A�ʐ^�E�̂悤�ɃI�C�������ނƁA�I�C���W���b�L�A�t���b�V���O�I�C���i����̓I�C��������ύX���邽�߁A�t���b�V���O�I�C���Ő����s���A�t�B���^���������܂��j�A����Ƀh�����{���g�̃��b�V���[(���m�ɂ̓p�b�L��)�A�I�C���t�B���^�ł��B�W���b�L�͂Ȃ��Ă��ǂ��ł����A���ڂ�������邽�߂ɂ͂������ق����y�ł��B�ʐ^�̂��L�^�R�̂Q�k�^�C�v�i\750�ʁj�ł��B �@�����菇�́A�g�@�����I�C���r�o���t���b�V���O�I�C���������g�@(���)���r�o���t�B���^�������V�I�C�������A�ƂȂ�܂��B |
�@�@  �@�p�������܂́A�傫�ڂ�p�ӂ��܂��傤�B �@�C���ɂ��Ȃ�A�I�C���{�V������ �@��邱�Ƃ������I�ɂ͉\�ł��B |
|
| �@�܂��A���_�[�J�E�����O���܂��B�t�B���^����������Ȃ�A�t�����g�������O���܂��傤�B�����Ԓg�@���āA�I�C�����_�炩�����܂��B�G���W�����~�߂���A�G���W���̃I�C���������̊W���Ƃ�A�p����p�ӂ��ăI�C���h�����{���g���ɂ߂܂��B�R��E�S����܂̓�d���p�������߂��܂��B �@���炭���u���ăI�C�����w�Ǐo�Ȃ��Ȃ��Ă���A�ԑ̂�O�㍶�E�ɗh�����āA�ēx���u���܂��B��������Ǝc���Ă����Ō�̃I�C�����o�܂��i�ʐ^�E�j�B����A1,000km���x���������Ă��܂��A���N�قnjo�߂��Ă��邽�߁A�I�C���͂����̒ʂ�B �@���ăt���b�V���O�I�C���ł��B �@����A�t���b�V���O�]�C��(PAPA Corp.)�Ɩ����܂������A��Ԉ�������Castrol�̃I�C���Ɍ���B�����\�ʉ����܂�SuperZOIL�̓I�C����������Ɩw�nj��ʂ��̊��ł��Ȃ��Ȃ邽�߁A�t���b�V���O���x�ł͈Ӗ����Ȃ��Ǝv��������(ZOIL�����ʂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��B�Y������ƃV�t�g�t�B�[�������������炩�ɂȂ�܂��B�O�̂��߁B)�B �@�h�����{���g�������߂��A�t���b�V���O�I�C�������܂��B���ʂ̃t���b�V���O�I�C���͏��Ȃ߂�(�K��e�ʂ̂R���̂Q���炢)�����悤�ł����A�ʐ^��Castrol�̃I�C���́A�K��ʓ����悤�Ɏw������Ă���̂ł���ɏ]���܂��B���Ȃ�V���o�V���o�̃I�C���ł��B���\�͂��d�����ď������͒Ⴛ���Ȃ̂ŁA�A�C�h�����O���Ă����~�߂܂��B �@��قǂƓ��l�A�c���Ă���I�C�����ő�������悤�ɂ��܂��傤�B |
�@ 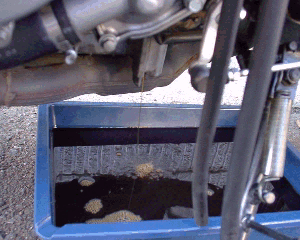 �@�ʐ^�ł͔p�����g���C�ɎĂ��܂����A �@���ځA�p�������܂̗e��ŎĂ��ǂ� �@�ł��B�ԑ̂�h����ƁA�ʐ^�̂悤�ɁA�܂� �@�o�Ă��܂��B |
|
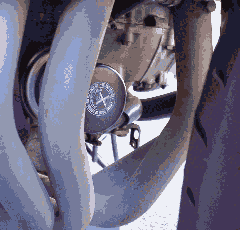 �@���\�h���h���ɉ���Ă���̂ŁA�O���O�� �@�ԑ̂�|�����܂��B�ʐ^�͐��|��B�t�B���^ �@�t�����́A��F�Ɍ����鏊���Y��ɂ��܂��B |
�@�V�i�̃��b�V�����g���A�I�C���h�����{���g���K��g���N(3.0kgfm)�Œ��ߕt���܂��B �@�t���b�V���O���I��������A�t�B���^�����ł��B�I�C���M�p�ӂ��Ă���A�t�B���^�����`�Ŏ��O���܂��B�ɂ݂����ƁA�G���W���{�̂Ƃ̐ڍ��ʂ���I�C������������܂��B���S��������\�o�܂��̂ŁA���ӂ��܂��傤�B�t���b�V���O�I�C���͐��݂����Ȃ̂ŁA���\�͂˂܂��B �@�t�B���^���t���������S���Y��ɂ��Ă���A�V�����t�B���^�����t���܂��B���̍ہA�t�B���^�̃p�b�L���ɁA���炩���ߐV�i�I�C����h�z���Ă����܂��B�I�C���t�B���^�̋K��g���N��1.0kgfm�ł��B �@����ŁA�V�i�I�C���𒍓����܂��B�e��̌��́A�����L�т�悤�ɂȂ��Ă��܂����A���̂܂܂ł͂��ڂꂻ���Ȃ̂ŁA�I�C���W���b�L�Ɉڂ��Ă��璍���܂��B�b�a�q�͑��v�ł����A�K��ʂ���C�ɓ���悤�Ƃ���ƃI�C�������ӂ��@�������悤�ł��B���������ꍇ�͂�����x����������A�A�C�h�����O�����Ȃ���K��ʂ܂Œ�������Ƃ����ł��B �@�I�C��������A�A�C�h�����O���Ă���_�����ŃI�C���ʂ��`�F�b�N���܂��B�G���W���I�C���͑�������̂��ǂ��Ȃ��̂ŁA���e�͈͓��ŁA�C�������Ȃ߂ɓ���Ă��܂��B |
|
�@
�@�`�F���W�y�_���A�u���[�L�y�_�����|
| �@�`�F���W�y�_���ƃu���[�L�y�_���𐴑|���܂��B �킴�킴��������قǂł��Ȃ�.....�ł����A���S�Ҍ����Ƃ������Ƃł����ق��B �@�p�ӂ�����̂́A�X�i�b�v�����O�v���C���[(�ʐ^)�A�w�b�N�X�����`�i�傫�ȗ͂�����̂Ń\�P�b�g�����ǂ��j�A�\�P�b�g�����`�A�g���N�����`�A���|�p��A�O���X���ł��B�u���[�L�y�_��������s��(��)���g�p���Ă���̂ŁA�K���V�i��p�����܂��B �@�`�F���W�y�_���̕��́A�ʐ^���̂悤�ɖ��Ղ��Ă��܂����B�y�_�����ɂ̓X���[�u���ł����܂�Ă��܂����ACBR�̂��͍̂X�Ƀe�t�����R�[�e�B���O�炵�����̂��{����Ă��āA�Â�������ł�(�����������Ă���Ƃ�����)�B�ڂׂ̍����y�[�p�[�Ŕ����ꂩ�����R�[�e�B���O�̃o���𗎂Ƃ��A�O���X�A�b�v(����̓����u�f���O���X���g�p)��A�������܂����B �@�g�ݗ��Ă�ۂ́A���b�V���[�̏��Ԃɒ��ӁB�ʐ^�̏��ԂɃy�_�����ɃZ�b�g���܂��B�`�F���W���b�h�����́A�S���J�o�[�����炵�ėǂ��A�O���X��h�荞�݂܂��B�ő��ɂ炳�Ȃ��̂Ńs�J�[���Ŋe���i���܂����B �@�u���[�L�y�_���́A�u���[�L�{�̂��X�e�b�v�ɌŒ肵�Ă���{���g���ɂ߂Ă���A�X�e�b�v�{�̂��O���܂��B���̃{���g�̓q�[���K�[�h�Ƌ����߂ł����A���E�̃X�e�b�v�Œ������Ⴂ�܂�(���R�A�u���[�L��������)�B���ƁA�y�_����[���A����s���ŗ��܂��Ă���̂ł�����O���܂��B�y�_�����O���ۂ́A�`�F���W�y�_�����l�A�X�i�b�v�����O���O���܂��B�ʐ^�̃X�i�b�v�����O�v���C���[�͍��֎��ŁA�S�ʂ�g���܂��B�g�p�p�x���l����ƁA�l�I�ɂ͍��֎��ŏ\���Ǝv���܂��B�Ȃ�����邵�B �@�g�ނƂ��͊�{�I�ɂ炵�̋t�ɂ�������̂ł����A���S�̂��ߊ���s�����ɐV�i�Ɋ����܂��傤�B����������h�~�̂��߂ɁA����s���̑��͎��ɓY�킹�Ċۂ߂܂��B �@����n���y���ƁA�^�]����̂��y�����Ȃ�܂���B�ɂ������Đ���A���܂��傤�B�Ǘ��l�̂悤�ɂȂ�O��...... �@�K��g���N �@�@�@�@���C���X�e�b�v�u���P�b�g�{���g �@�@�@2.7kgfm �@�@�@�@�����}�X�^�V�����_�}�E���g�{���g�@0.9kgfm�@������́A��(���o)�Œ��߂Ă����Ǝv���܂��B |
�@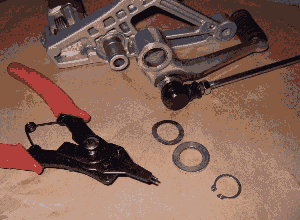 �@ �@  �@�^�̓R�[�e�B���O���c���Ă��܂����A���[�̓X���[�u �@�����Ēi�����Ղ��Ă܂��B�����Ƒ����������Ă����ׂ� �@�������Ɣ��ȁB |
|
�@
| �@�t�H�[�N�I�C���̌����ł��B �@�V���b�v�ɂ���Ă͕K�v�Ȃ������I�I�ȑΉ�������邱�Ƃ�����悤�ł����A���ɐV�Ԏ��ɂ̓X���b�W���o��̂ŁA���߂ɕς����ق����ǂ��Ǝv���܂��B�Ȃ�����͍�Ƃɒǂ��Ďʐ^���B���Ă��܂���B�X�p�[�_�̃y�[�W�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ă��������B �@�p�ӂ������ �@�t�H�[�N�I�C���BCBR���z���_�N�b�V�����I�C��10�����W���B�J���T�L�����������ĔS�x���߂��̂ł���ɂ��܂��B �@����p�ɁA�Ή�����傫���̃\�P�b�g�A�R���r�l�[�V���������`�B���i���|�p�Ƀp�[�c�N���[�i�[�ƁA���������̃s�J�[���ȂǁB �@���Ƃ̓V���R���`���[�u�ƒ��ˊ�B���ʒ����ɕK�{�ł��B �@��Ǝ菇 �@�܂��W���b�L�A�b�v��A�t�����g�t�H�[�N���O���܂��B���炭�J�E�������Ȃ��Ɛ����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�n���h����C�N���b�v���O���Ȃ��Ǝ��Ȃ��̂Œ��ӁB�n���h����t�{���g���ɂ߂���A�t�H�[�N���ԑ̂ɂ��Ă��邤���Ƀt�H�[�N�L���b�v���ɂ߂܂��B�t�����g�A�N�X�����ɂ߂Ă����܂��傤�B���C���[�o���h���Y�ꂸ����Ă����܂��B�g�b�v�u���b�W�Ȃǂ̊����{���g���ɂ߁A�t�H�[�N�����܂��B �@�t�H�[�N�P�̂ɂȂ�����A�t�H�[�N�L���b�v���C���i�[�`���[�u������܂��B�˂̓A�W���X�^�[�̃��b�h���Ƀe���V�������|���Ă��邽�߁A�������Ȃ�����K�v�͂���܂���B�A�W���X�^�[���b�h�����̃i�b�g(�J���[������������ƌ����܂�)�ɃX�p�i���|���āA�A�W���X�^�[���b�h����t�H�[�N�L���b�v�����܂��B����������邽�߁A�A�W���X�^�[���̂͌����ă��b�h����O���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�J���[��X�v�����O�����A�t���ɂ��ăt�H�[�N�I�C����r�o���܂��B���b�h�����k������ƁA�X���b�W���܂����I�C�����o�܂��B�b�����̂܂ܒu���Ă����܂����B �@����������܂�̃X�v�����O���������܂����B�Ǘ��l�͖Y��Ă��܂��܂��������R�����v�����܂��傤�B�g�p���x�� 329.3mm�B�Ȃ��A�C���i�[�`���[�u�̃g�b�v�u���b�W�ƃX�e���̊Ԃɗ��镔���́A���\���т����Ă܂����B�s�J�[���Ŗ����ė��Ƃ��܂����A�|�c�|�c�����_�Ƃ��Ďc���Ă��܂��܂����B�c�O�B�������ɂS�N�߂����ق����炩���ł͎d���Ȃ��ł��B�t���J�E���Ԃ͒��ӂ��Č��Ă����Ȃ��Ƃ��߂ł��ˁB �@�ŁA�g�ނƂ��ɂ́A���̕����ɂ�������Ə_�炩�߂��O���X��h��L���܂����B���ÎԂł�������̉��͈ӊO�ɐV�i���l�A�Ȃ�Ă��Ƃ�����܂�����A�K�ї\�h�Ƃ��Ă͂��Ȃ肢���̂ł́H �������h���͈����Ȃ�܂����A�J�E���ʼnB��Ă��܂��܂��B �@�I�C������ 475�}2.5cc�B�I�C�����x���� 118mm�ł��B�t�H�[�N���k�߂���ԂŁA�C���i�[�`���[�u��[����A���ʂ܂ł̋����𑪂�܂��B���b�h��L�k�����āA�b���u���Ă���v������Ɨǂ��ł��傤�B���R�A�I�C���ʂ����I�C�����x���D��Œ������܂��B �@���i��S���Y��ɂ��ăI�C������ꂽ��A�����ɓ���܂��B��{�I�ɕ����̋t�ł����A�t�H�[�N�̌Œ�ʒu�́A�g�b�v�u���b�W��ʂ���A�g�b�v�L���b�v��[�܂ł� 33mm �ɂȂ�悤�ɒ������܂��B�t�H�[�N�A�n���h�������t���A�A�N�X���{���g�ƉE���̃A�N�X���z���_�{���g���K��g���N�Œ��߁A�z�C�[�����t�F���_�[�ƃu���[�L�����g�݂�����A�t�H�[�N�����L�k�����āA�A�N�X���̎��܂��ǂ����܂��B���̌�A�����̃A�N�X���z���_�{���g���Œ肵�܂��B �@��ƌ��� �@����o���āA���ɏ����쓮���ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��܂��B�˂��グ�銴���������Ȃ��āA���S�n���ǂ��̂ł��B�������Ƃ����Ⴄ�͂��ł����A���̕ӂ�͊Ǘ��l�̘r�O�ł͍��͂킩��Ȃ����ȁB����̔�p�̓I�C���ゾ���ł����B �@�����e�i���X�̎d���ɂ��ẮA����̓�A�W���b�L���ƈӊO�Ǝx����ꏊ������܂���B�l�I�ɂ́A�t�H�[�N�W�̃����e�ɂ̓t�����g�A�b�v�X�^���h�������Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�t�H�[�N�����ł͂Ȃ��A�w�b�h�̎��Ŏx����^�C�v�B����Ȃ�X�e�A�����O�̃x�A�����O�����ȊO�͑Ώ��ł��܂��B�����e�����₷���Ƃ����Ǝ����̕p�x���オ��̂ŁA�w�����ł��ˁB �@�K��g���N �@�@�@�@�g�b�v�u���b�W�s���`�{���g �@�@2.3kgfm �@�@�@�@�{�g���u���b�W�s���`�{���g �@4.0kgfm �@�@�@�@�t�H�[�N�L���b�v �@�@�@ �@ �@�@ 2.3kgfm �@�@�@�@�L�����p�[�}�E���g�{���g�@ �@3.1kgfm �@�@�@�@�A�N�X���{���g�@�@ �@�@�@�@�@�@ 6.0kgfm �@�@�@�@�A�N�X���z���_�{���g�@�@�@�@ 2.2kgfm(�A�E�^�[���[�̃{���g�B�Б��Q�{����) |
�@
| �@�����e�i���X�����A���C���[�����ł��B �@�Ƃ肠�����A���S�Ҍ����ɉ�����B �@���C���[�ނ͒���I�Ȓ������K�v�ł��B����������G���A�X�p�b�Ɛ��悤�ɂȂ�Ə��₷�����i�������j����Ă��܂��B�A�N�Z�����C���[�����l�ɒ������܂��B�Ǘ��l�̓N���b�`�ɂ̓t�H�[�N(�T�X�y���V����)�I�C���A�A�N�Z�����C���[�ɂ̓V���R���I�C�����g�p���Ă��܂��B�t�H�[�N�I�C���͔S�x���G���W���I�C�����_�炩���̂ŐZ�����₷���A���C���[�\�ʂɂ͗��܂��Ă���܂��B���݂��ĂȂ��̂��ǂ����ł��B�܂��A���o�[�x�_�̃{���g���O���āA�O���X�A�b�v���܂��傤�B�N���b�`���͎g�p�p�x������������₷���̂ŁA�����u�f���O���X���ǂ��Ǝv���܂��B �@��Ǝ菇 �@�J�E���t���̎Ԏ�̏ꍇ�́A�܂����C���[�A�W���X�^�[�̂��鑤�i�ʏ�E���j�̃J�E�������O���܂��B���ɃX�p�i���g���ă��b�N�i�b�g�i���j���Œ肵�A�A�W���X�^�[�i�b�g�i�E�j���ɂ߂܂��B�ő�Ɋɂ߂��ق����ǂ��ł��傤�i�ʐ^�E��j�B���̌�A�N���b�`���o�[������A���C���[������������o�[������ƁA���C���[���y�ɊO���܂��B���o�[���O���Ă��܂��Ȃ�����Ɗy�B �@�����̓��C���[�C���W�F�N�^�Ȃǂ̐�p�H�������܂����A�Ǘ��l���w�T�b�N(�_�C�\�[�łT���� \100) �������o���h���g�p���܂��B�w�T�b�N�̎w�摤�Ɍ����J���A���C���[��ʂ��Ă��猋���o���h�Œ��ߕt���܂��B���ꂾ�ƃr�j�[���܂��g���̂ƈ���čĎg�p�o���܂����A���C���[�̃A�E�^�[���������Œ��߂�Ɩ��͘R��܂���B�I�C�������Ďb���u���Ă����܂��i�ʐ^�����j�B �@�b�a�q���������ӓ_���B�J�E�������̃t�����g�C���i�[�J�E���ƃT�C�h�J�E���A���̃v���X�r�X�́A���ӂ��Ă˂����݂܂��傤�i�ʐ^���E�j�B����Â炢����Ƃ����ė͔C���ɉ����������Ƃ���ƁA�T�C�h�J�E�����ɃZ�b�g����Ă��鎓�˂����i���A�O��Ă��܂��܂�(������т���)�B�O�����S���łł��Ă���A�͂ߍ���ł��邾��������ł��B���̎��˂����i�̓J�E�����O���Ȃ��ƁA�ăZ�b�g�ł��܂���B�r�X�́A�������ƗD�����˂����ނ悤�ɂ��܂��傤�B |
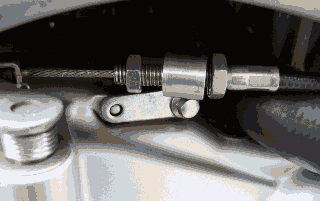 �@���C���[���͐�Ȃ��悤�A��ɒ�����S�����܂��傤�B 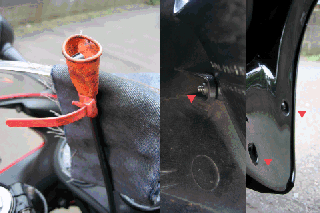 |
�@
| �X�p�[�N�v���O���� | |||
| �@CBR�̃X�p�[�N�v���O���������܂����B �@�T�[�r�X�}�j���A���ɂ��ƁA���W�G�[�^�[�����炵��.....�ƁA��ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂����A�r�b�O�}�V�����Ȃǂɂ��ƁA�V���b�v�ł��^���N�E�G�A�N���{�b�N�X���O���Č������Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̎菇�ōs�����Ƃɂ��܂����B�J�E����S���O�����ɏo����̂��ǂ��ł��B ��Ǝ菇 �@�܂��G�A�C���e�C�N�J�o�[�̃{���g�ƁA�^���N�O���̌Œ�{���g���O���܂��B�����ɂ��X�y�[�T�[�������Ă���̂ŗ��Ƃ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��B�^���N�������グ�A�戵�������̒ʂ�A�ԍڍH��̃��K�l�����`�ŕێ����܂��B�^���N���ʌ㕔�Ƀt���[�G���R�b�N������̂ŁAOFF�ɂ��āA�R���Z���T�[�̃P�[�u����`���[�u�ނ����O���܂��B�h�����`���[�u���u���[�U�[�`���[�u�̕Е��͌ł������̂ŁA����͂Ȃ����܂܃^���N���O���܂����B �@�����ăG�A�N���{�b�N�X�O���ł��B���E�_�N�g�A�����̃v���X�r�X���ɂ߁A�_�N�g���O���܂��B���̃n�[�l�X���G�A�N���{�b�N�X�̎���O���i���ߋ���y���`�ł܂ނƊy�j�A�㕔�̃o�L���[���`���[�u��(���P�A�ׂS�{)���O���āA���Ƃ̓L���u�ɂ��Ԃ����Ă���o���h���ɂ߂�ƁA��Ɏ����グ����̂ŁA����ɑO���̃G�A�x���g�z�[�X(���R�{)���O���܂��B����ŃG�A�N���{�b�N�X���O���܂��B �@�O���̃G�A�x���g�z�[�X�̂����Б��͊O��Ă����悤�ŁA���������G�A�N���[�i�[�����̂Ƃ����A�T�u�G�������g�̕Е��������Ȃ艘��Ă��܂����B�����ł�����̂͏��߂ĂȂ̂ŁA�O��̎Ԍ��̂Ƃ��ɊO�ꂽ�܂ܔ[�Ԃ���A���̂܂ܑ����Ă��܂����Ƃ������Ƃ�.....�B �@CBR�͓���ȃ^�C�v�ŁA�X�p�[�N�v���O�ɒ��ڃC�O�j�b�V�����R�C�������܂��B�ł����i�����j�v���O�L���b�v�Ƃ��������ł��B�n�[�l�X����L���b�v�̓��ɂ���J�v���[�֍ׂ������q�����Ă���A���̃R�l�N�^�[���O���܂��B�C�O�j�b�V�����R�C���́A�t���[���⋭�̊ۂ��p�C�v�̌��������ֈ�U�����o���A���o���Ɗ����X���[�Y�ɂł��܂��B ��ƌ��� �@������������̂�NGK CR9EVX�iVX�v���`�i�v���O�j�ł��B�W���̂W�Ԃ���A�X�ԂɔM����ύX���܂����i�A�o�d�l�Ɠ����j�B���������N�ł����\�Ⴄ�Ƃ����b�ł����A�ʂ����đ��v���H�����������Ă݂�ƁA�b�����m�C�Y���o��悤�ɂȂ����C�����܂��B�����ł͂��܂�Ⴂ������Ȃ�.....�B�ᑬ����͋����Ȃ����̂́A�ւ������̂�V�i�Ɍ������������ł��傤�B �@�`���[�u�ނ͑����ł����A�����͂��₷�����Ȃ̂ŁA�悩�����B�i��ł�邩�Ƃ������......�H(2005.10) |
|||
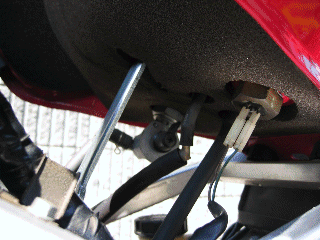 �@�@�ԍڂ̃��K�l�Ŏx���Ă��܂��B���ɔR���R�b�N���� �@���܂��B��O���̃S���z�[�X�i�I�[�o�[�t���[�H�j�́A �@�O��܂���ł����B �@�@��O�̔R���Z���T�[�̔z���͓��E�O�A�E��A�ł��B |
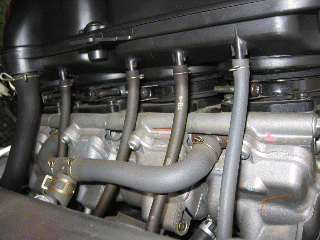 �@�G�A�N���{�b�N�X��둤�B���̑����z�[�X�ƁA����ł���ׂ��z�[�X�S�{���O���܂��B���������͂��̂S�{�ƃQ�[�W���Ȃ��ōs����悤�ł��B��ʉ������̓L���u�{�́B |
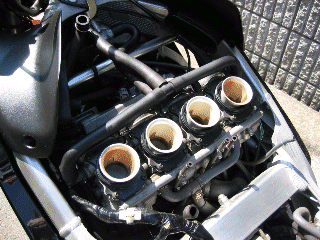 �@�G�A�N���{�b�N�X���O������B���̏�ԂȂ�A�_�v���O�������ł��܂��B�z�[�X�ނ������ł����A�ӊO�Ɛ������͈����Ȃ������ł��B�ł��l�C�L�b�h�Ɣ�r���Ă͂����܂���B |
|
�@