![]()
私の乗り継いできた(といっても、まだ5台ですが)バイクのページです。
選んだ理由、使ってみた感想や、ちょこちょこっといじった内容などを載せています。
●HONDA MAGNA FIFTY(マグナフィフティ)
| 購入のキッカケ 学生のときバイトに通う足として使用。マグナ250を見て格好いいなぁと思ったが、普通自動車免許しかないため原付を物色していると、兄弟車(といえるのか?)の原付があることを発見。早速購入しました。 乗り心地はよく1年ほど使用しましたが、出足のあまりの遅さにうんざりしました。普通なら改造などしてマニアへの道を進むはずですが、あっさり乗り換えを決意。普通自動二輪を取って、ちょうど魅力を感じていたバリオスⅡ(下記参照)に買い替えました。初期性能が低いので、いじりたい人向けと思います。カブ系エンジンなので改造パーツは山ほどあります。 |
 |
長所 見栄え。原付にしては大きく、ポジションが楽ちんです。取り締まり時に原付スクーターは止められていたけどこちらはパスしてくれました。
原付に見えなかったらしい。乗り心地も良いです。サスペンションがかなり柔らかいので、路面の継ぎ目も苦になりません。
フロントディスクブレーキ装備。でも効きはそれなりです。飛ばすバイクではないので充分でしょう。
あと長所としては、故障しそうもないこと。なにせカブ系でっせ。ゆったり走ってもサマになります。
短所 ノーマルでは出足が遅い。スピードも出ない。荷物を積む場所が全くないです。
マフラーガードについているゴム部品が、足に当たって取れてしまう。そのままで機能的には問題ないが、何とかして欲しいところ。
冷間時、チョークを引いてもなかなかエンジンがかからない。
エンジンオイルフィルターがない!! オイル量チェックも、ディップスティックをいちいち抜いて、ふき取ってからしないといけない。
●KAWASAKI BALIUSⅡ(バリオスⅡ)
| 購入のキッカケ マグナの遅さに閉口した勢いで普通二輪免許を取り、乗り換え車種をいろいろ物色。まだこの頃までは、~400cc新車の選択肢が今の倍くらいはありました。 4気筒で、何にでも使えそうなネイキッドがよろしかろうということで、面倒(車検)のない250から選ぶことにしました。最終的にホーネット、バリオスのどちらにするかで迷い、ホーネットはあの太~いタイヤのコストが高そうということで脱落。バリオスに決定しました(単にバリオスのスタイリングが好きだったということもあります)。 |
 |
|
| 長所 | 高回転まで回るエンジン。F1のような音に聞こえるのは私だけ? 安定感があるので、倒し込みも怖くないです。初心者でも少し走って慣れれば、すぐリヤタイヤの端っこまで使えるでしょう。 装備も充実しています。クラッチ・ブレーキレバーともにアジャスター付きで、燃料計もあります。シート下は結構大容量のボックスなので、カッパ(GWのコンパクトレインスーツなど)くらいなら収まるでしょう。アルミフレームのレプリカほどではないですが、ステップ周りが結構がっちりできているため、安心感があります。ただしステップ自体は、安っぽいです。 |
|
| 短所 | 冬の始動性は最悪。チョークを引いてもカブるだけです。温まるまではアクセルを開けて回転をかなり上げておかないと、確実にエンストします。温まると一発でかかります。あと、走行7000kmほどで、エンジンヘッドカバー合わせ面からオイルがにじんできました。オイル漏れというほどではないですが。カワサキなら当たり前? それなりに走ろうとしてニーグリップすると、タンクが細身のためひざの先端のみが当たり、あざになります。革パンツなら大丈夫だと思います。 普通に走っていても、結構エンジンがうるさいです。 |
|
走る楽しさを実感しました。講習会なんかに参加し始めたのもコレです。気軽に乗れるのがいいところ。その気になれば結構速いし、ツーリングなどには必要十分といった感じで、しばらく乗ってました。
メンテナンスについて
エンジンオイルキャップの溝には、金属棚のL字金具がぴったりです。普通のマイナスドライバなどではキャップの溝を痛めるので注意しましょう。
フォークオイル交換時は、純正指定オイルのショーワ製は高すぎるため、カワサキの10番が良いです。多少粘度は柔らかいようですが、値段は約4分の1(定価でSHOWA 500cc \2,000, Kawasaki 1L \1,200くらい)。その時に、フォークスプリングを磨くと効果的です。インナーチューブに擦れるところだけでいいので、800番くらいの耐水ペーパーにオイルをつけて磨きます。管理人はさらに1000番で仕上げ磨きをしました。初期作動が軽くなって、乗り心地も良くなります。ジャッキがない人は、片方ずつ開けるとメンテできます。
注意点としては、トップキャップは必ずステム割り締めボルト(フロントフォークのインナーチューブをステアリングに固定しているボルト)を緩めてから外しましょう。そうしないと絶対に外れないです。カワサキのサービスマニュアルって、そういうトコぜんぜん指示してないんですよねー(当たり前ってことか)。ドレンボルトがあるので、フォークを車体から取り外さなくても、一応オイル交換はできます。
便利なツールや、お気に入り用品、ケミカルなども含めて紹介。タイトルをクリックすると、そこへ飛びます。
| スライドヘッドハンドル | ソケットレンチを使用する際の便利なハンドルです。なんとダイソーにもありました。 |
| ヘックスレンチ | バイクに良く使われている、六角(ヘキサゴン)ボルトを締める工具です。 |
| ショックドライバと ピックアップツール |
固~いねじを緩めたりするための叩き用ドライバと、磁石でパーツなどをキャッチするツール。 |
| プライヤー類 | 差替式四徳スナップリングプライヤーと、ダイソーのラジオペンチ三種。侮れないです。 |
| キャリパーピストンツール | キャリパーピストンを抜き取るだけでなく、掃除の時にピストンを回して楽に手入れ出来ます。 |
| ポンチとドライバ用ケミカル |
意外と頼りになるポンチと、(特にプラス)ドライバ用ケミカルの紹介。これでボルト外しは完璧? |
| リヤスタンド | メンテナンス用のリヤスタンドです。使い始めると非常に便利。もう、元には戻れません。 |
| メタルラバーと ガソリン添加剤 |
ゴム部品の潤滑油と、ガソリン添加剤の紹介です。WAKO'S FUEL ONE を追加。 |
| クーラント添加剤など | 冷却水の性能を上げる添加剤と、ラジエーター洗浄剤について。 |
| ワックス | 使いやすい!効果的!安い!と、三拍子そろったワックスです。 |
| シリコンオイル | 安くていろいろに使える便利なオイルです。 |
| チェーンルブ | 定番のRKから、少し変わったところまで。CP重視なのはお約束です。 |
| ハンドクリーナー | シトラスクリーンとオレンジクリーンの対決。結果は.....。 |
| 防塵マスク(レスプロマスク) | ディーゼル車の粉塵まで防護するマスクです。フィルタはお手入れすると長持ちします。 |
| グローブ | 用品店でよくみるグローブ各種。夏用レザーメッシュを追加。 |
| ブーツ | 乗車用ブーツと運動靴ほか。暑い時期、おろそかになりがちなので載せました。 |
| ヘルメット | ライダー必需品。管理人はAraiユーザーですが、メーカーごとの気になる点など。 |
| 革ジャケットとパンツ | 上下を連結して使うため、ちょっと工夫してみました。 |
| 腰用サポーター | そろそろ腰をいたわるべき年齢(?)なので、腰痛予防を期待して購入、使用中です。 |
| 撥水加工剤 | 防水透湿ウエア用の撥水加工剤です。くたびれたレインウエアが復活! |
| 目止めボンド | レインウエアやテント用の目止めボンド、シームコートを使用しました。 |
| パンク修理キット | あってほしくないパンク修理ですが、修理キットを持っていると安心。多少コツが必要です。 |
| ハンドルカバー | 見栄えは悪いですが、快適です。梅雨対策として。本来の使用目的である冬場もGood! |
| 荷箱 | バイク便が使っている荷箱風ボックスを作ってみました.....といっても流用品です。 |
| エンジンオイル | シェブロン シュープリームオイルを使ってみました。モトレックスや純正オイルも比較。 |
| バッテリーチャージャー | 冬場のバッテリー上がりのため、遂に購入しました。あればやっぱり便利です。 |
| 参考書 | これは便利とか、すばらしいと思った本についての紹介です。 |
| 速乾Tシャツ | 暑い時期に快適な速乾Tシャツについて。効果の度合いなど。 |
| 防寒インナー | 最近話題の、汗で発熱する素材のものを、使ってみました。 |
| ワコールCW-X | 疲労軽減・運動能力を向上させるサポーター、使ってみました。 |
| タイヤインプレ | 管理人のタイヤインプレッション。スパーダのタイヤ交換をしたので、アップしました。 |
| ヘッド部分がスライドして使えるハンドルです。両端と真中でヘッドがカチッと止まるようになっており、ヘッドを端に固定してスピンナハンドルのようにして使ったり、また真中にヘッドを固定してエクステンションと組み合わせ、T字レンチのように早回しして使います(写真)。 本物(専用)のT字レンチよりも太めなので、干渉するものがあるときは使えない場合もありますが、だいたいの場合、OKです。 絶対強度は低いので、大きなソケットで本締めするのは気が引けますが、結構使えます。ラチェット機構のついたアダプタと組み合わせれば、ラチェットレンチ代わりにもなります。ただしこの手のアダプタはかなり高いです。 持ち歩くツール点数を減らしたいときには、特にいいと思います。写真は KTC スタンダード(旧型)で、ソケット差込口がくるくる回らないよう、棒に溝が入っています。新型21世紀バージョンは更に強度アップ。Koken のは、力の掛かる方向に強くなるよう、棒断面が楕円になっているようです。 ダイソーで1/4のヤツ(\105)を発見。精度は?ですが、メーカー物のソケットを使えばボルト側は大丈夫でしょう。なので車載用に買いました。(2005.1更新) |
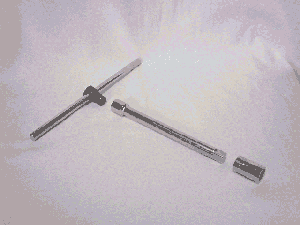 |
|
| ヘックス(六角)レンチです。写真では見づらいですが、長い方がボールポイントになっていて、少し斜めにしても使えるタイプ。選ぶときは絶対こちらにしましょう。本締めは短い方で行います。 左がEIGHT(日本)製。右がPB Baumann(スイス)製。PB の方が圧倒的に有名ですが、右の写真の通り、メッキなどの品質的にもほとんど違いはないです。写真は4mm用ですが、PB が EIGHTの1.5倍くらいするので、浮いたお金で他の工具を揃えられます。 ヘックスボルトは頭をナメるとえらいことになるので、こうした精度のいいものを使うようにしています。リングにじゃらじゃら繋がった安物は使わないようにしましょう。自転車用の携帯ツールは、値段の割にはわりとイイみたいです。なお自転車のパーツで、六角の穴が浅く、工具の掛かりの悪いものがありますが、写真のような先端の面取りがされていない安物の方が、引っ掛かりが良かったりします。 セットになっている6mmより大きなサイズのものは、重要な場所を固定しているものが多いため、しなりにくいソケットのヘックスとトルクレンチで作業します。なお車軸に使われているような、大きなヘックスボルトはソケットが非常に高価かつ、あまり出番がありません。大工センターなどに売っている、長ナットをメガネレンチで回して代用できます。100円くらいで手に入るためコストパフォーマンスは最高です。 |
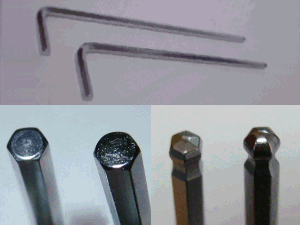 |
| ショックドライバ(インパクトドライバ)とピックアップツール | 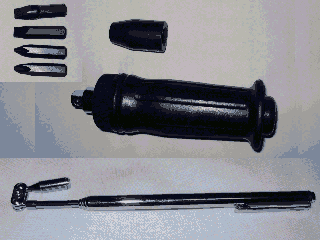 上がショックドライバ。火であぶったりしても全く 緩まなかったビスも、こいつで外せました。下は マグネット式ピックアップツール。先端が自由な 角度に固定でき、何段階か伸びます。 |
|
| ショックドライバ(\1,000 アストロプロダクツ、以下AP)です。 私は基本的に叩きのドライバは使用しない方針です。しかし、中古車のボルトが全く緩まない!といった状況では、仕方ありません。ベツセルなど比較しましたが、使用頻度を考えて、なるべく安く済ませることにしました。 APのショックドライバは、プラス、マイナスビットが2種類ずつ付いています。回転方向のセットは簡単にできますが、確実にセットできたかどうかはちょっとわかりにくいです。軽~いので、耐久性は?? なお、AP多摩店店長のお話によると、これで緩まなかったらあきらめろ、という最終兵器はコーケンのショックドライバ(\5,000くらい)だそうです(APのHPはこちら)。 ピックアップツール(\105 ダイソー)。自由に角度を変えられる先端部にマグネットが付いており、狭い隙間などに落ちた部品をキャッチできます。軽合金等は付かないという欠点はありますが、いざというとき無いと困るので、気軽に買えるのは嬉しいです。こうしたものは精度もそれほど重要ではないし。 また、ダイソーにはボルト、ワッシャ、スプリングワッシャのプラケース入りセット(全て鉄製)を売っていましたので、気になる方は近くのショップを覗いてみてはいかがでしょう。 |
||
| 左がスナップリングプライヤー(\714 パオックコーポレーションSP-15)です。値段は、確か特売だったので忘れてください。スナップリング向けの専用工具ですが、クリップ式チェーンジョイントの着脱時にも使用可能です。 スナップリングには広げて外すものと、縮めて外すものがあり、このプライヤーは真っ直ぐのと曲がった先端を差し替え4通りに使用できます。手間はかかるし、使い勝手は専用品とは比べ物になりませんが、使用する機会が少ないため、管理人にはこれで十分です。但し強度的には不安なので(固着したスナップリングが相手だと先端が曲がってしまう...)、ストレートタイプのものは一流品(KNIPEX)を揃えました。一箇所に力がかからないよう、先端が徐々に細くなるように加工されており、素材の良さとあわせて曲がりにくくなっています。 右はロングノーズプライヤー(各\105 ダイソー)。細いもの、先が曲がったもの、それに幅広のものを使い分けています。いずれも小ぶりで細かい作業の多いバイク向きと思います。荒っぽい作業にも気にせず使えて重宝します。一年ぶりくらいに見たダイソー工具は、ドライバーなどもかなり良くなり、更にラチェットハンドルまであるのに驚きました。作動はチェックできませんでしたが、間に合わせ以上の品質になっているようです。 |
|
 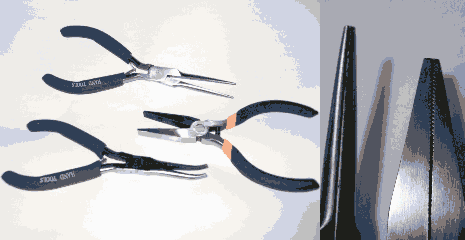 スナップリングプライヤー。差し替え式なので多少ぐらつき いろいろあります。先細と幅広の先端の品質は右側のような感じ。製品のばらつきは ますが、とりあえず使用するには十分です。 かなりありますが、それなりに使えます。いずれもワイヤーカット機能は無し。 |
| アストロプロダクツのキャリパーピストンツール(\2,980)です。 本家(?)は特殊工具メーカーのハスコーから出ている同種の工具と思いますが、ちょっと手が出ない値段なので、半額くらいのコイツで十分です。写真で見る限り、作りもそれほど変わりはないし。 ツール自体は、適合ピストン内径18~40mmなので、殆ど全ての車種で使えるでしょう。本来、固着したブレーキキャリパーのピストンを抜くための工具のようですが、キャリパーを洗うときに、これでピストンをぐりぐり回して、奥まった側のピストン側面についていた汚れが落とせます。 固着の一歩手前だったピストンも、これで回して汚れを落とし、シリコングリスを塗って押し込めば、滑らかな動きが復活します。ピストン内側に傷がつきますが、使用上問題ありません。但し、アルミ製ピストンのキャリパーだと、力いっぱいやるとピストン自体が歪んで問題が起きるかも。 実際の使い勝手を言うと、対向ピストンのキャリパーでは、向かい合ったピストンをかなり押し戻さないとこの工具が入らないため、もう少し頭が短いと良いです。ちなみにヘッドはこんな感じです。 ブレーキの手入れが断然楽に、しかも確実に出来るので、管理人のイチオシです。 (2006.9) |
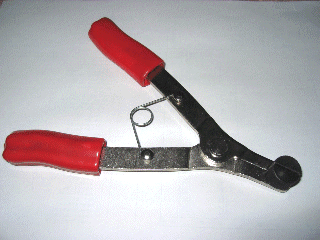 ピストン内側に先端をはめて、握るだけ。 握り部分がもう少ししっかりしていると 良いのですが(よく外れる)。 |
| ゆるめ系工具&ケミカルです。 ハンディポンチ(新潟精機㈱ Sサイズ 100mm \473)です。PB Baumann(スイス)製のものが一流品として有名ですが、こうした普及品でもかなり使えます。ただし最低限、先端を焼入れし、きちんと研がれたものにしましょう。 穴あけの際ドリルのセンターを出すため、あらかじめポンチを打つ、という使い方を普通に思いつきますが、緩まないボルトや、締め付けると頭がねじり取れるボルト(ブレイクオフボルト)をたたき外すのにも重宝します(ボルトの頭はかなり傷つきます)。後者の例としては、ヘルメットホルダーのボルト(写真)が該当します。 エンジン内部の外れてほしくないナットにゆるみ止めとして目打ちをしたりもしますが、管理人にはほぼ関係の無いところ。バイク用には小さいのでいいので一本あると、意外に頼りになります。 SCREW GRAB です。摩擦増加剤とでも呼べばいいのでしょうか? ボルトを緩めるために使用するケミカルというと、ラスペネあたりが定番ですが、こいつは視点を変えてねじの頭、つまり工具との接触面に、摩擦を増加する液体をたらしてねじを外しやすくするという、一見冗談のようなケミカルです。類似品は結構ありますが、一応、オリジナルっぽいこれにしました。同じものがシアーズのクラフトマンブランドでラインナップされているようです。 ざらざらした粒子物質と液体の混合物なので、よく振ってから使用します。意外なことにかなり効果があります。まあプラスドライバの先端をざらざらにコーティングしている商品もありますからね。また火が使える場合は、対象物にバーナーを当てるのも効果的。きつくしまってそうなものには始めからショックドライバを使うのも手です。 (2007. 11) |
 |
センタースタンドが無い車種をお持ちの方は、是非。 写真はJ-Tripのもので、ローラースタンド(JT-121 \12,075)というものです。レーシングスタンドとか呼ばれてもいるようですが、フツーに日常整備に使えます。センスタなしのスパーダの場合、チェーンメンテに要する時間が全く違います。注油・清掃するたび、車体を前後に動かしていた以前の努力が非常に空しく感じられます。 スタンド掛けは一人で出来るのか?と不安なものですが(購入するまで管理人もその一人でした)、物凄く簡単に出来ます。使い方は簡単で、フロントブレーキレバーを紐などでグリップと縛ってブレーキを掛けた状態にしておき、車体を直立させてスイングアームにスタンドのゴムフック部分を引っ掛けます。あとはスタンドのアームを押し下げるだけです。スタンドの保管時も、直立させて置けるので、そんなに場所は取りません。写真のタイプはは持ち手が最も長いタイプ(しかも最も低い位置で使用している)のため、てこの原理でとても軽い力でリフトアップできます(メーカーHPにも動画で説明あり)。 フック部分は、スタンダードがゴムタイプ、他にV字フックが選べます(J-Tripの場合)。V字だと、スイングアーム部分に専用のフックを取り付けないと使えませんが、ゴムタイプのほうはどれでも使用可能です。使いまわすのなら、車体側にフックをつける必要の無い、ゴムタイプの方が良いと思います。 周辺環境を整えてやると、整備が楽に出来るので、車両を良い状態に保てます。きっちり清掃注油してやると持ちが全く違うので、ローラースタンドの代金など、すぐ回収できるはず。 (2006.12) |
 丸いゴムの部分で支えています。金具の 幅を調整でき、殆どのバイクに使用可。 |
メタルラバーとガソリン添加剤
| 右がメタルラバー(CCI)。金属とゴム部品の摺動(しゅうどう)抵抗を劇的に減らすオイルです。 具体的にはブレーキキャリパーやサスペンションのダストシール、オイルシール部分に使います。オイルはものによってはゴムを傷めますが、これはゴムをいためず、ブレーキフルードに混ざっても大丈夫だそうなので、キャリパーのオーバーホールにも使えます。 \1,800 くらいのスプレー式のほかに缶入りタイプもあり、スズキの純正部品として手に入るそうです。私は急いでいたので、NAPS世田谷店で\2,500以上!してたのを購入しました(ときどき値札を付け間違ってるみたい....)。 私はほかに、MTBのフロントフォークについているゴムブーツ(インナーチューブと擦れる部分)にも使っていますが、いい感じで動くようになります。ただ、「持ち」はシリコングリス直塗りの方が良いです。 左はGAS TREATMENT(KURE 清掃・水抜き剤)です。レギュラーガソリンに添加して使っています。使用するとエンジンの回転具合が少し違うので、効果はあると思います。慣れればすぐ体感できなくなる程度の差ですが。もともと色々な添加剤が入っているハイオクを使っている人には関係ないかも。 使用するときは、ガソリンの量をきちんと計算して入れます。分量的にうがい薬(イソジン)の計量コップがちょうど良いです。12L給油で60ccくらい投入します。 フューエルワン(WAKO'S \1,575)を使用してみました。ハイオクガソリンに入っている洗浄剤をずっと強力にしたものだそうで、燃料経路および燃焼室の清浄化による、始動性・燃費・馬力向上が見込めるとのことです。50Lの燃料に対し一本(300ml)添加します。前述の計量コップがあっという間に白濁し、効果がありそうな雰囲気満点です。 スパーダでは始動性は変化なく、燃費はかなり向上。街乗りでリッター当り、平均25km程だったのが27km程度にアップ! が、最後の添加後、数百キロで燃費も元に戻ってしまいました。燃費アップの程度とその持続性からすると、コスト的にはペイしませんでした。CBR600Fでは、燃費の向上は誤差の範囲内.....何故だ。但し、マフラー交換後に感じていた、2000回転前後の引っ掛かり気味の感じが殆どなくなりました。 (2006. 5) |
 |
| ワコーズの冷却水性能復活剤と、ラジエーター洗浄剤です。熱対策になりそうなものということで、手軽に出来そうな添加剤を試してみました。 左はクーラントブースター(R140 \1,575)です。冷却性能復活剤ということで、少し古くなったクーラントに添加して長持ちさせるだけなのかと思いきや、消泡性能が上がり、冷却効率がアップするということなので、試してみることにしました。300ml入りで、冷却水5~10Lに対応。 まずスパーダにてテスト。クーラント交換時にチェックしたところ、添加すると明確にクーラントの性質が変化しました(冷却水交換の項参照)。実際の効果はスパーダではわかりませんでしたが、信号待ちでほぼ必ずファンが回るCBRでは、明らかに作動頻度が減りました。普及品のクーラントでは謳い文句どおり、冷却効率も多少はアップするようです。 右はラジエーターフラッシュ(R120 \1,260)です。冷却系等の錆、湯垢を洗浄するものです。500ml入りで、冷却水容量6~10Lに対応。使い方は、添加後20~30分アイドリングし、排水・水洗後、新しいクーラントを投入するというものです。 黄色い液体で、アンモニア系の臭いが若干します。年数の経っているスパーダに使ってみたところ、目立った汚れは出ませんでしたが、見える範囲では、ラジエーター内部はぴっかぴかになりました。 熱対策で不安を減らしたい方は、安いので、まず試してみてはいかがでしょう?(2006. 9) |
 どちらも気軽に買える値段ですが、 バイク用としてなら、かなりの分量です。 |
| シュアラスターのインパクトです。写真はインパクト・ジュニアという容量の小さいものです。自動車用品を取り扱うところで、ごく普通に見かけます。安いしただのワックスということで、最初は馬鹿にしていたのですが、使ってみると伸びが良くてふき取りやすく、しかもぴっかぴかになります。 SONAXのHart Wax(液状)を以前に使用していたのですが、やはり固形ワックスということで、こちらの方が、もちが良いようです。研磨剤は入っていないのですが、少しくたびれ気味の塗装面も、つやつやにしてくれます。値段も安くて言うことなしです。ずっと使い続けそう。 日本製の撥水コート剤(S●FT99など)は、かなり有機溶剤臭が強めですが、これは芳香剤っぽい香りがして、きつくありません。ふき取りも楽です。保護性能的にはそんなに大差ないかも知れませんが、実際の使用感は抜群に良いです。 使うときは、スポンジ(青い蓋に入ってます)を水で湿らせて、固く絞ってから、ワックスを撫でるようにして少量つけ、車体に薄く、薄~く伸ばします。ふき取りは不織布の専用品を使うと、仕上がりがやっぱり違います。 なお、シュアラスターとほぼ同じ形態の缶に入っている、IMPERIAL(BMD WAXと表記) という固形ワックスは、使用感で若干劣りました。缶の中で端の方からワックスが崩れてくる感じで、伸び・拭き取りもシュアラスターに比べると良くない感じ。管理人は買うならシュアラスターにします。(2005.11) |
 |
| シリコンオイル |  |
|
| グリーンエース㈱のシリコンスプレー(420ml)です。ミシンなどの潤滑、離型材として使用するもので、ホームセンターなどで普通に手に入ります。軽い潤滑に使用しますが、メッキ部品の仕上げ拭きや脱脂する必要のないパーツの汚れ落としにも使っています。 KUREの5-56のように臭わず、べとつかないのがいいです。5-56のノンテフロンの安いやつは、外れのノズルがあるようで、噴射するより垂れる方が多いものがあるようです。今もっているのがダメなやつなので、しっかりとスプレーできるこちらを多用しています。あとシリコンオイルなので、5-56で傷む恐れのあるプラスチック、ゴム部品にも躊躇せず使えます。古いワイヤーグリスを流すのにも使用しています。 耐水性は全くないので、ちょくちょく注油することになるでしょう。値段が安いのが最大のポイントです。写真のものはホームセンターで\200位で購入しました。 ドライブチェーンの手入れ後、外側プレートに付いた余分なチェーングリスを、これを吹き付けた布で拭き上げたりもします。RKホワイトグリスも簡単にふき取れます。ホイールにあらかじめ伸ばしておけば、飛び散ったグリスも多少はふき取りやすいです(あくまでも多少)。街乗り自転車なら、「持ち」は悪いですが、これ自体をチェーンオイルとして使用することもできます。フレームを拭くときにも使います。 ものによりますが、シールをはがした後の粘着材も、これを吹き付けて布でこすれば、結構楽に取れます。 KUREのシリコンオイルスプレーも安いので同様に使えそうです。 |
||
| ライダーにとって一番身近なケミカル、チェーンルブ(チェーンオイル)の比較をしてみました。 RKリフレッシュホワイト 420ml入り。いわずと知れた定番商品。メーカー推奨なので安心できる上、意外に安価 → NAPSのセールで\1,554(\3.7/ml)。通常のクリアタイプより飛び散りにくいとされています。これは注油後一日くらい置いといた方が良いようです。チェーンを真っ白けにして走っている人もたま~に居ますが、余分は布でぬぐっておきましょう。管理人はスプレーしてから布でチェーンをつかむようにして拭いています。ちょっともったいない気がしますが、潤滑が必要なのはシールのあたりのみ(あとローラー部)なので、他の部分についているのは飛び散るだけだからです。特にアウタープレートのは基本的にふき取ります。 チェーンルブロード(モチュール、クリアタイプ) 400ml入り、NAPS通常価格\1,890(\4.7/ml)。管理人の近所の用品店では最近見かけるようになりましたが、クリアタイプでは今まで使用した中でこれが最強です。ホワイトタイプでも若干の飛びはありますが、こちらは超高粘着タイプとかで、注油後きちんと余分を拭き取っておけば、飛びちりはほぼゼロです。ホイールをきれいにしておきたい方には特にオススメ。但し、飛び散ったこのルブは石鹸で軽く洗った程度では落ちなかったし、注油時の臭いもかなり独特な(危険そうな)感じなので、保護ゴーグルでもして作業したほうが良さそう。そのため雨天走行でも簡単に流れてしまうようなことはありません(注油後の持ちも良い)。 ついでにクリーナーを見てみると...... RKチェーンクリーナー 300ml、NAPSのセールで\819(\2.7/ml)。他社クリーナーより粘ついた感じで、乾ききったしつこい汚れに効きそうです。 チェーンクリーナー(KURE) 管理人のオススメ。480ml、\714(Unidy、\1.5/ml)。ホームセンターで普通に手に入り、Oリング対応では一番割安のようです。性能的にも問題なし。(2005.7) |
 左からMOTUL、RKホワイト、同クリーナー。 |
| KUREのシトラスクリーンと、CCIのオレンジクリーンです。 かなり前に購入したものなので、両者とも値段はわかりません。たしか実売価格はCCIの方が安かったと思います。その使用感はというと.....。 シトラスクリーンは軽石成分が入っていて、かなりざらついています。暫くこすって水で流すと、真っ黒だった手が見違えます。ラノリンという成分(羊毛の油らしい)が入っていて、肌に優しくなるようになっています。 オレンジクリーンは、安かったので買ってみました。使い心地はまあまあです。汚れは落ちます。が、汚れを落とした後のヘドロ状の洗剤が、結構手にこびりつきます。注意して洗い流す必要があります。 あらかじめ手を汚さないようにするには......管理人はラテックスゴム手袋を使用します。 宇都宮製作㈱のシンガーラテックス(ST No.24 100枚入り \1,200)です。内側にすべりの良くなる粉がふってあり、装着しやすいです。イメージ的にはお医者さんが手術で使うような手袋です。基本的に使い捨てですが、2回目くらいなら張り付くことなく着脱できます。これもオススメです。 |
 |
| 用品店などでよく見るレスプロマスクです。 交換式の活性炭フィルターで、有毒物質まで吸着してしまうもの。アレルギー性鼻炎である管理人にとっては、市街地走行には欠かせないものです(ないとくしゃみが止まりません)。 ラインナップはネオプレン製のシティマスク(写真 \5,565)、スポーツタマスク(\6,195)と、他に布製バンディットスカーフ等があります。シティはモーターサイクル用、一部メッシュのスポーツタは自転車などより汗をかくスポーツ用らしいです。呼気を排出するバルブも少し違います。いずれも、首の後ろのマジックテープ部分には汗をかきます。 シティマスクの標準付属品はテクノバルブというヤツですが、写真のはブリスターパックのものではなく、破損パックを国内で再袋詰めして販売している方です。バルブは白いの(新型?)が付いています。普通の物はひねって固定するタイプですが、これは単に二つの部品を押し込んではめ合わせるだけ。 結論から言うと、このバルブ、使えません。なんとマスク本体と、フィルターが簡単に外れてしまいます。おまけに内側の黒い部品がまっ平らなので、顔に当たるとかなり違和感があります。そのため、通常はスポーツタ標準のパワーバルブ(写真ではマスクに装着している方)を使用しています。 レスプロのHPを見ると、フルフェイスヘルメットにはテクノバルブを使うように書いてありますが、パワーバルブでも使用可能。バルブの分解・清掃方法はここで知りました。日本語の説明書をつけてくれればいいのに。HPでは、フィルター内蔵スカーフは煮沸して再使用とあるので、他のフィルターも同様に出来るかも.....と思い、少し使用したフィルタを、熱湯で洗ってみました。すると、お手入れなしだと汚れがフィルターを素通りするような感じになってくる時期になっても、まだまだ使えます。 なお、冬場にMTBで息があがるほどに走ると、マスクの中が結露して恐ろしく苦しくなります。なんかいい手立ては無いかなあ? |
 標準で付いていたバルブは使えません。再パック品 だからか?とてもコストの安そうな部品です。 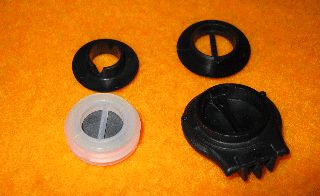 固定方法が違います。左はV字溝にはめ込むだけ、 右側は突起を合わせてからひねって固定します。 |
|
| 左から、SPIDI 3COMPOSITE(\19,800)、JRP DR2(\10,000位)、GW SPORTS マックスプロテクトグローブ(GSM6103A / \6,800)、MechanixBrand PROFIT GLOVES(\2,646 税込)です。 |
|
|
SPIDIは高いだけあって、操作性抜群。内側に当たる部分がなく、補強革を含めカッティングが良いので握るのが楽。甲が固めですが、ミンクオイルを部分的に塗っておくと、馴染みが早いです。プロテクターは小さめのが付いています。デザインの好みは分かれると思いますが.....。 似たコンセプトのものに、Buggy EP-218/219があります。私は指が細めですが、グローブの形自体が手に合っています。また手の甲側はプロテクション用に指先までクッションが入っていて、これが保温効果もあり、市街地なら冬場もOK。コストパフォーマンスも良いです。 JRPは上野で購入。現行DRNが後継改良タイプ。手の平が鹿革、甲が牛革製で、吸い付くようなフィット感です。メーカーHPはこちら。 長所は、鹿革のため、厚手(強度がある)なのにとても柔らかくグリップできること。また、手の平の当て革が正しいグリップ位置を教えてくれます。短所は、ずばり色落ちです。淡色のウエアでは、袖口がまっ茶になります。シーズン毎にお湯洗いして3年ほど使用していますが、色落ちは止まりません。また、手の平の衝撃吸収材のため、微妙なクラッチ操作がやりづらい様に思います。 多少欠点もありますが、落ち着いた雰囲気のものでいいなら買って後悔しないグローブだと思います。 その後、上記の衝撃吸収材を取り去りました。これでほぼ管理人の理想の街乗りグローブに(こんな感じ)。 |
 ウィンターグローブは使いません。スリーシーズン用の ワンサイズ大きめのものに、Goldwin の ポリプロピレン インナーグローブを併用しています。操作感が悪くなら ないので、お勧めです。 |
|
GW SPORTSのは、夏用メッシュグローブだけあって、素手のような感覚で操作できます。 新品時は、指の付け根の手の平周り部分が若干きつく感じました。あとメッシュ部分は写真のように、すぐ日に焼けて色が変わります。右手の人差し指・中指(変色しています)と、薬指・小指で色が全く違います。 MechanixBrandのはその名の通り、メカニック用のグローブです。しかし管理人は、MTB用メッシュグローブとして使用しています。平側が一枚ものの人工皮革、甲側が伸縮性のメッシュです。作業用に使うには勿体無いです。値段も手ごろで、耐久性も期待できそう。 |
|
| RSタイチ レザーメッシュグローブ RSタイチのベロシティレザーメッシュカーボングローブ(RST359 \7,140)です。 通常、夏用グローブというと化繊メッシュものが多いですが、指先から擦り切れて1シーズンでだめになることが多いですね。そこで今回は指先が革で出来ている、このグローブを選んでみました。指の股はメッシュになっています。手首の関節外側の骨の所に厚手のパッドがありますが、他は短めになっているので腕時計をしていても問題ないです。山羊革自体はかなり薄手ですが、夏用として考えれば充分。管理人は牛革とかなり違うこの匂いが好きです(^_^)。お値段は高めですが2シーズンの使用に耐えるなら、それほどコストパフォーマンスは悪くないのでは? しばらく使ってみて、手の平側の革が、少し余り気味。他はフィットしているのに、ここだけ少しだぶつく感じがして、多少違和感があります。恐らく街乗り用ということで、キツイのを嫌がるユーザー対策に、ゆったり目に作っているのかも? また山羊革自体が、少し伸びやすいのかも知れません。 しかし全体としての満足度はかなり高く、耐久性がOKならば、次も指名買いしてしまうかも。 (2007. 6) |
 |
| グローブを紹介しておいて、ライディング用シューズ・ブーツを載せていませんでした。 左から、Coleman(登山靴)、PLICANA、SIDI、Alpinestars(ブーツ)です。見ての通り写真はいずれも左足用。左側の二つは、ちょっと(かなり?)ヤレれてますが、まだまだ現役で使えます。 |
||
Coleman これはトレッキングシューズというか軽登山靴です。\10,000位だったと思います。乗車用としては、かかとが付いていればなお良いです。これに elf のシフトパッドを併用しています。しっかり装着しても少し浮いたりしますが、靴のもちが違います。また、これが無いと靴が傷むだけでなく、長時間乗車ではシフトレバーと当る親指の辺りが痛くなるはず。 管理人はバイク用短靴は使いません。それは、この手のシューズはとても歩きにくいからです。そのくせブーツほどの保護性能はありません。なので、歩きを重視する際はこうした軽登山系の靴で、プロテクションを重視する(殆ど歩きがない時も)場合はブーツで乗車しています。 PLICANA 上野のバイク用品店コーリンのブランド。品番不明で確か\21,000位。むかーしのブーツといった感じで、前後にシャーリングは入っていますが、スネ、クルブシ部分の硬質プロテクターはありません(ソフトパッド入り)。なので、保護性能はそれほどでもないと思いますが、その分、歩きやすくはあります。一応本革製(表牛革、裏豚革)。なお雨水は、ばっちり浸入します。 |
 |
|
|
WARRIOR(SIDI) 梅雨対策として購入(\22,000位)。合皮製で、テポールという防水透湿フィルムを内蔵していますが、しばらく使用していると、ばっちり浸水します。本格的な雨のときは、ブーツカバー併用でないと駄目です。管理人はサイズ42でジャストフィット。SM-X3 より足首(関節)部分が若干きつめかな? スネと、クルブシ部分に硬質プロテクターを内蔵しており、レーシングタイプに準ずる感じで結構硬めですが、多少は歩けます。かかと後部に再帰反射材あり。 同系統で Champion というハーフブーツ(\20,000位)もあります。落ち着いた感じのものが好みの人にはどちらも良いと思います。 SM-X3(Alpinestars) 合皮製。レーシングブーツらしく、かなりがっちりしています。そのため、最大のプロテクションが欲しい場合に穿きます(当然か)。見ての通り動かしやすいようにシャーリングが足首回り全体に施されており、サイドの硬質プレートで、左右への動きを規制しています。基本的に歩ける靴ではないので、乗車専用です。管理人は足の大きさ(長さ)に対して、足の甲周り寸法が細い(つまり細長い)ので、42(約26.5cm)サイズで、少し厚手のソックスを穿いているとちょうど良いです。インソールで工夫すると良いかもしれません。雨天未使用。 なお管理人は暑い時期でも最低限、足首を完全に覆う靴で乗車するようにしてます。これからの時期、きちんと配慮したいものです。(2005.7更新) |
||
| ヘルメット | |
| ライダーに絶対欠かせない用品、ヘルメットについて。 今年の夏は移動で走ることが多かったので、ジェットヘルを導入しました。かなり楽です。その購入時に、店頭で色々比較してみたところ、メーカーごとに特色があるようなので気がついた点を書きます。 自転車向けヘルメットを使用される方には常識でしょうが、海外製品は欧米人の縦長頭に合うように出来ており、国産OGKの方がしっくりくる、という方が多いのではないでしょうか。今回、モーターサイクル用ヘルメットで改めてチェックしてみたところ、メーカーごとに傾向が見られました。 ショウエイJ-Forceでは、管理人が試しに被ると頭の横が強く当ってしまいます(横がぴったりだと前後がゆるい)。つまり外国人向きというべきか、縦長の頭に合うような感じでした。 対してアライはどうかというと、内部形状はまん丸で、管理人の頭にほぼぴったりでした。知人のショウエイ派ライダー(J-Force&X-Elevenユーザー)に聞くと、やはりジェット・フルフェイスともアライよりしっくりくる、ということなので、恐らくフルフェイスも同様の傾向と思われます。 形状面から行くと、ジェット派・フルフェイス派に分けられるかと思いますが、内装のフィット感からすると、上述したようなメーカーごとの「色」があるようです。管理人は、ショウエイで気に入ったモデルがあっても被れないかもしれません。なおOGKは、特に廉価版で頑張っている印象がありますが、試着もしたことが無いので良くわかりません。(2005.9) |
 |
| 革ジャケットとパンツ |
|
| 装備品で小ネタをひとつ。 革ジャケットと革パンツは、連結できるようになっているものが多いですね。でも同一メーカーでも、互換性が無い場合があります。写真は、現在管理人が使用中のSPIDIのもの。ジャケットの方が新しく、腰周り全周で連結するタイプ。対して革パンの方は背面部分のみで連結するタイプ。当然、連結できませんが、せっかくあるのだから繋ぎたいのが人情です。 連結用ジッパーには、単独使用時にジッパーが他に引っかからないよう、ダミーのジッパー片割れが付いてきます。そこで、それぞれのジッパーの片割れ同士を縫製して、間接的にジャケットと革パンを連結できるようにしようと思いつきました。 縫製は通常のミシンで慎重に縫いました。ジッパーがミシンの押さえ金具に引っかかるため、完全に思い通りの部分では縫えませんでしたが、縫い目を二列にして縫合完了。これだけでは不安なので、皮革製品用のリベットを東急ハンズにて購入(\94/20セット入り)。厚みのあるものを固定する、軸が長いものと、薄いものを固定するものがあり、今回使用したのは後者(「並」の表示あり)です。 千枚通しで穴あけした後、リベットを通して金鎚でカシメます。リベットは軸の長い側とキャップのように短い側があり、軸の長い方を下にして、キャップ側を金鎚で叩きます。下には布などを敷いて傷付きを防止しましょう。ジッパーから少し離さないと、金具が引っ掛かって走らなくなります。 出来上がりは写真の通り。かなり頑丈にできて、満足です。まあサーキットなどは走らないので、これで十分でしょう。 |
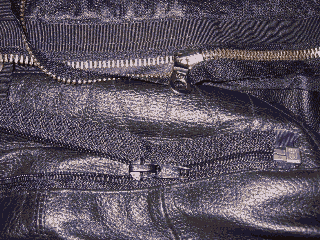 上がジャケット、下が革パンツのジッパー。互換性無し。  両端は力がかかるところなので念入りに補強しました。 |
| 腰の保護(腰痛予防)用サポーターです。 ご存知の方も多いでしょうが、モーターサイクル、バイク(自転車)では、背筋を使い、腹筋は殆ど使わないため、筋力のアンバランスにより、腰痛を起こしやすいです。その対策として、根本的には腹筋を鍛えるのがまず第一ですが、補助的な対策としてサポーターがあります。 写真は、REGUARD(アルケア㈱)というサポーターのラインナップにある、LUMBER GUARD(WG-3 \5,140)。この手のタイプとしては、調べた限りでは最も安価なものです。試着できるスポーツ用品店で購入。 実際の装着は、面ファスナー(ベルクロ)で本体を腹に巻きつけ、背中から腰の両脇まで伸びる補助ベルトを引っ張って面ファスナーで本体へ固定します。こうすることで、補助ベルトのテンションで腰を安定させつつ、呼吸も苦しくならないという優れものです。 で、実際の使用感はというと、まず、普段着ている服(特に腹回り)がぴったりだと、装着するのはちょっと厳しい感じ。あと、サイドの補助ベルトのテンションの掛け方が、結構微妙です。あまり強く補助ベルトを引っ張ってセットすると、かえって腰が凝る感じがします。程々にしたほうが良いようです。(2005.6) |
 |
|
| 防水透湿ウエア用撥水剤、NIKWAXです。英国製。 防水剤専門メーカーということで、前々から興味がありましたが、その効果のほどは? 写真は、専用洗剤と防水剤(スプレー式)がセットになったお試し版(\1,470)。標準ではレインウエア(上下)一着分を加工できます。同社の防水剤には透湿性能をスポイルする商品もあるので注意が必要です。スプレー式のもののほかに、洗剤のように洗濯機で使用して処理するものがあります。いずれも水溶性で安全性は高いです。アウトドアショップなどで手に入ります。 今回は、2年ほど使用したGoldwinレインウエア上着と、SPIDI撥水(防水ではない)ジャケットに施工。あと通勤で使っていたKappa防水透湿(一応)ウィンドブレーカーも一緒に処理しました。 防水処理 中段は、処理前の写真です。レインウエア(中)は、撥水効果が薄れてきており、多少の雨なら弾きますが、水「玉」にはならず、長時間水に触れているところは、徐々に布地に広がって生地自体が濡れてしまう状態です。 撥水ジャケット(右)、ウィンドブレーカー(左)は、雨天未使用なのでまあまあの状態です。 まず、防水処理の前に衣類の汚れを落とします。普通の洗濯洗剤かすがあると、防水処理に悪影響があるとのことで、専用洗剤を使うのですが、普通に洗うだけ。今回は説明書の指定よりも大目の衣類を処理するので、予めタライに濃い目に溶いた洗剤で下洗いし、その後に洗濯機にかけてみました。 洗濯後に撥水剤をスプレーするのですが、衣類が濡れた状態のまま方が効果的だとのこと。水ベースの薬剤なので、生地の水分に乗って、雨が染み込みやすいところに薬剤が染み込むという寸法です。スプレーなので、濡れてよい場所でやりましょう。難しいことは何も無く処理終了。 作業結果 最も変化があったのは、やはり劣化の進んだGoldwin雨合羽で、処理前は「撥水」というより水が全体に載っている、という感じでしたが、処理後は水玉コロコロで、布地をはたくと全て飛ぶようになりました。 SPIDIの撥水加工ジャケットは、雨天未使用なので撥水性能はもともと良かったのですが、水玉が一層落ちやすくなりました。雨の降り始めから合羽を着るまでの間、持ってくれそうです。 Kappaは、自転車でリュックを背負って使用した関係上、両肩と背中が劣化していましたが、その部分が回復しました。 あと性能には全く関係ないのですが、処理後の衣類は、木工用ボンドっぽい臭いが付きました。これは使用していくうちに和らぎます。性能的には処理剤の値段を考えると、かなり満足です。処理後の耐久性としては、丸一日ずぶぬれで使うような状況だと、やはり生地に染み込みますが、一度乾かすと、そこそこ復活します。日常的なお手入れの際に、時折使ってやると良いようです。 なお、Goldwinの合羽については、コンパクトレインスーツ(\10,000位)よりも、ひとつ上のグレードの方が、かなり持ちが良いようです。そのため梅入りを考慮し、上級グレードを購入したので、今回処理したものは予備として使用する予定です。(2005.4) |
 ジャケット2着分の選択洗剤とスプレー式防水剤のセット。 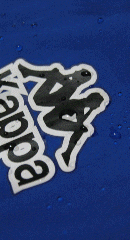 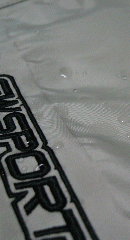  加工前のジャケット撥水状況。右から、SPIDI、Goldwin、Kappa。 Goldwinは、水玉コロコロといった感じはなく、すぐ生地に染み込みます。  加工後のレインウエア。初期撥水性が回復しているのがわかります。 他のは劣化が少なく、写真で見てわかるほどの差は無いため省略。 でも水の弾き方には明らかな違いがありました。 |
|
| アライテントのシームコートA-405(\420)です。 テントやレインウエアの縫い目の目止め剤です。雨の染みる場所に塗って、溶剤が抜けると、固まります。本当は縫い目を目止めしているシームテープ自体が欲しかったのですが、素材店・登山用品店等見た限りでは在庫しているところはありませんでした。東急ハンズでは、「そんな特殊なものは、ない」と言われました。みんな修理しないで買い換えるのかなぁ? この商品について言うと、ボンドタイプということで、広い面積は苦手です。というか、管理人は上手く塗り広げられません。今回補修するのは、合羽ズボンの股部分。縫い目自体ではなく、目止めテープ端辺りの生地(裏地コーティング)が、剥がれて無くなっています。このため、表地から殆ど直通で雨が入ってきます。そこで、このコート剤を塗ります。一度塗りだと不安なので、乾燥後、盛り上がるまで二度塗りしておきました。 効果のほどは、ばっちりです。水漏れしていた部分が小さかったせいもありますが、2度の塗り重ねだけで、防水性は完全になりました。ただし、長期の耐久性についてはあまり無いようです。補修するところがもともとこすれる部分なので、コート剤もやはり剥がれます。場所にもよりますが、10回着用くらいは耐えるのでは? よく使うものは、こまめに補修してやる必要性ありです。 その後の補修で、シームテープ代わりにハーネステープを使ってみました。キジマの補修用シームテープ(4m \630)もあるようですが、店頭では全く見かけません。シームコートは擦れるとすぐに浮いてきてしまうので、ハーネステープで上から押さえてしまおうという魂胆です。 雨天使用2日目に一部が剥げ始めました。しかし、生地を伸ばしながら圧着してやると戻ります。濡れた時の伸縮率の違いで、浮いてしまうようです。補修としては強度が足りませんが、嫌なべとつきも無く、応急処置としては有効だと思います。 (2007.10更新) |
 チューブに入った目止め剤。無色透明ですが、 つやがあるので目立ちます。  目止めテープ脇の黒い部分が浸水部分。 一応、二度塗りしてあります。 |
岡田商事製パンク修理キット(TTO-331 \3,500位)です。 炭酸ガスボンベが3本付いて、180サイズのタイヤも充填OKというもの。このキットの売りは、修理で埋め込むプラグがアンカータイプ(碇型)であることで、棒状の修理剤に比べ、プラグ自体の引っ掛かりがよく、大きな傷にも対処できるという点。その分釘の踏み抜きなどには挿入しづらいかも? 使い方は、 1.付属の錐で穴を広げる。 2.プラグに接着剤をつけ、挿入器具を兼ねる錐で、穴に押し込む。 3.出っ張った余分を切り取る。 ポイントは、付属の錐で穴を広げる時に、延々5分くらいぐりぐり回すこと。プラグが押し込めるようにタイヤ内部のコードを広げるわけで、これをやらないとプラグを差し込むときにゴムプラグが切れます。 もうひとつは、潤滑のためプラグの頭にもたっぷり接着剤を塗ることと、プラグを差し込むとき回さずまっすぐ押し込み、まっすぐ引き抜くことです。 一度やればコツはすぐつかめますが、初回に上記注意点を無視してやるとかなり厳しいかも(管理人も一回プラグを切ってしまいました。プラグ両端が碇型になっているので、反対側でもう一回出来ます)。 修理後100km走行のタイヤはこの通り。説明書では修理後の許容走行距離400kmとありますが、使えるうちは走ってしまいますよね。 写真下はマルニ製キット。 修理用チップが別売りであるのが良い。というか普通、消耗品は単品売りするでしょう。岡田商事のモノは補充チップがないです(がーん!!)。仕方なく新たにマルニの修理キットを購入しました。 器具の形状が違ったりしますが、使用手順は前者と変わりはありません。必要があって早速使ってみましたが、釘が刺さった所への修理用チップの押し込みは、かなり楽ちんでした。入れ易いので抜け易いというのでは困りますが、弾頭型のチップは通常の棒状補修剤より、芯が入っていて抜けにくいようです。自分で修理するのは釘の踏み抜きだけだと思うので、管理人はこちらで十分です。 (2006.12更新) |
 修理キット。右から、剃刀, チョーク, セメント, 錐, プラグ, エアアダプタ, ボンベ, 網。 チョークはパンク位置マーク用。網は、充填 する時に冷えるボンベから手を保護する物。  |
| 雨用グローブ使用に換えて、ハンドルカバーをすることにしました。 防水を謳うゴアテックスグローブでも、「完全防水」ではなく、染みてくるのが遅いだけです。雨中を一日走らざるを得ないような状況だと、全く意味がありません。従って、ハンドルカバーをして、通常のグローブ(管理人は夏用メッシュグローブ)を使用することにしています。冬暖かいというメリットもあります。 写真は、ホンダアクセス製のずばり「ハンドルカバー」(08T55-GEG-000)で\2,500位。適応機種は一応、CD125T・CD250U になっていますが、ネオプレン製の口を広げて入れるタイプなので、はまらない車種を探すのに苦労するはず。以前、バイク便でCBR600Fに装着しているのを見ました。さすがに似合いませんでしたが.....。 装着後に注意する点は、キルスイッチがOFFになっていないか(右側)、ハイビームに切り替わっていないか(左側)、を確認することです。アクセル、レバー操作がスムーズかも必ず確認します。管理人のスパーダは日常的に使用しているので、当然、雨の日も乗ります。なので、見栄えより実用性重視で行きます(想像以上にラクになります)。梅雨対策はこれで大丈夫かな。(2005.5) |
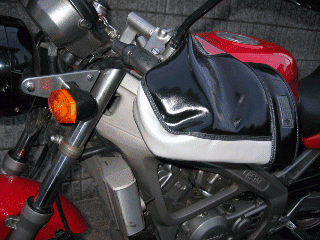 |
|
| 自作の荷物用の箱です。バイク便の箱をまねて、市販のRVボックスに荷掛けフックを取り付けました。取り付けは平ゴム(片側にフックの付いたゴムバンド)でくくり付けます。これはNAPSで1本\525でした。見栄えはイマイチですが、車種を選ばず使える利点があります。何より安い! RV BOX400(アイリスオーヤマ、\1,030位) ステン六角穴付きボルト(M3×10 50p \336 使うのはこのうち8本のみ。) バラ回転コート掛(和気産業㈱ BH-618 \105×4p) ステンワッシャー(M3 \3×8p) ステンナット(M3 \5×8p) RV BOXは、28L収納でサイズはW420×D375×H330mm、ヘルメット1個がぎりぎり収納可能な大きさですが、車体につけると結構大きく感じます。防犯面では南京錠をつけました。気休めにしかならない感じですが。 実作業は、まずコート掛(金具)をボックスに当て、穴位置を決めます。錐で穴を開け、ステンナット、ワッシャーを内側に当ててから、ボルトを通します。きちんと留めた後、シリコンコーキング剤を塗って、ゆるみ止め&荷物の傷つき防止としました。コーキング材の色は透明のほうが良さそう.....。 実際に使用するに当っては、底にセルスポンジを貼り、シートへの負荷軽減を図り、また内部の底には工具用の滑り止めマットを使用しています。本当は後ろに反射材を張りたいところですが、あまりコストを掛けたくないのでそのうちやるということで今回はパス。防水性は、蓋が結構深めなので大丈夫です。見栄えを気にする方には向きませんが、荷物を放り込むだけで良いので、かなり便利です。 (2005.8) |
 ヘルメットがちょうど1個入る大きさ。 意外としっかり車載することが出来ます。 |
| MOTOREXオイル 国内ではデイトナの販売している、スイス製オイルです。 POWER SYNT 4T(写真)。同社最高級グレードの化学合成油です。定価 4L \6,300(Rough & Road通販で安いです)。色はあめ色で、糸を引くような感じです。純正オイルは、結構すぐにへたった感じになるのに対し、値段の差以上の長期耐久性(もちろん性能差も)があります。管理人は走行距離ではなく期間で交換することが多い(距離を走らない)のでこれは重要。 始動時は若干固い感じ(10W-60のためか)で、純正オイル &SuperZOILと体感的には変わらないです。 POWER SYNT は走行2,000kmほど、7ヶ月使用で交換しましたが、純正オイルは同程度の使用でシャバシャバになっていたのに対し、オイルっぽさが残っています。残量確認窓から見える色は、純正が殆ど黒の濃い茶色に対し、モトレックスはキャラメル色で、もう少し使えそうでした。純正オイルでは金属粉が僅かに見られましたが、それも全くありませんでした。また、純正は温度が上がってくるとへたって柔らかすぎる感じがあったのが、それもありません。保護性能、長期耐久性については、かなりオススメできます。二週間ほど乗らずに放置しても、始動時に少し苦しそうな純正に対し、油膜が多く残っているのか普通に始動します。 TOP SPEED 現在使用中なのが、下位グレードの鉱物油ながら合成油並のパフォーマンスという触れ込みのオイルです。何と濃緑色。入れた感じは粘度(10W-40)の関係からか若干柔らかめです。気付いた点ですが、冷間時と温間時の性能の変化が激しいのか、外気温が冷たいとニュートラルの出方が少し悪い感じ。完全にエンジンが温まると問題ないので、今のところ許容範囲内です。以上、POWER SYNT や WAKO'S 4CT では感じなかった点。 純正オイル派の方は、HONDA ULTRA S9(但し見たのはいずれも20W-50)が、ホームセンター等で安いようなので(\1,000ちょいで売っていました)、コストを考えると良いかもしれません。 シェブロン シュープリーム(写真下 Shevron SUPREME) 激安アメリカ製オイル。なんでもアメリカ産の原油は潤滑油に適した組成(一部例外あり)だそうで、添加剤とかたくさん加えなくてもエンジンオイルに使用できるので、安価で高性能、ということです。で、こちらのオイルは会員制小売店コストコにて販売されていますが、そこから仕入れて通販している業者から購入しました。近所のNaps世田谷店では、普段は置いてあったのに、セール時は高級オイルだけ並べてコイツは隠してるようなので探しても無いでしょう(^^)。 肝心のオイルですが、VTの街乗りでの使用ではまったく問題なく、2,000kmで交換しましたがもう少し使えそうな感じ。シフトフィールが悪かったり、タペット音が大きくなるなどもなかったです。直前に使用していた合成油でシフトフィールが良いのが売り(メーカーによれば)のワコーズ4CTと比較しても、違いはわからず、ほぼ同等と言っていいと思います。値段を考慮すればシェブロンの圧勝です。あと使用後のオイルは汚れを落とす性能が良いのか、まるでディーゼルエンジンの廃油のように真っ黒けです。性能に関しては、まったく問題ないので、これからはシェブロン一本やりになりそうな気配。 (2007. 7更新) |
  |
| ちょっと遅くなりましたがご報告を兼ねてレポートします。 実は恥ずかしながら、冬にCBRのバッテリーが2回、上がってしまいました。 1回目はガソリンスタンドで直結してもらい、即NAPSへ行きました。そこで今更ながらバッテリーの高さに愕然とし(要は先立つものが無い)、その半額で購入できる充電器(YUASA MB-1212 \6,750)に目を付けました。 これから暖かくなる季節だし、充電器があれば、最悪またバッテリーが上がってもなんとなかなる、という希望的観測で、こういう選択をしたわけです。しかし一度あがったバッテリーは上がりやすく、少し寒さが戻ったら、たちまちあがってしまいました。バッテリー端子を外し忘れた私が悪いんですが.......。 で、意外に早く出番の回ってきたチャージャーですが、使い方は簡単。車体から外したバッテリーにつないでおくだけです。あとは表示が青になるまで置いておくだけ。充電中は水素が発生するというので、風通しの良いところに置きましょう。私は自室でやってしまいましたが。 間に合わせとしては良いのでは? バッテリー替えれば(買えれば)済むことですがね....。 と、言ってましたが、弱ったバッテリーは部品に余計な負荷を掛ける、という話を聞き、新しいバッテリーを買いました。それにこの暑さでファンが恐ろしく良く回るため、ちょっと走ったくらいではあまり充電されないのです。冬場はバッテリーに厳しい、とよく言われますが、夏も決して優しくは無いということですね(特にフルカウル車)。 |
 これは、一番安いユアサ製。複雑な機能はナシ。 |
| お勧め書籍です。以下、左から順に。 バイクメンテナンス(小川直紀著/山海堂) 良くある内容の本とちょっと違うのは、常識集みたいな内容がついていることです。サービスマニュアルには記載のない細かい所(例えばワッシャーの表裏の使い分け方、折れたボルトの抜き取り方など)が解説されているのがポイント。メカ初心者にはありがたい本です。 ハイパー2ストエンジンの探求(つじ つかさ著/グランプリ出版) 純粋に読み物として面白いです。なんでホンダがあんなに強いのか、その一端が垣間見える気がします。メカ好きの人にオススメ。 バルブタイミング(藤沢公男著/グランプリ出版) 4ストロークエンジン整備で欠かせないバルブタイミング調整に絞って解説。エンジン全バラする前に是非。データは車向けで書かれていますが、2輪も基本は同じなので役立ちます。 ミニバイクを手に入れていじろうと思ってたときに買った本ですが....。 |
 |
| 例の、汗をかいてもすぐ乾く、というやつです。 左がGoldwin(GW Sports)のクールマックスTシャツ、右がご存知ユニクロのクールマックスTシャツです。 Goldwinのものはいくつかグレードがあり、\3,000~\3,900くらいです。写真は\3,800のもの。体に当たる内側が細かい目の織り方、外側は放散しやすいよう粗めのメッシュになっていて、構造的にも速乾性があります。値段だけの価値はあるTシャツです。 ユニクロのは\1,000です。単純にクールマックス素材を使っているだけですが、速乾を謳っている他の同社製Tシャツより確実に効果を体感できます。\700くらいで売っている安いドライTシャツは全く効果がわかりませんでした。クールマックスのタグを確認して買いましょう。(2003年現在) 普段使うのは、ユニクロでもいいかな、と思います。 |
 |
防寒インナー(ブレスサーモ)
| 体から蒸散される水分を取り込み、発熱する素材を使った冬用のインナー(アンダー)ウェアです。 右がミズノのブレスサーモ(ミドルウェイト/\4,800)、左がユニクロのヒートテックプラスタイツ(\1,500)です。 ブレスサーモはさすがに暖かいです。革パンツの下に着ると、暖かいうえ脱ぐのが楽になります。着用していれば、冬場に峠に走りに行っても体はOK! こちらは用途別に三種類、ライトウェイト(\3,900)、ミドルウェイト(ウィンタースポーツ用/\4,800)、エキスペディション(極寒用/\5,800)があります。ライトウェイトは、スポーツ時に通年着用するコンセプトのようです。 ユニクロのヒートテックの方は、当然グレードはありません。冬の目玉商品('03~'04)として売り出されています。セール初日に1着試しに買って(\800以下でした。)良かったので、追加で買おうとしたら売り切れていました。値段を考えればかなり良いです。厚みとしては、ブレスサーモの薄手のものと同等くらいだと思います。自転車通勤でも使っていますが、速乾性もあるため不満はありません。 '04~'05シーズンも一着買ってみました。前年のものよりも心持ち厚手になったような印象があります。 |
 |
| イチローの宣伝で有名な、 ワコールCW-X(\12,600 エキスパートモデル(ロング)、2004年9月から、この値段より値下げされています)です。 念のため説明すると、運動時に筋肉や関節をサポートすることで、疲労軽減・能力向上させる機能のついたサポーターみたいなものです。下に穿くものだけでなく、上半身に着用するものなどいろいろあります。詳しいラインナップはこちら。 今回購入したもの(エキスパートモデル)は、関節の安定、運動時の疲労軽減を重視したもの。他にパフォーマンスアップモデルという、運動性向上により重点を置いたものもあります。速乾性素材のクールマックスを使用していて、汗をかいてもさらっとしています。 肝心の使った感想は.......。かなりきつめなのと、膝位置を合わせる必要があるため、着用にはそれなりに時間がかかります(脱ぐときも)。自転車通勤では、疲れ半減とまでは行きませんが、3分の2くらいには減りました。かなりオススメです。 モーターサイクルでは、あまり恩恵を感じられませんでした。下半身がもっと激しい動きのときに効果があるように思います。耐久レースで着用している選手もいるようなので、長距離で使用するといいのかもしれません。ロングツーリングにはあまり出かけない自分の使い方と、値段のことを考えると、モーターサイクル専用に買うにはちょっと勇気が要りますね。 なお、自転車向け(お尻パッド入り)にはパールイズミにもプリザーブタイツという、同様の機能を持った商品があります。モーターサイクル転用ならインナータイツ(\7,245)もあるので悩みましょう。 |
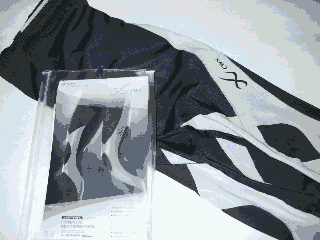 |
スパーダのタイヤを、下記のブリジストン BT-45に換えました。かなり気に入ってます。
こちらは管理人の使用したタイヤのインプレです。基本的に「街中メイン+峠流し少々+たま~に講習会」という使い方ですので、その点ご了解願います。
| BRIDGESTON BT-45です。スパーダで使用中。 管理人期待のブリジストンのバイアスタイヤ。持ちの良さとウェットグリップが売りのようです。 第一印象は、タイヤ全体が下記 IRC RX-01より 交換した日が雨だったのですが、初めから結構食いついてる感じがしました。雨にはかなり強そうです。普通の舗装の上なら、雨でもかなりバンクさせても大丈夫な気がする位、安心感があります。持ちもよさそうな感じ。前後セットで実売価格がBT-39と2千円位しか違わず、バリオスで使っていた時はそんなに減りも早くなかった(BT-45も、BT-39の倍は持たないと思う)ので、グリップを求める人はそちらにいった方が良いでしょう。 管理人レベルでは、街中はもちろん、講習会でちょっと走るくらいならこれで十分いけそうな感じ。その位グリップを感じます。ただしエッジのグリップは、やはり劣るのでしょうね。ですが、通勤快速号には関係ないところです。という訳で、今のところは、次に換えるのもコレになりそう。(2006.6) |
 |
| IRC RX-01です。スパーダで使用。 国産最廉価級バイアスタイヤ。対抗馬はブリジストンBT-45あたりでしょうか。 購入時につけてもらったので、まったく駄目タイヤかと思いきや、普通に街中を走る分には十分。ただそれなりに走ろうとすると滑るかも。講習会でたいした走りはしないのに、フロントが滑りかけたことがありました。但し数百キロしか走っていなかったので、ワックスが残っていたのか(乗り方のせい)? 普通に移動手段として走る分には、十分以上の性能です。ただ、アスファルトの路面上と、白線上などつるつるした表面のところでのグリップの落差が、若干大きいように感じました。また雨天のすり抜け中、綺麗な表面仕上げの側溝ブロック上で滑りかけました.....。リヤの方が滑りやすい感じがします。ですが、極端に雨天時のグリップが悪いわけではないです。 個人的には、この独特なパターン、面白くて好きです。「超」高性能を期待せず、街中を走り回るタイヤと思えば必要十分でしょう。持ちも良いです。管理人は約17,000km走行しました。さすがにリヤは平らになりましたが、新品時から極端にグリップも変化せず、溝の残りもあるのでもう少し走れそうな感じでしたが、パンク修理もしたため、早め?に交換しました。(2006.6更新) |
 |
| ミシュラン パイロットスポーツです。CBR600Fで使用中。 もっとツーリング向きタイヤにする予定でしたが、NAPSで安売りしていたことと、かなり気になっていたタイヤであるため、これに決定しました。 第一印象は、なんと自然に乗れるタイヤだろうということ。しなやかな感触があって、しかも奥でしっかり踏ん張ります(サス設定はD207と同じ状態での印象。後で設定変更)。タイヤ自体が柔軟な感じ。D207のごつごつ感と好対照です。倒し込みも、自然に回り込んでいく感じがします。タイヤが無いような感じといっては変ですが、意識することなく走れます。リヤが尖った形状をしているためでしょうか? あと、フロントにとても安心感があります。 グリップについては、限界まで攻めることはない(できない)ため、確かめたわけではないですが、さらっとした表面の印象からして限界はD207より低いかも......。しかし走り初めからかなり食い付きます。それでいて転がり抵抗は少ないので押し引きはとてもラク。雨天では、D207よりもグリップがいいように思います。単に新品だからという話もありますが.....。 ハイグリップの中ではもちが良いという話なので、今後にも期待しています。 因みにNAPSにて交換時、リムを削られました......(タッチアップ済み)。 |
 |
| ダンロップ D207。99国内仕様CBR600FのOEM(標準装着)タイヤです。 一言で言うと、硬い!粘る!タイヤです。グリップはめちゃめちゃ良いです。走行時に滑りそうな気配は全く無く、停車状態で車体を傾けてもフロントが切れない位、路面に食いついてます。その分持ちは悪そうで、夏場にちょっと走れば、表面はもうドロドロ状態です。割と溝の角が減っていく印象があります。 高速ではその硬さが安心感に繋がります。ボヨ~ンとしたところが全く無いので、安定感があります。雨の日はよく滑ります。フロントはまあまあ安心感がありますが、リヤはアクセルを殆ど開けてなくても、よく空転します。特に鉄板・ペイント上では直立していても油断できません(なぜか横滑りする)。 その剛性感と、グリップ重視の性格からして基本的に走り屋さん向きでしょう。管理人はもう少しグリップを落としても大丈夫なので、次はもっとツーリング向きタイヤにしたいと思っています。リヤはご覧の通り角減りしています。もっと早く換えた方が良いです。 |
 |