![]()
���w���̃L�b�J�P
�@���̐́A�݂肵���̃A�C���g���E�Z�i����`�ɏo�Ă����o�C�N....�Â��ł��i�W�X�N���j�B�O�Ԃm�r�q�W�O���v���̂ق��������ꂽ�̂ŁA������Ǝ����𑫂��ăZ�J���h�o�C�N�Q��ڂƂ��čw���ł��܂����B�A�����݂͊��S�ɉ��ʃo�C�N�����Ă���܂��B �@�I���R�̑��́A�������g�����Ȃ����ƁB�Z�J���h�o�C�N�P���̂m�r�q�W�O�����\�����������߂ł����A����͔r�C�ʂ��傫���̂ŏ[���ł��傤�B���ɁA�����ĉ��ɂ������ƁB���ׂĂ݂�ƁA�G���W���A�ԑ̂Ƃ��X�p�[�_���ǂ������ł��B�R��������炵���B �@�z���_�����Ђg�o�Ō��J���Ă����t�@�N�g�u�b�N������킩��悤�ɁA�J���ɂ��Ȃ�͂̓������o�C�N�ł��B�A���~�t���[���Ōy���ď�v�A��������������o���Ă��܂��B�c�O�Ȃ��璴�s�l�C�Ԃł���......�B���A�ň�����ɓ���邱�Ƃ��o���܂��B���ꂩ�珙�X�Ɏ�����Ă������Ǝv���܂��B |
 |
�@
���C���v���b�V����
�@�m�[�}���ōw���A�G���W���I�C���y�уt�B���^�����A�Y���܃X�[�p�[�]�C�������܂����B����ȊO�̓m�[�}���̂܂܂̂͂��B�����A�[�Ԑ�������ĉ��������́H��ԁi�A�N�Z���߂莞����������C���A�N���b�`�P�[�u���y?�l�܂�i���R��������j�B�܂��������肩�玞�܈ى�������A����͎d���Ȃ���...�j�������̂ŁA�ƂĂ��ēx�C����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�o����Ƃ��납�玩���Ŏ���ꂷ�邱�ƂɁB�J�E������A�^���N�̂ւ��݂����邽�߁A���X�ɒ����Ă��������Ǝv���܂��B
| �@���� | �ǂ����������܂��B�����悤�ȉ����͂͂Ȃ��ł����A�X�s�[�h�͊m���ɏo�܂��B �n�����ǍD�ł��B�^�~�ł��ꔭ�n���B �ᑬ�g���N���[���i�͋����͂Ȃ������\�S��܂��j�B �V�[�g���Ⴂ�̂Ŋy����B �t���[�����������Ȃ肠��܂��B�|�ǃt���[���̂���(Balius�Ȃ�)�����m���ɂ�������Ƃ������o�ł��B���Ȃ݂ɃX�C���O�A�[���̃s�{�b�g�\���́A�E�{�[���x�A�����O�~�Q�A���j�[�h�����[���[�x�A�����O�ŁA�b�a�q�U�O�O�e�Ɠ����\���ł��B�����������Ă܂��I �r�C�����Â�.....�Ǘ��l�ɂƂ��Ă̒����B �ԑ́A�G���W���Ƃ��A�V���v���Ŏ���ꂵ�₷���ł��B�܂���ɂ������Ă��Ƃł��ˁB ���Օi�̓��[�R�X�g�B�Ⴆ�Α�^�o�C�N�̃^�C���P�{���ŁA�O��^�C���{�����H�����y�ɕ�����ł��傤�B �I�C���_����������B�f�B�b�v�X�e�B�b�N�����ʓ|���Ȃ��ł��B |
| �@ | �@ |
| �@�Z�� | �w�����A�ӂ�ӂ�̃t�����g�T�X�ł������A�I�[�o�[�z�[���������ʁA��������悤�ɂȂ�܂����B�m�[�}���ł́A�������_�炩�����邭�炢�_�炩�߂ŁA�u���[�L�|���n�߂���p�����傫���ω����܂��i�X�Ƀ��b�V����lj����ĊX�����x���ł͏\���ɂȂ�܂����j�B ���r���[�ȃ|�W�V�����B���S�҂ɔz��������V�[�g���̂��߁A�ꍇ�ɂ��^���N�ƃt���[���̌��Ԃ�����ɕG�����Ă��܂��A���\�ɂ��ł��B�l�C�L�b�h�Ƃ��Ă͑O�X�p���̕��Ȃ̂ŁA�ǂ����Ȃ�V�[�g�͂���������ƍ��������ǂ��悤�ȋC�����܂��B �c�C���ŁA�}���`�̂悤�ɃG���W����]�����炩�ł͂Ȃ��̂ŁA�璹���s�Ȃǂ͂�����Ƃ��Â炢�Ǝv���܂��i�ᑬ�̔S��͂���j�B �������������ŁA�����炳�܂ɃX�s�[�h���݂�B��p���[�̂Ȃ��������镔���ł��B �m�[�}���n���h���Ńt�����b�N�̃^�[�����悤�Ƃ���ƁA�^���N�Ƃ̊ԂŎ���͂��݂܂��B ��p���ʊm�F�i���U�[�o�[�^���N�L���b�v�j�́A�l�C�L�b�h�ł���ɂ�������炸�A�J�E�����O���Ȃ��Əo���Ȃ��i������ĕ��ʁH�j�B �ӊO�Ɖו��̌Œ�͂��Â炢�i�c�[�����O�l�b�g�̃t�b�N�������|���Â炢�j�B�Ǘ��l�͏d�����̂��^�ԂƂ����q�u�a������ς݂܂��B ���낻�댇�i���i(��ɊO���Ȃ�)���o�Ă��Ă���B�������A���p�\�Ȃ��̂�A���Õi�̗��ʂ�����̂ŁA�H�v����ł��傤���H |
�@
| �ύX�_ | |
| �@�Ǘ��l�̓m�[�}���D���Ȃ̂ŁA�ق��t���m�[�}���ł��B�ł��C�ɂȂ�Ƃ��낾���������Ă��܂��B �Ȃ��A���Օi�͌����̂ǁA�O���[�h�̍������̂ɓ���ւ������Ǝv���Ă��܂��B |
|
| �A�[�V���O | �����܂�̃A�[�V���O�����Ă݂܂����B�ӊO�ƌ��ʂ���ł��B����ɃG���W���ɔz����lj����Ă݂܂����B |
| �u���[�L�L�����p�[ | ��{�I�ɂ̓I�[�o�[�z�[���ł����A�X�p�[�_���L�̕��i�����傢�ƌ������܂����̂ŁA�ύX�_�ɓ���Ă܂��B |
| �t�����g�T�X�y���V�������� | �������y�ɏo���āA�m�[�}���̎ア�T�X���A���Ȃ�D��ۂɕς��܂��B�p���ω��ʂ��v�����܂����B |
| �t�H�[�N�K�[�h���� | �t�����g�t�H�[�N�̔�ѐΏ���Ƃ��āB����i�Ɋ����ď������p�ɂāB |
| �w�b�h���C�g�� �}���`���t���N�^�[�� |
�Â����C�g���A�}���`���t���N�^�[���C�g�Ɋ����B�w�|�S�p�������C�g�Ȃ̂ŁA���Ȃ薾�邭�Ȃ�܂��B |
| �w�b�h���C�g�����[ | �펞�g�p���郍�[���̂݁A�s�̂̃����[���g�p���Č��x�A�b�v���Ă݂܂����B |
| �v���O�P�[�u������ | ���ÎԂ̌��A��Ƃł͂���܂����A������Ɖ��H���K�v�ł�����A�ύX�_�Ƃ��Ă��܂��B |
| �E�B���h�X�N���[���@ | �f�C�g�i�̃��m�Ƃ��F�X����܂����A���Ɛ��ŕ��h�����܂����B�ꕔ�蔲���ł����A���ʂ͏�X�ł��B |
| �J�E���Z�b�e�B���O�{���g | �T�C�h�J�E�����~�߂Ă���v���X�̓��̃{���g���A�����̘Z�p�{���g�ɕύX���܂����B�������p�ł��B |
�@
| �����e�i���X | |
| �����T�X�y���V���� | ���c���萫�ɉe���������Ȃ̂ŁA�����Ƀo�����Ď���ꂵ�܂����B���m�ɂ́A�����T�X�y���V���������N�ł��B |
| �t�����g�t�H�[�N | �S������Ȃ��T�X�������̂ŁA�I�[�o�[�z�[���ɏ��`�������W���܂����B�I�C�������Ȃ�����ƃ��N�B�����ẮH |
| �}�X�^�[�V�����_�[ | �I�[�o�[�z�[�����܂����B��͂�L�����p�[�ƃZ�b�g�Ō������Ȃ��ƌ��ʂ͔����ł��ˁB |
| �L���u���^�[�̓��� | ����m�F�̂��߁A�L���u���^�[�̓������������Ă݂܂����B |
| �^�y�b�g�����@ | ���ɃG���W���n�����A�J�`�J�`�������邳���̂ŁA�^�y�b�g�������Ă݂܂����B�O�o���N������Ă݂܂����B |
| ��p�������@ | ���܂�M�̂�����Ȃ��X�p�[�_�ł����A�Â��Ȃ��Ă����N�[�����g���������A���ƁA�Y���܂��g���Ă݂܂����B |
| ���M�����[�^�[���M�� | ����قǖ��͋N���Ȃ��X�p�[�_�ł����A�O�̂��ߑ�����Ă݂܂����B����ňُ�C�ۂ�����邩�H |
| �V�[�g���ւ� | ���ÎԂ��̔j��V�[�g���C���܂����B�����V�[�g�Ɠ��f�ނɂĒ���ւ��B�V�[�g�x���g�����ւ��܂����B |
| �K�\�����R�b�N | �悭�킩��Ȃ��Ǐo�����߁A�������Ă݂܂����B |
| �n�u�_���p�[ | �K�`�K�`�Ɍł܂��Ă����n�u�_���p�[���o�[�̌��������܂����B�`�F�[���̕��S�����炷���߂ɂ��L���ł��B |
| �u���[�L�f�B�X�N���� | ��������h�ȏ��Օi�B������ɂ���邪�T���`�V���L�����炢�Ō����ł��傤���H |
| �G�A�N���[�i�[���� | �X�p�[�_�ɂ͍Ďg�p�\�ȎЊO�i���Ȃ��̂ŁA����Ă݂܂����B��x�ڂ̐���̌��ʂł��B |
| �O���b�v�����@ | �X�p�[�_��������ACBR�̏����O���b�v�֕ύX���܂����B |
| �J�E����C | ���ꂽ�J�E���̕�C�ł��B�Ԃɍ��킹�ł����A�����͖ڗ����Ȃ��Ȃ����̂łn�j�B |
| �`�F�[������ | �N���I�ɂ͎����Ǝv����`�F�[�����A�l�グ�O�Ɍ������܂����B�V�����`�F�[���́A�ǂ��I |
�@
�@
���ύX�_
 �@�A�[�X�|�C���g�B���̃��W�G�[�^�����ƁA�����J�E�������B 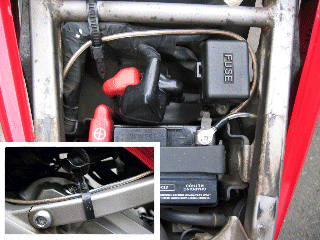 �@�A�[�X���ł��B�J�E�����ւ͏����̌����o���h�ŌŒ肵�A �@���W�G�[�^�ւ̓t���[���ɌŒ肵�Ĕz�����܂����B  ���Ɍ��h���ł����A�����A�[�V���O�Ȃ��A�E������ł��B ���Ⴞ�ƍ�������̂��͂�����킩���ł����B 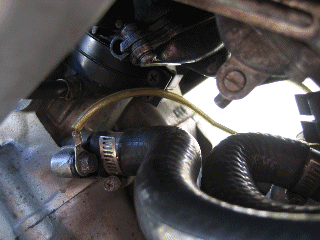 �����炪��o���N���̃A�[�X���B�Б��̃{���g���Ă��A ��p�����R��邱�Ƃ͂���܂���ł����B�ے[�q����������...�B 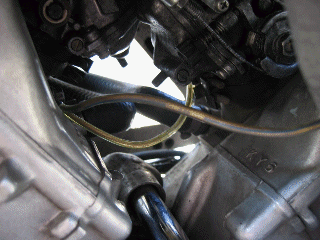 ���Ɍ��h���ł����A�E�̌�o���N����A���̑O�o���N �����o�R���āA�o�b�e���[�ɂȂ��ł��܂��B |
|
�@����y�Ƀo�C�N�{���̐��\�������o����Ƃ����A�[�V���O�����Ă݂܂����B �@�ȒP�Ɍ�������������......�B �@��{�I�Ƀo�C�N�̓o�b�e���[����o�����i�{���j����A�e�d�C��H�Ɍq����A��H�̃}�C�i�X���̓t���[���ɗ��Ƃ���Ă��܂��B�ԑ̎��̂�d�C���ʂ��āA�t���[���Ɍq����ꂽ�o�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�֑����A�Ƃ����o�H�ɂȂ��Ă��܂��B�ŁA��R�̑傫�Ȏԑ̕������A�`�������̗ǂ������ɒu�������悤�A�Ƃ����̂��A�[�V���O�Ȃ킯�ł��B�d�C�����ȊǗ��l�ł��A�z������{�Ȃ������Ȃ�ł������B �@���Ȃ݂ɁA�ŋ߂̋@��͂��Ƃ���A�[�X���������������Ă�����̂������悤�Ȃ̂ŁA����Ɂu�A�[�V���O�v�����Ă����ʂ����������肷��̂ŋC�����܂��傤�B �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`��(8,12mm ����јZ�p�{���g�p 6mm)�A�A�[�X���A���c���āA �@�@�ے[�q�A�����y���`�ł��B���̂�������m�r�q�̃y�[�W���Q�Ƃ��������B �@��Ǝ菇 �@�A�[�X�|�C���g�͂Q�_�B���W�G�[�^�E�t�@������ƁA�E�����J�E�����O���̌Œ�{���g�ł��B �@�܂��A�V�[�g���O���ă^���N�̃{���g�����܂��B�����J�E���E�������O���A�����̃A�[�X�[�q�����Ƃ���Ă���ӏ����m�F���܂��B�����ƃo�b�e���[�̃}�C�i�X���_�C���N�g�ɂȂ��킯�ł��B �@��Ǝ��͔̂��ɊȒP�A�ł����A�A�[�X���̎��ɂ͋C���g���܂��B����g�p�����̂͑ϔM�d�l�ł͂Ȃ��i�ƒ�p�I�[�f�B�I�X�s�[�J�[���j���߁A�G���W���͂������A�M���Ȃ镔���ɂ͐�ΐG��Ȃ��悤�ɂ��܂��B�l�������A�E�J�E���ւ̓n�[�l�X�ɉ��킹�Ĕz���A���W�G�[�^�ւ́A�o�b�e���[����T�u�t���[���̕⋭�����̉�(�C�O�j�b�V�����R�C���e)��ʂ��āA�t���[���`���Ƀ��W�G�[�^�ֈ꒼���ɔz�����܂����B�T�u�t���[���Œ�{���g�e�ƁA�`���[�N�P�[�u���Ɍ����o���h�ŌŒ肵�āA�G���W���ƐڐG���Ȃ��悤�ɂł��܂����B �@���ʂɂ��� �@�@���Ɍ��ꂽ���ʂƂ��āA���C�g�̌��ʃA�b�v���グ���܂��B�X�p�[�_�̃m�[�}�����C�g�͂ƂĂ��Â��A���[�^�[�������ƂĂ����Â炢�ł��B���Ԃ̓j���[�g�����A�E�B���J�[�����v�ȂǕ\�������猩�Â炢�ł��B �@�A�[�V���O���́A�\�����ނ��_�����Ă���̂����Ԃł��n�b�L���킩��悤�ɂȂ�A�w�b�h���C�g�͊m���ɖ��邭�Ȃ�܂����B��̓I�ɂ͉E�̎ʐ^�̂悤�Ȋ����ł��B �@�ʐ^���Ƃ킩��Â炢�ł����A�u���b�N���̌p���ڂɒ��ڂ��Ă��������B���ɖ��邢�Ɠ���ł��ʐ^�ł��A�p���ڂ������ɂ����Ȃ�܂��B���̃A�[�V���O�Ȃ��ł͒������������p���ڂ������Ȃ��Ȃ��Ă��Ȃ��̂ɁA�E�̃A�[�V���O����ł́A�p���ڂ̌����Ȃ����������E�����ɍL�����Ă���̂��킩��܂��B�ʐ^�͂Ƃ��Ƀn�C�r�[���A�ԑ̂͑S���ړ������A�z���̂ݕύX���Ă��܂��B���R�ʐ^�@���������ł��B��p���l����i�P�[�u���͔p�����p�Ȃ̂Ŋے[�q�ƒ[�q�J�o�[�� \160�̂݁j�A���ʂɂ͑喞�����Ă��܂��B �@����̃A�[�X���́A�G���W�����璼�ڂƂ��Ă��Ȃ��̂œ_�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A�A�[�X���Ȃ��Ɣ�r���āA�ᑬ�悪�ӊO�ɂ͂�����͋����Ȃ�܂����B����͊�������Z�ł��B�ł�������G���W���ɂ��A�[�V���O�����Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B �@�w�b�h���C�g�p�������[��H�ƍ��킹�āA�n�[�l�X�d�l�ɂ��Ă݂܂����B �A�[�V���O�lj� �@�G���W���ւ̃A�[�V���O�̒lj��ł��B�����̃A�[�X�|�C���g����A�[�X�����Ƃ邾���ł��A���C�g���ʁE�n�����A�b�v�͊�����ꂽ�̂ł����A�����Ɠ_�������������Ƃ������ƂŁA�_�v���O�̐ڒn���ɋ߂��V�����_�[�t�߂���A�[�X���������Ă��܂��B �@�Ƃ����Ă��A�Ȃ�����ꏊ�͌����܂��B�A�[�X���̊ے[�q�����܂��Ă����v�Ȃ悤�ɁA�G���W�����̂̍����ɂ������{���g�ł͂Ȃ����ƁA�Ȃ�ׂ��v���O�̋߂��ɂ��邱�ƁA�Ƃ����������l�����āA����͗�p���z�[�X�̐ڑ��{���g�𗘗p���܂����B �@�P�[�u���Ɋے[�q�������߂āA��o���N�̃{���g�ƑO�o���N�̃{���g���Ȃ��A�O�o���N�̃{���g����o�b�e���[�܂ł̒����ō��܂����B�܂��o���N�͑O�o���N�o�R�Ńo�b�e���[�֔z�����Ă���܂��i�ʐ^�j�B�Ƃ肠�������ʃe�X�g�p�̂���Ȃ̂ŁB �@��p�z�[�X�̍������̃{���g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł����A����A��p�����R��邱�Ƃ͂���܂���ł����B�{���g�͌Œ����Ă���A���X�y�l�ŏ�����A�ŏ��Ɋɂ߂�ۂ̓��K�l�𑫂œ��݂��āA���Ƃ��O��܂����i�H��[�J�[�ۏ؊O�Ȃ̂Ŏ��ȐӔC�Łj�B �@���� �@���ۂ̂Ƃ���A�̊�����قǂ̌��ʂ͂���܂���ł����B�c�O�B���Ɏ傾�����Ƃ���ɂ̓A�[�V���O�z�������Ă��������߂ł��傤�B�R��͗ǂ��Ȃ邩�H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2008. 2 �NjL�j |
�@
 �@��CB400SF�p�B��SPADA�����i�B��F�̂Ƃ��낪�A �@�s�X�g���{�̂��_�炩���ގ��ŏo���Ă��܂��B 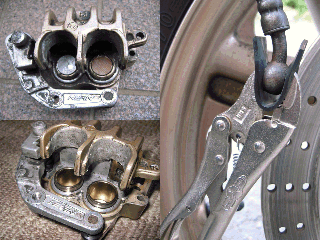 �@�t���[�h�R��~�߂̈��i�E�j�B�L�����p�[�́A�Y��� �@�|�����đg�݂܂��i���j�B�s�X�g���̈Ⴂ�������܂��ˁB 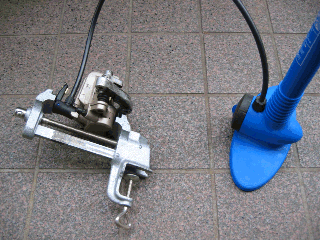 �@�s�X�g���́A��C����𗘗p���ĊO���܂����B���\���� �@�ǂ���яo���̂Œ��ӂ��܂��B���܂ڂ��ȂǂŔ�� �@�Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂��傤�B 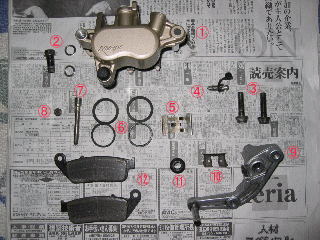 �@�p�[�c�ꗗ�B�@����߁A �ްAΰ����āA���ݸ�ܯ�� �@�B�����ϳ������ �C��ذ�ށA����� �D�߯����ݸ� �@�E�߽�ݼ�فA�ļ�� �F�߯����� �G�߯�������� �@�H���� �I�ð� �J�ް� �K��ڰ��߯��  �@�����s�X�g���̓�����ʂ����Ă݂�ƁA�ؕЂ��I �@�m���ɖ͐�x�ʂɂȂ�Ȃ��Ɣ����Ȃ��ł����ǁB �@���v�Ȃ�ł����A�z���_����B |
|
�@�m�[�}���̃X�p�[�_�́A�t�����g�u���[�L�̌������ƂĂ������ł��B�~�܂邱�Ƃ͎~�܂�̂ł����A�u�j���b�Ƃ������������Č��������ǂ�����܂���B�����ŃI�[�o�[�z�[�������˂āA�������i���p�̉��������Ă݂܂����B �@��̓I�ɐ�������ƁA�X�p�[�_�̏����L�����p�[�s�X�g���i�u���[�L�p�b�h����������p�[�c�j�́A�p�b�h�ɓ�����ʂ��_�炩���ގ��ŏo���Ă��܂��B���S�҂���邱�Ƃ�z�肵�āA�u���[�L���K�c���Ƃ����Ă��t�����g�����b�N���ɂ����悤�ɂ��Ă���킯�ł��B����͂���������^CB400SF�̃s�X�g���ɕύX���܂��B �@�u���[�L�͏d�v�ۈ����i�ł��B���M�̖������́A�����v���V���b�v�ɔC���܂��傤�B �@�`�������W������͈ȉ����Q�l�ɁA���ȐӔC�����肢���܂��B �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`��(8,10,12mm ����јZ�p�{���g�p 6mm�A�v���X�E�}�C�i�X�h���C�o) �@�@�t���[�h��(�y�b�g�{�g���ŏ\��)�A�u���[�L�t���[�h�A�ϖ����`���[�u�B �@�@���ƁA�o�C�X�v���C���[�Ɣ����S���Ђ�����ƕ֗��ł��B �@�p�ӂ������i�́A �@�@�V�[���s�X�g��(43209-MA3-006 \225) �@�@�_�X�g�V�[��(43109-MA3-006 \220)��SPADA���� �@�@�t�����g�L�����p�[�s�X�g��(45107-ML4-006 \1,050)�͏����^CB400SF�p�ł��B �@�l�i�͈������ł��̂ł��̔{������܂��B���̑g�ݍ��킹�́ACLUB SPADA�̂g�o�ŁA�悵�⎁�ɋ����Ă��������܂����B���ӁI�I �@�Ȃ��A����^CB�͑Ό��s�X�g���̃L�����p�[�i�܂�ʕ��j�ɂȂ��Ă��܂��B �@��Ǝ菇 �@����͂Ȃ�ׂ��t���[�h�������Ȃ������̂ŁA����`���Ǝ蔲�������܂����B�v���̂��A�������菇�ł͂Ȃ���������܂���B�L�����p�[�̂݊O�����������̂�.....�B �@�ŏ��ɃL�����p�[�ɐڑ�����Ă���u���[�L�z�[�X�{���g���ɂ߂܂��B��������t���[�h�����ނ̂ň�U���߂܂��i�L�����p�[�P�̂ɂȂ��Ă��O�����x�Ɂj�B�p�b�h�s���Ȃǂ��ɂ߂Ă����܂��B�t�����g���炷�̂ŁA�ׂ��������̓t�����g�t�H�[�N�̃I�[�o�[�z�[�����Q�Ƃ��������B �@�L�����p�[�̓��o�[�𑀍삵�āA�\���s�X�g���������o���������܂��B��������Y��Ă��Ǘ��l�́A�L�����p�[���O����A��C����𗘗p���ĊO���܂����B�����s�X�g���̓��������E�ňႤ�̂ŁA�Б������o�Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA�ؕЂȂǂ��p�b�h�ʒu�ɓ���Ă���s�X�g�����ϓ��ɉ����o���܂��傤�B �@�����܂ŏ����ł�����A�L�����p�[����u���[�L�z�[�X���O���܂��B�z�[�X�̃o���W���[�i�L�����p�[�ɐڑ��������j���S���Ђʼn������A�o�C�X�v���C���[�ŗ��߂܂��i�ʐ^�j�B �t���[�h�́A�h����v���X�`�b�N�A�S���Ȃǂ�ɂ߂��̂ŁA�����B���Ő����܂��B �@���ꂩ�炨�|���ł��B�����̈����s�X�g���̑��́A����̂��߃_�X�g�V�[�����悶��Ă��܂����B�s�X�g���V�[���A�_�X�g�V�[���Ƃ��ɁA������c�[���ŊO���܂��B�L�����p�[�������Ȃ��悤�T�d�ɁB�V�[�����O�����a�́A�ł܂����t���[�h�̌������A�������ė��Ƃ��܂��B�u���[�_�[�{���g���́A���Ȃ�l�܂��Ă����̂ŁA�p�[�c�N���[�i�[�Ŕ���܂����B �@�|�����ς�g�ݗ��Ăł��B���^�����o�[(�t���[�h����)��h�z�����ׂ��ǂ������V�[�����Z�b�g���A�s�X�g�����������Ɖ������݂܂��B�ԑ̂ɃL�����p�[��t���A�u���[�L�z�[�X���K��g���N�Ŏ��t���܂�(3.5kgfm)�B�t���[�h�́A�ӊO�ɏ��Ȃ��ʂōς݂܂��B �@�G�A���� �@�t���[�h�́ABP SuperDOT4 ���g�p���܂����B �Ǘ��l�̓t���[�h�ۊǎ��ɁA�d�C�z���̖h���Ɏg�����ȗZ���e�[�v���L���b�v���킹�ʂɊ����t���A�z����h�~���Ă��܂��B���\�����ł�(�{���g����̂��x�X�g)�B �@�G�A�����Ƃ́A�u���[�L���C���ɓ�������C��������ł��B��̓I�ɂ͎��̎菇�ŁA�t���[�h��r�o���Ȃ����C���ꏏ�ɏo���Ă��܂��܂��B�Â��Ȃ����t���[�h����������Ƃ��������菇�ł��B �@�P�D�}�X�^�V�����_�̎�����ی�̕z�ȂƂŃJ�o�[���A�W�����܂�(�{�l�W�Q�{)�B �@�Q�D�u���[�_�[�Ƀ��K�l�����`���|���`���[�u���q���܂��B�`���[�u�̖��[�́A �@�@�@�y�b�g�{�g���ɓ���܂��B �@�R�D�u���[�L���o�[���������܂܁A�u���[�_�[���ɂ߃t���[�h��r�o���܂��B �@�S�D�u���[�_�[����߁A�育������������܂ŁA�u���[�L���o�[�𑀍삵�܂��B �@�T�D�}�X�^�[���̃t���[�h�������Ȃ肻���ɂȂ�����A�V�����t���[�h��A���Ă�����܂��B �@�U�D�`���[�u����o��t���[�h���V�i�̐F�ɂȂ�܂ŁA�R�`�T���J��Ԃ��܂��B �@�ȉ��̓}���m���ł��B�}�X�^�[�V�����_�[�̌Â��t���[�h�́A�e�B�b�V���Ȃǂŋz�����ƁA�����I�B�}�X�^�[�̌�����t���[�h�����Ƃ�����̂ŁA�}�X�^�[�V�����_�[�̊W���悹�Ȃ����Ƃ����܂��B��ƌ�A�u���[�_�[�Ɏc�����t���[�h���A�p�[�c�N���[�i�[�ȂǂŔ���܂��B�����Ă����ƃt���[�h���z�����ĎK�тĂ��܂��܂��B �@��ƌ��� �@�܂��o�l���̌y�ʉ��B�Q���X�p�[�_����170g�ACB400�p104g�B����Ă��Ă��킩��܂��A�C���I�ɂ�낵�����ƁB���݂ɏ����i�́A�p�b�h�̓�����ʂɃi���g�ؕЂ������Ă܂����I�I�t�B�[�����O�������͂��ł���(�ʐ^)�B �@������́A�����傫���̃s�X�g���Ȃ̂ŁA���͕͂ς��܂���B�A���A�Ԃ�Ԃ悵���������Ȃ��Ȃ�A���菉�߂ƁA���肱��ł������Ō�̕ӂ�̌��������ǂ��Ȃ�܂����B�u���[�L���u�M���b�v�ƌ��������ł��B����ł��v�������般��Ȃ��ƃ��b�N���Ȃ��Ǝv���̂ł���......�B �@�u���X�p�}�X�^�[�V�����_�[�̗��p��������܂������A��������Ƌ��炭�t�����g�t�H�[�N�̃X�v�����O���������Ȃ��ƃo�����X�������Ǝv���܂��̂ŁA�m�[�}���h�̊Ǘ��l�͂Ƃ肠��������̎d�l�ŁA���炭�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B�i�����̌�A�t�����g�t�H�[�N�����b�V���[��lj����܂����B�j �@�K��g���N �@�@�@�@�z�[�X�{���g �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 3.5kgfm �@�@�@�@�u���[�L�L�����p�}�E���g�{���g �@2.7kgfm �@�@�@�@�u���[�_(�{���g)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@0.6kgfm �@�@�@�X���C�h�s���ɂ́A�V���R���O���X��h��܂��傤�B�S���u�[�c�ɂ��h�荞�ނƗǂ��ł��B |
�@
| �@����̓X�p�[�_�I�[�i�[���ʂ̔Y�݁A�ӂ�ӂ�t�����g�T�X�ɑΏ����܂��B���t���m�N�����͗ǂ���邻���ł����AMTB�̃T�X�y���V�����ł���Ă݂āA���Ȃ��ۂ��ǂ������̂ŁA�X�p�[�_�ł������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�C�ɓ���Ȃ�������ɖ߂���̂ŁA���C�y�ɏo����̂��|�C���g�����Ƃ���B �@�T�X�y���V���������i��������܂ށj�̂����́A �@�@�P�D�t�H�[�N�I�C�����ʂ��グ��i��C�o�l���ł�����j �@�@�Q�D�t�H�[�N�I�C���̔S�x���グ��i�I�C�����ł�����j �@�@�R�D�v�����[�h����������i�X�v�����O��\�ߏk�߁A��������T�X�y���V�������d������j �@���v�����܂����A�P�̓G�A�o�l�������t���{�g���t�߂ŋ}���Ɍł��Ȃ�A�Q�͐v���ɍl����ꂽ�_���p�[���\�ƒ������ω����Ă��܂��i�S�̂Ƃ��Ĉ����Ȃ�\����j��A�S�x�̍����I�C���͗����Ƃ��̐��\�ω����������炵���A�Ƃ������ƂŁA���̂�����͂�����Ȃ��ق�������ł��B �@�ŁA����͂R�����s���邽�߂ɁA�X�v�����O���k�߂Ă���J���[�i�����j����������킯�ł����A���ۂɃJ���[������Ǝd�l�ύX���ʓ|�Ȃ̂ŁA���b�V���[�Ȃǂ����Ē��߂���̂���ʓI�Ȃ̂͂����m�̒ʂ�B |
 �@�g�p�����X�e�����X���b�V���[�i�ۍ����j�B |
�@����� �@����͊O�a��30mm�X�e�����X�����b�V���[��p�ӁB�z�[���Z���^�[�ɂ�10������\288�B ����͂T���d�˂Ŗ�Pcm���ɂȂ�܂����i�Б��T�����g�p�j�B�W���b�L�������Ă��Б�����Ɠ���邱�Ƃ��o���܂��B�n���h�����~�߂Ă���Z�p�{���g���ɂ߂܂����A�t�H�[�N�̍a�ɂ͂܂��Ă���b�^�N���b�v�́A�O���K�v�͖����͂��ł��B�t�H�[�N�g�b�v��17mm�Z�p�Ŏ~�܂��Ă��܂����A�J���鎞����Ȃ��悤�ɏォ�炵�����艟�����Ă����܂��傤�B����̓J���[�̉��Ƀ��b�V���[��lj����܂����B���b�V���[����ꂽ��g�b�v�L���b�v����߂܂����A�t�����g�������グ��悤�Ȋ����Ŏx���Ȃ���������y�ɒ��߂��܂��B �@��ƌ��� �@�����̃Y�h�[���ƒ��ݍ��ނ̂������Ȃ�A�_�炩���o�l�͊����Ă��Ȃ��̂ŁA���Ȍł�������܂���B�X�����펯�I�ȃy�[�X�ő��镪�ɂ̓l�K�͂Ȃ��悤�ł��B�X���Ƃ��ẮA���������ʂɓ���i�ł��Ƃ����قǂł͂Ȃ��j����ɁA���̌オ������Ə_�炩�������B�_�炩���X�v�����O��ς��Ă��Ȃ��̂œ��R�Ƃ����܂��B���ʒ������������ǂ��̂ł��傤���H����̉ۑ�ł��B �@�������ȒP�ɕύX�ł���̂ŁA�t�����g�T�X���C�ɂȂ��Ă�����́A�����Ă݂鉿�l������Ǝv���܂��B �@�˂��o������ �@����̓˂��o�������́A�ڌ����Ő��~�����₵�܂������A�t�H�[�N�I�C�������ɔ����A�v�����Ă݂܂����B �v�������̂́A�{�g���u���P�b�g�`�A�E�^�[�I�C���V�[���㕔�̒����ł��B��������ԑ̂����肬��|��Ȃ����x�ɃW���b�L�ʼn�����x������ԂŌv���B �@�@�m�[�}����ԁ@�@�@ ���@��122mm �@�A���b�V���[�lj���@���@��129mm �@���݂ɎQ�l�l�Ƃ��āA�W���b�L�A�b�v���ăt�����g�T�X���L�ѐ�����ԁ@���@��140mm �ł����B �@��L�@�A����A���b�V���[�lj��ɂ��A�����d��ԂŖ�Vmm�O�オ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B ���̕����g�b�v�u���b�W��ɍX�ɔ�яo��悤�Ɂi�˂��o���j�����������܂����B����Ă݂�������.....�ω��͂��������̂́A���̒����ɂ����̂��s���B �@���͂قړ����ɍs�����^�C���������A�t�����g�^�C�����I�[�o�[�T�C�Y(110/70)�ł��邱�Ƃ��킩��A�W����100/80 �ɖ߂����̂ł��B�����ł��ω����Ă���̂ŁA���o���s���l�ł������ȕ]���̓����ȏ�ԁB�܂��������Ƃ͖����Ǝv���܂���....�B(2006.7�X�V) |
�@
�@
| �@����̓t�����g�t�H�[�N�̃C���i�[�`���[�u�ی�̂��߁A�t�H�[�N�K�[�h������Ă݂܂����B �@�t�H�[�NOH���A�ق�̏����ł��̍����C���i�[�`���[�u�ɂ���̂ɋC�Â��܂����B���܂ł����������������ŃI�C���R����N���������Ƃ͂Ȃ������̂ł����A�����ł��s���ޗ������炵�����Ƃ������ƂŁA����Ă݂܂����B �@�l�b�g��ł́A���@��łقڃA�E�^�[�a�ɋ߂��ʃX�v���[�̊W�𗘗p���č���Ă��܂������A�������������̂��肻�����K���{�g�����g���Ă݂܂����B �@��������H���ăA�E�^�[�Ɋ����������܂ł���ȈՃt�H�[�N�K�[�h�Ƃ��܂��B�Œ�͗��ʃe�[�v���n�[�l�X�e�[�v�ŁB�F�̓X�v���[�̍��ł����A�r���œh�����ꂽ�̂����h��L�����̂ŁA���Ȃ艘��....�B �@�����̓A���_�[�u���P�b�g�̃t�H�[�N�Œ�{���g������邽�߁A��O���ɐU���Ă��܂��B�������t���X�g���[�N�ł����͂���܂���B�͂��߂͕ʎԎ�̏������p�ł�낤�Ǝv���Ă����̂ł����A���߂Ɍ���Ύ��R�Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�������̂܂܍s������B�ƌ����āA���炭�g���Ă��܂������A���Ȃ肭���т�Ă������߁A���ւ��܂����B �������p�i �@���삵���t�H�[�N�K�[�h���A���Ɏ������}�������߁A���x�̂��鏃���i���痬�p���l���܂����B �@�����C���i�[�`���[�u�a�̂��̂���T���܂����A�܂��z���_�͂R�Vmm�a�̂��̂͊��ɐ�ł��Ă���A������ƒ��ׂ�����ł́A�t�H�[�N�K�[�h����������Ă������̂��Ȃ��悤�ł��B �@���낢��m�F���Ă����ƁA���}�nDS250�p�t�H�[�N�v���e�N�^�[(�i�ԁF5JX-2331G-00)���͂܂肻���Ȋ����B�������āA�I�[�o�[�z�[�����ɑ������܂����B �@����ɂ͂ߍ��ލۂ́A���Ȃ�͂܂�ɂ����ł��B�S���ɂ킽���ăS���̃n���}�[�Œ@�����݂܂��B�Е���@���Ƃ����ɊO��Ă��܂��A�ϓ��ɂ͂߂�͓̂�������ł��B��x�͂߂�ƁA�v���X�`�b�N�̗ւ��L�т�悤�ŁA���O���Ă�����x�͂߂�ۂ́A���������y�ł��B���܂���O�����̂ł�����܂��B �@������A�E�̎ʐ^�̂悤�ɂȂ�܂����B����i�������Ԃ�Ȃ��߁A�v���e�N�V�������ʂ͂ǂ����ƕs���ł������A������ł��B�J�V���s�ł��A�v���e�N�^�[�͈͔̔͂G�ꂽ���Ղ͂Ȃ��A�����𑖂�ƁA���ɂ����낢�뉘�ꂪ�t��������̂ł����A�V�[���ɐς��鉘������炩�ɏ��Ȃ������ł��B �@���ꂽ�Ƃ�����X�g���[�N����ƁA�V�[���̑ϋv���ɂ��e�����܂��B�Ǘ��l�̎g�������ƁA�����O�͖�P���T��L���ŁA�I�C���R�ꂪ�N���n�߂Ă��܂������A������A���������𑖂��Ă��R���C�z�͂���܂���B�Ȃ��A�C���i�[�ɏ��̂Ȃ��ꍇ�̃I�C���R��́A��ɃV�[���ɉ��ꂪ���܂��ċN����悤�ŁA�J�Ō����Ă���u�ϐ��y�[�p�[����������ŃV�[�������������ƁA�R�ꂪ����(���Ƃ�����)�v�Ƃ����̂́A���݂�������邽�߂��Ǝv���܂��B �����߂͂��܂��A��L���R����A���𐴑|����A�V�[���̍Ďg�p�͏o���܂��B�����𑖂�l�Ȃ�A�n�g�Q��ɂP�炢�̌����ŗǂ���������܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2009. 4 �NjL�j |
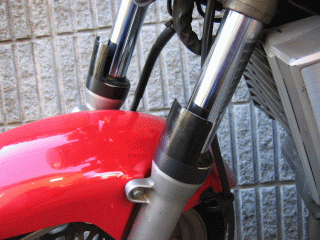 �@������ԁB���ڂɂ́A�����Ǝ��R�Ɍ����܂��B �@�s���͂���܂���ł������A���N�̎g�p�ɂ��A �@�����ƂȂ����̂ŁA������ƂƂȂ�܂����B 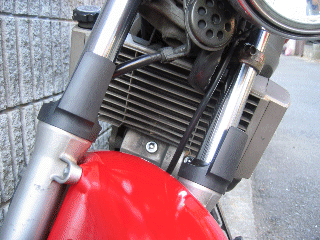 �@�����i���p�B�������Ɏ��܂肪�ǂ��ł��B�C �@�����O���ɃI�t�Z�b�g�����̂́A�O���̃{���g �@�Ɋ����Ȃ����߂ł��B |
�@
�@
| �w�b�h���C�g�̃}���`���t���N�^�[�� | ||
�@�X�p�[�_�̈Á`���w�b�h���C�g�̊����ł��B �@���ԃJ�X�^���ł͒�ԂƂȂ��Ă���炵���AX-4�p(���ɂ��Y������)�����w�b�h���C�g�֑g�ݑւ��܂��B�X�p�[�_�����̃w�b�h���C�g�ƈႢ�A�}���`���t���N�^�[�̂��̂ł��B���̃^�C�v�̓J�b�g����K���X�ł͂Ȃ��A���ڃ����v��������̂ƁA180mm�O�a�̂��̂����Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�ʐ^�Ō���������Ȃ蕵�͋C���ς���Ă��܂��܂��B���S�����h�ɂ͒�R�����邩���m��܂��A�Ǘ��l�͎��p�i���S�j�������܂����i�ʐ^��j�B �@�}���`���t���N�^�[���̕��@�́A���̌`���̃��C�g���̗p���Ă��鑼�@��̏������i�𗬗p���邩�A���C�u���b�N�Ȃǃ����t���̎ЊO�i�����A�ɂȂ�܂��B������̏ꍇ���A�w�b�h���C�g�P�[�X�͌��a����������X�p�[�_�m�[�}����ʂ̂��̂ɕύX���邱�ƂɂȂ�܂��B �@���ĊǗ��l�̓I�[�N�V�����ɂāA�O�a180mm��X-4�p�}���`���t���N�^�[�w�b�h���C�g����肵�܂����B���̎Ԃ̂��̂炵���A�����ɏ����c�݂ƁA����ɔ����Z���̂��߁H���K���������̂ŏC�����s���܂����B�P�[�X�����̍���́u61301-MAZ-000�@CASE HEAD LIGHT�v�ł����B �@���R�A�|���t���Ƃ����킯�ɂ͍s�����A�w�b�h���C�g�X�e�[�̕����L����K�v������܂��B��̓I�ɂ́A�m�[�}���̃X�e�[�̕t�����ɁA�J���[(���b�V���[)��17���lj����A�Б����15mm�L���đΏ����܂����B�{���͒���̃p�C�v�݂����Ȃ��̂������̂ł����A����������������(\8/��)�Ȃ̂ŁB�{���g�͒���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA30mm����6mm�X�e���{���g(\21/�{)�ɓ���ւ��i�ʐ^���j�B �@�X�Ƀw�b�h���C�g�P�[�X�̍��㑤�ƃX�s�[�h���[�^�[�P�[�u���A�w�b�h���C�g�P�[�X�㑤���S���ƃ��[�^�[�P�[�X�������A���ꂼ�ꊱ����̂ŁA�P�[�X�������E�\�N�̉��t��A���܂��܂����B�\�ʂ��u�c�u�c�Ə����A���ʂɂ��Ă���A�̖_�ʼn����������^���܂����B���h���͗ǂ��Ȃ��ł����A�g�ݍ���ł��܂��قڌ����Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ŗǂ��Ƃ��܂��i�ʐ^���j�BVTR250��o���I�X�p�̃w�b�h���C�g�P�[�X�Ȃ�A���s�������Ԃ�Ɍ�����̂ŁA���̂܂܂����邩��(�����܂Ŏʐ^����̉���)�B�A���A�z���̓m�[�}���ł����\�M�b�V���Ȃ̂ŁA���߂ɂȂ邩���m��܂���B �@�ׂ������ł́AX-4�ɂ͂Ȃ����ߍs������������|�W�V�������́A�R�l�N�^�[�����ŊO���A�h���̂��߃r�j�[���e�[�v�ŕ��ł����܂����B�܂��w�b�h���C�g�P�[�X�̔z������������Ȃ荶�����ɂ����̂ŁA�n�[�l�X�z���ɕ��S��������Ȃ��悤�A���R�ɋȂ������Ă����܂����B �@�ŁA���ۂɑ����Ă݂�ƁA���炩�Ɏ��F�����ǂ��Ȃ��Ă��܂��B���Ԃ͂���قlj��b�������ł����A��ԑ��s�����ρB�H�ʂ��ǂ������A�ƂĂ����S�ɂȂ�܂����B�R�X�g�͂���Ȃ�ɂ������Ă��܂��܂����A���ʂ͂��Ȃ�̂��̂ł��B�����o�����Ă��܂����CBR600F�i�m�[�}���j�����A�����Ɩ��邭�Ȃ�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2006.7) �@���̌�A�X�Ƀ����[��H�i���L�j��g�݂܂����B �@ |
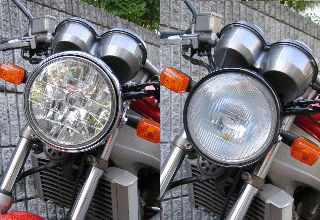 �@������ƁA�m�[�}���Ƃ̔�r�B�����̐F�� �@�Ⴄ�̂ŁA�ʂ̎Ԏ�̂悤�Ɍ����܂��B 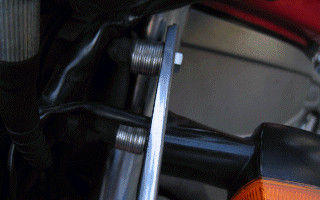 �@��a���C�g�ɂȂ�̂ŁA15mm���X�y�[�T�[ �@���K�v�B���̃X�s�[�h���[�^�[�P�[�u���� �@������̂Ń��C�g�P�[�X�����܂��܂��B  �@�ʐ^�E���̊����������܂��܂��B���� �@���A�㕔�ɓ��镔�����v���H�i��O���j�B |
|
�@
�@
| �w�b�h���C�g�����[ | ||
�@�X�p�[�_�̃w�b�h���C�g�ɁA����̋����z�������[��lj����܂��B �@�o�b�e���[���璼�ɔz�������A�w�b�h���C�g�𖾂邭������̂ł��B�n�C����[�����ɑΉ������s�̕i������܂����A����Ȃ�ɍ����ł��B�����ŁA��p���郍�[�������ɔz����g��ł݂܂����B���Ƀ}���`���t���N�^�[�w�b�h���C�g�̌��ʂ�����A�����[���ȏ�Ƃ����������ł��B �p�ӂ������ �@�����[(�G�[�����H�ƁAITEM No.1244) \1,344 �@���^�q���[�Y�z���_�[(�G�[�����H�ƁAITEM E432) \210 �@�R�l�N�^�[�[�q�iI�E�s�E�n�A�ʌ^��E���^��j �e\315�i20�{���j �@�g�S���C�g�p���^�[�q�iDAYTONA No.7�j \1,860(30�Z�b�g�A�������X�Q�g�p) �@�d��(1.25�X�P�A�A\420/4m����) �@�R���Q�[�g�`���[�u(���G�X�P�C�H�@�AKC10) \147 �@�����[��DC12V�ŁA�ő�360W(30A)�܂őς���S�Ƀ����[�ł��B���l�^�̃��g�����e�i���X���ɍڂ��Ă���REV'S�u�����h�̃����[�̕����A�������悤�ł��B�Ȃ��G�[�����̏��i�J�^���O�i�g�o�́u����܁��B�l����v�j�ɂ́A�d�H�y���`�̎g�����Ƃ����J�ɏ����Ă���̂ŁA�Ǘ��l�̂悤�ȏ��S�҂ɂ͏�����܂��B �@���ۂ̔z���́A�o�b�e���[�̃v���X������o�����z���ɁA���S��H�Ƃ��ăq���[�Y��g�ݍ��݁A�������烊���[�̓d���������ɓ���܂��B�����[����̓w�b�h���C�g�q��������A�i����́j�����w�b�h���C�g�R�l�N�^�̃��[���Ɍq���܂��B�w�b�h���C�g�̏����A�[�X��������Ƃ���ɂ́A�o�b�e���[�̃}�C�i�X����V���Ɉ������������܂��B �@�ŁA���Ƃ��Ə����R�l�N�^�̃��[���ɓ����Ă�����(��)���A�����[�̋N���z��(��)�Ɍq���A���l�ɏ����A�[�X��(��)�������[�̃A�[�X���Ɍq���ł��ƁA�����z�������[��_�������ԂɂȂ��Ă��鎞�����A�����[�̃X�C�b�`������A�o�b�e���[�������̔z���i�����[���������j�ɓd�C�������i���ۂɓ_������j�Ƃ����d�g�݂ł��B �@�Ȃ�����́A�ȑO�Ɏ{�H�����A�[�X�����܂߁A�n�[�l�X�Ƃ��Ĉ�̂ɂȂ�悤�ɍ���Ă݂܂����B�n�[�l�X�e�[�v�Ƃ����ׂƂ��Ȃ��r�j�[���e�[�v���g�p���āA�����z�����ۂ��d�グ�܂����B �@��ƌ��� �@���Ƀ}���`���t���N�^�[�����Ă��Ȃ薾�邢�̂ŁA���s���̑̊��I�ɂ͎�̌��x�㏸�Ƃ��������ł������A�ڂ̑O�ɎԂ���Ԃ��Ă����肷��Ɣ��˂��ł��Ȃ��ʁAῂ����Ȃ������߁A���Ȃ���ʂ͂���悤�ł��BCBR�ɂ����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2006.11) |
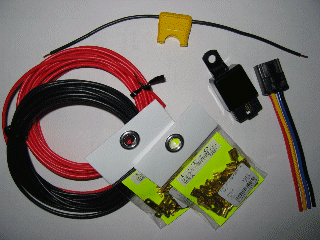 �@�K�v���i�ꎮ�B�v���X���z���Ɏ��t���� �@�q���[�Y�z���_�A�d���A�R�l�N�^�[�q�A�����[�B 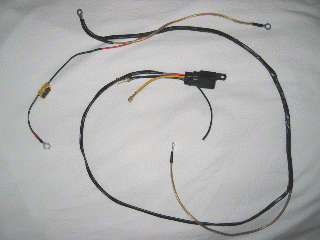 �@�����[�z���̐ԂɃo�b�e���[�̃v���X �@(�q���[�Y�L��)������́A������w�b�h �@���C�g���[�ցB�Ƀf�B�}�[�X�C�b�`�� �@��̏������[�z�������A�����珃�� �@�A�[�X(��)���Ɍq���܂��B |
|
�@
�@
| �v���O�P�[�u������ | ||
�@�v���O�P�[�u���̒���ւ������܂��B �@������L�W�}���V���R���R�[�h(�ԁA�i��304-401R \1,365/m)���g�p�B�m�[�}���̕��͋C�ō�肽�������̂ŁA�Ԃɂ��܂����B���i�͂P���p�b�P�[�W�ł����A�X�p�[�_�̃P�[�u���͑O�㍇�킹�Ė�90�Z���`�Ȃ̂ŁA�]�T���������ĂP�䕪�����܂��B �@�z���̓R�C�����͈�ʓI�Ȃ˂����ݎ��A�v���O�L���b�v���́A������n���_�t�����Ă���ς�����`���ł��B�܂����̋�����A�Ďg�p���邽�ߏ����P�[�u������O���܂��B �@�����̕�����@�́A�}�C�i�X�h���C�o�Ńv���O�L���b�v���̋�����O���A��R�ƈꏏ�ɔ������܂��B�n�C�e���V�����R�[�h���v���O�������Ɉ����o���ƁA�R�[�h�Ɏ��t����ꂽ����o�Ă��܂��B����͒��S�Ɍ��̊J�����~�Տ�̋���ŁA�c����ʂ��čL������A�n���_�t������(�n���_�Ŕ�����ɐ���グ)�Ă��܂��B �@�����ŁA�n���_��M���ċz�������Ȃǂő�܂��Ɏ�菜���A�c��̓J�b�^�[�i�C�t�ō��܂��B���̋�������ƁA�v���O�L���b�v����R�[�h���܂��B �@�R�C�����́A�P���ɂ˂����̃P�[�u���L���b�v���O���A�R�[�h���O���܂��B �@�ŏ��Ƀm�[�}���P�[�u�������������A�R�C�����̓P�[�u���ɔ����~�߂̏o�����蕔���ƁA����ɖ��p�����O������̂ŁA�O���Ƃ��ɒ��ӂ��܂��B �@�V�P�[�u���̐�[�ɋ����ʂ��āA�����`��Ɠ����ɂȂ�悤�Ƀn���_�t���E���X���������܂���(����Ȋ���)�B�G���W���̔M�ŗn������͂��Ȃ��ł��傤�A�����B �@�R�C�����̓m�[�}���̌Œ���@�Ɠ����悤�ɂ��邽�߂ɁA�z�b�g�����g(�O���[�K��)���g���A�Œ�̂��߂̏o��������P�[�u���ɍ��܂��B���炩���߃����O�ƃR�C�����L���b�v�A�v���O�L���b�v��ʂ��Ă����̂����Y��Ȃ��B����̃n���_�t���́A�P�[�u�����v���O�L���b�v�ɒʂ�����ɂ��������y�ł��B���Ƃ͌��ʂ�ɑg�ݏグ�邾���ł��B �@�Ȃ��P�[�u���̒E���́A�R�C���ԍڂ̂܂܍s���܂����B�������t�����g���̃v���O�P�[�u���́A�G�A�N���[�i�[�{�b�N�X�̏㔼���i�v���X�`�b�N�����j�����O���Ȃ��ƁA�ʂ����Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B �@���� �@�Ƃ肠�����ߏ�������Ă݂�ƁA�r�C�����͂�����͋����Ȃ�܂����B�������̏����P�[�u���͑������Ă���͂��B�܂��P�[�u�������łȂ��A����ɗΐ��������Ă���A���Ȃ�̓d�C�����ł��B �@�A�N�Z���̊J����͊m���ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A���ꂪ�R��ɈႢ���o�邩�ǂ����́A����m�F���Ă݂܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2008. 7�j |
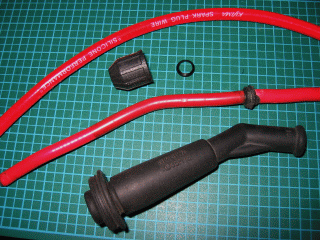 �オ�V�����ЊO�P�[�u���A�^���d������ �����P�[�u���B�R�C�����˂����L���b�v���� �����O�����Ă���̂ŁA��������Y��Ȃ��B 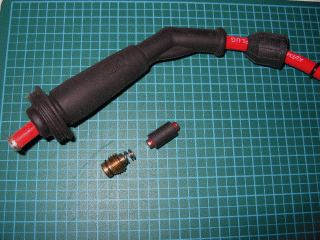 �v���O�L���b�v�̓����\���B�v���O�ɐڂ��� ����ƁA�S���H���i�̕t������R����B ���̋���K�тĂ���A�v���ӂł��B |
|
�@
�@
| �X�N���[���쐬 | ||
| �@�X�p�[�_�p�ɁA�E�B���h�X�N���[���i���h�j����邱�Ƃɂ��܂����B �ЊO�i�͍����̂ŁA����y�Ƀz�[���Z���^�[�ōޗ��B�B���Ƃ͍��C��.....�B �@�p�ӂ������� �@�@�@�A�N������(�A�N���T���f�[���A\1,344) �@�@�@�X�N���[���X�e�[�i�f�C�g�i�A�i��29883 \3,150�j �@�@�@�l�W�iM5�~10mm�A�l�i�Y�ꂽ�j �S�g�g�p �@�@�@�ۍ����i�v���X�`�b�N����10�����A\147�j �����S���g�p �@�h�D�J�e�B�E�����X�^�[�̂悤�ȁA���炩�ȋȐ��̓z���i�D�ǂ��ł����A���`�Z�ʁ����[�R�X�g�H�����l����Ɩ����B�����ŃV���v���ɂR�ʂ̃X�N���[�����l���܂����B���[�^�[�o�C�U�[���͒������āA�����h������_���܂��B �@���H �@�܂��^�����B��ɂ���Č������킹�ő�܂��ɊO�`�����߁A���̎��_�ōw������f�ނ̑傫�����m��B����̓A�N���T���f�[�� 320�~550�~2mm �A�N�����ł��B�f�ނ��O�H���C�������ŁA���݂P�D�T�~���ȉ��̂��̂͏퉷�ŋȂ���܂����A�Q�~�����Ƃ��Ȃ���ł��B�������Ȃ��悤�ɁA�ی쎆�������Ȃ����H���܂����B �@�y�b�g�{�g���f�ނƓ������̂́A�M�����|����ƊȒP�ɋȂ���܂����A�A�N�����͖����ł����B���ǁA�Ȃ�����̏������ŋ��ݍ��݁A���E�\�N���t���ċȂ��܂����i�ʐ^��j�B����قǘc�݂��o���A�Y��ɏo���܂����B�����t�邭�炢�̂���ł���������A������ƈ꒼���ɋȂ���܂��B �@�܂�Ȃ����^��A�\�ߌ��߂��`�ʂ�ɐ��������A�o�J�b�^�[�ʼn����������������܂��B�{���A�o�J�b�^�[�̓v���X�`�b�N�łɁu�����́v�a���@��A�܂��邽�߂̂��̂ł����A�Ȑ����ł��܂����B�A���C�����Ȃ��ƁA�]�v�ȂƂ���܂ň��������Ă��܂��̂ŁA�͂��߂ɉ��y�������Ȃ����ča���@��A�n�悪���肵���Ƃ���ōX�ɗ͂�������K�v������܂��B�d�M���H�����A�����Ɣ\���悭�ł���͂��B �@���ɂȂ�̂��Œ���@�ł��B���h�ȃX�e�[����낤�Ǝv���ƃR�X�g���|�����A���������Ȃ��̂ł͒E���̊댯������܂��B�����ō���g�p�����̂��A�f�C�g�i�̃X�N���[���i�u���X�g�o���A�[�j�p�X�e�[�Z�b�g�B����ő�������A���ɂ��̃X�N���[�����g�p�ɑς��Ȃ��Ă��A�f�C�g�i���X�N���[��������n�j�Ƃ����A���Ɏ�C�ȗ��R����ł��B���Ȃ݂ɂ��̃X�e�[�́uCB400SF/V-S(-98)���v�p�B�s�̕i�p�Ȃ̂ŁA�������Ɋ��ł��i�ʐ^���j�B �@�ԑ̑��̓w�b�h���C�g�Œ�{���g�ŋ����߂��A�X�N���[�����̌Œ蕔���̓X�g���X���U�̂��ߕ\(�v���X�l�W)���Ƀv���X�`�b�N���b�V���[�����݂܂����B�܂��A���h���������ł��ǂ����悤�ƁA�X�N���[���̃��[�^�[�O���ɓ��镔�����X�v���[�h�����d�グ�܂����i�ʐ^���j�B �@���� �@�C�ɂȂ���ʂ̕��́A�����͑����Ă��܂��A60km�`�ŕ������Ȃ������܂��B�͂��߃w�����b�g�̕��艹���傫���������܂������A���̕ӂ�ɓ��镗���Ȃ��Ȃ������A���ΓI�ɂ��邳���������悤�ł��B���������������Ă��Ȃ��̂ŃX�s�[�h�������������Ȃ�A�t���J�E���Ԃ̊��o�ɋ߂Â��܂����B�Ȃ̂ň�ʓ��ł�����Ȃ�Ɍ��ʂ���ł��B����������Ƒ啪�Ⴄ�Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@(2007. 1) |
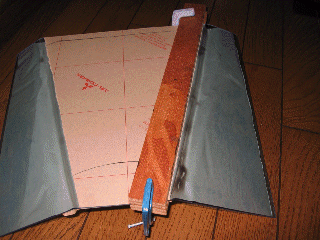 �@�܂�Ȃ���Ƃ���ō��ŋ��݁A���E�\�N�� �@�t��܂����B�X�X�́A�ȒP�ɗ����܂��B  �@�g�p�����f�C�g�i���X�N���[���X�e�[�B 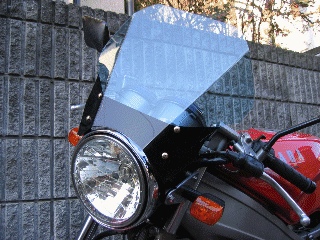 �@������ԁB�h�����ʂ͈ӊO�Ƃ���܂��B |
|
�@
�@
�@�����J�E���̃Z�b�e�B���O�{���g�����ł��B �@���̎���̃z���_�̃o�C�N�́A�{���g�̓��Ƀv���X�i�h���C�o�[�j���g���Ă�����̂����傱���傱����܂����A�X�p�[�_�̃����J�E���̃{���g�����̂ЂƂB���������p�ɂɕt���O�������Ȃ��{���g�́A�Œ����Ă���i�Ƃ����Ƒ傰�������O���ɂ����j���Ƃ������ł��ˁB�Œ������v���X�̓����͂������Ƃ���ƁA�ʐ^�̍����̂悤�ɂȂ�܂��B�B�B �@�����ŁA�ŋ߂̃o�C�N�Ɏg���Ă���A�Z�p�����`�d�l�̃{���g�Ɍ������܂����B����Ȃ瑽���������܂��Ă��Ă��A�H���������ƃZ�b�g���Ďg���A�Ȃ߂�S�z�͏��Ȃ��ł��B �@CBR600F�̃J�E���Z�b�e�B���O�{���g�����Ă����ƁA�J�E���ɂ͂܂鎲���҂����蓯���傫���i�ʐ^�j�ŁA���̂܂ܑ����ł����̂ŁA�������܂����B�����ڂɂ́A�J�E���̂ւ��݂�肩�Ȃ菬���߂̃{���g�̓��ɂȂ�̂ŁA����������邩�ǂ����ŕ]�����������Ǝv���܂���....�B �@CBR600F�̃{���g�i�Ԃ́A90106-KCZ-000(�X�N�����[�A�X�y�V����6mm)�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2007. 11�j |
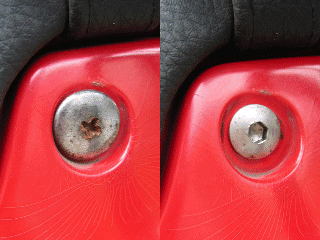 �@���̕��ꂩ�����v���X�{���g�ƁA�Z�p�{���g�B |
�@
�@
�@
�����탁���e�i���X
| �@�����T�X�y���V���������N���| �@ |
�@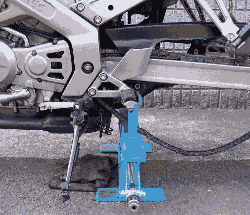 �@ �ʐ^�́A���ˍH�Ɛ��Q�A�W���b�L�ł��B �@ 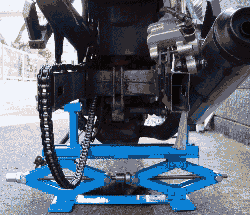 �@�����܂ŊO���ƁA�����N����̕����͊y���ł��B �@ 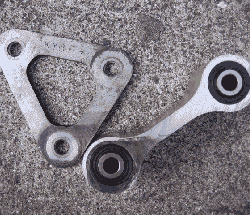 �@ �v���[�g�㕔�Ɏ�t�w���̕���������܂��B �@ 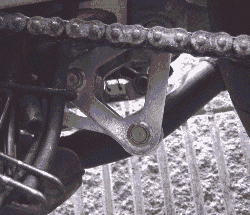 �@ ���������I���Ȃ݂ɂ��̃`�F�[���̂������ �@ �͑S���Ӗ��Ȃ������ˁi�^�o�C�N���̔[�Ԑ����j�B |
|
| �@���܁A���U����悤�Ȉى����o�邽�߁A�����T�X�y���V��������̎��������܂��B �@�p�ӂ������ �@�@�Ή�����傫���̃w�b�N�X�i�\�P�b�g�����ǂ��j�A�\�P�b�g�A�g���N�����`�A�G�N�X�e���V�����Ȃǂ̍H��B �@�@�W���b�L�B�Ԃ̎ԍڗp�̂悤�ȃ��c���A����g������A�W���b�L�̕����y�ł��B �@�@������܂ƃu���V�ށA�ϐ��y�[�p�[�i�ʎ�肾���Ȃ�400�Ԃ��炢�łn�j�j�A�^�J�u���V�A��������(�s�J�[����)�B �@�܂��A�W���b�L�A�b�v�ł��B�ǂ��ɓ��Ă邩���Ȃ�Y�݂܂������A�X�e�b�v�̕t�������W���b�L�A�b�v�|�C���g�ɂ��܂����i���Ȃ݂ɃG���W�������������グ��ƁA�O�ւ��オ���Ă��܂��܂��j�B���̂܂܂��ƕs����Ȃ̂ŁA�ԑ̂���Ԃɂ��Ă���A�u���[�L���o�[��R�Ŕ����āA�t�����g�u���[�L����������Ԃɂ��܂����i�ʐ^�ŏ�i�j�B���̃W���b�L�͐��ˍH�Ɛ���\19,800�ł��B�W���b�L�A�b�v�̌p������i�K�ɒ��߂ł��܂��B �@���悢�敪���ł��B�����T�X�����O���͖̂��Ȃ̂ŁA��ւ��O���܂��B���̕����������Ǝv���܂��B�u���[�L�L�����p�[�͎ԑ̂ɕR�Œ݂�A�h���C�u�`�F�[���̓X�C���O�A�[���Ɉ����|���Ă����܂��i�ʐ^����i�j�B �@�����N�v���[�g�𗯂߂Ă���E���̃{���g���ɂ߁A�炵�܂��B����A���Ԃ��Ȃ��̂Ń����T�X�㕔�͉������܂���ł����B������͎������Ƀ��|�[�g���܂��B�e�x�A�����O�ɂ̓J���[���͂ߍ���ł���܂����A���ꂪ��ł͂Ȃ��Ȃ����܂���ł����B�w�b�N�X�\�P�b�g�ɁA�G�N�X�e���V������t���A�y���@���o���܂����B�ꕔ�J���[���K�ѕt���Ă��܂����B �@�O�������i�𐴑|���܂��B�Œ���������͐^�J�u���V�ł�����Ɗy�Ɏ��܂��B �@�悭����ƁA�����N�v���[�g�����b�h�ƎC��Ă��܂���(�ʐ^�����i)�B �@�e�p�[�c�̖ʎ����y�[�p�[�ōs���A�C��Ă����Ƃ���͓��ɔO����ɖ����グ�܂����B �@�x�A�����O�����̓p�[�c�N���[�i�[�ŃR�P�F�ɂȂ����Â��O���X������A�V���Ƀ����u�f���O���X��h�荞�݂܂����B�J���[�ɂ��O���X��h��L���Ă���g�ݍ��݁A�g�ݕt����{���g�ɂ��O���X��h���Ă����܂��傤�B �@�����̓J���[���S���Ƃ������ƂȂ̂��A�i���炭�V�Ԏ�����炳��Ă��Ȃ������ł��낤�j�{���g�ɂ́A�����h���Ă���܂���ł����B�������A�d�������邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂ŁA�O���X��h���������ǂ��ł��傤�B�Œ��h�~�ɂ��Ȃ�܂��i���ӁF�����N�����ւ́A�ϐ������Ȃ������u�f���O���X�����A�E���A�O���X�����������悤�ł��j�B �@�g�ݕt����i�ʐ^�ʼn��i�j�B���炩�ɓ������ǂ��Ȃ�܂����B���������S�n�͂��قǕς�炸�A�X���𑖂邾���ł͂͂����茾���Ă킩��܂���ł����B�|�����݂����S���Ăł���悤�ɂȂ����C�����܂����A��芵�ꂽ���������m��܂���B �@�Ȃ��A��ԋC������Ȉى��͎��܂�܂���ł����B�ǂ����s�{�b�g�������炳�Ȃ��ƒ���Ȃ��悤�ł��B�����́A����H��v��܂���.....�B �@�K��g���N �@�@�@�@�����A�N�X���i�b�g �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9.0kgfm �@�@�@�@�����N�b�V�������A�i�A�b�p�j�}�E���g�{���g �@5.0kgfm �@�@�@�@�N�b�V�����R�����b�h�{���g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@5.0kgfm �@�@�@�{���g���̂͒[�܂��Ă��܂����A�v�̓����N����͂��ׂ�5.0kgfm�ł��B �@�@�@�Ȃ��A�N�b�V�����A�[���v���[�g(�ʐ^����̌������O�p�`�̃v���[�g)�ɂ́A �@�@�@�u���e�@�j�x�U�v�̕���������A���̕��̌����A�����T�X�y���V���������̎�t�p�ł��B |
||
�@
�@
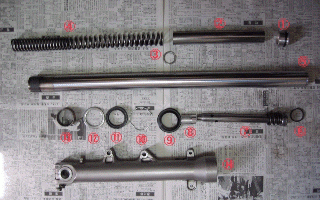 �@�S�o����ԁB�E���獶�ցA�@�t�H�[�N�{���g �A�J���[ �B���b�V�� �C�X�v�����O �D�t�H�[�N�p�C�v(�C���i�[�`���[�u�B�p�C�v�u�b�V���t) �E�s�X�g���V�[�� �F�t�H�[�N�s�X�g��(���o�E���h�X�v�����O�t) �G�I�C�����b�N�s�[�X �H�_�X�g�V�[�� �I�X�g�b�v�����O �J�I�C���V�[�� �K�o�b�N�A�b�v�����O �L�X���C�_�u�b�V�� �M�t�H�[�N�X���C�_(�A�E�^�[�`���[�u)�B��L�ȊO�ɁA�F�ƇM���A�E�^�[�����ŘA������{���g(�t�H�[�N�\�P�b�g�{���g�B���b�V���t)������܂��B 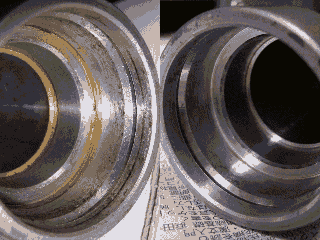 �A�E�^�[�`���[�u�ł��B�����������Ă�����Ɛ@������B�E����Ė�������B������Ɖ��ꂪ�c���Ă��܂����A���������ł͂Ȃ��̂ł悵�Ƃ��܂��B 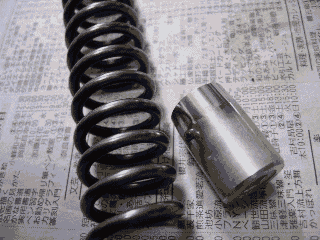 �������Ă������i���������݂܂����B�X�v�����O�͂�����ЊO�i�Ɍ������邩���m��܂��A�ꉞ�A�����Ă����܂����B  �����z�������i�B�X���C�h���^��(���A51415-MN4-003 \1,008/2��)�ƁA�V�[���Z�b�g(�E�A51490-KAZ-003, \2,646/2Set)�B���i��2004�N2�����݁ANAPS���c�J�X�ɂĔ���(�ɂ͂Ȃ�)�B |
|
| �@�u���[�L���O���ɁA�t�����g���u�Y�{�b�v�ƒ���ł��܂����߁A�I�[�o�[�z�[���ɒ��킵�܂����B �@�H���菇�̏��������������肵�Ă����A���Ɗy�ɂł��邩�ȁH�����͈ȉ��̒ʂ�ł��B �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`��(12,14mm ����јZ�p�{���g�p 6,8,17mm)�A�g���N�����`�A�W���b�L�A �@�@���X�V�����_�[(�t�H�[�N�I�C���v�ʂ̂���)�A���ˊ�ƃV���R���`���[�u(�����Ă���)�A �@�@���́i�����Ă��j�A���ƃI�C���V�[���ł����ݗp�ɁA�X���C�h�n���}�[�i����H��B��֕i �@�@�Ƃ��ĉ��r�p�C�v�ƃn���}�[�j��p�ӂ��܂��B �@�����菇 �@�܂��A�W���b�L�A�b�v���ăt�����g���炵�܂��B �n���h����t�{���g�A�g�b�v�u���b�W�����{���g(���C���[�ނ��O���Ȃ��Ȃ�A�u���[�L����12mm���K�l�����`���K�v)���ɂ߂���A17mm�Z�p�����`�Ńg�b�v�L���b�v���ɂ߂܂��B�O���K�v�͂���܂���B�Z�p�����`�͒��i�b�g(\�X�O��)�ő�p���܂����B���Ƃ͂ǂ�ǂ�O���Ă��܂��܂��傤�B�u���[�L�L�����p�A�n���h���͕R�ȂǂŌŒ肵�Ă����܂��B �@�g�b�v�L���b�v���O���āA�I�C����r�o���܂��B�X�g���[�N�����āA�Ȃ�ׂ��S���o���Ă����܂��B���Ƃ͐Ԃ��I�C����.....�������āA�Â����S�y�̂悤�ȏL�����Ă��܂����B�ꕔ�̃{���g�́A�{�E�̓C���p�N�g�ŊO���悤�ł����A����Ȃ��̂͂Ȃ��̂Ńg�b�v�L���b�v�����A�˂̃e���V�������|���ĊO���܂��B��������ƒ��̃p�[�c�i�t�H�[�N�s�X�g���j�����肵�܂���B�}���Ή��A�ł��B �@�_�X�g�V�[�����O���ƁA�I�C���V�[���������܂��B������Ƃ߂Ă���X�g�b�v�����O�i�b�N���b�v��̂��́j���A�h���C�o�Ȃǂł������ĊO���܂��B�A�E�^�[�`���[�u�ɉ��킹�ăh���C�o�����点��ƁA�C���i�[�`���[�u���������A�y�Ɏ��܂��B���Ƃ̓A�E�^�[�ƃC���i�[����������i���̓J�c���J�c���ƁA���������ĉ��x���@���ďo���܂����B�ǂ��Ȃ������B�j�A���S�ɕ������܂��B�C���i�[�`���[�u�̉��[�ɂ��Ă���p�C�v�u�b�V���́A�������̂݊O���̂ŁA���̂܂܂ɂ��Ă����܂��B�V�i�B���Ă������̂ł����A�R�[�e�B���O���Y��Ȃ܂܂ł����B���\�A��v�݂����ł��B �@�o�b�N�A�b�v�����O�ƁA�_�X�g�V�[���̓S�c�͐^���ԂɎK�тĂ��܂����B�_�X�g�V�[�����Ђъ���Ă������߁A�J���Z�������̂ł��傤�B�I�C�����������Ă����̂����̂������H �@���i�`�F�b�N�� �@�O�������i�́A�Y��ɐ��|���Ă����܂��B���ꂪ��ԑ�ς����m��܂���B����͎K�ї��Ƃ���A�S�Ă̕��i�𒆐���܂Ő���Đ@���グ����A�C���i�[�`���[�u���[�Ȃǐ��C����肫��Ȃ����̂݁A�p�[�c�N���[�i�[�Ő��������܂����B�Ȃ��A�I�C�����b�N�s�[�X��[�A�X�v�����O�O���ȂǁA�K�v�ȂƂ����ϐ��y�[�p�[�Ŗ����܂����B�n��800�ԁA�d�グ��1000�Ԃ��炢�Ŗ����Ɨǂ��ł��B�Ō�Ƀs�J�[���Ŗ����グ�܂����B �@�@�}�j���A���ɂ�镔�i�̃`�F�b�N���ڂ́A �@�@�@�@�X�v�����O���R�� 341.3mm ���ɂ��Ď��d�ŏk�܂Ȃ��悤�ɑ���B�����ۊǎԂł́A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�������K��l�ł����Ă��ւ����Ă���\������B �@�@�@�@�o�b�N�A�b�v�����O�@�@�@�@�@ �@�@�������A�߂ɍ�ꂽ�肵�Ă��Ȃ����i�G�b�W�������Ă� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�邩�j���m�F����B �@�@�@�@�X���C�_�[�u�b�V���@�@�@�@�@ �@ �A�E�^�[�ɂ����͓����A�C���i�[�ɂ����͊O���ɂ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �e�t�����R�[�e�B���O���A����������Ă��邱�Ƃ��m�F�B �@�@�@�@�s�X�g���V�[���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �V�i�͍����̌��Ԃ��J���Ă��Ē��͂���B �@�g�ݗ��� �@���悢��g�ݗ��Ăł��B�_���p�[�V�����_�[���C���i�[�`���[�u�ɓ���܂��B������_���p�[�̊炪�o����A�I�C�����b�N�s�[�X��Ƃ߂܂��B���̂܂܃A�E�^�[�`���[�u�ƍ��̂����܂��傤�B�{���g�Ń_���p�[���A�E�^�[�`���[�u�ɌŒ肵�܂��B���ꂪ�ł��i���₷���{���g���Ǝv���܂��B�����Z�p�����`���g���̂ŁA�T�d�ɍ�Ƃ��܂��傤�B���́A�A�E�^�[�`���[�u�ɕz�������A���͂ŌŒ肵�Ă����Ƃ��܂����B�����A����ł��i���������̂�(���Α��͕���O����Ȃ��Ă���)�A����͐V�i����z����\��B �@���Ƃ͏ォ��X���C�_�u�b�V���A�o�b�N�A�b�v�����O�����܂��B�I�C���V�[���̃��b�v��ی삷�邽�߁A�C���i�[�`���[�u��[�ɔ����r�j�[����킹�A�O���X��h�����I�C���V�[����Ƃߍ��݂܂��i���[�J�[�����j�B���̂܂܂��ƃX���C�_�u�b�V���Ȃǂ��͂܂��Ă��Ȃ��̂ŁA�ォ�牖�r�p�C�v(1m��\200��)�����Ă����A�n���}�[�ŃI�C���V�[���O�����ϓ��ɒ@���āA�X�g�b�v�����O���~�߂�a�����S�Ɍ�����܂őł����݂܂��B���̌�A�X�g�b�v�����O�A�_�X�g�V�[�������܂��B �@�I�C���͒l�i�̈�������J���T�L�̂P�O�Ԃ��g�p�i1L�����Kawasaki \1,300�AHonda \2,500�ʁH�j�B�����Ԏ�ł����[�J�[���ɔS�x�������قȂ�A�J���T�L�̂̓z���_�������_�炩�߂̂悤�ł��B �@��Œ�������̂����Ȃ�A��������v�ʂ��ē���܂��傤(371cc)�B���ꂩ��ł��k�߂���ԂŁi�X�v�����O�Ȃǂ͓���Ȃ��j�A�C���i�[�`���[�u��[������ʂ܂ł̋����𑪂�܂��B�X�p�[�_�� 103mm�ł��B�����ő��߂ɓ����Ă���I�C���𒍎ˊ�ŋz���o���܂��B �@���Ƃ͊�{�I�ɕ����̋t�ł��B�Ȃ��A�X�v�����O�͒��a�̏��������i�����̖��ȕ��j�����ł��B �@�K��g���N �@�t�H�[�N�{���g(�g�b�v�L���b�v)�@ 2.3kg��m �@�t�H�[�N�\�P�b�g�{���g�@�@�@�@�@ 2.0kgfm�i�˂����b�N�g�p�j �@�g�b�v�u���b�W�����{���g�@�@�@�@2.3kgfm �@�{�g���u���b�W�����{���g �@�@�@3.5kgfm �@�n���h�������{���g�@�@�@�@�@�@�@1.2kgfm |
�@
�@
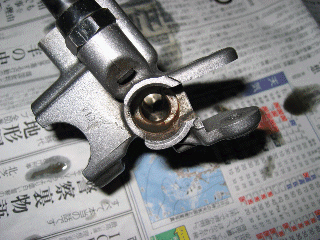 �@�ӊO���Y�킾�����}�X�^�[�V�����_�[�����B �@�A���X�i�b�v�����O�͌Œ��C���ł����B 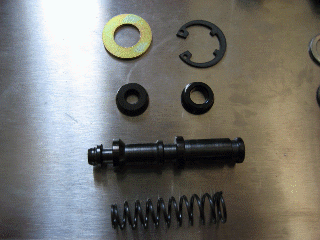 �@�}�X�^�[�V�����_�[�̃C���i�[�L�b�g�ꎮ�B �@�J�b�v�V�[�����s�X�g���ɑ������Ȃ�������܂���B  �@�ŁA���̂悤�Ƀ{�[���y���L���b�v���劈��B �@�V�[���ƃL���b�v�ɂ͏����܂����܂����B |
|
�@�}�X�^�[�V�����_�[�̕����ł��B���݂̎ԗ��͂P�T�N�I�肭�炢�Ȃ̂ŁA��������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��傤�B��ɓ��ꂽ��������A��a�����C�ɂȂ��Ă����̂ł����A�悤�₭���{���܂����B �@��̓I�ɂ͗͂����ă��o�[�������Ă����ƁA���傤�Ǐ����S�������点���Ƃ��̂悤�ȁA�Y�Y�Y...�Ƃ��������Ȓ�R�������Ă��܂����B�Ǐ�A�S�����i����������悳����....�Ǝv�����̂ł����A�P�̂ł͕��i���o�Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�}�X�^�[�̓������i�Z�b�g���w���B �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`�ނ���уv���X�E�}�C�i�X�h���C�o �@�@�t���[�h��(�y�b�g�{�g���ŏ\��)�A�u���[�L�t���[�h �@�@�X�i�b�v�����O�v���C���[�A �@�@�V�[���C���X�g�[���i�{�[���y���̃L���b�v���H�ʼnj���K�{�B �@�p�ӂ������i�́A �@�@�}�X�^�[�V�����_�[�Z�b�g(45530-MN9-305 \1,880) �@�@�I�C���{���g���b�V���[(90545-300-000 \140/��) �@��Ǝ菇 �@����̓L�����p�[���ԍڂ̂܂܂ɂ��Ă������߁A�t���[�h�����������Ă���A�}�X�^�[�V�����_�[�ƃu���[�L�z�[�X�̘A�����O���Ă��܂��܂����B���N�g�p�����}�X�^�[�́A�X�i�b�v�����O���Œ��C���ŁA�������肵���v���C���łȂ��ƊO��Ȃ��悤�ł��B �@���i���O������A�Ђ������܂��B�t���[�h���ł܂��Ă���悤�Ȃ��Ƃ������A�����Y��ł����i�ʐ^��j�B���������o�[�����͍d���Ȃ��Ă����悤�ł��B����Ȋ����i��V�i�A���g�p�ρj�B �@����A���i��g�ݕt���܂����A�s�X�g���Ƀ��o�[�J�b�v�i�V�[���j���͂ߍ��܂Ȃ��Ƃ����܂���B���̂܂܂ł͓���Ȃ��Ǝv���̂ŁA���傤�ǂ����傫���̃{�[���y���̃L���b�v��p�ӂ��āA�|�P�b�g�Ɉ����|�����肷��Ƃ��Ɏg���o������̕��������A�ȈՃC���X�g�[���ɂ��܂����i�ʐ^���j�B�V�[���������ɂ́A�����ɏ����܂����^�����o�[��h��܂����B �@�����A���i�����܂����Ƃ���ŁA�s�X�g���Ȃǂ��t���[�h�ɒЂ��āA�C�A���܂Ƃ��t���Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂��B�V�[�������ɃV���R���O���X��h��A���ʂ�Ɂi���R�A���i�͐V�i�j�g�ݕt���܂����B�u���[�L�z�[�X�͋K��g���N�Ŏ��t���܂�(3.5kgfm)�B �@���Ƃ̓G�A�����ł����A�}�X�^�[�V�����_�[�̓����ɂ��������i���t���Ă��āA�ǂ��ɋC�A������̂������āA�o�Ă���悤�Ɋp�x�̒��������Ղ������ł��B �@��ƌ��� �@���R�A��a���������Ȃ�A���S���āu�M���E�b�v�ƈ��荞��ł�����u���[�L�ɂȂ�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2006.10) |
�@
�@
| �@�L���u���^�[�̓��� | 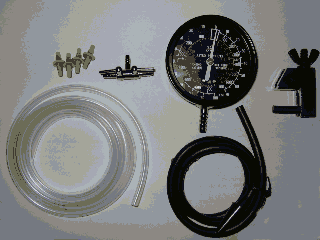 �@����g�p�̓���ꎮ�B����l�̐�ΐ��x�͖����� �@�v���܂����A����Q�[�W�Ȃ̂Ō덷���l���Ȃ��� �@�����̂��ǂ��ł��B 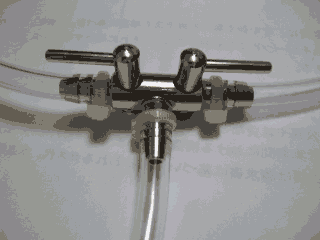 �@�ڑ��̓^�C���b�v���߁B��͕ق����S�ɊJ������ԁB 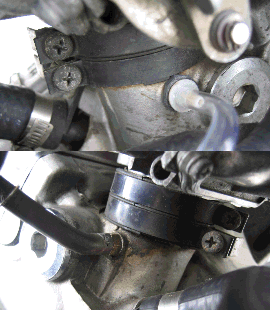 �@�オ�O�o���N�B�����̃v���X�˂����O�����A���b�V�� �@�E���ɒ��ӂ��܂��傤�B���̓z�[�X���Œ�������o �@���N���B������͌v���p�`���[�u�����܂��B |
| �@����́A�L���u���^�[�̒������s���܂��B �@�ꉞ�A�����Ȃ̂ł����A�ǂ̂��炢����Ă���̂������{�ʂ�.....�B�����~������Q�[�W�i�l�A�j���C�͖�������ǂ��A�P�i�Q�[�W�ŃL���u�̐�������ւ��đ��肷����@������̂�m���āA�^���Ă݂悤�Ǝv�����킯�ł��B �@�p�ӂ������ �@�o�L���[���Q�[�W�@�@�A�X�g���v���_�N�c(AP)�������E�R���e�X�g�Q�[�W(\1,380)�B �@����o���u�@�@�@�@�@�@�R�g�u�L�H�|�����B������(K-09 \260)�B �@�W���C���g�A�z�[�X�@�@�R�g�u�L�H�|�����B(�v���X�`�b�N���W���C���gK-11 \80/�� �A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�[�X2m K-41 \120/1p) �@�`���[�u�N�����v�@�@�@AP���̓�Z�b�g�� \596�B �@�@�ق��ɁA�^�C���b�v���z�[�X�������Ȃ��悤�ɌŒ肷�邽�ߎg�p�B �@�@�R�g�u�L�H�|���̐��i�́A�y�b�g�����ŊϏ܋��i�G�A�|���v�j�p�Ƃ��� �@�@�����Ă�����̂ł��B �@����`���[�u�̍쐬 �@�܂��������ł��B����z�[�X�����܂��B�Q�[�W�A����o���u�A�L���u�ƌq����̂ŁA�z�[�X�����̏��ԂɂȂ��܂��B�����Ȃ��悤�A�^�C���b�v�ŗ��߂܂����i�ʐ^���j�B������Q�Z�b�g���A�S�C���ɂ��Ή��ł��܂��B�o�L���[���Q�[�W�ڑ����͂��Ȃ葾�����߁A�p�ӂ����z�[�X�i�����Ȃق��j�͓���܂���ł����B�����Ńv���W���C���g���g���A�Q�[�W�ɕt���̃z�[�X��Z���������̂��g���āA�Q�[�W�A�t���z�[�X�A�W���C���g�A�z�[�X�̏��Ɍq���܂����B �@����� �@�X�p�[�_�̃L���u�O�o���N�́A�������o�������˂����ݎ��̃W���C���g�Ȃ̂ŁA�v���X�`�b�N�W���C���g���������A��C���z��Ȃ��悤�S���p�b�L�������܂����B����͉��������Ȃ�����n�j�B�G���W�����|�����Ă���Ƃ��͋z�������ŁA����ɋz���t���Ă���܂��B�ォ��킩�����̂ł����A���̃v���X�`�b�N�͂�����Ǝg�p�����i�K�\�������t�����j�����Ŏ��������悤�Ȋ����ŗn�������Ă��܂����B���܂艽�x���g�p�ł��Ȃ��悤�ł��B �@��o���N�̕��́A�K�\�����R�b�N�̕����`���[�u�ɐڑ�����Ă��邽�߁A������O���ăo�L���[���Q�[�W�̃z�[�X���q���܂��B�������̓A�C�h�����O�����Ȃ�������Ȃ����߁A�����R�b�N���J���悤�ɕ����`���[�u�ɒ��ˊ���Z�b�g���Ĉ������蕉������������ԂŁA�`���[�u�N�����v�ŗ��߂Ă����܂��B���̃N�����v�͗��߂镔�����ۂ݂�ттĂ���A�z�[�X��ɂ߂܂���B �@�������������Ƃ���ő���ɓ���܂��B����ق̑��肷�鑤�̂݊J���āA�Q�[�W�̐j�����肳���邽�߁A���莞�͕���ق��S�T�x���炢�ɕ�����Ԃɂ��܂��B����ق����S�ɒʂ��Ԃ��ƁA�����v�̐j���������U��Ă��܂��A�S���ǂ߂Ȃ��ł��B �@����菇�i�g�C�ς݂Łj �@�@�@�@�@�X���b�g���X�g�b�v�X�N�����ŁA�A�C�h�����O��]���� �@�@�@�@�@ �K��l�ɒ����i1,300�}100rpm�j �@�@�@�@�A�e�V�����_�Ԃ̕������𑪒肷��i40mmHg�ȉ��j �@�@�@�@�B�p�C���b�g�X�N�������W���߂���]���ł��邱�Ƃ��m�F(�Q��1/4��]�߂�) �@�@�@�@�C�t�����g�V�����_�p�����A�W���X�g�X�N������ �@�X���b�g���X�g�b�v�X�N�����́A��Ԃ�����ԂŌ����Ǝԑ̍����A�A�N�Z�����C���[�ʼn�]����v���[�g�̊J�x���ł���A�v���X�`�b�N�̓����t�����l�W�ł��B�����A�W���X�g�X�N�����́A�ԑ̉E���̂��傤�Ǔ������i��������̃L���u�̃A�N�Z���ƃ����N���ē����v���[�g�j�̊J�x��������̂ł��B�����̎�ꂽ�Ƃ���ŁA�A�C�h�����O�����X�オ��܂����B�ēx�X���b�g���X�g�b�v�X�N�����[�ŃA�C�h�����O��]�������A�����͏I���ł��B �@��ƌ��� �@��ƌ�A�������s���܂��B���܂肸��Ă��Ȃ������̂ŁA���s���͕ς�炸�B�A�C�h�����O�́A�y�₩�ɂȂ�܂����B���ʂɑ��镪�ɂ͖��Ȃ������̂ł����A����ꂪ�������悤�ł��B |
�@
�@
| �@�^�y�b�g���� �@ |
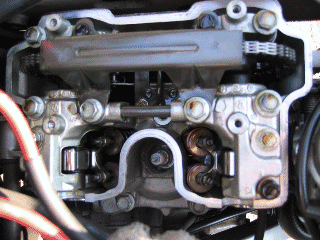 �@ �w�b�h�J�o�[���O������o���N���B������͒������₷�� �@ �ł��B�V�b�N�l�X�Q�[�W�͒��������g���₷���ł��傤�B �@ �ʐ^�����ɃJ���ƃA�W���X�g�X�N�����A�㑤�ɃJ���`�F�[ �@ ���������܂��B 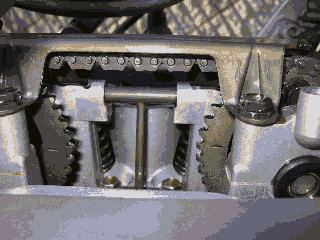 �@ �J���X�v���P�b�g�ɂ́A�����ʒu�̂������������₷�� �@ �Ƃ���ɂ���܂��B�O�o���N���͏\���Ȍ��Ԃ��Ȃ����߁A �@ ���̂�����������m�F���Â炩�����ł��B 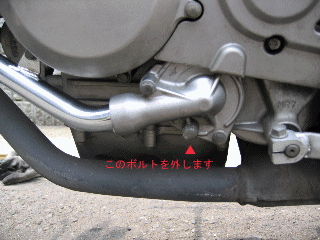 �@ �E�H�[�^�[�|���v�̃h�����{���g�B������O���n�j�ł����B 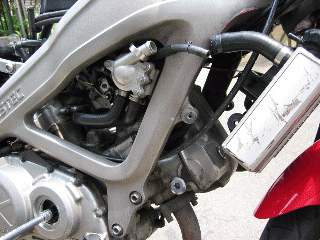 �@ ���W�G�[�^�[(�z�[�X�̘A��)���O�����Ƃ���B��������� �@ �y�ɒ�����Ƃ��o���܂��i�Ƃ��������K�̐����菇�ł��j�B |
|
| �@���ɃG���W���n������ɃJ�`�J�`�����C�ɂȂ邽�߁A�^�y�b�g���������Ă݂܂����B �@�p�ӂ������ �@�@�V�b�N�l�X�Q�[�W(���ԃQ�[�W)�A8,10,14mm�����`�A�}�C�i�X�h���C�o�ȂǁB �@�@�t�̃K�X�P�b�g��������ǂ����ƁB�������A��Ԏ�(35���ȉ�)�ɍs���܂��B �@����� �@�܂��A�^���N���O���܂��B����̓{���g���O���Ă���A�R�b�N�Ɍq�����Ă���K�\�����z�[�X�ƃo�L���[���`���[�u���O���܂��B �@����g�p�����V�b�N�l�X�Q�[�W�ł́A���݂�0.09�{0.10�̑g�ݍ��킹�Ŏg�p���܂����B �o���u�������Ă��镔���ɉ�����O�O�b�ƍ������݁A�����Ɛ�[���������������Ŏg�p���܂��B�`�F�[���̒��蒲���Ɠ����ŁA����߂��i���߁j�̕����ǂ��Ȃ������ł��B�Ȃ̂ŁA�T�[�r�X�}�j���A��(�ȉ��r�l)�̍ő�l�ł��� 0.19mm �ɋ߂Â��悤�ɒ������܂����B�X�p�[�_�́A�z�C�E�r�C���Ƃ��ɓ���ł��B �@�܂���o���N����B�t���[������A�K�\�����R�b�N�����̃v���X�`�b�N���O���A�R�[�h�ނ�R�ő��˂ăt���[���Ȃǂɂ�������܂��B�V�����_�w�b�h�J�o�[�̃{���g���ɂ߁A�J�o�[���O���܂��i�ʐ^��j�B������͏㑤�ɂ��\���ȃX�y�[�X������̂ŁA�����̓��N�ł��B �@�����́A�N�����N���ď㎀�_�ɍ��킹�܂��B�G���W���E���̃^�C�~���O�z�[���L���b�v(�\�P�b�g���|����悤�ɂȂ��Ă��܂�)���O���Ă���A�\�P�b�g�ɃG�N�X�e���V������}���āA���ɂ���{���g�̓������v���ɉ܂��B�v���O���O���Ă����ƒ�R�����Ȃ��悤�ł��B �@�@�P�D�^�C�~���O�z�[���̏㑤�茇���ƁA���̒��́uT1�v�}�[�N�����킹�� �@�@�Q�D�J���X�v���P�b�g��������(�ʐ^��)���V�����_�w�b�h��ʂƐ����ł��邱�Ƃ��m�F �@�@�R�D�V�����_�����k�㎀�_�ł��邱�Ƃ��m�F �@�R�́A�J���V���t�g�̍���ʂɗ��āA�J���X�v���P�b�g�̐������������ɂȂ����Ƃ���ł����A�V�b�N�l�X�Q�[�W���S������Ȃ����炢�̎��́A�����P��]������ƈ��k�㎀�_�ɂȂ�悤�ł��B�����̓V�b�N�l�X�Q�[�W��}�����܂܃A�W���X�g�X�N�����[�̓����}�C�i�X�h���C�o�ʼn������A���K�l�����`�Ń��b�N�i�b�g����ߕt���܂��B �@�O�o���N�́A���ł��B����A��p�����̂��ʓ|������(�蔲���ł�)�̂ŁA���W�G�[�^�����炵�Ē��������݂܂������A�w�b�h�J�o�[���t���[�������甲�����܂���ł����B���̃J�o�[������悤�ɕێ����A���Ԃ���V�b�N�l�X�Q�[�W���������݂܂����B�K���K��l���������̂ŁA����͒������p�X���܂������A���������܂ōs���Ȃ�A���̂����ł͖����ł��i�� ����������܂����j�B �@�ꉞ�r�l�ɉ����Ď菇�������ƁA �@�@�P�D�����𑪒肵����Ԃ���A�N�����N�����v����450�x��]������ �@�@�Q�D�^�C�~���O�z�[���Ő茇���ƁuT2�v�}�[�N�������Ă��邱�Ƃ��m�F �@���̌�ɒ����A�Ƃ����������ł��B �@�K��l �@�@�@�@�^�y�b�g�i�o���u�j���ԁiIN/EX) �@�@�@�@0.15�`0.19mm �@�@�@�@�V�����_�w�b�h�J�o�[�{���g �@�@�@�@�@ �@1.0kgfm �^�y�b�g�����i�O�o���N�j �@�O��A�������Ȃ������O�o���N�̒������s���܂����B �O�����͂قڋK��l���������̂ł����A��͂肸��Ă����悤�ŁA�A�C�h�����O���������Ȃ��Ă��܂����B������A�C�h�����O���グ�Ă��炭���܂����Ă��܂������A��͂肩�Ȃ�s����ɂȂ��Ĉ�a�����o�Ă������߁A����̒����Ƒ�����܂����B �@����� �@���W�G�[�^�[���O���i���炵�āj�s���܂��B�܂����W�G�[�^�[�L���b�v���O���܂��B�L���b�v�ɂ͌Œ�p�̃v���X�l�W������A������ɂ߂Ȃ��Ɖ��Ȃ��̂Œ��ӁB���ɎM��p�ӂ��Ă���A�E�H�[�^�[�|���v�̃h�����{���g������ė�p�����܂��B�}�j���A�����ƃV�����_�����̃h�������O���悤�ɂ���܂����A�|���v���������ł��Ȃ蔲���܂����B���W�G�[�^�[���O�������Ȃ炱��ŏ\���ł��B �@���̌�A�ʐ^�̂悤�Ƀz�[�X�N�����v���ɂ߂ăz�[�X�̘A���̕Б����O���܂��B�\�߃��W�G�[�^�[���Œ肵�Ă���R�{�̃{���g(���E�A�㕔����)���O���Ă������ق����X���[�Y�ł��B���ƁA���W�G�[�^�[�t�@���̃P�[�u���R�l�N�^���O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��B �@�ʐ^�Ō���Ƌ͂��Ȍ��ԂɌ����܂����A����ł��\�������͏o���܂��B �@�����O�ɑO�o���N�̑O���̌��ԂׂĂ݂�ƁA�����Ă����̂͋z�C���ŁA���b�N�i�b�g�����Ȃ肫�����߂��܂ꂽ��ԂɂȂ��Ă��܂����B�ɂ��Ȃ�̂��Ǝv���Ă����̂ňӊO�B����́A0.15�̃Q�[�W�ŏ����ɂ߂ɒ������Ă݂܂����B �@�������� �@�A�C�h�����O���҂����ƈ��肵�āA����Ȃɂ��Ⴄ���̂��ƁA���߂ċ����܂��B�O�o���N�̋z�C���i�Б��j���A�ق�̏�������Ă��������Ȃ̂ł���....�B�v���O���������Ƃقړ�������Œ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă�̂�����A����������Ƃ��₷���Ɨǂ���ł����ǂˁB(2005.7�X�V) |
||
�@�@
�@
| �@�N�[�����g���� �@ |
 �@ �z���c�̃����O���C�t�N�[�����g(LLC)�B �@ 2Liter����̌��t�𔖂߂�^�C�v�B 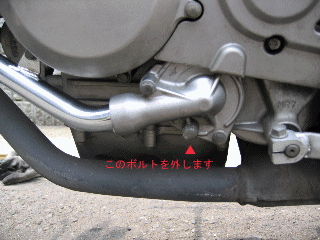 �@ �E�H�[�^�[�|���v�̃h�����{���g�B���\�����ǂ��o�܂��B  �@ �Y���܂̌��ʂ̌��B�E���N�[�����g�̂݁A �@ �����Y���ܓ���́A���ꂼ��ǂ��U��������B �@ �X�ɂ��炭�o�߂����������Ȋ����B |
|
| �@�ď�ɏ�Ԃ��Ă��āA�G���W�����疭�ɔM�C�����ăp���[����������Ȃ��悤�ȋC���������߁A��p�����������Ă݂邱�ƂɁB���łɃ��W�G�[�^�[�̐����s���܂����B �@�p�ӂ������ �@�@10mm�����`�A�v���X�h���C�o�A���|�p�Ƀu���V�A �@�@���U�[�o�[�^���N����̔������p�ɒ��ˊ���g�p�B �@�@���R�A�V�i�N�[�����g( Holts Long Life Coolant95 2000ml����)���B �@�@����͗�p�n���̐��ƁA�Y���܂������̂ňȉ��̓�B �@�@���W�G�[�^�[����(WAKO'S ���W�G�[�^�[�t���b�V�� 500ml����) �@�@�N�[�����g�Y����(WAKO'S �N�[�����g�u�[�X�^�[ 300ml����) �@����� �@��ɐ����s���̂ŁA��p�����O�ɁA���W�G�[�^�[���܂𓊓����܂��B�܂��A���W�G�[�^�[�L���b�v���O���܂��B����͂��ݎ~�߂̃v���X�l�W���ɂ߂Ă���A���ʂɍ��ɂЂ˂�ƊO��܂��B �@�K��ʂ̐��܂����A�A�C�h�����O���Ă���r�����A�X�ɗ�p���H�𐅐��܂��B���W�G�[�^�[�L���b�v���O���Ă���ƁA�h�������炩�Ȃ�̐����Ŕr�������̂Œ��ӂ��܂��B�Ȃ��p�t�͗L�Q�Ȃ̂ł��̂܂̂ĂȂ��悤���܂��B �@���U�[�o�[�^���N�́A�V�[�g���O���A�����̃V�[�g�J�E�����O���ƁA����o���܂��B�L���b�v�����A�N�[�����g���A�z�[�X���q�������ˊ�Ŏe��Ɉڂ��܂��B�ŏ������蓮�ŋz���o���āA�^���N���Ⴂ�ʒu�Œ��ˊ�̃s�X�g�����A�T�C�t�H���̌����𗘗p���đS�Ĕ������܂����B �@����g�p�����N�[�����g�́A���t�𐅂Ŕ��߂Ďg���^�C�v�ł��B�N�[�����g�͔Z�x�����������A��蓀�����ɂ����Ȃ�܂����A��p�����͔Z�x�����������ǂ��Ɖ����ŌĂL��������̂ŁA�ł������w���30���Z�x�Ŋ�߂��܂����B����ł�-16�x�܂œ������܂���B�ŁA�X�ɓY���܂��K��ʍ����Ă���A�ԑ̂ɒ������܂����B �@�g�p�� �@�@�@�@�N�[�����g�S�e�� �@�@�@�@�@1.4�k �@�@�@�@���U�[�o�[�^���N�e���@�@ 0.3�k �@�Y���܂̌��ʂ́H �@����͓Y���܂��g�p����̂ŁA�O�����Ă��̌��ʂ����Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�����ł��B ���ۂɎg�p����Z�x��30���N�[�����g�A�Y���܂�Y���������́A���Y���̂��̂�ʁX�̃y�b�g�{�g���ɓ���A���A���ʂ����Ă݂܂��B �@�Q�{�̃y�b�g�{�g�����ɂQ�O�b�قǐU���ĖA����������A���ꂼ��ǂ��Ȃ邩���Ă݂܂����B �@���Y���̂��́i�ʐ^�E���j �@�@���ʂ̐��Ɠ����悤�ȖA�������B�Y���������̂��A���������Ȃ��悤�Ɍ�����B�A���A�A�͑傫�߂ŁA������܂łɌ��\���Ԃ����������B���H�͕��ʂɃR���R�����������B �@�Y���ܓ���̂��́i�ʐ^�����j �@�@�ꌩ����Ƃ悭�A�����Ă���B�A���A�傫�ȖA�͏o�����A�ׂ����A���S�ď�ɏW�܂�A�N�[�����g���ɍ������銴���͖����B�Y�_���̂悤�ȃV�����[�Ƃ����������āA�����ɖA��������B���炵�Ă݂Ă��R���R���������H�͏o�����A�\�ʒ��͂��Ⴍ�Ȃ��Ă���悤�Ȋ����B �@�ƁA���炩�ɐ����̈Ⴂ�����Ď��܂����B���ۂ̐��\�ɂǂꂾ���e�������邩�́A�X�p�[�_�ł͊m�F�ł��邾���̕ω��������܂���ł������ACBR600F�ł͌��ʂ������܂����BCBR�͊X���Ȃ�~��ł����Ă��M���҂��łقڏ�Ƀt�@�������܂����A�Y���܂�����ƁA������������G�߂ł̓t�@���̉��p�x���ڂɌ����Č���܂����B��p�����̓_�ŁA����Ȃ�Ɍ��ʂ�����悤�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2007. 10 �NjL�j |
||
�@
�@
�@�M�Ɏア���M�����[�^�[�̕��M�����ł��B �@�u�s�̌Â��^�ł́A���炩�ɕ��M���ɖ��̂���@�킪����悤�ł����A�X�p�[�_�̓V�[�g���x����傫�ȕ��i�Ƀ��M�����[�^�[�𖧒������Ă���A�����������͏��Ȃ��悤�ł��B���������S�̂��߁A����Ƃ�܂��B �@��Ƃ����Ă���𖾂����V���R���O���X��h�邾���B�q���g�̓p�\�R���̂b�o�t(�W�ω�H)�Ƀq�[�g�V���N(���M��)��ݒu����ہA�b�o�t�ƃq�[�g�V���N�̊ԂɌ��Ԃ��o���Ȃ��悤�A�V���R���O���X��h����邱�ƁB�����M�`�������ŕ��M���郌�M�����[�^�[�ɂ�����Ă݂��킯�ł��B�l�b�g��ł̓��M�����[�^�[�̐ڐG���镔�i�i�T�u�v���[�g�j�����A�u�Ŗʂ������Ă���l�����܂�(������)�B�������A���t���鑤�̃��M�����[�^�[���̕��ʓx���H�H�Ȃ̂ŁA�O���X�Ō��Ԃ߂�̂ł��Ⴂ�͖����낤�Ɣ��f���܂����B�������茤���ɂ͎��Ԃ������邵�B �@��ƂƂ��ẮA���M�����[�^�[���O���A�O���X��h���Ă�����t���邾���B �@�܂��V�[�g���O���A���������J�E�����O���܂��B�O���̃O�����b�g(�J�E���x�����̎h�����Ă����S���̏�)�̗����ɁA���M�����[�^�[������̂ŁA���̃T�u�v���[�g���̂��O���K�v������܂��B �@�t���[�����̃w�b�N�X�{���g�A�V�[�g�X�e�C���̃{���g���O���A�T�u�v���[�g���t���[�ɂȂ�܂��B���M�����[�^�[�̃R�l�N�^�[���O���A�v���[�g���Ђ�����Ԃ��ă��M�����[�^�[�̌Œ�{���g���O���܂��B �@���ӓ_�́A�O���X�͂����܂ł��u���ԁv�߂邽�߂̂��̂Ȃ̂ŁA�ɗ͔����A���`���h�邱�ƁB���h��͕��M�̂��߂ɂ͋t���ʂł��B �@��ƌ�́A���ɖ�肪�o�Ă����킯�ł��Ȃ��̂œ��R���̕ω����Ȃ��A���ʂ̂قǂ͊m�F�̂��悤������܂���B�����܂ŕی��i�C�x�߁j�ł�����B���ƁA���������v���[�g���O���̂ŁA���M�����[�^�[�ɐڑ������R�l�N�^�ɁA�r�j�[���e�[�v���Ŗh���������{�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B�ӊO�ƉJ�������Ƃ��͂��̕ӂ������萅�𗁂тĂ���̂ŁA�O�ɂ͔O����ꂽ�ق��������ł��傤�i���̂����Ƃ͌���Ȃ������HP�Ƀg���u���Ⴀ��j�B �@�Ȃ��A���M�����[�^�[���̂��M��̋������ꂽ���́i��p�t�B���t���A�i�� 31600-MV4-010�j ������܂��B �ǂ���炻�̃��f���̏����ɂ͔M�Ɏア�t�B���Ȃ��i�����H�j���g���A�ݔ��̌������������f��������ɑ��i�ɕς��Ă���悤�Ȋ����BCBR600F�����l�ł����B���[�J�[�͑��ŃR�X�g�팸�����Ă�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2007.11�NjL) |
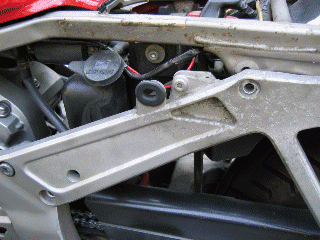 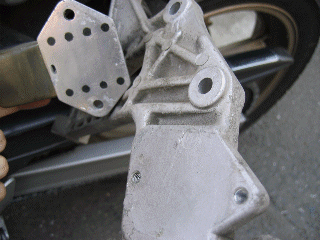 |
�@
�@
| �@�V�[�g���ւ��@ |
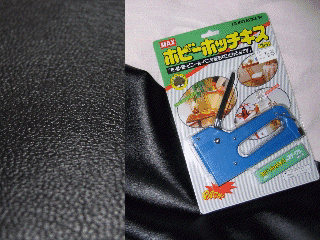 �@�^�b�J�[�ƍ���B���͕\�ʂ̃A�b�v�B�V�R�v���ۂ��ł���H 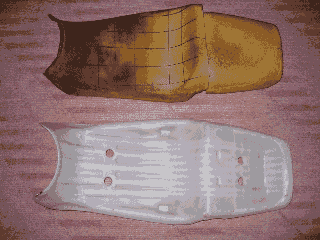 �@�V�[�g�x�[�X�ƃE���^���B�E���^���͉��H���邱�Ƃ��������� �@���ߑO��ɃJ�b�g���Ă��܂����A�\�蒼�������Ȃ�s�v�ł��B  �@�V�[�g�\��̉��H�B�O�������킹�āA���Ƃ͌������킹�B  �@��͑O��̂ݗ��߂���ԁB���͊�����B�V�i���ł��B �@�r�t�H�[��A�t�^�[�ł����A�ʐ^�̍����͉���ł��ˁB  �@�オ�Б��̂ݖD������ԁB���͌�������B �@���̌�A������͂߂ăJ�V���܂��B |
| �@�V�[�g���ꕔ�j��Ă���A�v�����Ȃ�d�����Ă��邽�߁A����ւ��邱�Ƃɂ��܂����B�V�[�g�̒��ւ������탁���e���H�Ƃ��v���܂����A�ȒP������A�����ĂˁB �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`(10mm)�A�z�b�`�L�X�i�^�b�J�[�j�A������v�A�r�j�[���V�[�g�A�����S���p�{���h�A �@�@���₷��A�J�b�^�[�A���W�I�y���`�A���������i�����Ă��j�A�ʂł��傤�B �@������v�ɂ��āB��ʓI�Ȃ��X�ōɂ��Ă�����̂́A���x�I�ɏ����ア�悤�ł��B�o�C�N�V�[�g���h�ŁA���[�J�[�����Ɠ����̕����̍���(\2,310/m)���Ă��������A���ւ��܂����B �@�r�j�[���V�[�g�͓��}�n���Y��(��90cm�A\80/��)�B����̉��ɏd�˂āA�V�[�g�̖h���������߂܂��B���g�����e�i���X�����Q�l�ɁA�lj����邱�Ƃɂ��܂����B �@�^�b�J�[�i�z�b�`�L�X�j�́A�ǂɑł����肷�邽�߂̐�p�̂��̂������Ă��܂��BMAX�K���^�b�J�[�ɂ��܂����i\1,154�j�B����̓V�[�g�x�[�X�ɖw�ǎh���炸�A���W�I�y���`�Ŏh�����ލ�Ƃ��K�v�ł����B�ڍׂ͌�q�B �@��Ǝ菇 �@�܂��A�V�[�g���O���܂��B�����s�v�ł��ˁB���ɃV�[�g���̃i�b�g�����A�V�[�g�x���g���O���܂��B �V�[�g�x�[�X�Ɏh�����Ă���^�b�J�[�̐j���A����������W�I�y���`����g���Ĕ������܂��B����ƃV�[�g�͊ȒP�Ɏ��܂��B�ȉ��A�V�[�g�W���C�̂g�o�Ȃǂ��Q�l�ɁA��Ƃ�i�߂܂��B �@�V�[�g�̃E���^���͎����Ă��邱�Ƃ������̂ŁA���炭���������܂��B���͔̂j��̂������^���N�ɐڂ��镔�����琅�������āA�E���^�����ϐF���Ă��܂���(�ʐ^)�B��T�ԂقǁA�\���Ɋ��������܂����B���낢��Ȃg�o���Q�l�ɁA�A���R��������Ă݂悤�Ƃ��܂������A���ǃm�[�}���`��ł������Ƃɂ��܂����B����t����E���^���ɓK�ȍޗ����A�Ȃ��Ȃ��������߂ł�(�ʐ^�ɂ͖����ł����A�������̂͏_�炩�����܂���)�B �@�����̂��߂ɂ��A��������V�[�g�x�[�X�ƃE���^�������܂��B���Ɗy�ɂ͂���܂��B�V�[�g�x�[�X�̃E���^����ڒ�����ʂɁA���₷����|������A�V�[�g�x�[�X�𐴑|���܂��B�E���^���ƃV�[�g�x�[�X���ʂ̑S���ɁA�����S���p�{���h�𔖂��h����܂��B���ʂƂ���ŐG��Ď��������Ȃ��ʂɊ�������A�ʒu���������荇�킹�ē\�荇���܂��B �@�O�����V�[�g����^������ɁA��܂��ɍ�������܂��B�I���W�i���͑S���ɂ킽���Đ܂�Ԃ���D���t���Ă���܂����A�ʓ|�Ȃ̂Ń^���N�ɂ����镔���̂ݐ܂�Ԃ����������A�~�V���ŖD���t���܂����B�����ɂ���ẮA�܂�Ԃ��͖����Ă����荞�݉\�ł��B �@��͌������킹�ŁA�V�[�g�x�[�X��Ƀr�j�[���V�[�g��킹�A���̏�ɍ�����悹�܂��B�O�ƌ����^�b�J�[�ŌŒ肵����A���X�Ɉ�������A�V�[�g�ɖ��������Ȃ����Ƃ�i�߂܂��B �@�����Ƃ��Ă͏c�i�ԗ��i�s�����j�ł͂Ȃ��A�������Ɉ�������̂����C���B����o�T�~���ʂɎg���A���~�߂��đS�̂̃o�����X�����Ȃ��炵�������ǂ��ł��B�Ō�ɃV�[�g���ʂ��������Ȃ���A�V�������l�Ɉ�������A�^�b�J�[��ł����݂܂��B�������Ȃ��ƍ���ƒo�����ɂȂ�܂��B �@�^�b�J�[�̐j�́A�V�[�g�x�[�X�ɖw�ǎh����܂���ł����i���ɉ��܂����Ƃ���j�B�����ٍl�̌�A���W�I�y���`�Őj��ł����ނ��Ƃɂ��܂����B �@�P�D�܂��A�^�b�J�[�Őj��ł��܂��B �@�Q�D���W�I�y���`�ŁA�y���`�̐悩��P�~���قǐj���o��悤�A�^�b�J�[�̐j�̕Б���݂͂܂��B �@�R�D���̂܂܃V�[�g�x�[�X�ɓ˂��h���悤�ɉ������݂܂��B �@�S�D���Α��̐j���A�������炢�������݂܂��B �@�T�D�S�̂����S�ɑł����߂�܂ŁA�R�D�S�D���J��Ԃ��܂��B �@�ƁA���Ō����̂͊ȒP�ł����A�q�W���[�Ɏ�Ԃ̂�����i����ɂ��Ȃ�j��Ƃł����B �^�b�J�[�̐j�ׂ͍��̂ŁA�Q�D�̎��ɂ��܂蒷����яo��悤�Ɏ���������ƁA�ȒP�ɋȂ����Ď��s���Ă��܂��܂��B�ł���A�^�b�J�[�͂����Ƌ��͂Ȃ���ǂ��ł��傤�B �V�[�g�x���g�̒���ւ� �@�V�[�g�x���g���T�C�h����Ђъ���Ă����̂ŁA�]��̍���Œ���ւ��邱�Ƃɂ��܂����B �@�x���g�̗��[������ŃJ�V���Ă���܂����A�}�C�i�X�h���C�o�[�ȂǂŋN�����āA�O���܂��B����͂��Ȃ�K�тĂ��܂����A�p�[�}�e�b�N�X�iPermatex�j�̎K���Ƃ��܁ANAVAL JELLY ���g�p���܂����B�s���N�F�̕����ʂ�[���[��̖�܂ŁA�����ς��L�������܂��B���C�̗ǂ��Ƃ���Ŏg�p����悤���ӏ������������̂ŁA��܂𐁂��t����������A���O�Ő����ԕ��u���܂����B���̌�A��܂𗎂Ƃ��Ă݂�ƁA���Ȃ��Y��ɂȂ�܂����B�\�ʂ����̎K�͊��S�ɗ����A�[���H�����K�͍����ϐF���āA�h�K�疌�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�A���A�K�тĂ��Ȃ����̈ꕔ�́A�����ϐF���Ă��܂��܂����B �@�x���g�̐c�́A�ʐ^�̂悤�ɏ�v�ȃ��[�v�̂悤�ȑf�ނŏo���Ă���A���̐c�ɍ�����������Č����p�~�V���ŖD���܂����B��ŖD���̂͌��\���C���v��ł��傤�B����ł͂��ނ悤�ɂ��Ă܂��Б���D���A���Α���D���Ƃ��́A�����������������ăe���V�����������Ȃ���A�D���܂����B�ꕔ�A�D�����Ԃ��o��ł��܂��܂������A�V�[�g�ɉ����t�����鑤�Ȃ̂ŁA���Ȃ��������Ƃ�.....�B �@�Ō�ɁA���t���{���g��ʂ������|���`�ŊJ��(��V�D�Tmm)�A�x���g�̕\���ɒ��ӂ��ċ�����J�V���܂��B����ŁA�V�[�g�͊��S���ւ��ƂȂ�܂����B (2006. 5) |
�@
�@�@
| �@�K�\�����R�b�N�����@ |
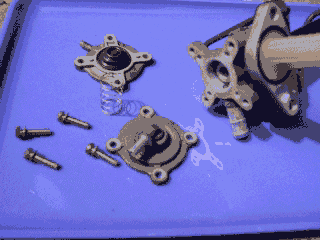 �@���������K�\�����R�b�N�B�オ�L���u�̕����ō쓮���� �@�_�C���t�����B����̕s���̌����͋��炭����B���� �@����ƃ��Z�b�g�����悤�ł���......�B 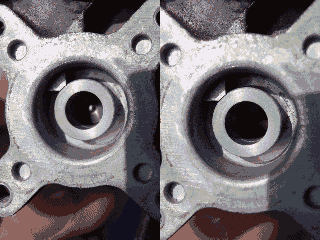 �@�R�b�N�����̍쓮�B����OFF���B�E��ON���B�����Ń{�[�� �@���K�\�����̒ʂ���~�߂Ă���̂��킩��܂��B�K�\������ �@��ʏ㕔����A�����̃{�[��������ʂ��ĉE�ɗ���܂��B |
| �@����́A�ˑR����Ă��܂����B �@�ᑬ�ł��������������������̂���ɁA���ɂ̓A�C�h�����O���Ȃ��Ȃ����̂ł��B���������ȏ�̃A�N�Z���J�x�ɂȂ�ƁA�h�b�J���Ɖ������܂��B�����ĂƂĂ�����܂���B �@�L���u�ł����Ă݂悤�Ǝv���A�K�\�����^���N���O���ׂ��`���[�u���O����.......�i���g�AOFF�ɂ��Ă���͂��̃R�b�N�����ʂ̃K�\�������I �@�C����蒼���āA�ǂ��������̂��K�\�����R�b�N�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�^���N���̃K�\�������y�b�g�{�g���Ɉڂ��ւ��A�V�[�g���O���č�ƊJ�n�B �@�K�v�ȓ��� �@�@�����`(10mm)�A���W�I�y���`(�悪����Ȃ���ǂ�)�A�V�[�g(�^���N��u���ꏊ)�Ȃǂł��B �@��Ǝ菇 �@�^���N�̌㕔�𗯂߂Ă���10mm�{���g���O���A�^���N��������Ɏ����グ�܂��B�m�[�}���̃K�\�����`���[�u�͒Z���ă^���N�������グ�ɂ����̂Œ��ӁB�E������K�\�����`���[�u(��)�A�o�L���[���`���[�u(��)���O���āA�t���[���ɉ��킹�ă^���N�����炷�ƁA�O��܂��B �@�R�b�N���̂̓{���g�ŃX�e�[�H�Ƌ����߂���Ă���A�ʐ^�̃_�C���t���������v���X�˂��ŗ��܂��Ă��邾���Ȃ̂ł����ɊO���܂����A�^���N���ɂ܂��K�\�������c���Ă���͂��Ȃ̂ŁA���ӂ��܂��傤�B�����߂͏o���܂��A�K�\�����c�ʂ����Ȃ��Ƃ��́A�^���N�O�������ɂ��ĕǂɗ��Ă�����ƃK�\���������ɃR�b�N���O���܂��B �@���ɔj���������i�������A�������킩��Ȃ��̂ł����A�����������L�̏Ǐ�͎���܂����B �Ƃ肠�����A�d�����Ă����K�\�����z�[�X��ʓr�w���������̂ɕt���ւ��č�ƏI���B �@�ォ��l�����v����������Ƃ��ẮA�R�b�NOFF�̂܂܁A�G���X�g����܂ő����Ă��܂����Ɓi�h�W�j������ƁA���̌ォ�甭������悤�ȋC�����܂��i�����܂ʼn����ł��j�B�_�C���t�������A����t���Ă��܂��̂ł��傤���H �@�@�K�\�����R�b�N�n�����O�@�O�a28.5mm ���a24.3mm ������2.0mm �@�@�K�\�����z�[�X�@�@�@�@�@ �O�a13.0mm ���a 9.0mm�@(���̓��a���������傫���ł��B�K�\����������....) �@�@�o�L���[���`���[�u�@�@ �O�a �@ -mm ���a �@-mm �@�K�\�����z�[�X�ɂ��āB���}�n���Y�ōw�����܂����B�σK�\�����z�[�X�Ƃ��Ĕ����Ă�����̂́A�����ȉ��r�x�[�X�̂��́B����NBR�S��(�ϖ����S��)�Ƃ����f�ނ̂��̂́A�K�\�����z�[�X�ɂ͎g���Ȃ������ł��B�ꎞ�I�Ȏg�p�Ȃ�\�ł����A�����Ԃ̎g�p�ɂ͕s�K�Ƃ̂��Ƃł��B �@���r�x�[�X�̂��͕̂\�ʂ̃R�[�e�B���O�ɂ��ϖ������o���Ă���A�o�C�N�̂悤�ȃN���b�v�ŗ��߂�g����������ƁA��������R�[�e�B���O�������ė��Ղ��悤�Ȃ̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B �@�n�����O�ɂ��āB�����ǎ���̕��i�Ƃ��Ĕ����Ă�����̂́A�ϖ����͂Ȃ��f�ނł��B�I�C���p�b�L���ȂǂɎg�p������̂́A�K��NBR�S���Ƃ�����ŏo���Ă��镨�ɂ��܂��傤�B �@�Ȃ��������i�ȊO���g�p����ꍇ�́A���ȐӔC�����肢���܂��B |
�@
| �@�n�u�_���p�[���� |
�@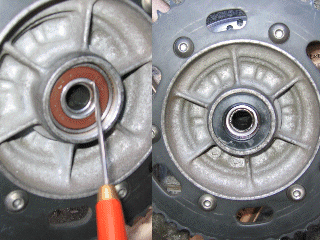 �@ �_�X�g�V�[���̓h���C�o�[�ŁA�x�A�����O�� �@�V�[���͐�̐�����c�[���ŊO���܂��B 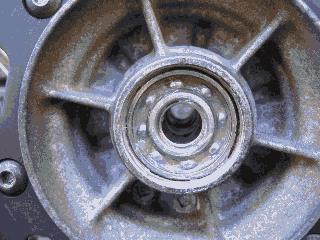 �@�x�A�����O�ɁA�O���X����������l�ߍ��݂܂��B  �@ �_���p�[�ł��B�E�͘A���������ꂽ�g���Â��B |
|
| �@�����z�C�[�������Ď�Ńz�C�[����O��ɓ������ƁA�͂��ɗV�т��������܂��B����Ȃ�K�^�͑S�������͂��B�����Ń_���p�[���������܂��B�������ɂ������������������܂������̌����͌�ق�......�B �@�p�ӂ������ �@�@�Ή�����傫���̃\�P�b�g�A�g���N�����`�A�G�N�X�e���V�����Ȃǂ̍H��B �@�@�W���b�L�B�����̓�A�W���b�L�ł��B �@�@���|�p�̃E�G�X�ށA�O���X�A�K�v�ɉ����ċ�������(�s�J�[����)�B �@�x�A�����O �@�܂��A�X�e�b�v�̕t�������W���b�L�A�b�v���܂��i�O�ւ̂Ƃ��̓G���W�������A���̏ꍇ�j�B���肳���邽�߁A���o�[��R�Ŕ����ăt�����g�u���[�L����������Ԃɂ��܂����B����Љ�Ă���̂̓����ł����A��{�I�Ƀt�����g�������ł��B �@�`�F�[��������A�J���[�A�X�v���P�b�g���t���Ă���n�u�A�z�C�[���A�J���[�Ƃ������i�\���ł����A�n�u�ɂP�A�z�C�[���ɂQ�i������͓����Q�j�A�x�A�����O���t���Ă��܂��B�x�A�����O�̏�ɁA�V�[�����ł����܂�Ă���̂ŁA�傫�ȃ}�C�i�X�h���C�o�Ȃǂŏ��X�ɂ������ĊO���܂��B�i�ʐ^��j �@�x�A�����O���̂��V�[���^�C�v�Ȃ̂ŁA�V�[���s�b�N�Ȃǁi�疇�ʂ����g���܂����j�ŁA���֑�����߂����Ď��܂��B�\������x�ɓh���Ă������O���X�́A���F�ɓ������Ă��܂����B���낲�늴�͂Ȃ����߁A�Â��O���X�𗎂Ƃ��A�V�����O���X���l�ߒ����܂��B�������蒆�܂ʼn������݂܂��B�i�ʐ^���j �@�u���[�L���̃x�A�����O�́A�O���X����āA�^���ԂȂ��т��o�Ă��܂����I�x�A�����O��p�ӂ��Ă��Ȃ��������߁A���т��o���邾�����Ƃ��A�O���X���l�߂Ă����܂����B�z�C�[���̃K�^�̌����͂����ł��ˁB�Ȃ�ׂ����߂Ɍ����������ł��B�O���X�A�b�v�I����A�V�[�������ʂ�ɂ͂ߍ��݂܂��B �@�n�u�_���p�[ �@����̎��̃_���p�[�ł��B�z�C�[���P�̂ɂ���ƁA�n�u�͊ȒP�ɊO��܂��B������J�`�J�`�ɍd�������n�u�_���p�[���o�[���o�Ă��܂����B�������A�������܂�Ă����肷��̂������āA���Ȃ�ւ���̂��銴���ł��B�_���p�[��n�u�̍��J�X��|�����āA���^�����o�[��h�z�����V�i�_���p�[���z�C�[���ɃZ�b�g���܂��B�i�ʐ^���j �@�����̌��� �@�����I����̊��z�́A�܂����̌y�����ƁI���ꂪ�{���̎p�ł��傤�ˁB ���炭�R����A�b�v����ł��傤�B���Ƃ̓x�A�����O�ɖw�ǃO���X�������Ă��Ȃ��������߂̕ω��ŁA���l������낵��.....�B �@���ƃz�C�[����]�����̃K�^�͂Ȃ��Ȃ�܂������A�������ւ̃K�^�́A �@�K��g���N �@�@�@�@�����A�N�X���i�b�g �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9.0kgfm �@�g�p���i �@�@�@�@�n�u�_���p�[�@�@�@�@41241-KB7-000 �@\357/�� �@�n�u�_���p�[�͂U�K�v�BCBR250RR�AHORNET250�ȂǂƋ��ʕ��i�ł��B NAPS�ł́A�U�Z�b�g�̂��̂��X���ɂł���܂����B |
||
�@
| �u���[�L�f�B�X�N���� | |||
�@���R�[�h�Տ�ɂȂ��Ă����t�����g�f�B�X�N�u���[�L���A�V�i���i�Ɍ������܂��B �@�{�������ł���ׂ��f�B�X�N�ł����A�g�p����ɂ�ď��X�ɂł��ڂ��ɂȂ��Ă����܂��B�p�b�h�̓���ʂ����ւ���Ԃł����B�Ƃ������Ƃ̓��[�^�[�͂P��]���Ă�H�H �@�������ɋC������_�́A�Ίp����ɒ��ߕt���Ă������Ƃł��B����́A�n�߂Ɏ�Ōy�����܂�Ƃ���܂őS�ė��߂���A 1.5kgfm�ɂĉ����߁A���̌�K��g���N�� 3.0kgfm�ɂĖ{���߂��s���܂����B�����W���Ă��镔�i�Ȃ̂ŁA���i���T�d�ł��B�V�i�̃{���g�ɂ̓l�W���b�N��(�ΐF)���h�z����Ă���A���̂܂g�p���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2007. 4�X�V) �@ |
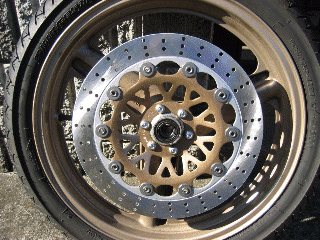 �@�{���g�͑Ίp����ɁA�������߂܂����B �@��M�Ő��}�[�N��`���v�̂ł��ˁB |
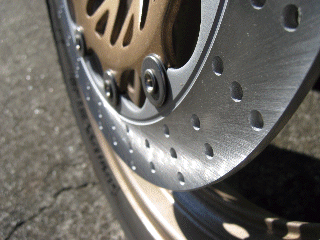 �@���R�Ȃ�����������ʂł��B���炵�͂ǂ� �@���炢�v�邾�낤���H�����O������Ȋ����B �@�p�b�h�̂�����R���̕��ŁA����ōa�� �@�ɂȂ��Ă���̂�������ł��傤���H |
|
|
�@�g�p���i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�K��g���N �@�@�@�@�u���[�L�f�B�X�N �@45120-KY6-000�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���[�L�f�B�X�N�{���g �@�@�@�@3.0kgfm �@�@�@�@���{���g�@�@�@�@�@�@ 90105-KV0-700�U�K�v |
|||
�@
| �@�G�A�N���[�i�[���� |
�@ 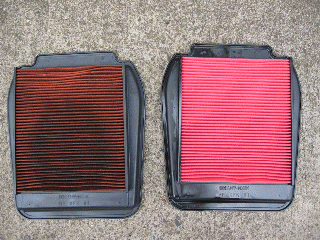 �@ ���Ȃ艘�ꂽ���G�A�N���ɑ��Aῂ������炢 �@���邢�V�G�A�N���B�r�X�J�X���Ƃ����A�뎆�� �@������ݍ��܂����g���̂ă^�C�v�ŁA���Ȃ� �@�������Ă���̂Œ��ӁB |
|
| �@�G�A�N���[�i�[�̌����ł��B�s�X�n�ł̎g�p���ƁA��������7�`8,000�L���ŃA�E�g�̂悤�ł��B�������ȏ�ł��g���܂����A���̂��炢�̋����Ŏ���������������ɂȂ�A���̌゠�܂芴���Ȃ��Ȃ�C�����܂��i����H�j�B �@�����͂܂��K�\�����^���N���O���A�G�A�N���[�i�[�{�b�N�X�̃v���X�l�W���O���G�A�N��������܂��BCBR600�e���ƃ^���N�O���������グ�ČŒ肷��A�G�A�N���{�b�N�X���J�����܂��B �@�ŁA�g���Â��̃G�A�N���͂����̒ʂ�B���Ȃ艘�ꂪ�l�܂��Ă܂��B���Ƃ͕t���ւ��邾���ł��B �@�����̌��� �@�ꏏ�Ƀv���O�����������̂ŁA�����オ�肪���Ȃ�y���Ȃ�܂����B�R��A�b�v�����҂ł��܂��B �{���͍Ďg�p�ł���A�j���m�Ƃ��̏����^�C�v�̃G�A�N���[�i�[������悢�̂ł����A�����̓}�C�i�[�Ԃ̉^���A������߂鑼�Ȃ������ł��B���Ȃ݂ɂ���͂u�s�q�Q�T�O�Ƌ��p�ł��B �@�@�@�G�A�N���[�i�[�G�������g�@17210-KFK-000 �@�@�@�X�p�[�N�v���O�@�@�@�@�@�@�@ CR8EH-9 �@���Ďg�p �@�����G�A�N�������A�I�C���h�z���Ďg�p���Ă݂܂����B�i���F���[�J�[�ۏؑΏۊO�j �@�V�i����8,000�L���قǎg�p�����Ƃ���A��ɂ���ď������C�������Ȃ��ė����悤�Ɋ������̂ŁA�ƒ�p������܂Ő�܂����B������܂��ƁA���Ƃ���܂܂��Ă���I�C���́A���S�ɂ͗����Ȃ��悤�ł��B�\��������������A�j���m�̃t�B���^�[�I�C�����y���h�z���āA�������܂����B �@������ʁA��L�̌��C�̖�������͉��A�V�i�G�A�N���̋C���ő���܂����B �@����ڂ̐���4,000�L�����ŁA�܂������������Ȃ銴�������n�߂��̂ŁA�Q�x�ڂ̐������܂����B����͂j���m�̃N���[�i�[�ɂāB������܂��A�����͏��Ȃ��ł����A����̗����͋t�ɗǂ��悤�ł��B��������p�i�Ƃ����������ł��i�����i�̐��p�ł͂Ȃ��ł��A�O�̂���....�j�B �@�����Ɏ��Ԃ������肻���Ȃ̂ŁA�������z�ŕs�D�z�������y���������Đ@���Ă��犱���܂����B�x�Ƀu���V�ł������Ă���̂ŁA�\�ʂ͑����щH�����Ă��܂����A�t�B���^�[���̂͂��Ȃ�ϋv�������肻���ł��B �@�ŏI�����ł��B���ڂ̐��|����Q��km������Ȃ������ɁA�����������������i�R������b�^�[����1km�߂��������j�̂ŁA���܂���p�I�ł͂Ȃ��ł��B�r������Ƃ��Ă��P��km���X��������A�f���ɐV�i�G�A�N���ɂ��������C���I�ɂ��o�ϓI�ɂ��ǂ������ł��B����̌��ʂ��炷��ƁA�W��km������łP����A�P���Q��km�ŐV�i�����A�Ƃ������������ȁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2007. 4�X�V�j |
||
�@
| �@�O���b�v���� |
�@  �@ �X�p�[�_�����ɑ��āA�w�Ǎa�̖��� �@�O���b�v�B�l�����w���ɍׂ����a������A �@��ׂ��Ȃ��Ă��܂��B |
|
|
�@�O���b�v�̌����ł��B �@�܂��A�v���X�l�W�ŗ��܂��Ă���o�[�G���h�����O���܂��B��������Ă���O���b�v�́A�p�[�c�N���[�i�[�𐁂����ނƃY���Y���Ɗ���o���A�v�������ȒP�ɔ������Ƃ��o���܂����B�Ďg�p���Ȃ��ꍇ�́A�J�b�^�[�Ő��Ă��܂��Ɨǂ��悤�ł��B �@�ŁA���������̂�CBR600F�����O���b�v�B�ꍠ�u���b�V�O���b�v�v�Ƃ��Ęb��ɂȂ������m�ł��i���}�n�ɈڐЂ������b�V�̓R�����g�������Ă��邻���j�B �@�Ǘ��l�̏ꍇ�A�X�p�[�_�I���W�i���̃O���b�v�ł́A���ɑ��쐫�̗ǂ��Ȃ��~�p�O���[�u�ŏ_�炩�����낤�Ƃ���ƁA�O���b�v����]���Ă��܂����Ƃ�����܂��i�����ƈ����I�Ƃ����̂͂��Ă����j�B���̃O���b�v���Ƃ��������܂���B�_�炩�߂̃S���ł����A�������i�炵�����肪����ȂɌ������Ȃ��̂��ǂ��Ƃ���B �@�g�p���i �@�@�@�@�q�O���b�v�@�@�@�@53165-MY9-890 �@�@�@�@�k�O���b�v�@�@�@�@53166-MY9-890�@ �@\920/�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2006.12�X�V) |
||
�@
| �@�J�E����C�@ |  �@�������犄��Ă���J�E���B����̓v�����y�A�� �@�ڒ����Ė�������B�Ԃ����ł͏����B���ł��Ȃ� �@�̂ŁA���h�蔒�A�Ԃ̏��ɓh��܂��B |
| �@�w��������T�C�h�J�E�������ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���̂ŁA������C���܂��B �@����̌����ł����A�J�E���ɓ]�|�ŎC�����悤�ȐՂ͖����A�P���Ƀo�L�b�Əc�ɂЂт������Ă��邽�߁A�O���u�o�[��͂ݑ��˂Ċ������悤�ł��B�I�[�i�[�̕��Ȃ炨������ł��傤���A�X�p�[�_�̓T�C�h�J�E�����Ƀl�b�g�|���t���O���u�o�[�����Ă��܂��B���ꂪ���܂�o�����炸�B��Ă��邽�߁A�݂͂ɂ����ł��B���������ƃv���X�`�b�N�̃J�E�����������|���Ă��܂��܂��B�����^�m�r�q�W�O�����l�ł����̂ŁA���̔N��̃z���_�Ԃ͂����Ȃ̂ł��傤�B�m�`�r����^�͉��ǂ���ăJ�E������傫���͂ݏo��O���u�o�[�ɕύX����Ă��܂����A�X�p�[�_�͂��̕s�l�C�䂦�ɁA���ǑO�ɐ�ʼn������̂��Ǝv���܂��B �@�p�ӂ������ �@�v�����y�A�@�@�@�@�@�@���������̃v���X�`�b�N��C�ށB�f�ޓ��m��n�����邽�߁A���ł� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڒ��͂������܂��B���}�n���Y�ȂǂŎ�ɓ���܂��B �@�p�[�c�N���[�i�[�@�@�h���p�̃V���R���I�t�Ȃǂ̒E���ނ̕������ǂ��B �@���ɓh���i���n�����̂��߂̃T�[�t�F�C�T�[���������ق����ǂ��j�A�ϐ��y�[�p�[�ȂǁB �@���ۂ̍�Ƃł����A�V�[�g���O���ăr�X���O���J�E�����ԑ̂���O��܂��B�ԑ̂�����Ă����̂ŁA�܂��J�E���𒆐���܂ŐA���ꂽ�������p�[�c�N���[�i�[�ŏ\���ɒE�����܂��B �@���Ƀv�����y�A�ł��B�������ꂽ�����ɏ����U��|���A�t������n�܂𐂂炵�܂��B�����ɔS���Čł܂�܂��̂ŁA�U��|���Ă͐��炷�A���J��Ԃ��Ċ���߂܂��B���̌�A�\�ʂ�ϐ��y�[�p�[�ŋς��A�T�[�t�F�C�T�[�A���h��A��h��̏��ɓh�����Ďd�グ�܂��B�h���̂��сA���n���o�Ȃ����x�Ƀy�[�p�[�Ŗ����Ɨǂ��ł��B����͊Ԃɍ��킹�œh�������߁A�Y��Ɏd�グ�Ă͂��܂��A������O�����I�[�����y�C���g���������̂ł��B |
�@
| �@�`�F�[�������@ | 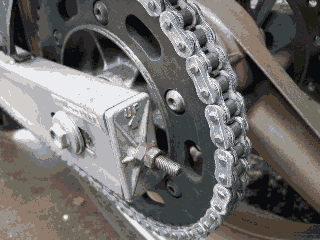 �@�y�F�̋��`�F�[���ƈႢ�A���C���X�Ƃ������Ƃ���B �@�V�i�ɂȂ��āA�R�������サ�܂����B |
| �@�\���N�O�̏����`�F�[�����t�����܂܂ŁA�������ǂ��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�������܂����B�S���ɂ͔̔����i���l�グ�����Ƃ����̂ŁA������ς�����肾�����̂𑁂߂��킯�ł��B�{���͑O��X�v���P�b�g�������������Z�I���[�ł����A�����̓S���ŁA�����Ă��Ȃ��̂ō���̓p�X�I �@��Ƃ̓V���b�v�Ɉ˗����܂����B�s���̓����O���C���_�[�ō���āi�ΉԂ̊C�I�j���`�F�[�����A�V�`�F�[�������Ă܂����B�J�V���H����������A�����p�x�����Ȃ��̂Ńv���ɗ��ނ��Ƃɂ��Ă��܂��B �@�ŁA����I�̂͂q�j�`�F�[���̃m�[�}���^�C�v(���b�L�Ȃ�)�A�q�w�����O�g�p�̃`�F�[���B �@�q�j�̃��C���i�b�v�͂n�����O��ޕʂɁA�m�[�}���n�����O�A�q�w�����O�A�w�v�����O�̏��Ƀ��[�t���N�V�����E���ϋv���̃`�F�[��(����)�ɂȂ�܂����A�Ǘ��l�͒ʏ�g�p�ɂ̓v���[�g�̃��b�L�ȂNJW�Ȃ��ƍl���Ă���̂ŁA��L�̑g�ݍ��킹��I�킯�ł��B�l�I�ɂ͂��ꂪ�ł��R�X�g�p�t�H�[�}���X���ǂ��Ǝv���܂��B �@���������[�J�[�ł́A�����ȃ��b�L�`�F�[��(���v���������H)�肽���̂��A�P�Ɏs��̃j�[�Y�������̂��킩��܂��A�g�o�ł��m�[�}���`�F�[�����ڂ��Ă��܂���iPDF���i�\�ɂ͕\������j�B ���� �@�V�i�`�F�[���ł́A�V�t�g�_�E���ŃV���b�N���S���Ȃ��Ȃ�A���Ȃ�X���[�Y�Ȋ����ɂȂ�܂����B�_���p�[��V�i�ɂ����Ƃ������ʂ��̊��ł����̂ŁA���͑����ւ����Ă����̂��Ǝv���܂��B�R��̓��b�^�[����Pkm���傢���P�B �@�Ȃ��X�p�[�_�͑O�P�V���A��T�S���̃m�[�}���ŁA428�`�F�[����132�����N�g�p�B����̂q�j�V�i�ŁA�P�O�R�}�̒[�̃s�������Ԓ[�̃s���܂łŖ�25.3mm�ł����B��P�`�Q���L�т�������A�ƌ����Ă���̂ŁA0.5mm�L�т�������ʖڂƂ������Ƃł��ˁB�i2005.2�j |