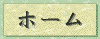良心的ダイビングショップの判別法
優良インストラクターを守ろう!優良ショップを応援しよう!
〜ここでのアドバイスはあくまでも一つの目安として参考にして下さい。ここの記述は、私の体験と取材からのもので、絶対的判断基準ではありません〜
●ショップを選ぶ際のチェック項目
私が書いた本にはそれぞれ詳しく書いてあります。
参考にしてください。「ダイビングマニュアルシリーズ」
ショップを選ぶ基準は、そのショップとインストラクターの個人的資質につきることは言うまでもありません。しかし、それをどうやって調べるのか?
が重大なポイントだと思います。
ここでは、その判断をする際の参考になるよう、私なりの判断の根拠とあるダイブショップのオーナーからの意見も入れて書いてみますので、みなさんはそれを参考にして、自分の命を守るためのひとつの手段にしてください。
ショップを選ぶときに頭に入れておかなければならないことは、有名なダイビング会社(指導機関とか指導団体と称している民間の営利会社です)の講習終了認定証=Cカード(いまだにライセンスとか免許とか言っている場合があるが、これは法的に問題があることが指摘されている)を扱っているからといって、そのショップがそのままいいショップとはかぎらないことです。では、みなさんがいいかげんなところにひっかかってしまわないように、ショップを選択するときに確認したほうがいい、いくつかの例をあげてみます。
- ダイビングの種類が自分に合っているかどうかを聞いてみよう。
・講習は厳しいが、結果として安全で高度な潜水技術を身につけられる。(体育会系)
・講習自身も楽しく、遊び感覚でふつうの技術が身につけられる。(同好会系)
ここで、よく、「ぜんぜん泳げなくてもダイビングはできますから」などとあまりにも簡単に言ったり、「事故なんて起こりませんよ」と言いきるところはやめたほうがいいでしょう。やはり、「泳げなくてはダメだ」と言ってくれるところは、泳げない人が陥る種類のパニックの怖さをよく理解している確率が高いと思われるからです。
また、「事故は起こり得ない」と言ったショップは、講習で事故のときの対処法についておざなりにしか教えてくれませんし、教える側にも確かな経験と技術がないと見て差し支えないでしょう。こんなショップで講習を受けることは、あの世への切符を買うようなものです。
- いざと言うときの保険はだいじょうぶかを聞いてみよう。
この件について、はっきりとしたことを答えられないショップは、事故に関しての認識が薄いか、保険料をケチッてその分を儲けにまわしているのかもしれません。事故が起こったときには、講習の前に書かせる、ショップ側の全面的な責任回避の書類をもって「無限無責任」を叫び、その事故の当事者を泣き寝入りに追いこむか、「ダメなら夜逃げしてしまえ」と考えていると思ってもそうはずれてないと思います。
- 講習時のレンタル器材は新しいのを使っているか、また何年で新しいのと替えているかを聞いてみよう。
講習のときの器材をレンタルで使う場合、見た目にあんまり傷んでいるもの、旧式のものは危険です。つねにいろいろな人が使う器材は、当然、その扱いが乱暴になったり、また、使用する頻度がかなり高くなるのでその寿命は短くなっているのです。もし、水中で器材が故障したら、それは生命の危険を意味しているのですから、注意すべきです。
器材と言うのは、あくまでも道具のひとつです。そして、新しい器材なら故障する率も低いと言えます。それを無視していつまでも古い器材を使っている業者は、講習生の危険も無視していることと思ってまちがいないでしょう。
- 1人のインストラクターが1回の講習で何人まで担当するのか聞いてみよう。
これは少ないほどいいと言えます。今言えることはせいぜい、1人のインストラクターで3人まででしょう。理想的には、インストラクター本人も入れて3人というのが私のアンケートに答えてくれたある有名なダイビングショップから聞いた真実です。また何人かのプロダイバーもこれに近い数字が上限値でした。
もし、インストラクターが「ベテランだから10人までだいじょうぶ」などと言うショップがあったらとっとと帰ってしまいましょう。命あっての物種だからです。
ただし、3人を超えたら1人サブのインストラクターを付ける、というのならOKです。(2〜3人ごとに)
- ショップが所属インストラクターに、職業として潜水をする場合に必要と定められている国家資格の潜水士免許を取らせているか聞いて見ましょう。
以上に加えて資格維持のために義務付けられている半年ごとの健康診断とその結果をちゃんと記載しつづけているかを聞いて見ましょう。日本国内で職業として潜水をする場合にはこれが定められています。資格を取らせていないところ、また一回取らせたら資格維持のために必要な正式な診断をさせていないところで講習を受けることは止めましょう。こういうところはショップのオーナーの経営者としての姿勢が社会的に評価されません。所属しているインストラクターを大事にしないで、単なる講習を受ける人たちを本当に大切にするとは考えられません。
- 講習時、どれだけの器材を買わねばならないかを聞いてみよう。
初めてダイビングをやるときに器材を全部揃えるとなると、講習費も入れて数十万円になってしまいます。いわゆる重器材(BC、レギュレーターなどの高額商品)を買わないと講習を受けさせないというショップは、講習後のフォローに不安がありますので、警戒したほうがいいでしょう(売ってしまえばこっちのもの的な商売と考えられる)。しかし、マスク、フィン(足ヒレ)、ウエット、ないしはドライスーツ、スノーケルなどは必要ですので、これは買いましょう。
- フリーのインストラクターに教わるときのチェック
フリーのインストラクターに講習を受けるときは、前述のチェックの他に、その人が認定するCカードの種類に注意しましょう。
法律的には、一度もダイビングの経験のない人がインストラクターと名乗って、任意のCカードを発行することには、何の制限もないのですから、本当のインストラクターなのか確認する必要があるかもしれません。また、本当のインストラクターだとしても、もし、ダイビングの経験が200〜300本ぐらいなら要注意です。ある高名なインストラクターは、「自分も5000本に達して、やっと一人前になった」と言っていたくらいですから。
この他に必要と思われるチェック項目について以下に記述してみます。
- ダイビングの経験が何本か確認する。
↓数百本なら前述の理由で不安です。この場合は過去に遭遇した事故の状況と、そのときの処理の状況を聞いてください。もし笑ってゴマかすような人なら、リスクが高いと言えます。冷静に事故の状況を分析できて、次回の対策を考えている人を探すべきです。
- そのインストラクターが、高圧ガスのタンク(ボンベ)を扱う資格を持っているかを確認する(もし、本人が自分で空気を充填するような場合)。(危険な違反の事例)
→空気を充填したタンクは、ほとんどの場合ダイブスポットでのレンタル(空気の販売)になりますが、もし、インストラクター個人自らがタンクに空気を充填してレンタル(高圧空気の販売)を行なう場合には、その高圧ガス取締法により、第一種製造者として都道府県知事の認可を得ていなければなりません。
- 国家資格の潜水士免許をもっていて、しかも資格維持のために義務付けられている半年ごとの健康診断とその結果をちゃんと記載しつづけているかを聞いて見ましょう。日本国内で職業として潜水をする場合にはこれが定められています。ただし、この資格の側面はショップに雇用されているプロダイバーを保護することを主目的としているので、この資格に実技試験はありません。
さて、以上に記述したショップを選ぶ基準を総括してみましょう。
つまり、ショップを選ぶ基準としては、そのショップの現実認識の確かさと、インストラクターの質を見て、その上で、発行される講習修了認定証(Cカード)の利用度という実利面も多少加味することです。さらに、カードの発行を受けた後のアフターフォローはしっかりしているか、商売っ気がありすぎないか?
をチェックしましょう。
くり返しますが、ダイブショップとインストラクターの個人的資質だけがきちんとした講習を受けられるかどうかの境目なのです。