| −狙撃さる− <再び、20:30> ハントが警察の包囲に気づく以前、野上の配備はあらかた終わっていた。 倉庫に面する市場の陰に、急遽仮設の基地が陣取られ、主要な関係者たちはその一角に集合させられていた。 野上はパイプ椅子にドッカと腰を下ろし、相変わらず憮然とした表情を崩さなかった。 「電波の発信源はあの倉庫に違いない。ここが決戦の地だな。移動には車を使ったようだから、おそらく犯人もいっしょだろう。この場所なら市民を巻き添えにする心配もないし好都合だ。あとは海上保安庁のスタンバイ待ちだ」 「警部、狙撃班長をお呼びしました」 「うむ、ありがとう」 制服の警官達が忍び足で各々配備に着く中、狙撃部隊の班長が野上に呼び出された。この現場を統括する野上が、狙撃班に特別な指示を与えるために呼んだのだった。 「最初に断っておくが、今回、犯人の狙撃命令を出す可能性は無い。なぜなら、いくら人間に似てるとは言え、人質になってるのはロボットだ。決して人間ではない。それを人質に取った犯人を、この法治国家に於いて、おいそれと銃撃なんて出来ないからだ」 「なら私達に出番はないと言うのですか」班長が怪訝なまなざしで野上に質問する。「でも我々の出動を要請したのは他ならないあなただ。他にターゲットがあるとでも?」 それに野上がダミ声で答える。 「その通りだよ...単刀直入に言おう。標的はロボットだ」 「ロボット? ロボ子をですか? でもいくらロボットとは言え人質ですよ。その人質を撃てと言うのですか!」班長は驚きを隠せない。 「いかにも。ただし決定ではなく、そういった状況もあり得るという話だ」野上がにやりと笑みを浮かべる。「俺の考えた作戦を言おう...我々に包囲され、追いつめられた犯人は、またロボ子を人質に逃走を図る可能性が高い。しかしそうなったら犯人ではなく、ロボ子を撃つのだ。君が驚くのは無理もないが犯人だって驚くぞ。加害者ではなく被害者が撃たれるのだからな。しかしこれは最も合理的、かつ安全な方法なのだ。 なぜそう言えるか、順を追って説明しよう。 まず人質が人間ではないということ、これは我々の事件解決方法にとって有利な点と不利な点が出てくる。もしロボ子が人間だったならば人質の人命尊重の見地から犯人を射殺する、という究極的手段もあり得る。しかしロボ子は人間ではない。犯人の手口がどれだけ非道であったにせよ、電子レンジを人質に取った奴を射殺するのは日本の法律の許容外だろう。射殺を救出手段とするにはその根拠が薄弱だ。いくら極悪非道な犯人とは言え電子レンジのために殺されるんじゃあ浮かばれないだろうしな」 「でも実際問題として彼女を...いやそのロボットを拉致されることは人質に相当するとは言えないでしょうか? こうして逃走の人質に立てたり日本国家レベルの重大事件を起こしている以上、人さらいとしての素質を十分構成します。それに犯人は人間だと思ってさらった確信犯ですし...」 「いいや、犯人だってもうロボットだと気づいているかも知れないぞ。しかし、気づいていなかったとしても我々が知っている以上、究極的手段は除外しなきゃならんだろう。従って狙撃の対象は決して犯人であってはならない。犯人は無傷で逮捕する事を要求される、これが最初に言った不利な点なのだ」 班長は憮然としながらも、それ以上食い下がることはなかった。 「一方、じゃあ有利な点とは何か...それは人質の身の危険を考えなくてもいい、という事だ。何しろ人質は電子レンジだからな。従って、多少荒っぽい方法を選ぶことが出来る。何をやっても犯人を逮捕出来れば万々歳」 「なるほど分かりました...即ち、逆にロボ子を狙撃することで、犯人唯一の命綱を奪い去り、奴を丸裸にするのが目的ですね」 「その通り。それでロボットを連れ去られる心配もゼロになる。だからロボ子をターゲットにするんだ...犯人はコンバット銃を持っているらしい。モデルガンかもしれないがそうでないかもしれない。しかしあいつにはどうもプロの臭いがする。奴は他にどんな強力な武器を持っているか我々には未知数だ。人質の安全を考慮しなくていいなら強行突入という手もあるが、我が方に負傷者が出るような手段も出来れば避けたい。だから人質を救出するのではなく、無くしてしまう...後はじっくり兵糧責め。これが俺の考えた作戦だ」 野上は勝ち誇ったように胸を張っている。 「...しかし、ただロボ子を破壊すればよいと言うわけにも行かない。人間ではないとは言え、ロボ子は大事な財産だ。ロボ子を失う場合の損害は我が国の国家的な損害とまで言えるかもしれない。この作戦はロボ子の足を止めるのが目的だが、それにはどうしてもロボ子を破壊しなくてはならないという事がネックになる。ロボ子の足を止めたいが壊したくはない...この矛盾する課題を両立する道があったのだ。...あとは博士にご説明願おう」 野上に促され、横にスタンバイしていた博士が一歩身を乗り出した。 「ロボ子は人間に似せてあるとは言え機械じゃ。鉄砲で撃たれようとも死ぬことはあり得ない。元々生命ではないのじゃからの。早い話、また同じ物を設計図通り作り直せばよい。それだけの話と思われるかもしれん。 しかしワシにとってはもはや子も同然。そのロボ子は今虜の身じゃ。何とか無傷で救い出してあげたいのは親代わりのワシの願いじゃ。まずはその心中を察してくだされ。 そしてここに困った問題があるのじゃ。ロボ子にはバックアップされていない貴重なデータがあり、これだけは何としても壊すわけにはいかないのじゃ。今までバックアップを怠ったワシの責任であることは事実じゃが、この2週間で収集した膨大なデータは、そのセキュリティーシステムのせいでバックアップに3日もかかってしまう。デモまで日もない状況で割愛せざるを得なかったのが事実じゃ。その点は了承願いたい。 しかし足さえ止めれば良いのなら一つだけ方法があるのじゃ。ロボ子の動きを止めるには人間で言う首筋を狙えばよい。運動中枢とCPUを結ぶラインがそこにあるからそれさえ切断出来ればロボ子は次の行動がとれなくなるはずじゃ。 ちょっと残酷に見えるかもしれんがそれでバッテリー液の循環も止まるからもう犯人の言いなりにはならないはずじゃ。犯人も手に手をとって逃走と言うわけには行かなくなるじゃろうし。 逆にその場所以外は致命的な障害になるかゼンゼンかのどちらかじゃ。確実に首筋を狙い撃つ事が出来る、というのが条件となるのじゃが...」 「かなり小さな的だ。この市場の屋上からは直線距離で200メートルはあるな。そんなゴルゴ・サーティーンみたいな奴はいるか?」野上が狙撃班長に問いかける。 「部下に、若いけど腕の立つ男が一人、居ます。そいつは300メートル先のラッキー・ストライクにストライクを撃つ事が出来ます。200メートルならジッポライター。我が部署ではそいつを、『平成の那須の与一』と呼んでいます」 −−−− <20:40> 「見えた、あの倉庫だ!...しまった、こちらに気づいたようだ。犯人が動いたぞ!」 「警部、たった今入った連絡では、PHSの電波がとぎれたそうです」 部下達が色めき立つ中、野上は悠然とたばこの火をもみ消す。 「犯人に気づかれたな。もう少し時間が欲しかったがまあ仕方ない。作戦開始だ」野上は用意された拡声器を手に取った。 「まずは時間稼ぎ、常套手段から行くか」 メガホンを持つ手はカラオケでマイクを持つ手といっしょで人それぞれにクセがある。野上は小指ではなく親指を立てるクセがあった。 野上の振り下ろす左手を合図に4基のサーチライトが一斉に倉庫を照らし出す。それを逆光にしながら野上がステージに上がるスターのようにゆっくりと4歩前進した。 「犯人に告ぐ、そこにいることは分かっている。無駄な抵抗はやめておとなしく出てきなさい。君は完全に包囲されている!」 ゴーストタウンのような波止場に野上のダミ声が轟き渡る。 「おいでなすったな。でも一体、何て言ったんだ?」ハントは倉庫の中、眉をひそめている。ロボ子は不快そうに顔をゆがめている。 ボリュームを最大にされた拡声器では音が割れた上に建物に反響し、猛烈なハウリングを起こしていた。側にいた博士達は慌てて耳をふさぎ、その身を捻ることになった。倉庫内のハントに於いては、その騒音の元は恐らく人の声だろうという事だけしか分からなかった。 「私には聞き取れました。私達は完全に包囲されたと言ってます。ハントさん、ここからどうやって逃げるつもり?」 「そうか、包囲されたか。でも相手の言うことを額面通りに取っちゃならねえ。奴らの包囲は完全じゃねえ。だから完全だと言い張るんだ。もし完全だったら先手必勝、さっさと突入すればいい。それをしなかったのは何か理由があるからさ。その何かとは、さてなんでしょう」 「分かりません。それはクイズですか?」 「ははっ、そうさクイズ。でも答は簡単だ。表は確かに取り囲まれている。でも後ろはどうかと言ったら...」 ハントはそう言いながら倉庫の扉をソッと開け、アゴを突き出してロボ子に外の暗闇を指し示した。 「海があります...じゃあ海へ逃げるのですか?」 「そう、それが正解だ。奴らは海上保安庁の警備艇を待っていたはずだ。奴らは電波を追ってここへたどり着いたのはいいがここは港だ。ここへ来て初めて逃走経路にボートが使われる可能性に気づいたはずだ。 俺は隠れ家をいつも港に探し出す。なぜならパトカーは海の上まで追ってこれないからな。 俺は傭兵出身だ。戦車だってヘリだって運転できらあ。ボートを操縦するのは自転車をこぐより得意だ。そしてその船着き場まで行けば金持ちや道楽人の高性能ボートがわんさかとある。ボートなんかはあのライトバンといっしょで盗み出すのはわけない。お茶の子さいさい朝飯前だ」 「盗みはいけません。悪いことです」 「おお、そうだな。じゃあちょっと借りるだけにしよう。それならいいだろう?」 「ええ、まあ、後でちゃんと返すのなら...」 「じゃあいいか、俺はここを脱出するためにあそこに見えるボートへ乗り移る。そしてエンジンを掛ける。それを20秒ほどで片づけるが、その間どうしても奴らに背中を見せなきゃならない。そこで頼みだが、その間お前が時間稼ぎしてくれないか...これを使って」 そう言いながらハントはロボ子の腕を掴み、その手のひらに一丁の銃を載せた。 「これで援護してくれ。この銃で威嚇射撃だ。でも俺は人殺しはイヤだから人間には当てるな。それとついでといっちゃあ何だが俺にもな。出来るか?」 「きっと出来ます」 「よし、じゃあこれからは時間との戦いだ。イチ、ニのサンでスタートするぞ、いいな」 「ちょっと待ってください。『サン』で出るのですか、それとも『サン』まではタイミングを計るためで事実上は『ヨン』で出るのでしょうか?」 「さすがロボットだ、勘定にうるさいね...じゃあこうしよう。お前が『サン』で俺が『ヨン』だ。それ、イチニの...サン!」 倉庫の扉から飛び出したロボ子を一斉にサーチライトが追った。 「おおロボ子や、こっちじゃ、こっちへ逃げておいで」 ロボ子の2時間ぶりの無事な姿に対面し、博士は大きく手招きしてロボ子を呼んだ。 ロボ子は声の方に振り向き、しばしの間博士の顔を見つめた。 「おお...ロボ子や」 しかしその後すぐにロボ子の持った銃から銃声が1発轟いた。 銃の反動を初めて経験したロボ子はその銃声とともにバランスを崩し、ひっくり返りながら後ろへ一回転した。 「博士、ロボットがこっちに向かって発砲しましたぞ。一体どっちの味方なんですか」 「な、なんということ...」 すぐに立ち上がったロボ子は辺りの様子を伺っている。 しかし間髪入れずにロボ子が発射した続く4発は、転倒されることなく上手に撃つことが出来た。 その4発全てが設置された4台のサーチライトに命中し、辺りに暗闇が戻った。警官たちは何か大声で叫びながら物陰に隠れたり身を伏せたりし、博士は、大きく口をあんぐりと開け、手招きで持ち上げた手をまだ下ろせずにいた。 「やっぱり軍事用だけのことはある。射撃の腕前は見事だぜ」 ボートにたどり着いたハントはさすがと思ったがロボ子は一度の失敗から学習したにすぎなかった。 建物の陰に逃げ込んだ警官は「あの銃は本物だ。あのとき飛びつかなくて良かった」と研究所でのにらみ合いを振り返った。 「おーい、ケガはないか」と呼び合う声がそこかしこから聞こえる。 「こりゃいかん。ロボ子は完全に犯人の言うなりだ。俺の筋書きとだいぶ違ってきたが、それはそれで結構だ。例の作戦を実行しよう。おい、狙撃命令を出せ」 「しかし警部、犯人はボートに飛び移った模様。狙撃手からは死角になってて無理です」 「ちがう、ロボットだ。ロボットの首筋を狙え!」 暗闇でも狙撃ライフルの暗視スコープにはロボ子の姿がありありと映し出されていた。 そのスコープの中、ロボ子は左手を腰に構え「ふっ」と銃口を吹くポーズをとっていた。 「よしロボ子、もういいぞ。こっちへ来い...おい、そんなポーズどこで覚えた?」 その呼びかけにニヤリと不敵な笑みを浮かべ、ロボ子はハントの方へゆっくり振り返った。 「ピーの奴、僕のポーズを真似してやがる」 助手が思わず口走る。仮設基地から見えるロボ子は灯台の光にシルエットとなり、その表情までは見極められなかったが、その姿は助手がテレビゲームで見せたガッツポーズを真似たものだった。 ハントは最初、ロボ子が少しよろめいただけだと思った。しかしそのあとすぐアスファルトの繋ぎ目につまずき、ロボ子は背中から倒れた。変装用のメガネが飛んでダミーのレンズが音を立てて割れる。銃声が遅れてやってきた時点で、ロボ子が撃たれたことがハントにも分かった。 「おいっ、ロボ子!」 ボートの上でハントが叫ぶ。ハントにとって、人質であるはずのロボ子が狙撃されるとは夢にも思わなかった。 ロボ子を撃ったのは若い狙撃手だった。その狙撃手はロボ子が首筋から血を噴いてその場に倒れるのを見て驚いた。 「うわああ、人間だよ。人間を撃っちゃった! 俺はなんてことしてしまったんだ!」 「バカ、あれはロボットだ。あいつが流しているのは血じゃなくて緑色のリキッド電池だよ。資料を読んだだろ」 仮設基地では博士が自慢げに解説を始めた。 「あの緑色はな、透明の液状電池をわざわざ着色したものじゃ。なぜかというと人間の肌色を再現するのが難しくてのう。膚というのは一言でピンクと言われるがピンク色で膚を作るとこれがまるで気味の悪い人形じゃ。そこで、そのままでは不自然だったピンクの肌を液状電池の着色で補おうと考えたのじゃ。その結果落ち着いた色が緑。不思議とこれが肌色らしくなるのじゃよ。試しに絵の具でピンクにちょっとだけ緑を混ぜてみるがよい、肌色らしくなるぞ。ちなみに、ピンクの液に緑色の皮膚も試してみたが、これは問題外じゃった」 再び屋上。若い狙撃手の動揺はおさまっていない。 「でも班長、でも、でも、あんなロボットなんているもんか! みんな騙されてるんだ。あああ、俺は人殺しだ」 「うろたえるな! あいつはちょっと尾室奈美似だが、ただのロボットだ」 「そんな言い方やめてください、僕は奈美ちゃんのファンなんです!」 「何いー!」 ロボ子は上体を起こし、キョロキョロと辺りを見回してからゆっくり立ち上がった。僅かばかりの躊躇い(ためらい)が狙撃手の狙いを逸らしたのか、回路切断に至ってはいなかった。 「おい見ろ、立ち上がりやがった。やっぱりロボットだ」 「ほ...ホントだ」 「お前らしくないぞ、外したな。第一撃目失敗っ。ターゲットは活動を再開、第二撃準備!」 「イヤだー!」 「馬鹿野郎! お前が撃たなければ誰が撃つ? この距離であの細い首筋を射止めることが出来る腕前はお前だけだ。他のヤツに撃たせてあの可愛い顔をザクロにしてもいいのか。それにこのままだと大好きな奈美ちゃんは犯人に連れ去られてしまうぞ。お前の奈美ちゃんはあいつに奪われようとしているんだ。 その優しさを捨てて鬼になれとは言わない。しかしお前のその優しさはかえって彼女を不幸にする事になるんだ。彼女を撃つことが奈美ちゃんを助けることになるんだぞ。さあ、撃つか? 撃たないか?」 その言葉は那須の与一に活を入れた。 「撃ちます!」 その涙声は叫びに近かった。若い狙撃手はにじんだ涙を拭き払い、暗視スコープをのぞいて狙いを正確に定め直した。 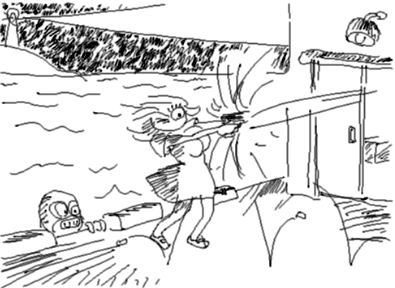
|