 | |||||
| 絵葉書:東京駅停車場北半部・南半部 1914(大正3)頃 ・・・ 所蔵/関田克孝氏 ◆東京駅開業90周年・東京のターミナル形成史 (2005/5) リーフレットより | |||||
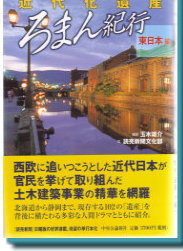 |
|
||||
| 「近代化遺産・ろまん紀行」 中央公論社 2003/7 | |||||
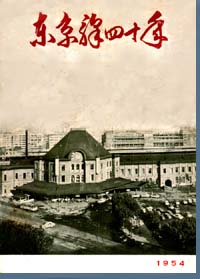 「東京駅四十年」 1954 |
|||||
|
|
|||||
(3)開業当時の東京駅
絵葉書:東京駅停車場北半部・南半部 1914(大正3)頃 ・・・ 所蔵/関田克孝氏
◆東京駅開業90周年・東京のターミナル形成史 (2005/5) リーフレットより
◆近代化遺産・ろまん紀行・・・東京駅 より
「皇室の玄関」意識、重厚に
長すぎる!
何しろ全長335メートルだ。堂々とした外観を示す丸の内側の駅舎に沿って歩くと、端から端まで到着するのに優に六、七分はかかる。駅というよりは、もしろレンガ造りの建物が軒を連ねた大きな街並みのようだ。
通過駅としてプラットホームに沿って建設されたことが、この形状の主な理由だろう。しかし、建築設計に取り組んだ日本近代建築の祖・辰野金吾がより重視したのは皇居との関係だった。
もともと駅舎の建設地周辺は、人気のない広大な野原だった。しかし、皇族が日本各地を訪問したり、国賓が皇居に寄る際に「東京の玄関」となる場がどうしても必要だった。このため、明治初期から繁華街だった銀座、日本橋ではなく、皇居の側に駅舎は建てられた。
駅舎が落成した1914(大正三)年、高橋善一初代駅長は、新聞の取材にこう語った。
「(皇居の)御膝元にある中央駅として、アノくらいのものはなくてはならぬ」
とはいえ、当初から壮大な駅舎が予定されていた訳ではなかった。最初の予算はわずか42万円で、平屋の建物として設計された。ところが、日露戦争の勝利を記念し、三階建てにすることが決定され、完成時には総工費287万円と、何と予算の七倍にも膨れ上がった。
工事では、地震に耐えられるように堅固な構造が採用された。水中で最も腐りにくい松の杭を地中深く打ち込み、その上に鉄骨を組み立て、それをレンガ壁で包んだ。 後略
***************************
◆昭和29年発行の「東京駅四十年」より
当駅開業前の丸ノ内付近の交通状態
市内に初めて電車が敷設されましたのは、明治三十三年で、丸ノ内につきましては、日比谷大手町間、日比谷数寄屋橋間が明治三十六年、大手町呉服橋間は大正元年十二月でありました。
従って明治三十二年頃の丸ノ内は、徒歩で新橋駅まで出て、東海道線に乗るほかは、なかったのであります。 後略
****************************
◆昭和43年発行の「週刊読売」より
原っぱにできた”中央停車場” にも 記述あり
「近代化遺産・ろまん紀行」
中央公論社
2003/7
「東京駅四十年」
1954
目次へ戻る
次ページ