![]()
管理人の乗っているMTB(マウンテンバイク)のページです。基本的に通勤使用がメインです。
殆どいじる必要性を感じませんが、交換時期の来た消耗品は、こだわって換えていこうと思っています。
| 導入編 | 乗り始めたキッカケ、購入の顛末、購入直後のインプレなどです。 |
| パーツ&改良点 | 購入後に必要となった物、気になって変更した点などです。 |
| 泥除け(リヤフェンダー) | |
| ヘッドライト | |
| セーフティライト(リヤ) | |
| センタースタンド | |
| サスペンションシートポスト | |
| サイクロコンピュータ | |
| スリックタイヤ | |
| 軽量チューブ | |
| 交換チューブ | |
| ボトルケージ | |
| リヤキャリア | |
| SPDシューズ | |
| SPDペダル | |
| アームカバー | |
| メンテナンス編 | メンテナンス等の実際の手順など。 |
| センタースタンド取り付け | |
| サスペンションシートポストのオーバーホール | |
| タイヤのローテーション | |
| ブレーキ調整とシフターワイヤー注油 | |
| サスペンションの整備(フォークオイル交換) | |
| チェーン交換 | |
| グリップ交換 | |
| 工作・加工編 | こちらは市販品などに管理人が手を加えてみたものです。 |
| シフターカバー作成 | |
| シート加工(コンフォート化) | |
| センタースタンドの塗装 | |
| サスペンションシートポストの加工 | |
| スペック | Giant XtC850 の出荷時のスペック表です。 |
【導入編】
●キッカケ
数年前から気になってたけれど、しばらく静観していた(流行モノには手を出したくなかった)のですが.........遂に購入。その直前に、最新の自転車(小径車)に乗る機会があったのですが、軽~く走れるし、意外にいい運動になります。それで、これならもう少し本格的なやつで走ってみるか!と思った訳です。通勤に使うことになったのは、勤務先の近くにけっこう立派な無料駐輪場を発見したのが決め手です。でも、なんだかんだ言っても、走るのが好きなんでしょうね。
●購入
全く知識がないので、専門誌で見当をつけます。自分は基本的に舗装路を走るので、山を下る装備(前後サスペンション付きのヤツ)は不要です。
管理人の使い道(舗装路主体だがオフロードもちょっとは走れるほうがいい)でのコストパフォーマンスを考えると、この当時はいわゆるハードテール(=リヤサスなし)が自分には最善の選択肢でした。そこで検討の結果、コストパフォーマンスの良いGiant
XtC840に狙いをつけました。
まず試乗できるショップに行くことに。(2003.8現在)
Y’s Bike Park(府中関戸橋・さくらサンリバー1F)・・・・MTBは予算(~\60,000)3倍以上する高いヤツだけ。試乗は、できます。
新宿JOKER本館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 折り畳み小径車から本格ロードバイクまでいろいろ。小物も含め、無いものはない?
店頭に飾ってあるXtCをここでよ~く観察しました。ライトなど小物のみ購入。
実際に購入するのはアフターケアを考えて、近所のショップにしました。で、在庫が一台あったのが型落ちXtC850(2002年型)。
大きさ確認のため跨らせてもらうと、在庫の430mmで、ちょうど良い感じです。雨天でも効力が殆ど変わらないディスクブレーキ仕様、グリップシフトという楽ちんな変速機(グリップを回転させて変速する)で、更にほんのちょっと安くしてもらえたため、これに決定。結局予算オーバーです.......。
●実走
納車初日のインプレ
雨の日に納車です(泣)。泥除けもないので背中に多少の泥はねを受けます。変速はスムーズですが、一部繋がりにムラがある感じ。まあ街中を走る分には充分でしょう。前に小径車で走ったところを同じように走ってみると、やっぱり速い。頑張れば42~3Km/h出ます(長い下りで)。
回転部分はスムースですがタイヤが抵抗になっていて、うなるようなロードノイズがすごいです。最初に替えるパーツは、タイヤになりそう→(変えました)
自転車通勤
直線距離で約13Kmありますが、電車でドアツードア45分。そこを着替え等を含め約1時間でクリア。走るのに慣れた現在で35分走行です。
歩道はやっぱり走りにくいです。歩きでは気づかない上下のうねりで疲れるのと、歩行者と接触の危険もあるので、車道メインで走っています。
私の場合、楽に走るために以下のことを実行しています。
①走行抵抗の少ない白線ペイントや側溝ブロック上を走る(ブレーキが必要なとき以外)
②かなり軽めのギヤを使って走る。平地だと殆ど力を加えず足を回しているだけ、っていうくらい(無理すると膝を痛めます)。
③無理して車道を走らない。特に登りは歩道をゆっくりと、回転数を一定に保って走る(きつくなる前にギアを落とす)。
なお用意したものはライト(前ヘッドライト、後セーフティライト=点滅するヤツ)、ズボンのすそを留めるベルクロ付バンド(名前忘れました)、ヘルメット(必ず!)、グローブ(防寒用はユニクロ スポーツグローブ \1,050 夏はメカニックスグローブ)、ワイヤーロック、冬季用にスポーツ用ウィンドブレーカー(Kappa 特売で\2,000位)などです。休みの日に通勤ルートを試走してみると良いです。所要時間だけでなく、自分に必要なものも見えてくると思います。
【パーツ&改良点】
街中で使いやすいように、細かい点を変更しました。なお文中の金額は、全て消費税込みです。
| 変更点 | 内容 | 写真 |
| リヤフェンダー(泥除け) | 雨の日の必需品。 SKSのX-TRA DRY(リヤ用/黒 、\1,860)を選びました。裏側にタイヤワックスを塗って汚れを落ちやすくしています。 脱着・調整ともに簡単ですが、角度固定のヘックスボルトをきつく締めようとすると、これを受けるナットが空回りして完全には固定できません。 走行中に歩道の段差などの衝撃を受けると、角度が変わってタイヤと擦れてしまいます。猛烈に削れます。ピボット部分(付け根近くの丸い所)に釘を打って対処しました。 フロントについては、雨の日は走らないので、まっすぐ走る分には車体が泥はねを受けてくれると判断し、省略しました。現在、リヤキャリアに変更しました。 |
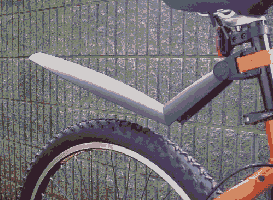 |
| ヘッドライト | 夜間走行の必需品。 CATEYEの白色LEDヘッドライト(HL-EL100)。単三電池4本を使い、それなりに明るいですが、ヘッドライトというには大袈裟。セーフティライトの明るいものと思っておいた方がいいでしょう。 電池はヘッドライトとして30時間、セーフティライトとして150時間もつと説明書にあります(点滅モードを搭載しているのは上位機種 HL-EL200です)。 ちなみに電池は「xxxxmA」のように容量が書いてあるので、数字の大きい方を選びましょう。各メーカーで微妙に違います。現在、三洋製が最も大容量のようです。 |
 |
| セーフティライト(リア) | こちらも夜間走行必需品。 セーフティライトというやつで、発光して自転車がいることを他の通行者に知らせます。 写真はUNICOのAQUA X-LITE(\1,680)。点灯と点滅が選べます。ゴムで車体に固定しますが、いつか切れそう......。 確かに明るいですが、個人的にはもう少し大きなライトを付けたいです。週三時間、一年ほどの使用で暗くなったので電池交換しました。 ライトとは関係ないですが、後方確認用に小さなバックミラーもつけています。車道をよく走るのですが、ドライバーはこちらをあまり(人によっては殆ど!)見ていませんので注意が必要です。 |
 |
| センタースタンド | かなり悩みましたが、メーカー不詳(KOBAの刻印あり。\1,365)の軽合金製センタースタンドに決定。見た目の安っぽさに反して割と重いですが、軽量化より利便性を取りたいと思います。 取り付けは直接だとフレームが傷みそうなので、ゴムシートを噛ませてスタンド取り付け部で挟む形にしました(詳細はこちら)。現在、店頭にあるものはゴム部品が付いているようです。 こうした部品(社外品)には統一された規格が全くないため、自分のMTBに付くか?頭の痛いところですが、ハードテール(リヤサスペンションなし)ならば大体対応できそうです。 あと、そのままでは車体と色が違って浮いてしまうので、塗装しました。 |
 |
| サスペンションシートポスト | KALLOY の SP-252 (\3,675)。体重を乗せて押すと作動します(18mmストローク)。これは26.4mm径ですが、車体付属のシムは27.2→30.8mm変換で、合いません。市販シムは、25.4か27.2mmを大きくするもののみだそうなので、自前でスペーサーを確保する必要があります。 仕方ないので、シートポストに缶ビールを切り開いたものを三重に巻きつけた上、車体付属シムを使用して凌ぎました。 ネガティブな面はガタがあること。立ち漕ぎで左右に振れます。作動調整用のねじを締め込んでいくと、単に初期作動の悪いサスになるだけです。 しかし、一度使うとサス無しには戻れない位、非常に楽です。オーバーホールの模様はこちら。 |
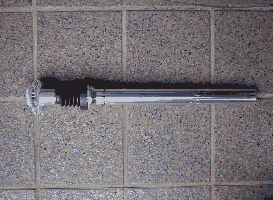 |
| サイクロコンピューター | CAT EYEのCC CL-200(無線式コンピュータ, \8,000位)。コンピュータといっても、走行距離・速度・時間が測れるというだけのものです。 ホイール(スポーク)に磁石を取り付け、フォークに取り付けたセンサーを通過することで前輪回転数を読み取ります。機器の取り付け以外に準備することは、時刻とタイヤ外周長を入力するだけ。 で、使ってみると距離も時間もきっちり測れるし、何より時速が表示されるのが一番楽しかったりして....。しかし表示される時速は結構いい加減(少なめ?)な気がします。タイヤ外周もしっかり実測したんですが。 実際に数値としていろいろ示されると、トレーニングとして自転車に乗るのにも大変役立つと思います。また、パーツを替えたときなど、過去のデータと比較検討できます。データ蓄積後のこれからに期待。 |
 |
| スリックタイヤ | IRCのスリックタイヤ SMOOTHIE(26×1.25)です。 初めのうちはNIMBUS(Specialized)やGIZMO Flex(三ツ星)辺りを狙っていましたが、CHARICの評価を読んでこちらにしました。値段が安い上、性能、耐久性のインプレで悪い評価が一つもないのです! かなり太め(1.5に近い)でパンクにも強く、溝も1.5mmで距離的にも持ちそう。重量 360g。Panaracer 仏式チューブ1.25(140g)と共に使用。もとのMICHELIN WILD GRIPPER X-COMP(1.95)は、真ん中のノブが減った状態で 520g、チューブ 170g。一本当たり 190gの軽量化です(実測値)。 規定圧95PSI(6.5kgf/cm2)を測れるゲージがないので、目見当で入れました。漕ぎ出しはとても軽くなった反面、乗り心地は固くなり、タイヤ外周が短くなったせいで、同じギヤで漕いでも前と同じようには進まない感じ。 巡航速度が28~30km → ~35kmくらいにあがりました。また長距離では、疲労がたまって加速しづらかった(脚が攣りそう....)のが、抵抗が減った分かなりラク。 なおHPによると、グリップが上がり、少し軽く(335g)なった改良版が出ています。定価\3,000 で、実売価格の上昇が心配です(2004.12)。 |
 |
| 軽量チューブ | マキシスのウルトラライトチューブです。 実測は70g。パナレーサーの通常タイプのチューブが135gだったので、約半分の重量になりました。漕ぎはやはり軽いです。また、空気を入れようとすると虫ゴムが張り付いているのか?空気入れをまったく受け付けないパナレーサーのチューブ(バルブ)にうんざりしていたので、それがなくなるだけでもOKです。 交換直後、走行音がかなり大きくなりましたが、その後落ち着きました。前に新品チューブにしたときもそんな感触があったので、チューブがタイヤと馴染むまで、抵抗が大きいのでしょうか?舗装路上での走行音は多少、大きめのような気がします。 しかし漕ぎ出しはやはり軽~く感じます。プラシーボを除いても、そこそこ効果はあると思います。普通に使うには、この位軽ければもう十分でしょう。管理人は耐久性を落としてまで軽量化はしたくないので、タイヤ周りの軽量化に関しては、ここら辺でやめておきます。 リヤタイヤのチューブは、2007.09に装着後、一年持たずにスローパンクしたので、下のシュワルベ製へ変更しました。タイヤには何も刺さっていなかったけど?? (2008. 5) |
 |
| 交換チューブ | シュワルベ(SCHWALBE)のチューブです。 頑丈なタイヤ「マラソン」で有名なメーカーです。チューブの方は、マキシスのウルトラライトチューブよりも重く、パナレーサーの普及品よりも軽いというところ。実測120gでした。 結構立派なタイヤカタログが同梱されており、商売にもぬかりはありません。なんとバルブキャップが透明です。果たして意味があるのか?装着タイヤがIRC SMOOTHIE で太さ1.25(実際は1.5相当)なので、対応範囲、26×1.0~1.5までのものを購入しました。 普通のチューブなので、特に難しいこともなく交換終了。一度タイヤのローテーションを間違えて組んでしまったのは内緒.....ってことで。 装着後、走行音が静かになった気がします。マキシスと比べ、それほど重くも感じないです。フロントがマキシスの軽量タイプのままなので、前輪のロードノイズだけが騒がしく浮いてる感じ。 競技をするわけでもないから、信頼性が上ならこれでいいかなと思う。 (2008. 5) |
 |
| ボトルケージ | ミノウラのペットボトルケージ(AB-500 \966)です。 説明する必要はなさそうですが、飲料水のボトルを車体に固定する部品です。500mlペットボトル専用で、飲み口のところにはめるゴム部品があり、これでボトル脱落を防止。その分取り出しにくくはなっていますが、多少跳ねたりしてもボトルが外れることは無いようです。製品には購入日から2年間の保障付き。まあ普通に使って壊れるようなものでも無いですが。 取り付けネジは付いていなかったので、自転車本体についていたボルトで固定しました。管理人は通勤時はここにボトルを収めることは無い(リュックに収納)ですが、散歩で出かける場合などは使用するため、リヤキャリアと一緒に購入しました。 (2005.12) |
 |
| リヤキャリア | AMOEBAのシートポストキャリア(JY-R1 \3,675)です。 一般的な荷台(後輪にかぶさる)形のものだと、後輪ディスクブレーキ車ではキャリパーがステーに干渉し固定できないというので、こちらのタイプにしました。耐荷重15kgですが、大体20kgぐらいまでならいけると店員さんは言っていました。他社製品でクイックレリーズのものもありましたが、頻繁に取り外したりしないのでこれに決定。このためリヤフェンダーは追い出されました。 取り付けはシートポストを部品で挟んで、5mmヘックスボルトで締めるだけ。荷台下部にある2本のネジ(3mmヘックス)を緩めて、荷台を前後に調整できます(写真上)。サドルとの位置関係から、一番後ろに下げた形で使うことになるでしょう。反射板(リフレクター)取り付け用ボルト・金具付き。なお反射板自体は別売りです。写真はXtC付属のものを流用。 これで、リュックを背負って背中に大汗かくこともなくなります。が、ボルトの締め付けが甘かったのか、初日の使用で20kmほど走行後、カタカタと音がしだしたので良く見ると、シートポストにキャリア本体を固定するボルトが緩んでしまいました。携帯工具で対処しましたが、後でロックタイトのネジロック剤(ネジの緩み止め)を塗ってから締め直しました。以後、問題はないです。 (2005.12) |
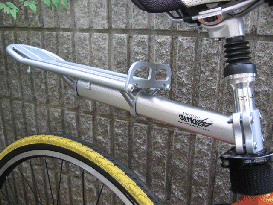 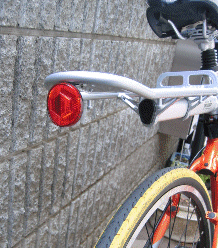 |
| SPDシューズ | シマノのSPDシューズ、SH-MT20M(モスグレイ/\7,140)です。サイズは43(EUサイズ)。これは 27.2cm相当らしいのですが、つま先まで固いせいでしょうか、結構小さく感じます。管理人が普段履いている靴のサイズ(25.5~26.0)で試し履きしてみると、つま先が当ってとても履けるような大きさでは無かったです。また、07ニューモデルのほうが、普通のスポーツシューズっぽくて格好いいのですが、こいつも写真で見るよりは実物の方が普通に見えるので、街中で履いて恥ずかしいというほどではありません。 紐をしっかり締めて履くことを前提にしているようで、いわゆるベロの部分にかなり厚めのクッションが入っており、紐が足に食い込んで痛くなるようなことはありません。但し、きつめに締めれば、当然ながら時間とともにしびれるような感じにはなります。ロード用シューズと違って、一応「歩きを考慮している」というMTB用のシューズなのですが、つま先も曲がらないためやはり歩きにくいです。 とりあえずSPDペダルではない、ケージペダルで乗ってみました。ソールが厚いのでサドルを少し高くしたほうが良いかと思った以外は、特に違和感も感じませんでした。普通の靴でなら足に少し痛みを感じるような距離を走っても、足の芯に若干疲れを感じる程度で済みました。(本来は下のSPDペダルと組み合わせて使います。) (2007.5) |
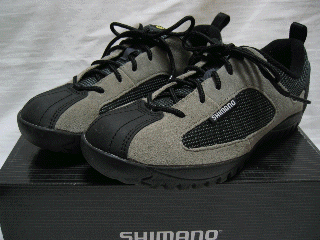 |
| SPDペダル | シマノのSPDペダル、PD-M520(ブラック/\3,990)です。実測重量は約190g(二個セットで375gだったので、もう少し軽いはず)。ノーマルのケージペダルが約200gだったので、多少の軽量化になりました。 上記のような専用シューズとの組み合わせで、足をペダルに固定できます。シマノのラインナップでは最廉価版ですが、見てのとおり安っぽくなくしっかりできています。固定にはペダルレンチを使うか、ペダルの軸が六角レンチを使えるようになっているので、ヘックスレンチで固定できます。足首をひねって外すやり方にはすぐ慣れましたが、意識しなくなってきた頃に、足を付こうとした反対側にバランスを崩して立ちゴケしました。イタタ..。意識していったん後ろへ抜かないと、前側の金具に引っかかって危険です。現在は、足を付く方をひねって外した後、土踏まずをステップ上に置くように踏み変え、停止に備えています。なお、シューズ側に取り付ける金具(クリート)は、ペダルに付属しています。 クリートの位置調整は、ペダル上で足がやや外側・拇指球(親指の支点となっている関節)直下といったところで使用開始。すんなりペダルに嵌まって(固定されて)くれません。そこから、クランク寄り・指先よりへ修正して、現在よい状態です。 驚いたのはその効果。ペダルに足が固定されるため、踏む面がずれないように踏み込む必要も無く、脚力がすべて推進力に変わる感じです。踏み込みで加速するのは体力的に限界かな~という時、脚を引き上げる力だけで進むことができ、脚力を温存できます(←正しい使い方ではないでしょうが、ホントに楽になりました)。 本格派の人だけでなく、脚力に自信の無い人(管理人含む)ほど使うべきだと感じました。超お勧め。 あと雑誌でビンディングペダルにペダルの踏み面をつけることの出来る部品を発見。通常の街乗りでペダルを付け替えなくてよいので、かなり欲しい....。 (2007. 7) |
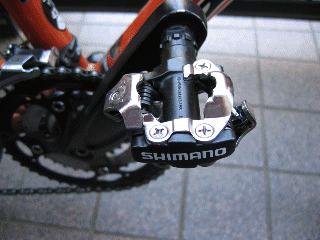 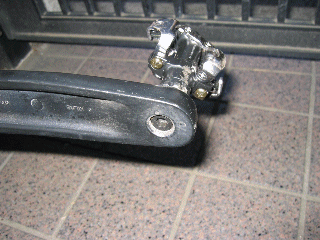 |
| アームカバー | DefeetのARMSKINS です(ブラックS-M/\3,500位)。 この時期、腕が焼けてきついですね。そのままで大丈夫な人はいいですが、管理人は日焼けに弱い人間なので、アームカバーを導入しました。 はじめワコールCW-X(夏用)にしようと注文してみると、見事生産中止で、仕方なく店頭在庫から選ぶことにしたのですが、ネットでチェックした情報によると、このメーカーのものが使い心地、耐久性の点で良さそうでした。 ただ、色はあまり選べません。管理人の感性だと、グレーやピンクはいい色ではなかったので、黒以外の購入は考えられない感じでした。 実際に装着すると、さすがにアームウォーマーとしても使うものなので、今の時期快適とは行きません。素材は厚手ですが、割と早く乾くようです。汗はかきますが、すぅーっと蒸発する感じがして、暑苦しくは無いです。 縫い目が無いので腕に装着の跡が付くこともなく、適度に締めつけられます。また厚みがあるので、万一の際、擦り傷防止には結構役立ちそうな感じ。 本来、夏以外の3シーズン用のものですが、日焼けする位ならば、管理人は夏場も使います。 (2007. 8) |
 |
【メンテナンス編】
| ボルトで締めこんで固定するため、そのままだと車体に傷がつきます。そこでウレタンシート(シール)を車体に貼り付け、そこに薄いゴムシートをその形に切って(写真右)、スタンドの固定部分で挟み込む形にしました。スタンドとして売っているもののオリジナルは、右の写真のゴム部品以外のセットです。 フローティング状態のため、少し動きます。ゴムシートは極力薄い方が良いです。あと標準では足が長すぎ、ほぼ直立状態になってしまうため、2センチほど切り詰める必要があります。切りやすいように、スタンドの足に長さの目安として目盛りが入っています。 軽合金なので、カナ鋸で楽に切れます。 |
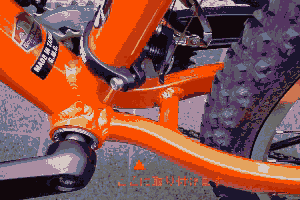 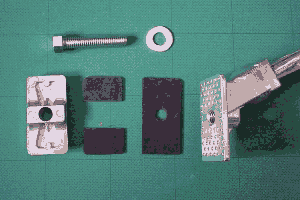 |
サスペンションシートポストのオーバーホール
| しっかり働いてもらっているXtCですが、シートポストからギシギシと音がしだしました。一応作動はしているようですが、確認を兼ねてオーバーホールしてみました。 用意するものはヘックスレンチ、スナップリングプライヤ、それにグリスです。 今回はマルチパーパスグリスと、一部にモリブデングリスを使用。 実際の作業 パーツの名前は全くわからないので、管理人が勝手にそれらしく命名してしまいます。説明書も付いていましたが、内容はアメリカンな感じで、パーツ名が "TOP" とか "BOLT" とかしか書いていないためです。 まず車体からシートを外し、6mmヘックスで外せるところを外します(シートとパイプ下部のスプリングキャップ)。上側のゴムカバー内にある調整用キャップ(手で回すところ)を外し、中にあるスナップリングを取ります。これでインナーパーツを全て取り出せます(写真)。 もともと塗ってあった粘着力の強そうなグリスは殆ど流れていました。いったいどこへ消えたのか? でもそのおかげで掃除は楽でした。掃除の後は、例によって動作時にこすれそうなところを磨き込みます。バネと、パイプの内面(手の届くところだけ)、シート取付部のパイプを耐水ペーパーで磨きます。綺麗になったら、グリスをつけて復元しました。黒いパーツのみ面取り後、モリブデングリスを使用。 仕組みの説明 このサスペンションの調整機構ですが、シート直下の調整リング(ねじ蓋)をねじ込むことで、シート取付パイプについている白い樹脂パーツが押し込まれ、円形スプリングを介して黒い楔パーツを押し込みます。黒い楔パーツはパイプ側に切られた、パイプ直径に対して徐々に狭くなる溝に押し込まれ、シート取付パイプとの間でフリクションを発生する仕組みです(読んでもわかりづらいですね)。 予めバネを縮めておいて見かけ上サスを硬くするプリロードは、シートパイプ下端の、スプリングキャップの締め込みで調整できます。ただ、車体からいちいち外さないといけないし、工具も必要なので面倒です。 作業結果 ちょっと乗っただけでは、はっきり言ってわかりません。初期状態に戻った程度でしょうか。もともとフリクションが多い仕組みなので、多少の加工では効果が体感できないようです。あと、少しグリスが少なかったかも。ただ、ギシギシ音は無くなったのでOKです。長距離走ったら違いがわかるかな? |
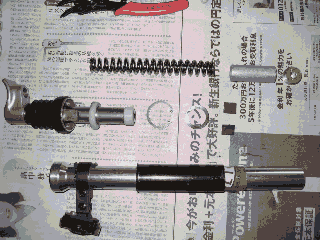 上から順に、スプリングキャップ、スペーサーパイプ、 スプリング、シート取付パイプ(調整リング付)、 スナップリング、円形スプリング、フリクションウェッジ (黒楔パーツ×2)、シートパイプ 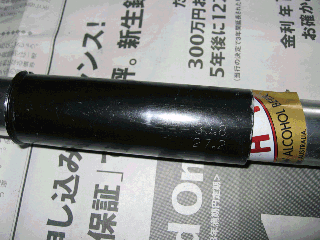 スペーサーとシートパイプがあっていないため、空き缶を 切り開いたもので調整しています。 |
|
| 使用開始から約1年経ったXtCですが、加速時に負担のかかるリヤの真ん中が、見事にまっ平らに減っています(写真)。これはこれで舗装路上の加速がラクでいいのですが、フロントはまだまだ山があるので、思い切って前後を入れ替え(ローテーション)をすることにしました。 なお左がリヤ、右がフロントで使用したものです。前後パターンは同じで、回転方向(タイヤサイドに指示あり)が違うだけです。だからローテーションできる訳ですが。 実際の作業は、サイクルベースあさひのHPのメンテナンスマニュアル「MTBのタイヤ交換」を参考に、行いました。ここの解説は、別にマニュアル本など買う必要を感じないくらい、とても詳しくて便利です。 簡単に手順を説明すると、 1.車体をひっくり返す。ハンドルとサドルに傷が付かないようにウエスなどを敷いておく。 2.リヤのギヤをトップ(一番小さい歯車)に変速しておき、ホイールを外す。 3.タイヤの空気を抜き、タイヤレバーでホイールから外す。 注意点はタイヤ全体を押しつぶすような感じで、なるべく空気を出し切っておくこと。バルブの根元にある、ホイールに固定しているナットを取れば、チューブをタイヤごとホイールから外せます。タイヤレバーは全く使用しないで出来ました。はめるときは逆手順で行います。 作業後、ハンドリングが良くなった感じがします。交換前は、直立(直進)から少しバンクさせてコーナーに入ると、かなり抵抗が増える感じがありましたが、それが違和感を感じない程度に改善されました。フロントがまっ平らに減っている方に変えたので、ハンドリングが悪くなるかな~と予想していたのですが意外な結果です。自転車では、いわゆる「リヤ重視」で曲がっているってことなのでしょうか。 今度リヤが減ったら、いよいよオンロード向けスリックタイヤに交換だ! → これに交換しました。(2004.12) |
 見事に真ん中が減ったタイヤ。ヒビはかなり 入っていますが、まだまだ使えます。右の方 がかなり細く見えるのは、ホイールから外した 状態だからです。左は規定空気圧の状態。 |
ブレーキ調整 ブレーキワイヤーが伸びてきたので、調整します。 ワイヤーの張り、いわゆる「遊び」を調整するわけですが、キャリパー側(ワイヤー飛び出し量)と、ブレーキレバー側(ロックナット+アジャストボルト)で調整します。大きな調整をキャリパー側で、出先などでの微調整をレバー側で行います。キャリパー側で調整する際は、レバー側アジャスターを捩じ込んだ状態にしておきましょう。 あと、ブレーキパッドとディスクの隙間がアンバランスになっていたので、これも調整しました。 このタイプのキャリパーは、パッドがキャリパーに固定されている側と、レバー操作で動く側があり、キャリパー側とディスクとの間が開いていると、ディスクに曲がる力が入るような形でブレーキを掛けることになります。利き味もなんともよろしくないので、隙間を揃えるようにしました。 やり方は簡単で、写真のヘックスボルトをまわすだけ。しかし、穴が段付きなので、ヘックスレンチをきちんと垂直にしないと奥まで挿し込めず、ナメそう(特にリヤ側)。注意が必要です。 シフターワイヤ注油 ワイヤーはアウターがあるので、なかなかきちんと注油できません。 そこでペダルを回しながらシフターで後ろをローギア(一番大きなギア)に変速したあと、シフターのみトップギアのポジションにします。メンテスタンドがあると楽ですね。そうすると、シフトワイヤーが写真のように弛みます。ぴっちり張った状態とは比較にならないくらい注油しやすくなります。 今回はワイヤーインジェクターという器具も使いましたが、スプレー式の潤滑油なら端から吹き込めばOKでしょう。余り粘度の高い油だと、使っているうちに汚れを呼んで動きが悪くなります。 但しこのやり方は変速機に負荷が掛かるそうなので、たま~にやれば良いようです。 ボルト交換(オマケ) ブレーキレバー(Avid)をハンドルに固定するボルトが錆付いたので、入れ換えます。左はオリジナルのメッキボルトで、右が置換用ステンボルトです。元のボルトはいずれ錆で六角が崩れそう。「ネジの永井(*)」で購入しました。2本購入でも全く嫌な顔をせずに対応していただけました。 (*)世田谷区上馬4-35-13(環七外回り、駒留陸橋脇) お昼時(12:00~13:00)はお休みの模様。 標準のボルトは、コスト削減のためかかなりメッキが弱く、一度雨に当たるとすぐに錆付きます。見えないところだし、今の所そのままでも良いのですが、錆びにくいステンレス製に交換しました。6mmの六角ボルトですが、長さがオリジナル18、ステン16mmです。既製品のボルトは、16の次は20mmのようです。オリジナルより長いと、ねじ込むところが貫通していない関係上、完全に締め切ることが出来なくなるかも知れないので、少し短めの16mmにしました。 このステンレスボルトは削り出しの切削跡が残る、非常に精度の高そうなボルトです。ちょっとオーバークオリティかも。値段は2本で\336でした。 作業結果 今回、一番効果があったのは、実はチェーンをきっちり清掃して注油したことだったりして....。灯油(下手なケミカルよりずっと効果的)と歯ブラシでしつこく洗い、泥状に詰まった油を落としました。クレの5-56しか使っていないのに、結構汚れはたまります。 結果、走行中に音が全くしなくなり、物凄く漕ぎが軽くなりました。ちゃんと手入れしましょう(自戒)。 |
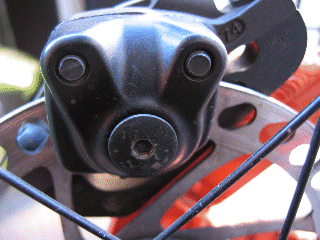 リヤキャリパー裏の調整ボルト。工具が挿し込み難いです。  シフトケーブルはこんな風に弛ませると注油がラクです。 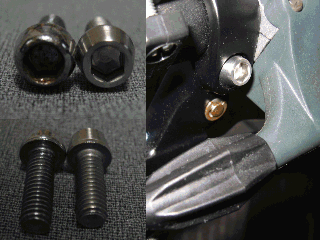 旧ボルトとステンボルト。若干、形と長さが違いますが 装着できました。ブレーキレバー支点のボルトの錆は 5-56で磨いて落としました。 |
|
| 下準備 最近、ほったらかしになっているMTBのフォーク、 ManitouMAGNUM Rのメンテです。購入から丸2年経過しましたがPrepMグリス注入以外ノーメンテのため、分解整備しようと思い立ち、遅っ~いマニトウHPから整備マニュアル(英語)を入手。部品図付きなので、英語が読めなくてもかなり役立つはず。 用意するもの 24mmソケット、6mm六角ロングソケット、エクステンション(250mm)。 外すのにかなり回すので、ラチェットハンドルがあると楽です。 分解 MAGNUM R(2001)は、左レッグ(乗車視点からのフォーク左側)がエラストマー&スプリング、右がオイルダンパーとなっており、オイル交換のみなら右だけ開ければ出来るでしょう。今回は分解整備するつもりだったので、両方バラしました。 始めに左レッグのスプリングアジャスターを、反時計回りに軽く止まるまで回し、最弱セッティングにしておきます。それから24mmソケットで、アジャスター台座であるトップキャップを緩めます。このキャップ、六角部分が薄いため非常になめやすいです。緩み始めより回している途中で、グニャっといきます。ソケットは意識して水平を保ったほうが良いです。 トップキャップと共に、エラストマー+コイルスプリングが出てきます。チューブの底に6mm(マニュアルでは4mmと書いてあった)六角ボルトがあるので、外します。これが左レッグのインナーチューブをアウターに固定している部分です。 右レッグも同様に外すと、トップキャップにピストン付きの棒が付いてます。オイル漏れ防止のため、キャップに接着してあるということなので外しません。オイルダンパーですから、オイルが出ないよう、ゆっくり取り出します。オイル排出後、マニュアルによると8mm六角でロッドを外し....となっていますが、そんなものはありません。結局、リバウンドピストンから先が分解できませんでした。 なお、オイルは注射器で吸い出しましたが、これだと多少残るようです。車体を逆さにして出すと、全て排出できるはず。 組み立て マニュアルによると指定オイルは5番ですが、今回はカワサキ10番(モーターサイクル用)を使いました。飛んだり跳ねたりするわけではないので、油面を下げておけば危険なほどの差はないだろうと判断しました。このオイル、割安なんですが、使うときは自己責任で。スプリング側は、インナーパーツにウレアグリスを塗ってから復元しました。 油面は95.2~120.6mm(推奨値107.9mm)の設定なので、オイルが固めなのを考慮して今回は115mmにしました。油面の測り方は、入り口(キャップのネジが切ってある一番上)から、油の表面までの距離です。巻尺か何かを突っ込んで、計測しましょう。 作業結果 オーバーホールすると、動きが別物になるという話ですが、オイルを入れ替えただけでもかなり効果ありです。但し今回は油面を下げているので、その分は差し引いて考える必要がありますが.....。 次回はきちんと、「完全分解整備」を目指そうと思います。(2005. 8) |
 メンテスタンドで立たせて、前輪を外したところ。 傷つき防止の為、軍手を穿かせています。  注射器でオイルを抜き取りました。ご覧の通り、 かなり劣化しています。 |
|
| XTCのチェーンが伸びきっていたので、交換します。 走り方、手入れで差が出ますが、距離で言うと 4,000Kmも走れば、交換時期になるようです。 用意するもの 対応するチェーン(HG53 114Links)、チェーンカッター(TL-CN23)、アンプルピン(接続ピン)。 ピンは新品チェーンに1個付属しますが、更に予備があった方が安心です。 実作業 始めに管理人の興味で、チェーンの伸び具合を測定しました。古いチェーンは20リンク(10コマ)で 25.5cm、新品は 25.35cmでした。つまり0.6%伸びてます。どこかで「チェーンは0.1%伸びたら交換時期」とか読んだ記憶があるので、とっくに交換時期過ぎているはず。古い方はリンクもゆるゆるで、横方向にかなりしなります。 実際の交換作業は、古いチェーンをカットし、新品を同じリンク数で切って、ギアに通して繋ぐだけです。例によって、サイクルベースあさひのHPを参照しました。工具さえあれば、チェーンについてくる説明書も詳しいので大丈夫だと思います。が、よく考えて組まないと、余計に切ったり繋いだりしなければなりません。 管理人は長さだけに気を取られて切断したところ、出荷時にカシメ用ピンをセットしてある方を切ってしまいました。仕方なく、チェーンに付属の補修用?アンプルピンを使って繋ぎました。こちらの方が強度が高いと説明書にあったので何とか自分を納得させました。 なお、ギアを変更した場合等は、正しいチェーンの長さにしなければなりません。これは前ギヤをアウター、後ギヤをロー(最大ギア)に掛けて、ピンと張った状態から2コマ余裕を持たせるのがセオリーだそうです。 作業結果 当然、変速はスパッと決まります。驚いたのが、漕ぐときに軽く感じること。チェーンの伸び(ガタ)が、かなりロスになっているようです。体感できるほど変化がありました。これなら高級品を使うより、普及品で良いから早めに換えた方が良いですね。次はもっと早く換えよう......。 (2006.3) |
 新品チェーン交換後。防錆用の機械油?が付いており、 そのままだと汚れがこびりつきそうだったので、柔らか めのオイルを塗布しました。 |
モーターサイクル用グリップを無理やりねじ込んでみた、の図。失敗です。 発端は、もともと装着されていたグリップのゴムが、変質してべとべとしてきて更に崩れてきたので、グリップを換えなければならなくなったこと。写真上の中段のグリップに穴が見えます。かなりべちょべちょしていて気持ち悪いです。 スラムの純正部品は出ないようです。売っているのは変速する側が短いタイプのものだけです。つまり買い換えろということでしょう。自転車ってこういうところがエコではないですね。消耗品ぐらい供給するのがメーカーの義務だと思うのですが....。シフター自体が消耗品?? 使用済みのモーターサイクル用グリップが家に転がっていたので、ハンドルパイプにあてがってみると内径がほぼぴったり!人間が手で握る部分ですから、同じ大きさになる方が自然ですね。それで転用してみようということになりました。 スロットルグリップ(右)側は内径がシフター部にほぼぴったり。クラッチ(左)側グリップは内径が小さく、XtCのハンドルパイプにぴったりなので、二つのグリップを切って片側に使用することにしました。どうせ使用済みですし、贅沢に使用します。 あとは写真上のように、オリジナルグリップの長さにあわせて切り詰め、更にシフターの形に合わせて削ってやれば....これはちょっと無理っぽいので、今回ははめられればOKということで進めました。 で、装着してみた結果は見た目はともかく、シフター側の溝にゴム部分が収まらないため、その分グリップが太くなってしまい、シフトするのに余計な握力を要求される感じ。安心して変速できるようにという当初の目的から逸脱した結果に....。 そういう訳で、シフターを変えてしまうか、元通り戻してハーネステープというべとつかないビニールテープで応急処置するか、このままにしておくか、現在検討中。 (2007. 10) |
 真ん中が穴が開いた純正グリップ。下がカットした Motorcycle用グリップ。滑り止めはかなりいい感じ。  完全に段差が出来てしまい、かなり後悔した所。 |
【工作・加工編】
シフターカバー作成
グリップシフトのカバーがない!(怒)。納車の翌日、自転車カバーを外して気づきました。どうせ部品も出ないので、自作することにしました。
左側のカバーを元に、型取りコピーします。左右で多少形は違いますが、ベースとなる部分はほぼ同じ形なので。手順は以下のとおりです。
| 用意するのは「型取くん」「プラリペア」のセット。結構有名な商品なので、ご存知の方も多いでしょうが一応説明します。 まず、型取くんを熱湯で温め、軟らかくしてから対象物に押し付けて型取りします。型が冷えたら対象物を外します。柔軟性があるので今回のような形ならば、簡単に外すことが出来ます。 型が出来たら、そこにプラリペアを盛り付けて成型していきます。粉と液体を混ぜて硬化させるのですが、型に粉をある程度ふりかけ、液体を垂らしてやると良いようです。樹脂が反応して固まったら、型から外します。硬化は早いので、ここまでで15分ほどでできます。 今回は、多少形が違うため、さらに現物合わせで削り込み・盛り付けをします。バリを取って、着色すれば完成です。ちなみにこのプラリペア、割れたプラスチックの補修などでは、プラスチックと溶け合って固まる(溶着する)ため、通常の接着剤よりかなり強力に固定できます。強度の必要な所の補修に是非。 |
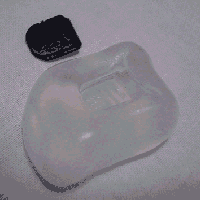 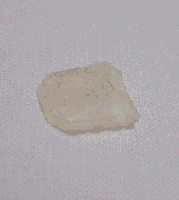 型取りをしたところ 出来上がった樹脂パーツ |
||
シート加工(コンフォート化)
| 加工その1 冬の間、休止していた自転車通勤再開のため、快適装備化を推進します。 狙っているのは、真ん中にスリットの入ったコンフォートサドル形状を実現することです。車体に付いてきたままのシートでは、中心が山のように盛り上がっており、長く乗っていると座ったところ(●●の裏側!)が張った感じがするようになります。この圧迫感を、くぼみを作って軽減しようというわけです。おしりの両脇で支える形状にするということですね。 用意するものはプラスドライバー(2番)と長めのマイナスドライバー、タッカー(ホッチキスのようなもの。SPADAのページを参照下さい)、それにゴム用ボンド(コニシG17)です。 まず、ばらせる所は全てばらします。プラスねじで固定されているプラスチックのカバーを外し、シート表皮がタッカーで止められているので、マイナスドライバーでこじって抜き取ります。全て剥がすと、後で位置決めが面倒になりそうなので、必要最小限外すことにしました(写真上)。 剥がした部分(写真上でシート後端の黄色いクッションが見えている所)からマイナスドライバーを突っ込み、クッションを削っていきます。削り取る部分のシート表皮とクッションの接着を剥がしてから、クッションを削るとやりやすいようです。クッションはかなり固めのウレタン?でした。乱暴に作った割には綺麗に削れたと思いますが、本来ならシート表皮を完全に剥がし、カッターで削ったほうが良いでしょう。 目的の形に削れたので、マイナスドライバーの先にボンドをつけ、奥の方から塗り伸ばしました。接着面が触れられるくらいになったら、貼り合わせてそのまま置いておきます。私は翌日まで待ってから組み立てました。サドル後端から中央部までスリット(窪み)ができました。 実際に走ってみて、件の圧迫感はかなり軽減されることが確認できました。めでたしめでたし~。 加工その2 前回の加工でかなり改善されたものの、更に快適さを増すために、座面に低反発ウレタンを追加することにしました。もう一度シート表皮を剥がして、薄くスライスしたウレタンを追加します(分厚いのしか手持ち在庫が無いため)。これは体温で暖められると柔らかく変形する、低反発枕に使用されるもので、もともとのクッションよりかなり柔らかめです(写真中)。 ついでにコンフォートサドルの市販品を参考に、スリットは更に前方まで延長し、同時に幅も少し拡大しました。あとは元通り表皮を被せます。ウレタンが入ったので強めに引っ張ってタッカーを打ちます。シート表皮の白い部分はかなり弱く、強く引っ張ると裂けてしまうので注意(一度やってしまった)。 出来上がりはシート後ろ側にかけて、かなり太めの見た目になりました(写真下)。毎日走っていると、尻に多少の違和感を感じていたのですが、それが全く無くなりました。 因みにこの素材はアライ化成のHPから注文したものですが、現在営業譲渡中とのことで、注文を受けてもらえるかは不明。ここの枕は非常に良かったんですが......。 |
 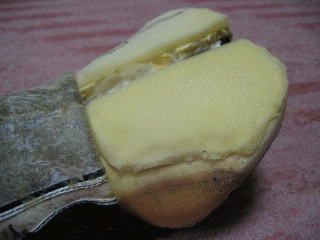  |
|
| 車体がオレンジ/黒、スタンドが銀色、と明らかに浮いてしまっているため、塗装することにしました(写真)。原付バイクを塗った塗料が余っているのでそれを使います。 用意するものは塗料と下地処理剤(メタルプライマー)です。 メタルプライマーは金属に塗装をするとき、塗料を塗る前の下塗りとして使います。塗料の食いつきが良くなり、ベロッと剥げにくくなります。 塗料は、今回のように隠蔽力の弱い明るい色は、下に白などを塗った上で、仕上げる色を塗ります。缶スプレーだと、エナメルよりラッカー系の方が、金属への食いつきが良い気がします。 まずスタンドに耐水ペーパーをかけます。足付けといわれる作業です。最低でも中性洗剤など油を落とせるもので、脱脂をしましょう。指紋などが付いていると、塗料を弾きます。 それから、メタルプライマーを薄く塗ります。乾燥後、白、オレンジの順で塗ります。塗料は薄く塗るのが基本で、厚みを稼ぎたい時は、乾燥後、重ね塗りをしましょう。 |
 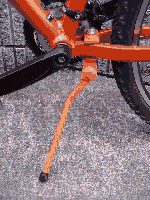 そのままだと後付け感が強いですが、塗装後は、多少 色味は違うものの、標準でついていたかのようですね。 |
| 今回のテーマ KALLOYのシートポストサスです。これによりかなり快適度はアップしましたが、まだ初期作動がイマイチだという不満もありました。スリックタイヤに変更したことで乗り心地が固くなったこともあり、サスペンション内部に手を加えて自分の要求に近づけることにしました。 ネットなどで見る限り、バイク(自転車)用高級シートサスは、エラストマー単体、あるいはコイルスプリング+エラストマーという構成のようなので、現在のコイルスプリング+金属カラーを、同じ構成に変えてみよう、というのが今回のテーマです。ちなみにエラストマー(Elastomer)とは、ゴムとプラスチックの中間の特性の物質で、あまり速い動きには対応できないようです。 このコイルスプリングは結構固く、作動開始までにかなりの荷重を受け止めます。つまり動かないので、これが長時間ではお尻の痛みに繋がると思われます。そこでカラーをエラストマーにすることで、荷重初期でエラストマーの弾性が働き、高加重域ではコイルスプリングの踏ん張りが働くという、理想に近い動きをするのでは、と考えた訳です。 で、一番の課題は素材の調達ですが、これはカラー(径18.9×長50.5mm)の大きさで探します。今回は、ゴム栓を試しました。円柱状だと固そうだったので、動き(潰れ)がよさそうな栓形状にしたのです。写真のものは最大径19mm、長さ22mm、4個入\147です。長さがカラーより短いので、別途ホームセンターで調達したステン丸座金(M8用、8枚で約10mm、\39)で調整します。 実作業 入れ替えるだけです。ゴムが柔らかめなので、無負荷状態で元のカラーより長くなるようにセットしました(ゴム2個と丸座金6枚使用)。バネがゴムに食い込むのと、ゴム同士が変形してシートパイプに詰まるのを防ぐため、バネ、丸座金、ゴム、丸座金、ゴム、丸座金4枚、という順序で入れました。ゴムと丸座金には滑りを良くするためグリスを塗っておきます。 プリロードは、とりあえず短距離で好印象だったのは、ボトムキャップを 15mmほど締め込んだ状態。乗車時の初期沈み込みは 10mm近くあります(フルストローク量は約18mm)。因みに管理人の体重(60kg)では、以前は全く締めこまなくてOKでした。なお部品構成はオーバーホールの項も参照ください。 作業結果 実走テストが必要なので、途中経過です。期待の滑らかな初期作動による乗り心地改善ですが、これはすぐ確認できました。あとは長距離乗っても適切な効きを示すかどうかですが、これは実際に走ってから......。 今回は動きの良さを重視して、円錐を切ったようなゴムにしましたが、もう少し押さえの利いた動きでも良さそうなので、様子を見て円柱状のものも試してみる予定。(2005.1) |
 ハンズにて調達しました。4個入りです。円柱状のは径が 大きすぎるのしか店頭にありませんでした。 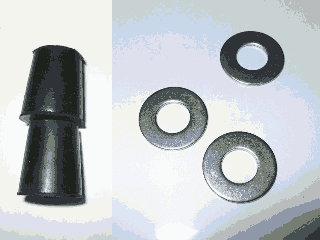 二個重ねてもカラーより短いので、右の丸座金を積み 重ねて調整します。6枚重ねでほぼカラーと同じ全長に。 |
|
●XtC850(2002モデル)スペック
出荷時のスペック情報は、メーカーのHPも含めてすぐに消えてしまうので、自分の備忘録としても書いておきたかったのです。この色はそんなに好きではなかったけれども、見慣れました。スタンドは安売りしていたUNICOのB-Stand(\1,575)。手でノブ(ねじ)を緩めるとぺったんこになって収納に便利。写真は壁にピントがあってしまいましたがご容赦ください。

初期状態のXtC850(ブラック×オレンジ)
| 部品 | 内容 | 備考 | |
| フレーム | GIANT ALUXX6061-T6アルミ オーバーサイズチュービング リプレーサブルリアエンド |
非常に軽いです。フレームの色が剥げないよう、ワイヤーのあたる部分に同色のシールやビニールテープを貼っています。 | |
| フロントフォーク | ANSWER MANITOU MAGNUM-R 76mm |  |
よく動きます。 インナーチューブ 25.4mmで、かなり頑丈。写真右側がスプリングで、作動の固さを調整可能(黒いノブを時計回りに回すと固くなります)。 背面にグリスポートがあり、専用グリスガンで日常メンテが楽にできます。 よく言われるように、シールは剥げ易いです。新品でも一部が浮いています。この辺りはやっぱりアメリカ(実際は台湾)製って感じ。 なおゴムブーツは、下側の穴(5個ぐらいある)の開いている側を、前(ブレーキアーチ側)にして水が入りにくいようセットしてありました。Motorcycleとは反対ですね。 |
| BBセット | CH-52 113-68mm | 回転も滑らかで全く不満ありません。 | |
| ギアクランク | GIANT 44/32/22T 170mm | 精度もよく、仕上げは綺麗です。がっちりしてます。 | |
| チェーン | SHIMANO CN-HG53 | グレードで余り変わらないようなので、同じものに変える予定。 | |
| ペダル | VP-992S スチールゲージ ブラック | 唯一、仕上げが安っぽく感じるところ。ですが、前後リフレクター付でグリップも良く、機能的にはこれで充分とも言えます。 | |
| ヘッドセット | VPアルミ 1-1/8 インテグラル | ||
| ハンドルバー | ARICLE YCA215A 580mm アルミアップバー | 中心と端とで、微妙に太さが変わっています。アクセサリを装着するときは注意しましょう。もうちょっとアップでも良いかも。 | |
| ハンドルステム | GIANT アルミBOX型 90&105mm 15D ブラック A-HEAD | ごつくて十分以上と思います。 | |
| ブレーキセット | HAYES HMX-1 メカニカルディスクブレーキ | ディスク厚 1.8mm。掛け始めからよく効く代わり「キーッ」と鳴きます。パッドの減りをチェックしづらいです。ハードブレーキでゆがみ、シャンシャン擦れる音が出ます(走っているうちに直ります)。ポストマウントタイプ(いわゆるラジアルマウント)です。 |
|
| ブレーキレバー | AVID AD-3 | 肉抜きはされておらず、剛性感あり。効力の調整機構は無いです。 | |
| フロント/リア・ハブ | FORMULA GDI81C 32H6穴ディスクブレーキ用クイックレリーズ | 初めかなり固く締まっていましたが、小指で起きない程度でいいそうなので、それぐらいに緩めました。 | |
| リム | WINMANN ZAC19R 26x32H CNC SIDE | 半つや黒仕上げで、見た目にも振れはなく、精度は良いです。 | |
| スポーク | 14G ステンレス ブラック | 詳しくはわかりませんが、充分、頑丈です。 | |
| タイヤ/バルブ方式 | MICHELIN WILD GRIPPER X-COMP 26x1.95 /仏式バルブ | 舗装路では当然重く、ロードノイズ多し。ブロックタイヤとしては、これでも漕ぎは軽いらしい。オンロード用スリックへ変更済み。 | |
| フロント・ディレーラー | SHIMANO DEORE FD-M510 34.9 トッププル | SRAMのシフターとあまり相性が良くないのでしょうか。 調整しても、変速後に時折、カラカラ音がします。変速後、戻す方向に力を入れるといいみたい。ほとんどアウターで走るので関係なし。 |
|
| リア・ディレーラー | SRAM ESP5.0 9S | 補修パーツがない.....。消耗したらSHIMANOに交換の予定。 多少厚ぼったいですが、性能的には充分満足しています。  |
|
| シフトレバー | SRAM ESP5.0 HALF PIPE 9S | 楽チンですが、カチッと変速するには向いていないです(前ギアは変速後、戻す方向に力を入れるといいみたい)。シフター自体のグリップゴムが、隙間が開く方向にずれ易い。他と擦れるより良いですが(写真は、ずれてくる前)。 |
|
| フリーホイール | SRAM7.0 34-11T 9S (34/28/24/20/18/16/14/12/11T) |
フロントをほぼアウター固定で使用しているため、リアも3~9段で使っています。ギアの繋がりは、7段までは滑らかですが、7段から8段へ変速する際のショックが大きいです。なお個人的には9段はいかにも後付けの感があります。また5・6段で変速操作しても変わらないことがたまにあります。 | |
| サドル | SDG U.S.A. BEL-AIR | 固めですが後ろの方は割とクッションが効いて乗りやすいです。でも長時間だとやっぱり痛くなります。なので加工しました。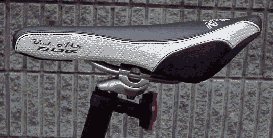 |
|
| シートピラー | KALLOY SP348 27.2x350mm ブラック | 自転車は多くがこうなっているようですが、ヘックスボルト一本固定のため、角度調整が少しやりづらいです。手でしっかり押さえつけながらボルトを締め付ける必要があります。 | |
| シートピン | アルミ 34.9 クイックレリーズ 30.8-27.2シム付 | 肉抜き穴あり。Giantのロゴ(ペイント)が入っています。 | |
| 付属品 | ベル、ロック | 普通の、指でハンマーを弾いて鳴らすベルが付いています。 | |
| 重量 | 12.7kg(480mm) | 片手でひょいと持ち上げられるので、充分でしょう。 | |