 『神への告発』を再読して
『神への告発』を再読して 『神への告発』を再読して
『神への告発』を再読して

781116ー000924
『神への告発』
(箙 田鶴子[えびら、たづこ]、筑摩書房、1977年)
[1]<ギャップ、ギャップ>
[2]<「神への告発」>
(2) 再読して、以前は記憶に残らなかったが「私の叔父も都知事ですけれど」(P.178)
という著者の発言が本文中にあった。
(3) 本文中には、テ−マに対する答えが直接的にある。
(4) 内容は、短時間には要約し難いが、
(5) 内容について述べるには、時間をかけて整理する必要があるが、
(6) (a)<出生から何らかの形で親がかりの時期>
(7) 本文中のいくつかのテーマ
(8) 前記(5)の「いやになる」感想に、終章で著者自身が結論に辿り着く。
(9) そして著者は、終章「弥勒の黄昏(たそがれ)」の中で、人間の業[「精神の汚
れ」(P.252)]が、悟りに到達するのを、弥勒が「五十六億七千万年の発願」を立て
たという、その満願に当たる日が、明日と言わずとも近い将来であることを願う、と
書いている(P.252)。
(10) そして、この本の発行[1977年(昭和52年)]後21年を経て、[1976年(昭和
51年)生まれの]乙武洋タダ(おとたけ、ひろただ)氏の「五体不満足」が出版され
る(講談社、1998年)。
<参考:目次>
『神への告発』(箙 田鶴子[えびら、たづこ]、筑摩書房、1977年)
第1部
第2部
第3部
第4部
Webサイト紹介 : <復刊ドットコム>
ある日(1999年)の深夜に、つけ放しのテレビで「インタ−ネットを利用したメ−
ルマガジンの発行」を紹介する番組があり、その中で実例に挙げた、人生相談的な内
容のものの発行者が、「相談を寄せた障害者を訪ねる場面」があった。
最初にパソコンの画面に、相談者のメ−ルが写し出されるが、「障害のために親が
かりで生きてきたが、年齢が高くなるに従い父親と考えが合わず、身体障害がある自
分だが、親から自立した生活が出来ないだろうか」という内容だった。
発行者が訪ねるのは地方の農村の一軒家で、迎えに出るのは車椅子に乗った障害の
ある相談者だった。彼は脳性まひで手足が効かず、けいれんし、発音も不自由なため
文字盤を指して意志を伝えるが、その指もふるえてどの文字を指しているか分かりに
くい。
パソコンの画面に映った論理的な文章と、その彼の外見にはギャップがあった。
「ギャップ、ギャップ」と頭の中で繰り返すと思い出したのは、以前読んだこの本
「神への告発」だった。この著者も脳性まひで、想像するその姿と本の文章にはギ
ャップがあった。

(1) あとがきに、「生まれてから死ぬまで、報われること無くして終えた人たちを想
うとき、(この著作を完成させた)私の幸せの感は苦みが混じって来るよう」(P.253)
とある。
考えを発表する機会を得た数少ない者である著者の意志に沿えば、この本のことを
人に伝えることが、その存在を知る者の義務と考えた。
1977年、著者43歳の発行(P.18)。
1999年9月に、東京都のI知事が重症心身障害児(者)施設である府中療育センター
を視察したが、記者会見で「ああいう人たちに人格があるのか?」と発言して批判を
浴びた。より詳しい報道では、重度の障害者に接した直後の素朴な感想を、きわめて
直截的に表現した「とまどい」と窺われるものだが、この一事で差別者と指弾しない
までも、この本が発行された1977年から既に20余年が経っていること、発言者の政治
経歴、年齢からすれば、余りに無知と言わざるを得ない。
この知事は、2000年に入り、自衛隊を前にした挨拶で、「不法入国の外国人が暴動
を起こさないよう威嚇する、治安出動も」という発言をして批判を浴びるが、外国人
犯罪組織の進出と、労働力としての不法入国者を混同して、そのどちらの当事者にも
メリットが無い「暴動」という妄想を流布して、人々の中の排外的意識を煽動してい
る。
このふたつは、「タカ派」というのは具体的な知識の無さの別名であることを明ら
かにしている。閑話休題(それはさておき)。
・ 重度障害者に意志(人格)があるか
・ 生きる価値があるか、本人が欲しているか
・ 生活保護と所得保障の違い
経済的基盤の有無と人格の独立のこと
・ 出生から何らかの形で親がかりの時期
・ 県立施設に入寮した時期
・ 生活保護から始まり画業の収入でひとり暮らしをした時期 に分かれる。
以前読んだときの印象そのままに、母親譲りのあくの強い著者の個性で、読む途中
で、「いやになる」(後述)こともしばしばあるが、
著者も「偏見の連鎖」の中に居て、著者自身も偏見から自由ではない。
「著者と母親、姉、義兄」、「精神障害者、知的障害者と著者」、「著者と小平氏」
「被差別部落と小平氏」、「著者と被差別部落」。
著者を人として理解した父親が病気で亡くなった後、所謂、道徳の基準を失った状
態になり、派手好みで生活感覚を持たず、外聞を気にする母親と姉、義兄に疎まれ、
次第に閉ざされた座敷の奥に追いやられる。
(b)<県立施設に入寮した時期>
後に、県立施設に入るが、当時の救貧的な施設のあり方に、著者が耐えられず、無
謀と言える「自立生活」に突入する。
(c)<生活保護から始まり画業の収入でひとり暮らしをした時期>
重度の障害を持つ著者に対する周囲の捉え方に安住できず、あがくことを重ねる。
(a)<親がかりの時期>
<就学> 学齢期になって、就学通知が来る。しかし、昭和16年頃、当時は養護学校
もなく、「就学免除」を申し出るしかなかった(P.7)。
父に促され、積み木で文字を覚える(P.9)。本を読む(P.25)。描く、書く(P.27)。
<稼得能力>著者を疎んで、その存在を認めようとしなかった母親も亡くなる(P.77)。
姉と義兄宅での生活は、より厳しかった。
食費は1日30円=食パン1斤だけ(P.92)。著者は呟く、「働かざる者は食うべからず、
働かざる者は食うべからず」(P.94)。
(b)<県立施設の時期>
<狭い福祉概念>1958年(昭和33年)に、23歳で、中国地方の県立施設へ入寮する
(P.105)。それから10年、在寮する(P.101)。精神障害者、知的障害者、身体障害者が
いる。81名の在寮者に、寮母3名なので手が回らず、障害の内容、度合いで6名定員の
部屋の組み合わせを決めて、人手不足を補っていた。
当時は、救貧政策としての狭い福祉概念で施設が運営されていて、福祉法にも差別
的表現があった。「身体、精神に著しい欠陥を有する者のみを収容しーーー」。
「頭の中によぎり想われる、幸福であった幼女の日の生活が夢のようだった。
(人間の命が、地球より重く尊いとは誰が言ったのだ。全部嘘っぱちだ。生きてい
ることが、私も含め、これだけ惨たらしい者が、どうして尊いと言えるだろう。全部
嘘だ。きれいごとなのだ。
造物主、神などもありはしないのだ。全能の、全知の神が、これほど悪意じみた蜘
蛛のような私の姿や、この狂い回り汚物を垂れ流す、生まれてから死ぬまで、治療の
見込みも無く生き続けねばならない生命など、造り給う筈はない。もし在しますとし
たら、私は神へ告訴状を突きつけなければ納得ができないーーー!)」(P.154)
(c)<ひとり暮らしの時期>
<障害と受容>著者は、文通していた善意銀行所長(ボランティア活動)の小平氏
の助力を得て、(ボランティア活動がほとんどない)当時としては、無謀と言える
「自立生活」に突入する(P.184)。
著者は、小平氏の手紙で「妻」(事実としても内縁のようなもの)となっていて、
対等でありたいと考えた(P.188)。
小平氏の生活全般に及ぶ援助を人々は善行と讃えるが、誰にも知られない「妻」で
あることに、著者は、小平氏の「善行」を疑い、安住できない(P.192)。しかし、実の
母親、姉が与えたのが座敷牢と蔑視であったのと比べて、赤の他人の小平氏は、事実
として、著者を支え続けた。
しかし、小平氏の立場は、仏教の言葉で「白色白光黄色黄光」という、「場に応じ
た救い」で、「夫と呼びたければ呼ばせ、妻と名乗りたくばそのままに」でもあった
(P.205)。
著者は、自暴自棄とも言える、あがきを続ける。
「既に中年になろうとしながら、まだ成長していなかった私の心、辛酸を舐め尽く
しながら、しかも生まれたとき、甘やかされ育った我が侭さは、無言で痛みに耐える
静けさを知らず、ひたすら頭撫でて欲しい、甘えに飢えた少女の、哭いて求める魂の
呻きを続けていたが、そこまで徹底して受け容れてくれるほど、人は神ではなかった」
(P.218)
<稼得能力:所得保障>小平氏と縁を切ったアパート暮らしを始める(P.220)。
介護者も自分で探す。最初は生活保護。その認定通知には「身体廃疾により、生活
不能力と認む」とあり、著者は、いずれ返上することを自らに誓う(P.222)。
以前から得ていた、外国資本の身障絵画団体の奨学金が増額されて生活が落ち着く
までの様子はすさまじい(P.225)。
生活が小康を得ても、著者は、重度の障害を持つ著者に対する周囲の捉え方に安住
できず、あがくことを重ねる(P.243)。
(P.251)「徹底して味わい続けた醜女の哀しみ、だが自身の中に、(迫害者と)同じ
感情が無かったと、片時でも言えただろうか。美を欲し選ぶのは自身もだった。人間
と言わず、仮に子犬一匹(を)抱こうときでさえ、より愛らしいものをまず腕は選ぶ。
それは(障害を持つ身である)「己れ」を見据えながら、なお決して醜さ、それも表
面の美醜を、意志以前に、絶対的瞬間、受け入れられないという極を見せつけた。
いま、迫害者、無理解者達を私は愛していた。皆、泣きたいまでいとおしい、私自
身の片割れであった。」
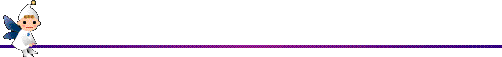
「母が、ボクに対して初めて抱いた感情は、「驚き」「悲しみ」ではなく、「喜び」
だった。生後1か月、ようやくボクは「誕生」した」(まえがき、P.4)
(心のバリアフリー)「ボクは日頃から、「環境さえ整っていれば、ボクのような
体の不自由な障害者は、障害者でなくなる」と考えている」(P.259)。「障害者が
「かわいそう」に見えてしまうのも、物理的な壁による「できないこと」が多いため
だ」(P.260)。「障害者を苦しめている物理的な壁を取り除くには、何が必要なのだ
ろうか。ボクは、心の壁を取り除くことが、何より大切だと感じる。(中略)では、
障害者に対する理解・配慮はどこから生まれてくるのだろうか。ボクは、「慣れ」と
いう部分に注目している」(P.261)。「これは、障害者に限っての話ではない。(中略)
障害者や外国人といったマイノリティ(少数者)への理解については、「慣れ」とい
う問題が大きな比重を占めている」(P.262)。「障害者を見れば「どうして?」との
疑問を抱くが、その疑問が解消されれば、分け隔てなく接してくれる。(中略)その
疑問を心に残したままにすることが、障害者に対する「心の壁」となってしまう」
(P.263)。
「「慣れ」と同時に、障害者に対する心のバリアを取り除くために必要なのは、他
人を認める心だと思う。(中略)さまざまな民族がひとつの国家で生活をしている欧
米では、他人と違うといった理由で否定をしていたら、きりがない」(P.265)。「そ
して、他人を認める心の原点は、自分を大切にすることだ」(P.266)。「障害者が暮
らしやすいバリアフリー社会を創るためだけではない。すべての人が、与えられた命
を無駄にすることなく、その命を最大限に活かして生きていくためにも、自分らしさ
を失わず、自分に誇りを持って生きていくことを望みたい」(P.267)。

1.不幸な出生/2.父母の相克/3.母の変身/4.九州への転居/5.5か月の孤独/6.離散する家族/7.他人の家へ/8.母の誇り/9.姉夫婦との確執/10.姉に追われて
1.入寮者たち/2.逆光の絵画/3.新しい寮長/4.純子の愛/5.裏切られた人間寮長/6.神への呪い/7.純子との別れ
1.初めての恋/2.小平との交際/3.自立を求めて/4.愛憎の日々/5.自殺行
1.再出発/2.つかの間の平和/3.満たされぬ愛/4.弥勒の黄昏

絶版や品切れの本を登録する。その本の復刊を希望する人が投票して、一定数に達
すると、出版社に復刊を交渉するサイト。
実は、今回の書評の「神への告発」も、今は在庫がなく手に入らない。このサイト
で投票してもらって、復刊すればと思う。覗いてみてください。

 ホームに戻る
ホームに戻る
 夢幻はじめに
・夢幻
・随想
・短歌連作
・音楽
・市民運動リスト・リンク集
・その他リンク集
・引用
・メール・マガジン
・ブログ掲示板
・ソーシャルネットワーク
夢幻はじめに
・夢幻
・随想
・短歌連作
・音楽
・市民運動リスト・リンク集
・その他リンク集
・引用
・メール・マガジン
・ブログ掲示板
・ソーシャルネットワーク