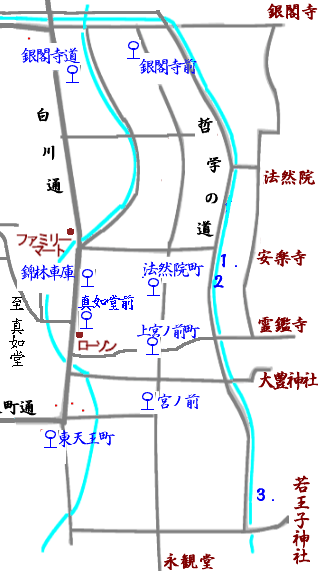坂道の洗心橋を登り右に折れるとすぐ法然院の参道に出ます。
茅葺の門を入ると白砂の砂絵が目に入ります。判りやすく砂絵と
表現しましたが、本当はお寺にとっては重要な意味合いがあります。
季節の絵柄が描かれますが、そこには幾筋かの線条の模様が
描かれていると思います。これは水の流れを意味しており、
この砂段の間を通ることによって、身を清めるという意味合いが
あります。
この法然院には「内藤湖南」、「九鬼周造」、「河上肇」、
「谷崎潤一郎」らが眠っています。本堂は特別公開の時以外は
非公開ですが、法然院サンガと云うつどいの会があり、頻繁に
イベント、法話、音楽会などが行われております。
その折りには本堂で行われる催しもあるので、ちょっと拝見は
可能です。なお境内は自由に散策できます。
法然院前の道を南下すると安楽寺、この安楽寺は後鳥羽上皇の
女御であった松虫と鈴虫が出家した寺として知られ、茅葺きの山門、
そして苔むした庭に咲くツツジなど美しい寺です。でも残念ながら
一般には「鹿ケ谷かぼちゃ」の催事がある時と、春と秋に公開される
だけで普段は見ることは出来ません。
安楽寺をあとにすると、すぐ右手には少し大きな森があります。
冷泉天皇桜本陵です。興味ある方ならすぐ陵墓であることは
判別できると思います。ちなみに正面は反対側の西側にあります。
そして霊鑑寺の門前にでます。鹿ケ谷比丘尼御所とも呼ばれ歴代
住職は皇女が勤めてきた門跡尼院です。
ここから坂道を下れば再び哲学の道に出ますが、話は再び洗心橋に
戻って橋のすぐ南には京都の土産によく登場する「八ツ橋」を
売る店があります。ここの「八ツ橋」はあの白い生八ツ橋では
なくて、焼いたせんべいのような堅八ツ橋です。目の前で
焼いています。ひと袋300円だったかの、お徳用を買って
みるのも良いかと思います。
|