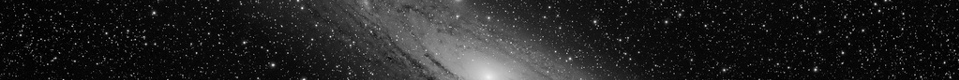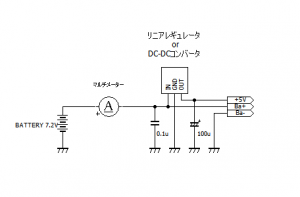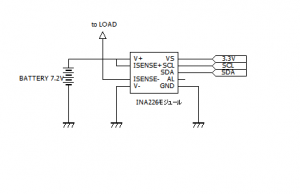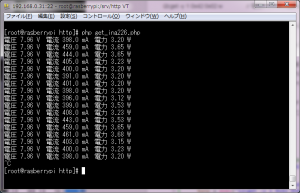迎春。
ハウスローバーの製作は、「きままに」 「無計画に」を、基本としているのですが、年頭にあたり「今年の製作予定と成果計画」を、おおまかに記録しておこうと思います。
前期
加速度センサーの検証
走行距離を知るために加速度センサーの実験を行います。 ジャイロセンサー同様、そこそこのCPU負荷とドリフトを考慮し、採用できるかを見極めます。 使えなければ、車輪へのフォトセンサーを取り付け等を検討します。
インターフェース基板の更改
実験の度に、ジャンパーを追加したりしていたので、基板上が煩雑になってきたのと、搭載するパーツが固まってきましたので、インターフェース基板を刷新します。 モータードライバ用ICも、別なものを使ってみたいと思います。
中期
コントロールWebページの更新
こちらは少し手を付けている部分でもあるのですが、加速度センサーの検証結果によって影響を受ける部分がありますので、その実験後になります。 情報表示をグラフィカルに、操作性の高いインターフェースにします。
シャーシ、ボディーの製作
ユニバーサルプレートのサンドイッチ構造は開発段階では機能的ですが、専用シャーシの製作は、まともな加工工具を持っていないので、なかなか着手できません。 素材も樹脂かアルミか検討中です。 既成品で良い物があれば飛びついちゃうかもしれません。(安易) 実は、IKEAのフードキーパーに製作意欲を掻き立てられる物があるんです。(かなり安易)
後期
ホストCPUの構成
Raspberry Piは、蓄積されたLinuxのソフトウェアが利用できる利点がありますが、電力消費が大きいのが欠点です。 また、ハードウェアに近い低レベルの制御には好適とは言えません。 開発を進めていると、ハードウェアの高速制御や割り込み制御を使いたい場面が度々あります。 計画としては、高レベルミッション用CPUとハードウェア高速制御用のCPUを搭載したいと考えています。 ハードウェア制御用CPUとしては、arduinoやPICが候補に挙がりますね。 Raspberry Piの+モデルは電源周りが改善されたようですが、更に消費電力を絞ったモデルが出ないか、期待したいところです。
自立性ソフトウェアの開発
外部からのコマンドにより動作する点は変わりませんが、部分的な自立性は随時組み込んでいく予定です。 例えば、コントロール信号が途絶えた時、「危険を避ける」 「バッテリー消費を抑える」などの制御ができるようにしていきたいと思います。
番外
「なんの役にも立たないハウスローバー」ですが、明確な(?)役割機能を持たせることを計画中です。 ヒントはこの動画ですが…。
さて、ロードマップとしてはかなり大雑把ですが、これらの計画、どこまで実行できるでしょうか?