 認識
認識 認識
認識

801200−810300
1970年大学闘争
ぼくは、全共闘運動を−−その積極的な面を知りながら、なお、破壊することはできても、
作りだすことができない運動・世代として、−−否定的に見る。1970年大学闘争についての考え方は、
党派が違えば見方が違う。党派と無党派でも見方が違う。党派にとっては、三里塚空港反対、沖縄返還や
ベトナム反戦など、より政治闘争だった。無党派も、もちろん参加した。
「私はこう考えている。」といいながら、本当に自分が「そう、考えている。」とは言えない。
「そう、考えている、かもしれないが、そう、考えていないかもしれない。」絶対に譲れないもの、として、
判断の基礎になるのは経験である。その経験を欠いている。経験と連絡をもっていない認識。
それは自己の喪失と言える。確たる自分がない。自己がないところに、他者もない。だから、感動も、
他者の存在に対する感謝もない。
学校教育では、考えることは、禁止されていた。判断することは禁止されていた。
だれであろうと、ボロボロになって生死の淵から自らはいあがることなしに、
この汚濁をよく払拭できない。
801200−980720
毛沢東「実践論」
〔「実践論」所載『実践論・矛盾論』岩波文庫1977年(昭和52年)第1刷1957年〕
第1に、この本は、マルクス・レ−ニン主義の立場から、書いている。
第2に、章立ては、「認識の基礎にある経験(実践)」、「世界の解釈と世界の改造(実践ということの
範囲)」、「マルクス・レ−ニン主義の適否」と進める。
認識の基礎にある経験(実践)
「全ての真の知識は、直接的経験にその源を発している。もっとも、人は全てを直接に経験することは
できない。(中略)一個人の知識は、直接に経験された部分と間接に経験された部分という二つの部分から
できていて、(中略)あらゆる知識の源泉は、人間の肉体の感覚器官による、客観的な外界の感覚にある
(16頁)」。
認識は、その基礎に、経験を持つ必要がある。他方、いったん得られた認識は、実践で検証することで、
修正されたり、確認されたりする。
「理論的なものが、客観的真理に一致しているかどうかという問題は、前に述べた感性から理性への認識
の運動のうちでは、(中略)解決できるものではない(22−23頁)。(中略)理性的な認識を再び社会的
実践の中に返し、理論を実践に応用して、それが予想した目的を達成することができるかどうかを見るより
他はない。(中略)人類の認識の歴史は、多くの理論が完全には真理ではなく、その不完全さが実践の点検
を通じて改められた(中略)。多くの理論は誤っており、その誤りは実践の点検を通じて訂正される
(23頁)」。
世界の解釈と世界の改造
さて、認識の方法として、「経験→認識(感性的、理性的)→実践→認識の確認・修正」という循環は、
前述のとおりだが、「知る」ということのあり方という視点から見ても、《知ることは実践すること》でも
ある。
「非常に重要だと考える問題は、客観的世界の法則性を理解することによって、世界を解釈できるという
ことではなく、客観的法則性の認識を用いて、能動的に世界を改造することである(22頁)」。
「認識は実践から始まり、実践を経て理論的認識に達したら、再び実践に返って行かなければならない
(22頁)」。「客観的世界を改造するとともに、又自己の主観的世界をも改造し−自己の認識能力をも改造
し−主観的世界と客観的世界との関係を改善することである(27頁)」。
<実践ということの範囲>
まず、 実践を狭く「活動家が行うこと」とすると、多くの人は前述の様な認識活動の埒外になって
しまう。又ぼくは、今、活動家ではなく、元活動家だから、ぼく自身の居場所も用意しないといけない。
そこで、以下、「実践ということの範囲」を、少し広くする確認をしよう。
第1に、本書の中で、毛沢東自身が広く設定している。
第2に、もう少し、《世界の改造》と上記の社会的生活がどう係わるか、という視点で確認すると。
例えば、現在、公共水域(海、川、湖沼)を汚染する汚濁物質を最も多く排出するのは、生活排水である。
昔は、工場排水に問題があったが、排水規制が行き渡り、汚染源としての割合は低下した。今、「海や川を
きれいにしよう(=世界の改造)」とすれば、野菜屑や古い食用油を流し台に捨てたりせず、洗濯に合成
洗剤(閉鎖水域を富栄養化し赤潮の原因になるリンを含む)でなく粉又は液体石鹸を使うことが必要だ。
特にリンは、下水処理場で取り除けない。
このように、「実践ということの範囲」を広く確認すれば、前述の様な認識活動の仕組みは、活動家に
限らず、多くの人の社会的生活に共通だと言い得る。
マルクス・レ−ニン主義の適否
さて、ここまで認識について書いてきたが、題材に取り上げた毛沢東「実践論」が、マルクス・レ−ニン
主義の立場を明確にしているので、最後に、マルクス・レ−ニン主義の適否について触れることにする。
第1に、この文庫本の冒頭に、「中共中央毛沢東選集出版委員会」が書いているのは、「教条主義的な
同志が、(中略)中国革命の経験から学ぶことを拒み、(中略)マルクス主義の書物の中の断片的な言葉を
鵜呑みにし(8頁)」たということだ。
前述のとおり、「認識は、その基礎に、経験を持つ必要があり、他方、いったん得られた認識は、実践で
検証することで、修正されたり、確認されたりする」。即ち、認識の方法として「経験→認識(感性的、
理性的)→実践→認識の確認・修正」という循環があるということだ。社会に関する理論的認識(=理性的
認識)は、「その時代、その地域」という限定的条件で有効であり、何十年前、何百年前の書物の文言を
そのまま現実の戦略戦術にするということは当初から想定していないというべきだ。《自ら考える》という
ことだ。
又、「客観的に存在する世界の変化の運動は、永遠に終わることがなく、(中略)マルクス・レ−ニン
主義は、けっして真理に結末をつけるものではなく、実践のうちで絶えず真理を認識する道を切り開く
(27頁)」と言っている。だとすれば、時代の進行とともに次々と考え方を付加するから、(時代、地域の
制約を受ける)個人の名前を冠する○○主義でなく、(空想的社会主義と区別して)科学的社会主義が、
より適切な呼称だろう。
第2に、これまで見てきた認識の仕組みの視点から、「マルクス・レ−ニン主義が真理だと言われるのも、
(中略)その後の革命的階級闘争と民族闘争の実践によって実証されたときにおいてである(23頁)」
とすれば、現在(1998年)から見てどうか。
《プロレタリア独裁(暴力革命)は、目的ではなく手段であり、かつ特定の時代、地域でのみ有効》で、
《計画経済は、集団としての人間の本能に反し、市場経済の方が有効》で、《社会的公正の確保には規制の
活用や所得の再分配で済む》し、《普通選挙、共和制・民主制・代議制は、大きな誤りを防ぐ人間の知恵》
である。だから、共産主義は科学的社会主義として、限りなく社会民主主義に歩み寄るだろう。
その中で、ひとつの見方をすると、あれは教育闘争だった。知ることが、経験から切り離され、
その当然の帰結として、実践から切り離されていた。書物からしか知るすべを知らない。
つまり、自分の頭で考え抜くことを知らない、事実が自分の固定観念を打ち砕く経験を持たないできた。
認識方法の欠陥。
学校教育の欠陥。学校教育の腐敗。
知ること。又、知ることは実践することでもある。
1970年大学闘争の敗北の結果、敗北した世代が限界を克服しないまま、教諭として教室に立っている。
認識の欠陥は、歴史の帯の中で増幅している。
まず、ここでの取り上げ方から始めよう。
ここでは、認識について書くので、マルクス・レ−ニン主義の適否、または賛否は、後に補足的に触れる
ことにして、とりあえず横に置いておく。
それでは、本題に入ろう。
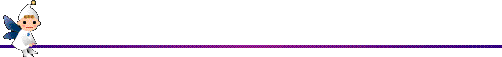
「理性的なものが信頼できるのは、それが感性に由来するからである。(中略)認識の感性的
段階は、さらに理性的段階に発展(20頁)」する。
「小さな認識過程についてもそのとおりであり、大きな認識過程についてもそのとおりである(21頁)」。
 アンダ−グラウンド気分を変えて
アンダ−グラウンド気分を変えて

マルクス主義は、このことを明確に意識し、又明確に主張・実行したが、マルクス主義への賛否に係わら
ず、生きるときの自分と世界の係わり方として、やはり重要だとぼくは考える。

「社会的実践は、生産活動(中略)、階級闘争、政治生活、科学活動、芸術活動などがあり(中略)、
社会的人間は社会の実際生活のあらゆる領域に参加している(9頁)」。だから、敢えて《世の中から断絶
した生活》を志向しない限り、誰でも何らかの社会的生活(=社会的実践)を行っているということになる。
 ここも見てね〔短歌連作〕1992/リサイクル
ここも見てね〔短歌連作〕1992/リサイクル
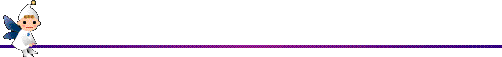
1990年に「ドイツ民主主義共和国(東ドイツ)」、1991年に「ソビエト連邦」が崩壊した。「中華人民
共和国」は1997年に香港返還を実現し、「ベトナム民主共和国(北ベトナム)」は1975年に「ベトナム共和
国(南ベトナム)」を崩壊させ、「キュ−バ」は経済的に苦境で、「朝鮮民主主義人民共和国」の個人崇拝
はどう見てもおかしく、ただし、ひと頃好況だった「大韓民国」も不況の只中にある。他方、西欧の社会
民主主義は、一定の成果を上げている。
 ここも見てね〔夢幻〕○○主義、イズムと個人史
ここも見てね〔夢幻〕○○主義、イズムと個人史
 ここも見てね〔夢幻〕市場経済の選択
ここも見てね〔夢幻〕市場経済の選択
 ここも見てね〔夢幻〕歴史における個人の役割(準備中)
ここも見てね〔夢幻〕歴史における個人の役割(準備中)

 ホームに戻る
ホームに戻る
 夢幻はじめに
・夢幻
・随想
・短歌連作
・音楽
・市民運動リスト・リンク集
・その他リンク集
・引用
・メール・マガジン
・ブログ掲示板
・ソーシャルネットワーク
夢幻はじめに
・夢幻
・随想
・短歌連作
・音楽
・市民運動リスト・リンク集
・その他リンク集
・引用
・メール・マガジン
・ブログ掲示板
・ソーシャルネットワーク