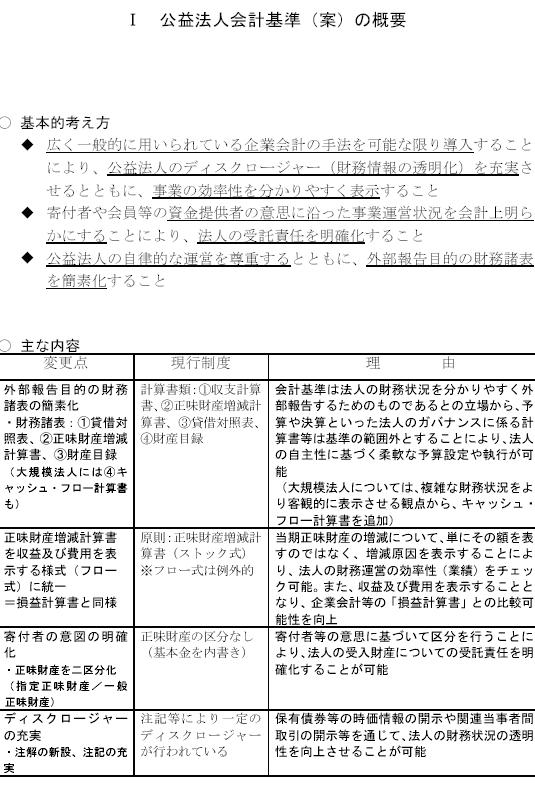�z�[���y�[�W�֖߂�
���v�@�l�̑����͍��Ɠs���{���̏��Ǖ������킹��Ɩ�Q���W��ɋy�ԁB�ŋ߂ł́A���c�@�l�u�P�[�G�X�f�B�[������ƌo�c�ҕ������ƒc�v�i�j�r�c�j�ɂ�鐭�E�H�쎖�����_�@�ɁA�����̎g�r�Ȃǂ̓�������O�ꂷ��K�v������Ɣ��f���Ă���A�����Ȃ͍������ǂ�����v�@�l�ɂQ�O�O�P�N�x����A�č��@�l����F��v�m�A�ŗ��m�Ȃǂɂ��O���č����`������B
�܂��A���{�͎�v�e�[�}�Ɍ��v�@�l�̌��������f���A�Ɩ��̌��Ȃ����ɒ��肷����j�i���{�o�ϐV���Q�O�O�O�P�N�Q���P���j�B
�����{�̌��\�����u���v�@�l�Ɋւ���N�����v�ɂ��A�����W�N�V���A���{�ɒ�o���ꂽ�^�}�s�����v�v���W�F�N�g�`�[���́u���v�@�l�̉^�c���Ɋւ���v�܂��A��
�v�@�l�ɑ���w���ē̈�w�̓K�����A���v�@�l�ɂ��s����s�I�s�ׂ̓������������͂ɐi�߂邽�߁A�����W�N
�V���P�U���A�u���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c�v�̐����J�Â��t�c�������������ƂƂ��ɁA���N�X��
�Q�O���ɁA�u���v�@�l�̐ݗ����y�юw���ē�v�y�сu���v�@�l�ɑ��錟�����̈ϑ����Ɋւ����v���t�c
���肳�ꂽ�B �@�܂��A���N�P�Q���P�X���ɂ́A�w���ē�̉^�p�ɓ������Ă̋�̓I�A����I�Ȏw�j�Ƃ��āA�u���v�@�l�̐ݗ��� �y�юw���ē�̉^�p�w�j�v���\�����킳�ꂽ�i�W�t����c������\�����j�B
�@����ɁA�������X�N�P�Q���P�U���ɂ́A�w���ē�����̊t�c���肪�s���A���v�@�l�́u�������ہv�u������
�L�v�u�����J�v�Ɋւ����̓I�����߂�ꂽ�B
�w���ē�̊t�c������āA�����W�N�P�O���A�c���@�l�ւ̓]���Ɋւ�������������邽�߁A�@���Ȗ�����
������Â���u�@�l���x������v�i�����F����p��喼�_�����j���������A�����P�O�N�R���A�u�@�l���x��������v�����܂Ƃ߂Č��\ �����B �@
���̕��ł́A���v�@�l�̉��U�i���U��̐��Z�̌����ɂ��@�l�͏��ł���B�j�ƁA���v�@�l����c���@�l���ւ̎�
�Ƃ̈ړ]�i���Ə��n���͌����o���j�Ƃ�g�ݍ��킹����@���ɂ��A���s�@���x�̉��ɂ����Ă��A���v�@�l����c���@�l���ւ̓]���́A��{�I�ɉ\�ł���Ƃ��Ă���B
�O�L�����āA�����P�O�N�P�Q���S���̊W�t����c������ɂ����āA�c���@�l���ւ̓]���̎菇�A�]����
�̑Ή��荞�u���v�@�l�̉c���@�l���ւ̓]���Ɋւ���w�j�v��\�����킹���B
�@�Ȃ��A�w���ē�̉^�p�w�j�ɂ��āA�c���]���w�j�̐\�����ɕ����ď��v�̉������s�����B
�����}�͌��v�@�l���v��i�߂Ă���A���v�@�l�̂�������������A�����c���@�l�iNPO�@�l�j�Ȃǂƈ�{�������u��c���@�l�v�ƈʒu�Â���@�Ă��܂Ƃ߂���j�B�V�@�ł́A�ݗ���F���Ƃ��喱�����̌������ɂߐݗ���e�Ղɂ��锽�ʁA���J���Ɋւ��鎖��I�ȋK�����������āA�Ő��D���[�u����@�l���p���I�ɐR�����ł���d�g�݂𐮂���i���{�o�ϐV���O�P�N�X���Q���j�B
����14�N8��2���A���t���[�s�����v���i�����Ǎs���ϑ��^���v�@�l�����v���i���́A�u���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɍ����āi�_�_�����j�v�����\�����B�u���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɍ�������g�݂ɂ����v�@�Q��
����́A����14�N3��29���̉��L�̊t�c����ɉ����ēZ�߂�ꂽ���̂ł���B
1. �@�ŋ߂̎Љ�E�o�Ϗ�̐i�W�܂��A���Ԕ�c���������Љ�E�o�σV�X�e���̒��ŐϋɓI�Ɉʒu�t����ƂƂ��ɁA���v�@�l�i���@��R�S���̋K��ɂ��ݗ����ꂽ�@�l�j�ɂ��Ďw�E����鏔���ɓK�ɑΏ�����ϓ_����A���v�@�l���x�ɂ��āA�֘A���x�i�m�o�n�A���Ԗ@�l�A���v�M���A�Ő����j���܂ߔ��{�I���̌n�I�Ȍ��������s���B
2. �@��L�������ɓ������ẮA���t���[�𒆐S�Ƃ������i�̐������A�W�{�ȋy�і��ԗL���҂̋��͂̉��A�����P�S�N�x����ړr�Ɂu���v�@�l���x�����v��j�i���́j�v�����肵�A���v�̊�{�I�g�g�݁A�X�P�W���[�����𖾂炩�ɂ���B�܂��A�����P�V�N�x���܂ł�ړr�ɁA��������{���邽�߂̖@����̑[�u���̑��̕K�v�ȑ[�u���u����B
���v�@�l���������A���݂̂m�o�n�@�W�I�ɉ������A���ĂƓ��l�̔�c���@�l���x���m�����悤�Ƃ�����̂ł���B
�Q�O�O�S�N�P�P���P�X���A���{�����v�@�l���x���v�Ɋւ���L���҉�c�́A���݂̌��v�@�l�i�Вc�A���c�j��p�~���āA�o�L�����Őݗ��ł���u��c���@�l�v�Ɉߑւ����邱�ƂȂǂ荞�ŏI�����܂Ƃ߂��B��c���@�l�ԗL���҂ō\�������ψ���u���v���̂���@�l�v�Ɓu��ʓI�Ȗ@�l�v�ɐU�蕪���A���v���̂�����̂ɂ͐Ő���̗D���[�u��F�߂�Ƃ������́B
���v�@�l���x���v�Ɋւ���L���҉�c���i�o�c�e�j
�i��
���j��c���@�l���x�̑n�݂Ɋւ��鎎���i�o�c�e�j
| ���s���v�@�l |
|
�V���Ȕ�c���@�l���x |
�i���c�@�l�A�Вc�@�l�j
��Q�U�O�O�O�@�l |
�� |
���v����L�����c���@�l |
| �� |
��ʓI�Ȕ�c���@�l |
���Ԗ@�l
�i�ƊE�c�́A������Ȃǁj
��P�Q�O�O�@�l |
�� |
|
|
����̉��v�̑ΏۊO
�ƂȂ��c���@�l |
�����c�������@�l�i�m�o�n�@�l�j
��P�X�O�O�O |
�w�Z�@�l�A�Љ���@�l
�@���@�l�A�E�E�E�E |
�S���ɖ�Q�U,�O�O�O������v�@�l�́A�����̓V�����ɂȂ�Ȃǂ̔ᔻ���������B���{�́A�P�Q���̊t�c����B�ł̗D���[�u���l�߂āA�Q�O�O�U�N�̒ʏ퍑��ɖ��@�����Ă��c���@�l�̑n�݂Ɋւ���@�Ă��o������j�B
�����c�������@�l�i�m�o�n�@�l�j�����v�Ɋ܂߂邱�Ƃ������������u���������v�Ƃ̂��Ƃō���͌����邱�ƂƂȂ����B�ƊE�c�̂⓯����Ȃǂ̒��Ԗ@�l�́u��ʓI�Ȕ�c���@�l�v�Ɉڍs�����p�~�����B�u��c���@�l�v�̐ݗ���o�L�����ōς܂��̂́A�����ɂ�錻�s���x�ł͎�NJ����̍ٗʂ������₷�����߁B�ݗ���e�Ղɂ������ɁA���v�@�l���ꌳ�I�ɏ��ǂ���t���̉��ɐݒu���閯�ԗL���҂̈ψ���(���t�{�E���v�F�蓙�ψ����E2007�N4��1������)�����v�����`�F�b�N����B��̓I�ɂ́A�@���v���Ƃ̋K�͂��@�l�̉ߔ����߂�A�A�c����Ƃ̎��Ƃ�j�Q���Ȃ��A�B���v�͌����Ƃ��Č��v���ƂɎg���A�Ȃǂ����f��ƂȂ�Ƃ��Ă���B�@���v�@�l�̉��v�ɂ����E�E�s�����v
���Ԕ�c������̊����̌��S�Ȕ��W�𑣐i���A���s�̌��v�@�l���x�Ɍ�����l�X�Ȗ��ɑΉ����邽�߁A�]���̎喱�����ɂ����v�@�l�̐ݗ������x�����߁A�o�L�݂̂Ŗ@�l���ݗ��ł��鐧�x��n�݂���ƂƂ��ɁA���̂����̌��v�ړI���Ƃ��s�����Ƃ��傽��ړI�Ƃ���@�l�ɂ��ẮA���ԗL���҂ɂ��ψ���̈ӌ��Ɋ�Â����v�@�l�ɔF�肷�鐧�x��n�݂��܂���
�B
�V���x�́A�����Q�O�N(2008�N)�x���Ɏ{�s����\��ł��B�܂��A�{�s������T�N�Ԃ́u�ڍs���ԁv�Ƃ���A���s�̌��v�@�l�́A���̊��ԓ��ɕK�v�Ȏ葱�����s���A�V���x�Ɉڍs���邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�{���i����20�N12��1���i���j�j�A���v�Вc�@�l�y�ь��v���c�@�l�̔F�蓙�Ɋւ���@���i�����\���N�@����l�\�㍆�j�y�ш�ʎВc�@�l�y�ш�ʍ��c�@�l�Ɋւ���@���y�ь��v�Вc�@�l�y�ь��v���c�@�l�̔F�蓙�Ɋւ���@���̎{�s�ɔ����W�@���̐������Ɋւ���@���i�����\���N�@����\���j���S�ʎ{�s����A�V���Ȍ��v�@�l���x���n�܂�܂����B
�@����܂ł̌��v�@�l�i�Вc�@�l���͍��c�@�l�j�́A�{���������āA�@������ᖯ�@�@�l�i����Вc�@�l���͓�����c�@�l�j�ƂȂ�܂��B�V���x�ւ̈ڍs�ɂ́A�{�����5�N�ԁi����20�N12��1���`����25�N11��30���j�̈ڍs�������݂����Ă���A���̊ԂɐV���x�ւ̈ڍs�葱���s�Ȃ��K�v������܂��B�葱���s�Ȃ킸��5�N�Ԃ��o�߂����ꍇ�A���U�����Ƃ݂Ȃ���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����ӊ肢�܂��B
�@�V���x�ւ̂����������͂�낵�����肢���܂��B
���v�@�l���x���v�i�@���@�l�A�w�Z�@�l�A�Љ���@�l�A�m�o�n�@�l�������j
110�N�Ԃ�̌��v�@�l���x�̉��v�`���v�@�l���x���v�֘A�R�@�ā`�@written by ���t�ψ�������v�ۓc���u���@��蔲��
���v�@�l�́A���Ԕ�c���@�l�̑�\�i�ł��邪�A���v�@�l���x�͐��x�J�n�ȗ��A���{�I�ȉ������Ȃ��܂ܗ������߁A����̗v���ɉ������V�������x�̍\�z���K�v�Ƃ���A����i2006�N3���j�A��ʎВc�@�l�y�ш�ʍ��c�@�l�Ɋւ���@����(�t�@��71���A�ȉ��u��ʎВc�E���c�@�l�@�āv�Ƃ����B)�A���v�Вc�@�l�y�ь��v���c�@�l�̔F�蓙�Ɋւ���@����(�t�@��72���A�ȉ��u���v�@�l�F��@�āv�Ƃ����B)�A��ʎВc�@�l�y�ш�ʍ��c�@�l�Ɋւ���@���y�ь��v�Вc�@�l�y�ь��v���c�@�l�̔F�蓙�Ɋւ���@���̎{�s�ɔ����W�@���̐������Ɋւ���@����(�t�@��73���A�ȉ��u�����@�āv�Ƃ����B)�̂R�@�Ă��A����ɒ�o���ꂽ�B
�{�e�ł́A�R�@���Ă̒�o�̌o�܁A���e�ɂ��ĊT�ς��A����̉ۑ�ɂ��Č�����B
�P�D���v�@�l���x���v�֘A�R�@���Ē�o�̌o��
���s�̌��v�@�l���x�́A����29�N(1896)�̖��@����ȗ��A110�N�ԁA�s���▯�ԉc������ł͖��������Ƃ̂ł��Ȃ��Љ�̎��v�ɑΉ����鑽�l�ȃT�[�r�X���_��@���I�ɒ���A���Ԕ�c���@�l���x�̒��j�Ƃ��đ������Ă����B����16�N10���P�����_�ŁA�Q��5,541�@�l�i�Вc�@�l�P��2,749�A���c�@�l�P��2,792�j�����v�@�l�Ƃ��Ċ������Ă���B
���̂悤�ɁA���v�@�l�͍��������ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邪�A���̈���A�喱�����̋���`�̉��A�ٗʂ̕����傫���ݗ����ȕւłȂ��A���ƕ��얈�̎喱�����ɂ��w���ē��c����ŔώG�A���J�����s�\���A���v���̔��f����s���m�A���v�������������v�@�l��������������A�Ƃ�������肪�w�E����Ă���B�܂��A���v�@�l�ɑ���Ő���̗D���[�u��s���̈ϑ��A���v�@�l���⏕����V����̎M�ɂȂ��Ă��铙�ɂ���
�̗l�X�Ȏw�E��ᔻ���s���Ă����B
���̂悤�Ȏw�E��ᔻ���A���{�́A�����V�N�R���Ɂu���v�@�l�̐ݗ����ɂ��āv���A�����W�N�X���Ɂu���v�@�l�̐ݗ����y�юw���ē�v�y�сu���v�@�l�ɑ��錟�����̈ϑ����Ɋւ����v�����ꂼ��t�c���肵�āA���v�@�l�ɑ���s����̊ē�������������ɐi�B�����āA����12�N12���Ɋt�c���肳�ꂽ�u�s�����v��j�v�ł́A���v�@�l�̒��ł��s���ϑ��^���v�@�l���܂����v�̑ΏۂƂ����B
�������A����13�N�P���ɊJ�n���ꂽ�����ǂ̌��v�@�l�̑��_���������N�S���́u�s���ϑ��^���v�@�l�����v�̎��_�Ɖۑ�i�s�����v���i�����ǁj�ł́u���{�I�Ȍ��v�@�v�A�l���x���v�Ɍ�������{�I�����������ׂ�������i�߂�v�Ƃ��A�s���ϑ��^���v�@�l�ɂƂǂ܂炸�A���v�@�l���x�S�̂̌��������s���ƂȂ����B
���̌�A����14�N�R���Ɂu���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɍ�������g�݂ɂ��āv���t�c���肳��Č��v�@�l���x�̔��{�I�E�̌n�I�Ȍ����������肳��A����15�N�U���ɂ͌��v�@�l���x�̔��{�I���v�̊�{�I�g�g�݂�X�P�W���[�����𖾂炩�ɂ����u���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɋւ����{���j�v���t�c���肳�ꂽ�B
���̊�{���j�ł́A(1)���v���̗L���ɂ�����炸������`�i�o�L�j�ɂ��ȕւɐݗ��ł����ʓI�Ȕ�c���@�l���x��n�݂��邱�ƁA(2)���v����L����ꍇ�̗D���[�u�݂̍���ɂ��ẮA���ʖ@�Ɋ�Â��@�l���x���܂߂��S�̂̑̌n�̐������ɗ��ӂ��Ȃ���A���v���̋q�ϓI�Ŗ��m�Ȕ��f��̖@�艻��Ɨ��������f��݂̂̍�������܂ߌ������邱�Ɠ��̉��v�̊�{�I�ȕ��j��������A����17�N�x���܂łɖ@����̑[�u�����u���邱��
��ڎw�����ƂƂ��ꂽ�B�����āA���v�@�l���x���v�ɂ��Ă̋�̓I�Ȓ�Ă��s�����߁A�s�����v�S����b�̉��Ɂu���v�@�l���x���v�Ɋւ���L���҉�c�v���ݒu����A����c�́A����16�N11���Ɂu���v�����܂Ƃ߂��B��������Ɍ��v�@�l���x���v�֘A�R�@�Ă͗��Ă���A����18�N�R��10���ɍ���ɒ�o���ꂽ�B
�Q�D��ʎВc�E���c�@�l�@�Ă̊T�v�i������`�ɂ���ʔ�c���@�l�̐ݗ��j
���s�̌��v�@�l���x�́A�@�l�̐ݗ��Ƃ��̖@�l�̌��v���̔��f�̓Z�b�g�ɂȂ��Ă���B
����̌��v�@�l���x���v�ł́A��������߂āA��c���@�l�̐ݗ����̂́A���ؐl�ɂ��芼�̔F���ēo�L����A��ʎВc�@�l���͈�ʍ��c�@�l�Ƃ��Đ������邱�ƂƂ��A�ŗD�������u���v�@�l�v�Ƃ��Ă̔F��́A���v�@�l�F��@�̎葱�ōs�����ƂƂ����B
��ʎВc�@�l�́A�Ј��ɂȂ낤�Ƃ���҂��������Ė@��̋L�ڎ��R�荞�芼���쐬���Č��ؐl�̔F���A���̎傽�鎖�����̏��ݒn�ɂ����Đݗ��o�L�����邱�ƂŐ�������B�@�l�̉^�c�̂��߁A�Ј�����őI�o���ꂽ�������̋@�ւ��u�����B�Ȃ��A�Вc�̍��҂ɑ���Ј��̐ӔC�͗L���ӔC�ł���B�@�l�̎��Y�Ƃ��Ă͊���̐��x�����邪�A���s�̗L���ӔC���Ԗ@�l�ƈقȂ����̐ݒu�͋`���t�����Ă��Ȃ��B
��ʍ��c�@�l�́A�ݗ��҂��@��̋L�ڎ��R�荞�芼���쐬���i�⌾�ɂ��쐬���A���A300���~�ȏ�̍��Y�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�l�́A�芼�����ؐl�́j�F���A���̎傽�鎖�����̏��ݒn�ɂ����Đݗ��o�L�����邱�ƂŐ�������B�@�l�̉^�c�͐ݗ��҂����̔C�����@���߂��]�c���Ƃ���ɑI�C���ꂽ�@�ւɂ��Ȃ����B
��ʎВc�@�l�y�ш�ʍ��c�@�l�i���̂��āu��ʎВc�E���c�@�l�v�Ƃ����j�́A�@��B
�̉��U���R�ʼn��U����ق��A�����ԓo�L�̂Ȃ��x���@�l�͉��U�������̂Ƃ݂Ȃ����B
�R�D���v�@�l�F��@�Ă̊T�v
�V�������v�@�l���x�ł́A��ʎВc�E���c�@�l�̒��Ō��v���Ƃ��s���ɂӂ��킵���@�l�ɂ��Č��v�F����s���A�ŗD���������邱�ƂƂ����B
���v�F�������@�l�́A���v�ړI���Ɓi�w�p�A�Z�|�A���P���̑��̌��v�Ɋւ���23��ނ̎��Ƃł����āA�s���肩�����̎҂̗��v�̑��i�Ɋ�^������́j���s���@�l�ł���B���v�F��́A�Q�ȏ�̓s���{���̋����Ɏ�������ݒu����@�l�A�Q�ȏ�̓s���{���̋����Ō��v�ړI���Ƃ��s���@�l�y�э��̎����E���ƂƖ��ڂȊ֘A��L������v�ړI���Ƃ��s���@�l�A�ɂ��Ă͓��t������b���A����ȊO�͎傽�鎖�����̏��ݒn�̓s���{�������ꂼ��s���i�ȉ��A�F���̂�����t������b�Ɠs���{�����u�s�����v�Ƃ����B�j
���v�F��ɂ����ẮA�\���@�l�����v�ړI���Ƃ��s�����Ƃ���ړI�Ƃ��邱�ƁA�K�v�Ȍo���I��b�y�ыZ�p�I�\�͂�L���邱�ƁA���v�@�l�̎Љ�I�M�p���ێ������łӂ��킵���Ȃ����̂��s��Ȃ����ƁA���v�ړI���ƂɌW����������̎��{�ɗv����K���Ȕ�p�������z���Ȃ��ƌ����܂�邱�Ɠ��̊�ɓK�����A�\�͒c�ɊW���铙�̌��i���R�ɓ�����Ȃ���A�s�����́A���Y�@�l�ɂ��Č��v�F���������̂Ƃ����B
�Ȃ��A���v�F��ɓ������Ă̑��̊����̊֗^�́A�@�l�����Ƃ��s���ɓ�����@�ߏ�s���@�ւ̋��F����K�v�Ƃ���ꍇ�ɋ��F��^����s���@�ւ���ӌ����悷�邱�ƂɌ����A���s�̎喱�������x�ɂ����鎩�R�ٗʂɂ��F�̂悤�Ȋ֗^�`�Ԃ͂Ȃ��Ȃ�B
���v�F�肳�ꂽ�@�l�́A���v�Вc�@�l���͌��v���c�@�l�̖��̂Ō��v�@�l�Ƃ��Ă̎��Ƃ��s�����A���v�ړI���ƂɌW����������̎��{�ɗv����K���Ȕ�p�������z���Ȃ����ƁA���v�ړI���Ɣ䗦��100����50�ȏ�ƂȂ邱�ƁA�V�x���Y�̊z�����z���Ȃ����Ƌy�ъ̕�W�Ɋւ��Ĉ��̍s�ׂ����Ȃ����ƂȂǂ��`���t������B�܂��A���v�@�l�́A���v���Ɠ����Ƃɋ敪�o�����A�������ւ̕�V���̎x��������\����ق��A�����ƔN�x���Ƃ̍��Y�ژ^�̔��u���E�{���A�s�����ւ̒�o���̋`�����ȂǁA�L���s���E�����ւ̐����ӔC�����߂��Ă���B
�s�����́A���v�@�l�̎��Ƃ̓K���ȉ^�c���m�ۂ��邽�߂ɕK�v�Ȍ��x�ɂ����āA���v�@�l�ɑ��ĕ����߁A�����̗��R�̂���ꍇ�͊������s���A�@��̎��R�ɊY������ꍇ�͌��v�F������������ƂƂȂ��Ă���B
���v�F��A�ē��ɂ��ẮA��O�ҋ@�ւ̖������d�v�ł��邪�A���t������b�ɌW����v�F��́A���t�{�ɐݒu��������v�F�蓙�ψ����i�ψ��V�l�ȓ��j��������b����̎���ɓ��\���Ŋ֗^����B�Ȃ��A�e�s���{���ɂ����v�F��ɌW�鍇�c���̋@�ւ��u������B
�S�D�����@�Ă̊T�v�i�����̌��v�@�l�̐V���x�ւ̈ڍs�j
���s�̌��v�@�l�ł���Вc�@�l�E���c�@�l�ŁA�{�@���{�s�̍ۂɑ��݂�����̂́A�{�s���Ȍ�́u����Вc�@�l�v���́u������c�@�l�i���̂��āu���ᖯ�@�@�l�v�Ƃ����B�j�Ƃ��āA��ʎВc�E���c�@�l�@�Ɋ�Â���ʎВc�E���c�@�l�Ɠ��������ƂȂ�B
���ᖯ�@�@�l�ŁA���v�@�l�F��@�ɋK�肷����v�ړI���Ƃ��s�����̂́A�@�{�s���i�@�̌��z������Q�N�U���ȓ��j����N�Z���ĂT�N�̊ԁi�ȉ��u�ڍs���ԁv�Ƃ����B�j�ɁA���v�@�l�F��@�ɂ��F��Ɠ��l�̎葱���o�āA���v�@�l�Ƃ��ēo�L���邱�Ƃ��ł���B
���ᖯ�@�@�l�̂����A���v�@�l�ł͂Ȃ���ʎВc�E���c�@�l�ւ̈ڍs����]����@�l�́A�s�����̔F���ēo�L�ɂ���ʎВc�@�l���͈�ʍ��c�@�l�ƂȂ邱�Ƃ��ł���B�������A�F�ɂ����ẮA���@��̌��v�@�l�Ƃ��Č`���������v�ړI�̂��߂̎��Y��{���̌��v�ړI�̂��߂Ɏx�o����u���v�ړI�x�o�v��v���쐬���A���ꂪ�K���A���m���Ɏ��{�������̂ƔF�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ڍs���ԓ��Ɍ��v�@�l�Ƃ��Ă̔F�薔�͈�ʎВc�E���c�@�l�Ƃ��Ă̔F���Ȃ��������ᖯ�@�@�l�́A�����Ƃ��āA�ڍs���Ԃ̖����̓��ɉ��U�������̂Ƃ݂Ȃ����B
�܂��A������̔���v�̔�c���@�l�ł��钆�Ԗ@�l����ʎВc�@�l�Ɉڍs�����B����17�N10�������݂Œ��Ԗ@�l��2,379�@�l�i�L���ӔC���Ԗ@�l��2,131�@�l�A�����ӔC���Ԗ@�l��248�@�l�j�ł��邪�A�L���ӔC���Ԗ@�l�́A��ʎВc�@�l�Ɉڍs���A�����ӔC���Ԗ@�l�́A���ҕی�̂��߂Ɂu���ᖳ���ӔC�@�l�v�̖��̂ň�ʎВc�@�l�Ɉڍs������A�@�{�s��P�N�ȓ��Ɉ�ʎВc�@�l�Ƃ��Ă̑g�D�`�Ԃɉ��߂Ȃ��Ɖ��U�������̂Ƃ݂Ȃ����B
�Ȃ��A���@�̂ق��A300�@���ɂ��ď��v�̉������s����B
�T.����̉ۑ�
����̌��v�@�l���x���v�́A�����́A180����@���Ɋ�Â��ʂ̔�c���@�l���x�̒ʑ��@�̐���Ɏ�����̂Ƃ��ڂ��ꂽ���A���ǁA����̖@�Ă͌��v�@�l���x�ƒ��Ԗ@�l���x�̓����ɂƂǂ܂����B�@���@�l�A�Љ���@�l�A�w�Z�@�l�A�����c�������@�l�i�m�o�n�j�Ȃǂ̔�c���@�l�́A���ꂼ��̗v���ɉ����č��ꂽ�����ł���A���x�ݗ��̌o�܂��l�X�ł��邱�Ƃ���A���x�̓������͍̂���ł��낤���A��c���@�l���x�S�̂̓������̊m�ۂ̊ϓ_����́A�@�I���ʊ�Ղ����݂��������ǂ��Ƃ̎w�E������B���v�F�蓙�ψ���͓��t�{�ɐݒu����邱�ƂƂȂ��Ă���A���t�{���m�o�n���x�ƐV���v�@�l���x�̗��������ǂ��邱�ƂɂȂ�A����A�����x�̗Z���ɐi�ޓ����͍������\���͂����B
�܂��A�V���x���ł̌��v�@�l�ɑ���Ő��ɂ��ẮA���v���Ɖېŕ����A�y���ŗ��E�݂Ȃ������x�A���邢�͊��D���Ő����ɂ��Č������Ȃ����ׂ��Ƃ���Ă��邪�A�Ő��ɂ��ẮA����̂R�@�Ă̒��ł͋�̓I�Ȏ蓖�͂Ȃ��ꂸ�A���N�ȍ~�ɖ@�������Ȃ���邱�ƂƂȂ�u�����疯�ցv�̗���̒��ŁA���I�����̎M�ƂȂ邱�Ƃ����߂��Ă�����v�@�l�ɑ���Ő��D�����̂ɂ͗]��٘_�͏o�Ă��Ȃ��悤�ł��邪�A�u��c�����v�@�l�ېł̐��x�_�͗��_�I�g�g�̌��@�䂦�ɍ������Ă���v�Ƃ̎w�E������A���v�@�l���ɑ���Ő������{�I�ȋc�_�Ȃ��Ɋ����̐��x�̉����Ƃ��č\�z���Ă��܂��ƁA�V���Ȕᔻ�������錜�O�����낤�B
�Ō�ɁA�����̖�Q���T��̌��v�@�l�̑命���͐V���Ȍ��v�@�l�ւ̈ڍs����]���Ă���Ƃ����B�ڍs���Ԃ͂T�N�Ȃ̂ŒP���v�Z�ŔN�ԂT��@�l�̔F�莖�����K�v�ƂȂ邪�A�F��\���͈ڍs���ԑO���ɏW������Ƃ��l������B�V���x���̌��v�@�l�́u�������v���m�ۂ���ϓ_������A�ڍs�ɂ̓X���[�X�Ȃ�������i�Ȏ葱�����߂��A�c��Ȏ����̒����Ȏ��{�̐��̍\�z�����z������@�{�s���܂ł̖�Q�N�U���Ԃ̋i�ق̉ۑ�ƂȂ낤�B
���v�@�l���x���v�̊T�v�i�p���t���b�g�j�@�Q��
���v�@�l�̉��v�ɂ����E�E�s�����v�F���t�{ �Q��
���v�@�l�Ƃ́A���@��R�S���Ɋ�Â��Đݗ�������Вc�@�l���͍��c�@�l�̂��Ƃł���A���̐ݗ��ɂ́A�@���v�Ɋւ��鎖�Ƃ��s�����ƁA�A�c����ړI�Ƃ��Ȃ����ƁA�B�喱�����̋��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�Вc�@�l�ƍ��c�@�l
�Вc�@�l�́A���̖ړI�̂��ƂɌ��������l�̏W���̂ł����āA�c�̂Ƃ��đg�D�A�ӎv���������A�Ј��ƕʌ̎Љ�I
���݂Ƃ��Ēc�̖̂��ɂ����čs������c�̂ł���A���c�@�l�́A���̖ړI�̂��Ƃɋ��o����A��������Ă�����Y�̏W
�܂�ł����āA���v��ړI�Ƃ��ĊǗ��^�c�����c�̂ł���B
�Вc�@�l�ɂ��ẮA�Ј��̌��R�����U���R�Ƃ���Ă���i���@��U�W���Q����Q���j�ق��́A�Ј����Ɋւ���v���͒�߂��Ă��Ȃ��B�Ȃ��A���c�@�l�ɂ��ẮA���x��A�Ј��͑��݂��Ȃ��B
�i1�j���@�ȊO�̓��ʖ@�Ɋ�Â��Đݗ��������v��ړI�Ƃ���@�l�̂��Ƃ��L�`�̌��v�@�l�Ƃ����A�w�Z�@�l�i�����w�Z �@�j�A�Љ���@�l�i�Љ���@�j�A�@���@�l�i�@���@�l�@�j�A��Ö@�l�i��Ö@�j�A�X���ی�@�l�i�X���ی쎖�Ɩ@�j�A�����c�������@�l(�����c���������i�@)��������B
�i2�j���v���c�����ړI�Ƃ��Ȃ����ԓI�Ȓc�̂́A���ʖ@�̋K�肪����ꍇ�Ɍ���@�l�i���擾���邱�Ƃ��ł���B�����
�́A��ʓI�����Ԗ@�l�ƌĂ�Ă���A�J���g���i�J���g���@�j�A�M�p���Ɂi�M�p���ɖ@�j�A�����g���i�e��̋����g���@�j�A���ϑg���i�e��̋��ϑg���@�j��������B
�i3�j����@�l�́A�u�@���ɂ�蒼�ڂɐݗ������@�l���͓��ʂ̖@���ɂ����ʂ̐ݗ��s�ׁi���{��������ݗ��ψ����s
���ݗ��Ɋւ���s�ׁj�������Đݗ����ׂ����̂Ƃ����@�l�v�̂��Ƃł���B
���v���c�����ړI�Ƃ��Ȃ����ԓI�Ȓc�̂́A���ʖ@�̋K�肪����ꍇ�Ɍ���@�l�i���擾���邱�Ƃ��ł���B�����
�́A��ʓI�ɒ��Ԗ@�l�ƌĂ�Ă���A�J���g���i�J���g���@�j�A�M�p���Ɂi�M�p���ɖ@�j�A�����g���i�e��̋����g���@�j�A���ϑg���i�e��̋��ϑg���@�j��������B
�������A������A�e�r�c�́A�ƊE�c�́A�ݏ���̔�c���A����v�ړI�̎Вc�ɂ��ẮA�ʂ̓��ʖ@���Ȃ��A���̖ړI��g�D�ɓK�����`�̖@�l�ƂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ɂ���B���̂悤�Ȓc�̂ɂ��Ă��@�l�i���擾���A���̖ړI��g�D�ɂӂ��킵���@�I�ȋK���ɕ����邱�ƂƂ���Ȃ�A�\��������l�E�@�l���c�̂̊����ɎQ�����A�܂��A�c�̊����̌��ʂɂ��l�X�ȗ��v�����邱�Ƃ��ł��A�����A����Ǝ���W�ɗ���O�҂̕ی���}���邱�ƂƂȂ�A���̎Љ�I�Ӌ`�͑傫���Ƃ��āA�@���Ȃ́u���Ԗ@�l�@���v�̓������������Ă���B
�����P�R�N�U���W���A�u���Ԗ@�l�@�v�́A�Q�c�@�{��c�Ő��������B�����P�S�N�i�Q�O�O�Q�N�j�S���P���Ɏ{�s����܂����B
�܂��A���v�@�l���v�ɔ����A������̔���v�̔�c���@�l�ł��钆�Ԗ@�l����ʎВc�@�l�Ɉڍs�����B����17�N10�������݂Œ��Ԗ@�l��2,379�@�l�i�L���ӔC���Ԗ@�l��2,131�@�l�A�����ӔC���Ԗ@�l��248�@�l�j�ł��邪�A�L���ӔC���Ԗ@�l�́A��ʎВc�@�l�Ɉڍs���A�����ӔC���Ԗ@�l�́A���ҕی�̂��߂Ɂu���ᖳ���ӔC�@�l�v�̖��̂ň�ʎВc�@�l�Ɉڍs������A�@�{�s��P�N�ȓ��Ɉ�ʎВc�@�l�Ƃ��Ă̑g�D�`�Ԃɉ��߂Ȃ��Ɖ��U�������̂Ƃ݂Ȃ����B
����@�l���ɂ��ẮA�Q�O�O�O�N�V���Q�V���t���Ō��\�����A�������̓���@�l�����J�����ψ���́u����@�l���̏����J���x�̐����[���Ɋւ���ӌ��v���ڂ����B�܂��A�ٌ�m�@�쑺�g���Y���̍쐬�����u����@�l�Ď��@�\�z�[���y�[�W�v���Q�Ƃ��������B
�u����@�l�̏����J�̐��x���Ɋւ��钲�������v�E�E����@�l�̒�`�A�ތ^�A�@���Ɋւ��钲�������Q��
�u���O���̓���@�l�Ή����x�v�E�E�A�����J�A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�̐��x�Q��
�X�֒����A�����N���A�����N���A�ȈՕی��ȂǍ�������̗a����i�����ɑ�����j�S�R�W���~�i�����P�P�N�x�̐��l�j�́A�呠�Ȃ̎����^�p���E���ʉ�v�����o�R���āA���ɁE���c�A���̑�����@�l�A�n�������c�̂Ȃǂɏo������ݕt���̖��ڂŎ���������Ă���B
�Q�O�O�P�N�S�������A�X�֒����A�����N���A�����N���A�ȈՕی��Ȃǂ͒��ڋ��Z�s��ʼn^�p���邱�ƂƂȂ�A���ɁE���c�A���̑�����@�l�͓Ǝ��ɍ����@�ւƂ��������@�֍������Z�s��Ŕ��s���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ����i�����P�R�N�x�͂Q�O�̋@�ւ��P���~�������s�j�B�s�������́A�����ȁE�����Z���������ʉ�v�������������Z�s��Ŕ��s���Ď������B���ē���@�l�ɗZ������i�]���ƕς�炸�j�B�����͍��̈��ŁA�����P�R�N�x�͖�S�S���~�s���A�X�������R�R���~�������Z�s��͂P�P���~�B
�����Ȃ́A�Q�O�O�O�N�R�����́A���ɁE���c�E�����Г��T�O�̓���@�l�i���ʉ�v���܂ށj�̍������e���u���A�N�Z�X�v�Ƃ��Č��\�����B�@�l���Ƃɉ�v�����̓��e���قȂ邪�����J�Ƃ��Ă͈���O�i�ƌ������Ƃ��B
���ЁE���c�A����@�l�A�F�@�l�̃��X�g
�X���E�N�����̍�������̗a���������@�l���̎����ɗ���^�p����Ă���B�Q�O�O�P�N�S��������Z�s����o�R����Ƃ͂����A���łɓ������ꂽ�o������ݕt���͂��̂܂c��A�������͐V���ȍ��̔��s�ƁA�����Œ��B���������͓���@�l�֗Z������邽�ߏ]���ƈقȂ�Ȃ��B����@�l����Q�̍��S�ƂȂ����Ƃ����獑���ւ̑S�z�ԍς͐ŋ����g�����ƂɂȂ낤�B�����Ȃ�Ȃ����߂ɁA����������邩�ǂ����͍����̖ڂɂ������Ă���B
| ����@�l�������������v�� |
�@����@�l�����v�ɂ��ẮA��N�P�Q���ɍ��肳�ꂽ�u�s�����v��j�v�y�ѐ�̒ʏ퍑��Ő��������u����@�l�����v��{�@�v�ɏ]���A��N�Ԃɂ킽�茩������Ƃ��i���Ă������A�����P�R�N�P�Q���P�W���ɓ���@�l�����v���i�{���i��T��j�E�s�����v���i�{���i��W��j�i��������{�����͑�����b�j������c���J�Â���A���̏�Łu����@�l�������������v��v�����肳�ꂽ�B
�@���P�X���Ɋt�c���肳�ꂽ���v��́A�P�U�R�̓���@�l�y�єF�@�l��ΏۂɁA���Ƌy�ёg�D�`�Ԃ̌��������e���ʂɒ�߂�ƂƂ��ɁA�e����@�l���ɋ��ʓI�Ɏ��g�ނׂ����v�����ɂ��Čf���Ă���B
�@����́A�{�v��ɏ]���A���e�̋�̉����}���邱�ƂƂȂ邪�A���������P�S�N�x���ɖ@����̑[�u���̑��K�v�ȑ[�u���u���A�����P�T�N�x�ɂ͋�̉���}�邱�ƂƂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�R�N�P�Q���P�W��
�s�����v���i������ |
�F�@�l�Ƃ́A�u���{�����ʂ̖@���Őݗ� �����@�l�v�ł������@�l�Ɠ����ł���B�@�l�ݗ��ɂ�����A�����ݗ��ψ���C�����Ă���Γ���@�l�A���Ԃ�����ݗ��ψ����I�o����Ă�����F�@�l�ƂȂ�B����@�l�͑������̐R���ΏۂɂȂ�A�F�@�l�͐R���Ώۂ���͂����B
�F�@�l�ꗗ�i��ǏȒ��ʁj(����10�N4��1������)�E�E������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���ʂ̖@���ɂ��ݗ�����閯�Ԗ@�l�i�ŐV�ł��u�����ȁ@�s���Ǘ��E�Ɨ��s���@�l�v���Q�Ɓj
���ׂĂ̓Ɨ��s���@�l�ƈ��̓���@�l�y�єF�@�l��ΏۂƂ���u�Ɨ��s���@�l���ۗ̕L������̌��J�Ɋւ���@���i�Ɨ��s���@�l���̏����J�@�Ƃ����j�v�A����13�N11��28���ɐ������A12��5���Ɍ��z����܂����B
�������Ȃ���A�F�@�l���͓Ɨ��s���@�l���̏����J�@�̑Ώۂ��珜����Ă��܂��B�Ɨ��s���@�l���̏����J�@�̑ΏۊO�@�l�i�����ȁj�Q�ƁE�E���F�̃}�[�J�[�̕t���Ă���@�l�������J�@�̑ΏۊO�Ƃ��Ă��܂��B
�F�@�l�̑����͌��������𑶗���Ղł���Ȃ�A�喱����������Ƃ��Ă��A���̌������f����͈̂�`�I�ɂ͍����ł��낤�B���̈Ӗ��ł͏��J���̂�����������ƌ������ׂ��ł͂Ȃ��ł��낤���B
�@�l�������Č��v�@�l�ƔF�@�l�Ȃǂ̋敪�͕s�\�B�č��ł́A���ׂĔ�c���g�D�iNot-for-profit
Organization�j�ɊY�����A��c���g�D�͐Ŗ@�Ō��߂��A���œ��ǂł���Γ����i�h�q�r�j���Ǘ����邱�ƂɂȂ��Ă���i�č��̔�c���g�D�i�m�o�n�j�Ő��Q�Ɓj�B
�Ⴆ�A���{�ł͔F�@�l�ɊY������ꍇ�ł����Ă��A�A�����J�ԏ\���ЁiAmerican Red Cross�j�̔N������A�č����F��v�m����i�`�h�b�o�`�j�̔N�����iAnnual Report�j�ɂ́A�������e�y�є�c���g�D�i�`�h�b�o�`�ɂ͉c���g�D�̎q��Ђ�����|�̋L�ڂ���j�Ƃ��Ă̘A���������\���O���Ɍ������Č��\���Ă��܂��B�܂��A�č���v���ݒ肵�Ă��������v��R�c��i�e�`�r�a�j�̕�̂ł���e�`�e�i������v���c�j�́A�f���E�G�A�B��ʉ�Ж@�Őݗ����Ŗ@501�i���j�i3�j�̔�c���g�D�Ƃ��Ď戵���Ă���B���J���́AFA�e�Q�O�O�R�N�x�N�����ŁA�����Ɖ�v�FAS No.117���u��c���g�D�̍������\�v�ɂ��������s���Ă��܂��B
���ۉ�v��ψ�����c�h�`�r�b�e�i���ۉ�v��R�c���h�`�r�a�̕�́j���Q�O�O�R�N�x�N�������Q�Ƃ��������B�č����l�̂��̂ƂȂ��Ă��܂��B
����A���{���i���j������v��@�\�i��Ɖ�v��ψ���i�`�r�a�j�̕���j���Q�O�O�Q�N�U���Ɍ��\�����u�Q�O�O�P�N�x���v�Z�����v�Ɣ�r���Ă݂�Ɖ�v�ɑ���F���̈Ⴂ����R�Ƃ��Ă��܂��B
�܂�A���{�̏ꍇ�́A���v�@�l�̉�v����Ȃ��������A��Ɖ�v��ψ���͋��Z�����ǂ̏،�����@�ɌW���v��̊J�����s���Ă��邽�߁A�i���j������v��@�\�i��Ɖ�v��ψ���i�`�r�a�j�̕���j����̍������͑����Ȃ̌��v�@�l��v��ɏ]���Ƃ������ۓI�ɂ͗���s�\�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂�c����s���̕��Q�ł��B����A���ẮA��c���g�D�̉�v��́A���Ԃ̉�v��ݒ��́i�e�`�r�a��h�`�r�a�j�����ԕ���̉�v��ꂵ�Đݒ肵�Ă��邱�Ƃɂ���܂��B
��Ȃ̂́A�������̊J���͖����ɒ�o���鏑�ނł͂Ȃ��A��ʎs���ւ̃f�B�X�N���W���[�i���J���j�ɂ��A��t���Ȃǂ̋��͎҂悤�Ɠw�͂���d�g�݂ɂ���܂��B
�č��̏ꍇ�i���ۉ�v������l�j�́A���͎ҁi��t���Ȃǂ̎����ҁj�𑝂₷���߂ɁA���g�̔�c���������e�̗����邽�߂ɕ�����₷�����J����K�v�Ƃ���C���Z���e�B�u�������Ă������哱��^�ł����A���{�̏ꍇ�́A�喱�����ɂ��F�E���ȂǂŐݗ�����A���A���J���͎喱�����ɑ��čs�������̖ڂ̓͂��Ȃ����哱�^�ŁA�Ⴆ�O���ɂ����J�������Ƃ��Ă��l���E���e���͌`���I�Ȗ����̕����Ŕ���ɂ����Ƃ�������������܂��B���哱�^�̎d�g�݂��\�z���Ȃ�����A���J���͉��P����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�Ȃ��A�����P�R�N�P�Q���P�W�� �s�����v���i�������́u����@�l�������������v��v�ɂ��A�F�@�l�ɂ��Ė��Ԗ@�l�Ƃ��铙�̌ʂɉ��v���邱�ƂƂȂ����B
�����c�������@�l�́C�����P�O�N�P�Q���Ɏ{�s���ꂽ�����c���������i�@�Ɋ�Â��Đݗ������@�l�ł���B��
���c�������@�l�́C���@�̕ʕ\�Ɍf����ꂽ�����ł����āC�s���肩�����̎҂̗��v�̑��i�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI
�Ƃ��銈�����s�����Ƃ��傽��ړI�Ƃ�����̂ł���i��Q���j���Ƃ���C���v��ړI�Ƃ���@�l�ɓ�����Ɖ������B
�@
�����c�������@�l�̐ݗ��́C���v�@�l�̂���Ƃ͈قȂ�C�喱�����̋���K�v�Ƃ����C�������i�����Ƃ��ēs��
�{���m���B�Q�ȏ�̓s���{���̋����Ɏ�������ݒu������̂ɂ����ẮC�o�ϊ�撡�����Ƃ����B�j�̔F���K�v
�Ƃ���Ă���i��P�O���P���j�B
�u�����c�������@�l�i�m�o�n�j�v�Q��
�N�x�ʖ@�l��
|
|
�������N |
�����T�N |
�����P�O�N |
| ������ |
�Вc |
3,317 |
3,557 |
3,691 |
| ���c |
2,967 |
3,242 |
3,178 |
| ���v |
6,284 |
6,799 |
6,869 |
| �s���{������ |
�Вc |
7,877 |
8,649 |
9,196 |
| ���c |
8,758 |
9,864 |
10,410 |
| ���v |
16,635 |
18,507 |
19,606 |
| ���v |
�Вc |
11,186 |
12,142 |
12,827 |
| ���c |
11,697 |
13,072 |
13,553 |
| ���v |
22,883 |
25,214 |
26,380 |
| ���Ɠs���{���Ƃ̋��ǖ@�l�����邽�߁A�����ǂƓs���{�����ǂƂ𑫂������͑S�̐��Ƃ͈�v���Ȃ��B |
| �e�N�P�O���P������ |
���i�ʖ@�l��
�����P�O�N�P�O���P������
|
�{����
���v�@�l |
�ݏ��E����
�c�̓� |
���̑� |
���v�@�l�� |
| ������ |
6,479 |
379 |
11 |
6,869 |
| �s���{������ |
16,656 |
2,519 |
431 |
19,606 |
| ���v |
23,042 |
2,896 |
442 |
26,380 |
���a�T�Q�N�R���A���v�@�l��v������肳��A���̌㌩�������s���āA���a�U�O�N�X���ɐV���Ȍ��v�@�l��v������肳�ꂽ�i���a�U�Q�N�S���P������K�p�j�B
�@�u���v�@�l��v��v�Q��
���̉�v��́A���@��R�S���Ɋ�Â��Đݗ�����邷�ׂĂ̌��v�@�l�ɓK�p����邱�Ƃ������ł���B
�@
���ۂ̌��v�@�l��v��̓K�p�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
|
���v�@�l�� |
���� |
| �E���v�@�l��v������S�ɓK�p���Ă��� |
16,674 |
63.2�� |
| �E���v�@�l��v����ꕔ�ɓK�p���Ă��� |
6,048 |
22.9�� |
| �E��Ɖ�v��K�p���Ă��� |
1,135 |
4.3�� |
| �E���̑��i������v���A���̉�v���K�p���Ă���j |
2,523 |
9.6�� |
| �����P�O�N�P�O���P�����ݍ��v |
26,380 |
100�� |
�I�E����������|���ɁA����8�N�x�Ő������ɂ����āA���v�@�l���̎��x�v�Z���̐Ŗ����ւ̒�o���鐧�x���n�����ꂽ�B
�]���́A���v�@�l���́A�@�l�Ŗ@����v���ƕ����݂̂��ېőΏۂƂȂ��Ă���
�A���v���Ƃ��c�ޏꍇ�̂ݖ@�l�ł̐\�����̓Y�t���ނƂ��Čv�Z���ނ̒�o���K
�v�Ƃ���Ă������A���̉����ɂ��A�@�l�Ŗ@��̎��v���Ƃ��c�܂Ȃ����v
�@�l���ɂ��Ă����x�v�Z���������Ŗ����ɒ�o����`���������邱�ƂɂȂ����B
�u���v�@�l���̎��x�v�Z���̒�o�v�Q�ƁB
�����ȁu���v�@�l��v��i���ԕj�v�̌��J���ĂQ�O�O�P�N�P�Q���Ɍ��\
�Q�O�O�P�N�T���Q�T���A���{�o�ϐV���́A�u�A����v���v�@�l�ɓ����v�Ƒ肵�āA�����ȁu���v�@�l��v�������v�����ԕƂ��ĂU���Ɍ��J���Ă����\���p�u���b�N�R�����g����t���A�N���ɂ��ŏI���܂Ƃ߂�A�ƕ��B
�Q�O�O�P�N�P�Q���P�X���A�����Ȃ͌��v�@�l�s�����i�����u���v�@�l��v��̌������Ɋւ���_�_�i���ԕj�v�����\���A�R�����g���Q�O�O�Q�N�Q���Q�W���܂łɋ��߂Ă���B
�����ȁu���v�@�l��v�������v�O�Q�N�R��
| ���v�@�l��v��̌����ɂ��� |
�����P�S�N�R���Q�X�����v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c������\����
�P�@��|�@
���v�@�l��v��ɂ��ẮA���a�T�Q�N�Ɍ��v�@�l�ē����A�����c��ɂ����Đ\�����킹����A���a�U�O�N�Ɍ��v�@�l�w���ēA����c����ɂ��������o�āA���v�@�l���v�Z���ޓ����쐬���邽�߂̊�Ƃ��Ē蒅���A�����Ɏ����Ă���B
�@
�����A���v�@�l���߂���Љ�I�y�ьo�ϓI���́A�ߔN�傫���ω����A��Ɖ�v�����v�̕���ɂ����Ă��A���ۓI�Ȓ��a�̊ϓ_������A��v��̐V�݁E���������s���Ă���B
�@�܂��A�u�s�����v��j�v�i�����P�Q�N�P�Q���P���t�c����j�ɂ����Ă��A���v�@�l��v��̉��P��̌������s�����ƂƂ���Ă���B
�@�ȏ�܂��A���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c������i�ȉ��u������v�Ƃ����B�j�ɂ����āA���v�@�l��v��ɂ��āu���_�y�ю����̐i�W�ɑ����čX�ɏ[���Ɖ��P��}��v���߂̌������s�����̂Ƃ���B
�Ƃ��Č��݁A�������Ɂu���v�@�l��v��������v�������������Č������Ă���B
�u���v�@�l��v��i�āj�v���\�i�O�R�N�R���j�F
��L�̂Ƃ��芲����̈˗��Ɋ�Â��A�Q�O�O�R�N�R���Q�W���A�����Ȃ́u���v�@�l��v�������v�́A�u���v�@�l��v��i�āj�v�����v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c���������Ăɒ�o����Ɠ����Ɍ��\�����B��{�I�l�����ɂ͑O�i�������邪��̓��e�́A����ɂ�����Ȃ��Ȃ����u��Ɖ�v�����v�ɉ������\���ƂȂ��Ă���B
2004�N10��14���A�����Ȃ͓˔@�Ƃ����A�ŏI�́u���v�@�l��v��v�����\�����B���e�́A��L�Ă����̂܂܂ƂȂ��Ă���B���䂦1�N�ȏ���Ă����u����Ă����̂���������Ă��Ȃ��B
| �� |
�����P�T�N�R���Ɍ�����犲����ɑ��āu���v�@�l��v��i�āj�ɂ��āv��� |
| |
�� |
| �@�� |
�V���ȉ�v��̎��{�ɓ������ĕK�v�Ȏ����ɂ��đ����Ȃɂ����Ď����I�Ȍ�����i�߁A���ʁA��v��̉����ɂ��āu���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�Ȓ��A����c�v�i�e�Ȓ����[���N���X�ō\���j�ɂ����Đ\����
|
| �R�@��ȉ�������
| �� ���s��Ƃ̑Δ���ʎ� (PDF) |
| �@�� |
�������\�̑̌n�̌������i���x�\�Z���y�ю��x���Z���͉�v��͈̔͊O�Ƃ���B��K�͖@�l�ɂ��Ă̓L���b�V���E�t���[�v�Z����lj��j |
| �@�� |
�������Y�̂Q�敪���i�w�萳�����Y�ƈ�ʐ������Y�j |
| �@�� |
�������Y�����v�Z�����t���[���ɓ��� |
|
|
| �S�@���{���� |
| |
| �@�� |
�����P�W�N�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x����ł��邾�����₩�Ɏ��{ |
|
���{�́i�V�j���v�@�l��v��i2004�N10��14�����\�j�ł́A�u���v�@�l�́A���Ɍf���錴���ɏ]���āA�������\�i�ݎؑΏƕ\�A�������Y�����v�Z���y�э��Y�ژ^�������B�ȉ������B�j���쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ��u��K�͌��v�@�l�ɂ��ẮA���̍������e�ɑ���S�������̗��p�҂���������Ă��邱�ƁA���Y�y�ѕ��̓��e�����l�����G�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A��L�̍������\�̑̌n�ɉ����āA�L���b�V���E�t���[�v�Z�����쐬����B�v�Ƃ��A�u�{��v��́A�����P�W�N�i2006�N�j�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x����ł��邾�����₩�Ɏ��{������̂Ƃ���v�Ƃ��Ă���B��v��̖{���ɂ͑O�N���l���f�ڂ�����r�������\�𖾕��ł͋��߂Ă��Ȃ����A�Y�t�̗l��������Ɣ�r�������\��������Ă����B�������Ȃ���A��r�������\�͎����т��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A���L�͒P�N�x�݂̂̊J������������A���Y�ژ^�i��ł͍��Y�ژ^���������\�̈�Ƃ��Ă����j�͒P�N�x�\���ł�������ƁA2����r���Ă���a�r�A�������Y�����v�Z���A�b�e���Ǝ����т��Ă��Ȃ��̂Œ��ӂ���K�v������B
�Q�O�O�T�N�U���P�R���A���{���F��v�m�����́A��c���@�l�ψ����Q�W���u���v�@�l��v��Ɋւ�������w�j�v�����\�����B�Ȃ��A�i�h�b�o�`�W���[�i���Q�O�O�T�N�P�P�����ɊW�҂̍��k��f�ڂ���Ă���B
| ���݁A���v�@�l���v�����t���[�̍s�����v���i�������𒆐S�̍s���Ă���A�u��ʓI�Ȕ�c���@�l���x��n�݂��āA���̔�c���@�l�̒�����A���Ԃ̗L���҂���Ȃ�ψ������̊���������̂ƔF�߂��A���v����F�߂�ꂽ��c���@�l�ƂȂ�Ƃ����A����Q�K���Ă̎d�g�݂Ō������Ă���v�Ƃ̂��ƁB�����P�W�N�x�̒ʏ퍑���ڎw���Ă���B�i�i�h�b�o�`�W���[�i���Q�O�O�T�N�P�P�������j |
|
���Ăł́u��c���g�D�i�m�o�n�j�v�Ƃ��Ĉ�{������Ă��܂��B
���{�ł́A���{���L�́u���v�@�l�v�Ƃ������̂����邽�߁u���v�@�l��v�v�ɉ����āA�ʓr���o�ϊ�撡�Łu�����c���@�l�̉�v�Ɋւ��錤����v������܂��B�s�v�c�Ȏd�g�݂ł���܂��B
�m�o�n�@�l�̏��NJ����ł������o�ϊ�撡���A�Q�O�O�P�N�P���̏Ȓ��ĕ҂����t�{�ֈڊ����ꂽ�B
�o�ϊ�撡������P�X�X�X�N�Ɂu�����c�������@�l�̉�v�Ɋւ��錤�����v���������ꂽ���A�P�X�X�X�N�S���P�U���̑�U���c�ŏI�����Ă���A���̌㌤����̋c�_����b���o�ϊ�撡�i���E���t�{�j���쐬�����u�����c�������@�l�̉�v�̎�����v�i�L���b�V���t���[�v�Z���͊܂܂Ȃ��j������A������Q�l�ɂ��ē����c�������@�l�̂قƂ�ǂ͍������ނ��쐬���Ă���B
�����v�@�l��v��̉����ɂ����E�E��v��E�w�j���������������n��Œǐ�
�������ȑ�b���[�Ǘ������@����18 �N�R��24 ���u���v�@�l��v��̉������ɂ��āv�i����16 �N10 ��14 �����v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�Ȓ��A����c�\�����j���̓K�p�ɓ������Ă̗��ӓ_�ɂ��āi�ʒm�j
���Ȃ��A���t�{�́u�悭���鎿��iFAQ�j�v����U-�S-�P�i��v��j(PDF
0.1MB) �ł́u���v�@�l�́A��ʂɌ����Ó��ƔF�߂�����v�@�l�̉�v����̑��̌��v�@�l�̉�v�̊��s�ɂ�邱�Ƃ����߂��܂����i���v�@�l�F��@�{�s�K����12 ���j�A����͓���̉�v��̓K�p���`���t������̂ł͂���܂����B���������Č��s�̌��v�@�l��v���K�p���邱�Ƃ��\�ł��B�������A�ǂ̂悤�ȉ�v���I������ꍇ�ł����Ă��A�@�߂Œ�߂�ꂽ���ނ�@�߂ɑ��������@�ɂ��쐬���A��o����K�v������܂��v�Ƃ��肩�Ȃ�B���ȋK��ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A���t�{���v�F�蓙�ψ������u���v�@�l��v��̉^�p�w�j�v�i�����Q1�N�����j���lj����ďo����Ă���A���v�@�l��v��̓K�p�ɂ͒��ӂ���K�v������B |
���t�{���v�F�蓙�ψ���ݒu
���v�F�蓙�ψ����͓��t�{�ɐݒu����A7�l�̈ψ�����\������Ă��܂��B
�@���v�F�蓙�ψ���́A����19�N4��1���ɔ������A���t������b�̎�����āA�V���Ȍ��v�@�l�̔F���ɌW�鐭�߁E���t�{�߂Ɋւ���R�c���s���A����19�N�U��15���ɓ��\���o���܂����B
�@���߁E���t�{�߂́A�ӌ�����葱���o�ĕ���19�N�X���V���Ɍ��z����A�ψ���͂��̌�A���I�m����L���镡���̎Q�^�̋��͂āA�u���v�F�蓙�Ɋւ���^�p�ɂ��āi���v�F�蓙�K�C�h���C���j�v��u���v�@�l��v��v���Ɋւ���R�c���s���܂����B�����͕���20�N�S��11���̑�34���ɂĐ������肳��܂����B
�@����20�N12��1���Ɏ{�s�����V���x�ɂ����Ă��A���v�F�蓙�ɌW����t������b�̎���ɂ��ĐR�c�����\���s���ƂƂ��ɁA���t������b����ϔC���A���v�@�l���ɑ������߁A���v�@�l�̎������ւ̗��������������{����ȂǁA�@�l�̊ē��s�����ƂƂȂ�܂��B
�V�E�V���v�@�l��v��i2008�N4��11�����\�j
�����P�W�N�Ɍ��v�@�l���x���v�֘A�O�@���������V���x�܂�����v�������K�v�����������߁A���ʁA���t�{���v�F�蓙�ψ���ɂ����āA���߂Č��v�@�l��v���ʎ��̂Ƃ����߂邱�ƂƂ����B
�����P�U�N���������̎�ȕύX�_�́A���̂Ƃ���ł���B
�A�D��v��̑̌n
�����P�U�N������͉�v��y�ђ����̕����ƕʕ\�y�їl���̕����Ƃ���\������邪�A����̐��x�^�p��̕X���l���A���҂�藣���A��v��y�ђ����̕�����{��v��Ƃ��A�ʕ\�y�їl���̕����͉^�p�w�j�Ƃ��Ď�舵�����ƂƂ����B
�C�D�������\�̒�`
���Y�ژ^�͍������\�͈̔͂��珜�����ƂƂ����B �������\�Ƃ́A�ݎؑΏƕ\�A�������Y�����v�Z������уL���b�V���t���[�v�Z���������B
�E�D��������
���������́A���������Ɋւ���K�肪�݂����Ă��Ȃ����߁A�{��v��ɂ����Ă�����߂邱�ƂƂ����B
�G�D���
�����P�U�N������ɂ́A����Ɋւ���K�肪�݂����Ă��Ȃ����߁A�{��v��ɂ����Ă�����߂邱�ƂƂ����B
�I�D��v�敪
�����P�U�N������ł́A���ʉ�v��݂��Ă���ꍇ�A��v�敪���ƂɑݎؑΏƕ\�y�ѐ������Y�����v�Z�����쐬���A�����\�ɂ��@�l�S�̂̂��̂�\�����Ă������A�{��v��ł͖@�l�S�̂̍������\�y�ѕ����������тɍ��Y�ژ^����{�Ƃ��A��v�敪���Ƃ̏��́A�������\�̈ꕔ�Ƃ��đݎؑΏƕ\����\�y�ѐ������Y�����v�Z������\�ɂ����āA���ꂼ��ɏ������l���ŕ\��������̂Ɛ��������B
�{��v��̎��{����
�{��v��́A�����Q�O�N�P�Q���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x������{������̂Ƃ���B
���������F
�V�E�V���v�@�l��v��ɂ����i2008�N4��11�����\�j ���v�@�l��v��̉^�p�w�j
���t�{���v�F�蓙�ψ����@�@���v�@�l�����i�����ȁj�@���v�F��Ɋւ���@�߁E�K�C�h���C���� �@���v�ړI���Ƃ̃`�F�b�N�|�C���g�ɂ���
�����v�F�蓙�K�C�h���C���������@��119 ���ɋK�肷����v�ړI�x�o�v�擙�ɂ��� �@���v�@�l�F��@��T�ɂ��āi���v�Вc�@�l�E���v���c�@�l�W�j
�ڍs���Ԓ��̓��ᖯ�@�@�l�����ׂ��v�Z�����E�E���������t�B�[���h�@��������
�V���x�̎{�s�́A�����Q�O�N�P�Q���P���ł��B�@�ڍs�������T�N���i����25�N11��30���܂Łj
���Ăł͔N�����ŏ��J��
���Ă̌��v�@�l���̏��J���́A�����������������\���܂��N�����iAnnual report�j�ɂ���čs���Ă���B���Ăł́A�N�������A����ƁA�����J��ƁA��c���c�́E�g�D�̊��������������ӔC���iAccountability�j���s���邱�ƂƁA���J�����邱�Ƃɂ���ė������i�Ƃ��Ď^���҂������⊈�������̉����t�����߂̈�ʓI�ȏ��ނł��B�N�����Ɋ܂މ�v���͂��̍��̉�v��ݒ��̂��ݒ肵����v��ɂ���Ă��܂��B
�Ⴆ�A�p���̏ꍇ�́A�u��c���c�̂��@�l�i���擾���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́C�P�X�W�T�N��
�Ж@�iCompanies Act�j��C���ϑg�����Ɋւ�����ʖ@�ɏ]���Ė@�l�i���擾���邱�ƂɂȂ邪�C������́C��L���
�@��̕ۏؗL����Ёicompany limited by guarantee�j�̖@�`���������p�����Ă���悤�ł���B
�@�����C���v�icharitable�j�ړI�̒c�̂ɂ��ẮC�@�l�i�̗L�����킸�C�����ŁC�@�l�œ��Ɋւ���Ő���̗D��
�[�u���`�����e�B�o�^�̐��x���K�p����C�o�^���ꂽ�Ƃ��́C���v�c�̂Ƃ��Ĉ����邱�ƂɂȂ�B
�@���������āC�O�L�̕ۏؗL����Ђł����āC�`�����e�B�o�^�����Ă��Ȃ����̂̒��ɂ́C��c������v�̒��Ԗ@�l��
����������̂����݂��邱�ƂɂȂ�B
�ۏؗL����Ђ́C�o�L���ɑ��C��Ж@���߂��Ă����N�������̒�o�`�����B
�����҂́C�`�����e�B�̉�v�L�^��ێ����C�N�������̑������z�ɂ��敪�ɉ�����������
�`�����e�B�ψ��ɒ�o����B�N�������̑��̕����́C��ʂ̉{���ɋ������B�v
�č��̏ꍇ�́A�u��c�����v�@�l�́C�i�@�����ɍ��Y�Ɋւ����N�������o����`��������C�i�@�����́C�@�l ���ړI�ɔ�����s�ׂ�@�߈ᔽ�̍s�ׂ��s�����ꍇ���ɂ́C�@�l�̉��U�����◝���̉�C�����C�i�ג�N�����܂ލL
�͂Ȋē������s�g���邱�Ƃ��ł���B�v�@�č��̔�c���@�l��v(�uNot-for-Profit Accounting �v, �uFinancial and Accounting Guide for Not-For-Profit
Organizations�v)�@�Q�Ɓ�Amazon.com�͏�����ǂނ��Ƃ��ł��܂��B
�u���O���̒��Ԗ@�l�@���v�̃C�M���X�y�уA�����J�Q�ƁB
���{��������������̂̌��v�@�l�Ƃ������̂���уV�X�e���ł����A���Ăł͔�c���g�D�܂��͖@�l�Ƃ������̂ŕ�����Ղ��A���J���̑Ώۂ̎�͎̂����҂ł����Ċē����̓`�F�b�N�ɓO���Ă���B
�č�����э��ۋ@�ւ̊J������
| ��c���@�l�� |
�J���������/�������\�̑̌n |
���{�̕��̖��� |
�R�����g |
�j���[���[�N�،������
�m�x�r�d |
�N�����Q�O�O�R
�EStatement of income, comprehensive income and equity of members
�EBalance sheet
�EStatement of cash flows
�ENotes to the financial statements |
Equity of members
������� |
���݁A������Љ��̌�����
�J�n�������c���@�l��
�����\��������B
(2005�N2������)
|
����Љ�v�Ď��R�c��
�o�b�`�n�a
�č��̏���Ђ̊č��Ď��@�� |
�N�����Q�O�O�R
�EStatement of financial position
�EStatement of activities
�EStatement of cash flows
�ENotes to the financial statements |
Net assets
�����Y |
|
�č��ԏ\����
American Red Cross |
�N�����Q�O�O�R
�EStatement of financial position
�EStatement of activities
�EStatement of functional expenses
�EStatement of Cash flows
�ENotes to the financial statements |
Net assets
�����Y |
|
���ۉ�v��ψ�����c
�h�`�r�b �eoundation
���ۉ�v��̐ݒ�@�� |
�N����2001�`2003
�EStatement of activities
�EStatement of financial position
�ECash flow statement
�ENotes to the financial statements |
Net assets
�����Y |
2001�N2���h�`�r�b������p���V�ݖ@�l�ƂȂ����h�`�r�b�e�ł��邪2001�N�x�̔N�����͑O�N�x�Ƃ���r�������\���J�����Ă���B |
�č����F�،��A�i���X�g����
CFA Institute
(Chartered Financial Analyst, CFA) |
2004�N����
�EStatement of financial position
�EStatement of activities
�EStatement of cash flows
�ENotes to the financial statements |
Net assets
�����Y |
|
���{�́i�V�j���v�@�l��v��i2004�N10��14�����\�j�ł́A�u���v�@�l�́A���Ɍf���錴���ɏ]���āA�������\�i�ݎؑΏƕ\�A�������Y�����v�Z���y�э��Y�ژ^�������B�ȉ������B�j���쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ��u��K�͌��v�@�l�ɂ��ẮA���̍������e�ɑ���S�������̗��p�҂���������Ă��邱�ƁA���Y�y�ѕ��̓��e�����l�����G�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A��L�̍������\�̑̌n�ɉ����āA�L���b�V���E�t���[�v�Z�����쐬����B�v�Ƃ��A�u�{��v��́A�����P�W�N�i2006�N�j�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x����ł��邾�����₩�Ɏ��{������̂Ƃ���v�Ƃ��Ă���B��v��̖{���ɂ͑O�N���l���f�ڂ�����r�������\�𖾕��ł͋��߂Ă��Ȃ����A�Y�t�̗l��������Ɣ�r�������\��������Ă���B�������Ȃ���A��r�������\�͎����т��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A���L�͒P�N�x�݂̂̊J������������A���Y�ژ^�i��ł͍��Y�ژ^���������\�̈�Ƃ��Ă����j�͒P�N�x�\���ł�������ƁA2����r���Ă���a�r�A�������Y�����v�Z���A�b�e���Ǝ����т��Ă��Ȃ��̂Œ��ӂ���K�v������B
�Q�O�O�R�N�Q���P�Q���A���{�o�ϐV���ɂ��ƁA�����J���Ȃ͑S�a�@�ɋ��ʂ���V������v����Q�O�O�S�N���瓱�����邽�߁A�u��ƌo�c�̂�����Ɋւ��錟�����v���R���ɂ܂Ƃ߂���ɁA��Ö@�Ɋ�Â��u�a�@��v�����v���Q�O�N�Ԃ�ɂQ�O�O�R�N�x���ɉ������邱�Ƃ荞�ށA�Ƃ��Ă���B�i2003�N�R���Q�U���ŏI���@��ƌo�c�̋ߑ㉻�E�������Ɍ���������̎�g�@�ˁ@��ƌo�c�̃z�[���y�[�W�@�a�@��v�������������ɌW�錤�����@�Q�Ɓj�@�����a�@�͊�����v�A�s���{���̕a�@�͒n�����c��Ɖ�v�Ȃǂ��ł������a�@��v�ԕa�@���܂ߋ��ʂ̉�v��ɂ���r�\�����m�ۂ��邱�Ƃ�ڎw���Ă���B�Ȃ��A�Q�O�O�Q�N�U���Q�U���ɁA�l�a�@�c�̋��c������u�a�@��v�������̌������Ɋւ��āi���ԕj�v�����\����Ă���B���ԕɂ��A�����a�@�i�Ɨ��s���@�l�j�A�����̗��a�@�A���{�ԏ\���З��a�@�A�Љ���@�l�������c�ϐ���a�@�A�����_�Ƌ����g���A����a�@�A�S���Љ�ی�����A����a�@�A���v�@�l���a�@�A��Ö@�l���a�@�A�w�Z�@�l���a�@�A�l���a�@�A������З��a�@���a�@��v�����̓K�p�ΏۂƂȂ�悤�ł���B�ˁ@�Q�O�O�S�N�T���Q�V���A�����J�����㐭�ǎw���ۂ́u�a�@��v�����̉����i�āj�v�����\��6��28���܂łɈӌ����W���Ă���B
�Ɨ��s���@�l������Ë@�\�̃z�[���y�[�W�ɂ́A2004�N8��19���ɁA�����J���Ȉ㐭�ǒ�����e�s���{���m���y�ъe�q����Ǖ��i�ǁj�����Ăɒʒm���ꂽ���e�̎����i�a�@��v�����k�����Łl2004�N8���ق��j�y�ѓY�t�������f�ڂ���Ă��܂��B
| �a�@��v�����̉����ɂ����@�i�����P�U�N�W���P�X���㐭����0819001���j�i�o�c�e�P�U�X�j�a�j |
�a�@��v�����̉����ɔ�����Ö@�l�ɂ������v�������ɌW�闯�ӓ_�ɂ���
�i�����P�U�N�W���P�X���㐭����0819002���j�i�o�c�e�P�X�j�a�j |
| �a�@��v�����̉����ɂ��ā@�i�����P�U�N�W���P�X���㐭�w����0819001���j�i�o�c�e�P�X�j�a�j |
�a�@��v�����̉����ɔ�����Ö@�l�ɂ����錈�Z�̓͏o�̗l���ɌW�闯�ӓ_�ɂ���
�i�����P�U�N�W���P�X���㐭�w����0819002���j�i�o�c�e�T�R�j�a�j |
| �a�@��v�����K�p�K�C�h���C���ɂ��ā@�i�����P�U�N�X���P�O���㐭����0910002���j�i�o�c�e�U�U�j�a�j |
| �a�@��v�����̉����ɔ���������̎戵�ɂ��ā@�i�����P�U�N�X���P�O���㐭�w����0910001���j�i�o�c�e�V�Q�j�a�j |
�J�������ȁE�E�E��Ö@�l�W�@�߂���ђʒm�@�Q��
�Q�O�O�O�N�Q���A�������́A���ی��̓����ɍ��킹��悤�ɁA�u�Љ���@�l��v��v�����\���A�Q�O�O�O�N�S���P�����K�p����Ƃ��Ă��܂��B����ɂ��ƁA���v���Ƃ͂��̉�v��ɏ]���A���v���ƕ����͊�Ɖ�v�����ɏ]���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�������\�ɁA�u�ݎؑΏƕ\�v�̂ق��Ɂu���Y�ژ^�v�����߂Ă��܂��B�����āA�S���P�V���t�Ō����ȉے��ʒm�̎����A���Ƃ��āw�u�Љ���@�l��v��v�y�сu�w����V�l�����{�ݓ���v��������v��������舵���w���w�j�v�ɂ���v�����ɂ����x���o����Ă���B�u���ɕ⏕�������ʐϗ�������z�͋t�����H�v�Ƃ��ĎЉ���@�l�̉�v�̕s�v�c�ȓ_���w�E����A�u�悭�A����������A������ȒP�ɐ������Ă���Ȃ����Ȃ��`�ƌ����܂��v�ƃR���T���^���g�͒Q���B
�Ď��́A�@�l�̉^�c�����č����������S���Ă���A���@��͐ݒu��C�ӂƂ���Ă��邪�A�w���ē�ɂ����ẮA�Ď���K���ݒu���ׂ��ƋK�肵�Ă���B�Ď��̑����͂T�W�A�O�O�V�l�A���ςQ�D�Q�l�ł���B�K�͕ʂł́A�Q�l���P�X�A�R�Q�U�@�l�i�V�R�D�R���j�Ƒ唼���߂Ă���i�Ď����u����Ă��Ȃ��@�l�͂X�O�j�B�P�l����R�l�܂łɂقƂ��
�̖@�l�����܂邪�A�T�l�ȏ�Ƃ����@�l���Q�R�R���݂��Ă���B
�@�Ȃ��A�Ď��̒��ɂ́A��ΊĎ��i�Œ�ł��T�R���ȏ�o���Ă���ҁj�Ƃ��ē���I�Ɏ����Ɍg����Ă���҂��A�킸���ł͂��邪���݂��Ă���B
�����Ȃ͍������ǂ�����v�@�l�ɂQ�O�O�P�N�x����č��@�l����F��v�m�A�ŗ��m�Ȃǂɂ��O���č����`���t����B���c�@�l�u�P�[�G�X�f�[������ƌo�c�ҕ������ƒc�v�i�j�r�c�j�ɂ�鐭�E�H�쎖�����_�@�ɁA�����g�r�Ȃǂ̓�������O�ꂷ��K�v������Ɣ��f�����B
�����̃`�F�b�N�@�ւƂ��āu�Ď��v�̐ݒu���`���t���Ă��邪�Ď��ɂ͖@�l�̂n�a�Ȃǐg���������u�s���ȉ^�c���\���ɊĎ��ł��Ȃ��v�Ƃ̎w�E���o�Ă����B���������܂��āA�����Ȃ͂Q�O�O�P�N�x����O���č����`���t����B
�Q�O�O�P�N(�����P�R�N)�Q���X���A�����Ȃ́A�Q�O�O�P�N�x���狭����Ƃ��āA���Y�K�͂łP�O�O���~�ȏ�A�����z�łT�O���~�ȏ�A�܂��͔N�ԗ\�Z���P�O���~�ȏ�̖@�l�ɊO���č���v�����邱�Ƃ��t�c�ɕ��������B�����Ȃ́A�O���č��̑���������D�悳���邽�ߖ��@�����Ȃǂɂ��`���t�������������i���{�o�ϐV���j�B�W�t����c������\�����킹�͉��L�̒ʂ�ł��B
|
|
|
���@���@13�@�N�@�Q�@���@�X�@��
���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���
�� �W �t �� �� �c ������\���� |
���v�@�l�ɑ��錵���Ȏw���ē��X�ɓO�ꂷ�邽�߁A�w���ē̐ӔC�̐����m������ƂƂ��ɁA�w���ē̑O��
�ƂȂ�@�l�̓I�m�Ȏ��Ԕc���̂��߂̗��������̏[������}�邱�ƂƂ��A�e�{�ȁi���ƌ����ψ���A�h�q���y�ы��Z
�����܂ށB�ȉ������B�j�ɂ����ĉ��L�̑[�u���u����B
|
| �L |
| �P |
�e�{�Ȃɂ�����w���ē̐ӔC�̐��̊m�� |
|
(1)�@�������v�@�l�w���ē����̐ݒu
�@�@�e�{�ȂɁA���ꂼ�ꑍ�����v�@�l�w���ē��A�������v�@�l�w���ē��⍲�y�ь��v�@�l�w���ē���u
���B �@�@
�A�@�������v�@�l�w���ē��́A���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c����������A�������v�@�l�w���ē��⍲�́A���v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c������{�ȘA����c�\�������A���v�@�l�w���ē��́A�e���ǂ̑����S���ۓ��̒��������ď[�Ă�B
�B�@�������v�@�l�w���ē��́A�{�Ȃɂ�������v�@�l�̎w���ēɊւ��鎖��������B
�@�@
�C�@�������v�@�l�w���ē��⍲�́A�������v�@�l�w���ē��̎�����⍲����B
�@�@
�D�@���v�@�l�w���ē��́A���ǂɂ�������v�@�l�̎w���ēɊւ��鎖��������B
|
|
(2)�@�{�ȓ��A����c�̐ݒu |
|
�e�{�Ȃ́A���v�@�l�̎w���ē�I�����ʓI�E�����I�ɐ��i���邽�߁A(1)�@�Ɍf����҂��\�����Ƃ�����v�@�l�̎w���ēɊւ���{�ȓ��A����c��ݒu����B
|
| �Q |
���������̏[�� |
|
(1)�@���������̒���I�Ȏ��{ �@�@
���nj��v�@�l�ɑ��闧�������́A���Ȃ��Ƃ��R�N�ɂP����{����B
�@
(2)�@�����������{�v��̍��� �@�@
�e�{�Ȃ́A(1)�̗����������v��I�Ɏ��{���邽�߁A�����������ꏄ������Ԃ��v����ԂƂ�����{�v�������
���A����Ɋ�Â��������������{������̂Ƃ���B
�@
(3)�@�Վ��������� �@�@
(1)�̗��������̂ق��A�e�{�Ȃ́A���nj��v�@�l�̋Ɩ��^�c�ɏd��Ȗ�肪����ƔF�߂���ꍇ�A�]�O����̉��P�w������������ꍇ�����ɕK�v������ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A�����ɗ������������{������̂Ƃ���B
�@
(4)�@�I�m���̌n�I�Ȍ����̂��߂̑[�u �@�@
�@�@�e�{�Ȃ́A�����������L�ڂ��������[�i�`�F�b�N���X�g�j���쐬���A����ɏ]���ė������������{����B�����[�i�`�F�b�N���X�g�j�ɂ��ẮA�ʎ��̗���Q�l�ɁA�e�{�Ȃ̎���ɉ����č쐬������̂Ƃ���B
�@�@
�A�@�s���ϑ��^�@�l���i��s���ϑ��^�@�l���̑��_���̐��i�ɂ��ģ(����10�N12���S�����v�@�l���̎w���ē��Ɋւ���W�t����c������\����)�̑Ώۖ@�l�������B�j�ɂ��ẮA�@�̌��������̂ق��A���\�����̕ʎ��Ɋ�Â��쐬��������������lj����āA���������{����B
�@�@
�B�@���������̌��ʁA�K�v������ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���F��v�m�����Ƃ̋��͂āA�@�l�̋Ɩ��^�c�̎��Ԕc���ɓw�߂���̂Ƃ���B
�@�@
�C�@���������̌��ʁA�@�l�̋Ɩ��^�c�ɉ��P���ׂ��������F�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�e�{�Ȃ́A���Y�@�l�ɑ��A���₩�ɕ������ɂ��A������t���ĕK�v�ȉ��P���w������ƂƂ��ɁA����Ɋ�Â��u�����[�u�ɂ��ĕ����߂�
���̂Ƃ���B �@
(5)�@���������̎��{���ʂ̌��\�� �@�@
�@�@�e�{�Ȃ́A���N�x�̗��������̎��{�����܂Ƃ߁A���̌��ʂ𑬂₩�Ɍ��\����ƂƂ��ɁA�����Ȃɕ���B
�@�@
�A�@�����Ȃ́A�e�{�Ȃ̗��������̎��{���ʂ̊T�v�ɂ��āA�K�v�Ȏ��܂Ƃ߂��s������A�u���v�@�l�Ɋւ���N�����v�ɂ����\����B
|
| �R |
���̑� |
|
(1)�@�E���ɑ������I�Ȍ��C�̎��{ �@
�e�{�Ȃ́A���v�@�l�̎w���ēɊւ��鎖����S������E���ɑ��A����I�Ɍ��C�����{����ƂƂ��ɁA���̓��e�̏[���ɓw�߂���̂Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ����āA�����Ȃ́A�e�{�Ȃ���̋��߂ɉ����A���Y���C�̎��{�Ɋւ��K�v�ȋ��͂��s���B
�@
(2)�@�O���č��̗v�� �@
�e�{�Ȃ́A���Y�z��100���~�ȏ�Ⴕ���͕��z��50���~�ȏ㖔�͎��x���Z�z��10���~�ȏ�̏��nj��v�@�l�ɑ�
���A���F��v�m���ɂ��č�����悤�v������B
�@
(3)�@�s���{���ւ̗v�� �@
���͓s���{���ɑ��A�{�\�����Ɠ��l�̑[�u���u����悤�v������B
�@
|
| �S |
���{���� �@ |
|
�e�{�Ȃ́A����13�N�x����{�\�����Ɋ�Â��[�u���u���邱�ƂƂ��A���̂��߂ɕK�v�ȑ̐����̐����ɂ��ẮA
����12�N�x���ɍs���B |
���̃y�[�W�̃g�b�v�֖߂� |
��L�A�u���v�@�l�̎w���ē̐��̏[�����ɂ��āv�ɋL�ڂ́u�������茟���v�̌��ʂ́A���\����Ă���B���Ȃ݂ɁA���Z�������\�����������茟�����ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B�����ȂƃI�[�o�[���b�v���Ă���A�s�v�c�ȕ��ƂȂ��Ă���B
�@�l���̍��ق́A���L�Ɂu�@�l���́A�����ȍ����ǁi�����x�Njy�щ��ꑍ�������ǂ��܂ށB�j���ǂ̌��v�@�l�i���Z�����������Ɋ֘A���鎖�������Ƃ̖ړI�Ƃ�����́j���܂ށB�v�Ƃ���A�����ȏ��ǂ̌��v�@�l���܂�ł���悤�ł���B�����ȏ��ǂ̂V�O�W�̌��v�@�l�̌����������ʓr���\����Ă���B�d�����Ă���̂��s���B
�e�Ȓ��̌��v�@�l�ւ̃����N
�@�l�Ŗ@�́A�ېł̊ϓ_����u���v�@�l�ېŁv�̋K��������A���v�@�l�ɑ���ېł���ʂ̖@�l�ېłƋ敪���Ă��܂��B�@���@�l���܂ތ��v�@�l�́A��ʎ��Ƃ����v���l�����銈���Ƃ͈قȂ邱�Ƃ���A���ʂȋK������v�����݂̂ɉې����A��ʎ��Ƃ̐ŗ��i�ېŏ�����8�S���~����W���ŗ�34.5%��99�N4���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x��30.0%�j�Ƃ͈قȂ�ᗦ�̐ŗ��i25%��99�N4��1���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x��22%�j�ʼnېł��悤�Ƃ�����̂ł��B
�@�l�Ŗ@�ł́A���v�@�l�����v���Ƃ��c�ޏꍇ�A���v���Ƃ��琶���鏊���Ǝ��v���ƈȊO�̎��Ƃ��琶���鏊���Ƌ敪���Čo�����邱�Ƃ����߂��܂��i�@�l�Ŗ@�{�s��6���j�B���������敪�o���́A��������є�p�����ł͂Ȃ��A���Y����ѕ��ɂ��Ă��s�����ƂƂ���Ă��܂��i�@�l�Ŗ@��{�ʒB15-2-1�j�B
���������āA���v���Ƃ��s���ꍇ�A���v���Ƃ����v���ƈȊO�Ƌ敪���Čo�����邱�Ƃ����߂������ƂɂȂ�܂��B
�@�l�Ŗ@�ł́A���Z����2�����ȓ��Ɋm��\�����ɑݎؑΏƕ\����ё��v�v�Z�����̏��ނ�Y�t���Ȃ���Ȃ�܂���i�@�l�Ŗ@��74���2���j�B�܂��A���v�@�l���́A�ݎؑΏƕ\����ё��v�v�Z�����̏��ނɂ́A���v���ƈȊO�̎��ƂɌW�鏑�ނ��܂܂�܂��i�@�l�Ŋ�{�ʒB15-2-14�j�B
�V���Ȍ��v�@�l�W�Ő��̎���E�E�Q�O�O�X�N�V���P���݁i���Œ��j
�Ő�������̎Вc�@�l�E���c�@�l�̋敪
���v�O�@�̐���ɂ��V���Ȗ@�l�̎�ނ̑n�݂ƎВc�@�l�E���c�@�l�̔p�~�ɔ����A�]���̎Вc�@�l�E���c�@�l�́A�@�l�Ŗ@��A���v�Вc�@�l�E���v���c�@�l�A��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�y�ѓ��ᖯ�@�@�l�̂R�ɋ敪����܂��B
�C ���v�Вc�@�l�E���v���c�@�l
�s����������v�F��������̂������A�@�l�Ŗ@��A���v�@�l���Ƃ��Ď�舵���܂��i�@�Q�Z�j�B
�� ��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l
���v�F����Ă��Ȃ���ʎВc�@�l���͈�ʍ��c�@�l�i�ȉ��P�Ɂu��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�v�Ƃ����܂��B�j�́A��c���^�@�l�y�є�c���^�@�l�ȊO�̖@�l�̂Q�ɋ敪����܂��B
(�) ��c���^�@�l
��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�̂������̗v���ɊY�����鎟�̂��̂��u��c���^�@�l�v�Ƃ����A�@�l�Ŗ@��A���v�@�l���Ƃ��Ď�舵���܂��i�@�Q�Z�A��̓�j�B
�@ ��c�������O�ꂳ�ꂽ�@�l
�A ���v�I������ړI�Ƃ���@�l
��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�̂����A���̇@���͇A�ɊY��������́i���ꂼ��̗v���̂��ׂĂɊY������K�v������܂��B�j�́A��c���^�@�l�ɂȂ�܂��B
| �ތ^ |
�v �� |
�@ ��c�������O�ꂳ�ꂽ�@�l
�i�@�Q��̓�C�A�߂R�@�j |
�P ��]���̕��z���s��Ȃ����Ƃ�芼�ɒ�߂Ă��邱�ƁB
�Q ���U�����Ƃ��́A�c�]���Y�����E�n�������c�̂���̌��v�I�Ȓc�̂ɑ��^����
���Ƃ�芼�ɒ�߂Ă��邱�ƁB
�R ��L�P�y�тQ�̒芼�̒�߂Ɉᔽ����s�ׁi��L�P�A�Q�y�щ��L�S�̗v���ɊY��
���Ă������Ԃɂ����āA����̌l���͒c�̂ɓ��ʂ̗��v��^���邱�Ƃ��܂݂�
���B�j���s�����Ƃ����肵�A���͍s�������Ƃ��Ȃ����ƁB
�S �e�����ɂ��āA�����Ƃ��̗����̐e�����ł��闝���̍��v�����A�����̑�����
�R����1 �ȉ��ł��邱�ƁB |
�A ���v�I������ړI�Ƃ���@�l
�i�@�Q��̓A�߂R�A�j |
�P ����ɋ��ʂ��闘�v��}�銈�����s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邱�ƁB
�Q �芼���ɉ��̒�߂����邱�ƁB
�R �傽�鎖�ƂƂ��Ď��v���Ƃ��s���Ă��Ȃ����ƁB
�S �芼�ɓ���̌l���͒c�̂ɏ�]���̕��z���s�����Ƃ��߂Ă��Ȃ����ƁB
�T ���U�����Ƃ��ɂ��̎c�]���Y�����̌l���͒c�̂ɋA�������邱�Ƃ�芼��
��߂Ă��Ȃ����ƁB
�U ��L�P����T�܂ŋy�щ��L�V�̗v���ɊY�����Ă������Ԃɂ����āA����̌l��
�͒c�̂ɓ��ʂ̗��v��^���邱�Ƃ����肵�A���͗^�������Ƃ��Ȃ����ƁB
�V �e�����ɂ��āA�����Ƃ��̗����̐e�����ł��闝���̍��v�����A�����̑�����
�R����1 �ȉ��ł��邱�ƁB |
(�) ��c���^�@�l�ȊO�̈�ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l
��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�̂����A��c���^�@�l�łȂ����̂́A�@�l�Ŗ@��A���ʖ@�l�Ƃ��Ď�舵���܂��B
(��) ���́u�V���Ȍ��v�@�l�W�Ő��̎���v�ɂ����āA��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�̂�����c���^�@�l�łȂ����̂��u��c���^�@�l�ȊO�̖@�l�v�Ƃ����܂��B
�n ���ᖯ�@�@�l
���v�O�@�̎{�s���i����20 �N12 ���P���j�ɂ����đ����Ă����Вc�@�l�E���c�@�l�Ō��v�Вc�@�l�E���v���c�@�l���͈�ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l�ւ̈ڍs�̓o�L�����Ă��Ȃ����̂����Вc�@�l�E������c�@�l�i���ᖯ�@�@�l�Ƒ��̂��܂��B�j�Ƃ����A���v�O�@�̎{�s���O�Ɠ��l�ɁA�@�l�Ŗ@��A���v�@�l���Ƃ��Ď�舵���܂��i����20
�N�����@����10�j�B
�@�l�敪���Ƃ̖@�l�Ŗ@��̎戵�����܂Ƃ߂�Ɖ��̕\�̂Ƃ���ƂȂ�܂��B
| �@�l�敪 |
�@�l�Ŗ@��̎�舵�� |
| ���v�Вc�@�l�E���v���c�@�l |
���v�@�l�� |
��ʎВc�@�l
��ʍ��c�@�l |
��c���^�@�l |
���v�@�l�� |
| ��c���^�@�l�ȊO�̖@�l |
���ʖ@�l |
���ᖯ�@�@�l
�i�����@34��@�l�j |
���v�@�l�� |
�V���Ȗ@�l�̋敪�̑n�݂ɔ����A�ېŏ����͈̔͋y�ѐŗ��ɂ��āA���̂悤�ɐ�������Ă��܂��i�@�S�@�A�V�A66�@�`�B�A�[�@42 �̂R�̂Q�A�߂T�j�B
|
���v�Вc�@�l
���v���c�@�l |
��ʎВc�@�l�E��ʍ��c�@�l |
���ᖯ�@�@�l |
| ��c���^�@�l |
��c���^�@�l�ȊO�̖@�l
�s���ʖ@�l�t |
�ېŏ�����
�͈� |
���v���Ƃ��琶��
�������ɑ��ĉ�
��
���v�ړI���Ƃ͔�
�ې�(���P) |
���v���Ƃ��琶
���������ɑ�
�ĉې� |
���ׂĂ̏�����
���ĉې� |
���v���Ƃ��琶
���������ɑ�
�ĉې� |
| �@�l�ŗ� |
�R�O��
�i�������z�N800 ���~�ȉ��̋��z�͂P�W��(���Q)�j |
�Q�Q��
�i �������z�N
800 ���~�ȉ���
���z��
�P�W��(���Q)�j |
�i���j�F
�P �s�����́A���v�F��������Ƃ��i���ᖯ�@�@�l�ɂ����ẮA���v�F����Ĉڍs�̓o�L�����A���̎|�̓͏o���������Ƃ��j�ɂ́A���̎|���������邱�ƂƂ���Ă��܂��i���v�@�l�F��@10�A�����@108�j�B���̌����̍ۂɂ͌��v�F������@�l�ɌW����v�ړI���Ƃ��L�ڂ���܂��̂ŁA���̋L�ڂ��ꂽ���v�ړI���Ƃ���ېłƂȂ�܂��B
�Q ����21 �N�S���P�����畽��23 �N�R��31 ���܂ł̊ԂɏI������e���ƔN�x�ɂ��ẮA�N800 ���~�ȉ��̋��z�ɑ���@�l�ŗ���18���i�]�O��22���j�Ɉ����������Ă��܂��B
���v���ƂƂ́A���̂R�R�̎��Ɓi�t�����ĉc�܂����̂��܂ށj�ŁA�p�����Ď��Ə��݂��ĉc�܂����̂������i�@�l�Ŗ@��Q��13���A�{�s��5��1���j�A�Ƃ��Ă��܂��B
�P�D���i�̔��ƁA�Q�D�s���Y�̔��ƁA�R�D���K�ݕt�ƁA�S�D���i�ݕt�ƁA�T�D�s���Y�ݕt�ƁA�U�D�����ƁA�V�D�ʐM�ƁA�W�D�^���ƁA�X�D�q�ɋƁA10.�����ƁA11.����ƁA12.�o�ŋƁA13.�ʐ^�ƁA14.�ȑƁA15.���ًƁA16.�����X�Ƃ��̑��̈��H�ƁA17.�����ƁA18.�㗝�ƁA19.�����ƁA20.�≮�ƁA21.�z�ƁA22.�y�̎�ƁA23.����ƁA24.���e�ƁA25.���e�ƁA26.���s�ƁA27.�V�Z���ƁA28.�V�����ƁA29.��Õی��ƁA30.�m�فA�a�فA�������t���A�ҕ��A��|�A�����A���e�A���e�A�����A���ԁA�����A���|�A���x�A�����A���y�A�G��A�����A�ʐ^�A�H�|�A�f�U�C���A�����ԑ��c�Ⴕ���͏��^�D���̑��c�i�ȉ��A�Z�|�Ƃ����j�̋����A31.
���ԏ�ƁA32.�M�p�ۏ؋ƁA33.���̑��H�Ə��L�����̑��̋Z�p�Ɋւ��錠�����͒��쌠�̏��n���͒��s�����ƁA
��L�̋Ǝ���s���Ă���Ήېł���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A��̗v�������Ă���ꍇ�ɉېł��܂��Ƃ������̂ł��B
�܂�A�i�P�j�p�����ĉc�܂�Ă���A�i�Q�j���Ə��݂��ĉc�܂��Ƃ����v�������Ă��鎖�Ƃ����v���ƂƂȂ�܂��B
������̎���ŁA�p�����ĉc�܂�Ȃ����̂͊܂܂�܂��A���Ə��݂��Ă��Ȃ��ꍇ�Ȃǂ͊Y�����܂���B
�t�ɁA���v���Ƃɕt�����čs�����������v���ƂƂɂȂ���܂��B�Ⴆ�A�o�ŋƂŏo�ŋƂɊ֘A���ču������J������o�ŕ��̍L��������炤�Ƃ������Ƃ͏o�ŋƂƂȂ�܂��B
���v�@�l�����v���Ƃ��c�ޏꍇ�ɂ́A�u���v���Ɓv�Ɓu���v���ƈȊO�̎��Ɓv�Ƃɋ敪�o�����邱�ƂƂ���Ă��܂�(�@�l�Ŗ@�{�s�ߑ�U��)�B���̋敪�́A�P�Ɏ����y�юx�o�Ɋւ���o�������łȂ��A���Y�E���Ɋւ���o�����܂ނ��Ƃɗ��ӂ���K�v������܂��B
�y��P �@�l�Ŋ�{�ʒB�W�z�i����ُ��ɂ�鎖�������̎�����j15�|1�|28 ���v�@�l�����A���������̎���̐�����L����Ɩ����s���ꍇ�ɂ����Ă��A���Y�Ɩ����@�߂̋K��A�s�������̎w�����͓��Y�Ɩ��Ɋւ���K���A�K��Ⴕ���͌_��Ɋ�Â�����ُ��i���̈ϑ��ɂ��ϑ��҂������z�����Y�Ɩ��̂��߂ɕK�v�Ȕ�p�̊z���Ȃ����Ƃ������B�j�ɂ��s������̂ł���A���A���̂��Ƃɂ����炩���߈��̊��ԁi�����ނ˂T�N�ȓ��̊��ԂƂ���B�j�������ď����Ŗ������i���ŋǂ̒����ۏ��ǖ@�l�ɂ����ẮA�������ŋǒ��B�ȉ�15�|�P�|53
�ɂ����ē����B�j�̊m�F�����Ƃ��́A���̊m�F�������Ԃɂ��ẮA���Y�Ɩ��́A���̈ϑ��҂̌v�Z�ɌW����̂Ƃ��ē��Y���v�@�l���̎��v���ƂƂ��Ȃ����̂Ƃ���B(��)
��c���^�@�l���P�|�P�|11 �̊m�F���Ă���ꍇ�ɂ́A�{���̊m�F��������
�Ƃ݂Ȃ��B
�y��P �@�l�Ŋ�{�ʒB�W�z�i���v���Ƃ��s���Ă��Ȃ����Ƃ̔����j1�| 1�| 1 1 ��ʎВc�@�l���͈�ʍ��c�@�l�i���v�Вc�@�l���͌��v���c�@�l�������B�ȉ��P�|�P�|11 �ɂ����āu��ʎВc�@�l���v�Ƃ����B�j���A���������̎���̐�����L����Ɩ����s���ꍇ�ɂ����āA���Y�Ɩ����@�߂̋K��A�s�������̎w�����͓��Y�Ɩ��Ɋւ���K���A�K��Ⴕ���͌_��Ɋ�Â�����ُ��i���̈ϑ��ɂ��ϑ��҂������z�����Y�Ɩ��̂��߂ɕK�v�Ȕ�p�̊z���Ȃ����Ƃ������B�j�ɂ��s������̂ł���A���A���̂��Ƃɂ����炩���߈��̊��ԁi�����ނ˂T�N�ȓ��̊��ԂƂ���B�j�������������Ŗ������i���ŋǂ̒����ۏ��ǖ@�l�ɂ����ẮA�������ŋǒ��j�̊m�F�����Ƃ��́A���̊m�F�������Ԃɂ��ẮA���Y�Ɩ��́A���̈ϑ��҂̌v�Z�ɌW����̂Ƃ��A���Y��ʎВc�@�l���̎��v���ƂƂ��Ȃ����̂Ƃ��ėߑ�R���Q����R���s��c���^�@�l�͈̔́t�̗v���ɊY�����邩�ǂ����̔�����s�����ƂƂ���B
�y�݂Ȃ���t�����x�z
�@���v�@�l���́A�@�l�Ŗ@��̎��v���Ƃɂ���ē������������v����(���v����)�̂��߂ɏ[�����邪�A���v���ƂɌW�鎑�Y�̂����������v���Ƃ̂��߂Ɏx�o�������z������ꍇ�ɂ́A��������v���ƂɌW���t���Ƃ݂Ȃ��đ����Z������ƂƂ��ɁA�����Z�����x�z�̌v�Z���s�����ƂƂ���Ă���(�@�l�Ŗ@37���S��)�B
�@���݂̂Ȃ���t���̑����Z�����x�z�́A���@�@�l(���c�@�l�A�Вc�@�l)��20���A�w�Z�@�l�A�Љ���@�l�A�X���ی�@�l��50���ł���B
| �����O�r�[����\���R��w�E�����(2007�N05��24��) |
|
���O�r�[�̊���w���[�O�Ȃǂ̑�����Â���u�����O�r�[�t�b�g�{�[������v�i���s�j����㍑�ŋǂ̐Ŗ��������A�O�T�N�x�܂ł̂T�N�ԂŖ�P���Q�T�O�O���~�̐\���R����w�E���ꂽ���Ƃ��킩�����B���ŋǂ́A���̓��ꗿ�����Ȃǂ��ېőΏۂ̎��v�ƔF�肵�A���\�����Z�ł��܂ߖ�S�O�O�O���~��ǒ��ېł����B
�@�W�҂ɂ��ƁA����͎�Î����̓��ꗿ��L��������o������������A�o��`�[���ɂ���t�����o���������łO�T�N�x���̗]�������P���~�������B�]��������z�ɂȂ邱�ƂȂǂ���A���ŋǂ͑��^�c�����v���Ƃ́u���s�Ɓv�ɂ�����Ɣ��f�����B����̓��O�r�[�̕��y�Ȃǂ�ړI�Ɋ������A�Ŗ@��́u�l�i�̂Ȃ��Вc�v�ɂ�����B
�@����S���҂́u���v�ړI�̊����Ŕ[�ł͕s�v�ƍl���Ă������A�w�E�ɏ]���Ĕ[�ł����v�Ƃ����B�iAsahi com �j���[�X�@�Q�Ɓj
|
������ɂ��ẮA�Ŗ����́u���E�n�������c�̂�����E���v�@�l��������� �v���Q�Ƃ��Ă��������B
���F��v�m�E�ŗ��m�@���R��
�i�@�l�̎ЊO�Ď��ł�����j
Tel 047-346-5214 Fax 047-346-9636
E-mail�F yokoyama-a@hi-ho.ne.jp
���̃y�[�W�̃g�b�v�֖߂��@�@�z�[���y�[�W�֖߂�