
����̎��X�̏�i��v���Ȃǂ��Â��Ă��܂��E�E�E

�h�m�c�d�w�i�ڎ��j�̕\��
�T�O�O�n�V�������O�n�ɑ�����YouTube�ɃA�b�v���܂���

���s���ɔ����������`�p���^�O���t�̗����̒����ƁA�⏕�p���^�O���t�̍đg���āE�E�E
���`�p���^�O���t�̉E���J�o�[���ɁA�܂肽���܂�Ă���̂��⏕�p���^�O���t�ŃV���[�������Ă��܂�
�ق��̐V�����ԗ��̃p���^�O���t�͋����ˏ㏸���ł����A���^�p���^�O���t��
��C�㏸�����̗p���Ă��āA�����Ԃ̒�d�Ȃǂɂ��ԗ��̈��k��C�����������ꍇ��
�p���^�O���t�����R�~�����A�ی�ڒn�X�C�b�`�i�d�f�r�j�ɂ��ː��n����
�ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�d�f�r�p�ɂˏ㏸���̗\���V���O���A�[���p���^�O���t��
�V�q�J�o�[���ɐ݂��Ă��܂�
���̃p���^�O���t�̐����ƃV���[�Ȃǂ��C�������܂���
�i�t�q�ł͎g�p���邱�Ƃ͂���܂���̂ŁA�_�~�[�ł̎�t�ƂȂ�܂�
�Q�O�Q�U�N�������ɉ^�s�����ߓS�A�[�o�����C�i�[��
�W�Q�n�R�A���}�u�܂����v��
YouTube������B�e���Ă��āA�v���Ԃ��
�O�n�V���������点�Ă݂܂���
�u�܂����v�Ɠ����ɂO�n�V������������B�e���܂����E�E�E
�������^�s�́u�܂����v�����ҏW��YouTube�ɃA�b�v�������ł�
�O�n�V�����̓�����ҏW���Ă݂܂����E�E�E
�B�肽�߂��O�n�̓��悪�A�߂��炵�������Ȃ��Ă��āE�E�E
�P�Q���ƒZ���i�t�q�̂g�n�Q�[�W�^�s�H���ł̑��s�ҏW�ɋ�J���܂���
���A�ҏW���I���ƁA�ĊO���Ă��Ă�������������ɁE�E�E
�Ȃ̂ŁAYouTube���O�n�V������ �A�b�v���܂����E�E�E���E�߂ł�(��)
�O�n�V�����́A���`���̊����i�ŁA�p���t���b�g�������Ďv�킸��т�
�i�t�q�Ŋy�ɉ^�]�ł���悤�ɒZ���U���Ґ��ōw���������̂ł��E�E�E��
���ꂪ��J�̎n�܂�ł����E�E�E
�ԗ��̃J�v���[�i�A����j���ʓd�J�v���[�ŁE�E�E
�E�E�E���͎ԂɘA�����Ȃ��Ƒ��̎ԗ��̎������Ȃǂ��_�����Ȃ��E�E�E
�E�E�E�A���͐��H��ŃX���[�Y�ɂ����Ȃ��E�E�E
�E�E�E��������ɂ͂Ȃ�ƕҐ����Ɛ��H����~�낵�ĉ��|�����Ă���E�E�E
�E�E�E�p���^�O���t���A�ː��ɓ͂��Ȃ��E�E�E
�ȂǂȂǖ�肪�����ς��ł���
���̂O�n�V���������K�ɑ��s���铮��́A�����g�����Ă��Ċy�����ł��E�E�E
���Ȗ����ł����ˁE�E�E
�����̋�J�H��
�O�n�V�����p���^�O���t
�O�n�V�����A�������
�ŁA���Ă݂Ă��������E�E�E
2026/�@1
�M���t���@�̍H�������������Ƃ���ɂP�Ԑ��i�R����ԁj�̏o���M�����̏�ł�
�ԐF�����̂܂܂ł��E�E�E�p�d��͐���ɓ��삵�Ă���̂ŁA�{���͐F�����ł�
�����͌p�d�킩��̐�ւ��X�C�b�`��H���s�ǂƂ킩��܂����E�E�E
�V������H���������ĕ������܂������A��͂�o�N�ł����E�E�E
�S���͌^���ĕ��ʂ��ԗ��̐����E�E�E�ł��傤��
�����̂Ƃ��떲�S���i�t�q�́A�M���Ȃǐݔ��H��������ł��E�E�E
���������ԗ������S�ɑ��点�邽�߂̍�Ƃł��ˁE�E�E
�����̂̂����~�S�����Ȃ������������v���o���������ł��i�j
-----�i�H�\���@��ݒu���܂���-----
�i�H�\���@�́A�|�C���g�i�����j�̎�O�ɐݒu���ꂽ�M���@���Ή�����
�J�ʕ����i�i�H�j��\������M�������@�ł��E�E�E
����A�o���A�����A�����A���p�M���@�ɕ������܂��E�E�E
�@���p�M���@
 �O���M��
�O���M��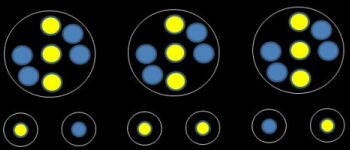
���̑����ց@�@�@�@�{���ց@�@�@�@�E�������@�@�@�@
���p�M���@�i�F�����j�̉����ɐݒu���Ă���Q���i�H�\���@�ł�
�����i�|�C���g�j����\������Ă���i�H��\�����Ă��܂��E�E�E
���S�Ȃǂ́A�{���i�H���\������Ă���ꍇ�͂Q���Ƃ��_�����܂�


�i�t�q�ł́A�{���\���͎g�p���܂���
�_�����Ă��鑤���i���ł�����H�ɂȂ�悤�ɐݒ肵�Ă��܂�
�w�̏o���M���̒��p�͗�Ԃ̗L���ɂ�����炸�\������邩��ŁE�E�E
���s���Ă�����Ԃ��i�H�\���Ȃ����p�M���݂̂ő��s�����
��Ԓ�Ԓ��̐��H�ɓ������邨���ꂪ����܂����E�E�E
���S�̂��߂ɂ͖{���K�{�ł����E�E�E

�`�s�r�i������Ԓ�~���u�j �̌x��x�������삵�x��{�^�����m�F����
�Ȃ̂ɁE�E�E�܂��x��x�����E�E�E
�`�s�r�́A�T�b�ȓ��Ɋm�F���������Ȃ����
�����I�ɗ�Ԃ͒�~�������܂�
�T�b�ȓ��Ɋm�F������s���ƌx���x������`���C���ɂȂ�
���̂܂܉^�]���p����������ʒu�Œ�~������菇�ł��E�E�E
�������Ăьx��x���Ō��ǁA���Ԓ��߂ƂȂ��Ԃ͎�����~���܂���
����ɁA���̂܂܉^�]�̌p�����ł��Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E
�{���`�s�r�n��q�́A��x���삷��Ƃ��̌ケ�̒n��q��
�����ɂȂ�ݒ�Ȃ̂ɁA���̂��L���ɂȂ��Ă��ĕҐ����ʉ߂���܂�
�J��Ԃ��x���o����Ă��܂����E�E�E
�O�����ԐM���͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�����I�ɒ�~�������Ă��܂����E�E�E
�`�s�r��H��_�����������s�ǂ̌��������炸
���ǃ����^�C���̋����Ւf�H���x���H�ɐݒ肵�ĉ^�]�ĊJ�ł��E�E�E
����Ȃ`�s�r����ɕ��A�͂������̂̉�H�s�ǂ��ǂ��ɂ���̂�
�o�N�̉�H�_���ɁA���炭�͋�J�������ł��E�E�E
�����̔��@�E�E�E
�F�c�ԗ��̉^�]������ɍs���܂����E�E�E
�W���~�S���̂ł��������C�A�E�g�Ɉ��|����܂������A������
�w��i�̃Z�N�V�����͌^���W������Ă��܂����E�E�E��
���̉w���ɍ��ꂽ�����̔��@�Ɏv�킸�����t�����܂���
�i�t�q�ł��A��߂Ƃ��w�O�Ɏ��̋@��ݒu���悤�ƁE�E�E
���[�J�[�e�Ђ̃T�C�Y�ȂǂׁA��������Ď��Ő��삵�܂���

�����̏Ɩ��ɍŏ��R���̃e�[�v�k�d�c�𗘗p�����̂ŁA���̋@���R��
���[�J�[�R�Ђ̎����̔��@��ݒu���Ă݂܂����E�E�E
�������S�~�����킷�ꂸ��(��)�ł�
2025/12
���炭�^�]���Ȃ��ł����}���^�C�iMultiple Tie Tamper)
���^�{�^���d�r�œ_�������Ă���ԓ��̂k�d�c�����������܂܂ł�
��H���m�F���Ă��Ƃ��Ɉُ�͖����A�X�C�b�`�����̐ڐG�s�ǂł���


�d�C�ړ_�����������u���������ŁA����Ȃɂ��ȒP�ɒʓd�s�ǂɂȂ�Ƃ́E�E�E
���^�̈����ȃf�B�b�v�X�C�b�`������Ȃ̂ł��傤���E�E�E�Ȍ�͕p�ɂɁH
�_��������悤�ɁE�E�E�Ǝv���Ă��܂�
2025/11
�d�e�P�T�֑��s���u���ڐ݂����d�e�T�W�̑�ւ��@�Ƃ��ď�z�^�d�g����
�����Ђ��������́@�d�e�T�W�P�O�T�@�j�`�s�n�������܂����E�E�E
�i�t�q�H��łP�R�����Q�[�W���A�ː��W�d�@���������Ȃlj��C��o��E�E�E
���^�]�ŋC�ɂȂ����̂��A���ԕ����̌X�ł��E�E�E
���[�J�[�̂j�`�s�n���X������͔̂����Ă����悤�ŁA�l�b�g�Œ��ׂ��
�Ȃ�ƕ�C�p�̃A�b�Z���p�[�c���̔�����Ă��܂����E�E�E
�j�`�s�n�������Ă���Ȃ玖�O�ɉ��C�������i�ɂ�������̂ɁE�E�E
�Ƃ��v���܂������E�E�E
�������������Ŏ�ɓ��������i�́A�����炭�����o�ׂ̍ɕi�����E�E�E
�Ȃ̂Ő��S�~�̃A�b�Z���p�[�c����t�ĂƂ͂����Ȃ��̂��Ȃ��E�E�E�Ƃ�
�����Ƃ������i�Ȃ̂ŁA���ʂ͂��̂܂܉^�]����̂ŁE�E�E�C�ɂȂ�Ȃ�����
�j�`�s�n�����ǂ�Ȍڋq��Ώۂɂ��Ă���̂��Ȃ��E�E�E
�A�b�Z���p�[�c�͎����ŕ���������l���Ώۂ��Ă��ƂȂ�ł��傤�E�E�E
���āA���ׂĂ݂�ƃA�b�Z���̃p�[�c�́A���b�V���[���Ɣ���
�\�����t�ł���ꏊ���m�F���ē���E�E�E
�莝���̃v�����g���ă��b�V���[�ɑ���p�[�c��A�������Ď�t�܂���

�������o���̎��^�]���ŁA�ēx�i�t�q�H��ŕ������Ē��������̂��E���ł�
2025/10
���삩��S�O�N�z���̂d�e�P�T���A���s���ɉ��h��Əu�ԓI�Z���������E�E�E
���������H���ɂ���̂ł͂ƁA�ې���ƂŐ��H�̓_�������{�E�E�E
���������ɐ��H�Ɉُ���Ȃ��A�^�p���J�n����ƕʂ̌��ł��Z��������
�ԗ������≏���H�Ɣ����ȓ��ւ̐U����������������Ɏ��炸
���������\��������ꏊ�⓮�ւ̒������J��Ԃ��Ă��邤����
�X�|�[�N���ւ̗S���͂����Ȃnjo�N�ɂƂ��Ȃ��̏Ⴊ�����E�E�E
�������Ă͒����Ƒg���Ď��^�]���J��Ԃ����ƂƂȂ����E�E�E

�C���T�C�h�M���̑g�����c�݂��E�E�E�����ɗ͂�������ƕ���E�E�E�o�N�ł�
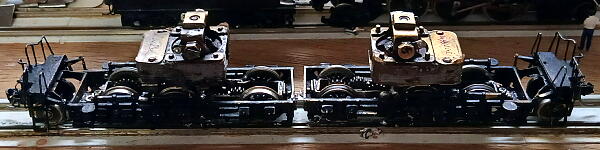
���[�^�[���s���ɂȂ�V�����\�����i�Ɍ������Đ���������A��͂�Z���E�E�E
�ǂ����S�̊O�ꂽ�X�|�[�N���ւ������Ƃ������邪�A���ʓI�ȑ�Ȃ�
�����ŁA�P�R�����ŗ]��̓V�ܓ��������i���d�e�T�W���瑖�s�n�S�̂�
�ڐ݂��v�����čl�����E�E�E�K�����Ԃ��d�e�T�W�Ƃd�e�P�T�̑�Ԃ������E�E�E

��́A�P�U�D�T�����̓V�ܓ����_�C�L���X�g�M�A�{�b�N�X�����P�R�����Q�[�W��
���͎���ŁA�C���T�C�h�M�A��g�ݍ��킹�āA�P�R�����Q�[�W�Ő��삵������
���̃C���T�C�h�M�A��Ԃ�P�����āA�V�ܓ����̃_�C�L���X�g��Ԃ����ł�


�藣�����d�e�P�T�̃f�b�L���d�e�T�W�̃_�C�L���X�g����ԂɎ�t�E�E�E
�ŁA�Ȃ�ƍ������E�E�E
���q�p�@�֎Ԃ̂d�e�T�W�̍����͕Б��R�Ȃ̂ɂd�e�P�T�͂U�ł��E�E�E
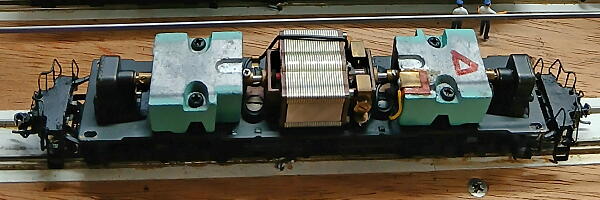
�d�e�T�W�̐��Ԃ�P�����A�V�����f�b�L���ڐ݂����V�ܓ��̓��͌n�ł�
���������������d�e�P�T�E�E�E�p���^�O���t���o�r�P�T�ւd�e�T�W����ڐ�

���^�]�̌��ʂ̓g���u�����Ȃ��A�ʏ�̉^�p�J�n����y���ɑ��s�ł��E�E�E
�p���^�O���t���o�r�P�S�����������O�̂d�e�P�T�E�E�E

2025/ 9
�C�ɂȂ��Ă����K�[�^�[�����o�[�W�����A�b�v�E�E�E
������E�E�E�K�[�^�[����ɂ�����W�߂������ɂ�
�����肪�ݒu���Ă���摜����������܂����E�E�E
���������̎�t���@��g�p����Ă���|�ނȂǕs���ȓ_������
�܂��͌�������ȗ������`��Ŋ��������܂����E�E�E
����͂i�t�q�H��œƎ��̐v���s�����������t�܂����E�E�E
���ۂƘ�����������������Ǝv���܂����E�E�E
����Ȃ�ɏo�����Ǝ������Ă��܂�



���Ȃ݂Ɍ�����̓��́E�E�E�������̖ԁE�E�E
2025/ 8
�N�����P�S�T�̃p���^�O���t�����s������E�E�E
�ː��W�d�։��H�ł���p���^�O���t�o�r�P�U�̊����i��͌^�X���߂ɂ����܂���
�\�肵�Ă������[�J�[�̍ɂ��Ȃ��A���X�l������\�Z�I�[�o�[�E�E�E�ł���
�ʃ��[�J�[�̐��i���Ȃ�Ƃ��Q�w�����܂����E�E�E
�����ڂ͂��̂Ȃ����i�ŃV���[�̉ː��Ή��������Ȃ��ł����̂̓��b�L�[�ł���
�ł��E�E�E���i�Ƀo���c�L���������悤�ŁA����͂������肵�����Ȃ��̂Ȃ̂�
�����̓p���^�O���t��g���Ȃ�Ɖ��H���ȒP�ɊO��Ă��܂��܂���
�E�E�E�͌^�X�ŊJ�����Ċm�F���Ȃ������E�E�E
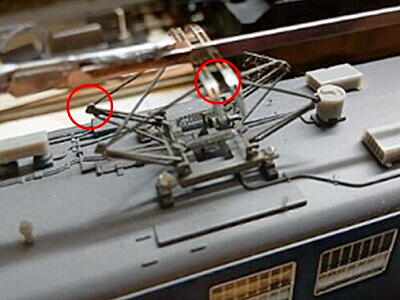
���̃p���^�O���t�͊��Ȃق��̐��i�ł��E�E�E
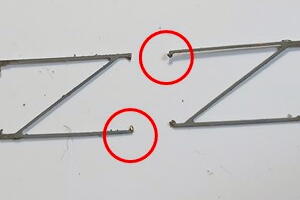
�ǂ����G�b�`���O�H���H�̂悤��
�q���W�������ɒ[�ɒZ���Ȃ��Ă��܂���
����I�ɓ_���������s���Ă����̂ł����A���̕Б��̃p���^�O���t��
���ɑ��s���͂���ė��������ł��E�E�E
�㑱�̉ݕ���Ԃ��x���Ȃǂ��炭�_�C�����݂���܂����E�E�E
�V���ɂȂ��ĂЂ��Ȃ��Ƃ����d�e�T�P�O�⊘���j�`�s�n�������i����
�P�R�����Ɖː��W�d�։������ē������܂����E�E�E

�j�`�s�n���̂d�e�T�P�O���P�R�����Q�[�W�Ɖː��W�d��
2025/ 7
���C�A�E�g�̐���J�n����Q�W�N�ɂȂ�܂��E�E�E
�P�R�D�R�����̘H�����g�����J��Ԃ� ���G�Ȕz���ɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E
�g���V�����P�U�D�T�����ŁA��߂Ƃ��w�������̂� ����Q�U�O�X�e�ł�
���s������H�͉w�\�����P�R�D�R�����Ƃ� �f���A���Q�[�W�i�R���j����ƂȂ�܂�

�摜�̂Ȃ��̎ԗ����N���b�N����Ƒ��s���悪����܂�
2025/ 6
���O�̉ː��I�[�ɂ��ݒu�����V���ȃe���V�����o�����T�[�E�E�E
�����͒������E�E�E
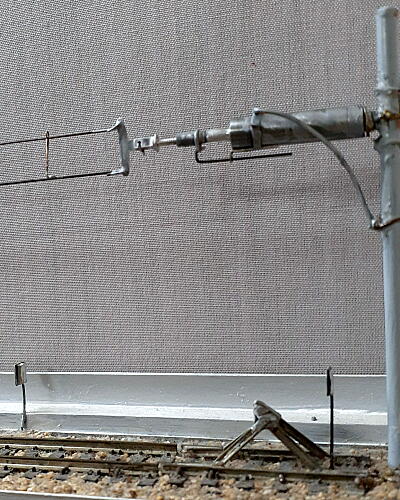
�R���������H�쏊����V���ɉ��ǔł̃e���V�����o�����T�[���͂��܂����E�E�E
�L�k�����������ɉ��ǂ��ꂽ�ː��e���V�����o�����T�[���Ăѐ��삵�Ă���܂����E�E�E
2025/ 5
�ː��I�[�ɐݒu�����e���V�����o�����T�[�E�E�E

�R���������H�쏊����Ɖː��̃g���u���ɂ��ĐF�X�b�������Ă��܂����E�E�E
�ː��̂���ݖh�~�ɁA���^�̃X�v�����O�Ńe���V�����������Ă���Ƃ����b����
�Ȃ�Ǝ������ː��e���V�����o�����T�[�̖͌^�삵�Ă���܂����E�E�E
�������X�v�����O���}������Ă��蓮�삵�܂�
���������W���O�Ԃ̏I�[�Ɏ�t���܂���

�ː��͉��x�Ȃǂ̕ω��ŐL�k���܂��E�E�E�����K���Ɉ�������̂ɕK�v�ȋ@��ł�

���^�X�v�����O�����H���Đݒu���Ă���i�t�q�̉ː��e���V�����o�����T�[�ł�
�����ԗ��Z���^�[�������ɐݒu�����|�̉ː��E�E�E

�|�̉ː��͒n���S���Ȃǂō��������̂���Ƃ���Ŏg�p����Ă�����̂ł��E�E�E
���ʂ̉ː��ƈ���āA�����ݔ����s�v�Ŏ������ɂ͍œK�ł��E�E�E
����ŁA�p���^�O���t�̓���m�F���ȒP�ɂȂ�܂���
2025/ 4
�x�����s�������@�U�U�{�ɑ����đ��Đ��������Q�W������z���܂����E�E�E
�����ŁA�U�U�{���W�������ʂɍĕ҂��܂���
�d�C�@�֎ԁE�E�E�E�E�E�P�T�{
�f�B�[�[���E���C�@�֎ԁ@�W�{
�����d�ԁE�E�E�E�E�E�E�P�S�{
���d�ԁE�V�����E�E�@�W�{
�C���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�@�V�{
����ԗ��E�E�E�E�E�E�E�@�R�{
���S�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�W�{
�O���ԗ��E�E�E�E�E�E�E�@�R�{
��Ԃ�������@�֎Ԃ��ƂɈ�̃W�������ɁE�E�E�ː������ԂȂǂ͓���ԗ��ł�
�z�[���y�[�W�����ł��{�����₷���Ǝv���Ă��܂����E�E�E
�ǂ�ǂ�y�[�W�������Ă����܂��E�E�E
2025/ 3
���q�ɏ���ė�Ԃ���H�ɓ������Ă���ƁA�z�[�����O�a��ԂɁE�E�E
�P�E�Q�ԃz�[����������֏o��������Ԃ́A�R�E�S�ԃz�[���֖߂��Ă��܂�
���̎��A�ʉߗ�Ԃ̑Ҕ��Ȃǂ��\�ɂȂ��Ă��܂��E�E�E
���ۂ̘H���Ƃ͈Ⴂ�܂����E�E�E�T�O�}�ł�
�}���N���b�N����Ǝ��ۂ̘H���}������܂�
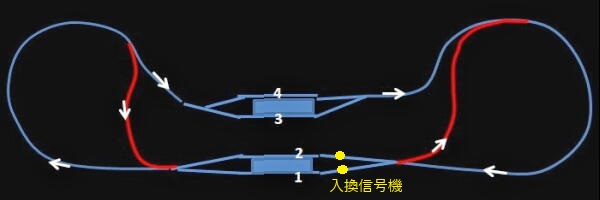
�������@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�������
�������A���łɂR�D�S�Ԑ��ɗ�Ԃ���Ԃ��Ă���ꍇ�ɁA�P�E�Q�Ԑ�����
��ԂԂ����邱�Ƃ��ł��܂���ł����E�E�E
�����ŁA�P�E�Q�Ԑ����甭�Ԃ�����Ԃ́A�A�����ʉ߂̂��Ɠn��|�C���g��
���o�[�X������ƁA�܂��P�E�Q�Ԑ��ɖ߂邱�Ƃ��ł��܂��E�E�E
�E�E�E�Ԃ̐��i�������܂��E�E�E
���o�[�X������Ԃ̐i�s�����͋t�ŁA������֔��Ԃ�����K�v������܂�
�K���A������g���l���̒��ɋ@�֎ԕ����]���p�̓n��|�C���g������܂�
����𗘗p����ƁA�Ăу��o�[�X���ĂP�E�Q�Ԑ��ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł��܂�
�E�E�E��������͋t�s�ɂȂ�̂ŁA�Ԃ̐��i�������܂��E�E�E
�����ɂ́A�F�����o���M��������܂����A���̉^�]�p�̉�����ɂ͐M��������܂���
�����łP�E�Q�Ԑ�������ւ̑��ԗp�ɁA���ꂼ������M���@��ݒu���܂���
�{���^�p�Ȃ̂ŁA�Q�����c�^�M���Ƃ��Ă��܂��E�E�E

�W�O���̂P�Ƃ����Ă����ǂ͏��������āA���̋Z�p�ł͓_��������Ƃ���܂ł�
�ł��܂���E�E�E�_�~�[�ƂȂ��Ă��܂��܂������A���͋C�͏[���y���߂܂�
�S�W�N���s���Ă����d�e�U�S�̑O�Ɠ��̕Б��������܂����E�E�E
�����d���̋ʐ�ł����E�E�E
�����V�[���h�r�[���ƌĂꂽ���a�T�C�Y�����^�̃��C�g�ł�
��i�P�Q�u�̓d���́A���a�R�����ŕė����ƌĂꂽ���̂���ʓI�ł���
�����ŁA�V�[���h�r�[���ɑΉ����Đ���ׂ����������Y������������Ă��܂���
�ė����̃X�g�b�N�͂���̂ł����A�c�O�Ȃ��炱�̃����Y���͂���܂���
���݂̖͌^�́A�k�d�c�����ʂȂ̂Ń����Y������ɓ���邱�Ƃ͂܂������ł��E�E�E
����ɓ����悤�ȃT�C�Y�̂k�d�c���Ȃ��A���ԈˑR�̎ԗ��ɐV���Ɏ�ɓ���k�d�c��
���H���đg�ݍ��ނ̂��E�E�E����ς�A�s�\�ɋ߂��ł�
�Ȃ̂ŒP���ɕė�����g�ݍ��ނ��ƂɁE�E�E
�����Y�̑���Ɍ��t�@�C�o�[��ؒf���ĉ��H�ł��E�E�E

�����Y�����ɒZ���J�b�g�������t�@�C�o�[���g���܂�


�����Y�����g�p���Ă������̑O�Ɠ��@�@�@�@�@�@�@�@���t�@�C�o�[�ƕė����։����o�[�W����

�Ԃ̃v���X�`�b�N�������͌������ė���
2025/ 2
�ԗ������́A�ԗ���ԗ����i�E���u�̏�ԁA��
���Փx�����������������S���s�Ɏx��̂Ȃ��悤�ɕ�C���s���܂�
�͌^���E�ł����̌����͌������܂���E�E�E
�����č��S�ł́A�قƂ�ǖ������R�`�P�O�����Ǝ��{�����
�d�ƌ����i�q�ݎԂ͗�Ԍ����j
�P�`�R�����܂��͑��s�R���j����
��Ԍ����i�q�ݎԂ͎d�������j
�@�֎Ԃ�d�Ԃ́A�U�����Ł@�Ǖ������@�Ȃǂ��K�肳��Ă���
���S�^�s���ۂ���Ă��܂����E�E�E
�S�N�܂��͑��s�U�O���j���ōs���@ �d�v������ �@��
�ԗ������ē��͔������u�A���s���u�A�u���[�L���u�A�v��Ȃ�
�d�v�ȑ��u�̎�v�������������܂�
�W�N�ōs���@�S�ʌ��� �@��
�p���^�O���t�A��ԁA�ԗւȂǎԗ��̎�v���������O���đ����I��
���ׂ�ł��傪����Ȍ��������{���܂��E�E�E
�i�t�q�ł��A�d�ƁE��Ԍ����͉^�]���ɂ��̓s�x���{���Ă��܂���
���s�����͌v���ł��Ȃ��̂ŁA�S�ԗ��Ƃ��@�S�N�@�Ł@ �d�v������
�W�N�Ł@�S�ʌ��� �@�����{���邱�ƂƂ��Ă��܂��E�E�E
�ۗL�S�W�W���̌������Ԍv����
�G�N�Z�����g�����������Ԍv���V�X�e�������Ă��܂�
�ȑO�́A�ԗ������L�^�\�����X�Ɋm�F���Č����v������ĂĎ��{���Ă��܂�����
�������Ԃ��Ă��Ă��C�Â������̂܂܉^�s���Ă����Ƃ������Ƃ�����܂���
���́A�V�X�e�����ғ�������ƁA�������{�P�����O���v�����\����
���Ԃ�����Ԏ��Ōo�ߓ�����������܂�
�Ԏ��ɂȂ�Ή^�s��~�ő��₩�Ɍ������邱�ƂƂȂ肷�E�E�E���S�̂��߂�
2025/ 1
���Ԃ��Ă���Ƃ���ς�M�����C�ɂȂ�܂��E�E�E
�����ŁA�����M���@�삵�Đݒu���܂���
�W�O���̈�̓����M���@�͑傫���T�������x�E�E�E
���̎��̔\�͂ł͎��ۂɓ_�������삳���邱�Ƃ͂ł��܂���E�E�E
���ǃ_�~�[�ł�
���������A�����́A�ԈႢ�Ȃ��A�b�v���܂����E�E�E
�_���ł��Ȃ��͉̂������̂ŁA�����Y�����Ɍ��t�@�C�o�[������܂����E�E�E
����Ɍ���������Γ_�����Ă���悤�ɂ݂��܂��E�E�E

2024/12
�d�Ԏ������̃e�[�v�k�d�c�֒�R�����t��H�����������܂���
����ł���ԃ��[�h�ʼn^�]����ƁA����ς薾�邢�E�E�E

�����H�������������P�S�T���ڂ̂S�W�T�n�E�E�E
2024/11
�d�Ԃ̎��������e�[�v�k�d�c�֒u�������鐮����Ƃ����������̂ł���
��ԃ��[�h�ʼn^�]���ĉ��߂Ă��̖��邳�ɁE�E�E
���s������J��Ԃ��ĂȂ�Ƃ����ǂ蒅�����P�x������Ƃł��E�E�E

�P�P�R�n�̖��邷���鎺�����ɔ�ׂč����̒����ς݂̂P�P�T�n�E�E�E
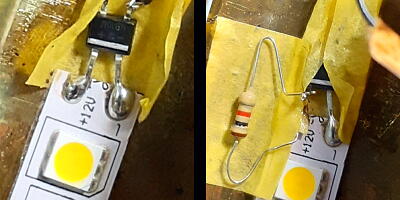
�k�d�c�e�[�v�Ɏ�t�������^�_�C�I�[�h�u���b�W�� �P�����@�O�D�Q�T�v �̒�R���lj�
�ȒP�ȉ��H�łȂ�Ƃ��[���ł���P�x�֒����ł��܂����E�E�E
���E�E�E���ꂩ���P�S�O���ɂP�{����R��lj������Ƃ��l����ƁE�E�E(��)
2024/10
�͂��݁H�Ƃ��������q�ɂ̂���YouTube�����L�n�P�W�P�n���}�u�₭���v��
�P�U�T�n��z�}�s�u���n�v�ɑ����ăA�b�v���܂����E�E�E
����B�e�̃A�C�f�A���������̓s�x�B�肽�߂Ă����摜����C�ɕҏW���܂����E�E�E
�B�e���Ȃ�����g���u�������ƏC���ɒǂ��Ă����̂�����ł����A�C���t����
�A�b�v����YouTube���悪�A�T�U�{�ɂ��Ȃ��Ă��܂����E�E�E
�̂�?����́A���ׂĈꔭ�B��ŕҏW�����ł��E�E�E
���܂���l����Ɖ��x���B�蒼���C�͂Ƃ������p���[����������ł��ˁi�j
�d�e�U�S�̂O�ԑ���d�A �ő��点�܂����B�ŏ��̓R���e�i���Z�łT�O�O�g���ݕ�
�Q�O���Ґ���g��ł����̂ł����A�i�t�q�̐M���V�X�e�����Ή��ł��܂���ł���
�ǐM����Ԃ̂P�u���b�N�ݒ苗�����R�D�T���Ȃ̂ŁA�P�S�������E�ƂȂ��Ă��܂��܂���
�P�S���Ȃ�@�֎Ԃ��d�A�ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł����E�E�E�����͖͌^���E�i�j
���s���{�[���ƒ��߂Ă��Đ̂̃�������̂Q���ݎԂ��������i�����������Ȃ���
�Ґ����l���Ă������ɁA��͂�̖̂�s��ԂŃI�[�v���f�b�L�̋��^�q�Ԃ��v���o���܂���
�Èł��P���S����n�鎞�ɁA�[���ł̐�ɊC�������āu������E�E�E�v��
�̂ɓݍs��Ԃŗ��������v���o�����n���̂悤�ɕ�����ł��܂����E�E�E
�ŁA���a�T�T�i�P�X�W�O�j�N����̉��������ݍs��ԁA�������s�E�E�E
���s�����o�_�Ԃ̖�s���ʗ�Ԃła�Q��A���́u�R�A�v ���Č��ł�
����A�����i�̉��������킹�Ď莝���̎ԗ��ŁA�����̃t���Ґ��i�X���j��g�ނ��Ƃ��ł��܂���
�������̂́A���܂܂łP�����������߂Ă��Ȃ������̂ɁA�Ґ���g��Œ��߂�ƍ��E�̎ԗ���
�����ɈႤ�E�E�E�Ȃ�Ɠ����`���̋q�Ԃ��S��������̂ɈႤ�̂ł��E�E�E�K���Ƀf�t�H�����H�H�H
���ꂼ��ɉ��\�N���O�Ɏ���Ɩ͌^�e���[�J�[�������������ԗ��ł��E�E�E�l�����Ȃ����Ƃł���
YouTube����ɃA�b�v ���܂������A�E�B���h�V����w�b�_�[�̍����������Ă��Ȃ��ȂǂȂ�
�A�b�v���Ă���A�������肵�Ă��܂��E�E�E
2024/ 9
�^�Ă̐M���̏�E�E�E
�M����H���m�F����ƌo�N�ɂ�郊���[�i�p�d��j�̐ڐG�s�ǂ��ꕔ�������C�E�E�E
����ŕ�������͂��Ȃ̂ɁA����x���o���M���́u�ԁv�̂܂ܑS���ς��Ȃ��E�E�E
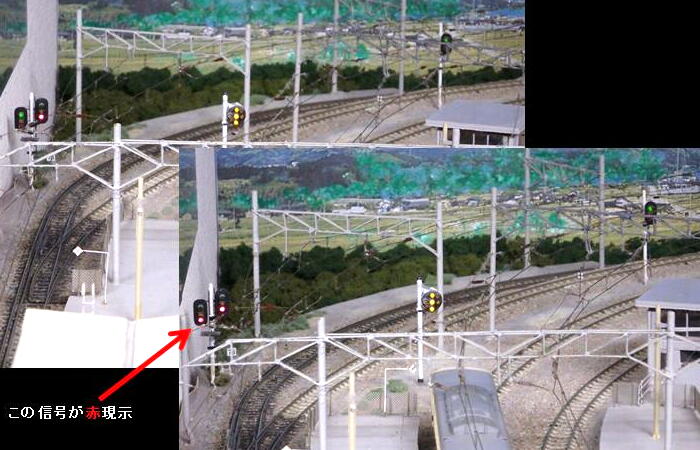
�e�X�^�[��Ў�ɉ�H�_�����J��Ԃ����A�ق��Ɍ̏�ӏ��͔����ł��Ȃ��E�E�E������߂�
�o�N�Ǝv����ԐF�M���p�����[�i�p�d��j���̂��̂���������i���ŕ��i��p�ӁE�E�E
���C�ɐF�M���p�����[���蓮�Ő�ւ����Ƃ��� �M�������E�E�E
�F�M�������[���g���u����
��H�S�ʂ������ɕ����I�Ɍ��������Ă����ƍ�Ƃ��Ă����̂��ԈႢ��
�L����������S���ɓ_�����ׂ��ł����E�E�E�luu
�����܂łQ���Ԃ̋��ł����E�E�E
�T�C�Y�ȂNjK�i �̒��ɕ\�����Ă��� ���Ђ̐��H�} �Ɉꕔ�摜�������N���܂���
���H�}��Ń}�E�X���N���b�N����A���̕����̉摜�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂���
2024/ 8
��߂Ƃ��w�O�́A�������i�����j�o�X�������Ă��܂��E�E�E
�V���̘A�x�ɂ͘H���o�X�Ƌ������Ĉꎞ���G(��)�ł��E�E�E

����ȕ��i���E�E�E

�R�c�v�����^�[�Ő��삳�ꂽ���o�C�ƌx�@���E�E�E
����̃t�B�M���A�Ɣ�ׂ�Ɛ���������R�ł��E�E�E
2024/ 7
����悠���Ǝ��͉߂�����܂��E�E�E
���������e�i���X�ɒǂ��C���t���U���Q�X���łQ�V���N�E�E�E
�i�t�q�͂��ꂩ����u���S���v�ő��葱���܂��E�E�E

�L�O��Ԃ͕��������b�T�W�ɂ��u�r�k��߂Ƃ����ʍ��v�ł�

�b�T�W�́A�ȈՃu���X�g���Ɣ������u��ύڂ��Ă��܂��E�E�E
�u���X�g���́A���ւP��]�ɂS��̂����Ԃł����A�ȈՃu���X�g�͓��ւɔ����p�̒[�q
�i�R���^�N�g�j���P�ӏ���������܂���E�E�E�Ȃ̂ł��̂܂ܓ��ւP��]�Ƀu���X�g���P��ł�
�ǂ����Ă��C�ɂȂ�̂ŁA���ւP��]�Ƀu���X�g�����Q��������������s���܂����E�E�E
�ŐV�̂c�b�b�T�E���h�Ȃǂɂ͋y�т܂��A�������ł����͋C�����͂Ȃ�Ƃ����킦��E�E�E
���Ȃ��E�E�E(�L;��;�M)
�������u�͒�i�d�����P�O�`�P�U�X�Ȃ̂ŁA���u�����܂蔭�����J�n����܂ŃG���h���X��
�����i���d���j�Ő��点��K�v������܂����E�E�E
��� YouTube���� �B�e���ɂ�葽���̔��������߂đ��点�Ă���ƁE�E�E
���̊Ԃɂ��E�E�E�C�Â����Q�O�X�z���̓d���������Ă��܂��Ă��܂����E�E�E
���ʂ͔������u�đ��I�I�@�@�����x���E�E�E
�z����ύX���āA�����]�M�X�C�b�`����t�܂����E�E�E
����́A�P�Q�u�ŗ]�M���������J�n���Ă��瑖�s����������ɕύX�ł�
�]�M������̂Œᑬ�ł��������m�F�ł��܂����E�E�E
�r�g�t�s�g�d�]�C�e�̔������u�ł��B�R�X�g�͍�����Ԃ�������܂������A���ɂȂ�܂���
���Ԃ͉Γ���ʕ����ŏ��C���E�E�E�{�C���[�̈��͂��グ�Ȃ��Ɠ����܂���E�E�E
�ǂ������Ă����E�E�E
2024/ 6
�Ăыً}�ې��H���E�E�E

�ɘa�Ȑ�����}�Ȑ��֓���Ƃ���ŒE���ł��E�E�E
�����͂Ȃ�� �X���b�N�E�E�E��^�@�֎Ԃ�ʉ߂����邽�ߍL�������H���E�E�E
���̃X���b�N�E�E�E���I�[�o�[�X���b�N�Ő��H����ԗւ��E���E���ł�
��������~�݂������H�������E�E�E�H�H�H

�ً}�� �}���^�C ���������Ă̕ې���ƂƂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E
���K�̐i�s�����ł̒ʉߏo���Ă����̂ɁA��ނ����ċN�������̂͑O��̃J���g�Ɠ���
�͌^�̌Œ���H�ł������E�E�E����I�Ȑ��H�_���ƕې���Ƃ͌������܂���E�E�E

��������d�c�V�T�d�A�̃R���e�i��ԁE�E�E
�܂����S���͌^�ɐ݂����X���b�N�������Ȃ�āE�E�E
���Ԃ̕ې���ƁE�E�E�����e�i���X�̍���Ɏv�����͂��܂����E�E�E(��)
2024/ 5
�o�N���́A��͂�|���E�E�E
�ˑR�ɉ^�]�s�\�E�E�E�}�X�R�������삵�Ȃ��̂ŋً}��~
���̌�A��Ԃ͗\���̃{�����[���R���g���[���ʼn^�]�������̂�
�}�X�R��������������
�����̈�ԉ��Ńm�b�`��i�i������J���̃E�B���O������E�E�E
���삵�Ă���S�O�N�ȏ�E�E�E
�o�N�͊ԈႢ�Ȃ��̂ł��������ō�����V�X�e���������ł��Ȃ�
���̂����A�������i�����ɂ��v�}������܂���E�E�E
�ړI�̃J���E�B���O�́A���������u���b�N�̂���ɓ����ōH��͂��܂���E�E�E
�܂����⎩���ō�����p�Y���Ƃ̊i���ł��E�E�E
�g���l���E�E�E
�V�����g���l�����ђʂł��E�E�E

�����ԁE�E�E�o�b�N���[�h�̎Ԍɂ◯�u���A�A�����̐�ɂ̓_�C�������h�N���b�V���O��
�Ҕ���������āA�^�]�Ȃ���ԗ��̏o���ɂ�s�m�F�̂��߂ɐؒʂ�݂��Ă��܂������E�E�E
�A�����̃K�[�^�[������ؒʂ֑��蔲�����Ԃ����Ă���ƁA�ǂ��ɂ���a�����E�E�E
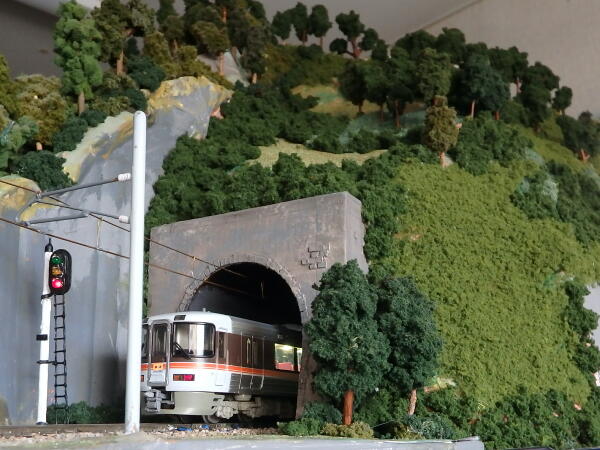
�v�����Đؒʂߗ��H�āi(��)�j�g���l�����ł�
2024/ 4
�x�����s�������ɓ���̑��Đ��������A�����Q�T�������܂����E�E�E
���ł�����E�E�E�̏Ⴊ�E�E�E�g���u�����o�ł�

�g�[�̌J��Ԃ��������ł��傤���A�ː����L�k���Ċɂ�ł��܂��܂���
�p���^�O���t���ɂː��������グ�āA�ː��̓V���[���犊�藎�������ł��E�E�E
�ː��̐ڑ������Ŕ��c���O���A�e���V�����������Ȃ����čĂє��c�t���łȂ�Ƃ������E�E�E
�ƁA�v������W���O�Ԃ̃��[�h�i���|�C���g���j���E�E�E
�g���O���[�������삵�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E
�㕔�ɂP�R�����̖{����A����������A�ː��������čH�����܂���E�E�E
���삷�鎞�ɏC���̂��ƂȂ�čl�����Ă܂���E�E�E��������ł�
�ꂩ���̔��c�t������蒼���ΏC���ł���̂ɁE�E�E
�H��B�����邽�߂ɁA�啝�ɕ����ł��E�E�E
2024/ 3
�ً}�ې��H���E�E�E
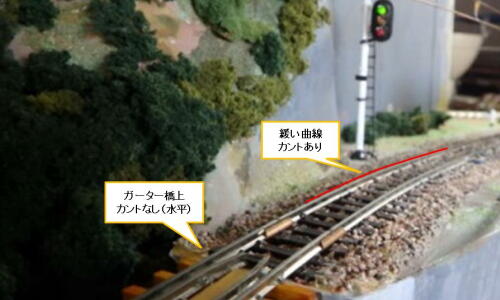
�Ȑ�����K�[�^�[���֖߂�Ƃ���ŒE���ł��E�E�E
�����͂Ȃ�ƂQ�O���ԗ��̑�ԃX�p���Ƃقړ�����̏�葤���[���� �J���g�E�E�E
���̃J���g�E�E�E�ŌX�����ԗ����K�[�^�[���Ń[���J���g�ɖ߂炸�E���ł�
�K�[�^�[���ɂ͂������J���g�͂��Ă��܂���E�E�E

���H�~�ݎ��ɐݒ肵���Ȑ��̃J���g���Ȃ�����������オ���Ă��܂����E�E�E
���K�̐i�s�����ł̒ʉ߂ɁA���̒��x�ł͎ԗւ̂���オ�肪�����Ă�
�E���ɂ͎��炸���ʂɒʉ߂ł��Ă��܂����E�E�E�Ƃ��낪�v�����������\�z�O��
�t���ł̏��s�́E�E�E�ԑ̌X�ł���オ�����ԗւ����Ƃ��ȒP�ɒE�������܂���
���ۂ̐��H�ł́A�o���X�g�Ń��[���̍���������̂ł����E�E�E
�i�t�q�̐��H�͖؍H�{���h�Ńo���X�g���Œ肵�Ă���̂Œ�����Ƃ͕s�\�E�E�E
�i�t�q�̕ې��H�@�͂P�O�O�v�i���b�g�j�̔��c�R�e�����[���ɉ������ĉ��M
�M�Ńv���X�`�b�N���̖���n�����Đ��H����������E�E�E�̂ł�
�����ēS���͌^�Ɉ��ՂɃJ���g������ƒE������E�E�E
�Ȃ�ăR�g�o���v���o���܂����E�E�E(��)
�Q�N�Ԃ�ɗF�c�ԗ�������}�V�O�O�O�n ���t���Ґ��i�W���j���������܂���
�i�t�q����}�W�O�O�O�n �́A�v���X�`�b�N���Ŏԑ̂��y����]�ɔY�܂��ꂽ������
�������Ȃnj����ԑ̂߂��ċ�J���܂����E�E�E
�������ɋ���������}�V�O�O�O�n�ԗ��͏d����������܂��B
�x�����s�������ɓ�����A�b�v���܂����E�E�E
2024/ 2
�x�����s�������ɓ�����A�b�v����ƁA �g�n�Q�[�W�Ƃ̃R�����g����������܂�
�K���p�S�X���{�̂W�O���̂P�K�i�ɁA���ەW���K�i�̂g�n�Q�[�W�i�W�V���̂P�j�̃��[����
�g�ݍ��킹�����Ƃ���̎v�����݂ł��傤�E�E�E
���ۂ̂Ƃ���A���[�������W���O�ԂȂ�P�S�R�T�����̂W�O���̂P��
�P�V�D�X�����ɂ��ׂ���������ł��E�E�E
���S�̋��O�P�O�U�V�������̗p���Ă���i�t�q�́A���ꂪ�䖝�ł����ɋ��O�̂W�O���̂P
�P�R�D�R�������̗p�����̂ł����E�E�E
���S�ȂǕW���O�Ԃ̎ԗ��𑖂点�邽�߂ɁA���ՂɂP�U�D�T�����Ƃ̕��p��Ԃ�
�݂������Ƃ����������E�E�E
�����ŁA�W�V���̂P�@���S�Ȃ�g�n�Q�[�W�ԗ����P�U�D�T������ɑ��点�܂����E�E�E
�h�C�c���S�̖��@�P�O�R�^�@�֎Ԃ�������s�d�d�Ґ��ł��E�E�E
�����������������̂́A�ː����E�E�E�ł�
���B�̓S���ɍ��킹��ɂ́A���ƂT�����͍������K�v�ł����i(��)�j
�M���p�̌p�d��i�����[�j���A�o�N�ɂ�������J�ŕ���ł�
�����[�̓d���œ��삷��S�S�ƃX�C�b�`���O�p���q���X�O�x�Őڑ�����
�O�D�T�������� �k�^�^�J�� ������������Ă܂����E�E�E
�㉺�o���M���ł܂����̓�������ł��E�E�E
�V�X�e���ُ펞�ɂ́A�u�ԐF�����v�ɐݒ肵�Ă���̂�
���̞��q���C������܂ŁA��Ԃ̉^�s�͂ł��܂���ł����E�E�E
��Ԏw�߂ɂ����S�m�F�Ŏ�M���ɂ��^�s���ꕔ���{���܂�����
�C���̍��Ԃł̑��Ԃɖ���������A���S�^�x�Ƃ��ĕ������}���܂����E�E�E
���q�̌����ɂ͑������Ԃ������邱�Ƃ���A���������ꂽ����
�������݂̐^�J�ŕ⋭�����c�Őڑ��E�E�E�Ȃ�Ƃ������ł��E�E�E
�T�O�N�߂��g�������Ă��鑕�u�E�E�E��͂胁���e�i���X�̋��������E�E�E
��͂Ȃ��̂ł��傤���E�E�E������̌p�d��i�����[�j�̑�ւ��i��
���ƂȂ��Ă͎�ɓ���܂���E�E�E(���j
���S�̂��߂ɁE�E�E
�������S���͌^�E�E�E����ǓS���͌^�E�E�E
�ː�����H����肱�ނ����ɁA�قڂقڎ��ۂ̓S���̂悤�Ȑ��E�ɁE�E�E
�}�Ȑ���ɒ���g�����[�������ꉺ��������A���[���̘c�݂����̂ցE�E�E
�J���g��X���b�N�ɔY�݈��S���s�֎��s����𖢂��ɑ����Ă��܂��E�E�E
�����i�t�q�ł͏����̒i�K������S���s�̂��߂�
�i�t�q�^�`�s�r�i���S�^�̂`�s�r-�r�j�����Ă��܂�
���̍��A�����̍��́A�������W���O�Ԃ��R����Ԃ�����܂���ł����E�E�E
���݂́A�P�R������W���O�ԁA�R����Ԃɂ����S��i�q�����łȂ�
���S�A�V�����A�O���ԗ����������Ă��܂��E�E�E
�V�������`�s�b�i������ԃR���g���[���j���A���S�ɂ͂��ꂼ��̉�ГƎ���
�`�s�r�i������Ԓ�~���u�j�����ۂɂ͑�������Ă��܂��E�E�E
�������O���ԗ������l�ł��E�E�E���A���ꂼ��̕�����Ǝ����i�t�q��
�J������������͖̂����Ȃ̂ŁA���̋�Ԃ̎ԗ����i�t�q�^�̉^�]�ۈ��@���
�ݒ�Ƒ������A�����`�ƒ����ԁ`�S�O���Ă��܂����E�E�E
�������W���O�Ԃ��g������^�]�p�x��������ƁA�|�C���g�̓]�Ă~�X�������E�E�E
�R����ԑ��s�W���O�Ԃ̎ԗ�������ĂP�R������Ԃi����
�E�����鎖�̂��N���܂����E�E�E
�����ŁA�`�i���̑�Ŏv�����Ďԗ��̎�ނɊW�Ȃ�
���ׂ��i�t�q�^�`�s�r�����邱�ƂƂ��܂����E�E�E
�������O���̃|�C���g�ɓ]�Ă~�X������A�M�����u�ԁv��������
���s���̎ԗ����`�s�r�����삷��悤�ɉ�H���\�����Ă��܂��E�E�E
�N���ɍ���x�̔z���p�Y��������Ă��܂��܂����i���j�E�E�E
���C�A�E�g�̉��ɂ����荞�݁A�g���V���ƂR����Ԃɔz�������{�����菄�点
�e�X�^�[��Ў�ɔ��c�t���E�E�E�v���Ԃ�ɃA�N���o�e�B�b�N�ȍ�Ƃł����E�E�E
�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
���ł́A��A�����猳�U����ƋߓS���I��^�]���s���Ă��܂�
�i�t�q��������}���^�s�����܂����E�E�E
����ɁA�_�b�̍� �o�_ �����āA��A���ɂc�c�T�S������̃u���[�g���C��
�Q����}�u�o�_�v���^�s���܂����E�E�E
YouTube �ɂ��A���s������A�b�v���܂����E�E�E
�Q�O�P�W�N�Q���ɁA�I���G���g�}�s�Ƃs�d�d�̑��s��������߂ăA�b�v���܂�����
���[�J���Ȗ͌^���E�������ł��������Ă��炦����E�E�E�Ƃ̎v���Ƃ͗�����
���������́A����ɐ��\���Ƃ������������Ă��܂����E�E�E
���X�ɃA�b�v���Ă�������ȓ��悪�A���ɑ�A���łS�P�{�ɂȂ�܂����E�E�E
�Ƃ��낪�A�ŋ߂́A����ɂT�O�O���ȏ�̎����������E�E�E�ق�Ƃɂт�����ł�
�����Ă��ɑ�A���Ɂ@�����������@�Q�O�����B���@�ł��E�E�E
2024/ 1
���������d�e�T�V�̎��^�]�Ŏx���̃A���_�[���[�h�֒ᑬ�Ői�������܂����E�E�E
�Ȃ�ƁE�E�E�|�C���g��Ő��Ԃ��E���E�E�E�}��~
�d�e�T�V�́A���z�u�� �Q+�b+�b+�Q�@
�a+�a+�a �̑�^�@�֎Ԃɔ�}�Ȑ��ʉ߂ɂ͒������K�v�ł������E�E�E
���̋�Ԃ́A���ɋ}�ȃ|�C���g�ł͂���܂���
�����ŁA�ʉߎ��т̂��铯�� �Q+�b+�b+�Q ���d�e�T�W�������Ői�������܂�����
�������Ȃ��ʉ߂ł��܂����E�E�E�|�C���g�g���u���͍l�����܂���E�E�E
�d�e�T�V�́A���Ԃ̎�t���@���d�e�T�W�Ƃ͈Ⴂ��Ԙg�̒��ō��E�ɓ����܂�
�E���ɂȂ���Ǝv������̒������J��Ԃ��܂������A�E���͎��܂�܂���E�E�E
�����s���Ń|�C���g���ē_���E�E�E�ォ�猩�Ă����|�C���g���p�x��ς��Č������܂���

�~�݂���S�����I���o�߂��A���X�̓_���ł��C���t���Ȃ������̂ł���
�Ȃ�� �t�����W�E�F�C�iFlange Way�j���ق�̏�������Ă����̂ł�
�d�e�T�V�̐��Ԃ́A���Ԃ��Z����ւ��t�����W�E�F�C�Œe�ݐ�ւˏグ�Ă��܂���
�ې���ƂŖ������d�e�T�V���������邱�ƂȂ��ʉ߂ł���悤�ɂȂ�܂�����
���܂܂łɈ�x�����̋�Ԃ𑖍s�����ĂȂ������H�H�H
�M�����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł��ˁE�E�E
�R���������H�쏊����W���C���g���i���������܂���

�������ɐV�������i����t�E�E�E���^�]������

�d�e�T�V�����ł��E�E�E
2023/12
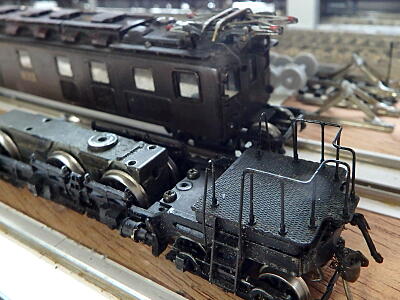

�T�O�N�ȏ㑖�点���d�e�T�V�ł��E�E�E
��ԊԂ̓��͓`�B�p���j�o�[�T���W���C���g������ł�
�d���v���H�������o�N�Ŋ�������W���C���g�����H�֗����E�E�E
�i�t�q�H��ɂd�e�T�V�̂��̃p�[�c�͔��i�������A�܂���ւ��i������܂���
�C���s�\�E�E�E�x���ł�

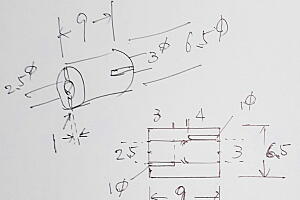
�Ή��s�\�Ŏv�Ă������� �R���������H�쏊 �ɏ��������߂܂����E�E�E
����E�E�E
�Q�ĂăW���C���g�p�C�v�}�����M�E�E�E�f�X

��߂Ƃ��w������ł��E�E�E
�@�֎Ԉ��グ�����N�����P�S�T�� �V�������U�O�T�O�n�A�b�T�W���E�E�E
�E�[���P�Ԑ��ŕW���O�Ƌ��O�̋��p��ԂŃ��[���R�����ł�
���̐�Ŋg���V���̕W���O�Ԃ֕��Ă����܂�
���̊Ԃɂ��A���菄�炵���ː������ɖԖڂ̗l�ɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E
2023/11
���S�^�s�̂��߂ɁE�E�E

�_�C�������h�N���b�V���O�̃��[���ɂ͉ː��v���X�ɑ���}�C�i�X��
�_����C���ԓ����s�p�̃v���X�E�}�C�i�X�̓d�������ꂼ�ꗬ��Ă��܂�
���̂܂܂ł̓V���[�g����̂ŁA�_�C�������h�N���b�V���O�����͑��s������
���E�̃��[���d����؊����Ă��܂��E�E�E
�؊������Ԉ���Ă��E���͂��܂��A�ԗ��͒�~���ē����Ȃ��Ȃ�܂�
���̂��ߐ؊�������v���Ȃ����ɁA�_�C�������h�N���b�V���O���O�M����
�ԐF�����ɂȂ�悤�ɉ��ǂ������܂����E�E�E
�摜�ł͐F�����Ȃ̂ŁA���̂܂ܘA��������i���\�ƂȂ�܂�
�������{���M���͐ԐF�������Ă��܂��E�E�E
�M���̐����ɂ��킹�āA�A�����p�`�s�r�n��q�̈ʒu���������܂����E�E�E
�������ł���������~�X�������悤�ɁE�E�E
�w�����ď��E�E�E�ł���
���H���ǍH���𑱂��Ă��܂��E�E�E
�X���Ɋ��������P�R������ԘA�����ɕ��s���Ďc����㗯�u���E�E�E
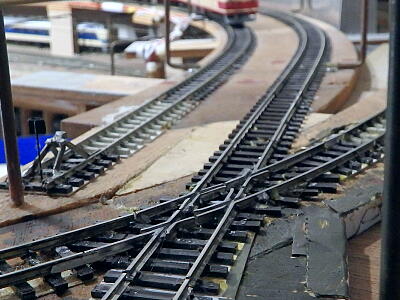
�Ԏ~�߂�P�����A�V�����|�C���g��ݒu�@�@�Ҕ�ʉߐ��ƂȂ�܂����E�E�E
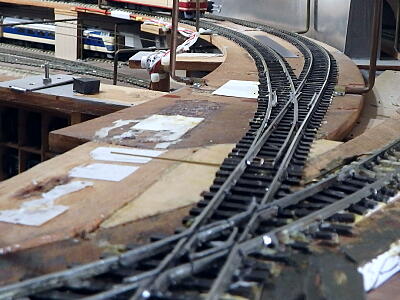
�|�C���g�ݒu��Ƃ̑O�ɂi�t�q�H��Ő��삵���p�[�c�̊m�F�ł��E�E�E

�ݒu�����������|�C���g�ł��E�E�E

�o�b�N���[�h�ɂȂ�̂ŁA�o���X�g�͏ȗ��@�ː��͒��݉ː������ł�
�V�ܓ����甭�����ꂽ�����S���U�O�T�O�n�f�B�X�v���C���f���ł��E�E�E

�P�U�D�T�����̃v���X�`�b�N���ԗցE�E�E���`���Ɛ��H�ɂ̂��Ă݂܂���
�W���O�Ԃ̐��H�ɓ����Ȃ���ԁE�E�E�v���X�`�b�N���p���^�O���t�E�E�E
�����E�E�E�i�t�q�ԗ��H��֓���ł�
���s�̂��� �P�R�����։��O ���[�^�[���g�ݍ��ݓ��͉�
�����ē_�����E�E�E
��Ԏ�ʂ�s��\�����������i�t�q�H������o��ł��E�E�E

���O�P�R������ ��߂Ƃ��w �֓������������U�O�T�O�n�E�E�E

�ː��W�d���ŋ������p���^�O���t�Ɍ������A�Ȕւ̔z�ǂ��lj��ł�

���͉��ɂ͂P�R�����։��O�������ԂQ�V�D�T�����̂l�o�M�����̗p�@�v������Ԏ��ɂ̓��^����ڒ�

���Ƃ̑�Ԃ����S�ɗ��p���邽�߂P�R�����։��O�����ԗւ͒Z���ƒ����̒��ԃT�C�Y�ł�
�����̂����� �z�� �������ł��E�E�E

�͌^���E�����������ł�������ł��E�E�E

�W���O�Ԃ̍�}�W�O�O�O�n�Ƌ��O�̓����U�O�T�O�n�ł��E�E�E

�u�����v�Ɓu��}�v�@�N���b�N����Ƃ��ꂼ��̑��s���悪����܂��E�E�E
��}�W�O�O�O�n�͂R����Ԃi�����܂��E�E�E
2023/10
���������A���V���E�E�E�^�p�J�n�ł��E�E�E
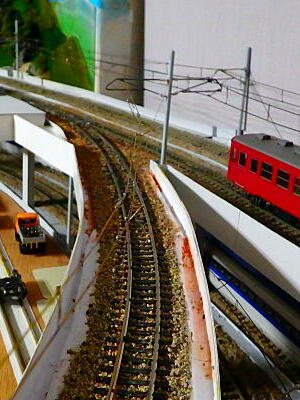

���ˈ���E���������番�܂��E�E�E�@�@�@���˕�������z��ցE�E�E


�z�炩��K�[�^�[����ʉ߂��{���ƕ��ʌ����E�E�E�{������ڑ����܂��E�E�E
�K�[�^�[���̉��E�E�E��������i���y����ł݂܂����E�E�E

�z��̉��͕W���O�Ԃ��J���g�����Ă��܂��E�E�E
������}�������Œʉ߂��Ă����܂��E�E�E

�W���O�Ԃ́A�z��̉���ʉ߂���ƁA�ɂ��Ȑ��ł�߂Ƃ��w�P�Ԑ���
�P�R�������P�U�D�T�����̕��p�R����� �i�f���A���Q�[�W�j�i�����܂��E�E�E

�z���́A�T�W�P�n�Q����}���J���g�Ŏԑ̂��X�����Ȃ���
�}�Ȑ���ʉ߂��Ă����܂��E�E�E

�z���́A�}���^�C����ƒ��ł��E�E�E
�ː��H�����������܂����E�E�E
�L���� ���{
�M���Ɠd�C�������p���L���P�X�P�n�ōs���܂���

�M���Ɠd�C�v�����L���P�X�P�n�ʼnː����̎������s���ł�

�M���̓���m�F�Œᑬ�ƍ����ŌJ��Ԃ��ʉ߂����܂��E�E�E

�L���P�X�O�̉���@��ł��E�E�E�p���^�O���t�v�����ɏ��^�J����������܂�

�J�����摜�͂Q�V����f�Ȃ̂ōr���ł����A�ː����m�F�ł��܂��E�E�E
�͌^���E�ł��L�����́A�d�v�Ȍ����E�E�E
�����āA�L���P�X�P�n�́A�ق�Ƃ��Ɏg������̗ǂ��ԗ��ł�
2023/ 9
�J���g�ƃX���b�N�ɂ��āE�E�E

�ʉߎ����ŋ}�Ȑ����������s���̂P�W�R�n�k�C���F�ł�

�܂����d���Ȃ̂ŁA���炭�̓f�B�[�[���Ԃʼn^�p�ł��E�E�E
�v�Z��ł͔��a�U�O�O�����̋Ȑ��ɂȂ�\��ł����E�E�E
�K�[�^�[���̉ˋ���A�����グ���̃|�C���g��ݒu���܂���
���ꂼ��Ɋɘa�Ȑ���݂��Ė{�Ȑ��ƂȂ�悤�Ƀ��[����~�݁E�E�E
������E�E�E�Ȃ�Ɩ{�Ȑ������a�T�T�O�����ցE�E�E
��^�d�C�@�֎Ԃœ��ւ��R���@�b�{�b �̒ʉ߂�����E�E�E
�J���g���ő�P�����i���ۂ̐��H�ł� �W�O���� �j�ɐݒ肵�܂���
����܂ł̂i�t�q�{���̃J���g�́A�ő�O�D�W�T�����i�U�W�����j�ł�
���Ȃ݂ɂi�q�i���S�j�̍ݗ����ő�J���g���P�O�T�����ƂȂ��Ă��܂�
�V������ �Q�O�O���� �Ƃ���Ă��܂��E�E�E
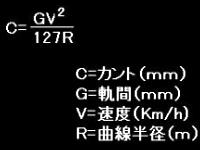 �J���g�͂��̎��ŎZ�o����܂����E�E�E
�J���g�͂��̎��ŎZ�o����܂����E�E�E�J���g�͐��H�ɂ˂��ꂪ�ł���̂ŁA�Q���ݎԂ����^�@�֎Ԃ܂�
�e��ԗ���E�������邱�ƂȂ����s�ł���悤�͌^���E�őΉ�������̂ɂ�
���E�������āA���Ԃ̂悤�ɑ傫���X������͓̂���̂ł��E�E�E
�J���g�ɉ����Ă���� �X���b�N���O�D�Q���� �݂��ĂȂ�Ƃ��Ή��ł��E�E�E
���ۂ̐��H�ł� �P�U���� �ɂȂ�܂�
�X���b�N�iSlack)�ɂ��āE�E�E�i�q�e�Ђł͋Ȑ��ŁA�ԗ��� �����܂Ȃ� �ŃX���[�Y�ɒʉ߂ł���悤��
�O�����[���͂��̂܂܂ŁA�������[�����Ȑ��̓����ւ��炵�� �O�Ԃ��g�� ���Ă��܂�
�X���b�N�ʂ́A�ʉ߂���ԗ����Q���ԁE�R���ԂŌ��߂��Ă��Ăi�t�q�̂悤�ɂR���Ԃ�����ꍇ
�Ȑ����a���Q�O�O�������ł́A�Q�O�����ƂȂ��Ă��܂�
�X���b�N�͊ɘa�Ȑ����܂߁A�S���ŏ��X�ɂO�����֖߂����ƂƂȂ��Ă��܂��E�E�E
�͌^���E�̂i�t�q�E�E�E�Ȑ����a�͋ɂ߂ċ}�ɂȂ��Ă��܂�
�ł��A���̃X���b�N��݂��邱�ƂŁA����ȋ}�Ȑ����������S�ɒʉ߂ł��܂��E�E�E
������H�̑�햡�ł��E�E�E���ˁ@(��)

�����͂̂d�e�T�W���c�c�T�P�������A�����Ƃ�������Ă̎��^�]�ł��B

�A���V���̐��H���Ȃ���܂����E�E�E

�i�t�q�H��ʼn��g�����|�C���g��ݒu���܂��E�E�E
���[���݂̂��O���āA�������̖��͂��̂܂g�p���܂��E�E�E

���̃��[������t�A�����lj��E�E�E
�o���X�g�͂܂��ł����ꉞ�����ł��E�E�E
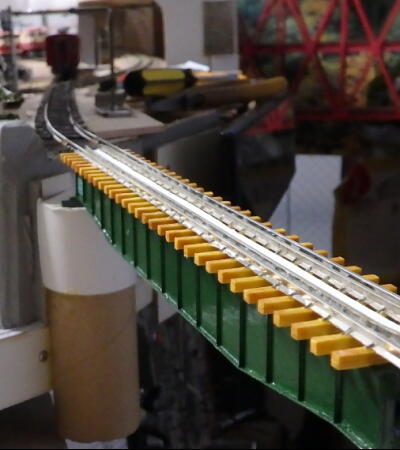

�ˋ������K�[�^�[���i�����j�����ʌ����i�_�C�������h�N���b�V���O�j�ł�
�g���V�� ���y���ɑ��s����W���O�Ԃ̗�Ԃ߂Ă���
�W���O�Ԑ��H�̏�ɂ���P�R������ԍ��ˈ���E���������C�ɂȂ�܂����E�E�E
�g���V���ɒz���݂��ĒZ���������ː݂���E�E�E
�قƂ�nj��z�ɉe�����Ȃ��E�E�E�{���̈��㗯�u���ɐڑ��ł���̂ł́E�E�E
�Ȃ�A�ǂ�����ʉߐ��ɂ���ƁA�^�]�Ƒ��Ԃ��y�ɂȂ�E�E�E
����ɁA�傫�ȃ��o�[�X�����ݒ�ł��܂��E�E�E
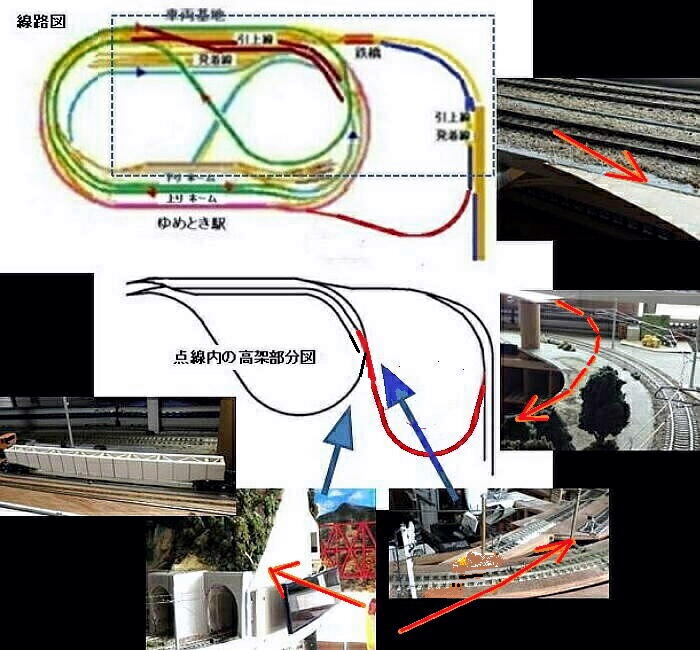
���H�}�͂�₱�����̂ŁA�P�R������Ԃ����������o���܂����E�E�E
�ԐF�̃��C�����\�肷��ڑ��A���V���ł��E�E�E
�����́A�P���K�[�^�[���E�E�E�����i�t�q�����ԗ��Z���^�[�ɔ�������܂���
�������y�[�p�[���Ńg���l�����߂ɉː݂��܂�
���̐�ɖ{���ƈ�����Q�{�̎Ԏ~�߂�����܂��E�E�E�����ɐڑ����܂�
�|�C���g�����삵�܂����A���͈�����Ɩ{�������ʃN���X���������܂��E�E�E
���ʃN���X�̎���Ɠd�C�z����M���V�X�e���\�z�ȂǁA�܂����炭�̓p�Y���Q�[���ł�
�v�H�����͖���ł����E�E�E�{����ԉ^�s�ւ̉e���͍ŏ����ɁE�E�E�ڂ��ڂ��ƁE�E�E�ł�
2023/ 8
�ً}�̕ې���ƁE�E�E
�S�����S�m�F�������ɑO�i�X�C�b�`�𓊓��E�E�E������Ȃ��E�E�E
�d�e�T�W�@�֎Ԃ����r�b�g�X�^�[�g�ƂƂ��ɔ����E�E�E�ŁA�E���@
�������ԗ��Ɉُ�͂Ȃ��A���̌�ʉ߂����Ԃ��A���ׂĈُ�Ȃ��ʉ߁E�E�E

�Ȃ�ƋȐ��̓������[�����A�O�D�U�T�����@�����Ȃ��Ă����E�E�E
���ւ��R������d�e�T�W���A���̐��H��ʉߎ��ɒ����ԗւł���オ��
�O��ǂ��炩�̓��ւ����[���ɏ��グ�Ă������Ƃ������Ɣ����E�E�E
���܂Œᑬ�łӂ��ɒʉ߂ł��Ă������̂́E�E�E
����͍����Œʉ߂����������S����������������Ă̒E���ł�
�ᑬ�ʉ߂ƍ����ʉߎ����ŁA�������̂���オ��E�����m�F�ł��܂����E�E�E
�ᑬ�ʉ߂̂��߂ɐ������x��ݒ肷��悢�̂ł���
���̖h�~�̂��߂ɂ́A���H���ǂ̍�Ƃ��s����������܂���E�E�E
�ً}�ې��H���̎��{�ł��E�E�E

�^�x�����}���^�C�𓊓��A ���ʁA�������[�������A�J�ʂ������H�ł��E�E�E
�v��ʉ^�]����~�X������H�̌��ׂ��E�E�E����
���[���̍���������Ƃ��A��Ԃ̂������Ƃł���Ƃ������������܂����E�E�E
2023/ 7
���葱���ĂQ�U�N�ł�
���N�ɓ����Ă��猻�݂܂ő��s�́A�P�T�C�Q�S�T��
�Q�U�N�ԂłS�X�R�C�Q�T�S���E�E�E
�^�]�Ȃɐݒu�������s�J�E���^�[�����ƂɃJ�`���Ɠ����܂��E�E�E
�͌^���E�Ȃ̂ɋ����̑��s�����ł��E�E�E
���[�h�ł̓�������x���̑��s�̓J�E���g����܂���̂ŁA���ۂ�
�����Ƒ������s�͂��Ă��܂��E�E�E
����A�w�ԐM���@���ԐF�����̂܂ܓ��삵�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E
�S���̐M���͐�Ζ��߂Ȃ̂œ����܂���E�E�E
��Ԏw�߂ƈ��S���m�F���Ď�M���ɂ���Ԃ��w�܂ňړ������܂�����
�Ȍ�͑啝�ȉ^�x���������܂����E�E�E
�����ŊJ�������M���V�X�e�� �Ȃ̂ɁA�̏������肷��̂Ɏ�Ԏ����������
�C���ɑ����L�͈͂̕������K�v�ɂȂ莞�Ԃ��������Ă��܂��܂���
�����͌J��Ԃ����삷�镔�i�̔��c���͂��ꂽ�i������J�H�j���Ƃł���
�Q�U�N�o�߂��āA����ԑ����̂��C���E�E�E������o�N��ł�
��������T�O�N�����̎ԗ����E�E�E
�͌^���E�E�E�E���������Ƃ��Ă���Ȃɒ����Ԃ��V�ё�����E�E�E
���̑f���炵�����E�ɏj�����I ---What A Wonderful Word---
2023/ 6

�������ɁA�u�����^�d���⋌���̃p�l�����C�g�����̓d�ԂP�S�T���E�E�E
�k�d�c���H�������ł�
���łɐV�����k�d�c�p�l�������̎ԗ��Ƃ��킹��
�d���P�U�V�������������k�d�c�ɂȂ�܂���


��Ԃł̉^�]�Ɍ��̑т������܂����E�E�E�Y��ł�
��������w�b�h�}�[�N���k�d�c�������Ƃ����X�Ƃ�����ł��܂��E�E�E

�u�����v�Ɓu�߁v�@�N���b�N����Ƃ��ꂼ��̑��s���悪����܂��E�E�E
���C���V�������J�ʂ���܂œ���������삯�������u�߁v��
�k���V������T���_�[�o�[�h�ɒǂ�ꂽ�u�����v�E�E�E��߂Ƃ��w�Ō����ł�
�����ɂ͂��肦�Ȃ��i�t�q�̓��ʂȐ��E�ł��E�E�E
���s�n�d�͂��ː��W�d�Ȃ̂ŁA���͒�Ԓ������邭�_�������邱�Ƃ��ł��܂�
�����A�C���Ԃ�f�B�[�[���@�֎Ԃ�����̋q�Ԃ́A�k�d�c�����Ò��͍��E�E�E
��Ԃ́A�S�X���x�œ����n�߂Ă��������͂܂��_�����܂���(�L;��;�M)
2023/ 5
�g���V���������z�W�Ȃǂ�ݒu���܂����E�E�E
�}���z������邽�߂ɑ傫���I��E�E�E

�ő�P�V�D�O�p�[�~���ʼn����Ă������H�͈����グ���ɐڑ�
�����ŁA�����iLevel)�ɂȂ�܂�
�Ȃ�Ƃ��Q�O�p�[�~���ȉ��ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂����E�E�E
�����Ƃ����z�W�́A�I�[�o�[�X�P�[���ł�
�ł�����Ȃ�̕��͋C�ɂȂ����E�E�E�ƁA�v���Ă܂�
2023/ 3
���������k�d�c��
�̂́E�E�E�Ȃ�Č����Ώ��܂����A�C�e�^�̂k�d�c���������ꂽ���납��
�d���̂����ɁE�E�E�ƁA���N���A���낢��H�v���J��Ԃ��Ă��܂����E�E�E


�P�X�V�V�i���a�T�Q�j�N�ɃC���W�P�[�^�p�����^�ԐF�k�d�c����肵�܂���
�����͕ė����i�����Y���j���W���̎���ŁA�������P�O�����߂���������
�ݕ��̎ԏ��ԂȂǂ̃f�b�L�Ƀe�[�����C�g����t���邱�Ƃ͕s�\�ł����E�E�E
���̓������Ƃ��ȒP�ɉ����ł����̂��A�����ԐF�k�d�c�E�E�E
�����I�߂��o�߂��āE�E�E�����Ȃ����邭�P���Ă��܂��E�E�E
���S���i�t�q�Ɂu���v���E�E�E�ł������͂܂��܂���ʓI�ł͂���܂���ł���
���P�x�k�d�c�̏o���ɋ����A����ɉ����Ȃ��Œ�R��_�C�I�[�h������āE�E�E
�Ȃ�āE�E�E���i���Ƃɋ�J�H�H���d�˂��̂ɁE�E�E���̗���H�i���͐����̂ł�
����́A���łɏo���オ�����H�e�[�v�k�d�c�ł��E�E�E

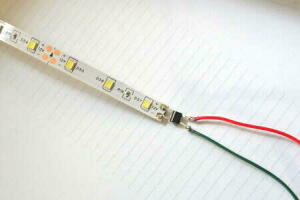
���F�k�d�c�����Ԋu�ɔz�u���ꂽ�����T���̃e�[�v�ŁA�d���͂P�Q�u�ł��E�E�E
�ŏ��T�b��(�k�d�c�R��)�̒����ŃJ�b�g�ł���̂ŁA�Ԓ��ɍ��킹�Đؒf��
���d���ɏ��^�̃u���b�W�_�C�I�[�h�����t���܂��E�E�E�i�������������H�j
����ŁA�i�s�����i�ɐ��j�ɂ�����炸�P�Q�u�������ł��܂��E�E�E
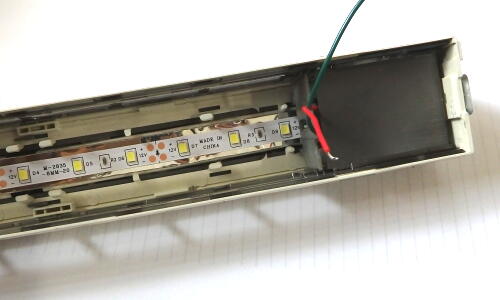
�ԓ��Ɏ�t������Ԃł��E�E�E���ʂ��S���e�[�v�Ȃ̂ŊȒP�ł�


�@���Ƃ̃p�l�����C�g�̎������@�@�@�@�@�k�d�c����E�E�E���邷����@���ȁH

�g���V���𑖍s���̃A�[�o�����C�i�[�ł��E�E�E

���邷���鎺�����k�d�c�̋P�x�������A�[�o�����C�i�[�ł��E�E�E
2023/ 2

�����e�i���X���[�h�ƕې��ԗ����[�h��A������K�i��ݒu���܂���
��A���Ɋ��������g���V���Ɠd���H���E�E�E
���̌�A�V�[�i����lj��E�E�E

�d���H�������������g���V���E�E�E
���H���ڑ��ł����̂ŁA�����`���^�]�Ǝv���Ă���ƋC���t�����E�E�E�i�j
�W���O�Ԃ̎ԗ��͂��ׂēd�ԂƓd�C�@�֎ԁE�E�E�ː���������Ή^�]�ł��Ȃ��E�E�E
�}���ʼnː��H����i�߂Đ��H�̐^��ɒ������E�E�E
���x�̓J���g��Y��Ă����E�E�E�i���j
�ԑ̂��X����̂Ńp���^�O���t������ė����E�E�E
�v���Ԃ���H�~�݂�ː��H�����s�����̂ŁE�E�E�ƁA�����Ɍ�����
���܂����E�E�E
2023/ 1

�ː��H�����قڏI���E�E�E���^�]�̏������ł��E�E�E

�g���V���͕W���O�ԂȂ̂Ő��H�~�݂͏����ł��E�E�E
�J���g�́A�r���J�[�u�Ȃ̂ō��E�̌X���y�����Ă��܂��E�E�E
���̌�͉ː��H���ł�
���N���N���X�}�X�C���������T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�^�s�ł��E�E�E

Santa Claus Express�E�E�E
�V���������i�|�C���g�j��ʉ߂��� �T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�E�E�E
�s�d�d�Ґ�������������i�t�q��
�P�O�R�^�@�֎Ԃ��b�|�b�z�u�̓��ւŁA�y���ȉ��ƂƂ���
�V���������i�|�C���g�j��ʉ߂��čs���܂�
�����i�|�C���g�j�̎���Őv���ċC�Â����̂��g���O���[���̓���͈�

�P�R�����ƂP�U�D�T�������[���̊ԂɌ��肳��]�T������܂���
�d�C�I�ɂ��≏���K�v�Ȃ̂ŁA���[��������Ă͎�����J��Ԃ��܂����E�E�E

���̂����A�t�����W�E�F�C�����[���Q�{����̂őg�����Ɏ肱����܂���
�R����Ԃ͎x�������Łu��߂Ƃ��w�v�P�Ԑ��ł��E�E�E
�����ɕW���O�Ԃ̎ԗ����W�����đ��ԂɎ�Ԏ�邱�Ƃ������Ȃ�܂���
���[�h�̒ʉߐ��ɑޔ����݂��Ă���̂ł����A���H�L�������T���ƒZ��
������}�̂W���Ґ����^�s����̂ɁA��ɂP�Ґ��������グ���֖߂��K�v������܂���

�z�[���P�Ԑ����肩��W���O�Ԃ݂̂��Ċg���V�������݂��܂��E�E�E

�g���V���̍H���ɂƂ��Ȃ������e�i���X���[�h���ڐ݂��g�����܂���
2022/12
��Ԃɉw�\����X����_������ƁA�����������t�����R�̂ӂ��Ƃ̊X���肪
�������ƈÂ��Ȃ�E�E�E
����g�����X���狋�d���Ă����e���ł��E�E�E�ʉ�H�ɕύX���z����؊����܂�����
����d�͂̑傫���c�������M���i�d���j�����ׂĂk�d�c�����邱�Ƃɂ��܂���


���g���ȓd�b�a�n�w��w�O�̃o�X��ɂ��k�d�c�Ɩ�����t�܂����E�E�E
2022/11
��ɉw��ԗ������邭�P���Ă���̂ɁA���i�̊X���݂ɖ����肪�����E�E�E
�^�]���Ă��ĂӂƎv�������Ƃł��E�E�E���ɏ�萳�ʂɃA���v�X�̎R���݁E�E�E
���̂ӂ��ƂɍL����X�E�E�E

�v�����Ăk�d�c�������đ���X����_�������邱�ƂɁE�E�E
�w�̏Ɩ����k�d�c�������������ŁA�z���ɔY�ނ��ƂȂ��ł����̂ł���
�ق�̈���Ǝv���ĊJ�n������ƂȂ̂ɁA�Ȃ�Ɠ���̐����������Ƃ��E�E�E�i��)(�j
�Q�O�P�W�N�Q���ɏ��߂� YouTube �ɓ�����A�b�v�����S�N�ɂ��Ȃ�܂����E�E�E
���������Đ������P�S�������z���܂����E�E�E���肪�������Ƃł�
�J�̃|�s�����[�Ȑ��E�ł��Ȃ��A���[�J���Ȗ͌^���E�ł����E�E�E
�����Ȃ��ӌ������������܂����B�ق�ƂɊ��ӂł��E�E�E
���ꂩ����܂��A�܁X�ɐV����������A�b�v���Ă��������Ǝv���Ă��܂��E�E�E
2022/10
���Ő��삵�Ă��甼���I�E�E�E�P�P�R�n�ߍx�^�d�Ԃ̓��͍X�V�ł�

�i�t�q�̋�����ʉ߂���y�[�p�[���P�P�R�n�ߍx�^�d�ԁE�E�E
���������S������]��ɂȂ������[�^�[��M���A�ԗւ�����܂���
���x�̍����P�R�����Q�[�W�����ꂽ�C���T�C�h�M�A��
���g�p���������イ�Ԃ�ɓ������[�^�[�ȂǑ����̕��i�ł�
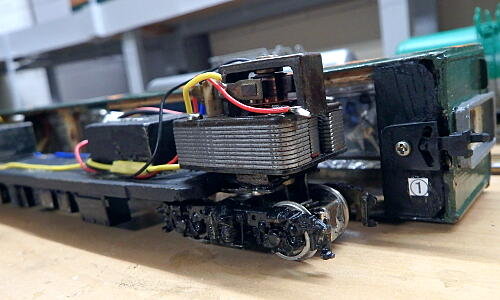
�P�X�V�P(���a�S�U�j�N�Ƀ��[�^�[���P����Q�։ˑ����Ĉȗ��T�O�N���E�E�E
������ł��A���[�^�[����N���ɂP�O�X�߂��d�����Q�D�W�`�̓d��������
���̗�ԂƂ̕����ł� �u���[�J�[�_�E�� �Ɍ������^�]�s�\�ɁE�E�E
�����Ŏv�����ē��͕�������ꂽ�p�[�c�ōX�V���邱�Ƃɂ��܂����E�E�E
�g�p�������[�^�[�͏c�^�j�s�l���c�u�P�W�P�ōĐ����ƒ����ŐV�i���l�ɁE�E�E
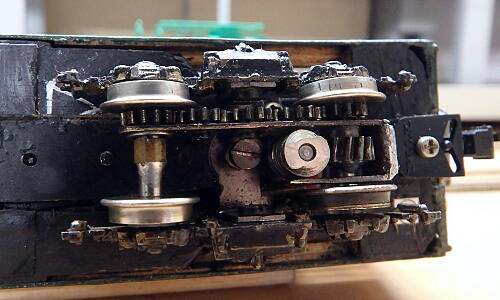
�̂Ȃ���̏c�^���[�^�[�ƃC���T�C�h�M�A�����̂܂܂̍X�V�ł���
�P�R�����Q�[�W�����ꂽ�C���T�C�h�M�A�́A�قڂ��̂܂܉ˑ��ł��E�E�E
�N�������U�u���O�D�T�`�Ƃ����ȃG�l���ʂŌy���ɑ���P�P�R�n�ɁE�E�E
�喞���̎��ł�(��)
�c�c�P�U�E�E�E�i�t�q�H��ŃI�[�o�[�z�[���E�E�E�S�ʌ���
![�c�c�P�U���^�]�E�E�E](dd168c.jpg)
�c�c�P�U�����������S��������I���o�Ė߂��Ă��܂����E�E�E
���S����ɂc�d�P�O�������ł��Ȃ��ȈH���p�ɐ������ꂽ�f�[�[���@�֎Ԃł�
�c�c�T�P�̂P�G���W���Ƃ����X�^�C���ł����A���S�̏��C����S���̊ȈՐ��H��
�^�p����āA�P�X�V�Q(���a�S�V�j�N����P�X�V�S�i���a�S�X�j�N�܂ł̊Ԃɐ���
���ꂽ�����͂U�S���ɂ��Ȃ�̂ł����A�ݕ��^�p�������������Ƃ���]��ƂȂ�
�����ɔp�Ԃ������ݍ��S����i�q�e�ЂɈ����p���ꂽ�ԗ��͐����ł���
�P�X�V�T�N�i���a�T�O�j���ɔ������ꂽ�r�`�m�f�n�͌^�̏����g���ăL�b�g��
�i�t�q�H����P�R�����Q�[�W�ɉ������ďv�H���������̂� �u�`�r���N�v
�ƈ��̂������悤�ɁA�i�t�q�ł����^�����āA���łɎg�p���Ă����c�c�P�R��
�^�p�ɉ���邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����E�E�E���ǁA�i�t�q�ݕ��ł��]���
�����ɂȂ�^�p���犮�S�ɗ��E���A�����́u��C�m�@��v���݂����������S����
�]���A���n���܂����E�E�E���̍ۂɎԐЕ�͔p���ƂȂ��Čo�܂̏ڍׂ͕s���ł�
�����́u��C�m�@��v�́A��d���P�R�����Q�[�W�łʼn^�s���Ă����̂�
�i�t�q�Ƃ́A���X�C���ԂȂǎԗ��̍s����������܂����E�E�E
���݂� ���������S�� �́A�m�Q�[�W�i�X�����j�ƂȂ�
�c�c�P�U�͌o�N�ƂƂ��ɋx�ԏ�Ԃł����E�E�E
�����c�c�P�U���߂��Ă����̂ł��E�E�E���A��͂�o�N�E�E�E
�i�t�q�H��Ŋ��S�ɃI�[�o�[�z�[���ł�
���i�̌�����A�j�����ő���Ȃ����i�͎��삵�ĂȂ�Ƃ������I�I
�S�ʌ��������{���Ĕ����I�Ԃ�ɂi�t�q�ł̎ԐЕ����ł��E�E�E
���͗��i���c�c�P�R�ɉ����A�i�t�q�̃��[�J�����^�p�ɑg���݂܂���
2022/ 9
YouTube �Ƀu���g�����V���[�Y�ŃA�b�v���܂����E�E�E
�d�C�@�֎Ԃ̑S�ʌ�����������C�ɐ����E�E�E
���������Ȃ̂Ō�����A�u���[�g���C��������������܂����E�E�E
�ŁAYouTube�ɃA�b�v�E�E�E
�����u���g���ł��q�Ԃ₯����@�֎Ԃ��ς��ƁA�т����肷��قǃC���[�W�������܂�
�܂����Ă��������E�E�E
2022/ 8
���H�ێ�E�E�E
YouTube �Ƀ}���^�C���A�b�v���܂����E�E�E
�}���`�v���^�C�^���p�[�@�l�s�s
MAINLINER DUOMATIC 07-32 ��DB(�h�C�c���S�j�d�l�̃��f���ł�
���H�ې��@�ނ̓���ԗ��Ȃ̂ɈĊO�Ǝ�������Ă��܂��E�E�E
���肪�������Ƃł��E�E�E�����E�E�E
�ŁA�摜�쒆�ɁE�E�E���͂��܂�܂���(�L;��;�M)
�T�O�N�߂��o�߂����v���X�`�b�N���̎ԑ̂͘c�݁A�萠�̓{���{���E�E�E
�X�e�b�v��萠�͋����Ɍ����ł��E�E�E
���f���ɂȂ������Ԃ̃f�[�^�[���W�܂����̂ŁE�E�E

�v���O�h�A�ɑΉ����đ傫����яo�����萠��

���~��q�̎�t���@�ύX�ȂNJe���ɕ⋭������������܂����E�E�E
�i�t�q���l�s�s�́AAustria �� Plasser & Theurer �Ђ� �O�V�V���[�Y
�ŋ߂̂i�q�⎄�S�e�Ђł́A���ꂼ�ꓯ�Ђ֓������A���V�����Ȃ���
�O�W����O�X�V���[�Y����������Ďԑ̂��p���Ă��܂�
2022/ 7

�Q�T�N�Ԃ̏o�����������ς��l�܂����z�[���[�W���A�ǂ������y���݂�������
2022/ 6
�h�b�d�R Class�S�O�U
���z�𑖍s�����h�b�d�R���A�������[�^�[���ƂƂ��ɋ}��ԁE�E�E
��Q�O�N�O�ɍw���������[���b�p�s�q�h�w���̊����i�ł��E�E�E
�����Q�����ŁA�ԓ��̃X�C�b�`�ʼnː��W�d�ɂ��Ή����Ă��܂�
�Ȃ̂ŁA�i�t�q�ɂ́A�p���^�O���t�̍쓮�����������œ����ł��܂����E�E�E

�v���X�`�b�N���i�Œʓd���������������ł����A�h�C�c���i�����ɋ��x������
�g���Ă̐��x�����炵���A�ː��W�d�ւ̐�ւ��ɕ������������ł����E�E�E
�����Ԏ��̃v���X�`�b�N���M�����I�o���Ă��蒍���ɂ͕֗��Ȃ��̂̏����C�ɂȂ�Ƃ���ł���
�����āA��N���S�ʌ����ŕБ���Ԃ̃M�A�ɏ����ȃN���b�N�������܂����E�E�E
�o�N���ł��E�E�E
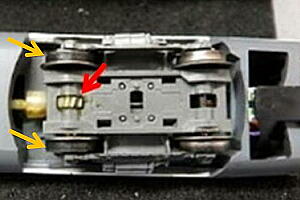 �����M���łP���쓮�E�E�E
�����M���łP���쓮�E�E�E
������͂𑝂����߂ɋ쓮���闼�ւ��g���N�V�����^�C��
���݂̂s�q�h�w�i�g���b�N�X�j�Ђ́A�𗬂R�����̂l�������������i�����N�����j�Ђ̎P���ł�
�����ŁA�����N�����X�g�A���g�q�r�ɁA�M�������̌������\���₢���킹�܂����E�E�E
�����N�������h�b�d�R�i�����Ă���A�p�[�c�͓��K�i�œ���\�ł����E�E�E
�����A�����N�����́A�ԗւ̕Б��≏�������𗬂R�����E�E�E
�g���b�N�X�������Q�����Ȃ̂őg�ݍ��ނƃV���[�g���邩���E�E�E��
���ۂɃp�[�c�����Č��Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����E�E�E
���ǁA�w����z�͂�����߂܂������A�����N�����h�b�d�R�̏ڍׂȑg�ݗ��Đ}�����������܂���
���̌�́A�ێ�̊Ԋu��Z�����ĉ^�s���Ă��܂����E�E�E�Ƃ��낪
�Ȃ�ƈُ킪�����������Α��̃M�����Ԏ���ŋ����]���J��Ԃ����̂ł�
���z����ނ��������グ���ւȂ�Ƃ��߂��܂������A���łɗ��ւ̃M�������Ă��܂���


�g�q�r���璸�����}�Ɋ�Â��ĕ���������ԂƂl�o�M��
�������Ǝԗa���S�������V�����p�̃G���h�E�l�o�M����g�ݍ��ނ��Ƃɂ��܂���
�Ⴄ�̂̓t�����W�̍����ł��E�E�E�E���h�~�ɂs�q�h�w�́A�ق�Ƃɍ����I�I
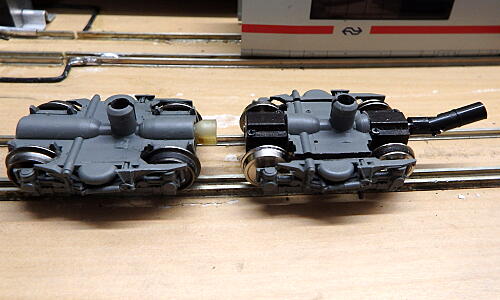
���Ƃ̑�Ԃɂl�o�M����g�ݍ��݁i�قƂ�ǖ������i�j�j���j�o�[�T���W���C���g�������ł�
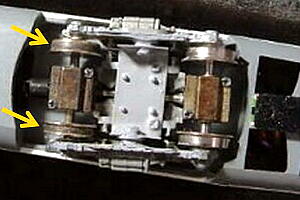 �l�o�M������g�ݍ���Ԃł�
�l�o�M������g�ݍ���Ԃł�������͊m�ۂ̂��߂ɁA�l�o�M���̕Б����ւɂ��g���N�V�����^�C��

�C�������������ԗ��E�E�E���Y�̃t�����W�̒Ⴂ�ԗւ��ЂƂ���P���Ă܂��E�E�E
�M���������o�N������ԁE�E�E�Ȃ�Ƃ����Y�̃p�[�c��p�ŕ����ł��E�E�E
�Y��Ȃs�q�h�w�E�E�E�܂��܂������ʼn^�s�����܂��E�E�E

�h�m�c�d�w�i�ڎ��j�̕\��
2022/ 5
�w�ɂɑ����ċ�����}�̎ԓ��Ɩ����A�v�����Ăk�d�c�����܂����E�E�E

�ԑ��̗�Ԏ�ʕ��������ĊO�N�����[�Ɍ����܂��E�E�E

�E���̎ԗ��͍H�����{�H�ŁA�d���Ƀu���[�I�[�o�[���C���g���Ču�����F���o���Ă��܂�
�d���͔��M����̂ŃI�[�o�[���C�̗��v���ӂł����E�E�E
�Q�O�N�ȏ���o�߂��āA�w�ɂ̏Ɩ���������k�d�c�����邱�Ƃɂ��܂����E�E�E
�����̌u�����^���M�����S�O�{�߂����邳��ۂ��߂ɁA���������Ɏ��t��
����ɓd���~���ňÂ��Ȃ�̂�h�����ߓd�����P�W�u�܂ŃA�b�v�����Ă��܂���
���Ďg�p�����k�d�c�͍��P�x�Œ�i�R�D�T�u�E�E�E�����������
�𗬂��璼�����E�E�E
�ϊ��p�̃_�C�I�[�h�u���b�W��lj��A�k�d�c�͒���ڑ��łP�W�u�Ή��ցE�E�E
�ȓd�͂Ɣ��M�h�~�Ɍ����ł�����͂��ׂĂk�d�c���ł�

�k�d�c�Ɩ��Ɍ����������Ė��邭�Ȃ�����߂Ƃ��w


�\���̏Ɩ������d���i�����j����k�d�c�i�E���j�ցE�E�E
2022/ 3
�v���Ԃ�ɓ�����Ԗ������Ґ��𑖂点�Ă݂܂����E�E�E
�d�ԋ}�s���S�����́A���a�S�O�i�P�X�U�T�j�N���납���Q�O�N�E�E�E
�W�O�n�d�Ԃ����}�Ƃ��Ēa����A�V���\�d�ԂP�T�R�n�₻�̋��͌^�P�U�T�n���a���E�E�E
����ɓd���̐i�W�ƂƂ��Ɍ��d�Ԃ��J������A��������Ԃ͋q�ԕҐ��Ƃ������E��
�d�ԗ�ԉ����ꂳ��ɋ}�s�Ƃ��đS���ɑ���o���܂����E�E�E
���}���A�V���\�d�Ԃ̓����ƂƂ��ɋ}�s�ցE�E�E�����ɂȂ��ē��}�ւƔ��W�E�E�E
����ȉ^�p���Č����Ă݂܂����E�E�E
�ŏ��Ɏv�������̂��u���C�v�ł��B
�������W�O�n����͒Z���唼���P�T�R�n�}�s�E�E�E�����
�i�t�q�̂P�T�R�n�́A���̐V�����p�Ƃ��ēh���ύX�ς݁E�E�E
���}�Ƃ��ĉ^�s�J�n����}�s������o�Ė�S�O�N��Ɂu���C�v�͓��}��
�����ĉ^�p��P�O�N��̕����P�X�i�Q�O�O�V�j�N�ɔp�~����Ă��܂��܂���
�܂��u���C�v�̏����̃w�b�h�}�[�N�̏ڍׂȎ����������炸�Č����c�O���܂���
�Ȃ�E�E�E�W�O�n�̏��}�u�x�m��v�E�E�E���̌�}�s��
�}�s�ɂȂ��Ă���Ґ��͂P�U�T�n�E�E�E���݂͂R�V�R�n���}�u���C�h�r���[�ӂ�����v�ł�

�K���W�O�n����̃w�b�h�}�[�N���쐬���邱�Ƃ��ł��܂����E�E�E

����Ȍv����F�c�ԗ��ɍ������Ƃ���E�E�E
�g�����͒ቮ���d�l�ł���
�܂肽���ݍ��̒Ⴂ�o�r�Q�R�^�p���^�O���t���E�E�E�ƁA�v�킸�����Ă��܂��܂�����
���ۂ̂Ƃ���W�O�n�W�O�O�ԑ�̃p���^�O���t�����̒ቮ���ԗ��𓊓����ׂ��ł����E�E�E��
�͌^���E�Ƃ������ƂŁE�E�E����ς育�e�͂Ȃ̂ł��E�E�E
���Ȃ݂Ɉ�ԐV�����R�V�R�n�́A�ቮ�����Ȃlj��������Ȃ��Ă��g�����ɓ����ł��܂�
���̂킯�́A�V���O���A�[���p���^�I�I
�쓮�������łȂ��܂肽���ݎ��̍������Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��ł��E�E�E
����H�ߑ㉻�H�E�E�E�Ƃɂ����т������ł�(��)
�d�� �R�`�i�A���y�A�j �̕ǁE�E�E
�i�t�q�̓d���\���́A���s�p�Ɠ_���p�ŕ������A���ꂼ��̉�H��
�d���̌��x�� �R�` �ł�
�����ɒ��Ґ��i�V�܂��͂W���j�̂R��Ԃ𑖍s�����Ă�
���イ�Ԃ�]�T�̂���\���ł�
��Z���������܂����E�E�E
�W�Q�n�C���ԓ��}�ł��E�E�E
��Ԓ����O�Ɠ��Ȃǂ�_�������邽�ߑ��s�p���[�^�[�ւ�
���d��x�点�邽���P�O���i�I�[���j���x�̒�R�����Ă��܂��E�E�E
���̂������ŁA��Ԓ���������x�_�������邱�Ƃ��ł��܂��E�E�E
�Ƃ��낪�A�o�N�H�ƂƂ��Ƀ��[�^�[���ׂ����� �H�H
�C���Ԃ͑��s�p���_���p������d�����狟�����Ă���̂Œ��Ґ��̉^�]��
�Q.�W�` �߂��d��������
����ɏ����z�Ŏ��ɉ�������� �R�` �I�[�o�[�E�E�E
���ʂ́A�u���[�J�[���_�E�����ċ}��~����H�ڂɁE�E�E
���[�^�[��R���T���ɉ����܂��������I�ȉ��P�ɂ͂Ȃ炸�E�E�E
�ȑO����̎������d�����ȓd�͂ɂȂ� �k�d�c�� ���l���˂E�E�E��
�v�Ē��Ȃ̂ł��E�E�E
2022/ 2
�`�s�r�g���u���E�E�E
�ԐM�������ł`�s�r������E�E�E�m�F�{�^���ŏI���ł��Ȃ��E�E�E
�ԃ����v�ƌx��x���������܂܂ŁA�x�����[�h�ֈڍs�ł��܂���
�`�s�r�p�̃����[�i�p�d��j���p�^�p�^�ƃt���b�^�[���N�����Ă���
����Ăĉ^�]�𒆎~�A���ׂĂ̓d�����n�e�e�ɁE�E�E
�����ʼn�H�ׂĂ݂���A�ǂ��ɂ��ُ�͌�������Ȃ�
�������S���킩�炸�A�ʓd�s�ǂ��H�Ɛړ_������
�����[�̌̏���^�������[���̂��̂�\����Ɍ����E�E�E
���炽�߂ăe�X�g�E�E�E����ς�m�F�{�^�������삵�܂���E�E�E
����グ�ł��E�E�E(���j
�`�s�r�́A����J�n�ŁA��Ԃ��~�����邽�߂�
�T�b�̃J�E���g���J�n���܂��E�E�E
�ǂ����A���̃J�E���g���n�܂��Ă��Ȃ��E�E�E
����n���Ă��邯�ǁA�����ɖ߂�̂Ń����[���p�^�p�^�H�H�H
�`�s�r�̃R���g���[���p�l����������x�m�F����ƁE�E�E�Ȃ��
�`�s�r���Z�b�g�X�C�b�`���n�m�ɂȂ��Ă���E�E�E
�m�F�{�^�������������
�V�X�e���͌x��x�����~���x���̃`���C���ֈڍs���܂�
�����ɁA�i�t�q�̃V�X�e�����T�b�̃J�E���g�𒆎~�����O�b�ɖ߂������
�s���܂��E�E�E�Ƃ��낪�܂�ɁA���̃J�E���g���O�b�ɖ߂炸
���̌�̂`�s�r���삪 �R�b���S�b�Œ�~���邱�Ƃ�����܂���
�Ȃ̂ŁA�m���ɖ߂����߁A�O�b�ɖ߂����m�F�����v�Ƌ����I���O�b�֖߂�
���Z�b�g�X�C�b�`��ݒu���܂����E�E�E
�Ȃ������̃X�C�b�`���n�m�ɂȂ��Ă����̂ŁA�V�X�e���Ƃ��Ă�
�J�E���g���J�n���Ă͖߂���J��Ԃ��Ă����̂ł����E�E�E
�킩���Ă݂�A�������Z�b�g�X�C�b�`���n�e�e�ɂ���Ε����ł��E�E�E
�����̍�����V�X�e���ɐU���Ă����̂ł��E�E�E(�L;��;�M)
���̃��Z�b�g�X�C�b�`���n�m�ɂȂ����̂��s���ł���
���Z�b�g�X�C�b�`�ɃJ�o�[����t���A�듮��h�~�Ƃ��܂���
2022/ 1
�ː��W�d�̂i�t�q�ԗ��́A�p���^�O���t�̃����e�i���X��Ƃ��������܂���E�E�E
���������ɕK�v�Ȃ̂́E�E�E�W�d����C������E�E�E�M��V���[�ƌĂ�Ă��܂�
�ː��i�g�����[���j�ɐڂ���Ƃ���ł�
���Ԃł́A���n�Č������@�S�n�Č������@�J�[�{���n�@���J�[�{���@�Ȃǂ̎C�������
���ꂼ��ː��Ƃ̖��ՁE�E�E�ʓd���A�ϋv���ɒ����Z��������܂��E�E�E
�V�����͓S�n�A���S�̓J�[�{���n�������ƕ����Ă��܂��E�E�E

�c�O�Ȃ��疢���ɓK�ȍޗ��͌������Ă��܂���E�E�E��
�ŋ߂̂i�t�q�ԗ��ł͓����ׂ��J�b�g���ĎC�������Ă��܂��E�E�E
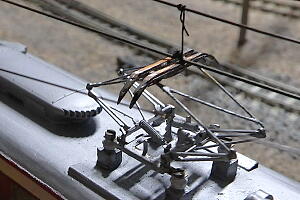
�����ɔ�ׂĉː��i�g�����[���j�Ƃ̐ڐG�ʐς��L���̂Œʓd�����ǂ��Ȃ����C�����܂�
���n�Č������Ƃ͂����܂��A�O�D�R�������Ŏ��p���ł��E�E�E
�Q�O�Q�Q�N�T�����R���������H�쏊����C��̕��i�������Ă��܂����E�E�E
�ʓd���\���傫�����P�ł������ŁA���ݎ����^�p���ł��E�E�E
�ː����ƃp���^�O���t�쓮���́A�ׂ��������Ǘ����K�v�Œ���I�ɓ_�����Ă��܂��E�E�E
����ł����s���̐U���Ȃǂʼnː��ƃp���^�O���t�ɂق�̏������Ԃ��E�E�E
�����闣�����������܂��E�E�E
���Ԃɔ�ׂ�ƁA�͌^�͂т����肷��قǒႢ�d���Ȃ̂ł����E�E�E
����ł��A�p���^�O���t��������X�p�[�N����т܂��E�E�E
��u�̋P�����ق�Ƃ��Y��Ȃ̂ł��E�E�E��
�ł�����Ȏ��A���͎C��������n���Ă��܂��E�E�E
�����Ă��ɂ͏W�d�s�\�Ɋׂ�܂��E�E�E
�C��̒���I�Ȍ�����Ƃ��K�v�E�E�E
�ː��W�d�͌^�̈�Ԏ�_�ƌ����邩������܂���(�L;��;�M)�i��)
�N���X�}�X�C�u�ɓ��ʗ�Ԃ��^�]�ł��E�E�E


Finland�i�t�B�������h�j�� Helsinki�i�w���V���L�j���� Kemijarvi�i�P�~�����r�j������
Santa Claus Express �i�T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�j�́A�f�G�Ȗ�s�Q���Ԃł��E�E�E
�����ԗ��͗p�ӂł��܂��A���N�̖����}�s�d�d�Ґ� �𗘗p�����i�t�q�̓��ʖ�s�Q���Ԃł��E�E�E
�T���^�N���[�X�G�N�X�v���X
���̐��E����ڊo�߂�ƁA�ǂ�ȃv���[���g���͂��Ă���̂ł��傤�E�E�E
�n���ɗD�����S������������Ă�������E�E�E���̂s�d�d����������E�E�E
����Șb���������Ă��܂����E�E�E�������N���X�}�X�v���[���g�ɂȂ�̂ł��傤���H
�E�E�E�y���݂ł��E�E�E
�E���i��������萳�ʂɂ��w�i������Ă݂܂����E�E�E
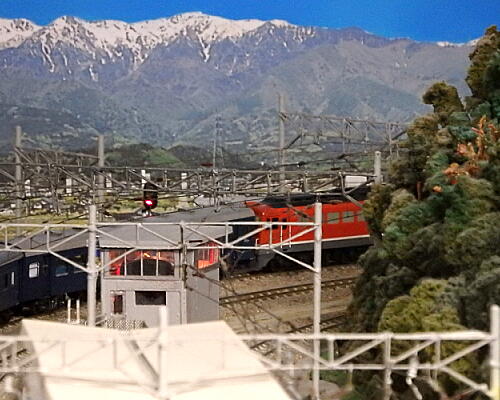
������E�E�E�ƌ����Ă��A������摜�Ƀy�C���g�ł���炵�����M�E�E�E
�傫�������A���v�X�H�̎R���݂��o�������Ă݂܂����E�E�E
����o���ĊԂ��Ȃ��P�N�ɂȂ��}�W�O�O�O�n�E�E�E
���s�n�ɔY�܂��꒲�����J��Ԃ��āA�Ȃ�Ƃ����肵���^�s���o���Ă����̂ł���
��Ԍ����i�����悻�����j�̓x�Ƀv���X�`�b�N����Ԃ��C�ɂȂ��Ă��܂����E�E�E
�A���J�[�ƈ�̉������v���X�`�b�N����Ԃ́A�������̏W�d�E����E�{���X�^�[�Ȃǂ�
��Ԙg�Ɏ�t���܂��̂Ō��݂����܂肠��܂���E�E�E����ł��T�C�h���猩��Ƃ���Ȃ�E�E�E��
�����ɂȂ�Ƃ��[�������Ă��܂������A���ɑ�Ԃ��������邱�Ƃɂ��܂���



�v���X�`�b�N����ԁi�����j���A���J�[���ԑ��Ɏ�t���W�O�O�O�n�p�ɑ�g�����H�������
�V��������ƕ��������A���J�[���ԑ̂Ɏ�t����ƁA�������I�ł��E�E�E
���^�]�������ŁA���Ă������A�v���Ԃ�ɋC������������ł�(��)
��}�d�Ԃ̑�Ԃe�r�R�U�X�`
�e�r�R�U�X�`�� �l�ԗp�i���́j��Ԃ� �s�ԁi�g���[���j�p�̂e�r�O�U�X�`�ƊO�Ϗ�͂قƂ�Ǔ����ł�
�����e�r�R�U�X�́A��}���R�R�O�O�n�����W�O�O�O�n�܂ł̊e�n��Ŏg�p����Ă��܂�
�ł����A�W�O�O�O�n�d�l�́A��g���Z���J�b�g����p�^�Œ[���Ƀt�b�N����t���Ă��܂��E�E�E
����w�������j�s�l�J�c�~�̃��f�����e�r�R�U�X�ł��W�O�O�O�n�d�l�ł͂���܂���ł����E�E�E
�Ȃ̂ŁA�W�O�O�O�n�p���e�r�R�U�X�`�։��H����K�v������܂����E�E�E



�w�������j�s�l���i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�t�q�ʼn��H�����W�O�O�V�̑�ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԂW�O�O�W�̑��


�j�s�l���i���i�t�q�̂W�P�O�V�p�։��H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԂW�P�O�W�̑��
��r������A���J�[�ȂNjC�ɂ͂Ȃ�̂ł����E�E�E�Ȃ�Ƃ����Ԃ߂Â����E�E�E�����H
2021/12
���ς�炸�̌o�N�ɂ��̏�ɔY�܂���Ă��܂��E�E�E
���삵�ďC���ł�����̂͏o���邾���撣���Ă��܂����E�E�E
���i�������K�v�Ȍ��͑�ւ����i��T���̂��A���A�������J���܂��E�E�E
���̗���͐i���ƂƂ��ɋK�i�܂ł��ς��A���p�i�͋����i�ɂȂ萻�����~�ցE�E�E
�����ČÂ��V�X�e���ɂ͑�ւ����i������A�s�̂���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��E�E�E�i���j
�^�]�p�̃p���[�R���g���[���Ɏg���Ă���_�[�����g���g�����W�X�^�Ȃǂ����łɐ��Y���~�ɁE�E�E
�́H�����������������̂ɁA����ƌ�������ւ��i�́E�E�E�т����肷��قLj����ɁE�E�E
����ȃ��b�L�[�Ȃ��Ƃ�����̂ł��ˁE�E�E
����Ȏ��A����s�ǂ����������}�C�N���X�C�b�`�E�E�E
�������Ă����o�[��ό`���������߂��A�Ȃ��Ȃ����܂������܂���
�Ȃ̂Ŏv�����ĐV�i���i�Ɍ������邱�ƂɁE�E�E
�ȑO�͓d�q�H�암�i�������X�ɏo�����Ă����̂ł����A��͂�l�b�g�V���b�v��
�����Ō������O�����i�E�E�E�Q�O�łP�O�O�O�~�ȉ��̋��z�ɂ��čw���E�E�E
������ɓ͂������i�Ɍ����E�E�E���A�Ȃ�Ɠ��삵�Ȃ��i�{�j
��H��������x�m�F���Ă��A�}�C�N���X�C�b�`�����̃g���u�������l����ꂸ
���炽�߂ēd�q���i���X�ɍ��Y�̃}�C�N���X�C�b�`���E�E�E
������͂P�O�O�O�~�łS��

�E�����Y���[�J�[�̐��i�ł��E�E�E
����������H�́A�\�z�ʂ�����I�I�ɓ���E�E�E
�s�Ǖi�Ɩ��g�p�i�̓���m�F�ł������̂��A�O�̂��ߕ������Ă݂��
�X�C�b�`���O����͈͂������H�E�E�E�ړ_�ɖ��i�ގ����ȁj�E�E�E
��p�Ǝ��ԁE�E�E�v�����艓��肵�Ă��܂��܂���
���܂����E�E�E
�o�N�ɂ��g���u���͑��ɂ��E�E�E
���ׂĂ͈��S�^�s�̂��߂ł��i(��)�j
�q�ԗp��Ԃs�q�S�V���o�Ă��܂����E�E�E
�Q�O�O�V�i�����P�X�j�N���I���G���g�}�s�̑�Ԍ����p��
�w���������̂ŁA�P������������̂܂ܖY�ꋎ���Ă��܂����E�E�E
�Ȃ�E�E�E���̑�Ԃ��g���Ă���ԗ��́H�ƒ��ׂ���I�n�S�U
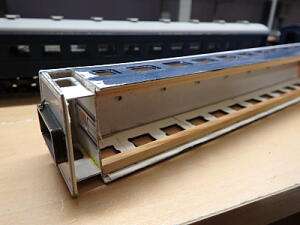

�����̂悤�Ɏ����̎ԗ��ł��E�E�E�@�@�@�@�⋭�͊p�ނ����ł�
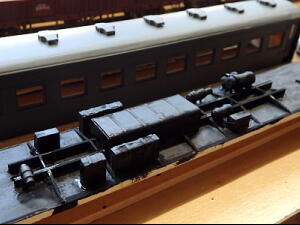

�i�t�q�ɃX�g�b�N���Ă������i���g�����̂ŁA����̐����p�́u�O�v�E�E�E
�����@�����������A��������Ԃ͂P�R���������։��O�ł��E�E�E
������Ԃ͂Q�T�Ԃł����E�E�E
2021/11
�P�O���@�X���ɂP�W�{�ڂ̓���� YouTube �A�b�v���Ă���X���o�߁E�E�E
�P�O���P�W���ɁA�Ȃ�Ƒ��Đ��� �P�O���� ���܂����E�E�E
2021/10
�E���i�������_�u���g���X���̉��Ɍk�J������Ă݂܂����E�E�E

������E�E�E�ƌ����Ă��A�摜�Ƀy�C���g�ł���炵�����M�E�E�E
������ƎR���̓S���炵���H�ł������ȁE�E�E�Ǝv���Ă��܂�
2021/09
�s�n�l�h�w�̂U�W�R�n�T���_�[�o�[�h�V�h���U���Ґ��������܂���
�v�킸�~�����Ȃ��`�Ǝv�������̂̂X���~�߂����i�ɂ��������荞��
�U�W�R�n�ׂĂ݂�ƁA�T�n�ƃ��n�����j�b�g�H�Ȃ�ƃT�n�Ƀp���^�O���t
�ː��W�d������ɂ͎ԗ��Ԃ̓d�͂̈����ʂ����K�v�E�E�E���H���ʓ|�H�H
����Ȏ��h�l�n�m���獂���Ȓʓd�J�v���[���T�Z�b�g�����Ă��܂����E�E�E�I�I�I
���Y�̔����Ă������i�Ƀg���u��������d�C��R�l�O���̉��Ǖi���Đ��Y�����Ƃ̂���
�w��������������i�Ƃ��đ����Ă����̂ł��E�E�E����ɂ͂т�����I�I
����Ƀ��[�J�[�̎p���ɂ��E�X�E�E�E�ł�
�ǂ����ʓd�J�v���[�̓d�C��R���傫���c�b�b�^�]���Ȃǂɒʓd���Ă��d�����ቺ��
�ԍڃf�R�[�_�[�ɕK�v�ȓd���ɂȂ炸�g���Ȃ��Ƃ̃N���[�����������炵���E�E�E�H�H
�����Ƃ��i�t�q�̓A�i���O�^�]�Ȃ̂ŁA���݂̂܂g�p���Ă����Ƀg���u���͂���܂���
�Ȃ�A�]���ɂȂ������̒ʓd�J�v���[���g���A�T�n����ː��d�͂����n�ɑ����I�I
��R�E�E�E�w���ӗ~���E�E�E�ŁA�����Ȃ��X���l�b�g�ȂǂŒ��ׂ�ƁE�E�E
����ς�A�ȑO�c�e�Q�O�O���w�������@��[�邬����[��������@���A��Ԉ���
�W�d�p�̋������p���^�O���t��lj��w���������������Ă��V���~��ł����܂�E�E�E


�����̉摜�͍w�������܂܂̂P�U�D�T�����E�E�E�R����ԂȂ̂�
�P�R�D�R�����։��O�����E���̉摜�́A�ԗ��Z���^�[������Ă��܂��E�E�E


�����̉摜�́A�v���X�`�b�N���T�n�̃p���^�O���t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���̉摜�́A�W�d�p�ɉ��H�����p���^�O���t


�擪�Ԃ̔����J���ĘA���E�E�E


���А��̌��z��Ԃł����A�ő�Q�W�p�[�~���ƂȂ��Ԃ�����܂��E�E�E
���쎞���炱�̌��z��Ԃŋ�]�ɔY�܂��ꂽ��}�W�O�O�O�n�E�E�E
���̌���E�F�C�g�̑��ʂ�[�^�[�̒������J��Ԃ��Ă��܂������A���I�ȉ��P�͏o���܂���ł���
�ŁA�v�����ē��͎Ԃ̐≏���ԗւ̈���� �g���N�V�����^�C�������邱�Ƃɂ��܂����E�E�E
��}�W�O�O�O�n�قǂł͂Ȃ��̂ł����A����W�O�O�O�n����͂���z��Ԃŋ�]���܂��E�E�E
���̍ۂɂ܂Ƃ߂ĉ������邱�ƂɌ��߂܂����E�E�E


����W�O�O�O�n�́A�J�c�~�i�j�s�l�j�̂l�o�M���ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��}�W�O�O�O�n�́A���Ѓ��[�J�[�̓��̓M���@�@�@
�ǂ�����ԗւ̓��ʂ��g���N�V�����^�C�����͂ߍ��ލa������̂ł���
��͂�A���[�J�[�ɂ���ăM���{�b�N�X��j�o�[�T���W���C���g�̎d�l���傫���Ⴂ�܂��E�E�E
������̂܂܂ł͎ԗւ�����Ƃ͂ł��܂���
�ʂɂ��ꂼ�ꃁ�[�J�[�̓����K�i�ԗւ�p�ӂ��A���̎ԗւ������H���Ă���ڐ݂�����@�ł��E�E�E
�j�s�l�̂l�o�M���ɂ͂j�s�l�̃v���[�����А�ԗւ��E�E�E
���Ђ̃M���ɂ͓��Ђ̃s�|�b�g���А�ԗւ�p�ӂ��܂��E�E�E
���ꂼ��Б��i�ʓd���j�ԗւ��O���A�Ԏ����h�����ցE�E�E
�h��������]�����≏���ԗւɍa���@��A�g���N�V�����^�C�����͂ߍ��݂܂�
������h�������[�X�ŁA�a�̓����N�����̃g���N�V�����^�C���i�V�P�T�S�j�K�i�ɍ��킹���܂�
���̌�A�l�o�M���͐≏���ԗւ݂̂����O���A���̉��������ԗւ��������Ď�t�����ł�
���Ђ́A�ԗւ��O���Ăт�����I�I
�������[�J�[�Ȃ̂ɎԎ��Ǝԗւ̎�t���@�����̓M���ԗւƃs�|�b�g�ԗւň���Ă��܂���
���̓M���͎Ԏ��Ǝԗւ̎�t���ɒi��������A���̂����M����t���ɂ��i�����E�E�E
�a���@�����s�|�b�g�ԗւɂ͎��Ƃ̒i�����Ȃ��āA���a���傫�����̂܂܈����ł��܂���
�Y���ʁA�s�|�b�g�ԗւ̎Ԏ��ɃM�����̂��̂��ڐ݂��ԗւ��ƌ������邱�ƂɁE�E�E
�h�������[�X�p�ɊO�����ʓd���ԗւ��Ăш������Ċ��������܂�
�j�s�l�̂l�o�M���͎ԗցi�^�C���j�����̌����E�E�E
���Ђ̓��̓M���̓M�A�����ڐ݂��ԗ֑S�̂̌����ƂȂ�܂����E�E�E
���̍�Ƃ̌��ʁA���z��Ԃł̋�]�͖����Ȃ�A��Ԃ��Ă��X���[�Y�ɔ��i�ł��܂�
�Y�݂͂���ʼn����ł��i(��)�j
2021/ 8

�͌^���E�ɏW�����J�E�E�E�r�����ǂ��������H�������E�E�E
�E�\�̂悤�ȃz���g�̘b�E�E�E
�A���̖ҏ��ŃG�A�R���̓t���ғ��E�E�E
�܂����̃G�A�R���h���C���i�r���ǁj���l�܂�E�E�E
�G�A�R�����炠�ӂ�o�������A�^���̃��C�A�E�g�ɁE�E�E�͌^�̎R������H��
���H��|�C���g��������ԂɁE�E�E���H���̓d�C��H�܂ŐZ���E�E�E
�C�Â��̂��x��A�G�A�R���̑|���ƕ��s���Ĕr���Ɠd�C��H�̕�����ƂŏI���^�x�ł���
�����̂Ȃ��ŁA�ǁ[���Ɣ��������o���܂����E�E�E
2021/ 7
�����U���Q�X���łi�t�q�͂Q�S���N�I�@�߂���������Ƃ����ԁE�E�E
�F�l�̂����͂̂������̂Q�S�N�Ԃł�����܂��E�E�E���ӂ���݂̂ł�
��ɍŗǂ̃V�X�e����ڎw���āA�V���Ȗ����ցE�E�E�����֏o���i�s�I
�|�C���g���܂��܂��̏�E�E�E
������̓A�b�v�̂��߁A���͎Ԃ̎ԗւɂ̓S�����̃g���N�V�����^�C�������Ă��܂��E�E�E
�ŏ��ɑ��������̂� �P�X�W�O�i���a�T�T�j�N�ł��E�E�E
�������Ɍo�N������A����I�Ɍ��������Ă����̂ł�������A�S�ʌ��������@�֎Ԃ�
�g���N�V�����^�C�����Q�{�O��Ă��܂����E�E�E�o�N�ŃS�����ꂽ�悤�ł�
���H��T�����̂ł��������ł����A���ɑ��s�Ɏx����Ȃ��A���̂����ǂ�����
�����邾�낤�Ǝv������ɏڂ������H��_�����邱�ƂȂ����u���Ă��܂����E�E�E
���R�Ɖ^�]���Ă����킯�ł͂���܂��A�ӂƓ���̋�Ԃŗ�Ԃ̎�������������̂�
�C�Â��܂����E�E�E����H����`�O�Ɠ��������������Ă���E�E�E������
�g���l������o�Ă����Ԃ͖��邭�O�Ɠ��⎺�������_�����Ă��܂��E�E�E
�ː��W�d�Ȃ̂ŁA���s�Ɏx��͂���܂���E�E�E�ː��Ɛi�s���������̃��[���ɂ�
�ʓd���Ă��܂����A�E���̃��[���ɂ����d�C������Ă��Ȃ��悤�ł��E�E�E
���H�Ƀe�X�^�[�ĂȂ���_�����Ă����ƁA�g���u���̓g���l�����ցE�E�E
�v���Ԃ�ɁA�g���l���̕������O���_�������猩�����̂͐��H�e�Ƀg���N�V�����^�C�����P�{
����ɁA�悭����ƃ|�C���g�̃g���O���[���ɂ����P�{�����܂�Ă��܂����E�E�E
�P�{�͗�Ԃɂ͂˂�ꂽ�̂����H�e�֗����������Ƃ���A���s�ɉe���͂Ȃ������̂ł���
�����P�{�̓|�C���g��ŊO��ăg���O���[���̊Ԃ֗����E�E�E�i�s�����͏�ɓ����Ȃ̂�
��Ԃ��ʂ�x�ɁA�ԗւƃt�����W�����̐ꂽ�^�C�����g���O���[���̊Ԃւǂ�ǂ�����
���ʁA���������ď��X�ɉ����ꂽ�g���O���[���Ɍ��Ԃ������ʓd���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��E�E�E
������l����Ƃ����ŁA���܂��܌�ނ����q�Ԃ��E�����܂����E�E�E��ނ͂��Ȃ��Ƃ���Ȃ̂�
�����ƋȐ����A����ɉe�������g���u�����Ǝv�����ݎԗ������܂�����
�܂������g���l�����̐��H�͌��܂���ł����E�E�E
�E���͂��̃g���O���[���̌��Ԃ������������̂ł���
�܂������l�����Ȃ��悤�ȃg���u���E�E�E�ł��A�����Ɛ��H��T���Ă�����E�E�E
�ێ�Ɠ_���E�E�E���炽�߂āA���S�̂��߂ɖY��ĂȂ�Ȃ���Ƃł��E�E�E
�o�N�ɂ��|�C���g�Ƃ�Ԃ�
�f���A���Q�[�W�i�R����ԁj �̕����i�|�C���g�j����ꂽ�E�E�E�ό`�̏�ł�
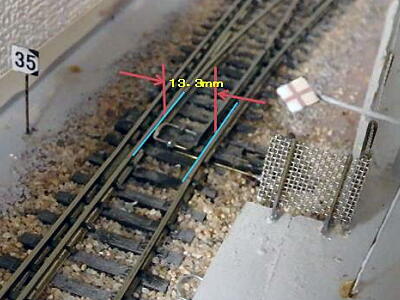
�Q�S�N�O�Ɏ��삵���|�C���g�ł��E�E�E�W���O�ԂƂ̂R�����狷�O������E�E�E
���̃��[���Ȃ�������Ȃ������̂��A�g���O���[�����琔�Z���`�̋�Ԃ�
�O�Ԃ��O�D�R���������Ȃ��Ă��܂����E�E�E
�o�N�ƋG�߂̉��x����ʉ߂̐U���Ō��B���ɂ�ł����悤�ł��E�E�E�H�H
�������O�D�R�����E�E�E�ƊÂ����Ă��܂���
�S�ʌ������I�������s�J�s�J�̋@�֎Ԃ������Ȃ�E���I�I
����ʉߐ������x����炸�����������������̂ł����E�E�E
���ׂ�Ɠ���̋@�֎Ԃ������E�����܂��E�E�E���̋@�֎Ԃ͎ԗւ̃t�����W�������I�I
������͑����̂��߂ɁA�g���N�V�����^�C���������ԗ��ł��E�E�E
���ւɃg���N�V�����^�C���p�̍a�����H����ۂɃt�����W������Ă����悤�ł��i���j
�ً}�H���ł������A�����ւ̐i�����烌�[���̋O�Ԃ��E�E�E
���B�̊ɂݖh�~�ɐڒ��܂������Ă̕�C�ƂȂ�܂����������ɊJ�ʂł��E�E�E
�ʉߑ��x�����͕ύX�Ȃ��E�E�E���̖h�~�I�I����������Ȃ���ł�(��)
�����ԑ��s���Ă����d�e�T�V���S�ʌ����œ��ꂵ�܂����E�E�E
�����I�����s���Ă������Ƃ������āA����̌����ł͎ԓ��z���X�V�̗\��ł���
�������Ă݂�ƁA�O�Ɠ��̐؊����ɉ���������^���Z�������������g���Ă���
����́A�������������V�������^���_�C�I�[�h�֒u�������邱�ƂɁE�E�E
�͌^�I�ɑ傫���ꏊ���Ƃ�Z�����������P������ƁA�ԓ��ɂۂ�����Ƌ�Ԃ��E�E�E
�ӂƎv�������̂��A������߂Ă��������A�e�[�����C�g�̓_�����ł��E�E�E
�P�@�␄�i�^�]���ɂ��_�����K�v�ƁA�����������Ƃ��������̂ł���
�O�t�������v���̃e�[�����C�g�́A�z���C�g���^�����p�[�c�ɐԐF�h�����{�����_�~�[��
�����ɐԐF�v���X�`�b�N���̃����Y���͂ߍ��ނɂ͉��H������E�E�E
���̂����ԓ��ɑ傫�ȃZ���������킪����̂Ō�����ݒu����ꏊ�̊m�ۂ������
���ǁA���̎��͖����ƒ��߂Ă��܂����E�E�E
����́A�Z����������̓P����̋�ԂɌ�����ݒu�A����������t�@�C�o�[��
�������ė��p���邱�ƂɁE�E�E�e�[�����C�g�p�[�c���ق�̏������H���ē_�����E�E�E
�T�O�N�̎����ĐԂ��P���܂����E�E�E



���͂Q�G���h�Ń_�~�[�e�[�����C�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�G���h�̉��H�����e�[�����C�g
�_�u���g���X����ʉ߂���d�e�T�V

2021/ 6
�w�ԐM���@ ����~�M���u�ԁv�̂܂܂����܂����E�E�E
�ĊO�ƒm���Ă��Ȃ��S���M���̂��Ƃł��E�E�E
�S���̐M���@�͕ۈ����u�̈ꕔ�ŁA�i�s�M���u�v�� ���̐M���܂ł̋��
��Ԃ̈��S�^�s��ۏႷ����̂ł��B�@�����A��~�M���u�ԁv���z���Đi�s�����
�E����Փ˂ȂǗ�Ԏ��̔����ɂȂ���܂��̂ŁA��Ɏ��Ȃ���Ȃ�܂���
�������A�q���[�}���G���[�͕K��������̂Ȃ̂ŁA�e����S���u �i�`�s�r���j��
��������V�X�e���Ƃ��Ă����S��ۏႵ�Ă��܂�
�S���M���͗�ԏ斱���ɑ���Ɩ����߂��A�ƕ��������Ƃ�����܂��E�E�E
���Ȃ݂ɓ��H��ʂ̐M���́A�~���Ȍ�ʂ̗�����m�ۂ��邽�߂̌�ʐ����ł�����
���Ƃ��u�v�M���Ō����_�ɓ����Ă����S�͕ۏႳ��Ă��܂���E�E�E
���ׂĂ͒ʍs����҂̎��ȐӔC�Ȃ̂ł��E�E�E
�p��ł́A�S���M���́@SIGNAL�@�ł����A��ʐM���́@TRAFFIC LIGHT ��
�M���ł͂Ȃ���ʕW���Ȃ̂ł��E�E�E
�i�t�q�̐M�� �g���u���̌����́A�Ȃ�Ɛݒu�̍ۂɍH���̊ȗ����̂��� �O�D�R���� ��
�A���~���g�p���Ă����Ƃ���A�����[�i�p�d��j�̓d�������삷��U���ł��̃A���~��
�ό`�A�������ɐݒu���Ă����_����H�̐ړ_������ĐڐG�s�ǂɂȂ��Ă����̂ł��i���j
�������^�s���̗�Ԃ� �`�s�r�̓���őO���́u�ԁv�M�����m�F����~���܂����E�E�E
2021/ 5

�����I���g�p���Ă����S�T�T�n�̃p���^�O���t������E�E�E
�莝���̐V�����p���^�O���t����t�悤�Ƃ��āE�E�E�p���^��̃T�C�Y������Ȃ��I
�o�r�P�U�n�ł������p�ƌ��p�Ŏ�t�T�C�Y���Ⴄ�I
���X�Ȃ�����߂ċC�Â�����܂����E�E�E
�S�T�T�n�͌��d�ԂȂ̂ɁA�����A��ɓ��钼���p�𓋍ڂ��Ă����̂ł�
��t�ʒu��ύX����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA���H�̎�Ԃ����Ȃ����̂܂�t�\��
���^�̒����p�p���^�O���t�𓋍ڂ��Ă����P�P�V�n���痬�p���܂����E�E�E
�P�P�V�n�ɂ́A�p���^�������S�T�T�n�̃p���^��ƌ�������
�莝���̐V�����p���^�O���t����t�܂����E�E�E
�摜�ŁA�p���^��̈Ⴂ���悭�킩��Ǝv���܂��E�E�E�i��)(�j
�Q�O�P�W�N�Q���Ɍ��J��������@�u���ւł̓��}�x�m�@�֎Ԍ����v�̍Đ���
�}�ɑ����Ă��܂��E�E�E���͎��I�ɂ́A��Ԍ��Ăق�������Ȃ̂ł����E�E�E
�ǂ����č�����ɂȂ��āE�E�E�H
�ł�����ς������
�������}���ʂȂ̂ł��傤���i�j
2021/ 4
�т�����ł��E�E�EYouTube �ɃA�b�v�����ː��W�d�̍�}�d�ԁE�E�E
��}�d�Ԃ̒��ł����̍D���Ȍ`���̂W�O�O�O�n�E�E�E�ł�
�Đ�����C�ɑ����܂����E�E�E����ς��}�d�Ԃ��Đl�C�������ł��ˁI
���������܂ŁA�Q�O�P�W�N�Q���R�����獡�܂łP�Q�{�̓���� YouTube �ɃA�b�v���Ă���
�R�N�ڂ̂Q���Q�W�ɑ��Đ����P������z���܂����E�E�E���ӁA���ӂł�(��)
2021/ 3
�i�t�q�ł́A�g�n�ԗ�������P/87�T�C�Y���^�p���Ă��܂�
��Ȏԗ��͐V�����Ȃ̂ł��� �A���B�̎ԗ����������Ă��܂��E�E�E
����Ȏԗ��ɂ��āE�E�E
�ԗ��̒������R�O�b�������^�łi�t�q�̌��z���E�M���M���ł�
�قƂ�ǂ������i�Ńv���X�`�b�N���E�E�E�����m���ɑ���Ηǂ��āA�܂��������Ȃǂ͂���܂���E�E�E
�ԗւ̃t�����W�������{���̂P�D�T�{���������āA���s�͒E�����Ȃ������قǂ̋}�Ȑ����ʉ߂��܂�
���[���b�p�ɂ͓S���͌^�ɂ��W���̋K�i�������āA�Ⴄ���[�J�[�Ԃł��A����₻�̑��̃I�v�V������
�������t���ł���悤�ɂȂ��Ă��āA�ԑ̂��͂ߍ��݂����������͊ȒP�ł��E�E�E
�������ԗֈȊO�͑�Ԃ��v���X�`�b�N���Ȃ̂Ŏc�O�Ȃ���ʓd���܂���E�E�E
�i�t�q�H��ʼn������O���������i�p�l�����C�g�j���A��Ԃ͉��H���ďW�d�u���V����t�ł�


�v���X�`�b�N���i�́A�������t���������ł������ԑ̂����Ă��܂����H���K�v�ł�


���̉摜�́A�����̌�둤�ɕė��d�������ꂼ��Z�b�g���Ă��܂��E�E�E�E�̉摜�͉��C��ł��E�E�E
�ė��d�����Z�b�g������������̎ԑ̂ɂ͌������߂��Ă��܂��Ă��܂��E�E�E�E
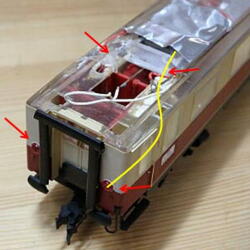 ���C���@�����t�@�C�o�[�̗��p�ł��E�E�E
���C���@�����t�@�C�o�[�̗��p�ł��E�E�E�������܂ŁE�E�E���t�@�C�o�[�̌����̓p�l�����C�g���ł��E�E�E
���F���C���ɉ����Č��t�@�C�o�[��L���Ă��܂��E�E�E
����Ō��R��͂���܂���
�d�P�O�R�^�@�֎Ԃ����B�͌��z���E���傫���̂ŁA �p���^�O���t���ː��������ɍ��킹
�傫�����͂ȃo�l�Œ��ˏオ��܂��E�E�E�i�t�q�̉ː����ɂ͑S���Ή��ł��܂���


���̂܂܂ł́A���s���ɉː��������グ�Ĕj���ɂȂ���܂��E�E�E

�������Ăi�t�q�K�i�ʼnː��ɐڂ��Ă���p���^�O���t�E�E�E
�ԗ��͎ԓ��Ƀp���^�O���t�W�d�̂��߂̐؊����X�C�b�`�����݂���Ă���̂͂������ł��E�E�E
�s�d�d�q�Ԃ̔������C�O�摜�ł����A���s���悪YouTube�Ō���܂��E�E�E
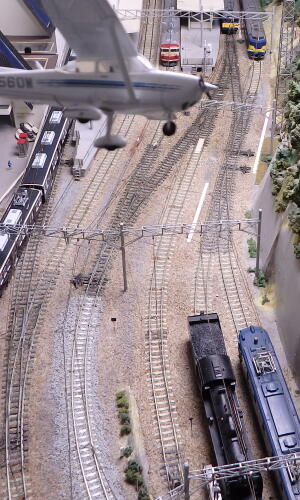

�Z�X�i�@�ŁA��߂Ƃ��w����B�ł��E�E�E

�N���P�T�V�̑O�A���n�P�T�U-�Q���^�]�s�\�ɁE�E�E
�������Ē��ׂ�������ɂ��ُ�Ȃ��E�E�E�e�X�^�[�ł̒ʓd�������n�j�E�E�E
�Ȃ̂ɁA�����������Ǝv������}��~���đS���������E�E�E
���s����E�E�E����g���Ă��J��Ԃ��킩�����̂́A�Ȃ�ƕ����̎��ɑS���G��Ȃ�������
�{���X�^�[�̃Z���^�[�s���[�ł���
�Z���^�[�s���ɂ́A�X�v�����O����ċ��d�p�̒[�q���l�W�~�߂��Ă��܂��E�E�E
���̃l�W���ɂݒʓd�s�ǂ��N�����Ă����E�E�E�������ڐG�i�ʓd�j���đ��s���A����Ē�~
�y�[�p�[�ԑ̂Ȃ̂ŏ����ؐ��ŁA�ʓd�[�q�̓��b�V���[���ŋ��܂��Z���^�[�s����
�l�W�����ŏ��Ɉ������Ă����̂������E�E�E�o�N�Ō��Ԃ��ł��Ă����炵���E�E�E�i���j
���Ȃ݂ɏ��a�S�X�i�P�X�V�S�j�N����ł��E�E�E
2021/ 2
������}�̑��s�摜��YouTube�ɃA�b�v���āE�E�E�ԗ��̑��ʂɉ���������Ȃ�
�ԑ����������E�E�E
�C�ɂȂ�ƁA�ǂ����Ă����u�ł��Ȃ��āE�E�E
�d�v�������łi�t�q�H��֓��ꂵ���̂��K���Ɏԑ����̎�t�H�������{�ł�



�����̎ԑ����E�E�E�@�@�@�@���t�����͌^�̎ԑ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ă_�u���f�b�J�[�̎ԑ����ł��@�@�@�@�@�@
�i�t�q�ł͎ԗ��̉^�s���u���b�N�R���g���[���ōs���Ă��܂��E�E�E
�u���b�N�̋��ڂ��M���b�v��݂��ă��[�����ː����ʓd���Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��E�E�E
���[���̋�ԃu���b�N�́A�M����Q��ԉ^�]�Ȃǂɂ��Ή����Ă��܂��E�E�E
�ː��W�d�ƎԍڃJ����������܂��̂ŁA�P�l�ł͓���ł���������
�S��Ԃ܂ʼn^�s�͉\�ł��E�E�E�i�^�]�m���Q�l�͕K�v�ł�(��)�E�E�E�j
�c�b�b�i�f�W�^���E�R�}���h�E�R���g���[���j���̗p����A�����ɗ��_��͂X�X�X��Ԃł�
�^�s�ł��܂����A���H�����������u���b�N��������K�v����������܂���E�E�E
�ȒP�ɂc�b�b���������A�펞���H�Ɍ𗬂P�Q�u��ʓd���܂��E�E�E
���[�^�[�ւ̓d���R���g���[���́A�f�R�[�_�[�𓋍ڂ����ԗ��������Ő������čs���܂��E�E�E
�Ȃ̂ŁA��ʓI�ȃp���[�p�b�N���璼������H�֗����X���b�g���m�u�ł̉������͂���܂���
�f�R�[�_�[�͂����鏬�^�R���s���[�^�Ȃ̂ŁA��Ԃ��Ƃɂh�c��ݒ肷�邾���łł�
�v���O���������o���Ă���A�p���^�O���t���グ����A�h�A���J������A�T�E���h�܂ł��点�܂�
�܂��ɁA���ꂼ��̗�Ԃɉ^�]�m������Ă���悤�ŁA�����Ȃ��Ƃ����R�ɃR���g���[���ł��܂��E�E�E
�����E�E�E�����ł���
�i�t�q�ɂc�b�b�����邽�߂ɂ́A�ԗ��P�䂸�i���͎Ԃ����j�ɂ܂��f�R�[�_�[
�i�P�䐔���H�~�j�𓋍ڂ���K�v������A���̂����V���ɃV�X�e�����č\�z����E�E�E
����Ȃ��ƁA�R�X�g�Ǝ��Ԃ��l���������ł��c�O�Ȃ���s�\�ł��E�E�E
��}�W�O�O�O�n�Ɠ����ɋ�����}�W�O�O�O�n���^�]����ƁA�ǂ�����W���Ґ�
�Ȃ̂ŁA�i�t�q�̃u���b�N�R���g���[�����I�[�o�[���Ă��܂��܂����E�E�E
�R����� �̂�߂Ƃ��w�P�Ԑ����Q�O�����ԂU���Ґ��܂ł����u���b�N�Ή����Ă��Ȃ��̂�
�����グ������̎��R�ȑ��Ԃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��E�E�E
�����Ńu���b�N�����M���b�v�̈ʒu��ύX����ً}�H�����s���܂���
��}�W�O�O�O�n�l�ԁi���͎ԁj������E�E�E
�^�]�𑱂��Ă���ƁA��͂���z��Ԃł̃p���[�s�����C�ɂȂ�܂��E�E�E
�ԗ���V������ۂɕ������Ċ����i�̓��̓Z�b�g���A�S���̂l�Ԃ��ׂĂ�
���t�����̂ł����A���̓��̓Z�b�g���Б���ԋ쓮�������̂ł��E�E�E�Ȃ̂�
�E�F�C�g�ʂ��Ă����ʂ����������ւ���]�������ʼn����ł��܂���

�����i�̓��͂́A�Б��̑�ԁi�����j�݂̂̋쓮�E�E�E

�S���̓��͎Ԃ����ăp���^�O���t�����̂Q���ɋ쓮���u��������t�E�E�E
����ŗ�����ԋ쓮�̎ԗ��ƂȂ��āA�E�F�C�g�̌��ʂ����҂��ł��܂��E�E�E

����Ɏԍڂ̃E�F�C�g��V���E�E�E��t�l�W��z����������v�ʼn���n�����H

�V�������E�F�C�g���ԓ��ύڂ�����Ԃł��E�E�E
����Ō��z��Ԃł̉^�]���y�ɂȂ�܂����E�E�E
���ԁ@��}�W�O�O�O�n�́A���a�U�S�i�P�X�W�X�j�N�P���P����ː����w�Վ����}�Ńf�r���[
������A�i�t�q�̍�}�W�O�O�O�n���P���P���̃f�r���[�ł��E�E�E�R�Q�N��ł����E�E�E
2021/ 1
��}�W�O�O�O�n �� ������}�W�O�O�O�n�ƕ��� �E�E�E

��}�W�O�O�O�n�́A���^�]���ɏ����z��ԁi�Q�W�p�[�~���j��
��Ԃ���ƁA�Ȃ�ƍĂє��i�ł����A���ɂ͌�ށE�E�E
���Ђi�t�q�̐��E�ł͂P���łQ�W���������Ȃ���z�ł����A���ۂ̓d�Ԑ��H�ł�
�����Ƌ}���z�̂R�T�p�[�~���܂ł͑��݂��܂����A�ꕔ�ł͂T�O�p�[�~���̂Ƃ�����E�E�E
�Ȃ̂ŁA���Ђ̌��z��ԂȂ�d�Ԃ͕��ʂɑ��s�ł��邱�Ƃ����߂��܂�
���R���Ŏv����������Ȃ��Ƌ삯�オ��Ȃ��E�E�E
��͂ȋ쓮�V�X�e���̌��_�������яオ��ȂǏ����g���u�������o�E�E�E
�Ȃ�Ƃ��ʏ�̉^�]���ł���悤���s����̌��ʁE�E�E����Ɗ����ł�
�i�t�q�H�ꂩ��W���O�Ԑ�p���֔���������}�W�O�O�O�n�E�E�E

���^�]�Ɍ����ʓd�����Ȃǐ������ł��E�E�E
 ������Ⴂ�܂���(��)
������Ⴂ�܂���(��)

�ː��Ǐ]�̂��ߍ����������E�E�E�͂���ꂷ���Ăo�s�S�W������ł�
�����������t�����p���^�O���t����������~�낵�܂����E�E�E
�C���̎v�Ē��ł��E�E�E
2020/12
�i�t�q�H��ł���}�W�O�O�O�n���������C���ɁE�E�E

�Ăъ��̎��S�E�E�E�W���O�Ԃ̎ԗ������ł��E�E�E
�S�l�S�s�̂W���t���Ґ��ł�
�����@�l��1+�l2+�s1+�s2+�s2+�s1+�l1+�l��2�@ �_�ˁE��ˁ�
�p���^�O���t�Ƃu�u�u�e�C���o�[�^���ڐ���d���ԁE�E�E�l���P
�u�u�u�e�C���o�[�^���ړd���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l�Q�@
���k�@�E�Î~�^�C���o�[�^�i�r�h�u�j���ڕt���ԁE�E�E�E�s�P�@
���ʂȋ@��͓��ڂ��Ă��Ȃ��t���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�s�Q�@
�p���^�O���t�Ƃu�u�u�e�C���o�[�^���ړd���ԁE�E�E�E�E�l�P�@
�u�u�u�e�C���o�[�^���ڐ���d���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l���Q
���ׂĂ̂l�ԂɃ��[�^�[�𓋍ڂ��܂��E�E�E��������ː��W�d
�Ȃ̂ŁA�l�Ԃ̘A���̓p���^�O���t��t�Ԃ��狋�d�p�W�����p�[�����H�H���K�{�ł�
��ː��Ŕ\���d������Ή��ԁE�E�E�����A���e�i���Q�{�삵�܂�
������L�����ƂɁA�K�v�Ȏԗ��f�[�^�� �F�c�ԗ� ���瑗���Ă��܂���
�ق�Ƃ��Ɋ��ӂł��E�E�E
2020/11
�N�����P�S�T�́A�P�X�W�O�N��ɒʋΌ^�P�O�P�n�d�Ԃ���������삳�ꂽ
�ԗ���n�̓������p�̒�����������ł�
�~�����Ƃ��Ă��g����悤�ɐ������ꂽ�P�O�O�ԑ�̎ԗ������f�����ł�
����ɗ��p�����̂́A�V�ܓ����甭�����̂s-Evolution�V���[�Y��
�v���X�`�b�N�����f�B�X�v���C���f���ł�
�i�t�q�ɔz�u���Ȃ��A�ȑO����~�����Ǝv���}�ʂƎ����͎����Ă��܂����E�E�E
�������ꂽ�ԗ��́A�����ڂ��Y��ő��s���ɕʔ��I�v�V����������Ƃ̂��ƁE�E�E
�ŁA�H�w�������w���E�E�E��ɂ��Ăт�����E�E�E�ق�Ƃɏ����p�ł���(��)
�ː��W�d���P�R�����Q�[�W���ɁA�ʔ��I�v�V�������p�͔�p�������O�ԕύX���ʓ|
�ǂ������H����Ȃ�莝���̕��i�����p���悤�ƁA�����Y��Ȏԑ̂����𗬗p���܂���
Evolution �i���H�V���[�Y�ɋt�s�ŁE�E�E�莝���̕��i�͂R�O�N�ȏ���O�̋������
����ɏc�^���[�^�[�Ƌ��ԈˑR�̑��s�V�X�e�� �C���T�C�h�M�A ��g���݁A�W�d�p��
�p���^�O���t���������ցA�A����������A�O�Ɠ�������A�������Ȃǂ���t���܂���


��߂Ƃ��w�\���ʼn^�p���E�E�E
�i�t�q�H���͓S���ȊO���q��@����������܂�
���ɂ͓S���ԗ��ׂ̗ōq��@�̐����������Ȃ�Ă��Ƃ��E�E�E


�ԗ��������C�������H�e�ŁA�C�������[�����̃G���W�����Ă��܂��E�E�E ���������쒆���s�S���K�@�E�E�E


�������̃Z�X�i�@�ƎO�H�l�t-�Q�`�E�E�E�i�t�q�ԗ��H��́A�z���A�����H�ɂ��אڂ��Ă��܂��̂�
�v���y������]���̃Z�X�i�́A���̂܂ܗ����Ɍ����ă^�L�V���O���\�Ȃ�ł�
�ǐ�������@ Cessna�E�E�Etaxi into position and hold�E�E�ERunway18�E�E�E �Ȃ�ĕ������Ă������ł�(��)
�w�ԐM���@ �����F�����E�E�E���s�Ői�s�E�E�E�����Ƃ����Ԃɐ�s��Ԃ��ڑO�ɁE�E�E
�ԍڃJ�����ʼn^�]���̏o�����ł��E�E�E
�w�o���M���Ɖw�ԐM���@�̋������Z���A�V�`�W���Ґ��̎ԗ�����s����ƕ�����ԓ���
��s��Ԃɒǂ��t���Ă��܂����E�E�E
�Ґ��̐擪�����̕Nj�Ԃi������ƐM���͐ԐF���������܂��E�E�E
���̎������Ɍ���̐M���͉��F���������܂����A�����Ґ����Ƃ܂����̋�ԂɎԗ����c���Ă��܂�
����ŁA���F�����Ői�s����Ɛ�s��Ԃ��ڑO�ɂȂ�g���u���ƂȂ�܂��E�E�E
�M���Nj�Ԃ������ꂩ���݂���E�E�E�ł����A�͌^���E�ł͋��������܂���E�E�E
�����ŁA�w�Ԃ̐M���@���P�Ґ����i�W���j����ֈڐ݂��܂����E�E�E
�������ڐݐ�͋Ȑ���Ԃ̐^�Ō��ʂ��s�ǁE�E�E
�Ȑ��i�����钼�O�ɒ��p�M���@��ݒu���邱�Ƃɂ��܂���
�V�������p�M���@�̐���ƈڐݐM����H�̍\�z���`�s�r�؊����ȂǂȂǁE�E�E
�v���Ԃ�ɓ����p�j�b�N�I�I�ł����i(��)�j
2020/09
�ې��ԗ��̕�C�⎎�^�]�Ȃǂʼn���� �ȈՕ����i�����|�C���g�j�𑀍삵�Ă���ƁE�E�E
����ƒʉߐ������z����I�[�o�[���[���̒����Ȃǂ��ʓ|�ɂȂ��āE�E�E
����� ��P�����ĕ�����V�����ݒu���܂���
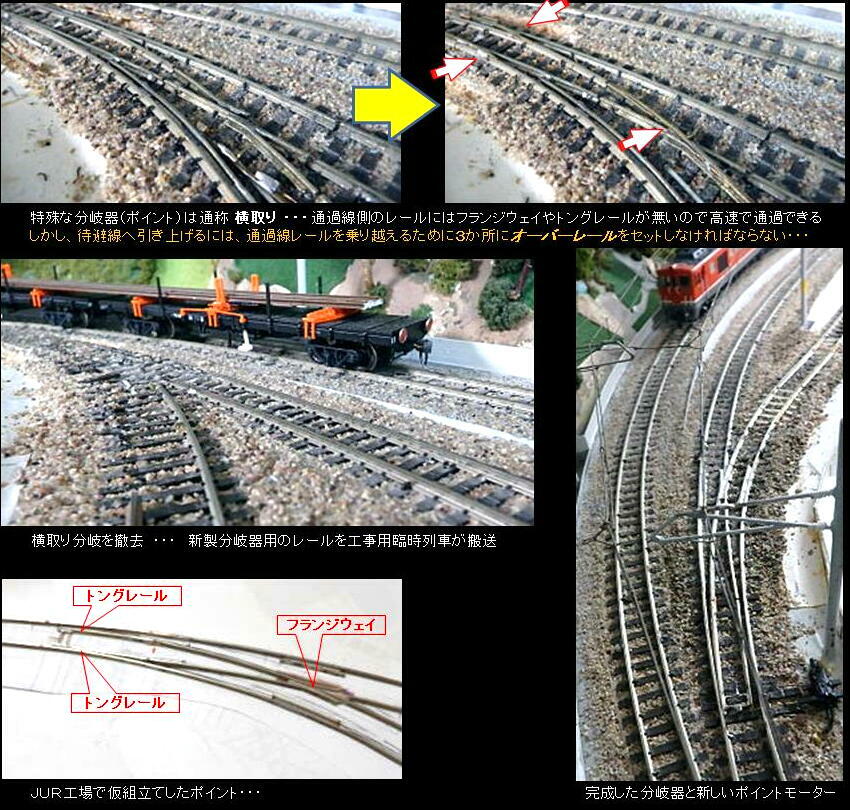
�ې��ԗ���p�̑����Ȃ̂ŕ����̐�ւ��ɁA�����]�Q�@��ݒu�������ł���
�������A���ۂɏk���T�C�Y�Őv���Ă݂�ƁA�����ʂ�̓����������ɂ͋��x�s���E�E�E
���̓s�x���̐����]�Q�@����œ������̂͊ȈՕ����Ƃ��܂�ς�炸������߂܂����E�E�E
�͌^���E�Ȃ̂ŁA�ʓd�̂��߂̐��H�I���X�C�b�`�삳����ƕ������ւ��悤��
�M�~�b�N���������|�C���g���[�^�[�i�_�~�[�p�[�c�j��ݒu�ł��E�E�E
![�����]�Q�@�E�E�E](mapw.jpg)

���̉摜���A�����]�Q�@�E�E�E�@�@�E���́A�|�C���g���[�^�[
2020/08
�}���`�v���^�C�^���p�[�l�s�s
�܂������}���^�C�Ƀg���u���E�E�E
���N�g�p���Ă����ې��p�ԗ��}���`�v���^�C�^���p�[���E���E�E�E
�}�Ȑ��̓�������v���菙�s����Βʉ߂ł��邪�A������������ƒE���E�E�E
���S�����ۂ���Ă܂���E�E�E�ŁA�l�����錴���͘A����I�I
���i�^�]������Ǝԗ����A����ɉ�����ĒE���E�E�E

���̎ԗ��̘A����́A���[���b�p�͌^�̎嗬�����E�E�E
���[�v�J�v���[���ԃ}�E���g���A�����Ƀo�b�t�@�����Ă��܂����E�E�E
�v�����āA�����A����������ăo�b�t�@���P���ł��E�E�E

�A����͂�������Ԃ���藣���Ďԑ̃}�E���g�ɕύX�E�E�E
�g�p�����A����̓v���X�`�b�N�̂j�`�s�n�������H�E�E�E
�����Œʉ߂��Ă��E���͖����Ȃ�܂����E�E�E
����ς����S����I�I�ł�
---�@�S�ʌ����@---
����Q�U�O�O�n���������āA�i�t�q�H��ł͋v���Ԃ�Ɏԗ��̌����J�n�ł��I
�����J�n�̑�P���́A���C�@�֎��b�T�W�̑S�ʌ����E�E�E


���������S�W�N�E�E�E�܂��܂������ő��s�ł���悤�ɒ����ł��E�E�E
�O�Ɠ��̌����A�z���⏙���ȂǁA�C���ӏ������������ɁE�E�E
�{�C���[�̊O���ɐV���ɔz�ǂ�lj������肵�āA�������O���[�h�A�b�v�ł�
������p�Ԃ��E�E�E�Ǝv���g���u�����畜�A���J��Ԃ����@�֎Ԃł����E�E�E
���݂͊ȈՂȂ�������C�T�E���h�┭�����u��g�ݍ��D����̂̋@�֎Ԃł�

�i�t�q�H����S�ʌ����������^�]�E�E�E ��߂Ƃ��w�łP�W�P�n�ƂP�T�V�n���}�Ґ��̊獇�킹
�Ƃ��@�͂P�X�U�Q�N�o��̏�z���}�P�U�P�n�ł��E�E�E
���@�͂P�T�P�n�łP�X�U�O�N�ɓW�]�ԕt�q�ԓ��}�u�߁v�u�͂Ɓv��d�ԉ�����ۂɓW�]�Ԃ�
�����ɍ��ꂽ�P���ԁi�����j�p�[���[�J�[�ƁA���̂Ƃ�����S���H���Ԃ��A�����ꂽ�Ґ��ł�
��ɏo�͑����Ɛ��������ύX���Ă��ꂼ�ꂪ�P�W�P�n�ƂȂ�܂����E�E�E


�P�X�V�P�i���a�S�U�j�N�����̂P���q���X���T�S���h�����E�E�E�S�ʌ����ōēh���ł�
2020/07
�U��Ԃ�����Ƃ����ԁI�I
�����Ȑl�E�E�E�݂�Ȃ̋��͂� �U���Q�X��
�Q�R�N�����}�̂悤�ɑ��蔲���܂����E�E�E
�V���������� �o���i�s�I �ł��E�E�E
�L�O��Ԃ͐�������������ʗ�Ԃł��E�E�E
�������Ɨ����y���݂Ȃ���E�E�E�F�l�Ɋ��ӂł��I�I
---�@Keihan 2600�@---
����Q�U�O�O�̐����ɂ��Ă��z�����E�E�E
���n�߂Ė��V�����E�E�E����Q�U�O�O�n�T���Ґ����A����Ɗ����ł��E�E�E
����̑z���́A�Ȃ�ƂT�O�N�O�E�E�E�P�X�V�O�N�i���a�S�T�N�j���܂ł����̂ڂ�܂��B
�ŏ��́A����������Q�O�O�O�n�`�X�[�p�[�J�[�`�ƌĂꂽ���������̒ʋΓd��
���̎ԗ��̖͌^����낤�Ǝv�����̂ł��B
��������ɂ͊����i�̑�Ԃ��w�����Ă���}�ʂ������n�߂Ă܂����E�E�E
����Q�O�O�O�n�͓Ɠ��̃G�R�m�~�J����ԂŁA�����������i�͂���܂���E�E�E
�����̎��ɂ͑�Ԃ܂ł͍��Ȃ��E�E�E�ł��A������Ԃ��̔����ꂽ�炻�̎��́E�E�E
�ƁA�܂��͎ԗ��f�[�^�̎��W���n�߂܂����B
�i�t�q�́A���O�̍��S�ԗ������łɉː��W�d�ʼn^�]���Ă��܂�����
���[���͊����i���g���Ă����̂ŁA�W���O�Ԃ��P�U�D�T�����E�E�E�ł����B
�����鐢�E���ʂ̂g�n�Q�[�W�Ń��[�����́A�W���O���P�S�R�T�����̂g�n�T�C�Y�W�V���̂P�� �P�U�D�T�����ɂȂ�܂��B
���{�̖͌^�͎ԗ����������H�̂Ń��[�����ȊO�́A�W�O���̂P�Ő��삳��Ă��āA �g�n�łȂ��P�U�ԂƌĂ�Ă��܂��B
�P�X�V�T�N�i���a�T�O�N�j���ɂȂ��āA�ԗ��ƃ��[���̕��� �M���b�v �ɔ[���ł���
�ǂ������Ȃ烌�[���̕����E�E�E�ƁA�O�Ԃ̕ύX���v�����Đi�߂܂����E�E�E
�����i�̃��[�����͂����A�V�������������Ȃ����A���[�������B�ŌŒ肵�܂��E�E�E
���̐��H�~�ݍH���́A�����i�|�C���g�j�Ȃǂ��ׂĎ��삷���H���ɂȂ�܂����B
���݂̃��C�A�E�g�O�ԁE�E�E�����ʂ�̋��O�P�R�D�R�����̒a���ł��B
�����̍��S�A���̂i�q�e�Ђ́A���O�̐��H�����P�O�U�V�����ł��E�E�E �W�O���̂P�ɂ�����P�R�D�R�����ł��B
�]�k�ł����E�E�E
�����č��S�����O�̏��������l�����W���O����ւ��悤�ƈꕔ�̎ԗ��ɂ͂��̏����H�����Ȃ���Ă��܂����B
�Ԏ������H���ɂ킩�����̂ł����A�����Ƃ����Ďԗւ��O���֍L���W���O�Ԃɂł���悤�ɁA�Ԏ�������
�܂���Ԃ̕����L���q�Ԃ�d�Ԃ�����Ă��܂����B������̎ԗ����Z�������O�̂̂܂܂ł���
���̖��́E�E�E�V�����Ƃ��Ĕ��W�������܂����E�E�E
���łɕۗL���Ă����ԗ��̎Ԏ����R�D�Q�����������邽�ߐؒf��ԗւ̈������H���n�܂�E�E�E
���̎��_�ŕW���O�Ԃ̎ԗ��́A����Q�O�O�O�n���܂ߐ����₩�炷�ׂĂȂ��Ȃ�܂����B
���̍��A����Q�O�O�O�n�́A�ː��d���U�O�O�u����P�T�O�O�u�֏����ɂƂ��Ȃ��ԗ�������
�Ή��ł����A�P�O�O�������̎ԗ����p�ԂցE�E�E����������́A�P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j��
���̂Q�O�O�O�n�̎ԑ̂𗘗p�����P�T�O�O�u�Ή��̂Q�U�O�O�n��a���������̂ł��B
����Ɋ��S�V���̂Q�U�O�O�n�R�O�ԑ���a�������A�����P�R�O���]�肪����o�����̂ł��E�E�E
�ԑ̂͂Q�O�O�O�n���̂܂܂ɁA����ɂ̓N�[���[�A�O�ʂɂ̓X�J�[�g�i�r���j����t��ꂽ
�Q�U�O�O�n������ƁA���̎ԗ����܂��܂��͌^���������Ƃ����C���������オ���Ă��܂����E�E�E
���������̎����̂i�t�q�͋��O�ŋO�Ԃ��Ή����Ă��܂���B
����ł������͍���Ă݂����ƁA�Q�U�O�O�n�̃f�[�^���W��V���ɂ͂��߂Ă��܂����B
�������i�t�q�H��Ő��삵�Ă����̂́A��͂荑�S�A�i�q�^����ł����B
�]�@�ƂȂ����̂́A�P�X�X�U�N�i�����W�N�j����V�������n�߂����C�A�E�g�ł��B
�����ɐV�����P�U�D�T�����ƂP�R�D�R������ ���p��ԁi�R������j��݂������Ƃ�
�ߓS�A�[�o�����C�i�[�ȂǕW���O�Ԃ̎ԗ����������Ă��܂����E�E�E
����Q�U�O�O�̖͌^�͂��̌チ�[�J�[���甭������܂������A�������[�J�[���̔����Ă���
������}�W�O�O�O�n�g���ăL�b�g���ɍw�����܂����B�������A���̃R�X�g�����ɂ͂��܂��
�����߂������Ƃ���A����ɋ���Q�U�O�O�n�̍w���́A�o�ϓI�ɖ����Ƃ�����߂܂����B
���̌㐔�N���ēX���Ō��������Â̋���Q�U�O�O�n�����i����͂荂����
�����Ė������Ď�ɓ��ꂽ���Ǝv���C�����͑S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�i�t�q�V���C�A�E�g���݂���Q�O���N�E�E�E
�~�ς����Q�U�O�O�n�̃f�[�^�ߎv�āE�E�E�ŁA�i�t�q�ԗ��H��̋Z�p�Ŏv������
���N�̖����������ׂ��A�Q�U�O�O�n�̐���E�E���Ԃ������Ă����S��������邱�ƂɌ��߂܂����B
�����Ń��[�R�X�g���߂����āA�ޗ��͎�Ɏ��E�E�E�y�[�p�[���̎ԑ̂ƌ���
�ː��W�d�̈׃p���^�O���t�����͋������̊����i�𗘗p������̂�
���̑��̕K�v�ȕ��i�͂��ׂĎ莝��������A��������Ԃ�����E�E�E���邱�ƂɁE�E�E
�ԑ̂̌^�����o���Ȃ���A�o�N�ʼn������d�˂��Q�U�O�O�̑��푽�l�ȑ�Ԃ̃f�[�^����
�̗p�����Ԃ�I�����邽�߂̉摜���������ɁE�E�E�Ȃ�Ɗ��������Ƃ�
�i�t�q�o���S�����A���������i�̑�Ԃ�����Ȃ��p���S����ƁE�E�E
���[�J�[�Ɋ����i���������̑�ԁA����ނ����ꂼ��P�A�Q������ՓI�`�Ɏc���Ă����̂ł��B
���������萶�Y�i���Ă��ƂŁA�ʏ�P�����Q�`�R��~�Ȃ̂ɂ��̂Q�{�ȏ�̉��i�ł����B
���ǂ̂Ƃ���́A�T�����Ő����~��������ɂ��o��ƂȂ�܂������E�E�E
��ނ̈Ⴄ��Ԃ����������삷���Ԃ��l����ƁE�E�E
��ɓ��ꂽ��Ԃ߁E�E�E���ӁA���ӂł��E�E�E
�U���Q�P���`�Ȃ����`�����Ԃ̑z�������߂Đ��삵���Q�U�O�O�n���A����Ɗ���
�i�t�q�ԗ��H�ꂩ��o�ꂵ�Ă����܂����E�E�E
2020/06
�L���g���Ƃ�����E�E�E�I
����A�m�l���i�t�q�ɎႢ������A��Ă��Ă���܂����E�E�E
������Ă����Ȏԗ��̃f�����s��A�^�]�̌����E�E�E�ŁA�i�j�R���E�E�E
�ڑO�����C�T�E���h�ƂƂ��ɔ��������̂����Ēʉ߂����Ԃ����āE�E�E
����͕�������ߘa�ցE�E�E�m���ɓS���}�j�A�ł��Ȃ����� ���a ��
�r�k ���C�@�֎ԂȂ�Č������Ƃ��Ȃ����i��������ł��ˁE�E�E
����d�˂��������@�����@������ꂽ�u�Ԃł����E�E�E
YouTube�@�@��߂Ƃ��w�@�b�T�W���C�@�֎� �i��
2020/05
����Ƒ��g�̐���ɖ����肪�E�E�E
����Q�U�O�O�̐����ő��̎�t�Ɏ�Ԏ���Ă��܂�
�⋭�����˂ē����v���X�`�b�N�𑋕�����������\��t���Ă��܂��E�E�E
�Ȃ̂ŁA�����Ƀ^�b�N�V�[���Ƀv�����g�A�E�g�������g��蔲��
�O������\��t����ΊȒP�ɂł���Ǝv�����̂ł����E�E�E
�O�D�T�����ȉ��ׂ̍��g���Ȃ��Ȃ���肭�蔲���܂���E�E�E
�����̃J�b�e�B���O�Z�p���ǂ������A�T�C�Y����肵�Ȃ��E�E�E
���X�Ȃ����Ȃ��v�������Ă��܂��E�E�E
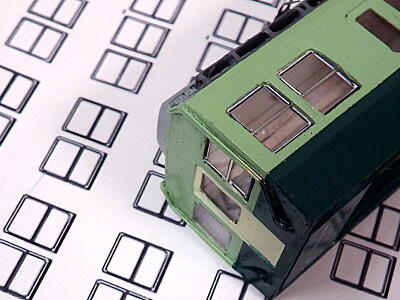
�ŁA���s����̌��ʁE�E�E��������ԂƎ��Ԃ�������܂���
���̏�i�ɂ���ɔ��������v���X�`�b�N��lj������Ԃ̂悤�ɂQ�i�����\����
�ׂ����g�Ƀz�b�`�L�X�̐j���g���A�T�C�Y���������Ƃ��Ȃ��o�����̂ł�
���ʁA���g���������I�ɂȂ����I�I�E�E�E�̂ł���
���g���H�́A�P���ɂQ�O���قǂ��E�E�E���ߑ����E�E�E
�ڂ��ڂ��Əł炸�ɁE�E�E�ł��傤���i(��)�j
2020/04
�킩��Ȃ��E�E�E
�����ō������H���킩��Ȃ��E�E�E
�`�s�r�E�E�E���x�����ǁH�������E�E�E����
����A����̏����ł`�s�r�����삵�Ȃ����Ƃ��������A��H��_��
���A���ɂȂ����z�������ăK�b�N���I�I
��{���z����ǂ������Ċm�F��Ƃ��J��Ԃ������S���킩��Ȃ��I�I
���ǁA�����[�i�p�d��j�̈ꕔ��H�ɕ⏕��H�i�o�C�p�X�j���\�������Ƃ��땜���I�I
�P�R�����Q�[�W�ʼnː��W�d�A�����ĐF�����M���A�`�s�r�����̃��C�A�E�g�I�I
�����̃��C�A�E�g
�Ȃ̂ɁA�����ō������H���킩��Ȃ��E�E�E�̂��i���j
�Ȃ�Ă��������E�E�E�I�I
�X�v�����O�������E�E�E
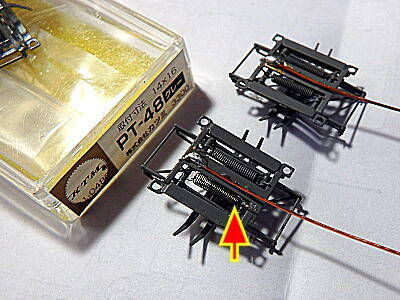
����Q�U�O�O�n�ɂ���ƃp���^�O���t����t�悤�ƁA��N�w�����Ă�����
�o�s�S�W�̊����i���S�J���ł��E�E�E
�ː��W�d�Ɏg���̂ŁA�P�Âp���^�O���t�g���ʂɔz���c�t�����ɁE�E�E
��ɂ����P���E�E�E������E�E�E
�X�v�����O���P�{�����Ă那�E�E�E��t�t�b�N�������E�E�E
���̒��ɂ������ɂ��X�v�����O�╔�i�͖����E�E�E�ŏ�������Ă��̂�
�O���猩�đS���C�����Ȃ�������������Ȃ��E�E�E
�ŁA���܂���s�Ǖi�����ƌ����Ă��E�E�E���������������Ă��邵�E�E�E
�i�t�q�̃W�����N�{�b�N�X�������ďo�Ă����X�v�����O�E�E�E
�������a���傫�����ǎ�t�t�b�N�����H���ĂȂ�Ƃ������ł�
�܂����܂����̃g���u���E�E�E�w�������璼���Ɋm�F���K�v�I
�Ȃǂƌ����Ă��A�X���ōw�����Ă����̏�ł܂������J���邱�Ƃ͂��Ȃ��̂�
���ʂ͓����E�E�E
�ׂ�����Ƃŗ]�v�ɔ��܂����E�E�E
�v��ʂ�ɂȂ��Ȃ��i�݂܂���E�E�E����Q�U�O�O�n�̐���
��p���������ɁA�����~���������ŁA���r���[�ȃf�[�^����ɂ͂��߂����ʁE�E�E
���ׂĎ���̃p�[�c���A�ł��オ���Ă����r�����炠�������Ƀg���u�����E�E�E
���쒆�̉���@��ɂ�����̃o�[�W����������Ƃ킩���Ď��ۂ̂Ƃ���т�����I
���̂��������g�̐��쐸�x�ߐM��������ԈႢ�̌����ł����E�E�E
���ł͗������Ă��Ă��A���ۂ͎肪�����Ă��Ȃ��E�E�E�܂��ɉ���̌��ʁH�I
�O�D���~���P�ʂł̌덷���p�o�A���p�Ɏ��ɃJ�b�^�[�ĂĂ�����肪
�J�b�g���I������Ƃ���߂ɁE�E�E�ŁA���łɌ덷���n�܂�A�ςݏd�ˁI�I
�ǂ�ǂ�傫�Ȏ��s�ցE�E�E��Ȃ�����ł��E�E�E�i�������j
�������x���Ȃ��č�Ƃ��x�X�Ƃ��Đi�݂܂���E�E�E
���s���Ȃ����߂ɂ��A�S�ɗ]�T�����鎞�Ɏ��|����˂Ǝv���Ă��܂����E�E�E
���������ƂɁA����Ȏ��ɉ䂪�Ђ̌o���S�����A����Q�U�O�O��
����g���ăL�b�g���w�����Ă���܂����I�I
����ň����ɔ[�߂����̎��ɂ́A�т����肷�鍂�z�ȉ��i�ł������E�E�E
�߂��Ⴍ����Ɋ��ӁA���ӂł�
�ł������܂ł́A�܂��܂��E�E�E�����������邩�Ȃ��E�E�E��
2020/03
����Q�U�O�O�n�̐����͎v���Ă����ȏ�ɐ���Ɏ�Ԏ���Ă��܂��E�E�E
�ԑ̂̓h����ɓ����v���X�`�b�N�ŕ⋭�����˂đ��K���X�����t����\��ł���
���̑O�ɉ���̃_�N�g��N�[���[�삵�悤�Ƌꓬ���ł��i(��)�j
�o�N�ɔY�܂���āE�E�E
�Q�O�O�X�N�ɓ��������v���X�`�b�N���̘A���킪�ꕔ����E�E�E
�v���X�`�b�N���i�͂P�O�N�����E�Ȃ̂����E�E�E�ƍl����ƕ|���I�I
��n���v���X�`�b�N���A���� ���o�N�ōd�����A���s�̏Ռ��Ńp�[�c���O����܂���
�K���\���������Ă����̂ŏC���ł������̂́A��͂�ێ��Ǘ��ɂ͎�Ԃ������邱�Ƃ������E�E�E
2020/01
����Q�U�O�O�n�̐���y�[�W��lj����܂���
��A���̃C�x���g��Ԃ��������ɁA����o���M�����ԐF��������S�������Ȃ��Ȃ�܂���
���̎��_�ŁA�{���̗�Ԃ͂��ׂĎ�M����p�^�]�ƂȂ�A�_�C���͂߂���߂���E�E�E
�����Ďx���̃��[�h�R���O�Ԃւ̐i���\�������\���������������܂܂�
�W���O�Ԃł̑��Ԃ܂ł��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂���
�Q�O�Q�O�N�ߑO�O���ɍ��؈�ࣂȗ�Ԃ���߂Ƃ��w�֓����i������_�C���E�E�E
����⒆�~�ɁE�E�E
�M���V�X�e���͉�H�ȂǂɃg���u��������A���ׂĐԐF�����ɂȂ�悤�ɐݒ肵�Ă���̂�
�`�s�r���܂ނ��ׂĂ̐M����H�̂ǂ����H�ɃG���[���E�E�E����͂�
�R���g���[���p�l����������A�v�����Ƃ�������ׂē_��������������킩��Ȃ��E�E�E
�e�X�^�[�����ɂ��ĂĂ݂Ă��A�v��̐j���S���U��Ȃ��E�E�E�����x��
�҂Ă�A�e�X�^�[�̐j���U��Ȃ��͓̂��ʂ������E�E�E�Ȃȉ��Ɩ������≏���Ă����I�I
�Ȃ�ŁH �Ǝv���Ȃ�����ғ�����[�q�̐ړ_���N���[�j���O�E�E�E
�����ł��I�I�d���Ȃǂ̓��암���ւ̒���������ł��炵���E�E�E�o�N������Ȃ���
���Ղȕێ炪�A�ێ�łȂ��j���֘A�Ȃ�Ȃ�āE�E�E�ڂ�����A���ł����i(��)�j�A�Z�A�Z
���N�����Ƃ킸���E�E�E
�Ђ����Ԃ�� �� �Ŏԗ��삷�邱�Ƃ��v�������܂���
����d�ԂQ�U�O�O�n
���Ԃ͉������d�˂Ă���ԗ��Ȃ̂ŁA����ԍ��ł͂Ȃ��Q�U�O�O���ǂ��H�ɂȂ�\��
�N��ƂƂ��ɐ���Z�p�̒ቺ�������Ȏ��E�E�E�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��E�E�E
����Q�U�O�O�̐����Ɍo�߂��ڂ��������Ă����܂��E�E�E
�y���݂ł�
2019/12
�ԍڃJ�����ʼn^�]���Ă���ƐV�����ݒu�����M�����A�Ȑ�����Ƃ����Ɏ��E�ɔ�э���ł��܂�
�� �����ōQ�Ăċ}�u���[�L�E�E�E
�����̗]�T������ꏊ�ɐݒu�����͂��̐M���@���A���ہH�̉^�]�ɂ͎��F����H������
�ł��A���p�M���@��ݒu����܂ł��Ȃ��A���s���鑬�x�𗎂Ƃ��Ηǂ����ƂȂ̂ł��E�E�E
�Ȃ̂� �� �����Ȃ猸�����[���Ԃɍ����܂�
�v�́A�ʓ|���`�s�r�̔z�����ȗ��������Ƃ��厸�s�ł���
�`�s�r�����삷��A�O���̐M���� �� �����ł��邱�Ƃ��킩���~�ցA����Ɍ��������邱�Ƃ�
�ł��܂��E�E�E���������ݒu���Ă���`�s�r�ɉ�H��lj�����ΊȒP�H�Ȃ͂��������ł���
�����z���ɂ� �T���قǂ��P�[�u�����K�v�Ȃ��Ƃ������āA�����蔲���H
���ǂ̂Ƃ���A�Q�������Ĕz���ƃe�X�g�I�I
�`�s�r�̒lj��ݒu�����ł��E�E�E�i���j(��)
�P�O���@�P���̑����ɁA���[���^���̍H���p�Վ���ԁi���[���H�Ձj�����s�E�E�E

�i�q�����{�ł͈�������w����̒����ԁA�`�L�V�O�O�O��
�Q���Ґ��ŁA��ڃ��[���i�Q�T���j���^�����܂��E�E�E
�����O���[�������˂点�đ��s���钷�Ґ��̃��[���H�Ղ��L���H�ł���
�͌^���E�ł̓��[�������˂�O���E���I�I�E�E�E������Ȃ̂ł�
�ł���ڃ��[���́A�͌^�T�C�Y���R�P�Q.�T�����Ȃ̂�
�Ȃ�Ƃ��ύڂ��Đ��H�ɒǏ]���đ��s�ł��܂�
�����Ă̎��t���L�V�u�����[����ؒf���H�����P�Q�{�̒�ڃ��[����
�ύڂ��đ��s����i�t�q���`�L ���[���H�Ղł�
�Q�l�܂łɁE�E�E
���[���̓����O���[�����Q�O�O���ȏ�ŁA���ڃ��[���͂Q�T���ȏ�Q�O�O�������ƂȂ�
��ڃ��[���Q�T���A����ȉ��͒Z�ڃ��[���ƂȂ�܂�
2019/10
�X���P�W���Ƀz�[���y�[�W�����������ǁH
�C���^�[�l�b�g�G�N�X�v���[���[�i�h�d�j�ŊJ���ƍs�Ԃ��l�܂��ēǂݓ�̂�
�s�Ԃ��L����R�}���h�����܂���
�����ȃL�[���[�h���摜���l�b�g��������ƁE�E�E
���̃z�[���y�[�W�̉摜���ĊO�q�b�g���܂�
�N���b�N���ĊJ���ƁA�s�n�o�y�[�W�łȂ������Ńq�b�g�����y�[�W�֒��ڃW�����v
���j���[��ʂ��Ȃ��J�E���^�[�ɂ����f���܂���E�E�E
�ŁA ���{����S���̖����Z�b�g ���A�������N���b�N�����
�s�n�o�y�[�W��\�� ����悤�ɃM�~�b�N�������܂���
�N���b�N����A�����I�ɐV���� �g�b�v��� ���J���܂��̂ŁE�E�E���e�͂�������
�X���@�U���@�w�ԐM���@�̐���V�X�e�����č\�z�u�E�E�E
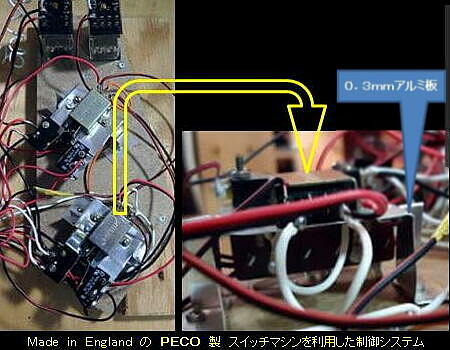
Seiga�����Haruto���M���@����G���[�������Ă���܂���
���Ƃ��Ɖw�̏o���M���ɘA���i�]���j�����\���̉w�ԐM���@���A���F�̎��ɓ��삵�Ȃ��Ȃ�
�g���u�����E�E�E�z����������l���Ă��������o�Ȃ��E�E�E
�ŁA�o���M���ɘA�����邾���łȂ��A�ʂɐ���ł���悤�ɃV�X�e�����č\�z�ł�
�M���@�̉�H�Ȃǂɂ��āE�E�E�i�t�q�̐��H�������ǎ��Ő��䂳��Ă��܂��E�E�E
�R���g���[���p�l���i����Ձj���M�����q����������Ă��܂��̂�
���m�ɂ��������ǎ��ƂȂ�܂��E�E�E
���ۂ̓S���Ŏ����ǎ����H�́A��Ԃ��ԗւō��E�̃��[���ނ��Ƃ�
���[���ɗ���Ă��� �O����H �̓d����Z���A�����[�d�����f����M�����u�ԁv�ɂ��܂�
�͌^�̒����Q�������H�ō��E�̃��[�����ԗւŒZ��������ƁA���s���̂��̂��ł��܂���
�i�t�q�ł́A�|�C���g�؊����p�̓d���i�X�C�b�`�}�V���j���g��
�O����H �͕Б����[�������ō\�����A�P���[���R���^�N�g�����ŐM���삳���Ă��܂�
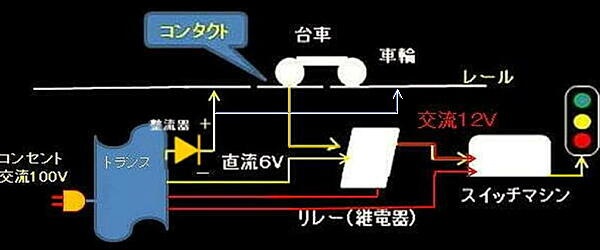
���[���̐i�s�����E�����R�������[���i���H�j�Ƃ��āA�����U�{���g�i�{�j���펞�����܂�
�i�펞�ʓd�͕Б����[�������Ȃ̂ŁA���s���̃R���g���[���ɂ͑S���x�Ⴀ��܂���j
�M���@�����̃��[�����P�O�������d��ԂƂ��A�����Ń����[�̃R���^�N�g�i�X�C�b�`�ł��j�����܂�
��Ԃ��ʉ߂���ƁA�ԗւ��疳�d��Ԃɏu�� �U�{���g�i�{�j������A�����[�i�����p�d��j������
����ƁA���d���i�͌^�I�ɂ́j�ŁA�펞�͗����Ȃ����P�Q�{���g���A���̃����[��H����
�X�C�b�`�}�V���֗���A�M����H��]�������ԐF�̌����ƂȂ�܂�
�ȍ~�̃u���b�N���Ƃɐݒu�������[���R���^�N�g�ŁA�g�ݍ��킹���X�C�b�`�}�V�������X�Ɠ]����
�M���̌��������F�A�F�Ɛؑւ��Ă����܂�
�����Ă`�s�r�̉�H�Ƃ��A�������Ă��܂�
���������Ƃɂi�t�q�Ƃ����͌^���E�ł́A�������Ȃǂ̖����ݎ���R���e�i�ԗ��͎ԗւ��≏�E�E�E
�Ԏ����v���X�`�b�N���ȂǂőS���ʓd���܂���E�E�E���Ȃ킿�M�������삵�Ȃ����ƂɂȂ�܂�
�Ґ���g�ނƁA�@�֎ԂƎԏ��ԁi�e�[�����C�g�_���ԗ��j�ɋ��܂���͂���܂��A���������Ȃ�
���ӂ��K�v�ł��E�E�E�����������M�������炽�ɐݒu���Ďԗ��̌��m���ԗւɗ���Ȃ�
�V�X�e�����\�z����悢�̂ł����E�E�E�Ⴆ�Ό��d��(���Z���T�[�j���g���H�E�E�E�Ȃ�
�������A���܂�ɂ����G�Ȑ��E�ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�����M���͂�����߁A�A����̉������@���܂�
�i�t�q�K���œ���^�p���߂Ď��̖h�~�ɂƂ߂Ă��܂�
�M������G���[�́A�V�����ݒu�������[���R���^�N�g�̔z���~�X
�Ƃ�������H���ȗ��������ʂ̃V���[�g�i��H�Z���j�ł���
�莝���̃W�����N�{�b�N�X�ɂ���ޗ����g�������ʁA��p�͗}����ꂽ���̂�
�V������H���Q�Z�b�g�lj������V�X�e���́A���H���G�ȃ}�V���E�E�E��
�M���V�X�e���́A�܂��Ƀp�Y���Q�[���̂悤�ł�
�ł��Q�l�ɂ͊��ӂł�
2019/09
�����M���@
�W���P�U���ɂ���Ɖw�ԂɐM���@��ݒu�E�E�E
�����������̏o���M���ɘA�����ĂU�u���b�N�i������ԁj�̒��Ԃ�
�F�����M���@���Q�����lj����܂���
�M����Ԃ̓u���b�N�������Ă�����̂́A�w�ԃu���b�N�̓o�b�N���[�h�ʼnː����ȗ���
�V�[�i���[�i��i�j������炸�A�M���@�̐ݒu���ȗ��i�蔲���H�j���Ă��܂���
���������ۂ̉^�s�ł́A�w�o���M���@�̌�A���w�̏o���M���@�܂ł̊ԂɐM���@������
�P�w�ԂP��ԕ����^�s�ƂȂ��Ă��܂��܂���
���S�ƌ����Έ��S�`�Ȃ̂ł���
����ł͂܂���ʕ[�i�^�u���b�g�j���������Ɠ����ł��E�E�E
�������͌^���E�I�Ȃ̂ŁA���H���͒Z�����ԁi�����j�M���@�ƌ����Ă����ʂƂ���
�w�ւ̐i���i����j�M���@�ƂȂ�܂������A����Ȃ�ɖ����ł�����̂ł��E�E�E

YouTube�ŐM����������邱�Ƃ��ł��܂�
�M���@���̂��͎̂芵�ꂽ�H��Œ����Ɋ������Đ��H�e�ɐݒu�����̂ł���
�o���M���ɘA�����ē��삳���邽�߂̔z���ɁA�߂��Ⴍ����Y�܂���܂����E�E�E
���ʁA�p�Y���̂悤�Ȕz���Ɏg�p�����d�C�R�[�h�͑������R�O���ɁE�E�E�i���j
��`���Ă��ꂽSeiga�N�Ɋ��ӂł��E�E�E
2019/08
�W���`���G�[�e���i�c�l�d�j �m���t�����K�X�Ƃ��ăG�A�[�_�X�^�[
������A�ق������Ɏg�p����Ă���K�X�ł��B
�g�p�@�͂P�O�Z���`�ȏ㗣���ĂP�`�Q�b�E�E�E
�ł��A�ː��ɂ܂Ƃ��z�R������C�ɐ���������Ɛ��Z���`�i�قڒ��߁j����
���b�H���������܂����E�E�E�m���Ƀz�R���͐�������Y��ɁE�E�E
���A���̌��ʂc�l�d���ː��̕\�ʂ��āi�K�т��H�j�S���ʓd���Ȃ���ԂցE�E�E
���������A�d�q�@��ɂ͎g�p���Ă͂����Ȃ��E�E�E�ƕ������o�����E�E�E
�ȑO�ɂ���C�̈��͍��őO�Ɠ��̃����Y���i���Ƃ����o�����������̂�
�ː��̃z�R���ƈ��Ղɍl���A�����ăe�L�g�[�Ɏg�����厸�s�ł���
�i(�L�D����
2019/07
�U���Q�X���@�Q�Q�N�������Ƃ����Ԃɉ߂�����܂����E�E�E
�����Ȃ��Ƃ�����܂������A���S���i�t�q�́A��͂薲���E�I�I
���ꂩ����V�����������߂đ��葱���܂��E�E�E
�����đ��葱���邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ�
����
�U���V���ɑ��������o�[�~���[�I�����W�̎ԗ������ށE�E�E
�ł��i�t�q�ł́A�܂��܂����݂ł��E�E�E

������}�ƕ��o�[�~���[�I�����W�̂P�O�R�n�E�E�E
���m�ɂ́E�E�E���S�F�@��F�P���@�I�����W�o�[�~���I���E�E�E�ł�����
�@

�@�@�@ ������P�O�R�n�Ɠ��C���{���̓ݍs�@�X�J�C�u���[�̂P�O�R�n�E�E�E
����Ȏ��������܂����E�E�E
2019/06
 �V���������c�c�T�P���}��~
�V���������c�c�T�P���}��~��߂Ƃ��w����o���ł���
�Ȃ�Ƃ��Ґ�����藣���Ĉ����グ���֑Ҕ�
�������A��߂Ƃ��w�R�Ԑ��Ɏc���ꂽ�Ґ���
�^�L�S�R�O�O�O�Ȃǂ̃I�C���^���J�[�P�Q���E�E�E
����̍�H�ŁA��s�����^�L�P�O�O�O�̂P�S���Ґ���
����肻���ƌ�ނ����ĘA���I
�������A����Ń^���N�Ԃ��Q�U���̕Ґ��ɁE�E�E
���̕Ґ����A�j�`�s�n���c�c�T�P����������邱�ƂɁE�E�E
��͂�c�c�T�P�́A�i�t�q�̌��z�ɏ��Ă�
��]���J��Ԃ�����ꓬ�I�I
�ԑ̂������Əd���q�ԗ�ԂȂǂ�
����������邱�Ƃ�����̂�
�v�����ē��ւɃg���N�V�����^�C����
�������邱�ƂɁE�E�E
�ԗւ̓��ʂɃh�������[�X�ōa����
�����ɃS���^�C�����͂ߍ��݂܂��E�E�E
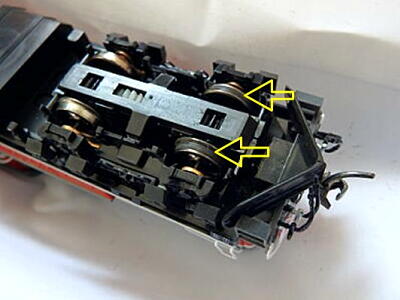

���ʂ͂������Q�U���̃^���N�ԂȂ�
�y�X�Ƃ�������Č��z���̂ڂ�܂�
��ϐg�̃p���[�A�b�v�ł��B
���Ȃ݂Ɏg�p�����g���N�V�����^�C����
�����N�����̂V�P�T�S�ł�
2019/05
�j�`�s�n����c�c�T�P���Đ��Y����܂����E�E�E
�c�e�Q�O�O�̉����߂Ă���ƁA�c�c�T�P�̏d�A�𑖂点�����Ȃ蓱���ł�
�i�t�q�̂c�c�T�P�͂P�X�V�R�N�i���a�S�W�N�j�ɓ��������������̘V���ԗ�
�j�`�s�n�̂c�c�T�P�̓v���X�`�b�N���E�E�E�芵�ꂽ�P�R�����Q�[�W����ɏd�A��
��]�C���Ȃ�����A�V���������c�c�T�P�Ƌ����H�d�A��������E�E�E����
�܂��܂��R���e�i�P�Q���Ґ����y�X�Ƃ�������Ă��܂�

�c�c�T�P�d�A�E�E�E�擪���j�`�s�n���v���X�`�b�N���f���A������S�U�N�o�߂����c�c�T�P
�⑫�E�E�E

���Ԃ́A������Ђ�����Ă��傫���T�C�Y���قȂ邱�Ƃ͍l�����܂��E�E�E
�������A�͌^���E�ł́E�E�E
���̂j�`�s�n���ƉE�̌Â��g�n�v�`���i�ł͂Ȃ�ƃf�b�L�̃T�C�Y�ɈႢ���E�E�E
�f�B�e�[���ׂ̍����Ⴂ�͎d�����Ȃ����Ȃ��E�E�E
�ł��E�E�E
�c�e�T�O�̃g���u���ł������K�b�N�����āA���낻��f�B�[�[���@�֎Ԃ�
�V�Ԃ��~�����Ǝv���Ă����Ƃ���A�S���G���̃f�B�[�[���@�֎ԓ��W��
�i�q�ݕ����V�������c�e�Q�O�O�̋L���������A�������v�������܂���
���X���삷��̂������ŁA�Q�N�قǑO�ɂs�n�l�h�w���甭������Ă����̂�
�v���o���C���^�[�l�b�g�Ō�������ƁA�т�����I
�����ł͂��łɔ����̗l�q�Ō����炸�A�v���X�e�[�W���f����
�Ȃ�ƒ艿�̂Q�{�ȏ�Ŕ̔�����Ă��܂����E�E�E
�����œ����͈�U���߂܂����I�I
�������܂Ă�A�l�b�g�ł͂Ȃ��̂���̊X�̖͌^������͂ǂ����낤����
���X�ɒ��ړd�b������ƁA��͂�����ł͔���ꂾ�������̂�
�v���X�e�[�W�ł��P�T���������i�Ŕ����Ă����V�܂������܂���
�u��[�邬����[��������v�@���O�̂Ƃ���i�q�Z�b���w�߂��̂��X�ł���
����ł���Ȃǂ�lj����Ă����[�J�[�Ŕ������i�������E�E�E���w���ł�


�����i�͎ԗւ݂̂����H���P�R�����Q�[�W�ցE�E�E��͂肱�̃��[�����ł��I
���āA�i�t�q�H��ł͎芵�ꂽ�P�R�����������̂͂����A�̐S�Ȏԗւ̉��H�O�Ƀg���u���E�E�E
���[�̂e�c�s�P�O�O��Ԃł͊ȒP�������ԗւ̎�O�����A�Ȃ�ƒ��ԑ�ԂŃX�g�b�v�E�E�E
�e�c�s�P�O�P�̑g���Ă����G�ŁA����������@���킩�炸���O���Ȃ��̂��E�E�E
�W�O�\�[�p�Y���̂悤�ȍ\���̉�͂ɂQ���ԋ߂���₵����Ɨ����E�E�E
�\�����킩��ƁA����Ȃɂ��ȒP�Ǝv����ƂŎԗւ����O���܂����E�E�E
�v���X�`�b�N���i�̂P�R�����Q�[�W���́A��Ԃ����H���Ȃ��Ŏԗւ���������Ɋ܂�
�ԗւ��̂��̂̉��H�ɕK�v�Ȏ���͑����Ă���Z���ԂŊ����E�E�E
���[���W�d�̃f�B�[�[���@�֎Ԗ{�̂́A�z������G�邱�Ƃ�����
�p�Y������������́A���Ƃ��ȒP�ȍ�ƂŎ��^�]�ւi�t�q�H��o��ł��E�E�E
�܂�������������o�N�H�E�E�E


�S�U�N�o�߂������[�^�[�����ɏđ��E�E�E
�P�X�V�R�N�ɍw�������V�ܓ����c�e�T�O�E�E�E
�P�R�����Q�[�W�ɉ��H����悭�����Ă���܂�����
���[�^�[�Ȃǂ̃g���u���ɂ悭�������A���̓s�x�C�����J��Ԃ��Ă��܂���
�����Ԃ悭�ێ��ł����Ȃ��E�E�ƁA���炽�߂Ďv���܂��E�E�E
���āA���X�Ȃ�������p�̑�^�������[�^�[����ɓ���邷�ׂ������A�v�������̂�
�莝���̃L���m���ʃ��[�^�[�b�m�Q�Q��w�����킹�Ɏ�t���Ă̗����쓮�ł����E�E�E

�����S�z�Ȃ̂͗����[�^�[�̓����ƃg���N�ł������E�E�E
�i�t�q�H��o���̎��^�]�͂������Čy���ł����i�z�b�I�j
�Ђ����Ԃ�ɉ^�]�����S�T�T�n�E�E�E
�����ɑ��s���Ă����}�s�u���R�v���N�n�S�T�T�̑���s�q�U�X������E�E�E
�P�X�V�O�N�i���a�S�T�N�j�ɐ��삵���ԗ��Ȃ̂Ō�����
�\�z�ʂ��_�C�L���X�g����Ԃ��o�N���ł����E�E�E
���Ђ̎ԗ��͐����Ƀ_�C�L���X�g���i���g�p���Ă��܂��E�E�E
���������i�̃o���c�L�ŗ������܂��܂��E�E�E
��������̂��E�E�E���������o�N�ɂ�����҂��H�E�E�E�Ȃ��
�����e�i���X���Ԃ̒Z�k��������i�̏����ȂǂȂǁA���̒ɂ����ł��E�E�E
2019/03

�k�����̋}�s�@��̂����@�Ɓ@���R�@���A��߂Ƃ��w�Ō����E�E�E
���������o�N�H�E�E�E


�Q�O���N�o�߂����e�[�����C�g�E�E�E�ԐF�����F�H�ցE�E�E
�N���A���b�h�Œ��F�����e�[�����C�g�̐Ԃ�ῂ����E�E�E
�}���^�C���Ɛ��H��C�I�[���}�C�e�B���}���`�v���^�C�^���p�[
�iMultiple Tie Tamper)

���H��C�̎���́A���a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�ɍw�������O����
�I�[�X�g���A �k�������������Ђ̃v���X�`�b�N���i�I�I
�w�����A�ԑ̂����܂�Ɍy���̂ʼn��̃E�F�C�g��ύڂ����O����
�����āA�Ȃ���S�R�N���o��
�����}���^�C���ȈՕ���ʉߎ����E�����J��Ԃ��悤�ɂȂ����B
��������Ă��܂��E���I�@
�悭�݂�ƃE�G�C�g�������Ŏԑ̒������������ĕό`�E�E�E
�قƂ�Ǎl���Ȃ��ɁA�߂������ɂ������͂��������Ƃ���A
�v���X�`�b�N�ԑ̂��o�L�b�ƕ���I�I �܂��Ɍo�N�E�E�E
��юU�����v���X�`�b�N�̔j�Ђ��W�O�\�[�p�Y���̂悤�ɏW�߂Ă�
�ڒ��g�����s���H�ڂɁE�E�E�ق�Ə�Ȃ������B
�ŁA�g���Ă��łɃM�~�b�N��lj����悤�ƁA�ԗ��ړ����ɑO���܂���
�㕔�ɂȂ�^�]���ɂk�d�c�ɂ��Ɩ������t�����B
�������I�[���v���X�`�b�N�Ȃ̂ŁA�W�d���H�Ɏ�Ԃ���������
�k�q�S�P�{�^���d�r�𗘗p�E�E�E
���邷����ԓ��ɂт����肷����[���̍Đ��ɁI(��)
2018/11
���̍��O�D�T�����E�E�E
�i�t�q�̎ԗ��́A�唼������Ȃ̂ł����A�Ƃ��Ɋ����i�̑g���ăL�b�g��
�����i�����点�Ă��܂��B��������i�Ƃ����Lj�x�͂i�t�q�H���
�P�R�����Q�[�W�ւ̉��O��ː��W�d�����։������s���������ł����E�E�E
�ŋ߂́A����̕Ґ��ɑ�������ԗ��͊����̃L�b�g�g���Ă⊮���i�������Ȃ�
�E�E�E���́A���삷�鍪�C�Ƃ������p���[���Ȃ��Ȃ���Ղȕ��@��I�����E�E�E
���ʓI�Ɉ�̕Ґ����ɂ����Ȑ������[�J�[�̎ԗ������Ԃ��ƂɁE�E�E
�ŁA����}��~�����P�W�P�n���}�d�ԁE�E�E�y�[�p�[������Ȃ̂ł���
�C���������Đ��H��ɕҐ���g��Ń{�[���ƒ��߂Ă�����A�ǂ������������H
�����I�@����̃N�[���[�`�t�P�Q�^�i�ʏ̃L�m�R�j�̍������Ⴄ�E�E�E
���̎ԗ��́A�v���X�`�b�N�̂s�n�l�h�w���p�[�c���g�p���Ă���̂ł���
�Ґ����̑��̎ԗ��́A�����v���X�`�b�N���Ȃ����J�c�~�͌^���J���C���f��
�ƃo���o���E�E�E
��ԑ����̂͂������ɉ��\�N�����p���Ă����J�c�~�͌^���N�[���[�E�E�E
���A���ꂪ��ԒႢ�E�E�E�m�M�X�����Ă�ƍ����S�D�W�����E�E�E
���Ȃ݂ɂs�n�l�h�w���͂T�D�R�����E�E�E
�ǂ����Ă��C�ɂȂ���Ԃ̐}�ʂ����炽�߂Ċm�F�ցE�E�E
���Ԃ̂`�t�P�Q�^�N�[���[�̍����\�L�͂S�Q�O�����E�E�E���̐}�ʂł�
�S�Q�S�����Ƃ����\�L���E�E�E�ǂ����C���ԂƓd�ԂłS�����̍��H
�s�n�l�h�w���T�D�R�����͂W�O�{����ƂS�Q�S�����Ək�ڂ͂҂�����I�I

�L�m�R�@�`�t�P�Q�^�N�[���[�@�X�y�[�T�[�lj��ʼn��ǁH����
���̎ԗ��ƍ����̈Ⴂ�H�͂O�D�T�����E�E�E
�C�ɂȂ�ԗ��͂Ȃ�ƂR�O���E�E�E��������N�[���[�͊e�ԂɂR��
�킪�i�t�q�ԗ��H��͌����Ă�Ă������Ȃ̂ł��B
(��)(��)�i���j(��)
2018/08
�т����肷��̏�I�I
�b�`�m�n�m���i�ʁj���[�^�[�b�m-�Q�Q���g�������}�d�Ԃ�
�{����ŋ}��~�E�E�E����ƈړ������āA�т�����I�I
���H��Ɏc���Ă����̂́A�Ȃ�����������E�I�[���M�A
�Ґ��̑g�݊����ŕK�v�ɂȂ������͎Ԃ��R�X�g�Ő��삷�邽�߂�
���[�^�[���ԓ��ɖڗ����A�ԓ��̃C���e���A�͍��Ȃ��̂�
���i�̎莝���ɂ��������C���T�C�h�M�A�ƃE�I�[���M�A��
�c�^���[�^�[�̑g�ݍ��킹�Ƃ����̂���̕�����I�������B
���[�^�[�͎莝�������������̂ŁA�����Ɏ�ɓ���c�^���[�^�[�̑�p
�Ƃ��Ďg����Ƃ��������ŁA�b�m-�Q�Q���l�b�g�ōw����������J�n�����B
�����ŏ��߂ė��������̂����A�ȑO�̃��[�^�[�͎��a���Q�D�R�����������̂�
���̐V�����b�m-�Q�Q�́A���a���Q�D�O�����ƍׂ��Ȃ��Ă����̂��B
�ŁA�d���Ȃ��E�I�[���M�A�̂Q�D�R�����z�[������x���c�Ŗ��߂�
�Q�D�O�����̃z�[�����h�������đg�ݍ���Ŋ������������͎Ԃ������B
���̔��c�߂���������]�̒�R�Ɣ��M�H��
�ɂ�ŋ�]�E�E�E�E���E�E�E���������E�E�E
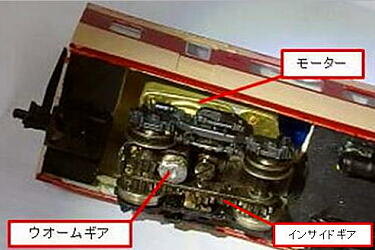
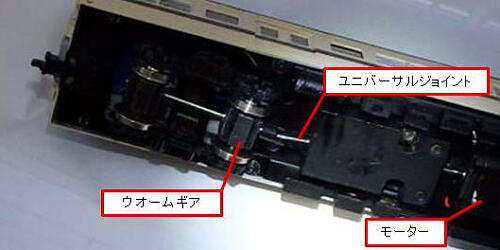
�c�^���[�^�[�͎ԓ�����E�I�[���M�A�ɒ����̂��߁A���ȂȂǂ̃C���e���A�����Ȃ��̂��B
���ݎ嗬�̉��^���[�^�[�̓��j�o�[�T���W���C���g�ŏ����ɐݒu���ԓ��ɂقƂ�Ǐo�Ȃ��E�E�E
���\�N��葱���Ď芵�ꂽ�����ł��A�v��ʗ��Ƃ��������������̂��B
���a���Q�D�R�����̃��[�^�[�Ɉ������Ă���E�I�[���M�A������������
�Ȃ�Ď��̂͂i�t�q�ł͍��܂ň�x�����������E�E�E
��͂�A�V�����^�C�v�̃��[�^�[�ɂ́A���ݎ嗬�̏�����t�ƂȂ�
���^���[�^�[�ƃ��j�o�[�T���W���C���g�������̗p���ׂ��������̂��E�E�E
�Â��^�C�v�̎ԗ����唼�̓��Ђɂ́A�����ɂ��b�ł���i���j
�O�n�V�����̘A����ɑ����āE�E�E
�܂��A����i�J�v���[�j�̃����e�i���X�I
�����P�O�N�i�P�X�X�W�j�ɂR���P�Z�b�g�����i�i�l�n�c�d�l�n���j��
�Q�Z�b�g�w�����A�P�R�����Q�[�W���Ɖː��W�d�ɉ������đ��点�Ă����ԗ���
�A���킪����E�E�E�i�q���C���R�V�R�n���}�p�ԗ��ł��B

�����i�q���C�̂R�V�R�n���}�E�E�E�E�͂i�q�����{�̂Q�Q�R�n
�s�n�l�h�w�̂s�m�J�v���[�Ɏ����\���̓d�A�t���A���킪���ɕ���I
�R���P�Ґ���g�ݍ��킹�Ď�ɂU���Ґ��Ŏ�ɑ��点�Ă������̂ŁA�悭�g���A���ʂ�
�A���킪���Ă��܂����E�E�E���Ƃ��ƌł��ގ��Ń^�C�g�ȘA���킾�����̂�
�A����̉����������ĉ�����Ƃ��s���Ă��܂������A�ǂ���疳����������H
�d�A��������ɒE���I�C�������Ȃ��瑖�点�Ă܂������A���̌�A����{�̂�����ł��B
�����ŁA�O�n�V�����ɑ����ĘA������s�n�l�h�w�̂s�m�J�v���[�������܂����B
������t�ɉ��H��K�v�Ƃ��܂������A�V�����قǂ̂��Ƃ͂Ȃ���t�ł��܂����B
����ʼn�������g�����ƂȂ��A�X���[�Y�ɘA��������ł���悤�ɂȂ�܂����B
�j�s�l�̋����������A������܂߉����ɖ��K�v�Ȏ���͏I���܂����B
���ꂩ��́A���H��ł��Ƃ������グ���K�v�ł��y�������ł���A����i�J�v���[�j
���̂s�n�l�h�w�̓d�ԗp�����A�����@�֎ԂȂǂ̂j�c�J�v���[��
�i�t�q�̂��ꂩ��̕W���ɂȂ�܂����E�E�E
2018/07
�U���P�W���ł�
�n�k �@�@
�U���P�W�����ɂi�t�q�͂߂���߂���ɁE�E�E�ł��ς���
�i�t�q���n�k�ł߂���߂���ɂȂ����̂��Q��ځI�I
�P�X�X�T�N�P���P�V���ɔ���������_�W�H��k�ЂŃ��C�A�E�g������A�ԗ���j��
���݂̃��C�A�E�g�͂��̌�ɐ��삵�����̂ł��E�E�E
�n�k�̋��P�͐������ꂽ�̂��E�E�E�������x�d�r�I�I
���C�A�E�g�́A�X�y�[�X�̊W�œ����Ɠ�����������P�D�R���̍�����
���삷�邱�ƂɂȂ�܂������A�����ɕ⋭���{������Ȃ�̑���Ƃ��Ă��܂���
�ԗ��͓����A�ǂɉ����ĕҐ����Ƃ��Y��ɕ��ׂď����Ă��܂���
���ꂪ�n�k�̉��h��ōő�P���]���I�I �������j���I�@�@�ւ��Ⴐ�Ă��܂��܂����E�E�E
�ŁA�ԗ��͕ǂɉ����Ăł͂Ȃ����p�ɍ�����i�q��̃P�[�X�ɂP�������[����������̗p
�������Ŏԗ��͑傫����яo�������̂́A�P�[�X�Ɉ����������ė����Ƒ�����Ƃ�܂���

��ԏ�̎ԗ��͓]���@�O�n�V�����͑S�ԗ��E����Ԃł��E�E�E
����Ƀ��C�A�E�g��̎ԗ��́A��ɗ������ӎ����č��ˏ�ɂ͋ɗ͗��u���Ȃ��I
�����A���u����ꍇ�́A�ː����Ȃǂœ]���h�~�ɂȂ�ꏊ�ƌ��߂Ă��܂���
����ł��A�d�����P�j��������d�C�@�֎Ԃ��S�����Ɖ��|���ɂȂ�{�����ǂ��ł����Ƃ���
�n�k�̕|���ɐg�k�����܂����E�E�E���A���C�A�E�g���痎�������ԗ��͂���܂���ł���
�����]�k�ɂ��т�����X�ł����E�E�E�Ȃ�Ƃ��Q���Ԃŕ����ł�
�i���������@�t�����@�q��������������
�撣���đ��葱���܂��I�I
2018/06/20
�O�n�V�����A�������
�^�s���̐V�����O�n�̃����e�i���X�ł�
�A�����̓��[�J�[�d�l���ʓd�����h���[�o�[�ł����A�A���E���������J�������I�I
�A���͂Ȃ�Ƃ��������߂悩�������̂́A�����ɂ͎ԗ��������グ�s���Z�b�g�Ȃǂ�
�������h���[�o�[��[�̓ˋN���������Ȃ����������������Ƃ�������ƁH���K�v�I


�ԗւ̉���̐��|��_���̓x�ɋ�J���Ă����̂ŁA�v�����ĘA����������ցI
�W���O�Ԃg�n�ԗ����i�t�q�̋}�Ȑ��ɑΉ�������̂ɍ̗p�����̂͂s�n�l�h�w��
���A�`�s�m�J�v���[�I�@�@�������L�k���傫���v���ꂽ���[�J�[�d�l�ɔ��
���̂܂��t���Ă��A���Ԋu�������Ђ낪�邱�ƂɁE�E�E����ɌŒ肳�ꂽ
�A���ʃK�[�h���ڐG���邽�߁A�ǂ����Ă��A���Ԋu��������������K�v���E�E�E
�A���E�����֗̕������l����ƁE�E�E����ς�����ցE�E�E
�K���莝�����������̂ł����ɍ�ƊJ�n�E�E�E�ŁA�������E�E�E
�ʓd�ł��E�E�E������Q��H�E�E�E�l�ԁi���͎ԁj����̋��d�H�ł�
����Ő擪�Ԃ̑O�Ɠ���������_����������ɂȂ��Ă����̂ł��E�E�E
�d���Ȃ��W�����p�[�i�n��j�����Q�{���t���邱�ƂɁE�E�E
����ł������͊i�i�Ɋy�ɁI�I�y���������邾���ŊO���d�g�݂ł�(��)

�h���[�o�[�ւ̔z�����Ԓ[�ɐU�蕪�����H�ł܂��͎��^�]�E�E�E
�ŏ��͉������������̂̏����E�E�E�W�����p�[�������s���ɔ���������E�E�E
�Ȃ�ƁA���������l���H�삵���y����������Δ�����d�g�݂ƘA���Ԋu������������
�̂ł��E�E�E���낢�뒲��������m���Ƃ͌������A�قڂقڂ�����߃��[�h�ցE�E�E
�S�@��]�I�@�l�Ԃɗ��炸�擪�Ԃ����œ_���ł���悤�ɉ�H�̓�����ł�(��)
�ː��W�d�������̎��Ɋm�F����悩�������̂́A���X�Ȃ����Ȃ��H
�X�ɒǂ��ł��́A���̐擪�ԁA�Ȃ�ƕ������ł��Ȃ��\���������E�E�E�i���j
�����Ăi�t�q�H�ꂩ�琰��ďo�ꂵ���O�n�V�����E�E�E�A���Ɖ����̓X���[�Y�ɁI
�������W�����p�[���Ȃ��E�E�E�Ƃ킢���A����ꓬ�̈�T�Ԃł����i���j
2018/06
�p���^�O���t�ɂ��āE�E�E
�ː��W�d�̓����i�t�q�ɂƂ��āA�p���^�O���t�̓���͒��N�̉ۑ�ł����B
�̂���̕H�^�Ɖ��g�����^����Ƃ��Ďg�p���Ă��܂������A
�^�]���ɑO��ɌX������A�W�d�s�ǂ��N��������g���u���������ς��ł����B
�Ȃ�Ƃ������ł����̂́A�ː��̍������ɗ͈��ɕۂ��ƂƁA�p���^�O���t��
�쓮�����ː��̍����v���X�P�����ɒ�������ƂƂ��ɁA�W�d�V���[�ɓƎ��̉��H��
�o�����T�[���J�����Ď��t�����������ł����B
�������͌^�Ƃ��Č����ڂ́A���ۂ̃p���^�O���t�ƂȂ��ς�邱�Ƃ�
�����悤�ɉ��H���Ă��܂����A���ۂ̃p���^�O���t�ɂ��悭����ƁA
�����悤�ȕ��i����t���Ă��܂����E�E�E�i�j
�p���^�O���t�̍쓮�����ł����������ŁA�E�����̂ł��p���^�O���t��
���ˏオ���āA�ː��Ɉ����|���j�����邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��Ȃ蒷���g�p�ɂ�
���Ԃ̂悤�ɁA�C����������邾���őς���悤�ɂȂ����͍̂K���ł����B
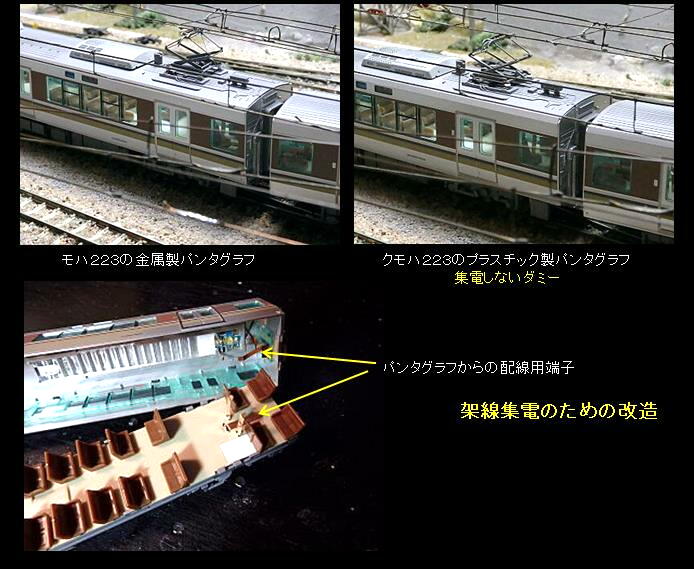
�p���^�O���t���狋�d���́A�ԑ̂̏㉺�����p�[�q�ցA���̒[�q�̓��[�^�[�ڑ�����Ă��܂��B
�i�t�q�̎ԗ��́A�ː��W�d�̂��ߓ��͎Ԃ��������p���^�O���t�����ԗ��ƂȂ�܂��B
�ȑO�͓n��������āA�V�����̂悤�Ƀp���^�O���t�̖����ԗ��ɂ����d���Ă��܂�����
���͑��s�n�̉��P�Ńp���^�O���t�̖����ԗ��ɂ͓��͂����t���Ă��܂���B
�Ȃ̂ŁA�p���^�O���t�������Ă����̖͂����ԗ��̏ꍇ�A�R�X�g�p�t�H�[�}���X����
������i�v���X�`�b�N���j�Ȃǂ���t�Ă��܂��B������_�~�[�p�[�c�ł��B
���Ƃ��A�Q�O�n�u���[�g���C���̃J�j�Q�Q�̃p���^�O���t�Ȃǂł��B

�P�X�T�T�N�Ƀt�����X�̃t�G�u���[�ЁiFaiveley)���J�������������V���O���A�[����
�p���^�O���t�i�y�p���^�j�͍쓮�����傫���A���[���b�p�e���̉ː������قȂ�
�S���ɑΉ��ł��邽�߁A���ۗ�ԂȂǂɑ����g�p����Ă��܂����B
�������A���{�ł͓����ی�̐��P�X�X�O�N����܂ŁA�قƂ�ǎg�p����܂���ł����B
�������A���݂̃p���^�O���t�́A�قƂ�ǂ������y�p���^�ɂȂ��Ă��āA���Ђł�
�R�V�R�n��Q�W�T�n���}�ԗ��Ɏ�t���Ă��܂��B
�y�p���^�́A�ق�Ƃɍ쓮�����傫���A�ː����痣�����邱�Ƃ������Ȃ�
�W�d�������A�b�v�ɂȂ�A�������Ɗ���̂́A�ԗ��̒E�����̎��Ȃǂɂ�
���̍쓮�����Ђ����āA���ˏオ�����p���^�O���t�̃V���[���ː��̃n���K�[��
�����|���A�p���^�O���t�{�̂𐁂������j���鎖�̂��������܂����E�E�E�i���j

��߂Ƃ��w�ɒ�Ԃ���A�V���O���A�[���p���^�O���t�̓��}���
�E�����̂́A�P�R���������H���̍�ƃ~�X�ŁA���s�n�����P�����������Ƃ��ł��܂����E�E�E
���Ԃł́A���̎��ɉː����p���^�O���t�̂ǂ��炩�����Ƃ�������������炵���A
���{�ł��ː����A���[���b�p�ł��p���^�O���t�����R���Z�v�g�ɂȂ��Ă���炵���E�E�E
���{�̃V���O���A�[���p���^�́A���ہA�ː���������߂��A�H�^�≺�g�����^�ɔ�ׂĂ�
�ؚ��ȑ���ƂȂ��Ă��āA�͌^�ɂȂ��Ă��A���[���b�p�̊��ȃp���^�O���t�ƈႢ
�ق�̍��ׂȐڐG�ł����i���O�ꂽ��j�����Ă��܂��܂��B
�i�t�q�̉ː����g�����[���͂O�D�T�������������A�n���K�[�͂O�D�R���������ł��B
�Ȃ̂ŁA���̎��ɂ̓p���^�O���t����ɔj�����܂��B


�R�V�R�n���}�̃p���^�O���t�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�Q�W�T�n�̊����i�i�����ŋ��������p���^�O���t�@

�@�@���[���b�p�̍��ۓ��}�h�b�d�R�̊��ȃp���^�O���t
�������W�d����W�ŁA�����i�̋������V���O���A�[���p���^�O���t���w�������H��
��t�g�p���Ă���̂ł����A�P�䐔��~�̃R�X�g��������p���^�O���t�̔j��������
�����ŁA�����ɂȂ�悤�ɍׂ������i���A���̓s�x���삵�Ă͌������Ă��܂��B�i���j
2018/05
�����ԗ����痣��āA��߂Ƃ��w�̉摜���E�E�E



�w�\���ł��E�E�E�ŋ߃G�X�J���[�^�ݒu �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �w�O�ƃo�X��t��
2018/ 3
�V�t�P�ԗ�Ԃɑ����ĕW���O�Ԃ̃��[���b�p�s�d�d�Ґ����I�I
�f���A���Q�[�W��Ԃ̂�߂Ƃ��w�P�Ԑ��ɂs�d�d�Ґ����E�E�E
�Q�Ԑ��ɂ́A�I���G���g�}�s�Ґ��������ł��E�E�E



���̊p�x����A�f���A���Q�[�W�R����������炽�߂Č����
�W���O�Ԃg�n�Q�[�W�̂P�U�D�T�������������ɍL���I�I
�R�����ЊJ�������́A�V�������g���l���ւ̐V���p��Ԃł݂���|�C���g�ł��B
�i�t�q�͓��{�^���O�̂P/�W�O�K�i�ŋO�ԂP�R�D�R�����ł��E�E�E
�ː��W�d�ƁE�E�E�F�����M�� �ɕۈ����u���`�s�r���^�p����
���ɂƂ��ẮA�ق�Ƃ��f�G�ȓS�����C�A�E�g�ł��E�E�E
2018/ 1
�����グ��������g���u���E�E�E
�i�t�q�̒��ň�ԍ����ɂ���|�C���g���̏�ł��B
�����P�D�T���̋r�����g�p���Ȃ����Ƃł��Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ł��B
�蔲���ł͂Ȃ��̂ł����A�_���ƒ����ɁA���������H����
���L���ă��X���������邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă����̂����s�ł����B
�g�[���[�ň�ԉ��x�ω��̑����ꏊ�ŁA���H���L�яk�݁H���������H
��͂�o�N�ƍ��߂��I�I
���ǁA�|�C���g�����Q�O�����̐��H���O���A���̌�����
�g���O���[����V������H�ڂɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E�i���j
�o�b�N���[�h�ō��ɐ��H�ڎ��t���������̍\���ŁA�o���X�g����
�~�݂��Ă��Ȃ������������K���H�������悤�ȁE�E�E�i���j(��)
2017/12
�����������}�f�r���[�ł��B
�Ȃ�Ɛ���J�n����P�P�N���������Ă��܂��܂����B
�P�P�N�̊ԂɃI���W�i���̎ԗ��́A�h�����j���[�J���[�ɕύX����A
�e���r�J�[�������Ȃ��Ă��܂��A���݂̓v���~�A���J�[���g�ݍ��܂�
�Ґ����̂��̂��A�傫�����j���[�A������Ă��܂��܂����B


�j���[�J���[�̂W�O�O�O�n�@������}�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I���W�i���h���̋���@��ʐF�Ɠ��}�F
���Ԃ����j���[�A�����ꂽ���ʁA�I���W�i���Ԃ̖͌^���쎑���ׂ̍����m�F��
�����W�߂ɁA������ʎ��Ԃ�������A���̂����v���ʂ�̃f�[�^�[���Ȃ��Ȃ�
�����炸�A�������삵�Ă͒��f���J��Ԃ��āA���Ԃ���Q��܂����B
���ɁA����N�[���[�̔z�u�Ȃǂ̃f�[�^�[�́A���݂̂W�O�O�O�n���Q�l��
���悤�ƁA���̕��@���v�Ē��Ɏv�������̂��Ȃ�ƁAGoogle Earth �ł��B
���㊞���ԌɁi�Q����H��j�̉q���摜���g�傷���
�W�O�O�O�n�̉���z�u����Ɏ��悤�ɁE�E�E��C�ɍ�Ƃ��i�݂܂����B
����������ɂȂ�܂����E�E�E

�i�t�q�H�ꂩ��o�ꂵ������W�O�O�O�n�́A�I���W�i���J���[�A�e���r�J�[�Ґ��ł��B

�����Ȏ����ɋ��p�̂��ߐ�s���삵���_�u���f�b�J�[�ł��B
2017/11
�ې��ԗ��p�����ƊȈՕ����
����W�O�O�O����ɂ��Ďv�Ē��A�ӂƊ���ɕ��ԕې��ԗ����C�ɂȂ�܂����B
���点�鎞�́A���̓s�x�@���ォ����H�ɂ̂��Ă����A�ې��ԗ��E�E�E�ł��B
�ې��ԗ��́A�}���^�C�@���ƃ}���`�v���E�^�C�^���p�[�@ Multiple Tie Tamper
�ې��̎�����ԗ��Ƃ������@�B�ł��B
�^���s���O�i�����̂��ł߁j
���x�����O�i���H�̍��������j
���C�j���O�i���H�Ȃ���C���j
���A��x�ɍs����^�@�B�ŁA���Ԃ͂P���ԂɂR�O�O������T�O�O���̕ې���Ƃ��ł��܂��B
����W�O�O�O�̐�������ɂ��āA���u�����炷���Ɏg�p�ł���悤�ɁA
�����i�|�C���g�j����C�ɍ��C�ɂȂ�܂����B
�����ƌ����A�߂����i�q�̉w�\���Ɂ@�s�v�c�ȕ�����@������̂��v���o���܂����B
�s�v�c�ȕ����́A�ȈՕ����i���摕�u�j�ŁA�ێ炪�ȒP�Ȃ̂�
��ɕې��ԗ����g�p����n����ȂǂɁA�ʏ�̕����̑���Ɏg�p����Ă��܂��B
�@�@

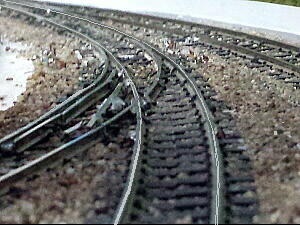
�@�@�@�@�@�@���ۂ̊ȈՕ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͌^�ōČ������ȈՕ���ł��E�E�E
���H�����z���鑤�����̃��[�����傫�������グ���Ă��܂��B
���̕����́A�������L�̐��H��U�蕪����|�C���g���i�g���O���[���j��
�ԗւ����[��������N���b�V���O���i�t�����W�E�F�C�j������܂���B
�ғ����镔���Ɛ茇�������������̂ŁA�{����Ԃ͌������̐����Ȃ����ʂɒʉ߂ł��܂��B
�ې��ԗ����ꎞ�I�Ɏg�p������̂ŁA���͂ɐ݂������H�����z�������郌�[����
�|�C���g���ƃN���b�V���O���ɂ��Ԃ��A���[���𗧑̓I�ɏ��z�������܂��B
�͌^�̎ԗւ́A���s���\���m�ۂ��邽�߂ɃX�P�[���ԗ��Ƃ����Ă��A
�͂邩�ɃI�[�o�[�X�P�[���I�Ƀf�t�H��������Ă��܂��B
��������z�����[���Ȃǂ̃p�[�c�͑����X�P�[������͂���Ă��܂��܂������A
�H���ԗ����傫�����H�����z���đ������o���肷��l�q�́A�߂��Ⴍ����y�����ł���B
�������d�C�I�ɂ��ؑւł���悤�ɂ��Ă���̂ōH���ԗ��́A
�ȈՕ��������z�����[������A�������������ł��܂��E�E�E


�������������֓��������u�����}���^�C�ƕې��ԗ�
2017/03
����W�O�O�O�n�̂��ƁE�E�E
�g���������̍ʼn��i�ɁA
�ŏ��ʉߋȐ����a�͂U�T�O�q�ł����A�o���邾���傫�߂̋Ȑ��ł̉^�]�����E�߂��܂��B
�Ƃ̕������L�ڂ���Ă��܂����B
�i�t�q�ł́A�U�O�O�q�̋Ȑ����W���ɂȂ��Ă��܂��B
�ԗ����悭�m�F����Ƒ�Ԃ��A���J�[�Ƃ̌��Ԃ��قƂ�ǖ����A�Ȑ��ŐڐG
���Ă��܂��B�M���M���ڐG�����ɒʉ߂ł���Ȑ����A�U�T�O�q�������̂ł��B
��Ԃ͓d�C�I�ɂ��ꂼ��≏����Ă��܂����A�A���J�[�͎ԑ̂ɒ��ڎ�t
���Ă���̂ŁA�Ȑ��ŐڐG����Ƃ��ꂼ��̑�Ԃ��V���[�g���ĉ^�]�ł��܂���B
�������ɉ^�s�ł����̂́A�h���̂������Ő≏���ۂ���Ă�������ł����B
���̌�̑��s�ڐG�ŁA�h�����͂���Ă������Ƃ������E�E�E
��s���������_�u���f�b�J�[�ɁA�i�t�q�ʼn^�]�ł���悤�ɑ�Ԃ̒�����
�≏����Ȃ�Ƃ��s���āA���̊m�F�̂��߂ɓ��ʎ�����Ԃ��d���Ă܂����B
�ߓS�A�[�o���Ƃ̕����Ґ��ł��B
�͌^���E�Ȃ�ł͂ł����A�≏��ƋȐ��ʉߑ�ɓ���Y�܂��Ă��܂��B�i�j
2017/02
�L�b�g����g���ēh���̏I���������W�O�O�O�n����ɂ����āA��t���i���Ċm�F�I�I
������E�E�E���i�������E�E�E
�e���r�J�[�̂a�r�A���e�i������܂���E�E�E�g�z�z�E�E�E
�ŏ��Ɏv�������̂������A�@�}�ʂ�����̂Ńh�������[�X�łł���I�I�Ǝv���Ȃ�������ߑ��I�I
�P�U�N�O���Q�O�O�P�N�ɔ������ꂽ�ԑ̃L�b�g�ł��B �����̍L���߂āA�܂����ߑ��I�I
�����Ɍf�ڂ���Ă����J�c�~�ڍ��X�E�E�E�@�������@ �ɂ�����@�Ɓ@�d�b���Ƃ�܂����B
�d�b�͒��J�ȉ��ł����B
�u�Â����i�Ȃ̂ŁA�{�Ђ̑q�ɂ��m�F���܂��B���炭�҂��ė~�����B�v�ƁA
�����āA�P�T�Ԍ�ɓ͂����̂ł��B
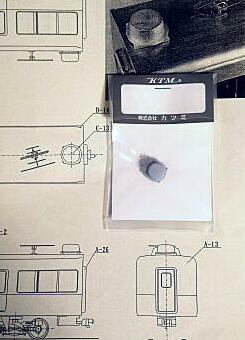
���ɂ͂܂�Ŋ�Ղ̂悤�I�I����
�i�t�q���悭�����i�╔�i���w�����Ă���S���͌^�̘V�܂́A���ł��B
������ςȂ��ł͂Ȃ��A �Â������ȕ��i�܂ŊǗ����ăT�|�[�g�ł���Ƃ́E�E�E
�����ɗ���鉽�����������������܂��B
�N���ɁA�F�c�ԗ�����A�˗����Ă�������W�O�O�O�n���}�W���Ґ���
�h�������̘A��������A�i�t�q�H������͉��I�@�������ɂł��B
�������ː��W�d�Ȃ̂Ńp���^�O���t�̃e�X�g�����˂Ă̑��s�ł����B
�������̖����Ȓ����ɁA���J�ɓ����Ă�����F�c�ԗ��ɂ́A �S���������ł��B
���ꂩ�琔�����������Ă�������ƁA�����Ȃǂ̊e��H���� �҂��Ă��܂����E�E�E
������}�I�I�E�E�E�������^�]���s�����������̂ł��B

�i�t�q�ł͏��߂Ẵ_�u���f�b�J�[�i�Q�K���āj�ԗ��ł��B
�h���́A�����Ă̋�����}�J���[�E�E�E����ς�A���̐F���D���ł��B
2017/01
�O�n�V�����p���^�O���t
�[��Ƀe���r�Ō����u����V�����v�E�E�E
�O�n�Ђ�������ŐV�̖k���V�����܂ŁA��B�Ȃǂ̉f��������Ă��鎞�ɁA
�Ȃ����A�����O�n�V�����𑖂点�����Փ��ɂ����Ă��܂��܂����B
�����̂悤�Ƀy�[�p�[�Ő���Ǝv�������̂́A���̐擪�`��������@�Ɏv�āI
����Ɏԑ̂̐}�ʁA��Ԃ�[�^�[�A�p���^�O���t�Ȃǂׂ�ƁA
���܂�ɂ��o���G�[�V�����������ς��I
��������̂͂��A�S�S�N�ԑ��葱�����O�n�V�����́A�J�Ƃ����P�X�U�S�N�̂P���Ԃ���
�Ȃ�ƂP�X�W�U�N�̂R�W���Ԃ܂ŁA�Q�Q�N�ԉ��ǂ��d�˂Đ�������Ă�������Ȃ̂ł��B
�E�E�E ����́A��������ł��B
�����i�́A�J�c�~�͌^�̋����ԗ��ł����E�E�E�R�X�g��
�i�t�q�ʼn^�]�ł���U���Ґ��ŁA�R�O���~���Ă��܂��܂��I
�ӂƁA�T�N�ʑO�����`�����������Ă����v���X�`�b�N���i���v���o���A
�l�b�g��������ƁA�����U���Ґ����E�E�E��V���~�E�E�E
�������ː��W�d�ɕK�v�ȃp���^�O���t���������Ƃ킩��v�����čw���ցI
�T�O�O�n�V�����̃v���X�`�b�N���̃p���^�O���t�ɒ���Ă����̂ŁA
�܂��͐��H�ցE�E�E�Ƃ��낪�ː��ɓ͂��܂���E�E�E


** �ː��ɓ͂��Ȃ��w�����̃p���^�O���t ** �@�@�@�@�@�@ �W�d�����H��̃p���^�O���t *******
����ɁA�i�t�q�ł́A���łɉ^�p���Ă���T�O�O�n�V�����ɍ��킹�� �ː�������
���܂����A��������s�^�p���^�O���t�́A�ԑ̒������Ɏ�t���Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�O�n�V�����̃p���^�O���t�́A ���܂�ɂ��Ԓ[���Ɏ�t���Ă��邽�߁A
�Ȑ��ɂ�������W�d�V���[���ː��̊O�Ɋ��S�ɔ�яo���� ���܂��܂��B
�ʏ�A�����d�Ԃ̃p���^�O���t�́A��Ԓ����̐^�㉮���Ɏ�t���Ă��܂��B
�𗬂���d�Ԃ�@�֎Ԃł͑�Ԓ�������Ԓ[��ԑ̒��������փI�t�Z�b�g
����Ă��܂����A�T�O�O�n��O�n�قNjɒ[�ł͂���܂���E�E�E
����ŁA�ː������H�����^��ɃZ�b�g����Α��v�ŁA���ɋȐ��ł͐��H�O�ԓ�������
�Ȑ������@�ɍ��킹�Ē���E�E�E���Ȃ킿���H�O�Ԃ̕��̐^��ɉː���
�u���v �̎��̂悤�ɒ���A�W�d�V���[�͏\���Ǐ]���Ă���܂��B


�ԑ̒����Ɋ��̂T�O�O�n�p���^�O���t **** �@�@�@�@�@�@ �O�n�̎Ԓ[�p���^�O���t *********
�@�ԗ�������Ƃɕ��s���āA�ː������Ԃ��J��Ԃ����s�����T�O�O�n�ƂO�n�V�����o����
�p���^�O���t�̏W�d���e�͈͂ɁA�Ȑ��̉ː����~���P���ňړ��������s���H�ڂɁE�E�E
�i�t�q�̋}�Ȑ��͑�^�ԗ��𑖍s������ɂ́A����ς薳���H������i���j
�������A�i�t�q�ł͂����Ƒ�^�̃��[���b�p�ԗ����A�Ȑ��ʂɑ��s��
�ː��W�d�ɂ��A�h���C�o�[�P�{�Ńp���^�O���t����̋��d�ɐؑւł���Ȃ�
�O�n�V���������s����̂Ɍ����Ė����͂Ȃ��͂��E�E�E��
�����v���X�`�b�N���i�ł��O�n�V�����́A�������ȒP�ȃ��[���b�p�ԗ��ƈႢ
�^�C�g�ȍ\���Ŏ肱����܂������A�Ȃ�Ƃ����͎Ԃ����Ĕz���`�F�b�N�I
���͎ԓ��́A�c�b�b�i�f�W�^���@�R�}���h�@�R���g���[���j�̓��ڏ����ς݁I
�z���͂��������ՂցE�E�E���ꂪ����������ƒቿ�i�ɂł����̂ł́H��
���S�K�b�N���i���j
�i�t�q�ɂ͕K�v�̖����V�X�e���Ȃ̂ŁA�c�b�b��Ղ��烂�[�^���C����
�p���^�O���t�֔z���ύX�E�E�E�ŁA�т�����I�I
�p���^�O���t�͂Ȃ�Ǝ�t�����͂��ׂăv���X�`�b�N���I�I
�o���o���ɕ��������p���^�O���t�̋��������ɁA�z�����Ȃ�Ƃ����c�t��
���ꂪ�A���肵�����s��܂ł̋ꓬ�̎n�܂�ł����E�E�E
���܂����i�j�i���j�i���j�i���j�i�j
2016/12
���z�p��^�̒����d�C�@�֎Ԃd�e�U�S�P�O�P�U�̑S�ʌ����ɂƂ��Ȃ���
���P�G���h�̘A������A�q�Ԃ�ݕ���ԁE�C���ԂɎg���Ă���
�����A����Ɠd�ԗp�̖����A����̑o���ɑΉ����邱�Ƃ��ł���
������o���^�A�����Ɍ������܂����B
����Ŏԗ����ɁA�d�Ԃ�q�ԂȂǂ��ׂĂ�A�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�ȒP�ɘA���킾����������Ηǂ��ƍl���Ă��������A�T�n�J�ł����i�j
�A����̓����������ւV�U�x��]�����邱�Ƃɂ��ؑւ�̂ł����A
�����A����͘A���퓷���{����㉺���E�ɓ������邱�Ƃ��K�v�ł��B
�Ƃ��낪�����A����́A�㉺�̍������Ԃ�Ă͑ʖڂƂ�����������
�����������āA�A����̎�ނɍ��킹�ď㉺�̓����̌Œ������
�o����悤���S���u���A������͂ނ悤�Ɏ�t���Ă��܂��B
�Ȃ�ƒʏ�̉�����q�̑���ɁA���̃V�����_�[�t���̕��S���u��
����܂ł��K�v�������̂ł��E�E�E�g�z�z�i���j


������q��P�����āA�A����̏�����i���h�j���g���č쐬�������S���u�ł��i�j
2016/11
�ː����쒆�̎v��ʗ��Ƃ����H
�W���ɓ����Ă��ɁH�@���������`����Ɩҏ���ł��B
�ː��̎�t���@��ύX���Ē������y�ɂȂ�܂����B
�ː��̐��ꉺ�����ό`�Ȃǂ̃g���u�������̂��߂ɁA����I��
�ː������Ԃ𑖍s�����Čv�����s���A�ʏ�̉^�]�Ɏx��̖����悤��
���܂߂ɕێ���s���ė��܂������A�ː��g���u���̎�Ȍ�����
���̉Ă̑����ҏ��ɂ���M�c���E�E�E
�p�ɂɔ��c�t�����J��Ԃ������H�����������A�L�k�ɑΉ����ł���悤
���u���P�b�g��g���X�r�[���ƃg�����[����t�n���K�[������
���c�t�����ɗ͖������ׂ����ǂ��s���܂����B
���̌��ʁA�قڕێ疳���ŁA�ː��̍��������ɕۂĂ�悤�ɂȂ����̂͐i���ł��I�I
�ԗ������łȂ��A�ː���{�݂ɂ��ẮA�����Ƃ����Ǝ��ۂ�
���H��w���������āA�m��˂Ȃ�Ȃ��I
�ƁA���炽�߂ĒɊ��E�E�E�����Ė͌^�Ƃ͂���
�����Ƃ�����{�̒��ɕK�������������Ǝ����ł��E�E�E
�ː������Ԃ́A�L���P�X�P�n�d�C�v�������C���Ԃ�
���s���Ȃ���ː��̏�M���̎������ł��܂��B�@


���Ԃ́A���S����̂P�X�V�S�N����Q�O�O�W�N�܂łi�q�����{�ȂǂŊ��Ă��܂����B
���Ȃ݂ɉE�摜�̉ː��́A�x�[�N�ō�����≏�Z�N�V�����i�����郌�[���̃M���b�v�j�ł��B
�i�t�q�̃L���P�X�P�n�����Ԃ��A����_�����ݒu�̏��^�r�f�I�J�����ő��s���Ȃ���
�ː���Ԃ̓_����[���R���^�N�g���e�X�g���A�M����`�s�r�̓���m�F���ł��܂��B�@
�͌^�Ƃ͂����A���Ԃɋ߂��D����̂̎ԗ��ŁA�܂��ɂi�t�q���h�N�^�[�C�G���[�ł��B


�g���X�r�[�����̉ː��𑖍s�_�����@�@�@ ���ǂ������u���P�b�g�Ɖː��n���K�[�E�E�E
�@�@�@ �i�t�q�̉ː��͉w�\���̓g���X�r�[���ŁA���̑��͉��u���P�b�g��
�͌^���A�����ɁA���傤�ː��c�t���Ŏ�t�Œ�A����Ƀn���K�[��
���ڃp���^�O���t���ڐG����g�����[�������t���Ă��܂����B
��C�͔��c�����̓s�x�O���Ă�蒼�����@�ł������A���c�ł̌Œ����߂�
�������������A�M�c���ɂ�鐂�ꉺ�����Ƃ��܂����B

�悭�悭�����̉ː����݂�ƁA����ς�Œ�͂���Ă��܂���ł����B�i�j
�܂��Ɍ����ڂ����Ƃ����H�E�E�E�����������Ă��܂��܂���
2016/08
�S�����玞�Ԃɗ]�T�H���ł����̂ŁA�Q�O�n�u���[�g���C���ɑ���
�Q�S�n�Q�T�^�̃u���[�g���C�����W���֑������邱�Ƃɂ��܂����B

��߂Ƃ��w��ʉ߂�����Q����}�x�m�E�E�E
�@�֎ԂƋq�ԂW���͒����E�E�E
�Q�O�n���Q�S�n���d���Ԃ��K�v�Ŏ����̐Q��q�Ԃ́A�U���ł����B
�P�S�n�u���[�g���C���͂V���ʼn^�s���Ă����̂ŁA�Q��q�Ԃ̗�����
���킹�邽�߂ɂQ�O�n�Q�Ґ��ɑ����ԗ��삵�Ă����̂ł����A
�Q�S�n�������U���Ŏc�����܂܂ł����E�E�E
�X�g�b�N�̎ԑ̂�����p�[�c�����p���āA�Ȃ�Ƃ��u���[�g���C���q��
�Q�S�n�Q�T�^�P�������đ����A�Ґ����������킹�邱�Ƃ��ł��܂����B
���ŋq�Ԃ����
�X�g�b�N�Ƀp�[�c�̐������A�ӂƁA�W�����N�{�b�N�X�ɁA �s�q�T�O�^
�y�ʋq�ԗp��Ԃ��P�����c���Ă���̂ɋC�Â��܂����B�����ł��̍ہA
���S����̋}�s��Ԃ̕Ґ����������A�a�Q��q�Ԃ�����Ă݂�C�ɂȂ�܂����B
���������a�S�O�N��̐Q��q�Ԃ̐}�ʂ́A�q�ԁE�ݎԃK�C�h�u�b�N�̂P�T�O���̂P�E�E�E
�X�g�b�N���������炽�߂ĒT���Ă݂���i�n�l�P�P�̂W�O���̂P�}�ʂ��E�E�E
���삷��̂́A���̎ԗ��ɗ�[���u�����t�����I�n�l�P�Q�ł��E�E�E
�ԗ��̐���́A�芵�ꂽ�y�[�p�[�I�I
�����͏㎿�̃P���g���i�O�D�T�������j�ɂW�O���̂P�ɏk�ڂ����W�J�}�ʂ�
���ڂɎ菑���ŕ`���Ƃ���Ȃ̂ł����A����́A���������}�ʂ��������̂�
�ڎʂ��ăf�[�^���A�y�C���g�\�t�g�𗘗p���X�P�[�����H�A�`�S�̃^�b�N�V�[��
�i�O�D�P�Q�S�������j�փv�����g�A�E�g��ɁA�P���g���֓\��t���܂����B
���ʁA���̌��݂������Ďԑ̂������H�ł����E�E�E
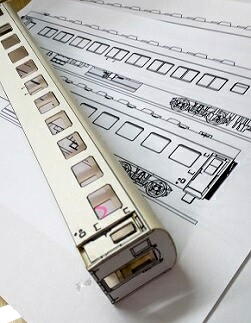
�܂��͉��g���Ē��̃I�n�l�P�Q�E�E�E
�����͋�J����W�J�}���A�v�킸�������ݏグ��قNJȒP�Ɉ���E�E�E
����A�h�A������蔲�������̋Ȑ���}�ʂɍ��킹�đg�ݏグ�܂��B
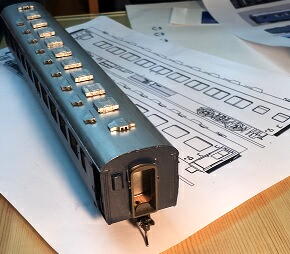
�h���܂ŏI������I�n�l�P�Q�E�E�E

�������̋}�s�Ґ��ɑg���ݑ��s���̊��������I�n�l�P�Q�E�E�E
���S�ɐ}�ʂ��蔲���H�����y�[�p�[���ԗ��E�E�E
����̎ԗ��X�V����ɂ́A���Ђ̑g���ĕW����@�ƂȂ肻���ł��B
2016/05
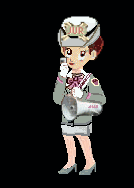
Japan Ueo Railroad
 �l��
�l�����Ђ̊T�v�� �s�n�o�y�[�W�֖߂� �H���̋L�^��