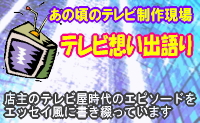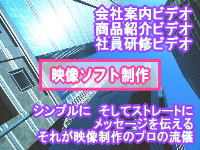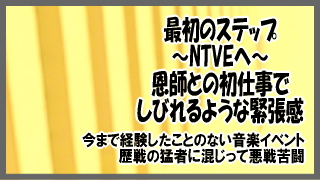|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 日本テレビの社外スタッフ管理の方針変更により『11PM』の担当をはずされる危機が私に迫った。 そんなとき、生涯の師と尊敬するようになる秋元近史氏と再会し、日本テレビエンタープライズという会社に入ることになった。 その面接はあっけないほど簡単なものだった。 秋元氏は私が『サントリーオープン・プロアマ』のディレクターをしていたことさえ忘れていたようだった。 最初の時は相当褒めてくれたのに…、とちょっとガッカリしたことを覚えている。 ところが、秋元氏が亡くなった後に奥様から聞いたことだが、この日師は帰宅するなり、とても上機嫌で「今日、俺にそっくりなやつが来たんだよ」といっていたそうだ。 「あの時は本当に嬉しそうだった」と奥様にいわれて、涙が出るほど嬉しかった。 日本テレビエンタープライズというのは『スター誕生』という番組がスタートするのにあわせて、日本テレビ音楽学院を運営する会社として設立された。 その現場責任者、常務取締役として秋元氏が日本テレビから出向していた。 そして次第に、秋元氏の演出力によってイベントを中心にその活動の範囲を広げつつあった。 五月。私が秋元氏の下で仕事をするようになって最初に取り組んだのは『広島平和音楽祭』という広島テレビが開催しているコンサートだった。 これはジャンルを超えて集まった歌手たちが歌を通して世界平和を謳歌するというもの。 その第一回目に美空ひばりさんが『一本の鉛筆』という曲をこの音楽祭のために作って発表したことで有名だ。 音楽イベントの現場など一度も経験したことのない私には緊張の連続だった。 頻繁に繰り返される広島テレビ関係者や構成作家も含め、美術、音響、照明スタッフとの打ち合わせ。 その会議の度に秋元氏の決まり言葉、「違うんだ!」「それじゃダメなんだよ!」が独特のポーズとイントネーションで繰り返し響き渡った。 そうした後に出される秋元氏の演出プランに列席者全員が困惑していた。 『11PM』のようなレギュラー番組では経験したことのない緊張感が会議の席上に流れていた。 いくつかのスペシャル企画や番組には参加していたものの、これほどギリギリまで内容を詰めていく会議というものを始めて経験した。 |
|||||||||||||
| MENUへ▲ | |||||||||||||
| 恩師と仰ぐようになる秋元近史氏の元で仕事をするようになって取り組んだ『広島平和音楽祭』は始めての経験の繰り返しだった。 中でも秋元氏の自身がイメージした演出を理解させようとする姿勢には驚嘆した。 「違うんだ!」「それじゃダメなんだよ!」という師の決め台詞と、それをいう時にする右掌を上に向けて上下に振るポーズは今でも語り草だ。 それ程この言葉を連発した。 ただそれは、自身の演出イメージを主張することのためだけではなくて、スタッフたちが陥りやすい「妥協」をギリギリまで高めるための表現だったのだ。 スタッフは誰もが予算の問題やら、他の仕事との兼ね合いなどの制約によって、言葉は悪いが安易な道に入ろうとしてしまいがちなものだ。 師はそれを諌めていたのだ。だが、それを私がそのことを理解するにはこの後まだ長い日数が必要だった。 私たちは平和音楽祭の開催に向けて三日前に広島に入った。 その移動の中で秋元氏がちょっと落ち着いた声で話してくれたことがある。 「俺は現場に行くといろんなことをいうよ。 それに必ず返事をしてくれ。 ほとんどの奴は返事をしないんだ。 演出しているとそれが一番頼りないものなんだ。」 演出家の心の中を覗いた気がした。 今思えばこれが師から最初に教えられたことだ。 『広島平和音楽祭』の会場となる県立体育館に着くなり、秋元氏は舞台監督の富坂氏、美術の田原さんや照明の磯部さんなど日本テレビから派遣されたスタッフ、それに音響の東京音研岡本会長からそれまでの準備段階での報告を受けた。 そして秋元氏は現場を見るなり矢継ぎ早に「違うんだ!」「これじゃダメなんだよ!」を連発。 修正を指示した。 師の傍に各チーフがいてくれた時はよかったが、彼らも指示を受けて持ち場に戻る。 それでも秋元氏からの指示は止まらない。 飛行機の中でいわれたことを肝に銘じていた私は、それらに対して、たとえ何かの準備をしていても、ことごとく「分かりました!!」を連発した。 最初のうちは「よし、小俣頼むよ!」といっていた秋元氏が、いくつめかの指示を出し、それに私が「分かりました!」と応えた時に、いった。 「小俣!そんなに全部一人でできるわけないだろ!!」 |
|||||||||||||
| MENUへ▲ | |||||||||||||
| わが恩師、秋元近史氏の演出の際にはいつも決まった制作メンバーが集まっていた。 構成は師の親友であるはかま満緒氏の弟子だった岩立良作氏。 彼は最近明石家さんまさんとテレビで競演して話題になった。 舞台監督の富坂氏とその弟分の三浦氏は、構成作家で演出家でもあった塚田茂さんの腹心だった人たち。 三浦氏は私より一歳年下だが、イベントや舞台進行のエキスパートだ。 それに、秋元氏と私のつなぎ役をしてくれたテレハウスの鈴木社長とその社員たちも加わることが多かった。 私の秋元氏の下での初仕事『広島平和音楽祭』では、それに加えて日本テレビから、大物セットを作らせたら右に出る者がいない美術デザイナーの田原さん。 照明は柔らかな人柄できれいな明かりを作る磯部さんが日本テレビから派遣された。 そしてその照明をオペレートするのは共立照明の宮下さん。 そして音響は東京音研の岡本会長の陣頭指揮の下、菊池さんなどのミキサーが音を作っていた。 ロックからクラシックまで出演するこのコンサートでは経験豊かなミキサーでなければ対応できなかった。 私はといえば、初めての音楽イベントだというのに三浦氏と同等の重い役割を与えられていた。 はっきりいって荷が重かった。 今でさえ気圧されてしまうような顔ぶれに向かって、秋元氏は情熱的にそして確固たる姿勢でダメを出していった。 では、その表現の仕方が的確で分かりやすかったか、といえばそうとはいえなかった。 どちらかといえば長嶋茂雄さんタイプといえるかもしれない。 だからこそ秋元氏の発する言葉を理解できるスタッフでなければ成立しなかったわけだ。 私も秋チン(秋元氏は仲間たちからそう呼ばれていた)語を一日も早く理解したいと思った。 だがそれには本当に演出するということの意味を理解しなければできないことだった。 『広島平和音楽祭』の本番を前にしたホテルの部屋で、秋元氏と始めて出合った『サントリーオープン・プロアマ』で氏がいったことを思い出していた。 「誰がどんなことをするかが大切なんだ。」 この言葉を最初に聞いた時から二年。 まだこの言葉の本意は理解できていなかったが、これが私の演出する時のキーワードとなってゆく。 |
|||||||||||||
| MENUへ▲ | |||||||||||||
| 『シャボン玉ホリデー』の生みの親である秋元近史氏の元で仕事をする幸運に恵まれたものの、始めての仕事、『広島平和音楽祭』での私の仕事ぶりは惨憺たるものだった。 今覚えているだけでもどれほどの失敗があったことか。 できれば振り返りたくない過去の実績だ。 今でも深く心に焼きついている私の失敗がある。 その年の音楽祭には西城秀樹さんが出演することになっていた。 秋元氏は当時人気絶頂であった彼に特別にある曲(残念ながら忘れてしまったが古い歌だったと思う)を歌ってもらおうというプランを立てた。 音楽祭では一人の出演者は3曲歌うことになっていた。 代表曲やヒット曲、新曲というのが一般的な構成だった。そのうちの一曲をこちらが企画した曲にしてもらおうというのだだった。 私たちは、そのために譜面と音源を用意し、音楽祭のバンド編成にあわせて編曲にも回した。 加えて師は、昔の『シャボン玉…』時代のアシスタントであり、その頃は『紅白歌のベストテン』のプロデューサーだった庄司文雄さんを介して西城さん側にその旨を伝え、OKをもらった。 あの秋元近史が演出していたら、そのプランにNOをいえる人などほとんどなかったはずだが、師はそこまで周到に準備をした。 庄司さんからOKの連絡を受けて、私は音源と譜面を西城さんの事務所に届けるようにいわれた。 だが、何か別の用事をしていてすぐには動かなかった。 指示を受けて一時間程したころだったと思う。 師が私のデスクにやって来て、「小俣、音源と譜面はまだ届けに行かないのか。これは演出的にすごく大切なことなんだよ。」といった。 いつもの会議の時に見せる情熱的な表現とは正反対の冷静な言い方だった。 私はその予想もしなかった師の表情にどう反応してよいか分からなかった。 とにかく慌てて事務所を飛び出し、資料を西城さんのマネージャーに届けに走った。 師の演出の狙いは、若者の代表である西城秀樹さんにその歌を歌わせることで平和を享受していることの意味を表したかったのだ。 そして、そのためには彼に完璧に歌って欲しかったのだ。 実際リハーサルでも何度もやり直しを要求していた。 演出の機微を教えられた。 |
|||||||||||||
| MENUへ▲ | |||||||||||||
| コンサートや音楽祭などのイベントの際に必ずといってよいほど行われることがある。 通しリハーサルが終わり、後は小直しをして本番という時に、スタッフ全員、アシスタントまで含む最終のミーティングを行う。 時には出演者やそのマネージャーまで加わることもある。 全員が集まって、さあこれから最終打ち合わせというところで、演出家またはプロデューサーが全員をいきなり怒鳴りつける。 「テメーバカヤロー!!」から始まって、唇は震え、蒼白になって、台本を机にたたきつけて怒鳴るのだ。 それこそ鬼気迫る勢いで激高する。 これは必ずしもリハーサルの出来が悪いから怒っているというわけではない。 一つのセレモニーだ。 その怒りの形相も演技である。 スタッフというのは事前のセッティングから始まって、本番前というのは疲労の極致だ。 集中力も散漫になっている。 だがこのセレモニーがあると、スタッフ全員の気持ちが一点に集中するから不思議だ。 その後の進行責任者からの確認事項で、スタッフたちからそれまでとは明らかに違う「はいっ!」という返事が返るようになる。 ところが、私が師と尊敬する秋元近史氏はこのセレモニーを行わなかった。 少なくとも私はその現場を経験したことがない。 なぜしなかったかは残念ながら聞く機会がなかった。 なので今はその真意を知ることはできない。 師は、打ち合わせ段階から、以前にも紹介したとおり「ダメなんだ!」と「違うんだよ!」を連発した。 それはリハーサルの段階でも何度も発せられた。 今思えば、ここまで自分の意図を伝えぬいたスタッフを信頼する心が強かったということなのかもしれない。 師はプロたちの集団ということを常に考え、その人たちの作業を信頼していると語っていたことがある。 いや待てよ。 それよりも本来テレ屋だったから、そんな演技は恥ずかしくてできなかったのか…。 普段の生活で笑いを取るためならどんなバカなことやった師の本質にあるテレ屋の気質がそれを許さなかったのかもしれない。 それでも高い評価を得られる作品を作り続けたのだから流石としかいいようがない。 そうした師の影響なのだろうか、とうとう最後まで私もこのセレモニーは行うことができなかった。 |
|||||||||||||
| MENUへ▲ | |||||||||||||
| 有限会社 SECOND EFFORT 〒092-0824 東京都八王子市長房町450-53 TEL:042-661-8788 Mail:info@2eft.com |
|
||||||||||||