「レポート ザ・ケーススタディー」
■生活スタイルその2 乗車編(2)「第三段階」
「Ⅶ.マウス・ステイック3」車椅子にて
第4章 マウス・スティックの「環境作り」と「条件の設定」
マウス・スティック・アクティブは、高位頸損のADL(日常生活動作)として有効なものと思う。それは、結果として、随意性が高いとわかったからである。
しかし、マウス・スティックを生活に取り入れるには、まず第一に、本人の「気持ち」の問題がある。
意識を切り替え、使用する環境を整え、条件をそろえる事が必要なのである。
そして、もし、高位頸損者、本人自らが中心となり、かつ自発的にこれを行えれば、リハビリは更に進むことになる。
【①残存機能活用訓練】
私にも、マウス・スティックに、抵抗がなかったわけではない。担当のOTから、絵を描くこと、文字を書くことを薦められた時、拒否感があった。マウス・スティックを使うことによって、「手や足が利かない事を、身をもって、強く認識することが怖かった」からかもしれない。
入院期に、訓練カードを見ると、赤いゴム・スタンプで、「機能回復訓練」とあった。毎日、カードを受け取って、訓練棟に向かいながら、このお題目を見ると「完全治癒はない」と分かっていても、どこかに期待するものが残っていた。
この期待は、多くの場合、結果として良いものを産み出さないと思う。
米国リハビリテーション・リサーチに、興味深いレポートがある。「OTによる『試み』の実践報告」とのことだが、そのテーマは、一貫して「残存機能活用訓練」。
つまり、失われた機能を思い悩むのではなく、「残された機能、筋力を『駆使』して、それに代わる『代償行為』を身に付けさせよう」というのである。
マウス・スティック・アクティブは、そのうちの、一つなのである。
【②マウス・スティックの拒否と受入】
例えば、ペインティング。絵は、好きな方で、極くたまに、良い景色などを見ると、発作的に描きたくなって描くこともあった。けれど、未だに、マウス・スティックで絵を描こうとは思わない。
訓練末期に、OTに説得されて描いてはみたが、「やはり、スムーズではない。」というのが実感だった。
どうしても、ペインティングに必要な、セット・アップがイメージできないのである。また、「環境的に不備を感じているのに、敢て、描きたいとも思わない。」介助量の多いことはしたくないのである。
そして、それどころか、口にマウス・スティックをくわえて絵を描くという光景が、自分が障害前に、イメージしていた障害者感に、はまってしまう事が何よりも許されなく感じたのである。
【③マウス・スティックの使用イメージ】
しかし、本当に、本人に強いニーズがあれば、それは別であり、条件がそろう事により「ソウ」でもなくなっていった。
例えば、ページめくりとワープロのキーボード・アクセス。それぞれ、OTにより提供された基本的な条件(書見台をしようするとか、傾斜角を付けるなど)を元に、マウス・スティックの操作イメージが拡がっていく。
「どうすれば、最低限の介助で目的を果たすことができるか。どうすれば、スムーズに、スマートにできるか。」
更に、必要な条件が明確になり、トータルの操作環境を具体的にイメージする事ができるようになっていった。
こうして、本人の操作イメージに合う環境が整い、後は本人が意識を切り替える事だけが残った。
[ページめくり]
書見台にセットした本を読むには、マウス・スティック。これを有効に使うには、スティック・スタンドと、その最適な設置位置を経験的に見つければ良いと思えた。
そして、ペン・ホルダー。偶然だったが、これを使ってページを押さえられることもわかった。ラッキーである。
面白いことに、環境が整うと、抵抗のあったマウス・スティックも、「くわえて、ページをめくって、スタンドに戻すだけ」と思えてくる。
実際、「一人で、ユックリ読みたい。」という強いニーズが実ったわけだが、電動車椅子に乗って、漫画あるいは本を読む時間が増え、これに伴い起立性低血圧が起こりにくくなっていくのが、自分でも分かった。
そして、ページを戻したり、読み飛ばしたりできる「一人で読む気軽さ」を思い出したのである。
[キーボード・アクセス]
ワープロは、文字を書く、あるいはメモを取る意味で、魅力的な文房具と言える。
それまでは、訓練で、腕をアーム・スリングに吊って、電動タイプ・ライターをタイピング。あるいは、口にサイン・ペンをくわえて、文字を書いたりしたことはあった。
しかし、口で書くのは随意性が低く、その割には、決定的に疲労が大きい。手によるタイピングは、随意性や疲労との兼合が決定的ではないにしろ、セット・アップも複雑で、まして背部からのオーバー・ヘッド・タイプのアーム・スリングを使うという事は、任意、タイムリーに移動できる電動車椅子の目的にはなり得ない。
最低限の介助で、一人でできるADLを拡大するために、日中、家族がいなくとも「済む」ようにマウス・スティックを考えたのに、電動車椅子の動きを制限するような形はナンセンスなのである。
その点、マウス・スティックによるキーボード・アクセスなら、合理性がある。電動車椅子で、経験的に角度をつけたキーボードにアプローチして、マウス・スティックをくわえて、タイピング。これは、任意、タイムリーである。
しかし、ワープロの機能をフルに引き出すためには、様々な工夫が必要だった。それが、「フロッピー・ディスクの交換」の問題だったり、シフト・キーなど「同時押し下げ動作」の問題だったり、印刷の問題だったのである。
【④マウス・スティックの環境】
直面する問題を解決すると、確実に、ADLは拡大する。そして、このマウス・スティック(レギュラ・サイズ)の有効性を認め、長さの異なるマウス・スティック(特大)。あるいは、用途を主体に考えられたフロッピー・ディスク交換用のマウス・スティック(ダブル・サイズ)は使用するに至った。
これらは、ほとんどの場合、その問題は一つづつケースが異なる。しかし、定型化は難しいが、その基本となるべき考え方はある。
以下、マウス・スティック・アクティブに必要な、環境を整えるのに、考慮すべき点を、A)、B)、C)の3つに分けて、述べる。
A)マウス・スティックの長さ
目的となる対象物に求められる「随意性」から、選ぶ。
(キーボード・アクセスなどの、より高い随意性を求めると、マウス・スティックはより短い必要がある。<割り箸程度>)
B)対象物を備え付ける場所
ステップなど心配なく、電動車椅子で「アプローチ」できる事。
対象物の「高さ」は、マウス・スティックの「長さ」から割り出す。
(短いマウス・スティックの場合、電動車椅子でもアプローチできるように、高いテーブルなどに対象物をのせると、距離も接近できる。)
b)リモコンの備え付ける場所
リモコンのある物は、本体ではなく、これを対象物とすることができる。
C)マウス・スティックの置き場
電動車椅子で、「アプローチ」できて、
高さは、口許。
マウス・スティックを楽に「くわえ」られて、
楽に「操作」できて、
楽に「戻せ」ればいい。
(室温管理など、操作が頻繁でない場合、対象物から離れてもよい。)
注)目 的=書字、室温管理、読書など。
目的物=ワープロ、冷房室などの機器。
対象物=キーボード、リモコンなどのインターフェイス。
これらを元に、各ケースを分類して、マウス・スティックの使用環境を述べる。追、この分類は、マウス・スティックの長さ(A分類)で大別されるが、ケースによっては設置環境(B分類)、またはリモコン(b分類)を中心に、解説する。
【⑤レギュラ・ステックの場合~A分類】
A)「ページめくり」や「キーボード・アクセス」に求められる随意性は、比較的高く、レギュラ・スティックが最適である。
B)短いマウス・スティックのため、キーボードや書見台の対象物は、高く設定している。
また、レギュラ・スティックは、潜在的に、随意性が高いが、その動作行為の性格上、対象物にも、傾斜角を付けるなどの措置がひつようとなる。
例えば、ページめくり動作ならば、本をもたれかける傾斜板は、70度。ワープロ打ちに、最適なキーボードの傾斜角度は、30度である。
ワープロは、キーボードを、本体から分離して専用の台に載せ、書見台と並べて「作業台」に備え付けている。
[作業台/ワークス・ステーション]
作業台の高さは、車高の高い前輪駆動の電動車椅子でも、十分に、アプローチできる様になっていて、コントロール・レバーや、ディバイスで付けた手の甲も邪魔にならない。
この高さは、訓練期に、ページめくり動作から経験的に、オーバー・テーブルで割り出している。
ワープロは、本体とキーボードを別に考える。キーボードは、この作業台の高さを規準に、足りない(マウス・スティックの届かない)分を、「底上げ」して、専用台の高さを決める。更に、本体は、画面をほぼ目線に合わせる様に、やはり底上げとしてゲタを履かせる。
その加減は、キーボードを打ち込む時、顔は下向きになるが、画面が、やや「上目」使いに見えるように備え付ける。
本体のゲタがコレぐらいだと、デッキの高さも、フロッピー・ディスクを、考案のハンドリング・デバイスで交換しやすい。
C)スティック・スタンドは、半固定。書見台の本載せ「台」部の左右と、キーボードを載せる「傾斜」面の手前右から、脱着できる。
その高さはマズマズで、それぞれ楽にマウス・スティックをくわえ、戻すことができている。
【⑥特大マウス・スティック~A分類】
特大マウス・スティックを活用すると、ECSでは「できない」より複雑なビデオ・デッキの操作など、ECS以外のADLができる様になる。
「ウィーン。」電動車椅子で、テレビの方向へアプローチ。
テレビは、高さ約120cmの台に備え付けられ、その台とテレビの隙間が、特大マウス・スティックの置き場である。
その様は、先端を差し込み、噛む部分はこちらを向いて、飛び出している様に見える。
「ウィーン。」間違っても、咽や口の中を突かない様に、噛む部分が、アゴあたりの「横」にくる様に、アプローチする。
「トッ、トン。」
頭部スイッチで、電源OFF、ON。マイコン・セレクターは、BACKのみ点灯する。
特大マウス・スティックをくわえ、テレビの音量ツマミの凸面に付けた「細い棒」の端に、これを引っ掛けて、テレビのボリュームを調整する。
[対象物/可変抵抗タイプのツマミの細工]
ツマミ式のボリュームは、特大マウス・スティックでは、操作しにくいが、少し工夫をくわえると、操作しやすくなる。
ボリュームの細工/ボリュームの凸面に、長さ5cm程の細い棒を、紙テープなどで固定すると、その両端に特大マウス・スティックを引っ掛けて、調節しやすくなる。
ア)特大マウス・スティック/形状・材質
全長約70cmと長い物を使用している。材質は、歯やアゴに負担がかからない様に、軽いスギ材を採用している。但し、噛む部分はツブレないようにタケを継ぎ足し、また歯に優しいようにこの上にガーゼを捲いて使用している。
また、棒の半ばには、補強のため、両端から割り箸をビニール・テープでとめている。この補強は、必要以上の「しなり」を防ぎ、操作しにくい「かたい」3段スイッチの「真ん中」にも、スイッチ動作がやさしくなる。
先端には、目標を定めやすい様に、より細い割り箸の割った「片方」を8cm程飛び出させて、ビニール・テープで固定している。
設備環境の基本になる判断材料は、レギュラ・スティックと同じ。但し、優先順位は入れ替わり、より複雑となる。
イ)ニーズ
ビデオ・デッキの操作は、既に、環境制御装置(ECS)により行われているが、制御できる数には、限りがあるので、電動車椅子に乗っている時に、マウス・スティックなどを利用して、より多くの操作が出来れば良いと思った。
B1)部屋を見回すと、対象物となるビデオ・デッキを備え付けるスペースは、テレビとの位置関係から、出窓しかない。
A1)操作は、ダビングやタイマー予約、時刻合わせなど。求められる随意性は、ページめくりやキーボード・アクセス程でもなく、頻繁でもないことから、特大マウス・スティックでも期待できる程のものだった。
B2)ビデオ・デッキは、出窓のスペースに、設置。操作しやすい様に、ほぼ目線になる様に、台にのせている。
A2)出窓ゆえ、電動車椅子のステップなどが邪魔になる。作業台への様にはアプローチできず、距離を長く取るので、マウス・スティックは特大となる。
C)特大マウス・スティックの置き場は、テレビの下。ほぼ、口の高さである。
こうして、ビデオ・デッキ(1台)の操作やテレビの音量調整に、特大マウス・スティックを利用するに至った。
これにより、マウス・スティックの環境は、対象となる物にも、その高さ、形態などを考慮し、ちょっとした細工だけでも、十分にその機能を果たす事を知った。
そして、更に、この利用価値から、壁に備え付けたスイッチ・ボックスの操作、冷暖房器のリモコン操作など、目的物のバリエーションが拡がることになった。
以下、目的となる対象物ごとに設置環境を述べる。
ⅰ.VTR/TV操作
ビデオ・デッキの操作方法は、本体操作の他、リモコン操作や、ベッド日のESC操作など、条件が複雑なので、テレビとも合わせて、後述する。
ⅱ.ミニ・コンポ
ミニ・コンポに関しては、リモコン操作をメイン、後述する。
ⅲ.スイッチ・ボックス
ボックス内の3つのスイッチを[入・切]する事により、蛍光灯をつけたり、他の2つの100V電源コンセントの[入・切]ができる。
3つのスイッチは、アオ、アカ、シロに色分けして、ベッド日でも、介助者に指示しやすくしている。
| [アオ] [アカ] [シロ] [左コ] [右コ] |
左上の[アオ]が、蛍光灯の[入・切]、
右上の[アカ]を[入・切]すると、
真下の、右下のコンセントを制御でき、
右中の[シロ]を[入・切]すると、
真下の、左下のコンセントを制御できる。
従って、[アカ]と[シロ]のスイッチは、コンセントに差し込む目的物(家電製品)を変えれば、制御する家電製品も変わる。
目的物)
現在では、[シロ]に、換気扇。
冬場は、[アカ]に、加湿器をセットしている。
電動車椅子で、テレビ下の特大マウス・スティックをくわえるために、アプローチ。くわえたまま、マイコン・セレクターを操作、壁際のスイッチ・ボックスにアプローチ。
スイッチ・ボックスの高さは、約150cmと、目線よりかなり高めであるが、何とか届く。首を、一杯に伸ばして[アオ]のスイッチの右側に、特大マウス・スティックの先端をアテて、スイッチをONする。
「チカ、チカ、パッ。」蛍光灯がつく。
特大マウス・スティックの使用後は、所定の位置に、電動車椅子で移動して戻す。(OFFも同じ要領である。)
ⅳ.冷暖房有線リモコン(CとAは、共に、上に同じ)
B)リモコン位置は、自動扉の左横の柱。高さは、特大マウス・スティックをくわえて、真正面に冷暖房のメモリがくるように設置した。
リモコンは、有線。当初、ベッド際に位置していたのだが、冷暖房の加減ができなくて、電動車椅子に乗った時に難儀していた。
例えば、冬場などは設定以上に寒くなるので困るので、メモリを強めに設定しておき、熱くなったらESCで電源を切り、寒くなれば電源をいれる。これがパターンであった。
しかし、これは暖房効率が悪く、特大マウス・スティックで調整できる様に、リモコンの位置を変更することになった。
目 的)位置変更により、冷暖房のメモリ調整の他、冷暖房の切り替えなど、タイマーの設定以外のすべて操作ができるようになった。
またメモリの調整が任意にできるようになった事により、メモリを低めに設定することができ、暖房効率も改善され、過暖房による疲れが極端に減ることとなった。
ⅴ.モデム(AとC、共に、上に同じ)
B)位置は、ワープロの左斜め下。棚の上に置いている。基本を外れ、かなり下に位置しているが、電動車椅子でアプローチして、何とか特大マウス・スティックの先端が届く。
目的)ワープロ通信時に何らかの事情で、回線が切れなくなった場合、モデムの[START/ STOP]ボタンでキャリアを切るか、〔POWER〕ボタンを押して電源落とす。
【⑦ワイヤレス・リモコン/ミニ・コンポ~B分類】
ミニ・コンポの操作方法は、以下のように分かれる。
ア)レギュラ・スティックによる「リモコン操作」(b)
イ)特大マウス・スティックによる「本体操作」(B)
ⅰ.機種の操作環境
ミニ・コンポの基本操作はワイヤレス・リモコン(以下、リモコンと略す。)によるが、カセット・テープの交換などの介助を要するため、本体の設置環境(B)も同時に考える必要がある。
B1)本体位置は、ワープロの左横。高さは、介助者が操作しやすい胸元。
かつ、また、あるいは、指示しやすい様に本人の目線が良い。
また、この高さは、特大マウス・スティックが届く位置なので、仮に、リモコンで操作できない(特種)操作が必要であっても、対処できる。
用意したスペースは、横幅50㎝×高さ約30cm×奥域約30㎝。
その他、モデムetcとの位置関係
B2)程よい高さにするため、本機は、ゲタを履いている。ゲタは、幅43㎝、刃(足)の長さは18㎝で、下にあるカラー・ボックスとの空間を支えている。右側は、板がそのままワープロを載せた台にもたれかけ、高さが合う。
そして、カラー・ボックスとミニ・コンポとの空間に、イメージ・リーダを置き、その後、モデムも設置することとなった。
ⅱ.選択基準
ミニ・コンポは、上記スペースに収まること。基本(ほとんどの)操作が、リモコンで、できること。ダブル・デッキであること。価格が、5万程度であること。以上を条件に、友人に機種選択を委ねた。
ⅲ.機種選択
本機は、SHARP COMPACTDISC STEREO MUSIC SYSTEM CD-X10
価格は、定価、9万8千円を、バーゲンで、5万5千円。
寸法は、横幅68㎝(×高さ26㎝×奥域31㎝)
脱着式のスピーカーを、片方(横幅19.5cm)を外すと、用意したスペースに収まる。外した右スピーカーは、ワープロの右横に投げ置いてある。
ア)リモコン操作の環境
リモコンは、対象となるボタンが、細いので、
A) 随意性の高い、レギュラ・スティックが好ましく、
b1)これの届く範囲に、リモコンを置くことが有効であると創造できる。
b2)そこで、ワープロのキーボードの手前に、リモコンを置ける位置を準備した。
C) レギュラ・スティックは、キーボード・アクセスに活用している物を、転用する。故に、スティック・スタンドの新たな設置は要らない。
[スペースの確保]
ミニ・コンポのリモコンの幅は、5cm。レギュラ・スティックでの利用を考えると、ワープロ・キーボードの手前が無難。
キーボードと専用(の傾斜)台の関係を見ると、キーボードが落ちないように設けた「引っ掛かり」が、キーボードと同じ高さにある。幅、2cm。
このスペースをリモコンを置くのに活かすため、カセット・テープの内ケースの段差を「引っ掛かり」に合わせ、ガム・テープで手前から付け足すことにした。
これにより確保できたスペースは、縦幅6㎝である。
追)後にビデオ・デッキのリモコンも置くこととした。
[実際の操作]
|
リモコンを図で示す。 ミニ・コンポの機能は、CD、TUNER、TAPE、AUXの4つ。 CDは、再生等の基本操作の他、OPEN/CLOSE、リピート、曲順指定、 メモリ、呼出、表示、クリアなど、すべての操作が可能。 TUNERで可能な操作は、機能の選択のみ。本体(上部)で、バンド指定、 選曲した局のみ、聞ける。 TAPEは、機能選択ボタンが、そのままテープ1又はテープ2のモード切替に なっている。供に、再生、裏面再生、頭出しなど、基本操作が可能。 録音はテープ2のみ。 CD、TUNER、AUX(外部入力)より可能。 AUXも機能を選択できるのみ。 その他、POWERの[入・切]と、電子ボリュームによる「音量の調節」が可能。 |
||||||
注)ここで言う基本操作とは、再生[>]、停止[■]、一時停止[||]の他
CDの場合、[>>]は曲番順送り。
[<<]は曲番逆送り。
APSS 一時停止[||]の後に、[>>]ないし[<<]を押すと、
[||]+[>>]は、前方向の倍速再生。
[||]+[<<]は、後への倍速逆再生。
TAPEの場合、[>>]は、早送り。
[<<]は、巻戻し。
APSS 一時停止[||]の後に、[>>]ないし[<<]を押すと、
[||]+[>>]は、次曲頭出し。
[||]+[<<]は、前曲頭出し。
イ)本体操作の環境
本体操作は、リモコン(の基本操作など)で、できない(特種)操作のみ。
A)特大マウス・スティック。
B)本体位置は、これに届く「ワープロの左横」に設置。
ⅰ.特大マウス・スティックでしか、操作できない項目
テープのダビング[EDITING]ボタン。
バンド切替 リバース・モードの切り替え、
テープ・ポジション。
音質関係 グラフィック・エコライザの調整、
[SUPER・BASS]ボタン。
ⅱ.その他/まったく不可能な、操作項目
TIMER関係 ナ イ ト[REC]TIMERと、
モーニング[PLAY]TIMERの設定と、
[時計合せ]である。
これは、同時押し下げ動作が要求されるからだが、その対処はしていない。
〔参考〕 接続による機能拡大
設置時に、AUXの入力端子に、ビデオ・デッキの音声出力を接続。
→TV/VTRのSTEREO/音声多重放送が楽しめる。
CDの出力端子は、ビデオ・デッキの音声入力へ接続。
→ビデオ・テープにオーデイオ録音ができる。
【⑧テレビとビデオ・デッキ/多数の操作方法】
注)ビデオ・デッキは、その後、NV-F3とNV850の2台になった。
NV-F3は、NV850より、多機能なので、これをメインとした。
ベッド日において、ビデオ・デッキは、ESCを通して操作されているが、その制御数には、限りがある。
しかし、電動車椅子に乗っている日には、特大マウス・ステイックを使えば、番組予約など、ESCでは不十分な面をカバーすることができる。
ビデオ・デッキの操作方法を、以下の様に分けて解説する。
ア)特大マウス・ステイックによる「本体操作」(B)
イ)レギュラ・ステイックによる「リモコン操作」(b)
ウ)ESCによる操作~第1編「Ⅲ.環境制御装置」にて、記述。
ア)本体操作の環境
特大マウス・ステイックを使って、本体操作をする。
ⅰ.可能な本体操作
VTR操作 ダビング。基本動作の他、[巻戻し]や[取出]、
チャンネル[順送り]など、ESCではできない操作。
録画速度切替、タイマー予約、時刻合せ、
録音ボリュームの調節(F3のみ)。
TVの操作 ボリューム調整、ダイレクト選局など。
その他、不可能な本体操作
ツマミ式(可変抵抗タイプの)スイッチを、細工するスペースがない。
以上の事を、ESC以外にも、ビデオ・デッキやテレビを操作するには、設置環境を整備しなければならない。
ⅱ.設置環境
NV-F3とNV850(以下、F3、850と略す。)の上下の位置関係や高さ、テレビの高さの位置関係を述べる。
2台のビデオ・デッキは、出窓に、重ねて、ゲタを履かせて、備え付ける。
F3は、操作ボタンを内蔵したオープン・パネルが上を向いているので、特大マウス・ステイックで操作するには、パネルを目線よりも「下」に位置させる様に、デッキを備え付ける。
850は、操作ボタンが正面にあるので、F3の「上」に乗せる。
ゲタは、高さはホボ目線になる様に、履かせる。
テレビの位置は、ビデオ・デッキのソバ、右側。テレビ鑑賞は、電動車椅子のリクライニングをフル・ダウンして見たりするので、ビデオ・デッキなどよりも「上」になる。
その加減は、特大マウス・ステイックが一杯にアプローチして、テレビの操作ボタンにギリギリ届くぐらいでよい。
また、直座で見る時も、チョットのけぞって、上目使いに見る態勢の方が、座位は比較的、楽である。
イ)リモコン操作の環境
ⅰ.リモコンの設置スペースは、キーボードの手前。ミニ・コンポのリモコンの右側に設置することができた。
普段は、ESCによる操作や、本体操作で十分だが、更に、キーボード手前などに、リモコンが備え付けてあれば、ワープロ操作中に、急ぎ録画ボタン(要改造)を操作するとか、チャンネルを選局する時に、便利である。
ⅱ.NV-F3のリモコン
NV-F3は、リモコンのモードに、「VTR1」と「VTR2」がある。モードの意味は、以下の通り。
設定
VTR1 NV850も同時に操作される。
VTR2 NV-F3が単独に操作される。
従来のNV850のリモコンは、環境制御装置(ESC)に接続されている。
これをそのまま、活かすために、NV-F3のリモコン・モードも、VTR1とする。
F3のリモコンは、より多機能だが、ESCにつないでも、その制御数に限りがあるので、これに変えるメリットがない。
ⅲ.リモコンで可能な操作は、以下の通り。
[NV850に対して]
850は、本体と元々のリモコンにも、チャンネルは[順送り]しかないが、F3のリモコンを使って、ダイレクト選局が可能。
その他、基礎操作、VTR基本操作も可。
[NV-F3に対して]
基礎操作 電源の[入・切]と[ビデオ][テレビ]のモード選択など
付加操作 [音声切替][メモリー][リセット]
VTRの基本操作 [再生][停止][早送り][巻戻し]
及びビクチャー・サーチ、[録画]の他、
リモコン特有の操作を、F3(850互換)のリモコンの図で示す。
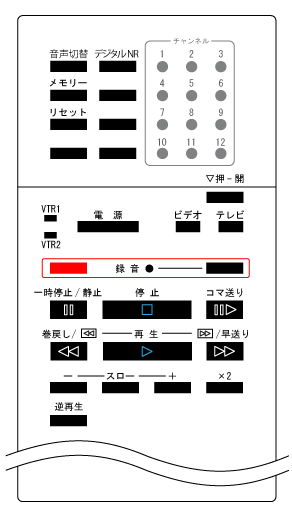
・F3のリモコン
[リモコン特有の操作1]
TVのチャンネル選局は、ダイレクト方式。
[特有操作2]
パネルを開くと、頭出し、デジタル機能を使えるが、スライド式スイッチは、切り替えにくい。どちらか一方に、固定して使う。
[リモコンの共用]
モードを、VTR1にしているので、850も、操作可能。
注)VTR2だと、F3のみ。
[リモコン改造]
録画ボタンは、同時押下式だが、「改造」して、[REC]1つを押すだけで、録画がされる。
[特有操作3]
スロー、倍速、逆再生。これらは、本体操作には、ない。
ウ)ESCによるリモコン操作~ベッド日
通常、ESCにより操作するビデオ・デッキはF3のみ。850は、ビデオ・テープを入れず、タイマー・ボタンを押して、リモコン受信しなくしてある。
但し、やり方によっては、リモコン1つで、ベッドの日に、両機を活用することもできる。
(以外と神経も費やすし、必要に迫られる事も少ないので、その機会は少ない。)
以下、参考までに記す。
参考1)F3は、[外部入力]バンドを、チャンネル[L]として、チューナー・バンドのチャンネル・ポジションに、登録することができる。
つまり、850からのチューナー及びビデオ出力を、F3のチャンネル[L]を通して、見ることができる。
当ケースにおいては、F3は設定チャンネル数が「11」(奇数)ポジション、850は設定チャンネル数は「16」(偶数)ポジションになっているので、共通のリモコンを使って、チャンネル順送りをすると、850に入ったすべてのチューナーの出力を、F3の[L]チャンネルを通して見ることができる。
但し、手間がかかる。
参考2)更に、850にビデオ・テープを装填し、F3を「空」にしておくと、例えば、ECSにより、85のチャンネルを任意に「選ん」で「録画」をし、その後F3のチャンネルを「順送り」すれば、ベッド日でも、裏番組として「録画」したものを、後に鑑賞(再生)することができる。
<おわりに>
以上の様に、環境を整えるなど、マウス・スティックを活用する条件をそろえると、ECS以外のADLが確実に増えていく。
条件の見極めがよければ、波及効果も高く、条件連鎖の起こる事もある。
そこには、障害者といえども本人の意思があり、この過程において、自立心が培われていく事になるだろ。
