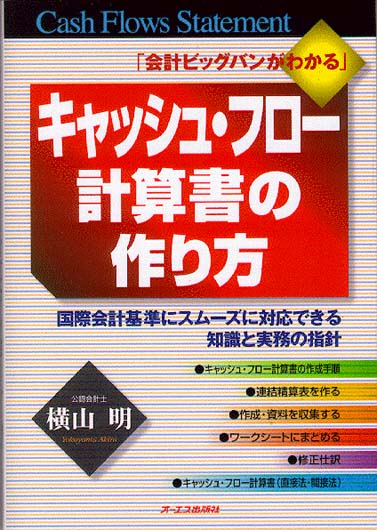 ISBN�ԍ�4-7573-0027-1�@�{�̂P�S�O�O�~�{����� |
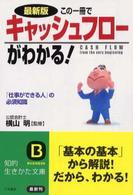 ISBN�ԍ�4-8379-7307-8 �{�̂T�R�R�~�{����� |
||||
| �C���^�[�l�b�g���X | |||||
�L���b�V���E�t���[�v�Z���̍��� |
| �u�A���L���b�V���E�t���[�v�Z�����̍쐬��i����10�N3��13�����\�j�v�ɏ������� |
|
|
| �o�ŕ� | �u�L���b�V���E�t���[�v�Z���̍����v���R�����A�I�[�G�X�o�� |
| �u���̈�����L���b�V���t���[���킩��I�v���R���ďC�A�O�}���[�u�m�I���������Ɂv |
|
�呠�Ȋ�Ɖ�v�R�c��́A�����P�O�N�i�P�X�X�W�N�j�R���P�R���u�A���L���b�V���E�t���[�v�Z�����̍쐬��v�����\�����B
�K�p�́A�A���������\����łȂ��A�ʍ������\�ɂ��ΏۂƂ���A���ԍ������\�i�A���E�ʑo���j�ɂ��K�p�����Ƃ��Ă���B
�K�p�����́A�A���L���b�V���E�t���[�v�Z���͕����P�P�N�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x�i�Q�O�O�O�N�R�����Z�j����[�u����悤���Ă���B�A���������\���쐬���Ȃ���Ђɂ��ẮA�����P�Q�N�S���P���Ȍ�J�n���钆�ԉ�v���Ԃ���K�p����悤���Ă���B
�Ȃ��A�V���ȁu�A���������\�����i�����X�N�U���U���t���j�v�́A�����P�O�N�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x������{���A�����P�P�N�S���P���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x����{�i�I�Ɏ��{�����悤�[�u����Ƃ��Ă���B
�����w�j�́A���{���F��v�m����W�҂Ƌ��c�̏�K�ɑ[�u���邱�Ƃ��K���Ƃ��Ă���B
�u�A���L���b�V���E�t���[�v�Z�����̍쐬��v�̌����́A�呠�Ȃ̃z�[���y�[�W�������ł��܂��B
�Ȃ��A�����Ɏ����܂��L���b�V���E�t���[�v�Z���́A�����̊�Ƃ��K�p����u�Ԑږ@�v�̍쐬���@��������A���ږ@�͎����Ă��܂���B
�Ȃ��A�u�A���L���b�V���t���[�v�Z�����̍쐬��v�́A���ۉ�v�����7���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���i1992�N�����Łj�v�Ƃقڈ�v���Ă��܂��B�Ⴆ�A�Ԑږ@�̏ꍇ�A�ŋ������O���v���n�߁A��旘���E�z�����A�x�������A�@�l�����ł��x���z�Ŏ�������A�u�����y�ь����������v�̓��e��ݎؑΏƕ\�̉ȖڂƂ̊֘A���J��������Ȃǂ͂���ӂ��ł��B
�������A���ۉ�v��̑ݎؑΏƕ\�́u�����y�ь����������v�̗p����g�p���L���b�V���t���[�v�Z���ƈ�v�����邱�ƂɂȂ�܂������A�킪���̑呠�ȗ߂ł͑ݎؑΏƕ\�Ɂu�����y�ь����������v�̗p����g�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��K���ƂȂ��Ă��܂��B
���ۉ�v��ŘA���������\���쐬���Ă����}�C�N���\�t�g�Ђ̃L���b�V���E�t���[�v�Z���i�Ԑږ@�j�͏����ȕč���ō쐬���Ă���A���{�̊����э��ۉ�v����Ȍ��ł��B
�Ȃ��A���{��ƂŊ��ɍ쐬������\����Ă���L���b�V���t���[�v�Z���́A���L�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B��������Ȍ��ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B
| �e�Ђ� �L���b�V���E�t���[�v�Z���� ���邱�Ƃ��ł��܂��B |
����� | �L���b�V���E�t���[�v�Z���� �J���@ |
�R�����g |
| �x�m�� | ���{� | �Ԑږ@ | ���{��ɏ������A�Ԑږ@�ɂ�� �ŋ������O�����v���\�����Ă��܂��B |
| �\�j�[ | �č���v� | �Ԑږ@ | �č���v��ɏ������A�Ԑږ@�ɂ�� �����v���\�����Ă��܂��B |
| �{�c�Z�� | �č���v� | �Ԑږ@ | �č���v��ɏ������A�Ԑږ@�ɂ�� �����v���\�����Ă��܂��B |
| �O�HUFJ�t�@�C�i���V�����O���[�v | �č���v� | �Ԑږ@ | �č���v��ɏ������A�Ԑږ@�ɂ�� �����v���\�����Ă��܂��B |
�č��ł́A�]���̎����ϓ��v�Z���iFund Statement�j���玑���T�O��ύX���āA������v����i�r�e�`�r�j��X�T���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���iStatement
of Cash Flows�j�v��ݒ肵�A�P�X�W�W�N�V���P�T���Ȍ�I�����鎖�ƔN�x���K�p�ƂȂ����B�X�T�����A���ږ@������iencourages�j�����ɂ�������炸���ʂ́A���������U�O�O�Ђ̓��P�T�Ђ݂̂����ږ@��K�p�����ɉ߂��Ȃ������i�`�������������������s�������������s�������������������j�A�Ƃ��Ă���B
�č���̒��ږ@�́A�ڋq����̎����A�d����y�ѐl����x�����z�����A���ږ@�ŊJ�����Ă��A���v�v�Z���̏����v�Ƃ̒����\�i�Ԑږ@�Ɠ������́j���J�����邱�Ƃ����߂Ă��܂��B���ۉ�v��y�ѓ��{�̊�́A���ږ@�̏ꍇ�A�č�������߂Ă��鑹�v�v�Z���̗��v�Ƃ̒����\�̊J�������߂Ă��Ȃ����߁A���v�v�Z���Ƃ̊֘A���s���ĂƂȂ�܂��B
| �Ȃ��A���Z�@�ւ���́u���Z�@�ւ̃L���b�V���E�t���[�v�Z���v�͂ǂ��Ȃ�̂��A�Ƃ̖₢���킹������܂����C�Ԑږ@�ɂ��ẮA��L�����O�H��s�̕č���ɂ��L���b�V���E�t���[�v�Z�����Q�l�ƂȂ�܂����C���ږ@�ɂ��ẮA���ۉ�v���V���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�́u�t�^2�v�Ɂu���Z�@�ւ̃L���b�V���E�t���[�v�Z���i���ږ@�j�v�̗Ꭶ��������Ă���Q�l�ƂȂ�܂��B���{�̃L���b�V���t���[�v�Z���́A���ۉ�v��̓���������ł���܂��B���{�̉�v�ƍ��ۉ�v��̊W�́A�u���ۉ�v��Ɠ��{�̉�v�̑���_�v����сu���ۉ�v��v��ʓr�p�ӂ��Ă��܂��B�����̂�����͂��Q�Ƃ��������B |
�L���b�V���t���[�v�Z���́A�u�c�Ɗ����v�u���������v�u���������v�̎O�̋敪�ɕ����ĕ\�����܂����A�u�c�Ɗ����v�敪�̕\���̎d���Ɂu���ږ@�v����сu�Ԑږ@�v�̓�̑I����������܂��B
�@�č���v��ł́u���ږ@�v��I������Ɓu�Ԑږ@�v�̓��e�𒍋L���邱�Ƃ����߂��܂����A���{����э��ۉ�v��͑I�𐧂��Ƃ�A�u���ږ@�v��I�������ꍇ�A�Ԑږ@�̒��L�ɂ��J�������߂Ă��܂���B
�]���āC�Ԑږ@�̊J���ƒ��ږ@�̊J���̈Ⴂ���悭�m���Ă��Ȃ��ƁA���߂鐔�l���\������Ă��Ȃ��Ƃ��������Ԃ��N����܂��B
��Ɖ�v�R�c��́u�L���b�V���t���[�v�Z�����̍쐬��v�Ɍf�ڂ̗l���ŁA�u�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���t���[�v���r���Ă݂܂��傤�B
| ���ږ@ | �Ԑږ@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�h�D�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���t���[
|
�h�D�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���t���[
|
�u���ږ@�v�ł͉c�Ǝ����A���ޗ����͏��i�̎d���x�o�A�l����x�o����т��̑��̉c�Ǝx�o���\������C�u���v�v���\������܂��B
����u�Ԑږ@�v�ł́A���v�v�Z���̐ŋ��������O���������v����n�܂�A������`��v�̑��v�v�Z�����玑���̗��o����ї����ɊW�������ڂ������̗��o�E�����ɂ��邽�߂̒����������u���v�v��\�����܂��B
���ږ@����ъԐږ@�́u���v�v�̋��z�͑o���Ƃ���v���A���v�ȉ��̕\������ы��z�ɑ���͂���܂���B
�����̒ʂ�C�u���ږ@�v�ł͑��v�v�Z���̂ǂ̋��z���\������Ȃ��Ƃ��납��A���v�v�Z���Ƃ̊֘A���s���ƂȂ�܂��B�����́A�c�Ǝ����A���ޗ����͏��i�̎d���x�o�A�l����x�o�A���̑��̉c�Ǝx�o���J�������Ƃ������Ƃł��B
����́u�Ԑږ@�v�́A���v�v�Z���̗��v����n�܂�܂��̂ŁA���v�v�Z���Ƃ̊֘A�����炩�ɂȂ�܂��B�܂��A�����̗��o�ɊW���Ȃ��������p���ݓ|�������̌J���z���\������܂��B
�ǂ���̕��@��I�����邩�͊�Ƃ̎��R�ł��B�������Ȃ���C�ǎ҂́A�o���̊J�����e��m���Ă��Ȃ��ƁA���҂��鐔�l���\�����Ă��Ȃ����Ƃɋ^�O�����\��������܂��B
�P�X�U�R�N�A�č���v��ψ���ӌ����iAPB
Opinion�j��R���u��������^�p�\�iThe statement
of source and application of funds�E�E�ʏ́@Funds�@Statement�j�v�ɂ��A�����̌���щ^�p���������\�����߂��������͂��܂���ł����B�܂��A�����T�O���^�]�����i�������Y���痬�������T�������z�j���L���T�O���̗p���A�L���،��̔��s�ɂ��Œ莑�Y���擾�������K������܂߂�ׂ��Ƃ��Ă��܂����B
�P�X�V�P�N�R���A��v��ψ���́A�ӌ����iAPB Opinion�j��P�X���u������ԕϓ��̕iReporting
changes in financial position�j�v�����\���A�ݎؑΏƕ\�y�ё��v�v�Z���Ɠ��l�Ɋ�{�������\�̈ꕔ���\�����A�������Ƃ̂ł��Ȃ���{�������\�ł���Ƃ��܂����B���̂��C������ԕϓ��\�iStatement
of Changes in Financial Position�j�Ɖ��߂���{�������\�̈�ɂȂ�܂����B
�P�X�W�V�N�A������v��ψ���(FASB)�́A������v����iSFAS�j��X�T���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�����\���A�]���̍�����ԕϓ��\�̎����T�O�����o�c���Ԃɑ������u�����y�ь����������v�ɕύX���A�P�X�W�W�N�V���P�T���Ȍ�I�����鎖�ƔN�x���K�p����������Ă��܂��B
���ۉ�v��i�h�`�r�j��V���u�i���j������ԕϓ��\�v�́A��{�I�ɂ͕č��̈ӌ����iAPB
Opinion�j��P�X���Ɠ��l�̂��̂łP�X�V�X�N�P���P���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x����K�p�Ƃ���Ă������A�č��ō�����v����iSFAS�j��X�T���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�ɂ�莑���T�O��ύX�������ƂŁA�č���v����l�Ɂu�����y�ь����������v�������T�O�Ƃ��Ĉ�v�������̂��L���b�V���E�t���[�v�Z���Ƃ����B�č���Ǝ�قȂ�B�č���̊Ԑږ@�������v����J������邪�A���ۉ�v��͐ň��O���v����J�����邱�Ƃ����߂Ă���B�J�����e�ɂ͑傫�ȈႢ�͂Ȃ��B�č���ł��@�l�����ŁA�x���������̎x�����z�͒��L�ɂ��J�������߂��Ă���̂ƁA���ۉ�v��͌v�Z����ɊJ������܂��̂ŁA�����I�ȈႢ�͂���܂���B
���{�̊�́A���ۉ�v���V���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�ɗގ����Ă��܂��B�Ȃ��A�u���ۉ�v��v����сu���ۉ�v��Ɠ��{�̉�v�̑���_�v��p�ӂ��Ă܂��B�����̂�����͂��Q�Ƃ��������B
| ��Ж@�i���@�j�̌v�Z���� �y�јA���v�Z���� |
���ۊ�̍������\ | ��v�ȑ���_ | ||
| �i�P�j�v�Z���ނ̑̌n�F �E�ݎؑΏƕ\ �E���v�v�Z�� �E���v������
|
�i1�j�������\�̑̌n�F �E�ݎؑΏƕ\ �E���v�v�Z�� �E���厝���ϓ��v�Z�� �E�L���b�V���t���[�v�Z�� �E�����I���L �u���ۉ�v��v�Q�� |
���@�ł́A���厝���ϓ��v�Z���A�L���b�V���E�t���[�v�Z�� �Ȃǂ̊�{�������\�͂Ȃ��A���L���n��B ���ۊ�ɗ��v�����ĂƂ����v�Z���͑��݂��Ȃ��B ���@��Q�W�P���1���̕��������͊J�����ނł� �Ȃ�����̎苖�ɂ͓͂��Ȃ��B
���@���z�����v�̌v�Z���d�����Ă���Ǝ咣���Ă��� ���Ƃ���A�L���b�V���E�t���[�v�Z���̊J�������Ȃ��̂� �_���I�����Ƃ��鍑�ۉ�v����̎��_������B |
�A���L���b�V���t���[�v�Z���́A�A���ݎؑΏƕ\�A�A�����v�v�Z���A�A����]���v�Z��������������ɍ쐬���܂��B�������A�A���L���b�V���t���[�v�Z���̎����̗��o�y�ї����̓��e�́A�A���x�[�X�ō쐬���邽�߁A�q��Ђ��玑���̗��o�y�ї����̖��ׂ���肵�Ă����K�v������܂��B�A���������\�y�јA���L���b�V���t���[�v�Z���쐬�ɂ́u�A�������v���d�v�Ȏ����ɂȂ�܂��B�����ӂ�ƁA�^�C�����[�Ő��m�ȘA���L���b�V���t���[�v�Z���y�јA���������\�͍쐬�ł��܂���B
�A����Ƃ́A�ʏ�A���̂悤�Ȏ菇�ōs���܂����A�u�A�������v�����m�ŏ\���ȏ�����Ă��ď��߂Č����I�ȘA����ƂƂȂ�܂��B
�@�@�A�������̓����ˁ@�A�@�A�������̃`�F�b�N���@�B�@�A�������̏W�v�E�d��쐬�i���Z�\�W�v�A�����Ǝ��{�̏��������̏W�v�E�d��쐬�A�������厝���̏W�v�E�d��쐬�A�A����ЊԎ���̏����̏W�v�E�d��쐬�A�A����Њԍ����̏����E�d��쐬�A�A����ЊԎ���̖��������v�̏W�v�E�d��쐬�A�A����Њԍ������ɔ����ݓ|�������̖ߓ��d��쐬�A�����@�̏W�v�E�d��쐬�A�Ō��ʉ�v�̏W�v�E�d��쐬�A���̑��A���C�����ׂ������̏W�v�E�d��쐬�A�L���b�V���t���[�v�Z���쐬�����̏W�v�A�Ō��ʉ�v�E�ސE���t�̉�v�E���ۏؓ��̋������ہE�Z�O�����g��̒��L�����̏W�v���j���@�C�@�A�����Z�\�̊������@�D�@�A���L���b�V���t���[�v�Z���̍쐬�ˁ@�E�@�A���������\�̒��L�����̍쐬���@�F�@�A���������\�E�L���b�V���t���[�v�Z���E���L�����̊��Ԕ�r���ɂ�蕪�͂����m�����m���߂����@�G�@�����ւ̕�
�A���L���b�V���t���[�v�Z���̍쐬���@�͉��L�̒ʂ��̕��@������ƏЉ�Ă���悤�ł����A�����Ɏ������L���b�V���t���[�v�Z���̍����͎����I���@�����������̂ł��B
| 1 | ���_�I���@ | �e��ЁA�A���q��Ђ��ꂼ��ʂ̃L���b�V���t���[�v�Z�����쐬���āA�ݎؑΏƕ\�E���v�v�Z���E��]���v�Z���Ɋւ���ʏ�̘A���C���d��f���āA���A�A����ЊԂ̃L���b�V���t���[�E���ĘA���L���b�V���t���[�v�Z�����쐬������@�B �������A���̕��@�͊���̗��_�ŁA�A���C���d��f����̂ɕ��G�ƂȂ��Ď����I�ƌ�����A���ӂ�v����Ƃ���ł��B�Ⴆ�A���ȉ����Y�̖��������v�̏����́A�������ȉ����Y�A���㌴���A�����]���i���O�������ȉ����Y�j���C�����܂����A�A���L���b�V���t���[�v�Z�����쐬�����ł����A���C���̔��f���ɓx�ɕ��G�ƂȂ�܂��B |
| 2 | �����I���@ | �A���ݎؑΏƕ\�A�A�����v�v�Z���A�A����]���v�Z�����쐬��A�A���L���b�V���t���[�v�Z�����쐬������@�B |
���_�I���@�́A�A���O���[�v�S�̂��ʃL���b�V���t���[�v�Z���𐳂����쐬�ł��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B�A������ɂ́A�ʏ�̘A���C���i�����Ǝ��{�̏����A�A����ЊԂ̍����̏����A���������v�̏����Ȃǁj�f�����A���A�L���b�V���t���[�̘A����ЊԂE�������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B�A���q��Ђ̐����ɂ߂ď��Ȃ��ꍇ�ɂ͓K�p�ł��܂����C���m���ɋ^�₪�c�邱�ƁA���A�쐬���Ԃ������邱�Ƃ��l�b�N�ƂȂ�܂��B���_�C�R�[�������ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�����I���@�́A�쐬���Ԃ����Ȃ��čςށA���m�����m�ۂ����A�A���q��Ђ̐��������Ă��ȒP�ɑΉ��ł���A���̗��_������܂��B���Ȃ݂ɁA�č����SEC�֒�o���Ă�����{��Ƃ͐��S�Ђ̎q��Ђ�A�����Ă��܂����A�����I�@���̗p���Ă��܂��B
�Ȃ��A�A�����Z�ƃL���b�V���t���[�v�Z���̍쐬�̊W�́u�A���������\�쐬�̊�b�v�ɏڂ����L�ڂ��Ă܂��̂ŎQ�Ƃ��Ă��������B
�킪������b�Ƃ������ۉ�v��i�h�`�r�j��V���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�́A�č��̍�����v��i�r�e�`�r�j��X�T���u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�Ɋ�b������܂��B�č��ł́A�������j�������Ă���A��v��ӌ����i�`�o�a�@�n�����������j��P�X���u�����ϓ��v�Z���v���P�X�V�P�N�X���R�O���Ȍ�I�����鎖�ƔN�x����K�p����A�P�X�W�V�N�P�P���A�����T�O���u�����y�ь����������v�ɕύX���Ăr�e�`�r��X�T���ƂȂ�A���ۉ�v���V���̊�b�ƂȂ��Ă��܂��B�č��ɂ͒������j�����邱�Ƃ����_�B���_�ɁA�����o���L�x�ȉ�v�l����������Ƃ����Ƃł��B���Ȃ݂ɁA�č��̉�v�m�́A���݂R�R���l�A���������v�m�i�Œᐔ�\�Ђ̊č������o������j����Ƃɏ]�����Ă���A��v�m���E�o�����������l�ނ���Ɠ��ɂ��Đ��x�̍����������\���쐬�ł���̐�������Ƃ������Ƃł��B
���������A�������j�ƁA�l�I��������b�ɂ���A�q��Ђ��܂߂Đ��m�ȃL���b�V���E�t���[�v�Z�����쐬����\�͂��邪�A�킪���ł́A�m���E�o���A�l�I�����̕s�����Ă��錻��ł́A�q��ЂɃL���b�V���t���[�v�Z�����쐬���Ă��炤�̂́A�i�K�I�ɓK�p���Ă������ƂɂȂ낤�B���Ƃ��A�d�v���̍����q��Ђɂ͍쐬���Ă��炤�Ƃ����悤�ɂł���B
�L���b�V���E�t���[�v�Z���́A�N�x�A�����Z����łȂ��P�ƍ������\�̈�ɉ������܂��B�܂��A�N�x����łȂ��A���y�ђP�Ƃ̒��Ԍ��Z�ł��쐬���v������܂��B
�L���b�V���E�t���[�v�Z���́A�����̗����y�ї��o���A�u�c�Ɗ����v�A�u���������v�y�сu���������v�̎O�ɋ敪���ĕ\�����܂��B
�u�c�Ɗ����敪�v�̕\���̕��@�ɂ́A���ږ@�ƊԐږ@������܂��B
���ږ@�́A�c�Ǝ����A���ޗ����͏��i�̎d���x�o�A���̑��̉c�Ǝx�o���J��������@�i��L�Q���j�ł����A�Ԑږ@�͑��v�v�Z���̐ň��O���v�i�č���͏����v�j����J���������̗��o��Ȃ��������p��A�ݓ|�������̌J���z�������Z���A�L�`�Œ莑�Y���p�v�������Z���A�������Y�E���̂��������܂��͍��������ɌW����̂��������������z�������Z���ĉc�Ɗ������瓾�����͎g�p�����L���b�V�����������̂ł��B
���������敪�y�ѓ��������敪�́A���ږ@�y�ъԐږ@������������ɕ\������܂��B
| �i1�j | �Ԑږ@�́A���v�v�Z���̐ň��O���������v����n�܂葹�v�v�Z���ƈ�v���Ă���B
|
|
| �i2�j | �Ԑږ@�̒������ڂɂ͔�����`��v����L���V���E�t���[�ւ̒������\�������B
|
|
| �i3�j | ���������̃L���b�V���E�t���[
|
|
| �i�S�j | ���������̃L���b�V���E�t���[
|
|
| �i�T�j | ���ׂĂ��\���������̂ł͂Ȃ��B
|
|
| �i�U�j | �u�����y�ь����������v�̊����c���͑ݎؑΏƕ\�ƈ�v����B
|
�Ԑږ@�̍쐬�����́A�A���ݎؑΏƕ\�������ƑO�����̂Q�����Ɠ����̘A�����v�v�Z������ї��v��]���v�Z������b�Ƃ��A�����ڂ̊����������ׂ���A�L���b�V���E�t���[�v�Z�����[�N�V�[�g�ɏC���d����s���쐬���܂��B
| 2011�N �R���R�P������ |
2012�N �R���R�P������ |
|
| �����y�ь����������i���L�̒��L1�Q�Ɓj | 300 | 320 |
| �L���،� | 200 | 220 |
| ���|�� | 350 | 390 |
| �ݓ|������ | -3 | -4 |
| ���ȉ����Y | 230 | 250 |
| ���̑��̗������Y | 50 | 30 |
| �����A�� | 500 | 610 |
| �������p�v�z | -300 | -350 |
| �y�n | 300 | 300 |
| ���`�Œ莑�Y | 50 | 60 |
| �����L���،� | 70 | 100 |
| �ۏ؋��E�~�� | 83 | 81 |
| ��؍� | 200 | 150 |
| �ݓ|������ | -100 | -110 |
| �A����������i���L�̒��L�Q�Q�Ɓj | 60 | 48 |
| ���Y���v | 1,990 | 2,095 |
| �Z���ؓ��� | 170 | 100 |
| ��N���ԍϒ����ؓ� | 30 | 20 |
| ���|�� | 300 | 280 |
| ������ | 252 | 233 |
| �����@�l�œ� | 50 | 60 |
| �����ؓ��� | 300 | 400 |
| �ސE���^������ | 250 | 260 |
| �������厝�� | 20 | 30 |
| ���{�� | 250 | 300 |
| ���{������ | 250 | 300 |
| �A����]�� | 130 | 120 |
| �ב֊��Z��������i���L�̒��L�R�Q�Ɓj | -10 | -5 |
| ���Ȋ��� | -2 | -3 |
| ���E���{���v | 1,990 | 2,095 |
���L�P�F�����y�ь���������
��Ɖ�v�R�c��̐V�����u�A���������\�����i����9�N6��6���j�v�ɂ́A�u�����y�ь����������v�̗p��͖�������Ă��炸�A�ݎؑΏƕ\�ŕ\���ł��邩�肩�ł͂Ȃ����A�L���b�V���t���[�v�Z���̍쐬�̕X��g�p���܂����B
�呠�Ȃ̘A���������\�K���i1998�N2��20���t���j�̗l���ꍆ�i�A���ݎؑΏƕ\�j�ɂ��A�u�����y�ь����������v�̗p���p���đݎؑΏƕ\�ɕ\���ł���悤�ɂȂ��Ă͂��܂���B
���Ȃ݂ɁA1997�N8���Ɍ��\����܂������ۉ�v���1���u�������\�̕\���i1997�N�����Łj�v�ł́A�ݎؑΏƕ\�Ɂu�����y�ь����������v�̗p��ŕ\������l�����Ꭶ����Ă���A���ڃL���b�V���t���[�v�Z���ɎQ�Ƃł���悤�ɂȂ��Ă܂��B�C�O�q��Ђ̊č��ύ������\�i�č���p�A�M�����̉�v��A���ۉ�v��j�̑ݎؑΏƕ\�́A�uCash
and cash equivalents�i�����y�ь����������j�v�̗p��ŕ\������Ă���B���{�̘A���ݎؑΏƕ\�쐬�ׂ̈Ɂu�����E�a���v�u�L���،��v�ɋ敪�C������K�v�������邱�ƂɂȂ�B
1998�N3��13����Ɖ�v�R�c����\�����u�A���L���b�V���t���[�v�Z�����̍쐬��v�i��2�j�����������ɂ��āA�ɂ��A�u�����������ɂ��A�Ⴆ�A�擾�����疞�������͏��ғ��܂ł̊��Ԃ�3�����ȓ��̒Z�������ł������a���A���n���a���A�R�}�[�V�����E�y�[�p�[�A���߂������t����A���Ѝ����M�����܂܂��B�v�Ƃ��Ă��܂��B
�u�����y�ь����������v�́A���ۉ�v��y�ѕč���ł́A�����E�a���̂���������3�����������a���͒Z�������ƂȂ菜�O����A�L���،��ȂǂɊ܂܂��Ă��������3�����ȓ��̌���Ȃǂ��܂ނ��̂ł��B���ۉ�v��y�ѕč���ƈ�v���Ă�����̂ƍl�����܂��B
���L�Q�F�A����������˖��`�Œ莑�Y�́u�̂��v�ɓ��ꂳ�ꂽ�B�i2006�N4��1�ȍ~�j
��Ɖ�v�R�c��̐V�����u�A���������\�����i����9�N6��6���j�v�ɂ́A�A����������̑ݎؑΏƕ\�̕\���ɂ��Ė������Ă��܂��A�呠�Ȃ̘A���������\�K���i����10�N2��20���j�̗l���ꍆ�ɂ��A�A����������͖��`�Œ莑�Y�Ɋ܂܂�邱�ƂɂȂ�܂����B
���L�R�F�ב֊��Z��������
��Ɖ�v�R�c��́A�u�O���������v������̉����Ɋւ���ӌ����i�����P�P�N�P�O���Q�Q���j�v�����\���݊O�q��Г��̍������\���ڂ̊��Z���琶�������Z��������͑ݎؑΏƕ\�̎��{�̕��ɋL�ڂ���ƕύX���܂����B���̉����ɂ��A���ۉ�v��ƈ�v���܂����B���̕ύX�́A�����P�Q�N�S���P���ȍ~�J�n���鎖�ƔN�x����K�p���A�����K�p���W���Ȃ��Ƃ��Ă���B
| 2012�N�R���R�P���I���̈�N�� | 2012�N | |
| ���㍂ | 1,121 | |
| ���㌴�� | 654 | |
| ���㑍���v | 467 | |
| �̔���y�ш�ʊǗ���i���L�̒��L�P�Q�Ɓj | 234 | |
| �c�Ɨ��v | 233 | |
| �c�ƊO���v�F | ||
| ��旘�� | 17 | |
| ���z���� | 11 | |
| �����@�ɂ�铊�����v | 28 | |
| �Œ莑�Y���p�v | 39 | |
| ���v | 95 | |
| �c�ƊO��p�F | ||
| �x������ | 26 | |
| �ב֍��� | 12 | |
| ���̑� | 69 | |
| ���v | 107 | |
| �ŋ������O���v | 221 | |
| �@�l�ŁA�Z���ŋy�ю��Ɛ� | 106 | |
| �������嗘�v�O���v | 115 | |
| �������嗘�v�O���v�i���L�̒��L�Q�Q�Ɓj | 15 | |
| ���������v | 100 | |
| �A����]������c�� | 130 | |
| ���v�����[�z���� | -100 | |
| ���v�����[�����ܗ^ | -10 | |
| �A����]�������c�� | 120 |
���L�P�F�A���������菞�p
�V�����u�A���������\�����v�̋��߂�Ƃ���ɂ��������A�A����������̏��p��͔̔����ш�ʊǗ���ɁA�����@�̓������v�͉c�ƊO�Ɍv�サ�Ă��܂��B�@�l�œ��́A���Ɛł��܂ݎ����ŗ��S�W���Ŏ����Ă��܂��B
���L�Q�F�������嗘�v
��Ɖ�v�R�c��̐V�����u�A���������\�����i����9�N6��6���j�v�ɂ́A�������嗘�v�̕\�����@�͖������Ă��܂��A�呠�Ȃ̘A���������\�K���i����10�N2��20���j�̗l���i�A�����v�v�Z���j�ɂ��A�������嗘�v�͖@�l�ŁA�Z���ŋy�ю��Ɛł̎��ɕ\�����邱�ƂƂȂ�A�������嗘�v�O�̗��v��\�����Ȃ��Ă悢���ƂɂȂ��Ă��܂��B
| 2011�N �R���R�P�� ���� |
2012�N �R���R�P�� ���� |
���� | �C �� �d �� �� �� |
�ؕ� | �C �� �d �� �� �� |
�ݕ� | �����c�� | |
| �����y�ь��������� | 300 | 320 | 20 | �� | 300 | �� | 320 | 0 |
| �L���،� | 200 | 220 | 20 | 31 | 20 | 0 | ||
| ���|�� | 350 | 390 | 40 | 32 | 40 | 0 | ||
| �ݓ|������ | -3 | -4 | -1 | 19 | 1 | 0 | ||
| ���ȉ����Y | 230 | 250 | 20 | 33 | 20 | 0 | ||
| ���̑��̗������Y | 50 | 30 | -20 | 25 | 26 | 26 | 19 | 0 |
| 23 | 22 | 23 | 17 | |||||
| 34 | 8 | |||||||
| �����A�� | 500 | 610 | 110 | 11 | 50 | 10 | 160 | 0 |
| �������p�v�z | -300 | -350 | -50 | �X | 80 | 11 | 30 | 0 |
| �y�n | 300 | 300 | 0 | 0 | ||||
| ���`�Œ莑�Y | 50 | 60 | 10 | 35 | 10 | 0 | ||
| �����L���،� | 70 | 100 | 30 | 16 | 28 | 0 | ||
| 17 | 2 | |||||||
| �ۏ؋��E�~�� | 83 | 81 | -2 | 36 | 2 | 0 | ||
| ��؍� | 200 | 150 | -50 | 20 | 50 | 0 | ||
| �ݓ|������ | -100 | -110 | -10 | 19 | 60 | 20 | 50 | 0 |
| �A����������@�i���R�j | 60 | 48 | -12 | 21 | 12 | 0 | ||
| ���Y���v | 1,990 | 2,095 | ||||||
| �Z���ؓ��� | 170 | 100 | -70 | 15 | 70 | 0 | ||
| ��N���ԍϒ����ؓ� | 30 | 20 | -10 | 14 | 20 | 13 | 30 | 0 |
| ���|�� | 300 | 280 | -20 | 29 | 0 | 30 | 20 | 0 |
| ������ | 252 | 233 | -19 | 37 | 19 | 0 | ||
| �����@�l�œ� | 50 | 60 | 10 | 6 | 106 | 7 | 96 | 0 |
| �����ؓ��� | 300 | 400 | 100 | 12 | 120 | 14 | 20 | 0 |
| �ސE���^������ | 250 | 260 | 10 | 27 | 30 | 28 | 20 | 0 |
| �������厝�� | 20 | 30 | 10 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ���{�� | 250 | 300 | 50 | 18 | 50 | 0 | ||
| ���{������ | 250 | 300 | 50 | 18 | 50 | 0 | ||
| �A����]�� | 130 | 120 | -10 | 1 | 221 | 2 | 100 | 0 |
| 3 | 10 | |||||||
| 4 | 15 | |||||||
| 6 | 106 | |||||||
| �ב֊��Z�������� | -10 | -5 | 5 | 22 | 5 | 0 | ||
| ���Ȋ��� | -2 | -3 | -1 | 8 | 1 | 0 | ||
| ���E���{���v | 1,990 | 2,095 | ||||||
| ������ | ������ | �L���b�V�� | ||||||
| �L���b�V���E�t���[�v�Z�� | ���o | ���� | �t���[ | |||||
| �T�D�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�F | ||||||||
| �ŋ������O���������v | 1 | 221 | 221 | |||||
| �������p�� | �X | 80 | 80 | |||||
| �A���������菞�p�z | 21 | 12 | 12 | |||||
| �ݓ|�������̌J����z | 19 | 61 | 61 | |||||
| �ސE���^�������̌J���� | 27 | 30 | 30 | |||||
| �ސE���̎x�� | 28 | 20 | -20 | |||||
| �����ܗ^�̎x�� | 3 | 10 | -10 | |||||
| ��旘���y�ю��z���� | 23 | 17 | -28 | |||||
| 24 | 11 | |||||||
| �x������ | 25 | 26 | 26 | |||||
| �ב֍����@(��2�j | 29 | 0 | 0 | |||||
| �����@�ɂ�铊�����v | 16 | 28 | -28 | |||||
| �L�`�Œ莑�Y���p�v | 11 | 39 | -39 | |||||
| �������Y����ѕ��̑����z�F | 0 | |||||||
| ���|���̑����z | 32 | 40 | -40 | |||||
| ���ȉ����Y�̑����z | 33 | 20 | -20 | |||||
| ���̑��̗������Y�̌����z | 34 | 8 | 8 | |||||
| ���|���̌����z | 30 | 20 | -20 | |||||
| �������̌����z | 37 | 19 | -19 | |||||
| ���v | 214 | |||||||
| �����y�єz�����̎��z | 23 | 22 | 33 | |||||
| 24 | 11 | |||||||
| �����̎x���z | 26 | 19 | -19 | |||||
| �@�l�œ��̎x���z | 7 | 96 | -96 | |||||
| �c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[���ۊz | 132 | |||||||
| �U�D���������ɂ��L���b�V���E�t���[�F | ||||||||
| �L���،��̎擾�ɂ��x�o | 31 | 20 | -20 | |||||
| �����L���،��̎擾�ɂ��x�o | 17 | 2 | -2 | |||||
| �L�`�Œ莑�Y�̎擾�ɂ��x�o�i��1�j | 10 | 160 | -160 | |||||
| �L�`�Œ莑�Y�̔��p�ɂ����� | 11 | 59 | 59 | |||||
| ���`�Œ莑�Y�i�ؒn���j�̎擾 | 35 | 10 | -10 | |||||
| �ۏ؋��E�~���̉��ɂ����� | 36 | 2 | 2 | |||||
| ���������ɂ��L���b�V���t���[�̎g�p�z | -131 | |||||||
| �V�D ���������ɂ��L���b�V���E�t���[�F | ||||||||
| �Z���ؓ����̌����z | 15 | 70 | -70 | |||||
| �����ؓ����̕ԍ� | 13 | 30 | -30 | |||||
| �����ؓ����̐V�K�ؓ� | 12 | 120 | 120 | |||||
| ���呝�� | 18 | 100 | 100 | |||||
| ���Ȋ����̎擾 | 8 | 1 | -1 | |||||
| �e��Ђɂ��z�����̎x�� | 2 | 100 | -100 | |||||
| �������厝���ւ̔z�����̎x�� | 5 | 5 | -5 | |||||
| ���������ɂ��L���b�V���E�t���[�̗��ۊz | 14 | |||||||
| �W�D�����y�ь����������ɌW�銷�Z���z | 22 | 5 | 5 | |||||
| ----- | ||||||||
| �X�D�����y�ь����������̑����z | 20 | |||||||
| �Y�D�����y�ь����������̊���c�� | �� | 300 | 300 | |||||
| ----- | ||||||||
| �Z�D�����y�ь����������̊����c�� | �� | 320 | 320 | |||||
| ===== | ||||||||
| ----- | ----- | |||||||
| �d�v | 2,285 | 2,285 | ||||||
| ===== | ===== |
��1�F
�Z�C�O�����g���ɒ��L�����u���{�I�x�o�iCapital
Expenditure)�v�́A���ʂȎ���Ȃ�����A�L�`�Œ莑�Y�̎擾�z�i�ݔ������z�j�ƈ�v���܂��B
�C�O�ŎЍ⊔�������傷��ۂɉp���ژ_�����ɋL�ڂ���Capital
Expenditure�i�ݔ������z�j�͂��̐��l���g�p���܂��B�L���b�V���E�t���[�v�Z���ɕ\�������ݔ������z���A�ژ_�����̐ݔ������z�ƍ��ق�����ꍇ�͏،���Б��ٌ̕�m���玿�₳��邱�Ƃ�����܂��B
���Q�F�ב֍���
�呠�Ȋ�Ɖ�v�R�c��̕����P�O�N�R���Ɍ��\�����u�A���L���b�V���E�t���[�v�Z�����̍쐬��i�ȉ�"�쐬��h�j�v�̒���7�u�A���L���b�V���t���[�v�Z���v�̗l���ɂ��āA�Ԑږ@�̗l��2�Ɂu�ב֍����v��\�����Ă��邪�A�쐬��ł͂��̓��e�ɂ��ċK�肵�Ă��܂���B
���{���F��v�m����̕����P�O�N�U���W���Ɍ��\�����u�A���������\�ɂ�����L���b�V���E�t���[�v�Z���̍쐬�Ɋւ�������w�j�v�P�U���ɂ��A�u�ŋ��������O���������v�ɑ�����Z���ڂƂ��Ĉב֍������Ꭶ����Ă��邪�A���̈ב֍����i�v�j�́A���v�v�Z���ɂ����Čv�コ�ꂽ�ב֍����i�v�j�̂����A�����Ƃ����A�u�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�v�̏��v���ȉ��̊e���ږ��́u�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�v�ȊO�̊i�\���敪�ɋL�ڂ�������ɌW��ב֍����i�v�j�ł���B�v�Ƃ��Ă��܂��B
���v�v�Z���̈ב֍����v�ƃL���b�V���E�t���[�v�Z���̈ב֍����v���قȂ��ĕ\������ǎ҂����������鋰�ꂪ����܂����A���{���F��v�m����̎����w�j�ɂ��A���|���i�c�Ɗ����j���甭�������ב֍����i�v�j�͏��O����邱�ƂɂȂ�܂��B�O���Ѝ�ؓ����Ȃǂ̈ב֍����v���Y�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���R�F�A�����������˖��`�Œ莑�Y�́u�̂��v�ɓ��ꂳ�ꂽ�B�i2006�N4��1�ȍ~�j
�P�D�ŋ������O���������v�E�E���v�v�Z�����쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P | �A����]�� | �Q�Q�P | �ŋ������O���������v | �Q�Q�P |
�Q�D�e��Ђ̔z�����x���E�E��]���v�Z�����쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q | �e��Ђɂ��z�����̎x�� | �P�O�O | �A����]�� | �P�O�O |
�R�D�����ܗ^�E�E��]���v�Z�����쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �R | �����ܗ^�̎x�� | �P�O | �A����]�� | �P�O |
�S�D�� �T�D�������厝���E�E���v�v�Z������ъ����������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �S | �������厝�� | �P�T | �A����]�� | �P�T |
| �T | �������厝���ւ̔z�����̎x�� | �T | �������厝�� | �T |
| �������厝���̑������� | ||||
| ���{�� | ���{������ | ��]�� | ���v | |
| ����c�� | 8 | 8 | 4 | 20 |
| �x���z�� | -5 | -5 | ||
| �������v | 15 | 15 | ||
| �����c�� | 8 | 8 | 14 | 30 |
�U�D�� �V�D�@�l�œ��̎x���E�E���v�v�Z���y�ъ����������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �U | �����@�l�œ� | �P�O�U | �A����]�� | �P�O�U |
| �V | �@�l�œ��̎x���z | �X�U | �����@�l�œ� | �X�U |
| �����@�l�œ��̊����������� | ||
| ���z | ||
| ����c�� | 50 | |
| �m��\���x�� | -50 | |
| ���Ԏx�� | -46 | |
| �����J���z | 106 | |
| �����c�� | 60 |
�W�D���Ȋ����̎擾�E�E�ݎؑΏƕ\�����i�X�g�b�N�E�I�v�V�����ȊO�̋͏��̏ꍇ�j
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �W | ���Ȋ����̎擾 | �P | ���Ȋ��� | �P |
�͏��ł���A�敪�\�������u���̑��v�Ɋ܂߂ĕ\�����Ă�������悤�B
�X�D�P�O�D�ƂP�P�D�L�`�Œ莑�Y�̑����E�E������������쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �X | �L�`�Œ莑�Y | �W�O | �������p�� | �W�O |
| �P�O | �L�`�Œ莑�Y�̎擾�ɂ��x�o | �P�U�O | �L�`�Œ莑�Y | �P�U�O |
| �P�P | �L�`�Œ莑�Y | �T�O | �L�`�Œ莑�Y�̔��p�ɂ����� | �T�X |
| �P�P | �L�`�Œ莑�Y���p�v | �R�X | �������p�v�z | �R�O |
| �L�`�Œ莑�Y�������� | |||
| ������ | �������p | ���뉿�z | |
| �v�z | |||
| ����c�� | 500 | -300 | |
| �w�� | 160 | ||
| ���p | -50 | 30 | -20 |
| �������p | -80 | ||
| �����c�� | 610 | -350 | |
| ���p��� | 59 | ||
| ���뉿�z | -20 | ||
| ���p�v | 39 | ���v�v�Z���ƈ�v |
�P�Q�D�P�R�D�� �P�S�D�����ؓ����̑����E�E�������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P�Q | �����ؓ��� | �P�Q�O | �����ؓ����̐V�K�ؓ� | �P�Q�O |
| �P�R | �����ؓ����̕ԍ� | �R�O | ��N���ԍϒ����ؓ��� | �R�O |
| �P�S | ��N���ԍϒ����ؓ��� | �Q�O | �����ؓ��� | �Q�O |
| �����ؓ����̊����������� | |||
| ��N������ | |||
| �ؓ��� | �����ؓ��� | ���v | |
| ����c�� | 30 | 300 | 330 |
| �ԍ� | -30 | -30 | |
| �V�K�ؓ� | 120 | 120 | |
| ��N���ԍ� | |||
| �U�ւ� | 20 | -20 | 0 |
| �����c�� | 20 | 400 | 420 |
�P�T�D�Z���ؓ����E�E�������������i�Z���̂��̂͏��z�\���j
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P�T | �Z���ؓ����̌����z | �V�O | �Z���ؓ��� | �V�O |
�P�U�D�� �P�V�D�����@�ɂ�铊�����v�E�E���v�v�Z�����쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P�U | �����@�ɂ�铊�����v | �Q�W | �����L���،� | �Q�W |
| �P�V | �����L���،��̎擾�ɂ��x�o | �Q | �����L���،� | �Q |
�P�W�D���呝���E�E�������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P�W | ���{�� | �T�O | ���呝�� | �P�O�O |
| �P�W | ���{������ | �T�O |
�P�X�D�ƂQ�O�D�ݓ|�������̌J���ꓙ�E�E�������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �P�X | �ݓ|�������|���� | �U�O | �ݓ|�������̌J����z | �U�P |
| �P�X | �ݓ|�������|�Z�� | �P | ||
| �Q�O | ��؍� | �T�O | �ݓ|�������|���� | �T�O |
| �ݓ|�������̑������� | |||
| �������Y�v�� | �����Y�v�� | ���v | |
| ����c�� | 3 | 100 | 103 |
| ��؍��Ƒ��E | -50 | -50 | |
| �����J���z | 1 | 60 | 61 |
| �����c�� | 4 | 110 | 114 |
| �|�T�O�͒�؍��̂����`�Г|�Y���`�Ѝ���ݓ|�ꏈ���������́B |
�Q�P�D�A���������菞�p�E�E�A���������菞�p���ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
|
���z |
|
���z |
| �Q�P | �A���������� | �P�Q | �A���������菞�p | �P�Q |
�Q�Q�D�ב֊��Z���������E�E�O���������\�̊��Z���ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q�Q | �ב֊��Z�������� | �T | �����y�ь����������ɌW�銷�Z���z | �T |
�u�����y�ь����������ɌW�銷�Z���z�v�́A����̌�������ь����������̊O�ݎc���Ɗ����̃L���b�V���t���[�̑����ɌW�銷�Z�����v�シ��B�����ł́A�ȗ����Ă��܂��B
�Q�R�D�� �Q�S�D��旘������ю��z�����E�E���ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q�R | ��旘�� | �P�V | ���̑��̗������Y�i���������j | �P�V |
| �Q�R | ���̑��̗������Y�i���������j | �Q�Q | �����y�єz�����̎��z | �Q�Q |
| �Q�S | ���z���� | �P�P | �����y�єz�����̎��z | �P�P |
��L�̎d��́A���z�����͌����������Ă���Ƃ���B
| ���������i���̑��̗������Y�Ɋ܂ށj�̖��� | ||||||
| �������� | �O������ | ���̑� | ���v | |||
| ����c�� | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
| ���� | -10 | -10 | -20 | |||
| ��p�� | -15 | -15 | ||||
| �������Z�Ōv�� | 5 | 8 | 13 | |||
| ���̑� | 2 | 2 | ||||
| �����c�� | 5 | 8 | 17 | 30 | ||
| ���������z | 22 | �����x���z | 19 | |||
| �������v�̖ߓ� | -10 | �O�������ߓ��z | 15 | |||
| ���������v�� | 5 | �O�������v��z | -8 | |||
| ��旘�����v�v�Z���v�� | 17 | �x���������v�v�Z�� | 26 |
�Q�T�D�ƂQ�U�D�x�������E�E���ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q�T | ���̑��̗������Y�i�O�������j | �Q�U | �x������ | �Q�U |
| �Q�U | �����̎x���z | �P�X | ���̑��̗������Y�i�O�������j | �P�X |
27�D�ƂQ�W�D�ސE���^�������̑����E�E�������ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q�V | �ސE���^������ | �R�O | �ސE���^�������J����z | �R�O |
| �Q�W | �ސE���x���z | �Q�O | �ސE���^������ | �Q�O |
| �ސE���^�������̊������� | |
| ����c�� | 250 |
| �x�� | -20 |
| �����J���z | 30 |
| �����c�� | 260 |
�x���z�́A���ۂ̎x�����z�������B
�Q�X�D�ב֍����E�E���v�v�Z������і��ׂ��쐬
| �C�� �d�� �ԍ� |
�ؕ� | ���z | �ݕ� | ���z |
| �Q�X | ���|�� | 0 | �ב֍��� | 0 |
�ב֍����܂ŊJ������K�v�������邩�^��ł��邪�A�Ꭶ�Ɏ����Ă���̂ł����Ď����Ă݂����̂ł���B
���|������݈̂ב֍������������Ɖ��肵�Ă���B
| �O���Ĕ��|���̊������� | ���̑� | ||||||
| �~ | �O�� | ���Z���[�g | �ב֍��� | ���v�x���z | �~�̔��|�� | ���v | |
| ����c�� | 100 | $1 | �����P�O�O | 200 | 300 | ||
| �x�� | -100 | ($1) | �����P�P�O | 10 | 110 | -200 | -300 |
| �d���v��{ | 240 | $2 | �����P�Q�O | 38 | 278 | ||
| �ב֍����v�� | 2 | 2 | 2 | ||||
| �����c�� | 242 | $2 | �����P�Q�Q | 12 | 38 | 280 |
���ӎ����F�ב֍����ɂ���
�呠�Ȋ�Ɖ�v�R�c��̕����P�O�N�R���Ɍ��\�����u�A���L���b�V���E�t���[�v�Z�����̍쐬��i�ȉ�"�쐬��h�j�v�̒���7�u�A���L���b�V���t���[�v�Z���v�̗l���ɂ��āA�Ԑږ@�̗l��2�Ɂu�ב֍����v��\�����Ă��邪�A�쐬��ł͂��̓��e�ɂ��ċK�肵�Ă��Ȃ��B
���{���F��v�m����̕����P�O�N�U���W���Ɍ��\�����u�A���������\�ɂ�����L���b�V���E�t���[�v�Z���̍쐬�Ɋւ�������w�j�v�P�U���ɂ��A�u�ŋ��������O���������v�ɑ�����Z���ڂƂ��Ĉב֍������Ꭶ����Ă��邪�A���̈ב֍����i�v�j�́A���v�v�Z���ɂ����Čv�コ�ꂽ�ב֍����i�v�j�̂����A�����Ƃ����A�u�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�v�̏��v���ȉ��̊e���ږ��́u�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�v�ȊO�̊i�\���敪�ɋL�ڂ�������ɌW��ב֍����i�v�j�ł���B�v�Ƃ��Ă��܂��B
���v�v�Z���̈ב֍����v�ƃL���b�V���E�t���[�v�Z���̈ב֍����v���قȂ��ĕ\������ǎ҂����������鋰�ꂪ����܂����A���{���F��v�m����̎����w�j�ɂ��A���|���i�c�Ɗ����j���甭�������ב֍����i�v�j�͏��O����邱�ƂɂȂ�܂��B�O���Ѝ�ؓ����Ȃǂ̈ב֍����v���Y�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�R�O�D���� �R�V�D�̏C���d��͒P���ȏ������d�Ă�����̂ł��B
�L���b�V���E�t���[�v�Z�� |
|||||
| 2012�N�R���R�P���I���̈�N�� | |||||
| 2012�N | |||||
| �T�D�c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[�F | |||||
| �ŋ������O���������v | 221 | ||||
| �������p�� | 80 | ||||
| �A���������菞�p�z | 12 | ||||
| �ݓ|�������̑����z | 61 | ||||
| �ސE���^�������̌J����z | 30 | ||||
| �ސE���̎x�� | -20 | ||||
| �����ܗ^ | -10 | ||||
| ��旘���y�ю��z���� | -28 | ||||
| �x������ | 26 | ||||
| �����@�ɂ�铊�����v | -28 | ||||
| �L�`�Œ莑�Y���p�v | -39 | ||||
| �������Y����ѕ��̑����z�F | |||||
| ���|���̑����z | -40 | ||||
| ���ȉ����Y�̑����z | -20 | ||||
| ���̑��̗������Y�̌����z | 8 | ||||
| ���|���̌����z | -20 | ||||
| �������̌����z | -19 | ||||
| ���v | 214 | ||||
| �����y�єz�����̎��z | 33 | ||||
| �����̎x���z | -19 | ||||
| �@�l�œ��̎x���z | -96 | ||||
| �c�Ɗ����ɂ��L���b�V���E�t���[���ۊz | 132 | ||||
| �U�D���������ɂ��L���b�V���E�t���[�F | |||||
| �L���،��̎擾�ɂ��x�o | -20 | ||||
| �����L���،��̎擾�ɂ��x�o | -2 | ||||
| �L�`�Œ莑�Y�̎擾�ɂ��x�o�z | -160 | ||||
| �L�`�Œ莑�Y�̔��p�ɂ����� | 59 | ||||
| ���`�Œ莑�Y�i�ؒn���j�̎擾 | -10 | ||||
| �ۏ؋��E�~���̉��ɂ����� | 2 | ||||
| ���������ɂ��L���b�V���t���[�̎g�p�z | -131 | ||||
| �V�D ���������ɂ��L���b�V���E�t���[�F | |||||
| �Z���ؓ����̏������z | -70 | ||||
| �����ؓ����̕ԍϊz | -30 | ||||
| �����ؓ����̐V�K�ؓ��z | 120 | ||||
| ���呝�� | 100 | ||||
| ���Ȋ����̎擾 | -1 | ||||
| �e��Ђɂ��z�����̎x�� | -100 | ||||
| �������厝���ւ̔z�����̎x�� | -5 | ||||
| ���������ɂ��L���b�V���E�t���[�̗��ۊz | 14 | ||||
| �W�D�����y�ь����������ɌW�銷�Z���z | 5 | ||||
| ----- | |||||
| �X�D�����y�ь����������̑����z | 20 | ||||
| �Y�D�����y�ь����������̊���c�� | 300 | ||||
| ------ | |||||
| �Z�D�����y�ь����������̊����c�� | 320 | ||||
| ====== |
�A���L���b�V���t���[�v�Z���̒��L�����Ƃ��āA���̎����𒍋L���邱�Ƃ����߂Ă��܂��B
| ���L���e | |
| �P�D | �����͈̔͂Ɋ܂߂��u�����y�ь����������v�̓��e���тɂ��̊����c���̘A���ݎؑΏƕ\�Ȗڕʂ̓��� |
| �Q�D | �����͈̔͂�ύX�����ꍇ�ɂ́A���̎|�A���̗��R�y�щe���z |
| �R�D | �V�K�A���q��ЁA�܂��́A�A�����珜�O�����q��Ђ��d�v�ȏꍇ�A���̎��Y�E���� |
| �S�D | �d�v�Ȕ���� �]���Ѝ̓]���A�t�@�C�i���X���[�X�ɂ�鎑�Y�̎擾�A�������s�ɂ�鎑�Y�̎擾���͍����A�����o���ɂ�銔���̎擾���͎��Y�̌��� |
| �T�D | �e�\���敪�̋L�ړ��e��ύX�����ꍇ�ɂ́A���̓��e |
��N���12��22���ɁA�呠�Ȋ�Ɖ�v�R�c��́u���āv�����\���A��98�N1�����܂łɈӌ������߂邱�ƂƂ����B3��13���̍ŏI�łƁu���āv���r����ƂقƂ�ǕύX�͂Ȃ��B
���ۉ�v���7���u�L���b�V���t���[�v�Z���v�i1992�N�����Łj������ƁA���{�́u�L���b�V���E�t���[�v�Z���v�́A���ۉ�v��Ƃقڈ�v���Ă���B
���̓_�A���ۉ�v��ƈقȂ���{�́u���[�X��v��v�Ƃ͉�v��ݒ�̃X�^���X��ς��Ă���Ƃ����Ă����B
�Ȃ��A�A���������\�i���ԁE�N�x�j���쐬�����Ђ́A�K�p�N�x�܂łɑ̐���������Ă����K�v������܂��B�܂�A�q��Ђ���L���b�V���t���[�쐬�̊�b��������肵�Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA�u�A�������v�̐v�ɍH�v���K�v�ƂȂ邩��ł��B�K�p���O�ɑ̐�����낤�Ƃ��Ă�����������܂��B�A���q��Ђ̗��������߂�̂Ɏ��Ԃ�v���܂��̂ő����̏����������߂��܂��B
1998�N3��19���u�A���������\�����v��蓖���쐬
1998�N3��23���Ɂu�A���������\�K���v����b�Ɏ�C���B�A���������\�K���ɂ��A�u�����y�ь����������v�̗p��́A�ݎؑΏƕ\�ɕ\���ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�u�L���b�V���E�t���[�v�Z���̓ǂݕ��v��
�ڎ��֖߂�
�z�[���y�[�W�w�߂�
| ���u��v�E�ŋ��E�������i�f�B�X�N���[�W���[�j�v�� | |
| ��v��E�������J���̑������T�C�g |
��L�́u�L���b�V���t���[�v�Z���̍����v��EXCEL�ł�5000�~�łd-���������ɂĔЕz���Ă��܂��B���N�̎����o������b�ɂ��ăm�E�n�E����Ă�����̂ł��B�o���͗��_�����邾���ł͎����͂ł��܂���B�����͗��_����̓I�Ȍ`�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�������A�N�ɂ����閾���Ȍ`�ɋ�̉����邱�Ƃł��B
����]�̕��́A���L�d-���������ɂĂ��������������B�Ȃ��A�����m�F��̂d-�����������t�ƂȂ�܂��̂łd-���������A�h���X�L���Ă��������B
�U����́A�݂��ً�s �V���ˎx�X ���ʗa��
�����ԍ� 1577705 ���` ���R��
�Ȃ��A��Ђɂ���Ċ���Ȗړ�����X�ł��̂ŁA���p�Ƃ��Ă����p���������B�������A�C�����Ċe�Ђ̃L���b�V���t���[�v�Z�����쐬���邱�Ƃ͉\�ł��B�Ȃ��A�u���ږ@�v�������]�̕��ɂ́A��L�Ɠ���̎�������b�ɓ����i�ŗp�ӂ��Ă��܂��B�ǂ����Ă��K�v�ł�����̎|�L�ڂ��Ă��������B
���đo���̘A�������̖L�x�Ȍo������b�ɃL�[�|���g����L�ɋL���܂����B�{�i�I�ȘA�����Z���x�̑̐��m���ɎQ�l�ƂȂ�K���ł��B�Ȃ��A��Ƃɍ��킹���m�����ʓI�E�����I�ȘA�����Z�̐��̊m���ɂ��Ďx�����Ă��܂��B����������܂�����A���L���Ă��A�����������B
���F��v�m ���R��
E-mail�F yokoyama-a@hi-ho.ne.jp
TEL:047-346-5214 FAX 047-346-9636
|
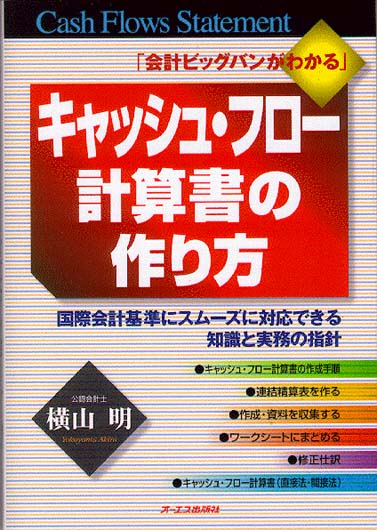 ISBN�ԍ�4-7573-0027-1�@�{�̂P�S�O�O�~�{����� |
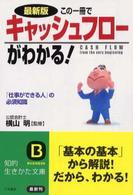 ISBN�ԍ�4-8379-7307-8 �{�̂T�R�R�~�{����� |
||||
| �C���^�[�l�b�g���X | |||||