Traditional Japanese Fly Tenkara 3 |
 |
これらの毛鉤は、各地へ釣行した際に入手したり、または 複製、再現したその土地土地の特徴のあるテンカラ毛鉤です。 |
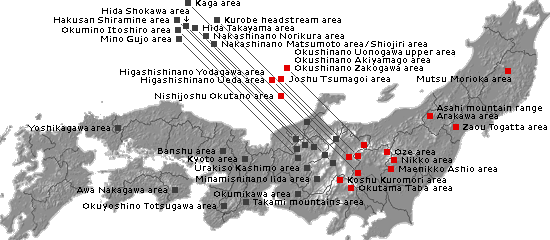 |
 |
 |
 |
 |
||||
Mutsu Morioka area
これらは石澤弘氏によって伝統的な技術で巻かれた現代のテンカラ用の盛岡毛鉤です。
従来の伝統的な盛岡毛鉤にはなかった羽(ウイング)がつけられているのが特徴です。
鉤は6-7号のマス鉤が使われ、モノフィラメントラインの環(アイ)がつけられています。
石澤弘氏は「海の庄内竿 (山形)、川の盛岡竿」と呼ばれる東北が生んだ二大伝統竿の一つである盛岡竿や盛岡毛鉤の継承者であり、それらの継承に努力されていますが、伝統に新たな工夫や改良を加えることにも積極的な方と思えます。 |
|||||||
 |
 |
 |
 |
||||
Zaou Togatta area
南蔵王温泉郷のマタギが伝えた「遠刈田毛針」。
キジや山鳥の尾羽をむしり取った時についてくるストークの皮を翅として使い、12号のセイゴ鉤に山吹色の絹糸で3重に連ねてとめてあります。
フライフィシングのフラッタリング カディスの釣りに似た釣り方をするとのことです。
遠刈田のクロカワ虫(ニッポンヒゲナガカワトビケラ)の多い澄川という環境と職漁師の知恵が生んだ他に類を見ない毛鉤です。
今ではこの毛鉤を作れる人も少なくなったと言われています。
写真は「風雲西洋毛鉤釣師帳」の詳細な紹介を参考にして私が巻いたものです。 参考資料: 風雲西洋毛鉤釣師帳 (参照 2006-9-27). 佳生のいつかきた道ぶらり日記 豊かな蔵王の山々の恵みにふれる旅. 宮城テレビ放送 (参照 2006-9-27). |
|||||||
 |
 |
 |
 |
|||||
 |
 |
 |
|
|||||
Nikko area
日光鉤(ゴロ蝶鉤)は湯川付近に多いヒゲナガカワトビケラに似せた大きめの鉤です。
明治中期から昭和初期、湯川や丸沼付近で鱒釣りを楽しんだ駐日外交官や東京アングリング倶楽部の紳士たちの誰かが湯川で実績のあるこの鉤
を英国のハーディ社に特別オーダーしたけれど日本のキジが入手できず他の似た鳥の羽を使ったため思わしい釣果が得られなかったそうです。
今でもハーディ社にはこの鉤の記録が残っているとのことです。
みの毛はメスのキジの胸毛、胴はゼンマイの綿毛を使って巻かれています。
目黒廣記氏の「鱒釣り」には、日光毛鉤の1号から8号まで図示されていますが、
図が不鮮明で確かなことは不明です。
特に7号はウイングのあるタイプに見えますが2号との相違点が判りません。 ストックしていた昔の釣り雑誌「Angling」通刊15号 (1986)を見ていたら、多田一也氏の「文献からのゴロ蝶探索」という記事に「ゴロ蝶とは毛翅目のゴマフトビケラらしいとあった。」とあります。 氏が参照された文献を調べると「山峡の釣」(1941)の「虹鱒の自殺」澤冷花氏著に確かに「ゴマフトビケラ」の文字があります。 今まで、ゴロ蝶はヒゲナガカワトビケラと信じてきたけれど、ゴマフトビケラという名称もでてきたことから、それは特定の種を指す呼称で無く、飛翔すると白っぽく見える大型のトビケラ全般の呼称と考えた方が良さそうに思えてきました。 参考資料: 西園寺公一 (1974).『釣り六十年』二見書房. 澤冷花 (1941). 「虹鱒の自殺」 ,『山峡の釣』春陽堂書店. 多田一也 (1986). 「文献からのゴロ蝶探索」 ,『Angling』通刊15号, 廣済堂出版. 目黒廣記 (1979).『鱒釣り 附いわな、やまめ』(名著復刻「日本の釣」集成) アテネ書房. 「日本のフライ・パターン 元祖・ごろ蝶毛針からの発展」 ,『入門日本のフライフィッシング 別冊フィッシング』1981年第22号, 産報出版. |
||||||||
 |
 |
 |
 |
|||
Nikko area
日光鉤は、ゴロ蝶鉤のほかチャボの頸羽(軍鶏の頸毛と書かれた文献もある。)をみの毛に巻き、胴にカワネズミの毛を撚りつけた金胡麻、銀胡麻と呼ばれる毛鉤があります。
みの毛に使われるチャボ(矮鶏)は1941年に天然記念物に指定され、胴に使われるカワネズミ(九州地方では環境省レッドリストに指定されている。)も捕る人が減ったことなどで、今ではいづれも入手が困難な材料になっています。
左二本の毛鉤は、胴をカワネズミの毛で、みの毛をゴールデン バジャーとシルバー バジャーで、左から三本目の毛鉤は、胴をカワネズミの毛とゼンマイの綿毛を混ぜて、みの毛をグリズリーで代用して巻いたものです。
カワネズミの毛で巻かれた毛鉤は美しくなめらかな毛の間に取り込まれた気泡が光を反射するため水中では銀色に輝いて見え、渓魚はもとより釣人にとっても魅力的です。
また目黒廣記氏の「鱒釣り」には「ゴロ蝶鉤の外、家鶏の心赤先黒の襟毛で巻いた毛鉤で、チョンチョンと水面を叩く、・・・」との行があり、右の毛鉤はそれを再現したものです。 参考資料: 西園寺公一 (1974).『釣り六十年』二見書房. 目黒廣記 (1979).『鱒釣り 附いわな、やまめ』(名著復刻「日本の釣」集成) アテネ書房. 日光鱒釣研究所 (参照 2010-7-22). |
||||||
 |
 |
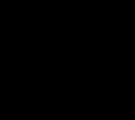 |
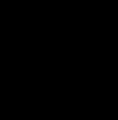 |
||||
Maenikko Ashio area
足尾は栃木県の最西端、群馬県との境、千から3千メートル級の山々に囲まれた渡良瀬川上流部に位置します。
足尾と言えば銅山の鉱毒事件が思い浮かぶけれど、足尾に限るとその影響を受けたのは備前楯山麓の渡良瀬川と庚申川(銀山平下流)で、源流の松木川は煙害と大火による前日光連峰の崩落で荒廃したとのことです。
急傾斜の山岳地帯は畑作が中心で牛馬を必要としないところから、馬素を用いない毛鉤釣りが足尾町掛水の八木沢柏一氏によって考案されました。
鉤は袖型の11号、みの毛は名古屋コーチンの頸羽、胴はクジャクまたはゼンマイの2種類で巻かれています。
馬素を用いないので毛鉤自体に重みをつけるため、下巻きから仕上げまで銅線が使われているのが特徴です。
竿は3m、仕掛は全長4.2mで、道糸からハリスまで通しの2号が使われました。
毛鉤は私が再現したものです。 参考資料: 鈴野藤夫 (1993).『山漁: 渓流魚と人の自然誌』農山漁村文化協会. |
|||||||
 |
 |
 |
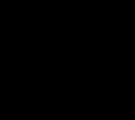 |
|||||
 |
 |
 |
|
|||||
Okushinano Akiyamago area
長野と新潟の県境にあり平家の谷と言われる秘境、秋山郷の伝承毛鉤。
非常にシンプルな毛鉤で、黒と黄色の2本の絹糸とチャボの羽とキツネ8-10号の鉤のみで出来ていて接着剤も使われません。
環(アイ)は2本よりの黄色の絹糸に穴を確保するための紙縒りを挟み込んで取り付けます。胴は軸に巻いたみの毛を半分ほどハサミで刈り込んで作ります。
秋山郷最後の職漁師、毛鉤釣り名人の山田重雄氏の毛鉤で、胴はすべて黒、みの毛は黒、白系統、芯黒の茶の3種類を流れの状況により使い分けたそうです。
竿は3mのグラス、仕掛は6本、4本、2本よりの2mの馬素、1mの2号ナイロン糸、1.5mの1号ナイロン糸。
馬素は重みで毛鉤が手前に引っ張られないようにするために短めです。
短めの馬素を使うのは雑魚川の高森氏の仕掛けと基本的に同じです。
下段の左二本は、秋山郷の伝承毛鉤釣りに拘り続けておられる林謙三氏の毛鉤。
右の二本は「風雲西洋毛鉤釣師帳」で紹介されている民宿「雄山荘」のご主人(山田重雄氏のご子息)と地元の元釣具店のご店主によってアレンジされた毛鉤。
下段の鉤は丸せいご7-9号が使われています。毛鉤はすべて私が複製したものです。 参考資料: 上杉大地 (2001).「林謙三の『秋山毛バリ』」,『テンカラ倶楽部』2, 廣済堂出版. 「秋山郷の重男が語る毛バリのはなし」 ,『フィッシング』1978年9月号, 産報出版. 風雲西洋毛鉤釣師帳 (参照 2008-9-27). |
||||||||
 |
 |
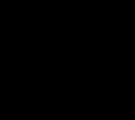 |
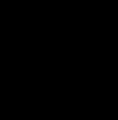 |
||||
Okutama Taba area
奥多摩は東京の奥庭、奥座敷と呼ばれ訪れる人も多く、職漁師や名手も数多く生れました。
丹波では古くから毛鉤釣りのことは「羽根釣り」と呼ばれていたそうです。
左はその伝統を受け継いだ守岡只氏の毛鉤。
鉤は袖型のヒネリ、胴はクジャクの尾羽、みの毛はチャボまたはニワトリが使われ、胴巻きの端に山繭の繊維が巻きつけられています。
古くから引き継がれた丹波の独特な伝統は伸縮自在のハリスで、傷んだチモトを胴巻き端の二つの結びコブを下に引き新たにできるようになっているところです。
左から二番目は丹波の毛鉤を知って取り入れ小菅川で使われた酒井嵓氏の毛鉤。
毛鉤はすべて私が複製したものです。 参考資料: 戸門秀雄 (2013).『職漁師伝』農山漁村文化協会. |
|||||||
My Best Streams |
Fukushima | Hinoematagawa Hinoemata | Tochigi | Ojikagawa Miyori | Yugawa Akanumachaya | Yamanashi | Yanagisawagawa Ochiai | Shiokawa Kuromori, Masutomi | Nagano | Daimongawa Iridaimon | Gifu | Shokawa Hirase | Oshirakawa Hirase | Isshikigawa Isshiki | A upper branch of Shokawa | | Mazegawa Kawaue | Itoshirogawa Itoshiro | Togegawa Itoshiro | Shirakawa Kashimo | Shiga | Adogawa Katsuragawa | Harihatagawa Furuya | Adogawa Kutsuki | Kitagawa Udotani | | Kitagawa Noge | A branch of Kitagawa | Asogawa Kijiyama | Amasugawa Amasugawa | | Echigawa Yuzurio | A branch of Echigawa | Shibukawa Kozuhata | Shibukawa Wanami | | Chayagawa Yakeno | Kyoto | Tananogawa Hora, Yamamori | Yuragawa Ashu | Naesugidani Ashu | Sasarigawa Sasari | | Katsuragawa Hirogawara | Kutagawa Kuta | Besshogawa Hanase | Nakatsugawa Kumogahata | Wyoming USA | Gibbon River and Madison River | Firehole River | Soda Lake | Colorado USA | Boulder Creek | South Boulder Creek (Upstream) | South Boulder Creek (Downstream) | Big Thompson River | Rocky Mountain National Park | South Island New Zealand | Lake Wakatipu | Mataura River | Ontario Canada | Credit River Erindale Park | |
Flies |
Equipment |
| Back to Main Home Page | Profile | Links |
Home |
Paper Craft of Japanese Trout and the World Trout © 1997 Yoshikazu Fujioka |

































