Traditional Japanese Fly Kabari 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
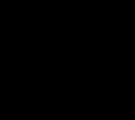 |
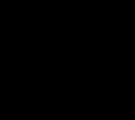 |
|||
Banshu Kabari
これらは 「蚊頭」 「蚊鉤」 「蚊針」 と呼ばれた 「ハエ、ハス毛鉤」 と 「ヤマメ毛鉤」 で、現在でも兵庫県 (播州) で製造、販売されています。
上段は 三蜂つり針ナガオ、二段目は ふじしょう鈎本舗、三段目は現在は無くなった もりもと鈎、四段目と五段目は 龍王鈎本舗の毛鉤です。
西洋式のフックサイズでおよそ #20 から #11 の大きさで、多くの種類があり、すべての毛鉤に名前がついています。
頭につけられた金玉 (きんだま) は西洋式フライに使われるビーズのように重みがあるように見えますが、
これは漆と光明丹 (または砥の粉) を練り合わせ玉 (宝珠型) にして、摺り漆をして金箔を貼ったものですので、
それほど重みはありません。 毛鉤は延宝6年 (1678) に刊行された「京雀跡追」に「はえ頭」として始めて現れます。 京都で オイカワ(関西ではハエ、ハス、関東ではヤマベ)やウグイ の釣りとして始まった「はえ頭 (蠅頭)」は、鮎も釣れることから、鮎釣りのために改良工夫された専用の毛鉤も作られ発達して行き、 寛政年間 (1789-1800) には 「蚊頭」 「蚊鉤」 「蚊針」 と呼ばれるようになりました。 江戸時代は戦いの無い平和な世の中になり、武士の心身の鍛練の一つとして多くの藩で釣りが奨励され、 秋田久保田藩、山形庄内藩、石川加賀藩、兵庫播州姫路藩、高知土佐藩など各地で釣針産業も奨励されました。 また他方で、この毛鉤はヤマメ(アマゴ)も釣れることから、ヤマメ(アマゴ)用の毛鉤としても改良や工夫がされていったと考えられますが確かなことは判りません。 天保5年 (1834) の「魚猟手引」に五種類の蚊鉤の挿絵があり、その一つは「蜂がしら」と呼ばれる他より大きめの毛鉤で、 オイカワ、ウグイ、鮎はヤマメ(アマゴ)と混生する場所が多いことからも、ヤマメ(アマゴ)用の毛鉤であった可能性があります。 古いヤマモやかつおかの大きめの毛鉤の袋には「山女魚毛鉤」と表示されていることからもそれがうかがえます。 しかし、この蚊鉤による釣り「都の毛鉤釣り」と同時に、各地の山棲みの生活者や漁師が独自の工夫をしながら行ってきたヤマメ(アマゴ)やイワナの毛鉤釣り「山里の毛鉤釣り」もあったと考えられます。 天保4年 (1833) 頃、様々な漁の様子が描かれ出版された葛飾北斎の浮世絵 「千絵の海 (全10点)」 の 「蚊針流」 は、190cm (6.3ft) - 270cm (8.9ft) の竹竿に馬素のテーパーライン、ハリス、先端の毛鉤と二本の枝鉤の仕掛け、網の部分に麻製の裃を利用して作られた受けダモを用いる熊本 (肥後) に伝承される 「カガシラ釣り」 とまさしく同じです。 また、明治30年 (1897) に刊行の「兵庫県漁具図解」の「蚊頭釣」とも四本の毛鉤を使うことを除いて酷似しています。 そして、明治45/大正元年 (1912) 発行の「日本水産捕採誌 全」の「鰥 (ヤマべ) 釣」の項に「武蔵國西多摩郡の山間に於ける鰥釣は(中略)蜂形の擬餌鉤三個を以てす」とあり、鰥は通常ヤモメと読みヤマメのこと、蜂形の擬餌鉤とは蜂がしらのことで、1600年代から1900年代初めまで「都」でも「山里」でも複数の毛鉤をつけた「流し釣り」が広く行なわれてきたことが判ります。 この流し釣りは複数の毛鉤を用いることを除いて現在のテンカラ釣りともそっくりなことから (伝承毛鉤釣りには毛鉤の他に掛け鉤をつけたものなどもある。) 二つの毛鉤釣りは無関係ではなく、長い歴史の中でお互いが影響しあいながら伝承されてきたのではないかと想像しています。 その後、河川開発による釣場の環境変化や、鉄道や道路網の発達により上流域へのアクセスが容易になったことなどにより、北東北 (北奥羽) 以南では一本の毛鉤を使う釣りに主流が移って行ったようです。 現在の流し釣りは 5 - 9 本と多くの枝鉤をつけ、浮子を用いる釣法が行われています。 参考資料: 歌野タケシ (2006)「カガシラ鉤の源流を探る」,『Fishing Cafe』23, シマノ. 小田淳 (1999)『「何羨録」を読む』つり人社. 小田淳 (2001)『江戸釣術秘傳』叢文社. 高崎武雄監修 (1981)『日本釣具大全』笠倉出版社. 永田一修 (1987)『江戸時代からの釣り』新日本出版社. 農商務省水産局編 (1979)「鰥(ヤマべ)釣」,『日本水産捕採誌 全』(名著復刻「日本の釣」集成) アテネ書房. 野間光辰編 (1976)『新修京都叢書』1, 臨川書店. 「魚猟手引 蚊鉤の挿絵」 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2012-8-29). 「千絵の海 蚊針流」 東京国立博物館 研究情報アーカイブズ (参照 2012-5-9). 「兵庫県漁具図解 播磨国 蚊頭釣」 関西学院大学図書館 デジタルライブラリ (参照 2019-2-24). 加賀毛針 目細八郎兵衛商店 (参照 2011-5-7). 播州毛鉤 伝統的工芸品 (参照 2011-5-7). |
||||||
Flies |
Equipment |
| Back to Main Home Page | Profile | Links |
Home |
Paper Craft of Japanese Trout and the World Trout © 1997 Yoshikazu Fujioka |